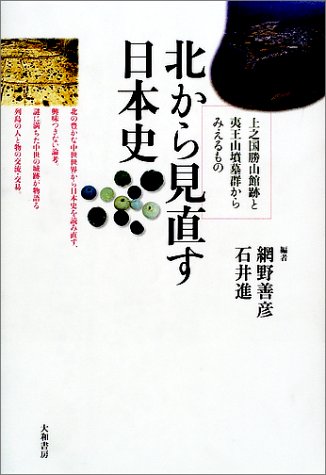
網野史学の文献?
これは図書館からもらった本ではありません。古本屋で買った本です。たぶん、当時は「地方から考える」というようなことが言われていたので「北から見直す」という題名に惹かれたからですし、網野さんの名前があったからでしょう。
実際には、網野さんの文章は、「初めに」(3P、石井進と共同署名)と「日本史像を変える発掘成果」(9P)だけで、どこまでこの発掘調査に関わっていたのかは不明です。出版にあたって名前を貸しただけかもしれません。ただ、内容は網野の学説に沿っている気がします。といっても、私は網野さんの歴史観に詳しいわけではありません。
農業・交易(商業)・都市
人間の社会は、最初から自分の小さな世界を自給自足で守るというのではなく、広い世界、社会との関わりの中で活動し、それによって支えられているのだと思います。まず自分が腹一杯になって、余ったものを交換するというのではなく、最初から他者を意識、考慮し、相互に依存しながら生活しているのです。その意味で商業・都市は人類の歴史とともに古いということができると思います。これはたしかエンゲルスも言っていた言葉ではないかと思いますが、それはともかく、これが事実に即していることが非常によく分かってきました。(P.403)
これは従来の歴史学の中に、農業こそが先進的で、商業・流通は社会を動かす力ではないという「確固」たる思い込みが極めて根深くあり、多くの歴史研究者たちは農耕民族、農業民族とは異なる交易の民、交易民族の独特なあり方をまったく視野に入れようとしませんでした。しかし人類社会全体を見ても、こうした交易に従事する民族の活動は広く見出されます。沖縄の人々、琉球人もそうした人々だと思いますが、このような観点が勝山館を理解する上で非常に重要な意味を今後とも持ってくることは確かで、こうした見方によって従来とはまったく違った視野の中で、この舘をとらえることが可能になってきたと思われます。(P.404)
エンゲルスの言葉は確認していません。こういう表現をもって、網野さんは「左翼的だ」とか「マルクス主義的だ」とか言われるのかもしれません。でも、「左翼的」「マルクス主義的」であることと、網野史学が「正しい」かどうかは別のことです。網野史学を批判するのにそんな言葉を使う学者がいたとすれば、私はその学者の言うことを聞く気にはなれませんが。
「都市と地方(あるいは農村)」との対立は、「地方再生」などという言葉で自民党も主張していることなので、あえて言及しません。
「農業の先進性」というのは、「狩猟採集から農耕へ」「移動から定住へ」というのが「文明化」であると主張されていることは、皆さんも御存知だと思います。世界全体で、そういう歴史を持っている地域が多いのかどうかはわかりません。「都市」というのは明らかに「定住」でしょうね。そして、都市から「国家」あるいは「権力や貧富の差」が生まれる、と言われます。それはマルクス経済学の中にも見ることができます。「生産至上主義」と言われるものです。それのもとになっているのは「労働価値説」です。そこでは、通常「流通(交易)は価値を生産しない」とされます(これにはマルクス経済学者の中にも批判的な人がいます)。「監督労働や資本家の労働は不要である」というのと同様に、流通そのものは商品を生み出したり、変形したりしない、ということでしょうね。
種と種の関係
「人間は昔、狩猟採集民族で、いつもお腹をすかせていた。食料を保存したり、備蓄することを知らず、手に入った食料はすぐに腹一杯になるまで食べてしまった。次いつ食料が手に入るかわからないからである。」というような歴史観を聞かされたことがあるでしょう。そして、「飽食の時代」と言われる今、「戦後の食糧難は大変だった。今の若い人は幸せだ」と続くのです。
戦争や干ばつなどの自然災害のあと、多くの人が飢えに苦しんだときはあったと思います。でもそれは人類の歴史、あるいは生物の歴史の中では、ごく短い時間だったのではないでしょうか。
野生動物の世界を見てください。ライオンは常に狩りをしていますか。そんなことはないと思います。ライオンが獲物を追う映像がよく流れていますが、あれを撮影するのは大変だと思います。まず、撮影者が襲われる可能性があります。そして、ライオンは滅多矢鱈と狩りをしているわけではないのです。空腹時以外は目の前を獲物が通っても見向きもしません。もしライオンが今の「先進国」の人間のように、食物を無駄にし、太っても食べ続けるとしたならば、ライオンに捕獲される生き物はすぐに絶滅してしまうでしょう。殆どの野生動物は、多くの時間を「食べる」ことに費やしているのではなく、寝ることや遊ぶことに費やしているのではないでしょうか。働き者のミツバチだって、人間が蜜を「搾取」しなければ、蜜を集める時間は相当に減るはずです(笑)。
つまり、動物たちが「働いた」結果を、他の動物(たとえば人間)が取り上げることが出来るということは、それだけの余裕が各動物種にあるということで、同時にそういう連鎖(関係)の中で、生物の世界は成り立っているということです。
植物は、草食動物が食べても種が滅びるわけではないし、肉食動物に食べられる種も、それで種がなくなるわけではないのです。
「種」についてはWikipediaを参考にしてください。
ある意味では、地中から養分を吸収し、太陽エネルギーを身体のエネルギーに変換する生物と、その生物を食べる草食動物、草食動物を食べる肉食動物・・・という「循環」あるいは「分業」が成り立って、全体として生物の世界があるとも言えます。
種と個体
種の内部ではどうでしょうか。ミツバチは嬢王蜂や働き蜂、雄蜂などに別れています。一種の社会を作っているわけですね。ボス猿や猿社会のカースト制を見て、「民主的じゃない」とか「それに比べ、わたしたちの社会は平等だ」、そして「アイツラは下等だ」とバカにする人もいます。その人は、自分の社会が「自由・平等・民主主義」を掲げていても、いかに不平等でいかに不自由か、そして、いかに非民主主義なのかを忘れているのです。
「自由・平等・民主主義」は達成すべき目標であり、その目標を掲げることだ大切なんだ、という人もいるかもしれません。でも、いくら「目標」にしていたとしても、現実がそうでなかったら、その人が考える猿やミツバチの社会と現実は変わらないということですよね。その人達は「言葉」と「現実」を区別できないのかもしれません。
最近、私にとって良くないことはこうして感想を書いている間に、関係する記述が見つかることです。私の観点で本を読んでいるので当然のことなのですが、ひょっとすると学問(自然科学も含めて)の関心事というのは、案外狭いのかもしれません。
その一つが、大杉栄の『奴隷根性論』です。そこではいろいろな部族が酋長に服従する姿が描かれています。
主人に喜ばれる、主人に盲従する、主人を崇拝する。これが全社会組織の暴力と恐怖との上に築かれた、原始時代からホンの近代に至るまでの、ほとんど唯一の大道徳律であったのである。(P.20、初出1913年『近代思想』、『大杉栄選 無政府主義の哲学Ⅰ』1971/03/31 現代思潮社)
政府の形式を変えたり、憲法の条文を改めたりするのは、何でもない仕事である。けれども過去数万年あるいは数十万年の間、われわれ人類の脳髄に刻み込まれたこの奴隷根性を消え去らしめることは、なかなかに容易な事業じゃない。けれども真にわれわれが自由人たらんがためには、どうしてもこの事業は完成しなければならぬ。」(同)
服従していれば「楽だ」というだけでなく、しだいに服従という「行為が苦痛でなくなって、かえってそこにある愉快を見出すようになり、ついに宗教的崇拝ともいうべき尊敬の念に変わってし」(同、P.17)まうのです。これは、サラリーマンなら多くの人が経験することだし、幼児期から「学校」にいって社会に出る間に、つまり「人生」で経験することでもあります。マルクス主義的な「社会変革」なんて「何でもない仕事」と喝破する大杉栄の豪快さがあります。この身分的上下性は、歴史の中でも何度も言われることですよね。
もう一つは、『ピダハン―― 「言語本能」を超える文化と世界観』(ダニエル・L・エヴェレット著 屋代通子訳 2012/03/22 みすず書房)です。
アメリカ先住民のほとんどの部族には、長などの権威の象徴がいると信じられている。これは誤りだ。アメリカ先住民の部族の多くは、伝統的に平等社会である。(P.158)
まず、他の社会を見るときに、自分たちの社会の価値観や仕組み、物事の進め方を投影してしまうこと。(同)
(中略)
最後に、おそらくここが最も重要なのだが、西洋社会にとっては、先住民社会に交渉相手となる指導者がいたほうが都合がいい。(中略)傀儡の長が立てられ、「彼ら」の法的な指導者であるという人造の権威を纏わされ、先住民の所有物に関して商取引が進められていくのだ。
あらゆる部族には長がいるはずという考えの背景には、社会には支配と管理が必要であるという事実がある。(同)
私は、西暦2022年の日本に住んでいます。私は私がいる文化というフィルターで過去をみるし、同じフィルターで他の文化を見ます。つまり同じ文化(歴史)を見たとしても、見る人の文化の数だけ違う解釈がある(可能性がある)ということです。
わたしたちが、自分の社会が「自由・平等・民主主義的」だと思うのは、いかに不平等・不自由・非民主主義なのかを忘れているからということだけじゃなく、そういう目で他の文化を見てしまうからなのです。
他の動物をみるときも同じです。働き蜂は、「女王蜂っていいよなあ。こんなにあくせく働かなくていいから」と思っていると思いますか。たぶん違いますよね。どう思っているか(何も思っていないか)わかりませんが、わたしたちの見方(考え方)で言えば、働き蜂と女王蜂は「個人と個人」ではないのです。擬人化するならば、「働き蜂と女王蜂で一つの個体」ということになります。そしてそれは、働き蜂と女王蜂がいることによって、ミツバチという種が成り立っているということです。
それを逆に擬人化して、「王と農奴がいるから人間という種が成り立っている」とか「資本家と労働者がいるから社会が成り立っている」などと言っているわけではありません。個人の集まりが社会だ、あるいは部分の集まりが全体だという発想そのものが、一つの文化に所属する思考形式だということです。
科学と歴史
科学的研究の基本は「分析と統合」「帰納と演繹」です。まず全体を部分に分けます(たとえば、物質を原子に)。そして、その部分同士の関係を探ります。そうすると元の全体がわかる、という考え方です。でも、机を分解した物は「机」という属性を全く持たない「木の切れ端」です。「木の切れ端」をいくら研究しても、そこには「机」の要素はありません。その証拠にその「木の切れ端」を使って、「机以外のもの」を作ることができます。同じことが社会にも言えます。個々の国民を集めたのが国家ではないのです。
歴史についても同様です。歴史的文献や、発掘史料から、その時代を形作るのが歴史学です。木の切れ端から机を作るときに木の切れ端同士の関係、つまり「設計図」が必要なように、文献・史料から歴史をつくるときには設計図に当たるものが必要となります。それが「思考形式」であり「思想」です。その証拠に、一つの文献・史料には様々な解釈があるのです。
学問の世界では、Aという解釈とBという解釈で論争が起こります。まあ学者はそれが仕事ですから、やってくださっていて結構です。わたしたちの文化の必然的産物ですから。でも、みんながそれに付き合う必要はありません。
この本が刊行されて以降も、様々な発掘史料があり、今後もあるでしょう。そのたびに学説が緻密になり、変更されるでしょう。でも、「現在の研究者が所属する文化のフィルター」というものの存在を考えない学問こそが「何でもない仕事」だ、と私は思うのです。
その学問自体を批判するためには、その学問を知ることが必要です。そして、「どこにフィルターが掛かっているか」を見つけることは、「自分自身の思考形式」を知ることそのものです。学者は職業柄、それができにくいのです。自分の職業に疑問を持ちながら、その職業を続けることは辛いことです。
細分化することが宿命の文化では、個々の学問分野もどんどん細分化していきます。結果として、「学者」とか「知識人」と言われる人でも、他の分野のことはわからいという時代になっています。「専門家」と名乗る人はワイドショーで引っ張りだこです。素人はそれを「信じる」以外にありません。何かを言おうとすると「専門でないやつは口をだすな」「素人は黙ってろ」と言われるのが落ちです(芸人だけは許される、という風潮はありますが)。
「高度に発達」しているけど「誰も知らない」という文化は、そう長くは続かないと私には思えるのです。
[スタッフ・キャスト等]
網野 善彦(あみの よしひこ、1928年1月22日 - 2004年2月27日)
歴史研究者。1928年山梨県に生まれ、東京で育つ。東京大学文学部卒業後、渋沢敬三の創設した「日本常民文化研究所」に勤務。その後都立北園高校教諭、名古屋大学助教授、神奈川大学短期大学部教授、同経済学部特任教授を歴任し1998年退職。1988年より勝山館跡調査研究専門員として勝山館跡の調査・研究を指導
石井 進(いしい すすむ、1931年7月2日 - 2001年10月24日)
東京大学名誉教授、鶴見大学客員教授。棚田学会会長。1931年東京生まれ。東京大学文学部卒業、同大学院修了。1993~97年まで国立歴史民俗博物館の3代目館長を務める。1988年より勝山館跡調査研究専門員として勝山館跡の調査・研究を指導
《書抜》
勝山館跡発掘調査二〇周年記 念
上ノ国シンポジウムに思いを寄せて 神の国町長 福原賢孝
勝山館への招待 ーー北の世界から日本史を見直す 石井進
アイヌ民族の去就(北奥からカラフトまで)ーー周辺民族との「交易」の視点から 榎森進
「つまり、異民族間の関係のありかたは、常に敵対関係にあるわけではなく、両者間に大きな矛盾が生じるに至った時には戦闘状態にもなるが、状況の変化によっては平和的な関係にもなるということです。」(P.52)
「しかし、寛永期(一六二四ー四三)になると松前藩は新たな政策を実施しました。それは蝦夷島を和人専用の地、和人の「村」の所在地としての「和人地」(松前地、シャモ地ともいう)とアイヌ民族の居住地としての「蝦夷地」の二つの地域に区分し、「蝦夷地」を藩主と上級家臣のアイヌ民族との交易の場としたうえで、「蝦夷地」を対象とした商場知行制を実施したことです。この地域区分制と商場知行制の実施は、松前藩のアイヌ交易独占権の効果的な実現と幕藩制国家の「鎖国」体制を特徴づけている長崎とオラン(FF)ダ船・中国船の関係、薩摩藩と琉球の関係、対馬藩と朝鮮の関係、松前藩と異域としての「蝦夷地」(アイヌ民族)との関係という四つの口を介した日本型華夷秩序を軸にした対外関係のありかたと密接に関わるものでしたが、こうした地域区分体制の実施を前提とした商場知行制実施は、アイヌ民族と松前藩の関係のあり方を根本的に変えることになりました。」(P.92-93)
「その内重要な点を上げると、まず第一に、「蝦夷地」内のアイヌ民族は、「蝦夷地」内に和人との恒常的な交易の場が設置されたことによって、アイヌ民族の社会が和人との恒常的な交易を媒介にして従来以上に急速に発展するに至ったこと。また、そのことによってアイヌ社会内部の階層分化が一層発展するに至ったこと。しかし第二に、こうしたアイヌ民族の松前藩との交易は商場知行制という枠の中での交易であったために、「蝦夷地」内のアイヌ民族の交易活動は他方で従来の自由な交易活動が制限され、松前藩のみとの交易を強要されるようになったことです。」(P.93)__「発展するに至ったこと」という価値観。
(シャクシャイン)「こうした松前藩による「蝦夷蜂起」の鎮圧過程に目を向けると、松前藩がその鎮圧に成功しえたのも当時のアイヌ社会が日本社会との「交易」がなければ再生産ができない社会になっていたという側面にもその大きな要因が潜んでいたと見ることが出来るでしょう。」(P.97)
「その大きな転換期が元禄・亨保期(一六八八〜一七三五)でした。いわゆる場所請負制の成立です。その結果アイヌ民族は、和人との「交易者」という立場から「漁場の労働者」へと変容していったことです。」(P.98)
「ともあれ、シャクシャインの戦いの敗北と元禄・亨保期(一六八八〜一七三五)を画期とした場所請負制の成立を大きな契機として、松前藩のアイヌ民族に対する政治経済的支配が一段と強化され、その結果、アイヌ社会では鉄砲や武具としての刀の所持が見られなくなると共に、特に場所請(FF)負制の成立・発展に伴いアイヌ民族の多くが場所請負人の経営する漁場の労働者としてかり出され、アイヌ民族の各共同体が場所請負人の漁業経営に都合のよい共同体として再編されるに至って、アイヌ民族の社会はそれまで発展しつつあった比較的広範囲な地域にわたる政治的社会が破壊されるに至っただけでなく、アイヌ民族の経済的基盤も場所請負人の漁業経営の拠点である運上屋で支払われる僅かの食料・物品と、場所請負人を含めた和人との「交易」で得る収益及び各コタンでの畑作に限定されるようになったものと思われます。」(P.99-100)
「こうして清朝の雍正一一年(日本の亨保一八年・一七三三)、清朝はサハリンのギリヤーク(現ニヴヒ)民族やオロッコ(現ウイルタ)民族の各首長層とともにアイヌ民族の一部の首長層にも「姓長」と「郷長」に任じて清朝への朝貢を義務づけるに至りました。」(P.103)
「サハリンのアイヌの女性は北海道のアイヌのように入れ墨をするものが少なく、奥地のアイヌの女性にいたっては、入れ墨をしない人のほうが圧倒的に多かったこと、」(・・・P.103)
日本史像を変える発掘成果 網野善彦
「人間の社会は、最初から自分の小さな世界を自給自足で守るというのではなく、広い世界、社会との関わりの中で活動し、それによって支えられているのだと思います。まず自分が腹一杯になって、余ったものを交換するというのではなく、最初から他者を意識、考慮し、相互に依存しながら生活しているのです。その意味で商業・都市は人類の歴史とともに古いということができると思います。」(P.403)__個体ではなく、種として生存する。人間も同じ。「他者」という視点が存在しない。
「これは従来の歴史学の中に、農業こそが先進的で、商業・流通は社会を動かす力ではないという「確固」たる思い込みが極めて根深くあり、多くの歴史研究者たちは農耕民族、農業民族とは異なる交易の民、交易民族の独特なあり方をまったく視野に入れようとしませんでした。しかし人類社会全体を見ても、こうした交易に従事する民族の活動は広く見出されます。沖縄の人々、琉球人もそうした人々だと思いますが、このような観点が勝山館を理解する上で非常に重要な意味を今後とも持ってくることは確かで、こうした見方によって従来とはまったく違った視野の中で、この舘をとらえることが可能になってきたと思われます。」(P.404)
「「海の領主」「山の領主」「道の領主」などの用語も、だんだん最近は通用するようになりましたが、人間の生活は定住することだけではなく、本質的に移動することが前提となっていると考えざるを得ないところがあります。地頭御家人、中世前期の領主もまた、広域的な交通を前提としてその支配を保ってきたのだと思います。」(P.406)
《end》
《メモ》
「西欧、西欧が進出している地域、西欧の文化の影響を受けている地域」以外の地域(つまり発展途上国の一部)は、慢性的な飢えに堪えているのでしょうか。先進諸国の人々のように一年中働いているのでしょうか。多分違うと私は思います。
別に南の太平洋の島の生活を知る必要はありません。二〇〇年前の日本の生活を思い起こせばいいのです。お盆や正月だけでなく、季節ごとに様々お祭りがありました。長時間労働も、徹夜の残業もなかったのではないでしょうか(残業したからといって、お米がたくさん穫れるわけでもないし、もちろん電気照明器具もなかった)。
種として存在する人間
定住ではなく、
__個体ではなく、種として生存する。人間も同じ。「他者」という視点が存在しない。
東大というだけで、「横目」で見てしまう。


