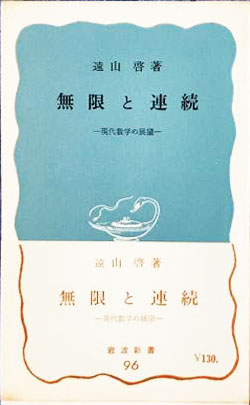
古い本
たぶん、友人にもらった本です。ぼろぼろです。縁がすり減っていて、ページを捲るのも一苦労です。
舊漢字ですが、旧仮名遣いではないので、それほど読みにくくはありません。
1952年の本ですから、70年前の本です。その間に数学は「進化」しているんでしょうね。
理解できない(;_;)
恥ずかしながら、全然理解できませんでした。数式は殆ど出てきません。ですから、「理解する」というより、数学の「考え方」を学ぶための本でしょう。算数から数学へ、具体から、抽象へという思考形式の変更です。そして、それは同時に現代数学への入門でもあります。
「無限と連続」というタイトルですが、内容は「集合から群」と言ったほうが近いでしょうね。
わからなかったので、書抜も少なく、すぐ感想が書けるだろうと思って、優先的に書き始めたのですが、わからないものは感想も難しいです(笑)。たぶん、高校時代ならもう少しわかったんでしょうが。
最近、難しい本の読み方を覚えました。今までは、「わかろう、わかろう」と思いながら読んだので、難しい本は途中で挫折してしまいましたが、むずかしくても「流し読み」をしたほうが得ることが多いようです。そして、「もっと分かりたい」と思う本なら、また読めばいいのです。
でも、流石にこういう本は、わからなければ、そのつぎの章はもっとわからなくなりました。(汗)
学問
こういう科学系の本を読むときに注意していることがあります。それは、浅い理解で曲解することの怖さです。
たとえば、ゲーデルの「不完全性定理」を単純に「不完全」と読むようなことです。「数学は不完全だ」と読むことは私には魅力的です。論理を追求していくと、論理で解明できないことにぶち当たるというのは、私の考えている意図そのものだからです。
同様のことは、ダーウィンの『種の起源』を理解せず(あるいは読まずに)「社会は弱肉強食で進化する」と考えると、「社会ダーウィニズム」になってしまいます。
でも、理科系でない人に「群論を理解せよ」というのは、『資本論』を読んだことのない人に「マルクスを理解せよ」というのと同じ程度に難しい。
今日から『講座進化1 進化論とは』(東京大学出版会)を読み始めました。最初の「進化学における<総合理論>の立場」(太田邦昌著)で、「素人は専門分野に口を出すな」的な事が書いてあって、驚きました。本人に聞けば「そんなつもりじゃない」と言うと思いますが、素人にわからない学問をなんのためにやっているんでしょうね。「わかっている人が決める。わからない人はそれに従えばいい」ということでしょうか。それなら、税金で学問をしている唐代の学者よりも、「エセ進化論本」を書いて生活している人のほうが、よっぽどマシです。
「学者」というのも一つの職業です。プロになるためには、一定の技術を身に着けていることが今の社会での条件になります。大学院を出て、研究室で数年勉強して、やっとスタートラインに立ちます。囲碁や将棋の世界では、初段になってプロになれば、もう段位は関係ありません。2段と9段でもハンディーはないのです。学者の世界も、そんな感じなんでしょうね。
学者が可愛そうだと思うのは、素人にわからなくなってからの学問は学者にもわからなくなっているということです。一つには、細分化されすぎて自分の専門以外がわからないということ。もう一つは、毎日新しい論文が発表されて、それを追うことに忙殺されること。ゆっくり「古典」を読む時間などないのではないでしょうか。「それは別の専門分野だ」と言ったところでしょうか。生物学者はみんなアリストテレスの『動物発生論』を読んでいるのでしょうか。それは「古くてまちがった理論」ではありません。自分がなぜ、何のために学問をやっているのかを知らないのは、目をつぶって自動車を運転するのに似ています。
わからないけど、あえて無限について
第一に我々の常識を驚かすのは「部分は全體に等しい。」という逆説である。(P.17)
無限の直線と、ある長さの線分に含まれる「実数」は「同じ」だということです。まるでフラクタル図形のようです。
生物の「種」についても、個々の個体は全て「種」の性格(情報、遺伝子)をもっています。また、「個体発生は系統発生を繰り返す」ということでいえば、生物の歴史は個体の歴史だということです。この「反復説」を否定するのはかってですが、日常、子供が学校へ行っておとなになる過程を同様に考えている人がほとんどなのではないでしょうか。
ここで、数を「数える」ということに著者は二つの方法があると言っています。一つは「1,2,3,4・・・」と指を折って数える方法で、もう一つは「1万、2万、3万、4万・・・」と数える方法です。前者を「戦後の新教育」と呼び、「非実用的だ」と言います。
算數と限らずすべての教育が實生活に即したものでなければならない。(P.7)
そして、後者の数え方を
數學者は論理によって肉眼の缺陷を補うのである。(P.8)
と言っています。
また、数が「同じ、多い、少ない」であることを、1対1対応で説明しています。数がわからなくても、リンゴ5個とみかん4個を1対1対応させれば、リンゴが1つ余るのでリンゴのほうが「多い」と説明するわけです。でも、リンゴとみかんは別のものです。わたしは、「リンゴとみかんは違うものなので、比べられない」という答えを期待したのですが。そこは疑問とされていません。
最近、「鳥インフルエンザでニワトリ5万羽を処分」「ウクライナで200人死亡」「知床沖で14人死亡12人行方不明」等の報道がされています。この「5万、200、14、12」の数字はどういう意味をもっているのでしょうか。「數學者は抽象するのが仕事」なので、関係ないのでしょうか。そこには「数える」ということに対する重大な意味が隠れている気がします。
著者は「忘數病」という例えを出しています。でも、それは「数を知っていたけど忘れた」ということです。数えるというのは高度な抽象化の一つです。數がない文化(民族)もあります。「アヴァロンの野生児」のように、「文明」から遠ざかって育った人間もいます。その人たちは、「忘數病」の人とはちがって、リンゴとみかんを1対1対応させることはできないでしょう。
「What」と「How」の関係については、高木任三郎さんの『いま自然をどうみるか』が参考になります。
わからないけど、あえて集合について
集合論によって斷ち切られた各要素間の相互關係、すなわち社會性を囘復し、集合を單なる群衆から社會へと再組織すること、これが現代數學の次の課題であった。この仕事を引き受けたのが抽象代數學とトポロギーであった。(P.48)
すなわち木片から成り立っている「群衆」は駒と盤のつくる「社會」にまで進化する。そのような「社會」の憲法に當たるのがルールである。(中略)そこで問題となっているのは、「桂馬が何か」ではなく「桂馬はいかに動くか」である。何か(what)ではなくいかに(how)が重要である。(P.51)
相互關係を手がかりとする分類法はおそらく數學に特有なものであって他の科學には見かけないものであろう。(P.72)
集合の基本は、「要素の集まり」でしょう。部分が集まったものが「全体」としての集合です。その要素となり得るのは抽象化された個です。リンゴの集合を作るには、青いリンゴ、赤いリンゴ、小さなリンゴ、虫食いリンゴ・・・などの「個別生」「特殊性」を捨象して、抽象化したリンゴにしなければなりません。これは著者の例のごとく「個性」を捨象された「個人」が「社会」を作っているという構造と同じです。その構造においては、個が全体を規制し、全体が個を規制するというフィードバックが絶えず行われていますが、それだからこそ、個は全体としてはとらえられません。
「個体発生は系統発生を繰り返す」というと、なんとなく「個と全体」が関連づけられているように思えますが、そこでは個体についても全体についてもなにも言われてはいないのです。個を全体としてとらえてはいないのです。
「個々人の意思を反映する」ための選挙制度で、投票は「1票」であり、私の1票とあなたの1票の関係は問われません。問わないことが選挙の前提にあるからです。
「頼朝は義朝の子供」というのは、二人の関係を表しています。でも、それは頼朝のすべてを表しているわけではありません。更に頼朝を表すのに、「1147年生まれ」とか「鎌倉幕府初代征夷大将軍」とかを集めても、「頼朝」を表したことにはならないでしょう。「各要素間の相互關係」を集合論に取り入れることは面白いことですが、それは集合を考える時、すでに前提されていたことではないでしょうか。リンゴでいえば「《同じ》リンゴ」という抽象が前提となりました。そこに「《同じ》親子」という新しい抽象が加わっただけです。いくら抽象を重ねていっても「全体」にはならないのです。ここにも「部分を集めたのが全体」という発想が深く根付いている気がします。
P.72〜P.75にかけて「反射、對稱、移動」が述べられていますが、アリストテレスの「排反律、同一律、因果律」と似ている気がしました。
帰納と演繹
具体から抽象、抽象から具体への操作です。これは個別から全体、全体から個別へのアプローチとパラレルです。
学問は、その間を常に行き来しています。あるときは前者が、あるときは後者が優勢なだけです。しかしその動きは「学問が発展している」ということではありません。アリストテレスより現代の分子生物学者のほうが「進んでいて、正しい」とは思わないのです。子供が親より優れているわけでも、親が子より偉いわけでもないのと同じです。
部分と全体の関係を問い直すことが必要なのではないでしょうか。机の部品そのものは机ではありません。壊れた机は木の破片です。細分化する(部分に分けて探求する)学問、あるいは学問の細分化の意味をもう一度考えてみる必要があると思っています。
[著者等(プロフィール)]
遠山 啓
(とおやま ひらく、1909年8月21日 - 1979年9月11日)日本の数学者。東京工業大学名誉教授。数学教育の分野でよく知られる。熊本県下益城郡(現・宇城市)出身。
《書抜》
はしがき
第一章 無限を數える
「ガウスが無限の意義を軽視したとは思えない。たゞ、「野蠻人どものわめき聲」を恐れて非ユークリッド幾何學の公表を差しひかえたガウス一流の用心深さが、こゝでも「無限」に近よることの危險を本能的に感知したのかもしれない。」(P.3)__無限が印欧語の自我の延長と対応することを証明したい。
「數學者は論理によって肉眼の缺陷を補うのである。」(P.8)
「第一に我々の常識を驚かすのは「部分は全體に等しい。」という逆説である。」(P.17)__フラクタル図形。種と個体。
「こんなことは有限集合には決して起こる気づかいはないので、デデキント(一八三一―一九一六)という學者は部分が全體に等しいかどうかを、有限集合と無限集合とを區別する大切な目安にしたくらいである。」(P.17)
「集合の上に二本棒を書いて、集合の係數を表す流儀はカントールに始まるが、その理由は、集合から要素の個性と順序を無視する所から二本棒を書いたと言われている。つまり一本の棒は一囘の抽象を意味するものであった。」(P.20)
「集合論によって斷ち切られた各要素間の相互關係、すなわち社會性を囘復し、集合を單なる群衆から社會へと再組織すること、これが現代數學の次の課題であった。この仕事を引き受けたのが抽象代數學とトポロギーであった。」(P.48)
第二章 「もの」と「はたらき」
「すなわち木片から成り立っている「群衆」は駒と盤のつくる「社會」にまで進化する。そのような「社會」の憲法に當たるのがルールである。」(P.51)
「そこで問題となっているのは、「桂馬が何か」ではなく「桂馬はいかに動くか」である。何か(what)ではなくいかに(how)が重要である。」(P.51)
「相互關係を手がかりとする分類法はおそらく數學に特有なものであって他の科學には見かけないものであろう。」(P.72)__排反律?ちがう
(移動的)(P.74)__因果律
(反射的)(P.75)__同一律
第三章 つくられた空間
(P.112)__どうして距離は、二乗と平方根なのか。三次元は三乗と三乗根ではないのか。
アンリ・ポアンカレ「空間はなぜ三次元を持つか?」『晩年の思想』
第四章 初めに群ありき
「ボヤイはハンガリーの血氣盛んな陸軍士官で、書齋の學者ではなかったし、(FF)ロバチェフスキーも學生時代に學校黨局との間に騒ぎを起こしたことが傳えられている。彼等が野蠻人を恐れなかったのは彼等自身いく分か野蠻人だったためかもしれない。」(P.149)
「教育的勞働と官僚的な雑務がロバチェフスキーの天才を殺したのである。」(P.149)
「パースピレーション(汗)」(P.152)__perspiration
「唐人の寢言」(P.153)__何を言っているのかわからない言葉のたとえ。また、くどくどと筋の通らないことを言うたとえ。「唐人」は中国人、外国人のこと。ただでさえ言葉の違う外国人の寝言はまったくわけがわからないという意から。
「このようにして、圖形の表面的な關係から、背後にある群の方へと重點が移されて行った。一切の書かれた圖形は本來は運動し、變化する圖形の全系列の一斷面であり、いわば連續したフィルムの一コマにすぎない。」(P.167)


