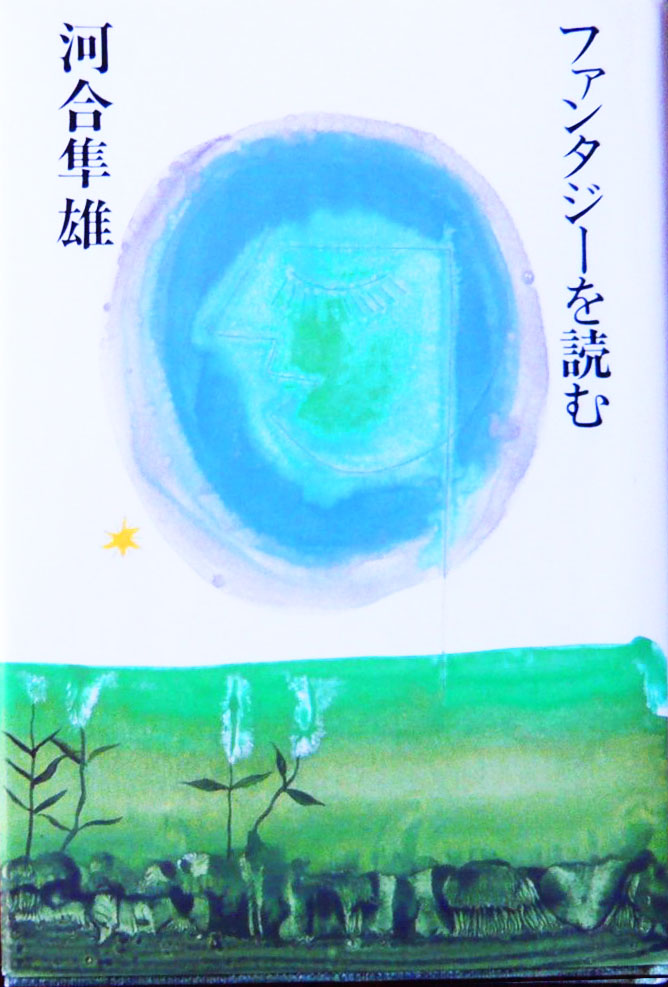
危険な本
いま、ちょっと限界に近づいています。「本を読んだら感想を書く」と自分に課したのですが、読んだまま棚においてある本が増えてきています。そのために、棚に25cmほどの専用スペースを確保したのですが、すでに溢れて、本の上に本が積み重なっています。
難しい本でなければ、本は1〜3日で読めてしまいます。ところが感想を書くのには、何日も、何週間も、場合によっては何ヶ月もかかります。いい本であればあるほど、書けません。頭がその本を吸収するには時間と経験が必要です。時間は勝手に経過していきますが、経験は偶然です。求めて得られるのもではありません。
そのうちに、本の内容を忘れてしまいます。(笑)
この本では、13冊の本が紹介されています。河合さんは文章がうまいので、どの本も面白そうに思えます。ついAmazonやBookoffで中古を探してしまいます。だって、原書(もちろん日本語版)を読まなければ、その本の本当の面白さも、河合さんの評価もわからないじゃないですか。大抵の本は、その本を読むと読みたい本が数冊できてしまうものです。
ちなみに、この本は図書館のリサイクルです。
ファンタジー
From Old French fantasie (“fantasy”), from Latin phantasia (“imagination”), from Ancient Greek φαντασία (phantasía, “apparition”), from φαντάζω (phantázō, “to render visible”), from φαντός (phantós, “visible”), from φαίνω (phaínō, “to make visible”); from the same root as φάος (pháos, “light”); ultimately from Proto-Indo-European *bʰh₂nyéti, from the root *bʰeh₂- (“to shine”). Doublet of fancy, fantasia, phantasia, and phantasy. (Wiktionaryから)
よくわかりませんが、ラテン語の"phantasia"(空想、想像)から来ていて、もともとは古典ギリシャ語の"φαντάζω"、"φαντός "、"φαίνω"、"φάος"、「見える」とか「見えるようにする」で、結局は古インド=ヨーロッパ語の「光る」から来ているということらしいです。
河合さんは、
「妄想とつくり話との間にファンタジーが存在しているが、それは心理的に言えば、無意識から湧き出てくる内容に対して、意識が避けることも圧倒されることもなく対峙し、そこから新しく生み出されてくるものがファンタジーである、ということになる。」(P.15)
と、ファンタジーを定義しています。
河合さんの物語論を読むのはこれが最初なので、詳しいことはわかりません。ファンタジーと似たものに、「昔話」「おとぎ話」「民話」「神話」などがあります。これらは作者がわかりませんが、「民衆の無意識」のようなものを設定し、そこから湧き出てきたものと考えることができるかもしれません。
「つくり話」としての小説や戯曲も、登場人物が「自律性」を持って動いているように見えなければ面白くありません。登場人物やストーリーが自律性をもって動くとき、そこには無意識から湧き出してくるものが在るのではないでしょうか。絵画などの芸術作品(と言われるもの)の制作過程でも、筆や絵の具の自律性が現れるような気がします。まあ、このへんは「無意識」をどう捉えるかの問題でしょうね。
意識
「自分」・〈自我〉を形作っている「意識」ですが、皆さんはどのくらい「意識的」に行動していますか。「寝ているとき以外は、ちゃんと意識を持って生きている」でしょうか。
ロボット(コンピュータ)に「物を掴ませる」ことは、とても大変です。方向、手の角度、動かすスピード、握る強さ、・・・。すべてを設定して、なんとか掴ませることができます。でも、人間が何かを掴むとき、そんな事を考えているでしょうか。
もっと人間にとって簡単なこと、歩くことはロボットにはもっと難しいです。体重移動や、関節の動きだけじゃなく、視線の制御や手の動きなど、全身が関係しています。でも、「右足を出して、おろして、左足を・・・」などと考えてしまっては、人間は歩くことができません(実際、そういう状況になる人がいます)。
「背中(頭)を掻く」なんてことは、「無意識」に手が動いて、「事後的に」「かゆいなあ」と思うことも多いのではないでしょうか。そして、普段意識しない「手の存在」は、手の怪我や病気で突然現れるのではないでしょうか。
筆者は、およそ病いはすべて意味をもっている、と考えるほどになった。(P.29)
さいきん、私はあちらこちらが、痛かったり痒かったりして、自分の体を認識することが増えました。「老けたなあ」と思うのです。
私は、人間はほとんどの行動を「無意識」に行っていると思います。何かを考えているときはあります。この文章を書くとき「意識的に考えて」います。でも、その意識はどこから生まれてくるのでしょうか。
何かを決断するとき、「意識的に考えて」決めているように思います。でも、その判断を「論理的に」説明できるでしょうか。もし、それができるのなら、「コンピュータ」にプログラムすることができます。どうも最近の風潮は、「今はできなくても、いずれできる」と考えているようです。そうなれば、人間は「判断」する必要がなくなります。コンピュータが「正解」を出してくれるので、人間はそれに従えばいいのです。
コンピュータの能力が人間の脳に達して追い越す地点を「シンギュラリティ」と呼ぶそうです。そして、それを歓迎する人と、それに危機感を感じる人がいるようです。
私はどちらにも与しません。「論理」というのは、西欧文化の形態に過ぎないと思おうからです。「三段論法」や「因果律」などの論理は、一つの考え方に過ぎないのです。別の文化には、西欧から見たら「非論理的」な考え方があるのです。数学は、世界共通だと言う人がいます。でも、「1たす2は3」というのは、「1」を決めて「2」を決めて、「たす」をきめれば「3」である、と決めたに過ぎません。簡単に言えば、「3」がない文化では、「1だす2」は「たくさん」なのです。
ここで「西欧文化」と言っているのは、インド=ヨーロッパ語圏の文化という意味です。当然インドは含まれます。中国は入らないでしょうが、中国語の構造はかなり似ていると思います。
因果関係は、原因と結果です。すべてのものに原因と結果が在るという考えは、西欧的なものです。実際、因果関係を探すことは、小さい頃から学校で教わりますが、人生で思ったとおりに事が運ぶことなど、偶然の重なりに過ぎないのではないでしょうか。「事後的に」因果関係をつけることは可能ですが。
論理と文字
一緒にしてはいけないのは、「論理」「考える」「言葉」です。
論理は「ロゴス(λόγος)」です。ロゴスにはたくさんの意味がありますが、基本は「言葉」です。でも、わたしたちは言葉で考えているのではありません(『言語なき思考』H.G.ファース、『言葉のない世界に生きた男』スーザン・シャラー)。
「音がない」という意味でもありません。殆どの「行為」や、その基となる「意図」は「事後的」に現れるということです。
コップを持ち上げて、コーヒーを飲んだとき、「こっぷをもちあげよう」「こーひーをのもう」と「言葉で」考えますか。言葉にしないと動けない人もいるでしょうが、大抵は「言葉」にはしません。「いま何をしたのですか?」と聞かれたときは、「コップを持ち上げてコーヒーを飲みました」と答えられますが、言葉にするのは事後です。実は考えていないのです。だから、新聞を読みながらでも、テレビを見ながらでも、夕食のメニューを考えながらでもコーヒーを飲むことができます。
それを言葉で、日本語で、考えていると錯覚するのは、普段「文字」と接しているせいです。同じ状況で、「What are you doing?」と聞かれたら、英語が得意な人は英語で答えるでしょう。手話で聞かれれば、手話ができる人は手話で答えるでしょう。少なくとも行為は言語に規定されないのです。
だから、そこには論理はありません。因果関係もありません。
コーヒーを飲もうとしたら、コップが空っぽだったらどうでしょう。「コーヒーを入れなくっちゃ。もうコーヒー豆がなくなったから、買いに行かなきゃ・・・」とか「隣の人のコーヒーがある。飲んじゃおうかな・・・」となっていきます。そうするとどこかで「社会性」が発生します。どこかで「言葉」が必要になります。
そのときに、「論理」や「因果関係」が発生するかどうかは、文化によります。つまり、「言語」によるのです。貨幣経済でなければ買いに行くことはないし、所有・占有関係が全くなければ隣の人のコーヒーを飲むのが当たり前かもしれません。
無意識
「無意識」というのはおかしな言葉です。意識していないことは、意識できない、つまり、認識できないのです。それは同時に、「意識」以外のもの、意識に対立しているものがなければ、意識を意識・認識することはありません。「赤」を認識するのは、「赤以外」のものが在るからです。寝ている状態と起きている状態、気絶している状態と気絶していない状態、酔っている状態とシラフの状態、というような意味での「意識」は考えられます。
フロイトの無意識はちがいます。起きているとき、シラフのとき、正気のときに「意識」を侵略しようとする「あがなえない力」です。それは、フロイト自身が、精神的に「正気と狂気」の間を行き来し、「自我」の崩壊を、つまり「意識」を極端に「意識」したから生まれた概念ではないでしょうか。つまり、「自意識過剰」だったわけです。
フロイトはそれまで「排除」されるだけだった「狂気」、それも「自己の中の狂気」と「折り合い」をつけようとしたのです。その狂気は、ある場合には「精神病」あるいは「ヒステリー」として現れ、あるいは「夢」として現れます。夢の中では、普段の「理性的」は自分は影を潜めます。フロイトは患者の夢を解釈しようとしますが、それは彼自身の夢を解釈することであり、彼は患者以上の夢を見ていたのではないでしょうか。
そのフロイトの理論を受け継いだユングは河合さんの先生です。私はユング以降の精神分析には詳しくないので、シュルレアリスムの話をします。
シュルレアリスムの理論的指導者、アンドレ・ブルトンはフロイトのもとに訪れています(1921年?)。シュルレアリスムの代表的な表現技法に「自動記述(Automatic writing、Automatisme)」があります。シュルレアリストは無意識や狂気の広大な領域を全面的に認めました。それは、欲望を全面的に認めることでもありました。しかし、ブルトンはその無意識を利用し、組織化し、制御しようとしました。フロイトが無意識に名前をつけ、意識を「イド」と「超自我」に挟まれた狭い領域に押し込み、無意識を「分析」「解釈」しようとはしましたが、統御できるとは考えていなかったのではないでしょうか。それはあくまでも「意識外」のものですから、意識が行えるのは、せいぜい「わからないなりに」「折り合い」をつけることだけです。
芸術家が作品を生み出す瞬間は、「それは人間が考え出すものではなく、どこか他の世界から、人間の心の中に湧き出てくるものなの」(P.14)なのです。それは「陶酔」「エクスタシー」なのです。それを作品にするためには、「無意識の圧倒的な力に耐えてゆくため、ファンタジーの作家は強靭な意識をもたねばならない」(P.17)のです。陶酔したままでは作品はできません。圧倒的な力に負けると、帰れない「狂気」の領域に埋没してしまいます。統合失調症、アルコール中毒、ギャンブル狂、薬物中毒などその形態は様々ですが。
しかし、「湧き出てくるもの」に意識を介入させることは、湧き出てくるものの「純粋性」を阻害します。欲望の絶対性・全体性に反するものだと思います。そこにブルトンとバタイユの差が在ると思うのです。
多層としての現実
「単層の現実は、自分から切り離した存在として記述することができる。そのもっとも精密なものが自然科学である。現実の多層性に目を向けるとき、それは観察者の個性と関連してきて、「物語る」ことによってしか他人に伝えることができないのである。」(P.16)
「現実の多層性」は、理論化(論理化)を拒否します。夢の中では、重力に逆らって空を飛び、自分は風に姿を変えます。それは、分析したり、分類したり、解釈したり、説明したりすることを拒否します。あえて行うとすれば「物語る」ということでしか表現できないものです。それを統御(制御)するとき、「語り」は「つくり話」になります。少なくとも、単層(一般的に「現実」と言われているもの)でしか描かれない「物語」は面白くありません。
その単層の世界の「自然科学」、つまり「ある一つの層」の現実のみを唯一のものだと考えてしまうと、夢の世界や狂気は「否定すべきもの」としてしか存在しません。でも、自分の中の狂気を否定し、捨て去ることができないというのが、フロイトの「無意識」の考えであり、「イド」の存在です。
実際には、「絵空事」と思いながらも、多くの人がファンタジーや昔話に心を惹かれます。小説や、テレビや映画を「絵空事」としてその存在を否定してしまう人は、むしろ少ないのではないでしょうか。
そのこと(そのもの)を河合さんは、「たましい」と呼んでいます。それは西欧流の「霊魂」とは違います。
「筆者が最近考えていることは、ーー先に述べた「割り切る」との関連で言えばーー人間存在を身体と心とに割り切って考えた場合、どうしてもそこに取り残されるもの、あるいは、身体と心というものを統合して、一人の人間存在たらしめているもの、それがたましいである、ということである。」(P.24)
物質と精神とを統合しているもの、それは他者(社会)と自己とを結べつけるものでもあります。それが「人間」を「人間存在たらしめているもの」と河合さんはいいます。
それは、とても東洋的なものをふくでいるように思います。自然、社会、人間、そして個人をつなぐものが「たましい」です。フロイトが「意識」の役割に求めたのは、超自我とイド(無意識)との仲介(調停)であって、「自然」との関係という視点は薄かったのではないでしょうか。
若者と老人
『ゲド戦記』は読んだことがありません。とても面白そうですね。「少年文庫版」でも字が小さくないでしょうか。やっぱり単行本の中古を買おうかな。
河合さんが読み取ったテーマのうち、私が興味のあるのは2つ。一つは、人間が生まれ、成長し、年老いて死ぬということはどういうことか。もう一つは、生きていく上での深い闇を竜や女性で表現していること。
若いうちは、勢いで行動することがあり、ある意味で「自分本位」であり、老人を「情けない」と蔑んで見るところがあり、自分が老人になったときには深い洞察で行動し、最終的には次の世代にすべてを引き継で行きます。河合さんはそれを「人間としての当たり前」のように捉えていますが、私はそうは思わないのです。
老人を敬うか疎んじるかはその社会の文化によって様々であることを、ボーヴォワールは『老い』で描いています。そして、それぞれの社会で、「なぜそうなのか」を説明しています。「労働力にならなく、食料を消費するだけ」「表面的には敬いつつ、機会があれば老人の財産を奪おうとしている」等、その理由づけは様々です。
気をつけなければならないのは、歴史的文献や民俗学(人類学)的資料を読むとき、まずは文章化した人の主観がどのくらい入っているかを疑うこと。そして、ボーヴォワール自身が、現代のフランス社会と彼女自体の思考のフィルター・フレームで「解釈している」可能性が在るということです。
「成人の儀式」は、私の知る限り、どんな社会にもあります。男子にも女子にもありますが、女子は初潮と結びついていることが多いようです。男子の儀式はよく取り上げられますが、それは文字やマスコミが未だに男性中心であることも大きな要因だと思います。割礼やバンジージャンプを「自分のこと」として感じる人が本を書き、放送を作っているからです。
成人儀礼があるということは、「大人」と「子ども」の区別があるということでしょうか。ただ、その境目はまちまちです。そして、成人儀礼が強制なところもあれば、それを受けるかどうかを子どもが決めることができるところもあるようです。子供の「自主性」「主体性」を「育てる」とか「尊重する」とかいう社会でも、ある年齢に達すれば強制的に「大人にする」、あるいは成人儀礼を受けさせる社会もあります。
『老い』を読んでいると、とても暗い気持ちになるのですが、ボーヴォワールは前提としてるようで、問題としていないのは、若者が老人を「自分の将来の姿」だと思っているかどうかです。誰だって「自分は年を取らない」とは思っていません。喜ぶ、喜ばないかに関わらず「誕生日」というイベントはあるのです。
『LIFESPAN(ライフスパン): 老いなき世界』(デビッド・A・シンクレア、マシュー・D・ラプラント著)という本を面白く読みました。「そんなことがあったらいいな」「ありえるかも」とも思いましたが、世代交代をして「種」を継続していくのが生物です。だから、「老いない」ということは「生物のあり方に反する」ということになります。遺伝子学や分子生物学が解明したのは老いる仕組みの一部ですが、前提として「老いも生命に組み込まれている」ということを忘れてはいけないように思います。
日本を例に挙げてみます。若者は自分が老いることを知っています。自分の両親やテレビや本でも見ています。でも、「老人は古くて汚くて、何もできない」と思っています。自分は親と違って「新しい」ので、「親より優れている。正しい。」のです(そして、消臭剤によって「匂い(臭い)」もない)。新製品は旧製品より「新しくて優れている」のが当たり前のように。科学は進みます。昨日できなかった「がん治療」が「明日」はできるようになるかもしれません。親は「ボケ」ても、自分が年を取る頃には「アルツハイマーの特効薬」ができているかもしれません。平均寿命は伸びて、自分は親より長生きをし、「ボケ」ることなくいつまでも生きていけると思っています。私はそう思っていました。そして、老人になるくらいなら、若いうちに死のうと思っていました。
死なずに老人になってしまった今、若者達から疎んじられるようになって、「私の考え方は間違っていたのかも」と思っています。どうも「新製品」は「旧製品」より品質が良くなっているようではないのです。まず、よく壊れます。昔は構造が簡単だったこともあり、なかなか壊れませんでした。そして、壊れても修理が可能でした。今は壊れることが前提です(3年保証、5年保証が当たり前になったのは、壊れるのが前提だからです)。壊れなくても「性能がいい新製品」が「新規格」で登場します。旧製品は壊れていなくても使い続けることができないのです。
本からラジオ、白黒テレビからカラーテレビ、地デジ、ハイビジョン・・・と、どんどん新規格の新製品が現れます。さて、本とハイビジョンを比べると、情報量は格段に増えています。それでは、人々の認識や思考は深まったのでしょうか。どうもそうは思えないのです。今は、行ったことはもちろん、存在すら知らなかった街の美術館に収蔵されている絵をネットで見つけて、カラーで見ることができます。でも、それで私の認識は広がったのでしょうか。私は「広がった」と思っていたのですが、それでは白黒の図版でしか見れなかった頃の人は、その絵の良さがわからなかった、とは思えなくなってきたのです。むしろ、私は白黒の図版からその絵の良さを見る能力を失ってしまったのではないかと。
かすかに残っている私の能力は、書や水墨画の良さをいくらか感じさせてくれます。でも、ゴッホやモネの良さは白黒写真ではわからないでしょう。
脳神経の細胞数は、生まれた瞬間からどんどん減っていくと言われます。それを補うようにシナプスの数が増えていくのだとか。多分それが「死に向かって生きていく」ということなのだと思います。そして、記憶量は有限です。忘れることによってしか、新しい情報は保存されないのではないでしょうか。
能率的で効果的な学習法は、あるのかもしれません。重い辞書を引かなくても、ネットで検索すれば答えは得られます。でも、辞書を引くというのは「引く」という行為自体が意味を持っています。その時間自体が意味を持っていると思います。「100ページくらいの右の上段真ん中」という場所の感覚や、隣りにある単語との関連などもネットではありません。
過程がなくて得られた結果の持つ意味はとても軽いのです。だからすぐ忘れてしまいます。親はそれを知っています。でも親としては「忘れてもいいから、目の前の受験が大切」と思ってしまいます。それが子供のためにならないことは、薄々わかっていても。
女性
河合さんが「女性」というときには、多分「女性性」のことだろうと思います。ただ、ユングとフロムの関係や、一般書として難解さを避ける意味で「女性」と表現しているのではないでしょうか。
女性性は、女性にのみあるわけではありません。
「男性にとって大切なことは、このような闇の世界を、「女のものであって自分のものではない」と思うのではなく、自分のなかにあるものとして知り、手さぐりで調べてゆくことである。ただ、そのような奥深い世界に至るには、内なる女性の手を借りねばできないのであるが。」(P.281)
と河合さんが言うとき、「人間の中にある闇を手さぐりで調べていかなければならない。そのときには〈他人(他者)〉の手を借りなければならない」と読んでいいと思います。
女性の方が、「闇」とそれに見合う「慈悲」を備えているのかもしれません。でも、それは問題ではありません。その「闇」こそが「無意識」であり、そこから「湧き出てくる」のが「ファンタジー」なのではないでしょうか。
ファンタジーは、「語り得ないものを語ること」であり、「たましい」、そして、〈内なる自然〉と〈外なる自然〉の「自己表出」なのではないでしょうか。
[著者等(プロフィール)]
河合 隼雄
(1928-2007)兵庫県生れ。京大理学部卒。京大教授。
日本のユング派心理学の第一人者であり、臨床心理学者。文化功労者。文化庁長官を務める。独自の視点から日本の文化や社会、日本人の精神構造を考察し続け、物語世界にも造詣が深かった。著書は『昔話と日本人の心』(大佛次郎賞)『明恵 夢を生きる』(新潮学芸賞)『こころの処方箋』『猫だましい』『大人の友情』『心の扉を開く』『縦糸横糸』『泣き虫ハァちゃん』など多数。
なぜファンタジーか
「それは人間が考え出すものではなく、どこか他の世界から、人間の心の中に湧き出てくるものなのである。」(P.14)
「ファンタジーはそれ自身の自律性をもって、われわれに迫ってくる。」(P.14)
「この逆にファンタジーの自律性が少なく、頭で考え出した作品は、「つくり話」というべきであって、筆者が問題としているファンタジーとは異なるものである。」(P.15)
「もっとも、「つくり話」はそれ相応の評価があるべきで、特に商業価値としては非常に高いものもある。ただ、筆者にとっては興味のない領域である。」(P.15)
「妄想とつくり話との間にファンタジーが存在しているが、それは心理的に言えば、無意識から湧き出てくる内容に対して、意識が避けることも圧倒されることもなく対峙し、そこから新しく生み出されてくるものがファンタジーである、ということになる。」(P.15)
「単層の現実は、自分から切り離した存在として記述することができる。そのもっとも精密なものが自然科学である。現実の多層性に目を向けるとき、それは観察者の個性と関連してきて、「物語る」ことによってしか他人に伝えることができないのである。」(P.16)
「無意識の圧倒的な力に耐えてゆくため、ファンタジーの作家は強靭な意識をもたねばならない。」(P.17)
「つまり、述語論理は論理的には間違いであるが、印象的なことを相手に伝えたり、感動をもたらすためには潜在的に用いられているのである。」(P.20)__市川浩『身の構造』1984、青土社、河合隼雄『宗教と科学の接点』1986,岩波書店
(P.21)__よく出てくるけど、なぜ?超自我に対する自我の防御?
「そのように、割り切ってものごとを考える考え方に抗するところにこそ、ファンタジーの重要な特性があるのではなかろうか。」(P.23)
「筆者が最近考えていることは、ーー先に述べた「割り切る」との関連で言えばーー人間存在を身体と心とに割り切って考えた場合、どうしてもそこに取り残されるもの、あるいは、身体と心というものを統合して、一人の人間存在たらしめているもの、それがたましいである、ということである。」(P.24)
「たましいそのものをわれわれは知ることができない。たましいは何かにつけて明確にきめつけることに抵抗する。」(P.25)
Ⅰ キャサリン・ストー『マリアンヌの夢』
「一見、損をしたように見えるけれども、長い目で見た場合、得たところのほうが大であると思えるのである。このような考えを拡大して、筆者は、およそ病いはすべて意味をもっている、と考えるほどになった。」(P.29)
「人間は成長するためには秘密をもたねばならない。」(P.33)__私にはそれができない。
「大切なものは自分の力で守らねばならない。」(P.33)
「しかし、誰かが私に向かって、「どうしてそこに居るのか」、「どこから来たのか」と問いかけてきたとき、私は本当に答えられるだろうか。私がこの世に「居る」ということは、階段のない二階に居るようなものではないだろうか。」(P.34)
「マリアンヌが病気になったり、ふと絵を描いたり、つまり本人の意志や行為が、たましいの顕れ方を規定すると共に、たましいはたましいで自律的なはたらきをもつ。そして、両者のぶつかりの中で愛が創造されるのである。たましいはそれに関心を向けない人には、その姿を顕さない。あるいは、常にいろいろな形で顕れているのだが、見えない人にはさっぱり見えない、と言うべきだろう。」(P.35)
「しかし、たましいというわけのわからぬ存在を、われわれの人生の出来事の背後にあるものとして考えてみると、随分考えやすいし、人生の見方が面白くなってくるように思う。」(P.37)__フロイトの無意識と同じ。仮定すると説明しやすい。いろいろなものが説明できる。は仕事しての仮説。仮定は最後には捨てなければならない。心象、心像と外的存在との一致
「たましいのことは「たましいの導者」以外には語ってはならないのである。」(P.41)
「実際、すべての人は「二つの世界」に属しているのだが、どうしても一つの世界しか見えない人が多すぎるのである。」(P.42)
Ⅱ ルーマー・ゴッデン『人形の家』
(P.71)__商品というものが私に語りかける。それは私の声か商品の声か、商品所有者の声か。区別することはできない。どれでもである。
Ⅲ リンドグレーン『はるかな国の兄弟』
(P.80)__死後の世界がなくて、命をかけた行動ができるか。自我がなければ可能。自我があるときは、死後の世界も執拗。
「ヨナタンの勇気は、自分の運命に従って生きる強さによっても支えられている。そして、人の運命を尊重する限り、ある人の命を永らえる方に努力するのが、人間の努めというものであろうか。」(P.91)
Ⅳ ポール・ギャリコ『七つの人形の恋物語』
「簡単に他人の笑いを引き出すような方向を拒否したときに、自分のつくり出したものは個性を発揮しはじめるのだ。」(P.100)
「そこには自己への道に深く足を踏み入れた者が必ず体験せねばならない、強烈な自己破壊と自己救済の葛藤が存在した。」(P.108)
「しかし、ミチェルが人形たちのもつ自律性に気づき、その動きを許容したところから、彼の自己への道が開かれてくる。」(P.113)
「七つの人形は最後のところでムッシュ・ニコラが解説してみせるように、ミシェルという男のいろいろな属性であり、それはそれなりの自律性をもつものの、ある程度、ミシェルの支配に従うものである。しかし、ミシェルの分裂を癒やすためには、これらの人形だけでは不十分で、ミシェルにとってもっと他者性を強く有するムーシュという女性が必要であった。」(P.114)
Ⅴ E・L・カニグズバーグ『エリコの丘から』
「「私が私である」という現実を深く深く支えるために、人間はファンタジーを必要としている。」(P.118)__「現実」ではなく「文化(文字)」である。
(P.119)__クローンと「選択」。多様化とは何か。
「私が私であることを実感するため、「私は父である」、「私は教授である」、などというとき、それは他者の存在を必要とする。」(P.123)
「他人の目を気にするとき、われわれのアイデンティティは「私の」ものから「皆の」ものに移行し、クローン人間に近づくのではなかろうか。」(P.123)
「しかし、死者の目をあざむくことは不可能だ。」(P.124)__死者の目は自分の目。自分に嘘はつけない。パノプティコンは自分の目。内在化した他人。
「このことを知らないために、生前は眉間にしわを寄せて、忙しく忙しく立ちまわっているうちに、文字どおり「我を忘れ」、アイデンティティは拡散してしまうのだ。」(P.125)
「彼女のアイデンティティ確立に必要だったのは、レジナ石がシンボルとして意味していることであり、その意味を知ったときにはダイヤは無意味になる。シンボルはその意味を人間源が明確に把握したときに、もとの「もの」にかえってしまう。「もの」としてのダイヤはエマシーンに必要だったのだ。」(P.137)__お金が「紙切れ」であると明確に把握するのはいつだろうか。
Ⅵ フィリパ・ピアス『トムは真夜中の庭で』
「秘密が秘密でなくなったら、その効力は失われてしまうのだ。」(P.144)
「わたしたちはみんな、じぶんのなかに子どもをもっているのだ。」と述べている。これにつけ加えて、私は「子どもたちのなかに大人も老人も居るのだ」とつけ加えたい。」(P.159)
「たましいの国の「とき」は円環的、全体的で、直線的な流れから自由になっているはずである。」(P.159)
Ⅶ メアリー・ノートン『床下の小人たち』
(P.163)__ペットは小人?
「しかし、少し視点を変えるならば、人間がにわとりの卵を食べるとき、それは「盗み」なのか「借り」なのか、あるいはそのどちらでもない何かなのか、言うのが難しくなってくる。」(P.167)
「それはやはり、まちがいにしろ大切な真実を内包しているからである。」(P.170)
Ⅷ M・マーヒー『足音がやってくる』
「マーヒーによると、家族一同が全部魔法使いなのではなく、ある(FF)家のなかに、ときどき魔法使いの系統をひく人間が生まれ、その人間はどうしても家族との関係がうまく持ちにくいというのである。」(P.190-191)
「「身内」というのはいい言葉である。それは自分という存在の内部という意味ももっている。」(P.201)
Ⅸ G・マクドナルド『北風のうしろの国』
「未分化な存在」(P.211)__「分ける」「分かる」
「(・・・)親切と残酷の基準ということもあいまいであることをほのめかす。」(P.212)
(P.213)__インドのバクシーシの女の子
「マクドナルドにしろ宮沢賢治にしろ、じぶんの体験したことを基にして語っているのだ。」(P.226)
「やはり、母と子だけで海辺に行く(FF) ような、言わば、あちらとこちらの中間地帯の体験のようなことを必要とするものである。」(P.217-218)__海に叫ぶ=>いまは?どのように変化してきているか。遊園地、窓からの夜空。海、あるいは非日常。どんなドラマにもある。考える場所、場面
Ⅹ アンリ・ボスコ『犬のバルボッシュ』
(P.230)__大人の世界と子どもの世界。文字以前にもあったかもしれない。なかったとおもうけど。
「言葉のない犬だからこそこんな言葉が言えるのかもしれない。「ここにいる」ということ、それがすべてなのだ。」(P.231)__自分ではなく、対象(犬)が表現している(ように見える)。表現しているのは自分。他人も自分が表現している。他人の心を感じることができなければ、他人の言葉は理解できない。
(P.235)__感情と言葉と文字。言葉(ロゴス)で理解しなくては。論理的に「納得」しなければならない。感じるだけではだめだという観念。それを表現できない。言葉にしなければ、感じられなくなっている「理解しなければならない」という束縛。対象に見る原初の感情、それは対象も実際に感じているし、人間の感情のもとになっている。
「星の本当の美しさを知るためには、それ相応の仕掛けを必要とするのである。」(P.237)
(P.240)__歩くことと車輪
Ⅺ ル=グウィン『影との戦い ゲド戦記Ⅰ』
(P.250)__アシタカ
(P.252)__内界と外界の区別など、文化が決めたことだ。
Ⅻ ル=グウィン『こわれた指輪 ゲド戦記Ⅱ』
「明確な個の意識は、人間が死の体験という犠牲の上に獲得したものなのである。」(P.280)__成人の儀式が念頭にあるのかもしれない。あるいは思春期。子どもから大人へ、大人から悟りへ。
「愛憎の二面に引き裂かれるような体験をせずに、女性の成長はありえないのではないだろうか。」(P.280)
「地下の大迷路は女性の神秘を表すのにふさわしい。大宝庫をもっているが、多くの者はその宝を手に入れる前に死んでしまうのだ。男性にとって大切なことは、このような闇の世界を、「女のものであって自分のものではない」と思うのではなく、自分のなかにあるものとして知り、手さぐりで調べてゆくことである。ただ、そのような奥深い世界に至るには、内なる女性の手を借りねばできないのであるが。」(P.281)
「人間の死に対する抵抗は実に強いものだ。」(P.287)
ⅩⅢ ル=グウィン『さいはての島へ ゲド戦記Ⅲ』
「「誰が正しいか」とか「どちらが悪いか」という問いにではなく、その「意味は何か」という問いに答えようとするのである。」(P.305)
「竜はまた、ことを為さない。彼らは在るだけだ。」(P.306)__『ゲド戦記』からの引用
「延命装置は、「永遠の別れ」や「いつか再会する願い」などの多くの夢をぶち壊し、死んでいく人を他の人から遠ざけてしまうのである。」(P.309)__コロナ禍での死。
あとがき
〈end〉


