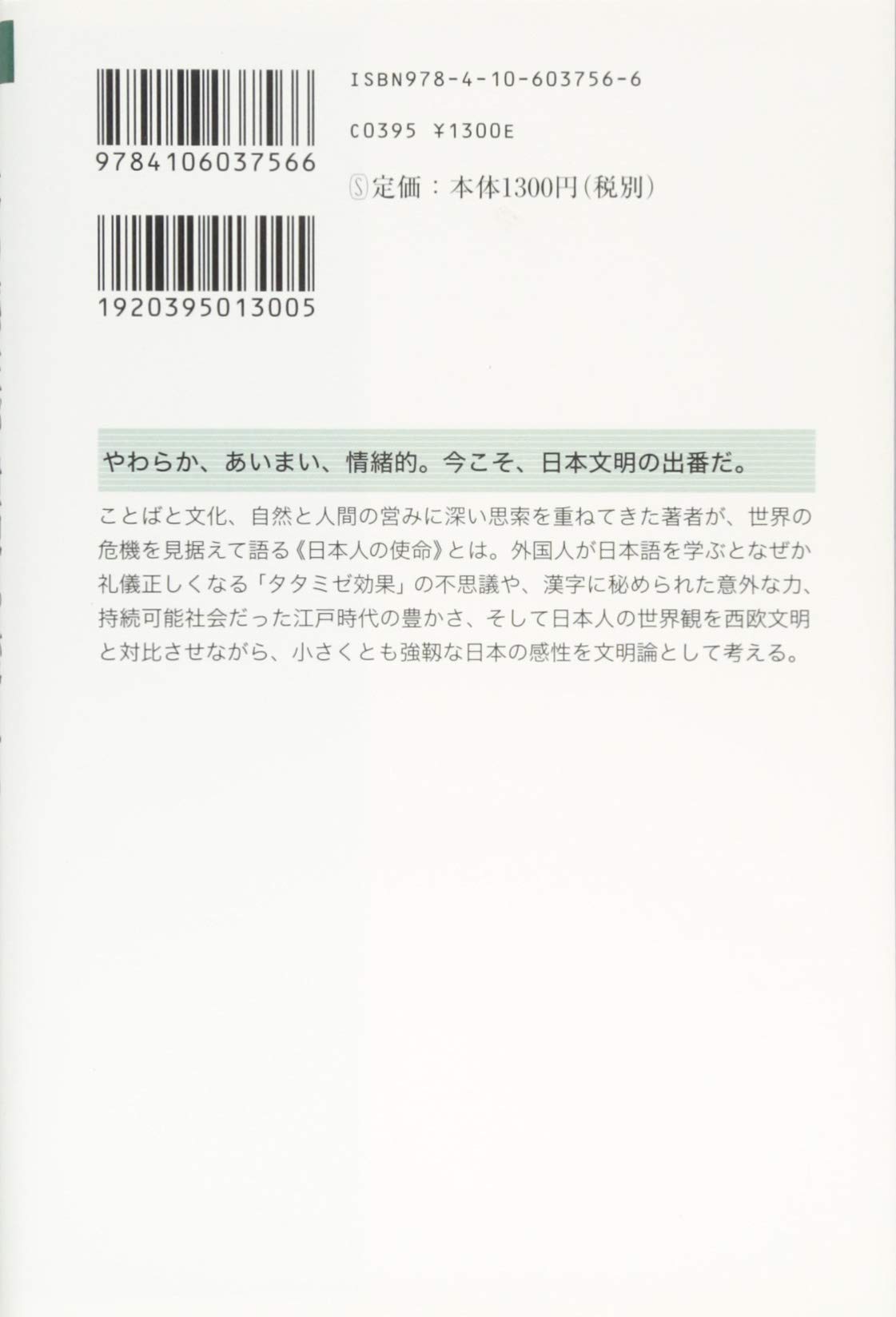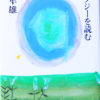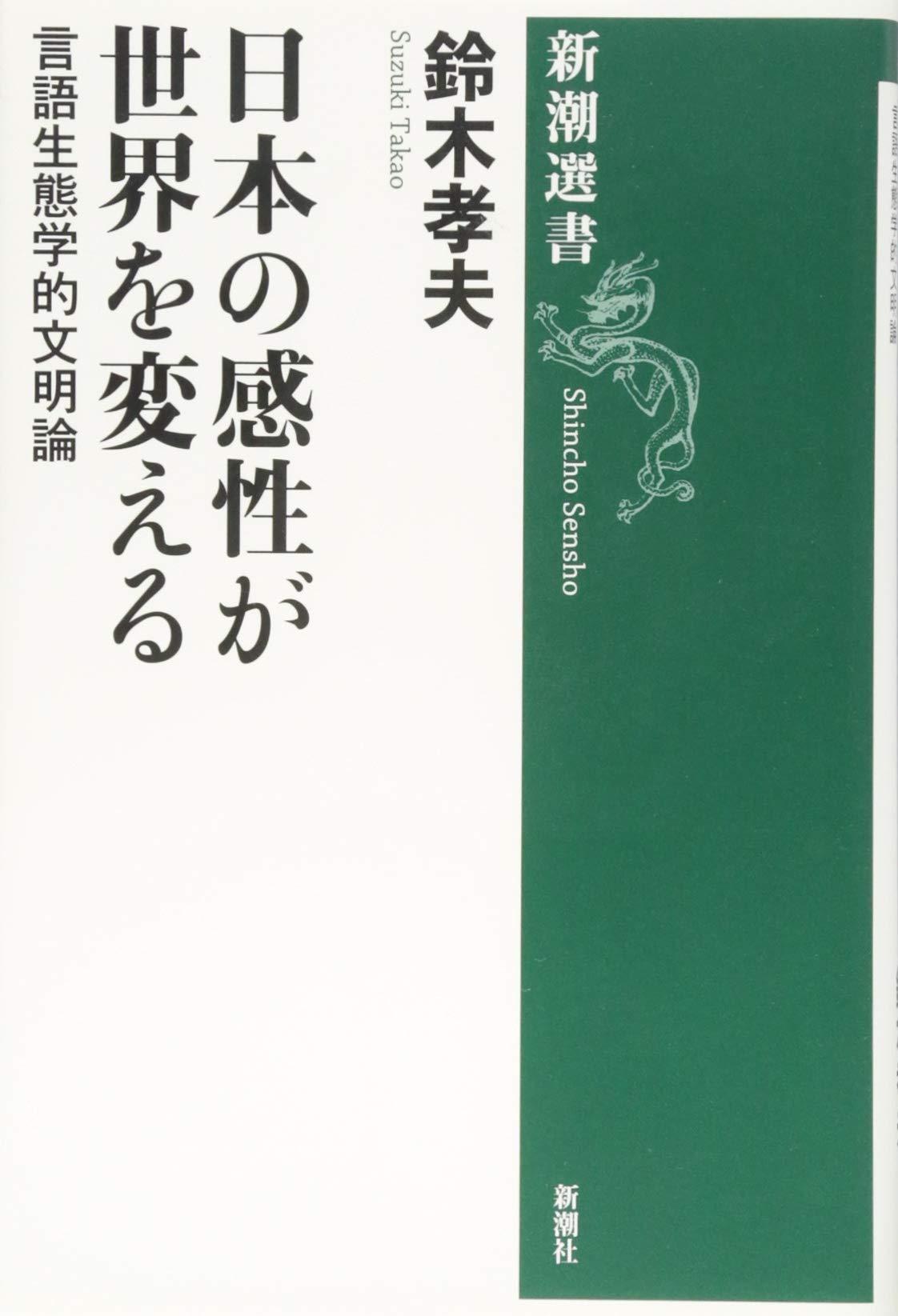
問題の所在
この人間中心主義(または人間至上主義)に裏打ちされた、理性と論理を極端に重視する西欧文明が、いろいろな点で行き詰まりを見せ始めているからです。(P.9)
地球温暖化に代表されるような環境破壊が進んでいます。「人間至上主義」・西欧論理主義がその原因で、日本語がそれを変える力を持っているという、言語学者・日本語学者としての鈴木さんの本です。
鈴木さんは、『ことばと文化』(1973/05/21 岩波新書)で、すでに日本語の特殊性を強調しています。本書の前に『ことばと文化』を読まれることをおすすめします。そうすれば、本書の「日本語至上主義」的な論理に至った理由がわかりやすいと思います。
日本語は「論理的じゃない」と言われ続けています。「主語がない」ということが常に取り上げられます。鈴木さんは、日本語における主語を『ことばと文化』で丁寧に解説しています。日本語を印欧語(インド=ヨーロッパ語)の文法に当てはめて「主語はないのではなく省略されているのだ」とか、日本語をこねくり回して印欧語の論理に当てはめ「人が日常使っている言語のなかに非論理的な言語はなく、言語の非論理的使用があるだけだ」と豪語したり(『日本語と論理 哲学者、その謎に挑む』飯田隆著 2019/09/10 NHK出版新書、P273)、それでも自分が納得できない場合は、「新しい文法用語」を作ったりします(日本語用の文法用語が結構ありそうです)。
「文法」というのは、印欧語圏で印欧語を説明するために作られたものです。そして欧米に於いても、自国の言語をきちっと「文法」に当てはめることはとても難しいようです。
上記の文章で、「理性」と「論理」と言う言葉が出ています。論理は「logic(λόγος)」です。「ロゴス」は「ことば」です。ですから、人間を特徴づけている「ことばの使用」が「自分たち人間とは何か」を考えるときには「論理」つまり「ロゴス・ロジック」がとても重要なのです。「考える」こと自体が「言葉」を使うという矛盾がそこにはあります。
「理性(ration、reason)」はラテン語の「ratio」ですが、これはギリシャ語の「λόγος」を当時のラテン語に当てはめたものです。つまり、「論理(ことば)」と「理性」はもともと同じものです。ただ、言語が違うということは文化が違うということです。「みかん」と「オレンジ(orange)」は違いますよね。日本で昔から栽培されている「みかん」とヨーロッパで栽培されている「orange」が異なるように、地域が違う、自然が違う、文化が違うと単語の意味は変わるのです。
でも、それをもってして「日本のみかんはオレンジじゃない。日本のみかんは偽物だ」とか「日本のみかんは劣っている」というのは滑稽ですよね。でも、多くの言語学者がそれをやっているのです。日本のみかんをヨーロッパのオレンジに近づける努力です。
インプリンティング(刷り込み)
小学校入学前から、「正しい日本語」や「論理的説明」を刷り込まれている私たちが、そこから抜け出すことはとても難しいことです。
未だに日本の知識人の多くが殆ど無意識の、動物行動学で云うインプリンティング(刷り込み)にも比すべき、西洋の文化文明と欧米人の物事のやり方や考え方こそが、人類の在り方としては最も普遍に近い至善至高のものだという、幕末明治維新の頃に叩き込まれた考えに支配されているからだと私は思うのです。(P.13-14)
と鈴木さんは言っています。
私は、戦後の「民主主義教育」というものを受けてきた人間です。そこでは、「戦争はいけない」とか「平等で自由な社会でなければならない」と教えられました。「正義を貫かなければいけない」とも。日本の政治、社会の不正、不平等は明らかです。学生運動はほぼ終わっていましたが、戦後の民主主義教育を受けていれば、社会に反抗するのは当然です。義務とすら考えていました。
でも、「自由」「平等」「民主主義」などは、西欧社会が考え出したものです。それが人類にとっての「終局的真理」でしょうか。
社会を動かしている「西洋論理」と自分が学んだ「自由」「平等」とが「矛盾」していると思うのは当然だと思います。その矛盾を説明するのに「建前と本音」などが持ち出されました。最近なら「忖度(そんたく)」ですね。そして、日本の文化を説明するために、「単一民族説」や「島国根性」などの言葉が用いられました。
私は、単一民族なんてありえないだろう、でもたしかに島国根性だよね、という程度にしか考えていませんでした。そして「戦争」「不自由」「不平等」「不正」は、「悪いこと」と考えていました。でも、どうして「反戦」「自由」「平等」「正義」が「なぜ正しいこと」なのかは説明できませんでした。
どうやら日本国民の半数程度は、「自衛のための戦争」はやむを得ないと考えているようですし、アメリカ国民の半分以上は「正義のための戦争」は「いいこと」だと思っているようです。私は、その人達を論理的に説得できる気はしなかったのです。感情に訴えることはできますが。
最近、「戦争・不自由・不平等・不正」等が「悪いこと」と考えることは「刷り込み」なんじゃないかな、と思い始めました。単にそういう教育を受けてきただけなんじゃないかと。とすると、「反戦・自由・平等・正義」が「いいこと」というのも「刷り込み」だということになります。そう考えるようになった本の一冊が、鈴木さんの前述の本でした。
そうして、サルトルの「自由の刑に処せられている」ということの解決が見えてくるような気がするし、フーコーの「性的であることを強制されている」というのもわかる気がしてきたのです。
印欧語と論理
私は「論理的」であることに努めてきました。できるだけ、合理的に、数学的に行動してきました。何をどう持つか、どこをどう歩くか、・・・。常に考えて行動してきました。答えができる限り一意に決まるように。できるだけ数値化して、最小、あるいは最大を選択できるように。そんな私は冷たい人間に見えていたかもしれません。
すべてのことに「白黒」をつけようとしました。0(ゼロ)か1(いち)かです。0.5というのは許せなかったのです。デジタル人間です。だから、「正しい」か「間違っている」かのどちらかです。まあ、実際は沢山妥協してきましたが。
戦争は、「悪い」か「正しい」かどちらかです。「自衛のためなら」とか「正義のためなら」という曖昧な条件は認めませんでした。私の中に「倫理」や「感情」などという曖昧なものはありませんでした。すべてが「論理」です。
「AはAである」「AはAであって、Aじゃないものではない」「Aであって、同時にAじゃないものではない」・・・
排中律、無矛盾律、自己同一性・・・。それと「因果律」です。必ず原因があって、結果があると考えていました。
それ、つまり「論理」というものがインド=ヨーロッパ語(印欧語)の構造、つまり文法そのものであることを教えてくれたのが鈴木さんです。
日本と日本語
私のように言語学といっても、音声や文法といった物理的論理的な構造面の比較ではなく、言葉を人々が実際どのように使っているのかを主な考察の対象とする、言語社会学(語用論)の立場から西洋諸語と日本語を比べると、日本人の言語の使い方は、まさに日本人の生き方を反映して、どちらかと言えば人々の感情や感性の表出に重点が置かれ、これに対し欧米人は理性と論理面を極力重視しながら言語を使うといった大きな違いがあると言えます。
なぜこのような言語の使い方に生まれたかというと、狭い島国の日本では、社会の成員の間で事実(fact)の同一性を重視することが可能であったのに対して、広大なユーラシア大陸では、至るところに基本的な事実の相違つまり多様性が見られるため、(fact)の同一性に頼って合意形成をはかることは不可能であって、もっと抽象性の高い(fiction)のレベル、つまり理屈のレベル、ということは言葉の論理的な側面に頼らざるを得なかったからだと私は考えています。
つまり日本が等質性を前提とした「論より証拠」の事実社会であるのに対して、西洋や中国を含むユーラシア大陸では、あまりにも地域差、つまり多様性が大きいため、「証拠より論」の理屈社会となっているのだと考えられるのです。(P.145)
日本は自然環境に恵まれた「美しい国」だとよくいわれます。『新しい国へ 美しい国へ 完全版 (文春新書 903)』は安倍晋三の著作です。反吐が出ました。彼がホンキでそう考えていたのだとすれば、それは妄想です。
確かに今、東京にいて「自然」を感じることは難しいでしょう(ここでいう「自然」は「人工物」ではないもの、程度の意味です)。虫の声なんか聞こえません。虫は「駆除するもの」そして「デパートで買うもの」でしかありません。そして、田舎に行っても「自然」は「汚いもの」「劣ったもの」、つまり「垢抜けない物」としてしか現れません。だから、「美しい国へ」という文言は「今はないけど目指しましょう」という意味では、一つの理想ではあります。でもそれは、「自然に帰れ」と同じで、今の文化的な生活を捨てなさいということで、単なる「夢(ユートピア)」でしかなくなります。
日本の地理的状況を「狭い島国」と言うのは「世俗的な思考」です。庶民からすれば、自分が住む「ムラ」が世界の全てだったことでは、西欧も変わりないのではないでしょうか。ただ、それは主に農業を行っているような定住民に言えることで、定住していない遊牧民は常に広い世界にいました。でも、遊牧民でも広い地域を移動するだけで、通常出会うのは同じ文化の人です。常に異文化、価値観の違う文化と接触していたわけではありません。
異文化と接触するのは、家畜を売ろうとするときです。「市(いち)」です。それは、共同体と共同体の境に作られました。定住民であればムラの境目の峠などに、遊牧民でも牧草地と牧草地の境目に作られたのではないでしょうか。そこで働いている原理は共同体内の原理とはまったく異なります。違うものを交換するわけですから、計量化、数量化と所有関係が必要になるからです。
これは「論理的に」考えるなら、そうかも知れいない、ということです。そこには、モースが『贈与論』で書いたような「贈与」が必ずあるはずだし、論理を超えた人と人との交流があるのです。
それが言語形成にどのくらいの影響を与えるのかはわかりません。羊が逃げたときに、家の人には「羊が逃げた」と言うだけで「私の羊が逃げた」とか「私たちの羊が逃げた」と言う必要はないですよね。そこには所有関係も所有の主体も必要ないのです。羊を見つけたときも、「見つけた」と言えばいいので、「私が見つけた」と言う必要はないのです。
島国日本、単一民族説
私は日本がわずか百五十年前の十九世紀後半まで、広い外の世界と可能な限り接触交渉を避け、国内だけですべてを基本的には賄うという、いわゆる鎖国(海禁)体制を、十七世紀初頭から二百五十年もの長きに渡って維持したことは、近代の歴史上特筆に値する偉業だったと考えています。(P.67)
よく戦後日本の平和主義の誇るべき実績の一つとして、七十年近くも戦争で日本人が一人も死んでいないことが挙げられますが、この点で江戸時代はその三.五倍近くもの長期間にわたって、鎖国のおかげで日本人が一人も対外戦争で死んでいない、なんとも素晴らしい時期だったのです。(P.680
鈴木さんは簡略化のためにこういう言い方をしているのだろうと思います。でも私には「日本人」とはなんなのかがわかりません。「鎖国」という言葉にある「くに」は、西欧の国家とは違います。戦後の国家でもありません。江戸時代になっても、アイヌとの戦争はありました。それを「内乱」だというのでしょうか。
琉球との関係はどうでしょうか。鎖国下でもオランダやポルトガル、朝鮮、中国、その他多くの国と交易を行っていました。
つまり、私たちは「現在の目」で、歴史を観てしまうということです。「過去の目」は誰も持っていないので、現在というフィルターを通してしか見ることはできないのです。ですから、異文化と触れたときに自文化の目だけで見てはいけないのと同じように、歴史も「一つの異文化」であるという意識を常に持っていないと間違うことになります。歴史は過去として「固定」していると考えてはいけません。歴史が常に「変わりつづけている」ということは、みんな経験しているはずなのに、変わらない事実として、「事件」としての歴史があるという幻想にとらわれている人が多いと思います。変わらない事実があって、ただそれを捉えられないだけだ、というのは一つの考え方、イデオロギーに過ぎません。「自己同一性」の呪縛です。
言語相対論
このような事実は、私たち人間のもつ世界認識が〈かなりの程度まで、用いている言語〈自然言語〉のタイプ、文法構造、そして語彙体系などによって規定されている〉、つまり使う言語が違えば人間は必ずしも世界を同じようには見ていないという、いわゆる言語相対論(サピア=ウォーフの仮説など)と呼ばれる考え方の一つの根拠となる面白い問題なのです。(P.51 注4)
「相対的」だというのは、違うということです。そして、違うというのは「優劣がつけられない」ということです。
りんごとみかんとパイナップルに優劣をつけられるでしょうか。むしろ、同じものだから優劣をつけるのではないでしょうか。たとえば、スポーツは男女別です。子供と大人も別なことがほとんどです。そして、同じ男、同じ大人だからスポーツは成り立ちます。「同じ」ということが比較する条件なのです。日本語と英語は違います。その違うものを比べて「日本語が優れている」と言えるでしょうか。もし比べるとしたならば、そこに「言語として同じ」という別の概念が必要になります。りんごとみかんを比べるときには「くだもの」という概念が導入されます。りんごやみかんが存在するとして、「くだもの」は存在するでしょうか。存在するというのも一つの考え方です。「イデア論」ですね。
この考え方をさらに深めると、「みかん」というのも一つのイデアです。同じみかんの中で、「大きい、小さい」「甘い、酸っぱい」という比較が可能になります。「大きい」というのは、物の属性ではないですよね。そのものより大きな物があれば、「小さい」という属性がものに付属します。「数」も同じです。「2」というものを見たことがありますか。「2個のみかん」や「2個のりんご」はあっても、「2」自体は見ることができません。これも物の属性ではありません。別のみかんが近づけば、「3個のみかん」になりますから。この辺の議論はイデア論の元祖プラトンが盛んに論議していますが、私は最後まで納得できませんでした。
確かに、人間には「象徴能力」と言われるものがあります。「概念」を作り出すのもその能力です。でも、そのこととイデアが必然だというのは違います。数の概念や、色の概念、左右という概念すらない文化があります(『ピダハン―― 「言語本能」を超える文化と世界観』ダニエル・L・エヴェレット著)。象徴作用と概念化は同じではないのです。
このあたりは、言語学の専門家である鈴木さんはよく知っていると思います。
私たちは、「万」とか「億」とか「兆」というような数の概念を持っています。でも、実生活でどれほどの実物の数を使いますか。たしかに、「980円のりんご」とかお金としての大きな数は使っていますが、実際には「980円のりんご1個」を見ているのです。「980円」というのは、そのりんごにつけられた「ラベル」に過ぎません。だから、そのりんごに一切手を付けることなく、「880円」とか「1020円」とか別のラベルをつけることができます。それをりんごの属性のように勘違いしているだけです。980個のりんごをいっぺんに食べることはできません。2個のりんごすら、いっぺんに食べることは難しいでしょう。
あと、3人家族とか、数えられるものはたくさんあります。今、部屋を見回してみると沢山の本がありました。数えるのも大変ですが、980冊の本があったとして、実際は同じ本は2冊とありません(たまに間違えて同じ本を買うことがありますが)。家族が3人いるとしても、一人ひとり別の人間ですよね。
「1億2千万人」というのは、概念でも実体でもないかもしれません。
漢字とかな
「文字」とはなんなのかについては、沢山書いた気もするし、未だによく分かっていない気もします。漢字は阿辻哲次さんの話が面白いです(『中国漢字文化論』Youtube)。
日本語の文字使用についてA. C. ムーアハウスは
「日本は、難しい文字形式をもっている場合でも、文盲撲滅にどれほどのことを達成できるか、ということを示すのに、よい例の国である。日本文字はふるい漢字体系と、それにもつづく音節文字とのごった煮であり、したがって半分は語標的であって、あとの半分は表音式である、余りにふくざつなので、大衆向刊行物(たとえば新聞)などでは、一つの語を二つの方法でかくのが普通である。最初には漢字で、そのつぎにはその語の音を示すための日本の音節文字(カナーー訳者)というふうに。これは、もとから日本の言葉と、日本語のなかにある数多くの中国語からの派生語とを区別する助けになる。しかしながら、その障害にもかかわらず、徴集兵のなかには文盲がほとんど存在しないといってよい。この字体をローマ字にあらためる方法も提唱されており、やがてはこれが勢力をえるかもしれない、なぜならば、ここでは中国ほど、克服しなければならない強い反対論が存在しないからである。」(『文字の歴史』P.164)
と言っています。欧米人から見ても、日本の文字使用は特殊なんでしょう。
漢字は、象形文字(表意文字)です。基本的には「意味」と「発音」を同時に持っています(「発音」だけのものも多いです。「意味」だけのものもあるでしょう)。「発音」の方は、時代や地域で異なりますが、「意味」はあまり変わりません。
話し言葉の標準形としての北京語さえ、中国人の三分の一にしか知られていない。たとえば北京出身の中国人と南部出身の中国人がであったとしよう。彼らはたがいに相手の言葉が通じないのである。しかし相手の文字なら理解するだろう。なぜならば、文字こそ全中国を通じて標準文字語であるからである。もしも官庁の告示を彼らが見たならば、二人とも自分の方言の音をその文字にあてはめて、読みとることができるのである。(『文字の歴史』P.62)
このようにして漢字は中国人に(いやしくも字の読める人であるかぎり)、自国の古典の知識を、すなわちわれわれには容易に推しはかれそうもない意味を中国人の生活のなかにおいて、持っている知識を享受させたのである。さらに、それは行政上の長所をもっていた。一般的に知られている標準口語がないので、文字が共通の媒介手段を提供することができた。(『文字の歴史』P.111)
これは、発音だけを持っていて意味を持っていないアルファベットではありえないことです。この漢字の特徴が、漢字と仮名を用いる日本文化に影響を与えました。ムーアハウスが知っていたかどうかわかりませんが、「訓読」という方法です。
また日本語とは語順の異なる漢文を、頭から読み下すのではなく、レ点や上、中、下と言った記号を用いて日本語の語順に直して読むといった日本独特の解読技術を工夫することができたのも、外国語の学習が殆ど外国人抜きであったからこそ生まれたものと言えるでしょう。(P.207)
ドラマの寺子屋の風景でよく出てくるのが、
「しのたまわく、まなんでとき(ここ)にならう、またよろこばしからずや」
『論語』の始まりのことばです。原語では
「子曰學而時習不亦説乎」
です。中国語の発音はわかりませんが、北の方の人の発音と南の方の人の発音は違うのでしょうね。「子」は「し」と音読みですが、それ以外は訓読み、つまり「やまとことば(日本語)」です。(「子」を「こ」と読んでしまうと「こども」の意味になってしまうからでしょうか。「師」とかけているのかもしれませんね。)「先生はおっしゃいました。ものを教わって・・・」などと完全に日本語に翻訳しなくても、なんとなく分かってしまいます。国際共通文字として、漢字はアルファベットよりも優れているかもしれません。ただ、文字一つ一つに意味があるということは、意味の数だけ文字が必要だということです(まあ、熟語という文字の連結もある程度は可能ですが)。ですから、
中国では、ただ読み方をならう仕事だけに大変な労力がうちこまれる、このことが、教育の普及といい、一般に国内の諸条件の改善といい、つねに重大な不便となっていた。(『文字の歴史』P.108)
英語を習い始めたときに思いませんでしたか。「アメリカ人はいいよなあ。26文字だけ覚えればいいんだから」って。日本では、小学校のうちに1,026文字の漢字を習います。もちろん、その他にひらがなやカタカナを習いますし、最近ではアルファベットも習います。大変ですね。
でも逆に言うと、漢字一文字を覚えることは、概念を一つ習得することになります。英語では、「水」は「water」、「風」は「wind」などと、単語ごとに綴りを覚えなければなりません。阿辻さんが挙げている例ですが、「風速計」と書けば、実物を見たことがない人でも「かぜのはやさをはかるもの」という予想が付きます。英語では「Anemometer」(あるいは「Anemometre」)と書きます。「anemo」はギリシャ語の「ἄνεμος(wind)」なので、ギリシャ語が分かる人は、なんか「風に関係してるものだなあ」とわかると思いますが、一般の人には予想もつかないそうです。つまり、漢字圏の人は「風」と「速」と「計」を憶えているだけで、ギリシャ語がわからなくても済むのです(笑)。
そういう日本文化だから、「翻訳書」が大流行したんでしょうね。ただ、欧米の学術用語を翻訳するときに、あちらでは日常的に使われる単語に新しい概念をつける(意味づけする)ことも多いのですが、それを無理に漢字で表現しようとして決して日常では使われない漢字(熟語)にすることも多いです。「哲学用語」とか「学術用語」とか言われるものです。最近は、横文字をそのままカタカナで学術用語することも多いのですが、ドイツ語、英語、フランス語など、日本で流行った時期によって、元の言語が違うのが難点です。
日本語の場合は漢字(語)で表される、もともと日本語にはなかった様々な概念が、訓読みという、いわば「外国語の手引」のお陰で、当たらずといえども遠からず、その意味を察することが出来るために、漢字がそれとは気づかれないうちに日本人の知的生活のレベルを高める働きをしているのだと、私は考えています」(P.212)
鈴木さんの言う「知的」とはなんなのでしょう。「理性的」という意味ではないですよね。「いろんなことを知っている」という意味でしょうか。「知的」な文化と「知的じゃない」文化があるということでしょうか。
少なくとも「知的な人」と「知的じゃない人」がいると考えているのでしょう。鈴木さんから見ると、私は「知的じゃない人」に見えるのかもしれません。少なくとも、鈴木さんは自分を「知的な人」と思っているのでしょう。それが「自分の仕事」だと思っていると思います。でも、みんなが学者で、みんながスポーツ選手であるような社会が「良い社会」だとは思えません。むしろ、「学者」も「スポーツ選手」もいない社会のほうが良い社会だと思うのは、「負け犬の遠吠え」でしょうか。少なくとも、日本でも欧米でも、学者でもスポーツ選手でもない人がほとんどで、その人たちが社会を支えているのです。いや、その人達が「社会」なのです。
人と人、あるいは文化と文化に優劣をつけること、比較すること、分類すること、それこそが「西欧論理主義」であり「西欧文化の呪縛」なのではないでしょうか。
多様性・種としての人間
人間という生物だけは、他の生物のように自分の体や性質を環境の変化に応じて変化させることをせずに、環境と自分との間に『文化』という名の言わば中間地帯を介在させ、この中間地帯を自然環境の変化に応じて変化変形させる、つまり自然環境の変化をそれに吸収させることで、自分自身は環境の変化を直接には受けずに生き延びていく生物なのです。(P.221-222)
種の多様性が、生物社会を作っていて、それぞれが全体の一部として、一つの全体をなしています。それぞれが生物社会の中で一つの地位(場所)を占めています。「棲み分け」です。そして、多様性(柔らかさ、柔軟性)が生物のクッションとして自然の変化から生物社会全体を守っています。今西錦司さんの生物社会論です。
そして、今西進化論では、「突然変異」や「自然選択(淘汰)」と進化の要因とは考えません。環境(自然)を「生物の他者」と考えないのです。
ダーウィン以降の正統派進化論では、生物の外部に自然環境があって、それが変化するとき、生物は「生き残るため」に進化するとされています。というか、「変化したものが生き残る」ということです。そして、その変化は突然変異(この言葉はダーウィンの時代にはなかった)の個体から始まり、その中で「環境に適した個体」が生き残り、「種」全体が変わっていく(進化していく)というものです。
とてもわかり易いです。なぜわかりやすいのかと言えば、私たちがそういう発想(論理)の中で生きているからです。原因があって結果があり、その過程が説明できるという論理です。そこで忘れられているのがその原因が何故起こったのかということです。すると科学者は急に論理から外れます。それを支配しているのは「偶然(突然変異)」だと。
生物の進化も、その始まりのところは「条件+偶然」と説明されます。。宇宙の始まりだって最初は「ビッグバン」という偶然です。因果律、科学的論理主義も、その根底に流れているのは不可知です。ただ、「絶対わからない」のではなく、「いつかはわかるけど、今はわからない」という信仰が西洋科学や西洋論理主義を支えています。そこは宗教のための領域なのです。
今西さんはこの論理に異議を唱えました。個体は全て「種」の性質すべてを備えている。だから、どの個体が事故等で死んだとしても、種社会は成り立っているのだ、と。私が死んでも、あなたが死んでも、総理大臣が死んでも、大統領が死んでも、「人間」という種がなくなるわけではありません。個体のどの細胞も完全な遺伝子を備えています。だから、原理的にはどの細胞が死んでも、個体の体は維持できます。その証明のひとつが「iPS細胞」です。
部分〈個〉と全体
「個体」から変化が始まると考えるのは、〈個〉が集まって、全体(種)が成り立つという発想です。その発想の原点は「個」「個人」〈私〉から、すべてを考察するというものです。それは「直接、全体を見ることができない」という技術的な問題ではありません。「私(という主体)から見る」という習慣がついているからです。私を中心に据えるので、「人類至上主義」になります。人間は進化の頂点にいるのです。そして、それを「発見」した「先進諸国」が「白人」が一番「進んで」いるのです(だから、黄色人種にノーベル賞を与えるのは屈辱です)。
西欧では、〈個〉、つまり〈自我〉の意識が強いのです。西洋の学問はアリストテレス以前から、それを基礎にしているのです。デカルトの「我思う故に我あり」はその高らかな宣言です。サピアが言葉の変化を個人の言語が変わって、それが全体に広がると言語の変化について述べているそうです。〈個〉と〈全体〉との対立が西欧の学問の基礎にあって、結局〈個〉が「主体」としての地位を占めるのです。
今西さんは自分で「全体主義者」だといっています。でも、それがファシズムとは違うのは、今西さんはそれまで、「個体が変わって、やがて全体(種)が変わるのが進化の法則だ」としていたのを、「種全体が変わるんだ」と言ったわけです。そこには「個体」と「種」、「部分」と「全体」の対立・矛盾そのものがありません。だから、今西さんが「全体主義」というのは違うと思います。あえて言うとすれば「非個人主義」ですね。
この考えを広げると、「種の主体性」や「生物全体の主体性」という考えに至ります(『進化とはなにか 』講談社学術文庫)。つまり、環境の変化が要因で、生物が変わるのではなく、生物そのものに変化の主体性があるという方向に向かうのです。多分、それは少し違っていて、「因果関係」で説明できないということを今西さんは考え始めたのではないか、と私は思うのです。個人を離れた〈主体〉というものは設定できないからです。今西さんにとって、なぜ進化するのかという問いは不要です。「生物は変わるべくして変わる」のです。そして、生物と自然との主従関係も意味がなくなります。環境が変わるから、種が(生物社会が)変わるのではありません。生物社会の主体性を認め、生物による環境の変化も考えつつ、最終的には、「主体(性)」という印欧語の特色、論理や因果関係そのものすら今西さんは乗り越えつつあったのかもしれません。
「社会の主体性」「国家の主体性」など、アナロジーとしての主体性を「個人」の延長と考えるとき、つまり、「〈自我〉の呪縛」から逃れられないとき、そこに「全体主義(ファシズム)」の香りが漂い始めます。
種、あるいは個体を一つの全体として考えると、その部分は「全体のために存在する」という発想になります。多くの動物はたくさんの卵(子供)を作りますが、その殆どは食べられたり、事故にあったりして死にます。種の保存には、その生き残った個体だけで必要かつ十分なのです。これは、簡単に「お国のために散る」という発想になります。今、ウクライナでも、「ウクライナのために戦っている」多くの人がいます。戦時中の日本人が間違っていて、今のウクライナ人は正しいというのは矛盾だと思います。
いま、ドーキンスの『利己的な遺伝子』を読み直しています。「利己的」「利他的」を「主体の意思」から切り離して考えたり、「ミーム」という文化の伝達を考えたりして、一見、「主客構造」を取り払っているように見えます。読み終わっていないのでなんとも言えませんが、「利己的」「利他的」あるいは「私と他者」という対立を、「遺伝子」に置き換え、それに「ミーム(社会、文化)」という色付けをしただけかもしれません(『利己的な遺伝子』が初めて邦訳されたときのタイトルは『生物=生存機械論』です)。
日本(語)が特別なわけじゃない
この本を読み始めたとき、とても全体主義的な香りがしました。人間は「環境と自分との間に『文化』という名の言わば中間地帯を介在させ、この中間地帯を自然環境の変化に応じて変化変形させる、つまり自然環境の変化をそれに吸収させることで、自分自身は環境の変化を直接には受けずに生き延びていく生物」だという定義はとても納得ができます。でも、それが「人間という生物だけ」と言われると、そうかなあ、と思ってしまいます。巧く反証を挙げることはできませんが、生物は何かしら環境と体の間に何かを設けているものです。それは巣だったり、毛皮だったり、あるいは皮膚だったりします。極端に言えば細胞膜だって外部(環境)と内部との壁です。そしてそれを環境の変化に応じて変化させているのです。
「外部・内部」というのも、自己・非自己(自己と他者)のアナロジーです。去年から新型コロナウィルス(と呼ばれるもの)の「ワクチン」を国家予算に匹敵するんじゃないかと思われるような大金で各国が購入していますが、ワクチンの作用である「免疫」の機能というのが、この自己と非自己の識別に関わるものです。たとえば、がん細胞は非自己でしょうか。同様に、腸内細菌や常在ウィルスは非自己でしょうか。あなたの「体」はあなたの「心」から見ると自己ですか、非自己ですか。
自己と非自己、外部と内部という境目は、とても曖昧です。それは「主観的に」定めるしかありません。今まで仲良く共存していた腸内細菌が暴れだした途端に、抗生物質を飲むのが西欧的論理です。
「自虐的な自国史観」
日本語の特性は、鈴木さんたちの努力によって次第に明らかになってきました。それが西欧的(インド=ヨーロッパ語に特有の)主客構造とは異なることも明らかにされてきました。この主客構造こそが、「西洋論理」であることも今では明らかだと思います。世界の6000種の言語のうち、主客構造を持つ言語がどのくらいあるのかを私は知りません。むしろ印欧語が特殊なのかもしれないのです。西欧から見れば、日本語も日本文化も特殊でしょう。だからといって、「私たちは特殊なんだ」と言えるでしょうか。
太平洋戦争中に日本(軍)が行った行為を「侵略」と捉えるか「解放」と捉えるかは、日本語の特殊性とは(直接には)関係がありません。「南京大虐殺」があったのか、「従軍慰安婦」は強制だったのか、「盧溝橋事件」は誰が起こしたのか・・・私にはわかりません。今後どんな史料が出てきたとしても、わからないと思うのです。史料はそれを書いた人、記録した人の影響を免れることはできません。今のウクライナで起こっていることだって、「攻撃した」と書くか「攻撃された」と書くかで意味は変わってきます(「侵攻」がいつの間にか「侵略」に代わったことに気づいている人がどのくらいいるのでしょうか)。「攻撃させられた」と書くことだって可能なのです(「攻撃されさせられた」という日本語は不自然ですが、他の言語では可能です)。どれも私は「体験」していないのです。体験していないことを「知っている」とか「わかっている」というのも、特定の思考形式で「サピア=ウォーフの仮説」からすれば、言語に関わっている可能性があるのです。
「客観的」「客観性」というのは、「主観的」「主観性」があって成り立つのですから、〈主脚構造〉による表現なのです。つまり、印欧語の中でのみ成り立つのです。
私が受けた民主教育の中で、歴史は「現代」までたどり着かないことが多かったです。受験の影響もありますが、先生の良心もあったかもしれません。それでも、「戦後は民主国家となった」「戦争はナチスドイツと同じ日本のファシズムが起こした」等の考えを身に着けました。そして、GHQの「農地改革」や「財閥解体」を手放しで(無批判に)に褒め称える風潮がありました。戦後が「正しい」とすれは戦前・戦中は「間違っていた」ことになります。だから、日本が戦時中に行ったことは「悪いこと」なのです。「大東亜共栄圏」を認めることは「戦争賛美」であり「間違い」だったのです。
なにせ日本は「一億総懺悔」をしたわけです(つまり、誰も責任を取らないということだけど)。その後に育った私たちが、日本のこと、父や祖父が戦争を行ったことをどうして負い目に感じないでいられるでしょうか。
高度成長の間はそれで良かったのです。戦後の復興で、欧米に再度「追いつけ追い越せ」という勢いがありましたから。オイルショックがあり、バブルが弾け、リーマンショックを迎える中で、安保闘争が終わり、学生運動が消滅し、左翼政党が総崩れになる中で、資本は見栄も恥もない再編成を行い、農地法、種苗法が改正され大土地経営以外は不可能な状況になるにつれ、太平洋戦争の再評価がなされるようになりました。
戦争は、その当事者にとっては、いつの時代も「正義」です。「悪い戦争をします」などとは言いません。歴史は、その時の権力者によっていつも再評価されます。それが、その時の「社会」あるいは「民衆」の状況を反映しているのかもしれません。私にはその関係がわかりませんが、それが「戦争賛美」につながらないかという「懸念」はどうしても拭いきれないのです。私が感じる「全体主義」あるいは「ファシズム」の「臭い」というのがそれなのです。
テレビ型言語
このように日本語の漢字は音声と字面(じづら)が組み合わさった複合体として、今述べたように元々音声の持ち駒が極端に少ない上に、その組み合わせまでがきつく制限されている。つまり音声言語としては変化の幅がきわめて乏しい日本語の持つ宿命を、実に巧く補い、日本語を世界のどの言語にも引けをとらない、効率のよい言語へと高めるのに大変な働きをしているのです。(P.188)
このような伝達行為は、音声だけではなく、音声に文字(画像)という視覚的刺激が加わって成立していることは明らかです。まさにこのことが〈日本語は(ラジオではなく)テレビ型の言語だ〉と私が言うことの意味なのです。(P.194)
「しりつのがっこうにいっています」という言葉を聞いたときに、私は「市立」「私立」という漢字が頭に浮かびます。そして、話の大筋の内容からどちらかを判断できないときな、「いちりつ?わたくしりつ?」と聞き返します。確かに、漢字という視覚的なものを頭に浮かべているわけです。そして、「がっこう」も「学校」という漢字を思い描いているような気がします。英語の話者が「privateかcityか」などのアルファベットが頭に浮かんでいるとは思いにくいです(「municipal(市立の)」なんて単語は私は知りません)。そもそも、英語には同音異義語が少ないそうです。
でも「ばら」はどうでしょうか。「薔薇」という漢字が浮かんでくる人はそう多くないんじゃないでしょうか。難しい漢字の単語の音を聞いたときに、その漢字を「ぼやーっと」「あいまいに」思い出すことはありますよね。でも、「その漢字を書いてください」と言われたときに、書こうとすると、私は「ぼやー」がはっきりしないことがほとんどです。テレビのクイズ番組で出題される、小学校で習った簡単な漢字ですら書けないことが多いのです。きっと私だけじないでしょう。だからクイズになるんだと思います。
私は「ばら」は「薔薇」ではなく「バラ」というカタカナが浮かぶし、むしろ「赤いバラの花」の映像が浮かびます。単純なことです。漢字を知っているから、漢字が浮かぶし、カタカナを知っているからカタカナが浮かぶのです。バラの花を見たことがない人は、バラの映像が浮かぶこともないでしょう。
「テレビ型言語」という定義はとても素晴らしいと思います。それは、日本語の特徴を表す以上に「文字」の本質を表しているのかもしれません。また「テレビが文字文化である」というウォルター・J.・オングの考え(『声の文化と文字の文化』)の別の表現じゃないかとも思っています。
学問、そして学者であるということ
鈴木さんの文明論、言語論は「文字の存在」を前提としています。本人がそれをどこまで自覚しているのかはわかりませんが、言語学者ですから、文字の重要性は認識しているはずです。「テレビ型言語論」の本質は、日本語という特殊言語の問題ではなく、文字の問題です。
フレーザーらが「書斎の学問」「安楽椅子の人類学」と批判され、今でもフィールドワークが重要視されています。でも、フィールドワークは大切ですが、それを「文献」にすると、それを読む人は「安楽椅子の〇〇学者」になってしまいます。
「そうじゃない。文献を読まない学問なんてありえない。」「文献に残さなければ、成果を発表できないし、人に伝えることができないじゃないか。」「それじゃあ、ビデオに撮って、ビデオで発表すればいいのか。」「ビデオがない時代のことはどうやって知ればいいのか。」「そういう君も〈文字〉を書いているじゃないか。」・・・
様々な意見がありそうです。文字は「情報を伝える手段」です。〈ことば〉そのものが「意思や感情を伝えるコミュニケーションの手段」ですよね。
なぜ「書斎の学問」は批判されるのでしょうか。それは、「文献」が虚偽を伝えている、あるいはその可能性がある、ということではありません。それが著者の「主観」を含んでいるということでもありません。それが、フィールドワークで得たもの(情報、体験)のすべてを含んでいないということです。ある現実・体験、観察対象は、「一つの全体」です。それを文字で描きつくすことは不可能です。
その全体を見る(聞く)私たちは、その全体から「自分の見たいもの」を選んで見ます。「自分の聞きたいもの」を選んで聞きます。それ以外のものは、見えなかったり雑音だったりします。その「選択」や「切り取り」は、その人の「経験」「文化」等によって決定されます。
もちろん、それ以外のものを見たり聞いたりすることはできます。それはその人の「才能」とも言えるし、「偶然」とも言えるでしょう。それこそが、フィールドワークの醍醐味、学問することの喜びですよね。それがなければ、「論文」は書けません。
ビデオ・映像は「事実」あるいは「真実」を伝えているでしょうか。昨年は「フェイク動画」が問題になりました。私もいくつか観てみました。顔を有名女優にすげ替えたAV(アダルトビデオ)です。まるで本人、というものも、全然似てないな、と思うものもありました。フェイク動画だと知りながらも、「面白いなあ、楽しいなあ」と思いましたし、「あの女優だって、プライベートではこういうことをしてるんだろうなあ」とも思いました。誰でも(ほとんどの人は)セックスをするわけです(どんなセックスをするのかは別として)。
私は50年以上前から、フェイク画像を作っていました。好きなアイドルの写真の顔を切り取って、ヌード写真の顔の部分に貼るのです。それとフェイク動画は同じじゃないかと思いました。
ワイドショー番組(今は「情報番組」というらしい)で、毎日「イラク情勢」が流れます。そこで流れる映像は、「ホンモノ」でしょうか。中には、人物と背景に違和感がある「フェイク動画」っぽいものもあったりしますが、それは別としても、「ロシア〇〇局」とか「ウクライナ〇〇省」とか「SNS」とか「視聴者提供」とか、様々な「出所情報」が書いてあります。小さく書いてあるので、あまり気にしませんが、「ロシア、極超音速ミサイル使用」というニュースで、ビルがミサイルで(?)破壊される画像と、そのミサイルを搭載したジェット機の映像(軍用空港)が流れました。その前に、破壊されたウクライナの街の瓦礫の中で泣いている女性の映像がありました。観ている人は、ロシアがそのミサイルで街を破壊し、それで家族を失った女性がいる、その家族は子供だったのではないか(!!)、などと思うでしょう。そして、「ロシアはひどいことをする」「プーチンはヒトラーのような独裁者だ」ということになります(ヒトラーの映像を流した局もありました)。
ミサイルで破壊されたビルの映像は、雪景色です。軍用空港と瓦礫の街の映像には雪はありません。軍用空港の戦闘機の映像には「ロシア軍提供」と書いてあります。多分、破壊されたビルの映像もロシア軍の提供だと思いますが、確認できませんでした。瓦礫の前の女性の映像は、町の名前が書いているだけで、誰が提供したのかはわかりません。放送したテレビ局の記者が撮影したものでないことは想像できますが。
つまり、様々な状況で撮影された映像を組み合わせて放送することで、一つのストーリーを構成する、それがエイゼンシュテイン以来の映像技術なのです。それが一つの言説であることを、認識する人はあまり多くないのではないでしょうか。
映像は、文章と同じで「ある状況」を作り出す(「再現する」ともいう)ものです。それは(当たり前ですが)書く人・作る人が「伝えたいこと」を伝えているのです。
もう一つ、文字、あるいは映像に特有なことは、それが「記録」であるということです。言葉や身振りは、発せられた瞬間に消えてしまいます。でも、文字が手紙から始まったと伝えられるように(『シュメル ー人類最古の文明』小林登志子著)文字は発話者の意思を「時間・空間を超えて」伝えることができます。でも、それは「意思の全体」を伝えてはいません。発話された状況も伝えていないし、その状況や意思は常に変化するのです。或るものが「変わらずにそこにある(有る、在る)」という「自己同一性(アイデンティティ)」こそが〈自己〉のそして「論理」の前提です。
文字や映像は、「すべて」を伝えない代わりに、「蓄積」されます。その蓄積が個々の「人間を小さく」していくのですが、それは別として、一度記録したことは変わらずに存在していると考えるのは「自己同一性の呪縛」でしかないということです。すべてのものは変化します。摩耗したり、火災や地震で失われたりします。古い文献がそのまま偶然残っていることもありますが、確実に残っているものは継続的に「書き写された」ものです。ビデオテープもDVDもハードディスクも定期的にバックアップ(コピー)しなければ、情報は失われます。そして、「書き写す(コピーする)」たびに、手が加えられるのはその性質上必然的なことです。失われたデータ(部分)はその時の状況で補填されるのです。つまり、「再解釈」されるのです。前述の歴史解釈の変更はここに基づきます。
〈終わりよければ万事よし〉
その常識とは〈終わりよければ万事よし〉の諺(ことわざ)の視点に立ってみることです。それは、どうしてアジアの遅れた一小国の日本が、明治以来「近代化には不向きな遅れた劣等言語」と日本の知識人によって、自虐的に蔑(さげす)まれ続けてきた日本語だけを使って、わずか百年足らずの短期間のうちに、先進西欧諸国にすべての点で追い付き、遂にいくつかの領域では追い越してしまうという、驚天動地の成功を収めることができたかを考えてみるだけでいいのです。(P.143)
面白い考えです。この言葉の出所はイギリスの古いことわざで、シェークスピア(『All’s well that ends well 終わりよければ全てよし』)が有名にしたもののようです。
私は、シェークスピアの戯曲は読んでいません。日常あまり使うこともありません。ドラマなどで使われるときは、無理やりハッピーエンドにしようとするときでしょうか。そこに至る過程は忘れよう、とか、その過程で悪い事したっていいじゃないか、とか、どうしてそうなったのかわからないとか、論理的に考えるのを諦めるとか、使い方はいろいろです。
「論理的な整合性は問わない」ということは「因果関係を問わない」ということです。それは、私が今目指しているものなので(笑)、鈴木さんが因果関係や論理的整合性そのものに疑問をいだいているとするならば、それは意味のあることです。
そうでないならば、本書のここまでの展開や、これ以降の展開との不整合が生じるでしょう。
〈終わりよければ万事よし〉と「なるべくしてなった」とは同じようで、違います。「なるべくしてなった」なんていうのは、誰も素直には信じません(笑)。だから、これからも、「なるべくしてなるとはどういうことか」「どうしてなるべくしてなるのか」、と問い続けるでしょう。今西さんにもそれは分かっていたのではないでしょうか。だけども、今西さんにはそう言うしかなかったのではないでしょうか。でも、〈終わりよければ万事よし〉は、その探求そのものを拒む、潔さと言うか、冷たさと言うか、威圧的な権威主義的な感じが私にはします。
〈進歩〉というもの
日本は「遅れ」ていたのでしょうか。そして、西欧は「進んで」いたのでしょうか。「追いつき追い越し」たのは「気持ち・精神」西欧論理・西欧の世界観だと私は考えています。
そもそも、「進んでいる」とか「遅れている」とかいうのはどういうことで、何を基準に考えたらいいのでしょうか。基準とするのは「科学技術」「産業(経済)」「生活水準」などでしょうか。つまり、「文化の水準」ということなのでしょうね。
私たちは、「進化論」の論理の只中にいます。「人間は猿から進化した」なる言説が跋扈していますが、正確には、「人間と猿は共通の祖先から進化した」ですね。
この「進化」という言葉が曲者です。英語は「evolution」、動詞は「evolve」、ラテン語の「volvō」は「巻く」という意味です。「e」は「ex(外へ)」という接頭辞なので、「ēvolvō」は「外に巻く」つまり「巻き戻す、開く、展開する」という意味です。そのことばを誰が日本語にしたのか、確認していませんが、「展開」とは訳さずに、「進化」と訳しました。日本語には「進歩」という言葉があります。だから、進化には進歩というニュアンスがあります。
ダーウィンが『種の起源』を出版したのは1859年です。その時の西欧の雰囲気はわかりませんが、「産業革命」という言葉が初めて使われたのは1837年だそうです。18世紀に始まった西欧の資本主義的発展が進展していく頃ですよね。その雰囲気と相まって、進化という言葉は「社会的によい価値観」を帯びていたものと思います。
「人間が猿から進化した」という学説は、簡単に受け入れられたわけではありません。人間と猿が親戚だというのは、かなりの反感を呼び起こしたし、生物が「変化」するというのは、キリスト教の「創世神話」と相容れないのです。日本だったら、人間と猿が親戚だというのはすんなりと受け入れられたと思います。人間と動物は地続きだからです。哺乳類だけでなく、昆虫とも植物とも地続きです。お盆に祖先が虫になって帰ってくる、などというのがすんなりと受け入れられていますから。西欧では、宗教と科学が分離することで、併存(「共存」と言えるかどうかはわかりません)するという道を歩みました。
今いる「自分」を中心に考えたとき、過去の、たとえば「子供の頃の」自分から見ると、今の自分が到達点です。同様に、今の人類が進化の頂点であり、過去の類人猿や爬虫類(恐竜)や魚類や植物や細菌やアメーバやウィルスよりも、進んでいるものです。
前述の『利己的な遺伝子』は次のように始まります。
有る惑星上で知的な生物が成熟したといえるのは、その生物が自己の存在理由をはじめてみいだしたときである。(中略)地球上の生物は、三〇億年もの間、自分たちがなぜ存在するのかを知ることもなく生き続けてきたが、ついにその一員が真実を理解しはじめるに至った。その人の名がチャールズ・ダーウィンであった。(P.15)
なんという大それた、自己中心的な考え方だろうと思うのです。「私はダーウィンを知っている、つまり真実を知っている」「西洋科学はすごい」つまり「西洋こそが真実を知っている」という「人間至上主義」「西洋至上主義」の考え方です。
私も鈴木さん同様、その「人間至上主義」は嫌いです。そして、日本文化の感性、すべての動植物、そして森や山や川や海などを人間と同等に扱う感性が好きです。それらは、そして自己の体や他人、他の村、他の国等々を利用するもの、支配するもの、所有するものと考えない感性が好きです。
カントのいう「他人を手段ではなく、目的として扱え」というのは、この日本の感性そのものだと思います。ただ、感とはデカルト以来の〈我cogito〉を捨てることができなかったと思います。だから、この言葉は「矛盾」としてしか現れなかったのです。〈我(私)〉を中心に据える思考は、戦後の民主教育の「自由・平等・民主主義」で強められましたが、明治維新前後の「西洋に追いつけ追い越せ」から一般に広められたものだと思います。夏目漱石の「則天去私」は「〈自己〉を捨てよ」という意味に聞こえ、それは全体主義的な発想に近いと感じてしまいますが、西洋の「自己」が普及し始めた当時の知識人として、私とは違う意味で使われていたと思います。
前述したとおり、私は「自由・平等・民主主義」「論理的、科学的思考」が「刷り込み」されています。刷り込まれた思考・発想方法は多分一生消えないでしょう。でも、刷り込まれたことを「自覚」することはできます。
私の残された人生は、その刷り込みを一つ一つ明らかにしていくこと、そして、幼児までさかのぼっていくことだと思っています。
<おわり>
テレビと文字(本)が同様なものだということ(テレビが文字の発展型だということ)は明らかなのですが、通常テレビと本とは「相反するもの」と思われています。その割に、テレビとネット(スマホ、パソコン)は「同様なもの」と思われている気がします。
今西進化論だと思う。今西さんは1902年生まれ(いまにし きんじ、1902年(明治35年)1月6日 - 1992年(平成4年)6月15日)、鈴木さんは1926年生まれ(すずき たかお、1926年〈大正15年〉11月9日 - 2021年〈令和3年〉2月10日)。京大と慶應。でも、考え方は似ていると思う。
人間と自然
[スタッフ・キャスト等]
鈴木/孝夫
慶応義塾大学名誉教授。1926年、東京生。同大文学部英文科卒。カナダ・マギル大学イスラム研究所員、イリノイ大学、イェール大学訪問教授、ケンブリッジ大学(エマヌエル、ダウニング両校)訪問フェローを歴任。専門は言語社会学
序章 世界の主導文明の交代劇が今、幕を開けようとしている
「それはこの人間中心主義(または人間至上主義)に裏打ちされた、理性と論理を極端に重視する西欧文明が、いろいろな点で行き詰まりを見せ始めているからです。」(P.9)__「極端に」とはどういうことか。「論理」や「倫理」が印欧語特有なものであることを、筆者は強調してたのではないか。
「今ではほとんどの大文明が失ってしまった、古代のアニミズム的で汎神論的な自然館を、未だにかろうじて保持している唯一の、しかも強力な先進近代国家だからです。(LF)日本は長らく孤立していたがために、近代になって圧倒的な西欧文明の影響を受けたにもかかわらず、本来の古代文明の要素をも完全には失うことなく基層文化として残している、言ってみれば二枚腰の二重構造を持っている唯一の、しかも強力な文明なのです。」(P.12)__「強力」ってなんだろう。大きいとか、強いとか、速いということに価値を持つこと自体が西欧文明、あるいは印欧語の特徴ではないか。比較級のない言語
「その理由は、未だに日本の知識人の多くが殆ど無意識の、動物行動学で云うインプリンティング(刷り込み)にも比すべき、西洋の文化文明と欧米人の物事のやり方や考え方こそが、人類の在り方としては最も普遍に近い至善至高のものだという、幕末明治維新の頃に叩き込まれ(FF)た考えに支配されているからだと私は思うのです。」(P.13-14)__被植民地の思想。ただ、印欧語は話していない。
「これまで書かれた様々な文明論は私の見る限り、その扱うところは人間社会の変貌、民族や国家の栄枯盛衰といった主題が中心ですが、私のこの本では、人間を全生態系の一つの構成員として見ながら、本能の代わりに文化と言語を使って繁栄してきたことから生まれる悲劇と矛盾に満ちた姿の一面を考察してみたいという意味で、副題を「言語生態学的文明論」としました。」(P.14)__種としての人間。今西錦司。
第一章 全生態系の崩壊を早める成長拡大路線はもはや不可能
「その理由の一つはこの報告書の前提であった「世界の石油資源はあと二、三十年で枯渇する」という予測が、一九八〇年代になると豊富な埋蔵量を持つ油田が次々と発見されたため、緊急性が薄らいだせいでもあります。」(P.18)__人類は滅んでも仕方ない。でも幸せに暮らしたい。最後の日までは。
「ところで私の文明論の主な立脚点は、このような私の専門外の資源や経済の問題というより(FF)は、地球の自然圏の安定性を支えている、人類の文化の多様性をも含む生物多様性が、あまりにも度を越した経済活動によって急激に失われ始めていること、そしてそれに直接関連する事実として後で詳しく述べるように、今世界で用いられている人間言語の多様性も激減する方向にあるという問題です。」(P.18-19)
(牛、羊、豚、山羊、馬、騾馬、水牛、駱駝等)「これらの大型家畜はすべて競合する野生の大型動物の棲家や餌を次々と奪い、そして彼らを絶滅に追いやりながら、人間の止め処のない欲望を満たすための奴隷の繁栄を誇っているわけです。(LF)また小型の肉食哺乳類に属する、現在世界での総数が二億を超すといわれている犬や猫といったペットとしての動物も、昔と違って今は、人間と殆ど同じ内容の餌を消費しているという点では、これも野生動物の生存を直接間接に脅かしていると言えるのです。(LF)ところがこのような事実は、伝統的に遊牧・牧畜文化を基本とし、人間の幸福繁栄だけしか眼中にない西欧の人々の視野には殆ど入りません。」(P.20)
(P.50 人口増)__インドで増加しているのは、産業のせいか?
「このような事実は、私たち人間のもつ世界認識が《かなりの程度まで、用いている言語〈自然言語〉のタイプ、文法構造、そして語彙体系などによって規定されている》、つまり使う言語が違えば人間は必ずしも世界を同じようには見ていないという、いわゆる言語相対論(サピア=ウォーフの仮説など)と呼ばれる考え方の一つの根拠となる面白い問題なのです。」(P.51 注4)
第二章 日本の感性が世界を変えるーー日本語のタタミゼ効果を知っていますか
第三章 鎖国の江戸時代は今後人類が進むべき道を先取りしている
「目新しいものを常に欲しがるという発展向上を求める気持ち、他人と少しでも差をつけたいという競争心そのものは、人間が生まれつきの本能ではなく大脳の知的な働きによって生きることを宿命として持っている生物である以上、人間の本性そのものに深く根ざしている性質です。」(P.71)__微妙だと思う。大脳ではなく、(同じことだけど)社会的生活を営む、つまり言語を用いる、といえば少し近くなるかも。それでも、やっぱり、文化や言語に規定されているという方が正しいと思う。実際、富や名誉を求めない文化があります。
第四章 今の美しい地球をどうしたら長期に安定して持続させられるか
「すべてが規格化されて、一箇所で大規模に集約的に作られ、そうして出来た製品をできるだけ広く早く、理想としては世界のすみずみにまで普及させ、そしてその製品をなるべく早く人々に捨てさせることで資本の回収回転を早めることが、現代の工業製品すべての望ましいあり方となっていますが、農業や畜産といった生物の命の分野までが、このような効率優先の工業化の論理にどんどんと支配されていく流れは、根本から見直しを迫られているのです。販売した製品が長持ちしすぎると、買い替えのスピードが遅くなるからと言って、わざと特定の部品が早く劣化するように仕組む、ビルトイン・オブソレッセンス(計画的に組み込まれた劣化)のような考えは、まさに〈儲かりさえすればなんでもよい〉、〈あとは野となれ山となれ〉(FF)の憎むべき思考の典型です。」(P.97-98)
「仮想水とはこのような輸入国の人々の目には見えない水なので英語でvirtual(実質的、事実上の)waterと名付けられたわけです。」(P.99)
「しかしそうは言っても、人類が太古から持ち続けてきた成長願望が、もはや善ではなく悪となってきているということを、日々の暮らしに忙しく追われている人々に認めさせることは、並大抵のことではできません。とりわけ未だに豊かな生活を実現しておらず、恵まれた社会環境の恩恵に良くしていない、いわゆる発展途上国の人々に分かってもらうことは大変です。」(P.103)__成長願望を持たない人が、地球上の人類の多くを占めていることは忘れられているのでしょうか。発展途上国の人は、西洋論理の知識だけ与えられている。私たち「先進国」の人は、本当に豊かなのでしょうか。「成長願望」は先進国、つまり、西洋論理が支配的な国の人々にあり、それは、現状に満足しない(できない)ということの反映に過ぎないのではないでしょうか。
第五章 自虐的な自国史観からの脱却が必要
(ヘンリー・S・ストーク 東京裁判は)「それは侵略戦争が悪いからではなく、「有色人種が、白人様の領地を侵略した」からだった。白人が有色人種は侵略するのは『文明化(シビィライゼーション)』で、劣っている有色人種が白人を侵略するのは『犯罪(クライム)』であり、神の意向(ゴッズ・ウィル)に逆らう『罪(シン)』であると、正当化(ジャティファイ)した。」(P.129)
第六章 日本語があったから日本は欧米に追いつき成功した
「この日本語に対する日本人の劣等意識は、日本人が明治以来抱いてきた、自分たちの体や顔つきが西洋人のようでないことに対して持ち続けた劣等感と同根のものです。」(P.142)
終わりよければ万事よしという視点(P.142)
「さて私の見るところ、この自己否定的な日本語観は、実のところ宗教、言語、人種、そして文化の全てにおいて、西欧のものこそが至上最善なものであるとする西欧人の手前勝手な偏っ(FF)た世界観を、世界の事情にまだ疎(うと)かった日本人が、なるほどと鵜呑みにしただけのことなのです。」(P.142-143)
「その常識とは《終わりよければ万事よし》の諺(ことわざ)の視点に立ってみることです。それは、どうしてアジアの遅れた一小国の日本が、明治以来「近代化には不向きな遅れた劣等言語」と日本の知識人によって、自虐的に蔑(さげす)まれ続けてきた日本語だけを使って、わずか百年足らずの短期間のうちに、先進西欧諸国にすべての点で追い付き、遂にいくつかの領域では追い越してしまうという、驚天動地の成功を収めることができたかを考えてみるだけでいいのです。」(P.143)__にほんは「遅れ」ていたのでしょうか。そして、西欧は「進んで」いたのでしょうか。「追いつき追い越し」たのは「気持ち・精神」西欧論理・西欧の世界観です。
「しかし私のように言語学といっても、音声や文法といった物理的論理的な構造面の比較ではなく、言葉を人々が実際どのように使っているのかを主な考察の対象とする、言語社会学(語用論)の立場から西洋諸語と日本語を比べると、日本人の言語の使い方は、まさに日本人の生き方を反映して、どちらかと言えば人々の感情や感性の表出に重点が置かれ、これに対し欧米人は理性と論理面を極力重視しながら言語を使うといった大きな違いがあると言えます。(LF)なぜこのような言語の使い方に生まれたかというと、狭い島国の日本では、社会の成員の間で事実(fact)の同一性を重視することが可能であったのに対して、広大なユーラシア大陸では、至るところに基本的な事実の相違つまり多様性が見られるため、(fact)の同一性に頼って合意形成をはかることは不可能であって、もっと抽象性の高い(fiction)のレベル、つまり理屈のレベル、ということは言葉の論理的な側面に頼らざるを得なかったからだと私は考えています。(LF)つまり日本が等質性を前提とした「論より証拠」の事実社会であるのに対して、西洋や中国を含むユーラシア大陸では、あまりにも地域差、つまり多様性が大きいため、「証拠より論」の理屈社会となっているのだと考えられるのです。」(P.145)__日本を「島国」と決めつける世俗的な思考。日本は鎖国時代も、オランダや琉球やアイヌなどと交易を行っていました。国としては、異文化と接していたのです。また、庶民からすれば、「ムラ」が世界の全てだったことでは、西欧も変わりないのではないでしょうか。ただ、それは農業のような定住民に言えることで、遊牧民は常に広い世界にいました。でも、遊牧民でも広い地域を移動するだけで、通常出会うのは同じ文化の人です。ただ、家畜を売ろうとするときには異文化と触れたでしょうが。それが言語形成にどのくらいの影響を与えるのかはわかりません。羊が逃げたときに、家の人には「羊が逃げた」と言うだけで「私の羊が逃げた」とか「私たちの羊が逃げた」と言う必要はないですよね。そこには所有関係も所有の主体も必要ないのです。
(P.145)__fictionの語源 From Middle English ficcioun, from Old French ficcion (“dissimulation, ruse, invention”), from Latin fictiō (“a making, fashioning, a feigning, a rhetorical または legal fiction”), from fingō (“to form, mold, shape, devise, feign”). Displaced native 古期英語 lēasspell (字義どおりに “false story”). factはよくわからないけど、dhē- はめることや置くこと、判断することを表す印欧語根。doなどの由来として単に動作を表す。接尾辞-fy, -ficなどの由来として、動作、特に作ることを表す。他の重要な派生語は、fact, affair, effect, perfect, face, themeなど。とあるので、これも「作る」という意味でしょう。多分ニュアンスとしては、fictionは人間が「考える」ことによって、作り出すもの、factは意識的かどうかは別として作る=認識する、ということなのではないでしょうか。
(P.149)「客観的科学的な統計」__客観的とか科学的という西欧論理
(P.149)「すべての国民が入ることのできる、アメリカにはない健康保険制度」__できる、じゃなくて「強制加入」です。税金と同じです。
「今でも非西欧世界で、国内で英語、フランス語、ロシア語といった西欧の大言語に頼らずに、日常生活のすべてから政治経済のあらゆる分野、幼稚園から大学院までのすべての教育を行える国が日本だけなのはなぜだと思いますか。」(P.165)__別に日本だけじゃない気が。中国語やヒンズー語は?
「つまり伝統的な日本語に不足していた、というよりはその必要がなかったために発達していなかった、近代化に必要な言語の理性的論理的側面を、漢字の持つ力でうまくカバーしたということです。」(P.165)__たしかに西周はすごい。
「これは今になって思えば後で詳しく述べるように、人間と環境世界との関係のあり方やそれに対する接し方は、どこでも同じではあり得ないという、これまであまり注目されてこなかった、人類のもつ言語文化の質的多様性をめぐる大きな問題意識が、私の頭の中に初めから一貫してあったからなのだと思います。」(P.166)__言語相対論は、過去70年間、議論されてきたことは鈴木氏もよく分かっていると思うし、彼のこの話はまさしくサピア=ウォーフの仮説です。
「この流れの根底にある思想は、世界各地に存在するアメリカとは違う考え方や文化(宗教)的慣(FF)行を、自由な国際貿易を妨げる不公正な非関税障壁だとして執拗に避難攻撃しながら異端視するもので、大変に危険なものです。」(P.166-167)__「自由」「平等」「公正・公平」「正義」「勝利」「発展」「冨」「罪」など、「分類・区別・比較」や「価値付け・順位付け」を行うことが「西洋論理」なのではないでしょうか。
「これは、人間以外の生物がほとんどすべて本能で生きているのに、人間だけは本能に代わる知能で生きているため、そこから戦争という同種間の集団的な殺し合いや、近頃ますますその傾向の強くなった、この生存を種の生存に優先させるといった、他の生物には見られない人間(FF)特有の行動が起こるのです。」(P.174-175)__今西錦司
第七章 日本語は世界で唯一のテレビ型言語だ
「それはいわゆる一般に広く受け入れられている科学的といわれる常識や因(FF)果関係が、いつも正しいとは限らないことを、このパプア族のエピソードがはっきりと示してくれるからです。つまりあらゆる迷信と偏見から解放されて物事を客観的に眺めることができるようになった筈の西欧の科学者でも、まだまだ彼ら自身が殆ど自覚すらしていない、自分たち西欧人の持っている文化や世界観に基づく、偏ったものの見方や先入観から完全には自由ではないのです。」(P178-179)__腸内細菌がタンパク質を作る、というのは、理解できない事象を細菌で説明したに過ぎません。分子を原子で、原子を素粒子で説明したと同じです。理解できないことにも「因果関係」を見つけようとしているだけです。理解できないことを理解できないまま理解することが必要なのではないでしょうか。つまり、理解の方法が文化や自然に影響されているということです。世界の見え方が違うということです。自然が違えま、自然の見え方が違ってきます。文化(言語)が違えば、物の見方、人の味方が違ってきます。「兄」と「弟」がない言語圏の人は、「兄」と「弟」という見方ができないのではないでしょうか。
「それは私の見るところ、一般に学問の研究対象が人間から遠ざかれば遠ざかるほど、その学問の持つ客観的普遍性が増し、反対に対象が人間に近くなればなるほど、学問は不確実性を増すということがあるからなのです。(LF)なぜかというと人間にとって一番わからないものは、結局自分自身だからです。」(P.180)__それは「学問」が〈自我〉を中心としているからです。このような発想(客観性、研究対象)になるのは、学者の宿命です。そこから解放されなければなりません。鈴木さんや今西さんはかなりはみ出しているけどね。権威があるから、「気が狂った」といわれなかったけど。
「このように観察者と観察される対象がつながっていては、客観性など望むべくもありません。ですからそのような学問を、たとえ「人文」とか「人間」などという形容をつけたとしても、科学と呼ぶこと自体がそもそもおかしいのです。」(P.180)
「たとえば芸術作品の人の心を打つ美しさや、我々がそれから受ける感動、あるいは恋愛という身近ではあるがなんとも不思議な心理現象を、いくら科学的統計的に分析しても何も出てきません。そして大学とは本来は人間とはなんぞやを探求する場であって、もの作りは現場で行うも(FF)のだったのです。」(P181-182)__「工学部」の位置づけ。
「それは、日本人はその言語活動の重要な部分において、音声という聴覚的刺激だけではなく、漢字という文字の持つ視覚的刺激をも併せて伝達に利用する、世界の他の言語には見られないきわめて独特の仕組みを活用しているというものなのです。これが私の《日本語は世界で唯一のテレビ型言語だ》という主張の根拠なのです。」(P.186)__確かに、漢字は表意文字なので、文字自体が意味を持っています。「桃」という漢字は「p」とは違って、まるで「絵」のように視覚化されます。鈴木さんは、「もも」は「peach」と同じだと思っていのでしょうか。聞いてみたいです。テレビは半世紀ほどの歴史しかないし、たぶん、オングが言うようにテレビは文字文化の結晶です。音声は音、映像は文字ということにとらわれてはいけないと思います。文字は「音読」とともにあったのですから。声に出して読めない文字、音のない言語・・・
「このように日本語の漢字は音声と字面(じづら)が組み合わさった複合体として、今述べたように元々音声の持ち駒が極端に少ない上に、その組み合わせまでがきつく制限されている。つまり音声言語としては変化の幅がきわめて乏しい日本語の持つ宿命を、実に巧く補い、日本語を世界のどの言語にも引けをとらない、効率のよい言語へと高めるのに大変な働きをしているのです。」(P.188)__文字(漢字、かな)が一般に普及する以前が長い。私は文字が果たした影響を大きく考えるのですが、社会が文字を持つことと、個人が文字を持つことは別です。だから、「文字がある社会」と「文字がない社会」というのが正確かもしれません。漢語の読み下し文。国破れて山河あり。春眠暁を覚えず。
「このような伝達行為は、音声だけではなく、音声に文字(画像)という視覚的刺激が加わって成立していることは明らかです。まさにこのことが《日本語は(ラジオではなく)テレビ型の言語だ》と私が言うことの意味なのです。」(P.194)__音声で理解できないときはたしかに漢字(らしきもの)が頭に浮かびます。西欧の言葉で、アルファベットが頭に浮かぶことはあまり想像できません。少なくとも、日本人が感じを思い浮かべるより頻度は低いと思います。ただし、その同音異義語の漢字を知っている、勉強している場合に限りますが。その漢字を知らない人には、その言葉は無意味、あるいは意味が曖昧なものになります。
「同一の思考領域、これを今後は《同一の文脈》ということにしますが、」(P.197)__同音異義語。近代の話?文字が普及していない地域はどうか。単純ですね。上記のとおりです。
「漢字語は音声と文字表記との複合体」(P.198)__文語と口語との関係は?
「この意味で私は言語学、特に言語社会学は、通常の意味での科学ではない、科学という狭い特定の前提と視野に役立つ学問分野ではないということをいつも強調しています。人間にとって本当に重要なこと大切なことは、いわゆる厳密な自然科学的手法では扱いきれない、もっと複雑で奥深いものだということを忘れてはならないと思うのです。」(P.205)__それでも「学問」に固執するのでしょうか。仕事だから?その科学に役立っている「論理」は、思考そのものの構造です。その構造が個人の頭の中にあって、社会を形成しているうちはいいのです。それが頭を離れ、物質化し、かつ蓄積していくとき、つまり「文字」が社会の中心となるとき、その文化は暴走します。人間は、記憶の全て、100%を使うわけではありません。むしろ、知識はその殆どが使われません。文字が、人が記憶できる知識の何倍にも、何十倍にも何億倍にもなるとき、為政者は自分が記憶する必要はありません。1億人から、そのときに必要な知識を引き出せばよいのです。1億人は為政者の外延された身体となります。
「また日本語とは語順の異なる漢文を、頭から読み下すのではなく、レ点や上、中、下と言った記号を用いて日本語の語順に直して読むといった日本独特の解読技術を工夫することができたのも、外国語の学習が殆ど外国人抜きであったからこそ生まれたものと言えるでしょう。」(P.207)__解読というか翻訳というか。
「以上のような日本特有の歴史的事情で生まれた、本来は外国語である漢字をめぐって、それをあちら式に読む音読みと、こちら式に読む訓読みが広範囲に併存するという奇妙な言語習慣は、見方を変えると同一概念の二重音声化という、世界でも珍しい現象だと言うことができます。」(P.207)
「ところが日本語の場合は漢字(語)で表される、もともと日本語にはなかった様々な概念が、訓読みという、いわば「外国語の手引」のお陰で、当たらずといえども遠からず、その意味を察することが出来るために、漢字がそれとは気づかれないうちに日本人の知的生活のレベルを高める働きをしているのだと、私は考えています。」(P.212)
第八章 なぜ世界には現在六千種もの異なった言語があるのだろうか
「ところが人間という生物だけは、他の生物のように自分(FF)の体や性質を環境の変化に応じて変化させることをせずに、環境と自分との間に『文化』という名の言わば中間地帯を介在させ、この中間地帯を自然環境の変化に応じて変化変形させる、つまり自然環境の変化をそれに吸収させることで、自分自身は環境の変化を直接には受けずに生き延びていく生物なのです。」(P.221-222)__今西進化論だと思う。今西さんは1902年生まれ(いまにし きんじ、1902年(明治35年)1月6日 - 1992年(平成4年)6月15日)、鈴木さんは1926年生まれ(すずき たかお、1926年〈大正15年〉11月9日 - 2021年〈令和3年〉2月10日)。京大と慶應。でも、考え方は似ていると思う。この本は全体主義的傾向が強いけれども、今西さんは自分で「全体主義者」だといっています。でも、それがファシズムとは違うのは、今西さんはそれまで、「個体が変わって、やがて全体(種)が変わるのが進化の法則だ」としていたのを、「種全体が変わるんだ」と言ったわけです。西欧では、〈個〉、つまり〈自我〉の意識が強いのです。西洋の学問はアリストテレス以来、それを基礎にしているのです。サピアが言葉の変化を個人の言語が変わって、それが全体に広がると言語の変化について述べているそうです。〈個〉と〈全体〉との対立が西欧の学問の基礎にあって、結局〈個〉が「主体」としての地位を収めるのです。
「私はそれよりも現在の新幹線や在来線のもつ様々な隠れた問題、たとえばトンネルや橋梁の劣化、なおざりにされている保線業務の強化といった地道な仕事に、膨大な資金を惜しみなく使うという、もはや発展拡大ではない、人々の安心と安全を求める気持ちに答える方向に事業を転換すべきではないかと考えます。そしてこのように従来型の発展拡大を、言わば足踏み状態に置いている間に、どうすれば人類社会を少しでも後戻りさせることができるかを、衆知を集めて考えるのです。」(P.231)__そうなんだけどね、そんな政策はありえないでしょう。高度経済成長で、明るい科学未来を抱いていた私にはよくわかります。今の若い人は、経済的停滞の中で育っているので、より分かるのでしょうか。それとも、「夢よもう一度」と思っているのでしょうか。
「自然は神が人間のために作られたものであり、したがってそれは人間が正しいと思う仕方で人間の管理下に置かれるべきものという考えは、人間至上主義のキリスト教西欧文明に根強い世(FF)界観で私たちの精神風土にはそぐわないものなのです。」(P.231-232)
「このことは個人として熱心に自然保護のために努力している人が、アメリカには沢山いるということとはまったく別の、文化の基本的性格の問題です。」(P.232)
「つまり神が望まなかった〈人間が天界にまで活動範囲を広げること〉を現代人に可能にした大きな要因の一つは、英語が今や人類の共通語の地位を、ある程度手に入れたためであると考えることができます。」(P.234)
結語
エピローグ 人間は果たして賢い動物だろうか
あとがき
二〇一四年八月
《end》