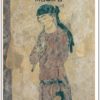オナニストが書いた小説
著者の金塚さんは「オナニズム三部作」で知っていました。私の尊敬する「在野の思想家」(たぶん)です。Wikipediaに没年が載っていないということはご健在なのでしょうね(たぶん)。
私は小説を殆ど読みません。金塚さんは思想家だと思っていたので、思想家の書いた小説は基本的に読みません。面白いと思えないからです(だからサルトルの小説も読んだことがありません)。この本は、たまたま図書館リサイクルでもらったものです。
「トイレ本」(トイレで読む本)として読み始めたのですが、初めの数ページは面白いとは思えませんでした。頭に情景が浮かんでこないのです。「17世紀のフランスの鏡工場」なんて、想像しようがないじゃないですか。工場内部の銅版画らしきものが1枚載っていますが、それだけでは私には無理です。誰かが、最初のページが面白くない小説はダメだ、というようなことを言っていましたが、本屋で立ち読みをしていたら、この本は買わなかったでしょうね。
でも、それが私に想像力が足りないせいだということが分かってきました。だんだん面白くなってきたのです。設定・ストーリー展開が面白い。会話文が多いのですが、その会話が実にみごとなのです。なんか、イタリア訛りのフランス語が聞こえてくるような気になりました(私はイタリア語もフランス語もわかりませんが)。
後半はどんどん引き込まれ、短いトイレ時間にあっという間に読んでしまいました。
鏡の向こう側
鏡を見たことのない人はほぼいないでしょう(日本や欧米諸国では)。鏡を見たことのない人や鏡を怖がる人は、それだけで文学作品の題材になりそうですね。
日本では「三種の神器」の一つ「八咫鏡(やたのかがみ)」が有名です。同様の銅鏡(銅合金製の鏡)は古墳から多く出土されているようですが、私は実物を見たことがありません。写真では裏の文様ばかりが映っているので、どのくらい「現在の」鏡のように顔が見えるのかはわかりません。
権力者の象徴で、庶民は持っていなかったんでしょうね。庶民には、イソップ童話の『よくばりの犬(犬と肉)』のように、水面が自分を写すものだったのではないでしょうか。
今では、100円ショップにも沢山の鏡が並んでいるので、とても身近なものですが、私が若い頃は結構貴重なものでした。女性は手鏡を大切にしていましたし、大きな鏡や三面鏡は一種の「あこがれ」でもありました。お化粧の必需品として、狭いアパートでも鏡台は必ずと言っていいほどあったように思います。私の妻も、嫁入り道具として義父が買ってくれました(すぐに物を置く台になりましたが)。
その鏡を私の母や祖母は、手鏡は鏡の面を必ず「下」にして置いていましたし、化粧用の大きな鏡には必ず布が掛けてありました。汚れたり、傷がつかないため、ということも有るのでしょうが、「そうしないと、鏡に雷が落ちる」とかなんとか言っていたような気がします。
鏡にはいつも「神秘性」が伴っています。だから、多くの小説や映画になっています。『白雪姫』は多くの人に知られています。『ひみつのアッコちゃん』は何度もアニメ化されたし、2012年の綾瀬はるか主演の実写版は記憶に新しいですね。
鏡についての言い伝えも多いでしょう(「鏡に関する言い伝えについて」Yahoo知恵袋、「【鏡に関する色々】」Hatena、など、ググればたくさん出てきます)。それらが昔からの言い伝えなのか、そういう小説や映画の影響なのかわかりません。どちらでもいいのです。伝わっている、残っている、言われているということは、そのような感情を人間は抱くのだということですから。
たぶん、弥生時代や古墳時代の人も、17世紀のパリやヴェネチアの人も同じような「神秘性」を感じていたのではないでしょうか。
ルネ・デカルト(René Descartes、1596/03/31 - 1650/02/11)
この小説の舞台は、1665年10月に設立されたパリの王立鏡ガラス工場です。1997年1月に殺人事件が起こるのですが、デカルトが死んでから17年経っています。だから、デカルトが実際に登場するわけではありません。
デカルトのことは、『世界の名著』の「デカルトの生涯と思想」(野田又夫)が詳しいです。もちろんWikipediaにも詳しく載っています。生後まもなく母をなくし、デカルト自身も病弱だった、父は再婚し、デカルトは祖母のもとへ、乳母に育てられる、という、「よくある人生」です(笑)。こういう育ち方をすると、「素直な」「平凡な」人間には育ちません。逆に「素直でも平凡でもないこと」の免罪符が「非凡な生い立ち」ということもしばしばあります。
学校では「朝寝」を許されていたといいますが、すぐ起きずに「思索していた」ようです。身体が弱かったからなのか、寝坊の言い訳なのかわかりません。デカルトは様々な学問で優秀でしたが、特に数学が好きだったようです。すべてを数学的に解釈しようとしていました。
学校を卒業すると、「書を捨てよ、街へ出よう」ということで、寺山修司より400年ほど早く「世間」に入ります。その後軍隊に入ったりしますが、「炉部屋」(よくわかりませんが、暖炉のある部屋でしょう)に閉じこもって考え事をしつくします。
そして、1637年(41歳頃)に『方法序説』を出版します。「我思う故に我あり」という有名な言葉を、私はしばしば引用しますが、実は『方法序説』はしっかり読んでいません(笑)(^_^;)ので、詳細は書けません。まあ、若い頃に形而上学や数学ですべてが説明できる、と思っていたんだけど、それに挫折して、今まで学んだことを一旦全部捨てちゃうんですね。でも、その代わりの新しい「真理」を得るまでの間、「仮のもの」を持たなければならない、云々というのが『方法序説』のようです。そうして、自分が考えた(内の)もの、自分の心に映る(外の)もの、全てを疑って削ぎ落としていった結果、最後に残ったのが「考える自分」です。そこで言ったのが「Je pense, donc je suis」です。そこに有る2つの「Je(1人称単数の主語)」は疑わなかったわけです。フランス語(英語もそうだけど)主語はほとんど強制的に存在します。動詞(述語)の変化でいくらかは対応できるのですが、文法構造のせいか、思考方法のせいか、主語をつけちゃうんですよね。ギリシャ語やラテン語では、このへんは緩いようです。「cogito ergo sum」というラテン語が有名ですが、これはデカルトの言葉ではありません。『方法序説』はフランス語で書かれているのです。「cogito」も「sum」も主語と動詞が一体化したものです。動詞の格変化で主語を表している、ということになっていますがよくわかりません。ただ、「Je pense, donc je suis」の「Je」が「私の」という強い意味を持っていると、考えたくなるのがヨーロッパの人です。日本語で「考えるってことは有るってことでしょ」というくらいの意味かもしれません。
「好きだ」でいいのに、「I love you」と言う文化です。「【すきだ】じゃ【だれ】が【だれ】を好きだかわからないでしょ」なんて、勘違いする人もいますが、「I」だって「YOU」だって誰のことだかわからないでしょ。
ともかくも、これがヨーロッパにおける「(個)人の宣言」、「近代合理主義の夜明け」として、称賛されたわけです。
自己の(再)発見
あなたは「いつ・何(なに)で」「自分」を知りましたか。
「赤ちゃんだって、自分のことがわかる」というのは正しいのですが、「犬だって自分のことがわかる」というのは犬と話をしたことがないのでわかりません。「ポチ、ご飯だよ」というと「ポチ」が走ってきます。でもそれは、「呼ばれたから走る」のか「自分が呼ばれたから走る」のはわかりません。
ピエトロ「本物と影を見比べるなんてもんじゃないんだ。おれは、鏡を見てはじめて、おれの顔を知るんだ。」(P.256)
自分は「自分の顔」を見ることができません。見ることが出来るのは『他人の顔』(安部公房)ばかりです。「私・自分」を「発見する」のは「鏡を見たとき」なのかもしれません。
ジェスティニアーニ「一度こうやって鏡を見だすと、もう見ないではいられなくなってしまうものらしい。人と会う前なんか、特にな。自分の顔がどうなっているのか、いや、ちゃんと顔がついているのかどうか、確かめずにはいられないんだ。鏡を見るっているのは、なんかこう、そうだ、仮面をつけるような感じかな。いや、顔っていうのは、結局は仮面、取りはずしのきかない仮面なのかもしれない」(P.141)
私は今でも鏡を見ると、「私はこんな顔だったのか。嫌だなあ」と思うことがあります。「ドギマギする自分」や「笑っている自分」の顔の表情はわかりません。そのときに頭に浮かぶのは、ドラマで見た俳優の顔だったり、過去に見た鏡の中の自分だったりするのではないでしょうか。
ピエトロ「他人は、それを見て、おれに違いないって言うんだろうが、おれにとっちゃ、絶対におれじゃないんだ。おれはここにいて、見てるんで、そっちにいるのはおれじゃないって、ううん、そうじゃないんだ・・・」(P.97)
まさしく「自我の問い」です。
「個性・人格」は英語で「パーソナリティ(personality)」です。「パーソン(person)」は「人」という意味ですが、元々はラテン語の「persōna」で、「仮面」という意味です。お祭りの屋台で売られているの仮面から、「能面」まで、様々な仮面があります。詳述はしませんが、仮面というのは一つの鏡です。
人は人形に「人格」を見るように、「仮面」に人格を見ます。そして、「他人という仮面」に自分を見つけます。つまり、自分は「他人」の中に(で)「自分」を見つけるのです。他人は「自分の鏡」なのです。「人の振り見て我が振り直せ」とか「人こそ人の鏡」(『書経』)とか言うじゃないですか。「殷鑑遠からず」(『詩経』)という言葉もあります。「鑑」は「鏡」です。
デカルトは鏡を見たか(以下ネタバレ注意)
ピエトロ「もっと綺麗な、もっと明るい、傷も歪みもない、染みも曇りもない鏡が欲しくなるんだ。本当のおれを見せてくれる鏡が・・・」(P.97-98)
デカルトは自分を見つめ続けました。そして、デカルトは「自分の中に自分を見つけた」と思いました。それが「Je pense, donc je suis」「おれはここにいる。おれは生きているんだ。」だったのかもしれません。炉部屋に引きこもり、(それまでの)自分を否定し続けたデカルトが発した叫び、それは助けを求める「悲鳴」のようなものだったかもしれません。
「Je pense, donc je suis」というのは「我思う故に我あり」であり、それは同時に「我疑う故に我あり」です。
ジュスティニアーニ「デカルトの哲学というのは、いや、哲学というものがそもそもそうなのかもしれませんが、他者に対する不信、絶望に発するような気がするのです。だとしたら、それは鏡と同じではありませんか。鏡を見る人間、鏡を見ずにはいられない人間、鏡なしでは生きてゆけない人間、そんな人間の哲学が、デカルトの哲学なのではないでしょうか。」(P.303-304)
ところが、鏡から目をそらした瞬間に、自分は見えなくなります。自分を存在し続けるためにはどうすればいいのでしょうか。それは「自分」を「外に出す」こと、「外在化」して、「存在」たらしめること、です。その一つは「書く」ということです。デカルトは「話す(書く)こと」を「強いられている」と感じていました(『方法序説』中央公論社、P.187)。そして、もう一つが有るとすれば、それは「人間」を、「純粋な人間」「本当の人間」を作るということです。
鏡は、ふつう話をしません。『白雪姫』では話をします。話をすること、言葉を理解し、理解できる言葉を発することが西欧人にとっての人間の条件です。
ピエトロ「あんたたちは、あんたたちと同じように話せなければ、もうそれで口がきけないって決めつけて、それ以上はもうわかり合おうとはしないんだ。だから、カテリーナは何もわからないってことにして、身体だけおもちゃにして遊べるんだ」(P.258)
話せないもの、理性を持たないものは「人間」ではなく「物」です。物なら、「所有」したり「支配」することができます。「物に対する行為」は「暴力」でも「悪」でもないのです。「物言わぬ」虫や草花に「声」を聞く日本の感覚とはだいぶ異なります。でも、西欧人でも人形の中に人間を見つけることはできます。孤独で絶望の淵にあったデカルトは、鏡の中にみつけた「自分」つまり「人間」を作り出そうとしました。
ジュスティニアーニ「ピエトロにとって、人形であるカテリーナこそが、一番心を許し合える友人であり、本当の人間なのだ。カテリーナに比べれば、他の人間たちなど邪心に満ちた木偶の坊にしか思えなかっただろう。」(P.300)
「カテリーナが、デカルトが作った人形だとしたら、これこそ、デカルトの最高傑作だ。『方法序説』よりも、他のどの本よりもずっとすばらしい傑作だ・・・それに、それにだ、ヴェネチア鏡など足元にも及ばない、世界で最高の鏡を作ったことになる、デカルトこそが!」(P.300-301)
「ヴェネチア鏡はそんなにすばらしいものでも、形のあるものしか映せない。最高の職人が何人集まって、考えられるかぎり明るく澄んだ鏡を作り上げたとしても、本物を見るよりも、もっと明るく細かく見ることができるようになったとしても、形のないものは絶対に映せない。しかし、カテリーナは、デカルトの作った鏡は、形のないものをも、人間の心、魂をも、映し出すことができるのだから!」(P.301)
学術と芸術
デカルトの哲学を、そして近代西欧の思想を、「鏡」で表現する試み、傑作小説だと思います。
冒頭に書いたように、私は小説は殆ど読みません。何冊の小説よりも哲学書の一行のほうが真実を表していると思っていました。でも、逆なのかもしれません。真実は言葉で表現できないのかもしれません。言葉ではなく、たとえば小説で表現できない真実は、人に伝わらない、つまり「意味がない」のかもしれません。『ゲルニカ』が表す戦争の真実、俳句が表す一瞬の自然や季節、それは「絵」や「文字」「ことば」を超えて、「なにか本質のようなもの」を表現しているように思えてきました。
「さすが金塚さんだ」と、改めて尊敬の念をいだきました。お元気であられますことを心からお祈りいたします。
[著者等(プロフィール)]
金塚 貞文(かねづか さだふみ、1947年8月22日 - )
日本の評論家、翻訳家。東京都生まれ、早稲田大学文学部中退。英語、フランス語の翻訳をし、1982年から『オナニスムの秩序』などオナニスム三部作を刊行。また1993年には柄谷行人の主導で「共産党宣言」を「共産主義者宣言」として新訳した。
主な活動は、自慰についての哲学的思索である。デビュー作『オナニスムの秩序』では、西洋哲学におけるオナニー論を通史的に整理したのち、独自の現象学的オナニー論を展開。その後『オナニスト宣言』で、ミシェル・フーコーのセクシュアリティ論を批判的に継承しながら、近代消費社会におけるセクシュアリティとしてのオナニーを論じている。
このほか、フェミニズムに関する論考や近代消費社会批判なども発表している。
1667年1月、パリの鏡工場でヴェネチア人職人が謎の死を遂げた。そして奇しくも同じ1月、頭と右手のないデカルトの遺骨がパリに戻ってきた…。面白くてスリリングな歴史ミステリー。
内容(「MARC」データベースより)
1667年1月パリ王立鏡ガラス工場で職人が二人謎の死を遂げたと歴史にある。ルイ十四世のフランスとヴェネチア共和国の熾烈な暗闘。奇しくも同月、デカルトの遺骨がパリに戻ってきた…。想像力と史実を駆使した歴史ロマン。
《書抜》
「しかし、城外、特にフォビール・サン・タントワーヌ周辺は、十(FF)三世紀以来、修道院に与えられた特権のおかげでそうした規制の一切を免れ、パリの城壁から修道院に至る道の両側には、家具製造を中心とした零細な町工場がそこかしこに立ち並び、典型的な場末の新興工場地帯の趣、つまり、都市からはみ出した貧困が農地を侵食してゆく、まさにそんな雑然たる趣を呈していたのである。」(P.67-68)
ピエトロ「鏡に映った自分を見つめ、外の世界を忘れ、自分一人の世界にうっとりとしたように閉じこもった女の姿には、人を寄せつけぬ、ひたむきな美しさがあった。」(P.83)
(P.96)__本当の自分、自分の存在
ピエトロ「他人は、それを見て、おれに違いないって言うんだろうが、おれにとっちゃ、絶対におれじゃないんだ。おれはここにいて、見てるんで、そっちにいるのはおれじゃないって、ううん、そうじゃないんだ・・・」(P.97)__自我の問い
ピエトロ「もっと綺(FF)麗な、もっと明るい、傷も歪みもない、染みも曇りもない鏡が欲しくなるんだ。本当のおれを見せてくれる鏡が・・・」(P.97-98)
ピエトロ「あそこのやつらはみんながみんな、鏡に映ったおれを見て、おれだおれだって、本当のおれが別にあるのを認めようとしはないんだ・・・」(P.98)__「私には、鏡に映ったあなたの姿を見つけられずに、私の目の前にあった幸せにすがりついてしまった」(かぐや姫 『22歳の別れ』1975年、伊勢正三)
ジェスティニアーニ「一度こうやって鏡を見だすと、もう見ないではいられなくなってしまうものらしい。人と会う前なんか、特にな。自分の顔がどうなっているのか、いや、ちゃんと顔がついているのかどうか、確かめずにはいられないんだ。鏡を見るっているのは、なんかこう、そうだ、仮面をつけるような感じかな。いや、顔っていうのは、結局は仮面、取りはずしのきかない仮面なのかもしれない」(P.141)
ピエトロ「本物と影を見比べるなんてもんじゃないんだ。おれは、鏡を見てはじめて、おれの顔を知るんだ。」(P.256)
「顔と、自分の本当の顔、自分には決して見ることのできない自分、他人から一方的に見られるしかない自分、そんな自分を背負ってしか、本当の自分になり得ない、ピエトロの言葉に深遠な哲学を聞くような思いがして、ジュスティニアーニはえも言えぬ感動を覚えていた。」(P.257)__女性。自己の発見
ピエトロ「あんたたちは、あんたたちと同じように話せなければ、もうそれで口がきけないって決めつけて、それ以上はもうわかり合おうとはしないんだ。だから、カテリーナは何もわからないってことにして、身体だけおもちゃにして遊べるんだ」(P.258)
ジュスティニアーニ「ピエトロにとって、人形であるカテリーナこそが、一番心を許し合える友人であり、本当の人間なのだ。カテリーナに比べれば、他の人間たちなど邪心に満ちた木偶の坊にしか思えなかっただろう。」(P.300)
ジュスティニアーニ「カテリーナが、デカルトが作った人形だとしたら、これこそ、デカルトの最高傑作だ。『方法序説』(FF)よりも、他のどの本よりもずっとすばらしい傑作だ・・・それに、それにだ、ヴェネチア鏡など足元にも及ばない、世界で最高の鏡を作ったことになる、デカルトこそが!」(P.300-301)
ジュスティニアーニ「ヴェネチア鏡はそんなにすばらしいものでも、形のあるものしか映せない。最高の職人が何人集まって、考えられるかぎり明るく澄んだ鏡を作り上げたとしても、本物を見るよりも、もっと明るく細かく見ることができるようになったとしても、形のないものは絶対に映せない。しかし、カテリーナは、デカルトの作った鏡は、形のないものをも、人間の心、魂をも、映し出すことができるのだから!」(P.301)
ジュスティニアーニ「人間、他人に対する絶対的な不信ですな。デカルトの哲学というのは、いや、哲学というものがそも(FF)そもそうなのかもしれませんが、他者に対する不信、絶望に発するような気がするのです。だとしたら、それは鏡と同じではありませんか。鏡を見る人間、鏡を見ずにはいられない人間、鏡なしでは生きてゆけない人間、そんな人間の哲学が、デカルトの哲学なのではないでしょうか。」(P.303-304)
ジェスティニアーニ「他人を信じられない、孤独な人間ほど、鏡を欲するんじゃないでしょうか。国王ご自身が一番いい例かもしれませんな」(P.302)
「鏡は、新しい時代の主人公として、燦然と輝き、新しい時代の人々を照らしてゆくだろう。鏡とは、裏を暗く遮断するほどに表面の明るさを増し、そして、奥行きのない明るさによって、見る人の孤独を祝福するものなのだ。」(P.329)
《終了》