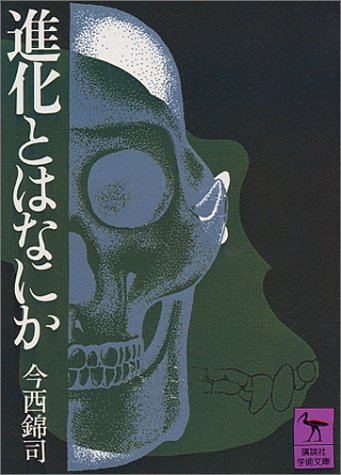
今西進化論のエッセンス
今西進化論に出会ったのは何年前でしょうか。30年前くらいだったかもしれません(憶えていません)。はじめに今西理論に触れたのは、彼の「棲みわけ理論」です。『生物の世界 (講談社文庫)』だったと思います。はじめに読んたときには、「ふ〜ん、どこがすごいんだろう」という感じでした。
その他にも何冊か読んだかもしれません。著作を読むよりも、いろいろなところで今西氏の名前が出てきます。私は、生物学の本をほとんど読まないのですが、それでもいろんなところに今西氏の名前が出てきました。賞賛する意見も「科学じゃない」という切り捨てる意見もありました。今回読んだ感想は、「確かに科学じゃない」ということです。それは、「科学」という範疇には収まらないのです。
なるべくしてなる、変わるべくして変わる
これが、今西進化論のエッセンスだと思うのですが、うまく本文中の文章を見つけられません。そして、これこそが私が今西進化論に感じていた抵抗感なのです。実は、私はダーウィンの『種の起源』を読んだことがありません。科学者と言われている人たちは、みんな読んでいるのでしょうか。ユークリッドの『原論』、アリストテレスの『自然学』や『動物発生論』を読んでいるのでしょうか。「基本文献」を読んではいても「古典」というものは案外読んでいないのではないでしょうか。
なぜ、こんなこというのかというと、今西進化論は、ダーウィン以降の「正統派進化論」に対する批判ではなくて、その根底にある「西洋的論理」そのものの批判だからです。
「突然変異はある確率で起こる」=>「突然変異の結果、自然選択(自然淘汰)がおこる(おこった)」=>「適したものが生き残り、子孫をのこす(のこった)」、これが正統派進化論です。「適したもの」が「強いもの」「すぐれたもの」におきかわると、「弱肉強食」、資本主義の競争社会の理論そのものです。私のように「弱いもの」(それは資本主義社会では「お金がない貧乏な者」と同一です)は、「論理」としては認めつつも、「でも、人間には理性がある。だから、弱いものを守る義務がある。弱いものにも生きる権利があるんだから。それが民主主義だ」と反論して、「正義感」を示したりします。
その「論理」から見ると、「なるべくしてなる」などというのは、なにも説明していないと思ってしまうのです。
けっきょく、コーモリにしてみれば、前足が翼に変わったから、空中生活をしなければならなくなったのであろう。けっきょく、コウモリにしてみれば、コーモリになるより仕方なかったから、コーモリになっただけのことであるかもしれない。(P.155)
今西氏の自然を見る目、その暖かくも厳しい目が感じられそうです。ここには、因果の超越があります。
因果
「強い」だから「生き残る」というのは、「因果律」です。ここでは、原因があって結果があるという意味で使っています。日本にも「因果」という概念はあります。「親の因果が子に報い」というやつです。仏教の用語です。仏教で言う因果と、西欧の因果律とはちがっているようですが、正確にはわかりません。
さて、「強いから生き残る」というのと「生き残ったから強い」ということのちがいが分かりますか。後者を「それは結果論じゃん」ということがあります。正統派進化論は実はその後者であると私は思います。人間は生物の頂点に立っている、だから人間は強い。西欧論理は世界を支配しつつある、だから西洋論理は正しい。民主主義が世界の指導的思想である、だから民主主義は正義だ・・・。そこから、「社会は民主主義的であるべきだ」「論理的であるべきだ」「人間は動物を管理・支配して当然だ」ということになります。
今西氏が「因果論」を否定しているのかどうかを、本文中から読み取ることはできませんでした。多分、そこまでは思っていないでしょう。そう表現してしまえば、もう科学者とはいえないでしょうから。
目的論
人間は、猿や犬よりすぐれている、縄文人より現代人のほうがすぐれている、などというのは「白人(西欧人)は黄色人(アジア人)や黒人よりもすぐれている」というのと同じです。それは、カンブリア紀よりも現在のほうがすぐれているというくらいばかげていると私は思います。
今西氏が「定向進化」というとき、生物が「ある目的に向かって進化している」という意味ではないと思います。
生物に主導性をおくことが目的論になるのであったら、どうして環境に主導性をおくことも目的論にならないのだろうか。(P.149)
これは、今西進化論にたいする批判を逆手に取った表現です。「主導」とか「目的」というのは、人間の意図が入っています。つまり「人為的」あるいは「恣意的」という批判を受けるわけです。「科学には人間の意図は入ってはいけない」という思い込みがあるからです。
そして、その意図というのは価値観をふくんでいます。ある目的をもって意図的に行為を行った結果、目的が達成されることがすぐれているという価値観です。これがまた微妙で、その意図や目的には「いい意図」と「悪い意図」があります。そして、「いい目的」と「悪い目的」があります。その上、これらが直接的にはつながらないのです。
この「価値観」は「進化」という言葉にも含まれます。
スペンサーの考えというのは、ひと口でいえば進歩至上主義とでもいえるであろうか。そのため、進化と進歩との混同をきたし、進化ということを進歩であると誤解するひとさえ、現れるにいたった。(P.122)
「進歩」を悪いことだと考える人もいるでしょうが、通常は「よい」という価値観を持って「進歩」ということばを使います。では、「進化」には価値観が含まれないのでしょうか。今西氏はそう考えているようです。では、「進化」は「変化」にすぎないのでしょうか。私は今西氏の考えを読み取ることができません。氏は生物学者だし、西欧語にも詳しいと思うので、私より深い感覚があるのだろうと思います。
(・・・)進歩や発展だけをみて、衰退や滅亡を考えないというのは、一面的なものの見方である。なにもやるだけのことやって滅亡するんなら、いわば天寿を全うしたようなもので、大往生をとげるのであるから、人類は滅亡してもいいんじゃないかというのが私の考えなのであります。(P.92)
子どもがおとなになることを「進歩」だと捉えると、子どもは「未完成の大人」で「大人より劣っているもの」ということになります。大人は、やがて歳をとって死んでいきます。それは、「進歩に価値」を持っている人たちには許されないことです。おとなになっても自分が「完成」していないことは分かります。だから、つねに完成を求めて進歩(発展)していく不完全として自分を位置づけなければなりません。
「進化(evolution、ēvolūtiō)」は「巻いてあるものを開く」というような意味らしいです。明治時代に翻訳したひとは、西欧の進んだ文化を日本が取り入れて「(文明)開花」していくことを「いいことだ」という「価値観」を持っていただろうと思います。
全体主義
私は、「全体主義(Totalitarianism)」ということばが嫌いです。「ファシズム」や「ナチズム」、あるいは「戦前の軍国主義」をイメージしてしまうからです。
(・・・)種社会は生物全体社会の部分社会であり、生物の個体というものもまた種社会を構成している部分にすぎないということを認識するならば、生物全体社会の立場を無視して、種社会のみが独走的に変化したり、種社会の立場を無視して、その種社会の構成要素である個体が、勝手気ままに変化してもよいものだろうか、という疑問が、当然おこってもよいはずである。すくなくとも私のように、若い時から生物学におけるホーリズム(全体主義)の影響を、濃厚にうけてきたものにとっては、これ以外の考えようはないのである。(P.129)
今西氏のいう全体主義は「ホーリズム(holism)」です。「全体論」とも訳されます。ここでは、個(部分)がそれ自体で「全体をなしている」ことを表しています。これに対立するのが「還元主義(reductionism)」です。
だから、慎重を期する科学者にとって、生じっかな起源論や進化論に言及することは、タブーとされていた時代もあったのである。一方で実験室のミクロ屋さんたちにすれば、生物というものがそれなりに歴史をもったものであるとか、社会をもったものであるとかいうことを、考える必要などすこしも感じないであろう。その人たちにすれば、そうした生物の歴史性や社会性を捨象して、できるだけ生物を物質扱いし、物理学的化学的操作をとおして生物を物質的に解明することが望ましいのであり、それがまた現在の科学を育ててきた還元主義(reductionism)に忠実である、ということにもなるのであろう。(P.169-170)
ここのところを表現するため、私はよく種社会とそれを構成するところの種の個体とは、二にして一のものであるという表現を用いる。二にして一のものであるということは、どちらか一方が変わるときがきたら他方もまた変わるということである。これをもっとミクロにみれば、種の個体が変わるときには遺伝子の構成のうえでも、やはりそれに応じた変化があってしかるべきであろう。そうなるとまた種の個体とその遺伝子とは二にして一のものであるといわねばならなくなる。すくなくとも、いままで信じられてきたように遺伝子がさきに変わり、その結果として突然変異を生じ、さらにその結果として種が変わるといったような一連の因果関係によって、生物の種が進化してきたものではない。それを、そのようにしか考えられなかったというのは、だれもかれもが還元主義のおとし穴におちこんでいたからである。変わるべきときがきたら、種社会も種の個体も、またその個体のなかにしまいこまれた遺伝物質も、みな時を同じうして変わるのでなければ、システムがこわれてしまう。(P.196-197)
西田幾多郎の「絶対矛盾的自己同一」を彷彿とさせる文章です。
私は、全体主義(ホーリズム)に対立するのは、「個別主義(個人主義)」あるいは「部分主義(分析主義)」だと思います。有機的(オーガニック)な全体(ὅλος、総和)を理解しようとするとき、西欧ではそれを部分に分けて単純化しようとします。そしてその、単純化された部分の総和(集合)が全体だ、とするのです。
机をバラバラにして分解すると、それぞれは「木片」です。その木片をいくら調べても、「机」の性質は出てきません。そこで、机を成りたたせるものとして、木片同士の関係を表すもの、つまり「設計図」に相当するものを考えます。それは「イデア」と言われたり、「構造」あるいは「ゲシュタルト」などと言われています。西欧の哲学や科学も還元主義(分析主義)を乗り越えようとしてきましたが、それは分析を否定するものではありませんでした。
分析と主体
西欧では、現象や行為に必ず「主体」を置きます。その主体は「ego」であったり、「神」であったりしますが、主体と客体(主客構造)というのはインド=ヨーロッパ語の主語述語構造自体が要請するものです。
heやsheなどの西欧文における役割は、第一に、行為の主体である主語を、常に明確にしておく、という構文上の機能である。横文字の文章では、heやsheなどは、いくらでもくり返される。言わないと分からないからではない。論理的に必要である以前に、形式上の要請であり、三人称代名詞など人称代名詞の多い文は、西欧人にとって、読者が親しみを持つ第一の条件なのである。その背後には、行為の主体を常に明言し、責任者を、個体としてとらえて明らかにしておく、という思考の構造がある。(『翻訳語成立事情』柳父章 岩波新書、P.204)
分析とは、主体と客体を分離することによって可能になります。〈私〉が客観的存在を観察して、分析するのです。
物理学などで、「観察者」ということが言われます。アインシュタインの相対性理論も、量子力学も観察者が大きな役割を演じます。観察者のいない現象があるのかどうかというのは、認識論や存在論の領域ですが、ニュートン力学などは観察者に関係なく成り立つ「法則」を目指したものです。でも、そこに観察者はかくれていなかったのでしょうか。
主体・〈私〉から考えること、それは、〈個〉から考えるということです。全体から分離された〈個〉としての私の存在がまずあって、それから〈他者〉や「社会」「全体」を考えるということです。「主客構造」ははじめから「還元主義」的な傾向をもつのです。
〈私〉の存在に頼ることなく「全体」あるいは〈他者〉を考えること、それは西欧人には難しいことです。「論理」は「ロジック(logic)」です。これはギリシア語の「λόγος」から来ています。「ロゴス」は「ことば」です(「始めに言葉ありき」ヨハネの福音書、第1章1.1)。考えたり感じたりしたことを「ことば」にして「表現する」ことが西欧の基本です。心のなかにある「主観的」なことを、「客観的」なものにしなければならないのです。そのことばを「客観的実在」にしたものが「文字」です。でも、ことばや文字では「全体」を表現することができません。
心の中をことばや文字にせず把握すること。全体を全体のまま知るということ。「以心伝心」という文化は、その可能性を持っていると思います。
科学とは
自然科学は物理学を範として、自然の法則を求め、その法則は実験によってくりかえし検証できるということを標榜している。それにたいして、あえて異議を申したてるつもりはないのだが、自然科学者ーー生物学者もふくめてーーのなかには、この地球の歴史のうえで、ただ一回きりしかおもらないで、二度とはくりかえさぬ進化ということを、実験室のなかでくりかえせることのように考えているひとが、ないとはいえないのである。はたしてそういうものだろうか。進化を、突然変異と自然淘汰という、ありもしないことをまことしやかに考える実験遺伝学にまかせることは、人類の将来をコンピューターにまかせるのと同じくらい浅はかなことである。進化ということをとりあげるまえに、この辺でいま一度、それがはたして今日の自然科学の対象に、なりうるものかどうかを、検討してみる必要がある。(P.156-157)
だから、慎重を期する科学者にとって、生じっかな起源論や進化論に言及することは、タブーとされていた時代もあったのである。一方で実験室のミクロ屋さんたちにすれば、生物というものがそれなりに歴史をもったものであるとか、社会をもったものであるとかいうことを、考える必要などすこしも感じないであろう。その人たちにすれば、そうした生物の歴史性や社会性を捨象して、できるだけ生物を物質扱いし、物理学的化学的操作をとおして生物を物質的に解明することが望ましいのであり、それがまた現在の科学を育ててきた還元主義(reductionism)に忠実である、ということにもなるのであろう。(P.169-170)
今西氏は、分子生物学の福岡伸一さんの先輩ですから、福岡さんは当然、今西理論を知っているはずです。そして、西田幾多郎とも格闘しています(『福岡伸一、西田哲学を読む』)。福岡さんは、「動的平衡」と西田哲学が似ていると言っています。
西田哲学の用語を挙げてみます。
「絶対矛盾的自己同一」「歴史的自然の形成作用」「主客未分」「純粋経験」「自覚」「行為的直観」「逆限定」「多(一)の自己否定的一(多)」「絶対現在」・・・
これらが今西理論と共通することがおわかりいただけるでしょうか。西田哲学が難しいと言われるのは、「言葉(文字)で表すことができないものを言葉(文字)で表そう」とした(拙稿)ことにあると思います。そしてそれは、科学で科学を、論理を論理で批判した今西理論にも言えることだと思います。
子どもを「未完成な大人」ではなくて、一つの全体としての「子ども」と捉えること、そして自分自身も「未完成」や「不完全」な存在ではなく、一つの全体としての「実在」として捉えること。そして、その存在(〈私〉、生物、自然等)は、過去や未来(歴史性)、そして他者(社会性)をふくんだ「一つの全体」(「完全存在」「主客未分」)として捉えることが、今、求められているのではないでしょうか。
余論:「メガネ理論」
私は目が悪いので、メガネをかけています。今日、木を削っていて、その後パソコンに向かいました。なにげなくメガネを外してメガネを拭きました。メガネを外すと、10cmくらい先からは世界はぼやけていて見えません。メガネを見ると、木の削りカスが飛び散っていて汚れていました。きっと顔にも服にも飛び散っているのでしょう。ネガネを拭いて掛け直したとき、世界がスッキリと鮮明に見えました。
目の悪い私は眼鏡がないと、近いところ意外は見えません(どうして目が悪くなったかは、今回は問題にしません)。メガネは文明の利器です。科学技術がつくり出したものです。今のところ、私はメガネを捨てようとは思いません。でも、メガネが当たり前になると、メガネが汚れていることになかなか気が付かないのです。
すごいことを発見したような気になりました。これを「メガネ理論」と名付けることにします。(笑)
赤いセロファンをとつぜん通して世界を見るととても変に見えます。でも、次第に慣れてきます。透明なセロファンが段々と赤くなっていったとすれば、赤くなったことにも気づけないのです。
たまに、「眼鏡を拭いてみる」ということの大切さに気づきました。
[著者等]
今西錦司(いまにし きんじ、1902年(明治35年)1月6日 - 1992年(平成4年)6月15日)
1902年京都市生まれ。京都帝国大学農学部卒業。京大人文研究所員、同大教授、岐阜大学長などを歴任。1972年文化功労者に選ばれる。京都大学名誉教授、元日本山岳会会長。理学博士。主著に『生物の世界』『山岳省察』『生物社会の論理』『日本山岳研究』『私の進化論』など多数。また『今西錦司全集』(全14巻)がある。1992年6月15日没。
序
「一九七六年三月二十九日 著者しるす」(P.5)__「進化とは何か」は書かれていない。正統派進化論の批判。「どのように」進化するかであって、「なぜ」進化するかではない。ダーウィンと同じ基盤。そもそも、進化に「因果論」「原因結果論」「目的論」を導入すべきではない。「なぜ」と問うことそのものがおかしい。
正統派進化論への反逆
「ここで種の起源ということも問題になるだろう。いったい三六〇度の変異を考えるから、自然淘汰ということを、持ちだしてこなければならなかったのである。いいかえるならば、環境の主体化を考えないで主体の環境化のみを考えようとしたから、このよ(FF)うな組合せになってしまったのである。」(P.18-19)__『生物の世界』からの引用
「生物と環境とのバランスが保たれているかぎり、その生物にとっては突然変異を必要としないが、環境との間にアンバランスが生じ、それによって生物がテンションを感じるようになれば、その解消のために生物はそのレパートリーの中から、これに適した突然変異をとりだし、自分を作りかえることによって環境とのバランスをとりもどし、再適応をとげていく」(P.22)
「仮に最初の一回の突然変異で、これらの変化の端緒がえられたとしても、もし突然変異がランダムにおこるものとしたら、つぎにこれを促進するための変化は、いつになったらおこるのかわからないし、その間にあるいはせっかくのこの変化を、もとにもどしてしまうような突然変異が、おこらないともかぎらない。」(P.23)
(P.25)__子孫を残せるような突然変異
「結論。形態的・機能的ないしは体制的・行動的に同じようにつくられた同種の個体は、変わらねばならないときがきたら、また同じように変わるのでなければならない。したがって、この変化をもたらす突然変異は任意の個体におこって、そこから遺伝的に拡散していくだけではなく、原則的にいうならば、そのような突然変異は、遅かれ早かれ、やがて種の全個体におこることによって、種のかちえようとしている適応を、促進するものでなければならない。」(P.26)
「もちろん、突然変異の可能性を否定するわけではないが、必要もないのに突然変異なんかしない、というのである。しかしそのかわり、必要が生じたときには、生物のほうで、突然変異のレパートリーの中から、これぞという切り札を出すことによって、危機を乗りきろうとするのである。それも、一匹や二匹の個体が問題なのではない。同種の個体である以上は、危機にのぞんで、どの個体もが同一の突然変異を現すのでなければならない。同種の個体とは、そういうときにそなえて、はじめから、同じものとして作られているのである。(LF)だから、必要に応じて体質改善をしなければならないのは、じつは種なのである。それでうまくいかないときに、悲運に見舞われるのもまた種なのである。その点で、種のレベルにおいては常に自然淘汰がつきまとい、適応できなかった種は滅亡し、今日われわれのみる完成された生物の種は、すべてこれ、自然淘汰の合格者ばかりである、というようなことはいえても、個体レベルにおいて、かつてダーウィンが考えたように、同種の個体間に自然淘汰のはたらく余地はありえない。」(P.27)
「いや、生物の主体性を抹殺して、進化を説明しようなどというのは、機械論をとおりこした一種の神秘主義でさえある。(LF)これに対し、適応あるいは進化に導く突然変異は、もともと環境に対する生物の側からの(FF)はたらきかけであると私は考える。そう考えるかぎり、環境は進化を誘発するものではあっても、進化の主導権は、どこまでも生物によって掌握されていなければならない。その結果として、適応に成功する場合も、失敗する場合も、あることだろうが、いずれの場合についても、くわしく調べれば生物の側にそうなるべきちゃんとした理由があるからこそ、そうなったのである。それを、生物からみればいわば中立的傍観者であるべきはずである環境のせいにして、自然淘汰というものをその代弁者にでっち上げ、いちいちこの代弁者にお伺いを立てないことには、進化が説明できないというようでは、これはおかしい。生物のことは一応生物の枠内で片づけるというところにこそ、生物学の学としての自律性も、認められるというものではないだろうか。」(P.28-29)__環境は主体か。自然は神?「主体性」を考えるのは今西の限界か。欧米を意識した表現か。
「ここに二つの進化論がある。その一つは、ランダムな突然変異に基礎をおいた進化論であり、これがいわゆる正統派進化論である。もう一つは、方向性をもった突然変異に基礎をおいた進化論であって、私が二〇年以上前から、主張してきたものである。」(P.30)
「もう一つのちがいというのは、ランダムな突然変異に基礎をおく進化論というのは、もと(FF)もと個体の変化から種の起源を、あるいは生物の進化を、説明しようという立場である。これにたいして、方向性をもった突然変異に基礎をおいた進化論は、種の変化から種の起源を、あるいは生物の進化を説明しようとする。すなわち、種とは、環境に適応するため、たえずみずからを作りかえることによって、新しい種にかわってゆく。これが進化であるとすれば、進化とははじめから、種レベルでおこる現象であるというのである。」(P.30-31)
「ひと口にいうならば、それは、生物がなんらかの目的をもって行動すると考えることを、”目的論”的解釈として、極度に排斥する傾向が芽生えつつあった時代であり、ダーウィン自身が、いわば、そうしたムーブメントに対する先覚者の一人であった、ということができる。」(P.32)
「かくして、「生物に、眼ができたから物を見るようになったのではなく、物を見るために眼というものもできたのである。」(西田幾多郎)、ということになるのである。」(P.33)
(一九六四)
人間以前と人間以後 アーサー・キース卿の『人類進化についての新説』について
「生態学でいうコムペティションが、かならずしもつかみあいの闘争を意味するものでないように、コオパレーションも、かならずしも手をとりあっての(FF)助けあいを意味してはいない。この二つは、一つの社会関係をいわばうらおもてから見ているのである。」(P.44)
「グループ間の関係と同じように、グループ内の関係だって、やはりこれをコムペティションの状態にあるとも、コオパレーションの状態にあるとも、解すことができる。われわれはグループのメンバーが、ばらばらにならずに、ひとかたまりとなって生活できるのは、各メンバーの間に順位ができているからだ、と考える。それを、グループ内のメンバーが、その社会的地位のちがいに応じて機能的に棲み分けた、一種の棲みわけ現象である、と(FF)解するならば、さきと同じように、棲みわけることによって、かれらはお互いの生活を成りたたせているのだから、それはコオパレーションの状態にある、ということができるのである。」(P.44-45)
「だからグループ自身の中にも、団結というようのこととは反対な、分裂や崩壊の危険がはらまれていることを、認める必要があるであろう。」(P.45)
「こうした文化のちがいが生ずるまえに、人種はできていなければならぬ。」(P.47)
(P.52)__脳(容量や構造)で人間を判断するのは、人間中心主義。=>男が女よりすぐれていることになる。体格の良い西欧人がすぐれていることになる。
「生物が、自分一個の生活を支えていくために努力するのは、労働ではない。個体本位の立場からいえば、生物としてそれ以上のことをする必要はないであろう。しかるに生物が、自分一個の生活を支えていくだけではなくて、自分以外の者の生活まで支えてやるために努力するとき、この余分の努力のことを労働というのである。」(P.56)__それを労働というのかは分からない。ただ、あまりにも単純な定義だと思う。workとlaborの違い、勤労とのちがい、勉強との違い等。自然との物質代謝ではないかもしれない。
「だからわたくしは、ここのところのつなぎとして、♂が♀に食物を与えなければ、♀が子どもを育てていけなくなったという、種族維持上の一つの危機を仮定することによって、家族の起源と同時に労働の起源を、説明しようとしたのである。」(P.57)__それと恋愛の起源も。
「しかし、考えてみると、頭(FF)蓋容量七五〇ccでもって、サルと人間を区別するというのだって、数字を用いるから正確らしくみえるだけで、内容的にいえば、まことにアービトラリーなものである。境界のないところへもっていって、境界をひこうとするから、そうなるのである。」(P.58-59)__アービトラリーarbitrary 任意の、恣意(しい)的な、勝手な、独断的な、専横な
(一九五二)
人類の進化
「そういう人間のつくりだしたものをひっくるめて、われわれはこれを文化といっていますが、要するに人間というものは、そこのところが他の生物とひじょうにちがっているのでありまして、身体の外に自分の必要なものをつくって、それで人間は環境に適応してゆく。この文化による適応があったから、もうその身体を変える必要がなくなった。また変えるには時間が少し足りないのかもしれない。(LF)それにしても黒い皮膚のものやら、白い皮膚のものやら、いろいろのものができているのは、やはり多少でも身体のつくりかえがおこなわれておった証拠である、といえないこともない。」(P.79)__鈴木さんに言われると「そうかなあ」と思ったけど、今西さんに言われると「なるほど」と思ってしまう。(笑)
「身体をつくりかえるかわりに、そのとき、その場所に適合した文化をつくって適応していったから、身体をみれば同じ一種類のホモ・サピエンスであっても、地域による文化のちがいにはひじょうに大きなちがいが生じることになった。言葉というものも文化の中に入れるとすれば、言葉のちがいというのも、やはり文化のちがいのなかにはいってくるわけです。人類は一種類であるといっても、この文化の分化は、生物における種の分化とまったくおなじ現象でありまして、すこしむずかしい言葉ですが、これを生物学では放散といっております。(FF)これが今日、一度放散した文化が収斂(しゅうれん)しはじめているようにみえる。」(P.80-81)
「そうすると革命というか、下層のものがこれをひっくりかえすなり、あるいは周辺におる野蛮人が出てきてこれをこれを打ち倒した。これは一種の新陳代謝とみてもよいわけです。」(P.90)
「こういう見方をとるひとはあまりないかもしらないけれども、進歩や発展だけをみて、衰退や滅亡を考えないというのは、一面的なものの見方である。なにもやるだけのことやって滅亡するんなら、いわば天寿を全うしたようなもので、大往生をとげるのであるから、人類は滅亡してもいいんじゃないかというのが私の考えなのであります。」(P.92)
(一九六八)
パラントロパスの行方
「学問のなかには日々進歩しているような面も、ないとはいわないけれども、それはおおむね一定の枠ぐみのなかに現れた進歩であって、枠ぐみとなっている大前提そのものはそうそう変わるものでもなく、またそれがそうそう変わるようなものだったら、学問は成立しがたいであろう。」(P.93)
「けれどもここで注意しなければならないのは、この進化史を支えるものがすなわち進化論であるということである。いいかえるならば進化論がまちがっていたら、それに基づいてつくられるであろう進化史も、また当然ちがってきてよいはずであるということである。」(P.96)
(異種間の闘争)(P.104)__西欧人は異種=闘争と結びつける
「いつごろからか人類は、戦争による相手方の殺傷を是認するようになり、いまではゼノサイドといった恐ろしい言葉まで使われるようになってきたけれども、それだからといって人類は、大昔から平気で大量殺戮をやっていたように考えたり、動物の社会ではいつでも弱肉強食が横行しているかのように考えたりするのは、どちらもものの見方をまちがえている。闘争が絶対にないというのではないが、できるかぎり無駄な闘争やそれにともなう殺傷をさ(FF)けて、種族維持の万全をはかるというのが、私のみるかぎりどうやら自然の変わらぬプリンシプルであるらしい。」(P.104-105)
「種の立場を個体の立場に劣らず、ときとしてはそれ以上に重視する私の進化論からいえば、これという理由もないところに新しい種が誕生したり、あるいは既存の種が絶滅したりするようなことは、かりそめにもあってはならないのである。」(P.105)
「どうしてこういうことが可能だったのかという説明は、いずれのちほどするつもりであるが、こういうことから考えても、人類ははじめからただ一種類で進化してきた、生物として例外的なユニークな存在であって、その進化の途中で二種類に別れたり、絶滅種を派生したりしたようなことはかつて一ぺんもなかったというのが、結論をさきに出したことになるかも(FF)しれないけれども、まず述べておきたい私の人類進化しにかんする見解なのである。(LF)そこでつぎに、私のこの見解を支えている進化論に触れておかねばならないが、いままでにすでにたびたび述べてきたとおり、種というものは変わらなければならないときがきたときには、その種に属する個体のどれもこれもが、セレクションなどということとは無関係に、みな同じ方向にむかって変わるのでなければならない。種の個体というものはそういうときにそなえて、平素からつねに甲乙のないようにつくられていなければならないということを、ここでもう一度繰りかえしておくことにしよう。」(P.106-107)
「しかるに人類は早くから道具という便利なものを使用し、道具の使用はそれをとおして、使用者である個体のあいだに甲乙ができないようにはたらいたから、それは分離という方向とは反対に、むしろつねに人類を一つの種として統一していくことに、役だっていたと見なしたいのである。」(P.117)
「それは長い旧石器時代の終わりごろからはじまったものと考えてよいであろうが、やがて人類における道具の使用が急激に強化されだすとともに、人類は新たにつくりだした道具をとおして、それぞれの環境に適応しはじめ、それとともに、その進化史上はじめて分化ないしは分離の方向に歩みだすのである、人類共通文化といったかぼそい紐帯だけを後にのこして。」(P.117)
「しかし、道具の進歩と身体の進化、たとえば脳の発達というようなことに、はじめからそう密接な関係を設定していない私などは、この不均衡をつぎのようにも解してみるのである。」(P.118)__別の種概念。飛ぶもの、光るもの・・・。文化のちがい=>種のちがい
(一九七〇)
進化とはなにか
「スペンサーの考えというのは、ひと口でいえば進歩至上主義とでもいえるであろうか。そのため、進化と進歩との混同をきたし、進化ということを進歩であると誤解するひとさえ、現れるにいたった。」(P.122)
「一五〇万種の生物によって、一五〇万種の世界がつくられている、とみてもよいであろう。」(P.125)__世界=場
「そして、ここに生物の進化がみられるといったが、これを結果的にみたら、生物はこの三五億年間に、たえずまだ他の生物によって利用されていない生活の場を開拓することをつづけ、その開拓に成功し、生存の保証をうることは、みずからを別種として、他の生物から棲みわかれることに他ならなかったから、開拓のすすむとともに生物の種の数はふえていったのである。これを棲みわけという立場からいえば、開拓がすすみ、種の数がふえるとともに、棲みわけの密度が、しだいに高められていった、といってもよいであろう。」(P.126)__生殖で分類するということ。性の肥大化。女と女では子孫はできないから別種?有性生物のみで出現した分類学
「棲みわけはたしかに進化のはたした所産の一つであり、棲みわけをとおして種というものが強化され、確実にされていることは確かだけれども、種の生成ということは、棲みわけとは別個のところで行われているのかもしれない。」(P.127)__弱点?突然変異に頼るか?
「しかしそのまえに、種社会は生物全体社会の部分社会であり、生物の個体というものもまた種社会を構成している部分にすぎないということを認識するならば、生物全体社会の立場を無視して、種社会のみが独走的に変化したり、種社会の立場を無視して、その種社会の構成要素である個体が、勝手気ままに変化してもよいものだろうか、という疑問が、当然おこってもよいはずである。すくなくとも私のように、若い時から生物学におけるホーリズム(全体主義)の影響を、濃厚にうけてきたものにとっては、これ以外の考えようはないのである。」(P.129)
「だから、個体差というものは、個体レベルの問題であっても種レベルの問題ではない。したがって個体差から種の進化を導きだそうとしたところにダーウィンの進化論の誤りがあり、そのところを修正するために突然変異が持ちだされて、今日の正統派進化論が成立するに至ったのだ、というように説明しておいたところを、ここにおいて多少改めねばならなくなったということである。なぜかというと、人類の頭が大きくなることも、その歯が弱小化することも、あるいはウマの足の指が変わることも、みな個体レベルで個々の個体をとおして、達成された並行進化であり、定向進化であるとすれば、そしてまた、それらが並行進化であり、定向進化であるといっても、何十万年、何百万年という時間を必要とする変化であるとすれば、それらはいずれは同じ到着点に至るものとしても、その長い時間のある断面をとらえたときには、個体によってさきに進んでいるものとおくれているものとがあり、それが個体差となって現れているにちがいないであろう。」(P.145)
「するとここのところは、個体差といっても、そのなかには進化に関係のない個体差ばかりでなくて、進化に関係のある個体差もまたふくまれている、というように訂正しておかねばならないであろう。」(P.146)
「これらはいずれも、われわれが生物の現状を近視眼的にみているかぎりにおいては正しくても、悠久な時間をかけて眺めるならば、遺伝情報もおのずから変わり、個体差もおのずからその頻度分布が移動して、いつかは種の枠をこえるにいたるであろう。」(P.146)
「生物に主導性をおくことが目的論になるのであったら、どうして環境に主導性をおくことも目的論にならないのだろうか。」(P.149)
「それよりも生物は、ある程度の幅をもって、あるいはゆとりをもって、環境に対応している、と見ておいたほうがよいのかもしれない。(LF)われわれは普通、新らしい環境にたいし、身体のつくりかえによって生物が適応するところに、新らしい種ができ、進化がすすむというように考えがちであるが、じっさいはこの逆で、種の分離の方がさきにはじまり、そのあとで種それぞれの環境に対する適応がおこるのであるのかもしれない。種の分離とここでいうのは、一つの種社会が二つにわかれて、自然状態においては、もはやこの二つの社会に属する個体のあいだに、交配がみられなくなることをいったのである。」(P.152)
「ホッキョクグマにかぎらず、北極地方に棲むものは、キツネでもフクロウでもみな毛が白くて、それがいままでは環境にたいする適応だといわれてきたから、種社会の分離ののちに環境にたいする適応がおこる、というように考えたのだが、種社会の分離が完全に行われ、分離した二つの社会が完全に交配しない状態がながくつづくものとしたら、この二つの社会に属する個体のあいだにちがいを生じ、適応とはなんの関係もないにもかかわらず、そこに二つのちがった種が、あるいは二つのちがった種社会が生ずる、これがすなわち、隔離(アイソレーション)による種の形成であり、適応とは関係がない以上、このような進化にたいしては、さすがの自然淘汰も手のほどこしようがあるまい。」(P.153)__白いことの説明にはなっていないと思う。
「けっきょく、コーモリにしてみれば、前足が翼に変わったから、空中生活をしなければならなくなったのであろう。けっきょく、コウモリにしてみれば、コーモリになるより仕方なかったから、コーモリになっただけのことであるかもしれない。」(P.155)
「自然科学は物理学を範として、自然の法則を求め、その法則は実験によってくりかえし検証できるということを標榜している。それにたいして、あえて異議を申したてるつもりはないのだが、自然科学者ーー生物学者もふくめてーーのなかには、この地球の歴史のうえで、ただ一回きりしかおもらないで、二度とはくりかえさぬ進化ということを、実験室のなかでくりかえせることのように考えているひとが、ないとはいえないのである。はたしてそういうものだろうか。進化を、突然変異と自然淘汰という、ありもしないことをまことしやかに考える(FF)実験遺伝学にまかせることは、人類の将来をコンピューターにまかせるのと同じくらい浅はかなことである。進化ということをとりあげるまえに、この辺でいま一度、それがはたして今日の自然科学の対象に、なりうるものかどうかを、検討してみる必要がある。」(P.156-157)__(自然)科学の本質について。
(一九七四)
私の進化論の生いたち ーーそしてそのもっとも新しい展開までーー
(P.165)__人間の「社会」という環境。隣の人も環境!!
(P.168)__社会という環境。体という環境
「だから、慎重を期する科学者にとって、生じっかな起源論や進化論に言及することは、タブーとされていた時代もあったのである。一方で実験室のミクロ屋さんたちにすれば、生物というものがそれなりに歴史をもったものであるとか、社会をもったものであるとかいうことを、考える必要などすこしも感じないであろう。その人たちにすれば、そうした生物の歴史性や社会性を捨象して、できるだけ生物を物質扱いし、物理学的化学的操作をとおして生物を物質的に解明することが望ましいのであり、それがまた現在の科学を育ててきた還元主義(reductionism)に忠実(FF)である、ということにもなるのであろう。」(P.169-170)__〈私〉から始まると、歴史や社会とは別に、すべてが存在するということになる。〈私〉は「結果」ではない。
「種社会というのは、その種に属する個体のすべてを包含し、そのすべてによって構成せられた、ひとつの全体であり、多種とみだりに交わらないという点では、それ自体が独立体であるとともにまたひとつの完結体でもある。しかし、さきほども述べておいたように、生物的自然そのものが全体として、やはりひとつの完結性をそなえたものであるとするならば、この生物全体社会としての生物的自然の完結性は、その構成要素としての、あるいはその部分社会としての、それぞれの種社会の完結性に待つものであり、その完結性を反映したものに他ならない、と考えざるをえない。そして、この全体と部分との完結性をとおして結ばれた相互関連性こそは、生物進化のもたらしたもっとも偉大な、もっとも巧妙なプロダクトであると思うのであるが、いま種社会のインサイドをのぞくといっておきながら、こうしたことに触れたのは、種社会の完結性といい、独立性といっても、それはそれ自体が気ままに、他のもろもろの種社会と無関係に、獲得した完結性でも独立性でもなくて、むしろ、他のもろもろの種社会とともに、生物全体社会を構成し、その堅実な部分社会であらんがために発達さした完結性であり、独立性でもある、ということがいっておきたかったからで(FF)ある。多少観念的な表現に流れているきらいはあるけれども、つまり種社会を生物全体社会の部分社会とみる以上、全体に対する部分の位置づけということも、進化の過程でおのずからきまってこないわけにはいかないから、全体をはずれて、ある種社会だけが独走的に変化し、進化するととは許されないはずである、ということである。」(P.173-174)__全体と部分というのは、前の科学批判と同様に「分析」的思考に対する批判である。部分に分けて考えるということ、それは本質を捉えようというギリシア的思考とはまたちがったものです。
「ただし、人為淘汰の場合は見えざる手ではなくて、明らかに人間がある目的をもってセレクションを行うのであるが、自然淘汰の場合はそこのところがどうなるかというと、ダ(FF)ーウィンはそこで適応ということを考えるのである。適応も棲みわけと同じように、進化のプロダクトであるにはちがいないが、それ自体では進化の説明にならない。そこで適者生存ということを仮定することによって、はじめてダーウィンはかれのセオリーがまとまったと思ったことであったろう。」(P.187-188)
「これもまえに一度いったことの繰りかえしになるが、ダーウィン以来の進化論じゃが、個体変異のなかの最適者であろうと、突然変異として現れた最適者であろうと、そうした個体が端緒となって種がかわり、進化がおこるように考えていたということは、生物といい、種といっても、個体以外に手がかりとなるような研究対象を持ちあわせていなかったからである。」(P.192)__その後の進化論は、どんどんミクロの世界にはいっていきます。それは技術的、環境的限界ではなくて、思考形式の問題です。
「しかし、なにもないところへひょっこりと個体変異のなかの最適者が現れたり、突然変異としての最適者が現れたりするのではなくて、そこには最適者でなくてもその他大勢の同種の個体というものが、つねに存在しているのである。最適者はそれらのものとは絶対に交配しないというような条件をつけぬかぎり、いくら最適者であろうとも、そしてその最適者(FF)が生きのこって子孫をのこすようになろうとも、たった一個体であったり、あるいは少数個体であったりするかぎりは、交配を重ね世代を重ねてゆくうちに、いずれはその他大勢の同種の個体のなかに、埋没してしまうに相違ないのである。」(P.192-193)__民衆の存在
「それにもかかわらず、どの種をとってもその個体のあいだにダーウィンの着目したような個体変異というものの存在することも、また事実である。しかし、このような個体変異は、種の規格をこえたものではなくて、その規格の範囲内に生じた一種のばらつきにすぎないと考えたならば、このような個体変異の存在によって、種の個体に甲乙があるというわけにはゆかぬのである。」(P.193)
「われわれの考えている自然とは、そのような突然変異がおこらないように仕組まれた自然なのである。」(P.195)__「偶然と必然」参照
「ここのところを表現するため、私はよく種社会とそれを構成するところの種の個体とは、二にして一のものであるという表現を用いる。二にして一のものであるということは、どちらか一方が変わるときがきたら他方もまた変わるということである。これをもっとミクロにみれば、種の個体が変わるときには遺伝子の構成のうえでも、やはりそれに応じた変化があってしかるべきであろう。そうなるとまた種の個体とその遺伝子とは二にして一のものであるといわねばならなくなる。すくなくとも、いままで信じられてきたように遺伝子がさきに変わり、その結果として突然変異を生じ、さらにその結果として種が変わるといったような一連の因果関係によって、生物の種が進化してきたものではない。それを、そのようにしか考えられなかったというのは、だ(FF)れもかれもが還元主義のおとし穴におちこんでいたからである。変わるべきときがきたら、種社会も種の個体も、またその個体のなかにしまいこまれた遺伝物質も、みな時を同じうして変わるのでなければ、システムがこわれてしまう。」(P.196-197)__西田幾多郎。と、自然に対する全面的な信頼。
「私はいま言語の進化を考えながら、こういうことをいっているのである。」(P.206注)
解説 小原秀雄
(P.210)__生物の進化を社会進化に安易に結びつけた社会進化社会進化論。でも、根本ではつながっていて、それを可能にした論理構造が、親は子より優れているとか、子は親より進んでいるとかというのもどちらも「論理」。もともと日本にはなかった。
(P.211)__構造主義的?主体ではなく、構造が支配する。
「自然の豊かさやダイナムズムを、現在の自然科学が十分にとらえていないと思われるが故に、この今西進化論は魅力的である。そして、それが仮設として定式や「科学的」説明や論証の重箱の隅までもの完全さを期さないが故に、一般の人々にもわかりやすいのである。それはまた、自然を見、そして描いた生物像が、形骸化した自然科学を超えて拡がりがあるからにほかならない。しかも自然による実証性を備えている。」(P.218)__差し障りのないように書いたつもりかもしれないけど、どこかピントがずれている気がする。


