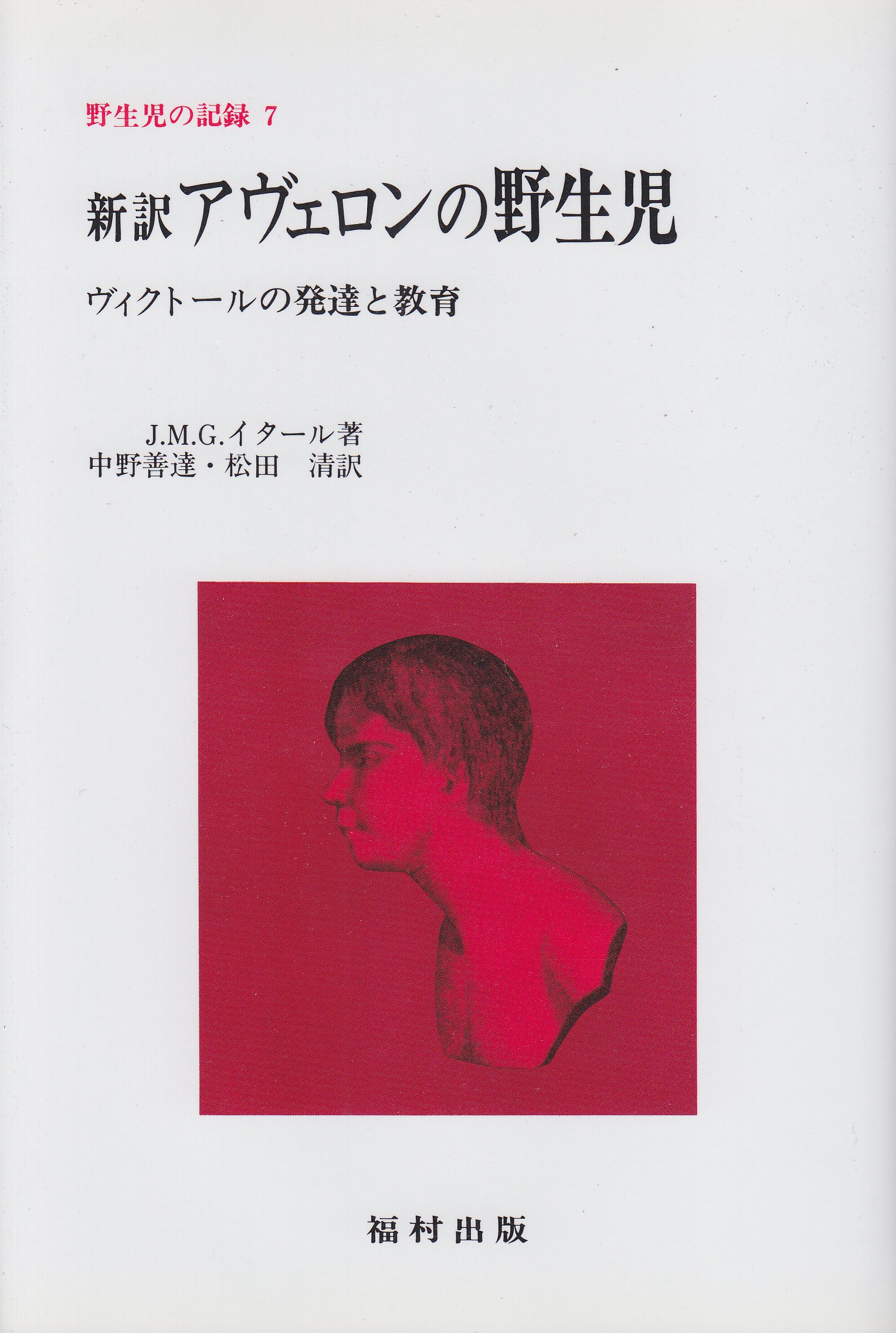
「国際障害者年[wiki(JP)]」
私の本には帯が二重にかかっていて、「完全参加と平等を目指して 国際障害者年 81年版障害児教育図書総目録」と書いてあります。
私の本には珍しく、図書館の払下げのしるしも古本のしるしもありません。新本を買ったのでしょうね。1980年3月20日第4刷 900円。
「野生児の記録 7」です。『漢詩のレッスン』に「カスパー・ハウザー」が出てきて、このシリーズの中古を探していたら、私の本棚にこの本がありました。多分購入当時に一度読んでいると思います。
ただ、わたしたちが物を見たり感じたりする仕方は、それぞれが属している文化の枠組みの中で規定されているということは確かです。それはしかし、わたしたちの物の見方を決め、狭く固定されたものに制限してしまう一方、同時にわたしたちの物の見方を保証もしているのです。
もしこうした文化の保証がなかったら、人の文化と切り離されて成長した少年、カスパール・ハウザーのように、美しい風景を目にしてもすべてがまだらにしか見えない、ということになってしまいます。(種村季弘『謎のカスパール・ハウザー』)。(『漢詩のレッスン』、P.159)
社会性(あるいは文化)をもたずに育った(人間の社会で育たずに育った)子どもは、言語を習得できるののでしょうか。
また、自己表現、セックス、抽象的思考・・・ができるのでしょうか。
ヴィクトール
フランスのアヴァロンで1797年に全裸で発見された野生児は「ヴィクトール」と名付けられました。発見当時は9〜10歳だったようです。1800年1月に捉えられ、ナポレオン・ボナパルトの弟リュシアン・ボナパルトの命でパリに移送されます。「見世物」のような扱いを受けていましたが、医師のフィリップ・ピネルは「先天的な知的障害」と診断しました。
その後、1801年にジャン・イタールに引き取られます。19世紀の始まりの年です。そしてこのヴィクトールを生徒として、いろいろな機能の回復訓練(実験)をします。この本はその記録です。イタールの捉え方はつぎのようなものです。
「そこで、彼は四歳か五歳のころ棄てられたこと、その時なんらかの観念や単語を教育によって身につけていたとしても、孤立の結果それらがすべて記憶から消え去ってしまったことは確かであり、立証されているといえる。
現在の状態をもたらした原因について、私は以上のように考えた。原因の予測をなぜ治療の成功にとって都合のよいものにしたかは、〔読者に〕わかっていただけるはずである。実際、人間社会にわずかの期間しかいなかったという点からすると、「アヴェロンの野生児」は低能の青年というよりも、むしろ〔生後〕一〇か月か一二か月の子どもであり、そうした青年とはちがって、どうしようもないような注意散漫、可塑性を欠いた器官、偶然に鈍感になった感受性といった、反社会的な習慣を身につけた子どもである。この最後の観点からすると彼の状態は、純粋に医学的な症例といえる。しかもその治療は、精神医学に属するものである。(P.28)
19世紀初頭に知的障害者がどのように扱われていたのかは、ミシェル・フーコーの『狂気の歴史』あたりが参考になります。現在(21世紀のはじめ)とは状況がちがいます。上記のピネルは、「精神病患者を鎖から解き放った初めての医者」と言われています。当時の精神病棟のイメージは、私は映画『アマデウス』(ミロス・フォアマン監督、1984年)のイメージが強いですね。
時代としては、資本主義が勃興してきて、フランス革命直後です。「自由・平等・博愛」です。でも、それは「働く能力がある者」を「人間」として見た時のスローガンです。エンクロージャー(囲い込み)などで耕作地を追われ都会に来たものの、「働けない者」、あるいは「働かない者」は、犯罪者や狂人と同様の扱いをされました(イギリスの『救貧院』の実態についてはマルクスの『資本論』に詳しい)。「矯正」されて、労働現場に行く人は人間扱いをされましたが、そうでない人は悲惨だったようです。だから、ヴィクトールを「低能の青年」「知的障害」と見るのか、「子ども」と見るのかでは大きなちがいがあります。前者は労働ができない、つまり人間の扱いはされませんが、後者なら、教育(訓練)次第で労働が可能になる「可能的人間(労働者)」だからです。
イタールの自然観
イタールは、フランスの上流階級の出身だそうです。彼の自然観は詳しくは書かれていません。
自然というものは、見かけ上は矛盾する法則にしたがって、自らひそかに傷つけたり解体しようとするものを、公然と修復し維持しようとするのである。」(P.27)
ここでは「自然」は、野生の動植物をイメージしていると思われます。野生の動植物は、雨風や他の動物によって傷つけられても、自分で傷を治して生き延びます。「アヴェロンの野生児」というのは、そのイメージが重なっているのではないでしょうか。
自然(nature)についての感覚は、当時のフランスと当時の日本では異なります。今の日本とも違うでしょう。分類学の父カール・フォン・リンネが発展させた博物学はラマルクらによって、「生物学」となり、ダーウィンの進化論に続いていきます。自然は客体として、〈主体〉の目の前に「投げ出された」ものです。だから、〈主体〉が観察したり、実験したり、あるいは支配する「対象」です。ですから、客体としての自然は〈主体〉とは相容れないものです。ですから、客体は〈主体性〉をもってはいけないのです。〈主体性〉をもつものが「人間」であり、その多くは当時の「労働者」なのです。ヴィクトールに対するピネルとイタールの判断の違いは、「どこまでを人間と認めるか」の違いです。この本(報告書)で書かれている様々な教育(訓練、実験)は、ヴィクトールを「人間にしようとする教育」です。
最後に閣下、こうした長期の実験をどのような観点から捉えようとも、自然人の方法的教育と考えるにせよ、自然に疎んじられ、社会に棄てられ、医学に見放された者の一人に対する身体・精神療法として見るにせよ、後に施された治療もまだ施さなければならない治療も、すでに起きた変化もこれから期待できる変化も、人間愛の声も、これほど完全な遺棄、これほど数奇な運命が引きおこす関心も、あげてこの異常な青年に対する学者の注目、当局者の配慮、政府の保護を呼びかけているのです。(P.140-141)
人間になるかもしれない「自然人」「野生児」に手を差し伸べようとするイタールの訴えです。もし人間として認められないとしても、「症例」であれば社会的に価値を持ち、保護の対象になりえるでしょう、ということです。
精神的治療、あるいは教育の目的と成果
イタールはヴィクトールの教育の主要目的を5つあげています。
第一の目的ーー彼がいま送っている生活をもっと快適なものにして、とりわけ、彼が抜か出したばかりの生活にもっと近づけることによって、彼を社会生活に結びつけること。
第二の目的ーー非常に強い刺激によって、時には魂を激しくゆさぶる感動によって、神経の感受性を目覚めさせること。
第三の目的ーー彼に新しい欲求を生じさせ、周囲の存在との関係を増すようにさせて、彼の観念の範囲を拡大すること。
第四の目的ーーどうしてもそうしないではいられないという必要性によって模倣訓練をさせ、彼を話しことばの使用に導くこと。
第五の目的ーーしばらくの間、非常に単純な精神作用を身体的欲求の対象に働かせ、その後、その適用をもっぱら教育課題に振り向けさせること。(P.29)
これらが、「人間であること」の条件であり、「啓蒙」「開化」「文明化」の目的です。これらのうち、成果がなかったものとあったものをイタールは率直に記載します。まず、否定的な評価。
(一)、聴覚および音声器官がほとんど完全に無能なため、この青年の教育はまだ不完全で、永遠に不完全であるにちがいないこと。(二)、不活動が長かったため、知的能力の発達は緩慢かつ困難であること。この発達は、文明の中で育った子どもなら時間と環境の自然のたまものだが、ここでは、きわめて積極的な教育で成果をあげるにも労力と時間が必要であり、どれほど強力な教育手段もごくわずかの効果をあげるだけで尽きてしまうこと。(三)、感情能力も、その長いマヒから抜け出るのが遅く、適用のさいは根深い利己心に従属してしまうこと、また、思春期はこの能力を大いに発達させる心か、きわめて判然と発言したのに、次のことを証明したにすぎなかったこと。すなわち、〔一般の〕人間において、感官の欲求と心の感情との間に関係があるとすれば、その共感的結合は、寛大な情念のほとんどと同じく教育によってもたらされたものであることを。(P.139-140)
次に、肯定的な評価。
(一)、視覚と触覚の発達、味覚の新しい快感は、われわれの野生児の感覚と観念を増大させ、知的能力の発達に大いに貢献したこと。(二)、この〔知的能力の〕発達を全面的に考察すれば、好ましい変化のなかでも、とりわけつぎの変化がみられること。すなわち、思考サインの規約的価値の認識、この認識の応用による対象の指示、対象の性質や行為の表示、したがって、周囲の人間と生徒との関係のひろがり、自分の欲求を彼らに表現する能力、彼らから命令を受ける能力、彼らと思想を自由に継続的に交換する能力。(三)、野外の自由に対する際限のない趣味、社会生活のほとんどの快楽に対する無関心にもかかわらず、ヴィクトールは、自分の受けた世話には感謝し、あたたかい友情を抱くことができ、良いことをする喜びを敏感に感じ、間違いを恥じ、自分の激怒を後悔すること。(四)、最後に閣下、こうした長期の実験をどのような観点から捉えようとも、自然人の方法的教育と考えるにせよ、自然に疎んじられ、社会に棄てられ、医学に見放された者の一人に対する身体・精神療法として見るにせよ、後に施された治療もまだ施さなければならない治療も、すでに起きた変化もこれから期待できる変化も、人間愛の声も、これほど完全な遺棄、これほど数奇な運命が引きおこす関心も、あげてこの異常な青年に対する学者の注目、当局者の配慮、政府の保護を呼びかけているのです。(P.140-141)
(四)は引用が重なってしまいました。
実験と教育
ここでヴィクトールとイタールの立場は微妙です。「人間」であれば、「実験対象」にすることはできません。それは「タブー」です。その場合は「実験」ではなく「教育」になります。逆に、人間でなければ、実験です。でも、やっていることは同じなのです。
「教育」は、「人間を育てるための技術・方法」の総体です。教師は「対象」としての生徒を「人間」にすることが使命であり目的です。言い換えれば〈対象〉を〈主体化〉することが目標なのです。生徒が「人間」になれば、教師の行為は称賛され、なれなければ批判されます。
日本で教育や育児における「体罰」が問題化されて長い時間がすぎました。私は小さいころ、よく親に殴られました。殴られて私が泣くと、「メソメソ泣くんじゃない」といって殴られました(笑)。その頃から「体罰」は問題となっていましたから、もう半世紀にはなるでしょう。いまでも、体罰があればすぐに「ワイドショー」に取り上げられます。「コメンテータ」と言われる人は、口を揃えて「時代錯誤だ」と言います。スポーツ界でも、「体罰」のようなものは批判されます。でも、その生徒が社長や総理大臣になれば、「あの先生のおかげだ」というのではないでしょうか。選手がオリンピックでメダルを取れば、「あのコーチのおかげだ」というのではないでしょうか。そんな気がします。
教育、そして学校制度を考える時には、この「対象の主体化」をどうとらえるのかということを考える必要があります。ヴィクトールとイタールの関係が、今も続いているのです。
言語
ヴィクトールは言葉を話すことができませんでした。イタールも一旦諦めます。
それでもめげずに辛抱し、もっと長期にわたってこの器官の頑固さと闘いましたが、治療を継続し時が流れても何の変化もおきないのを知り、とうとう、話しことばをあたえる最後の試みに終止符を打ち、生徒を不治の啞のままに放置したのでした。(P.124)
言語習得には「臨界期」があると言われています(第一言語の臨界期、第二言語の臨界期)。その年齢を越えるとその言語を習得できないという肉体的年齢のことです。
でも、それは「文法に則った音声言語」として言われることが多いようです。二七歳の男性イルデフォンソは、聾者です。かれは、『言葉のない世界』(スーザン・シャラー著)に生きてきました。聾者ですから音声言語は意味をなしません。スーザン・シャラーは彼に手話を通じてことばを教えます。結果、イルデフォンソは手話で抽象的な思考ができるようになります。言葉を覚えたのです。
ヴィクトールとイルデフォンソの違いは、イルデフォンソはことばをもたなかったけれど、ずっと文化(社会)の中にいたということです。発音(調音)器官が正常かどうか、音声としての言語かどうか、年齢が何歳か、というようなことよりも、その人が文化をもっているか、どのような文化で育ったのか、ということが大切な気がします。
同一性
最後に、気になったある実験の報告を取り上げます。
つまり、使用法や特性の同一性を生徒に証明することで、対象の同一性を成り立たせ、外見上違っている物がどういう共通の性質で同じ名前に値するのかを理解させる、ひとことでいえば、対象を相違関係でなく共通点で考察させることが問題となったのです。(P.112)
ヴィクトールは「違い」は認識できても、「同じ」が認識できなかったということです。私たちは「同じ」という考えのもとで、「違い」を考察しがちです。「[同じ]がなければ[違い]なんてあるわけないじゃないか」と思ってしまいます。そのいい例が「間違い探し」です。「同じ」という前提を持って「違い」を見つけ出すゲームです。
でも、本当にそうでしょうか。これを読んで私は、「同じ」が前提となっているのではないし、「同じ」が「違う」の対立概念でもない、と思いました。いってみれば、すべては違っているのです。当たり前です。ただ、「違いの差」は生存上必要なことなのです。「おいしい、まずい」という差と「食べられる、毒」の差のようなことです。ヴィクトールにとって、食事をくれるゲラン婦人と優しく接してくれるイタールは別の人です。「同じ人間」という事を考える必要はないのです。
昨日の私と今日の私は違います。昨日の獲物(たとえばお腹がいっぱいの時の熊、名前はカムイ)と今日の獲物(お腹を減らした時のカムイ)が違うように。「昨日と同じ熊だ」と頭を撫でるのは危険です。「柳の下の泥鰌」、漁師は「昨日はここで捕れたから、今日もここで捕れる」と単純には思わないのではないでしょうか。その時の天候や、水の温度・色、海鳥の動き・・・等々から経験を駆使して判断すると思います。農業でも同じようなことが言えると思います。でも、工業ではそれではだめですね。
上記の「同じ熊」というのは、「熊」という同じイデア(概念)をもとにして判断しているのです。これが西欧論理の中心的原理である「同一性原理」です。工業では、ある製品のイデア(完成品)があります。そのイデアという全体があって、個々の製品は「要素(部分)」になります。その「部分」は部分であるが故に、さらに「部分」に分けることができます。それが「ユニット」であったり「部品」であったりします。人間も同じです。「人間」というイデアのもとでは、「個人」は部分です。でもこれは分けることはできません。それが「アトム」です。これを分けてしまうと、考察、観察の〈主体〉がなくなってしまうからです。これが「自己同一性(アイデンティティ)」です。近代以降の西欧論理はすべてここから出発します。アトムは自己同一性を対象に投影したものなのです。
うまく説明できなので、「問い」を説明にします。
「うちのタマも隣のミケもどちらも同じ猫だ」というのと「一郎と花子は同じ生徒だ」というのの違いは分かりますか。ねこに興味がない人や、一郎と花子の担任の先生もいるのでとても微妙ですが。
〈抜き書き〉
訳者まえがき
第一報告 野生人の教育について あるいは、アヴェロンの野生児の身体的・精神的な初期発達について 国立聾唖学校医師、パリ医学会会員 E.M.イタール
共和暦一〇(一八〇一)年葡萄月(ヴァンディエール)
はじめに
「アヴェロンの野生児」の初期発達について
「これら消去できない多くの証拠は、この不幸な子が、長期にわたって完全に遺棄されていたことを示している。また、もっと一般的・哲学的見地からするならば、これらは、自分の力だけに委ねられたときの人間の弱さとか無能力〔といった主張〕に対する反証であると共に、自然の豊かさをも証明していることになる。自然というものは、見かけ上は矛盾する法則にしたがって、自らひそかに傷つけたり解体しようとするものを、公然と修復し維持しようとするのである。」(P.27)__自然natureについての感覚は、フランスと、明治以前の日本と、今の日本と異なっている。ここでは、野生の動植物をさしていると思われる。
「そこで、彼は四歳か五歳のころ棄てられたこと、その時なんらかの観念や単語を教育によって身につけていたとしても、孤立の結果それらがすべて記憶から消え去ってしまったことは確かであり、立証されているといえる。(LF)現在の状態をもたらした原因について、私は以上のように考えた。原因の予測をなぜ治療の成功にとって都合のよいものにしたかは、〔読者に〕わかっていただけるはずである。実際、人間社会にわずかの期間しかいなかったという点からすると、「アヴェロンの野生児」は低能の青年というよりも、むしろ〔生後〕一〇か月か一二か月の子どもであり、そうした青年とはちがって、どうしようもないような注意散漫、可塑性を欠いた器官、偶然に鈍感になった感受性といった、反社会的な習慣を身につけた子どもである。この最後の観点からすると彼の状態は、純粋に医学的な症例といえる。しかもその治療は、精神医学に属するものである。」(P.28)__「低能」ではなく、「症例」であることによって、価値があり保護される存在となる。
「第一の目的ーー彼がいま送っている生活をもっと快適なものにして、とりわけ、彼が抜か出したばかりの生活にもっと近づけることによって、彼を社会生活に結びつけること。(LF)第二の目的ーー非常に強い刺激によって、時には魂を激しくゆさぶる感動によって、神経の感受性を目覚めさせること。(LF)第三の目的ーー彼に新しい欲求を生じさせ、周囲の存在との関係を増すようにさせて、彼の観念の範囲を拡大すること。(LF)第四の目的ーーどうしてもそうしないではいられないという必要性によって模倣訓練をさせ、彼を話しことばの使用に導くこと。(LF)第五の目的ーーしばらくの間、非常に単純な精神作用を身体的欲求の対象に働かせ、その後、その適用をもっぱら教育課題に振り向けさせること。」(P.29)
第一章
「子どもの習性にさからわず、むしろそれと妥協し、そうすることで最初の指導目的を果たすことができたのである。」「確かに、人間というものは、どんな境遇にいようとも、新しい感覚を心から待ち望むものなのである。」(P.32)__感情があった?観察者がそう感じたということ?犬の喜びがわかるか?
(感情の叙述)
第二章
第三章
第四章
「こうした身振りや表情による言語(langage á pantomimes)のことを補っておくと、ヴィクトールは、こうしたものを表現するだけではなく、同じぐらいたやすく理解もできるのである。ゲラン婦人が彼に水をもってこさせようとする時は、壺をひっくり返してみせ、それが空(から)なことを見せるだけで十分だった。一緒に食事中、私に水を注がせようとする時も同じやり方で十分だった。だが、このようなコミュニケーション手段についての彼の対応の仕方で最も驚かされるのは、こちらの意志を伝えるのに、事前の教育やお互いの取り決めもぜんぜん必要ないということである。」(P.61)
第五章
「不変の時の流れは、体力の面でも発達の面でも、幼年期に与え老年期にすべてを奪ってしまうが、彼の教育はそうした時の流れに期待する成果とは独立したものなのである。」(P.76)__以下、「自然に帰れ」への反論
「一 純粋に「自然状態」(étre de nature)にある人間は、多くの動物よりも劣ること。〔自然状態というものは〕根拠もなしにたいへん魅惑的な色彩を帯びさせられてが、それは無能と野蛮の状態であり、個人は同類〔人間〕に特徴的な能力を奪われ、知性も感情ももたず、動物的機能だけに局限された不安定な生活をみじめに送るにすぎない。(LF)二 人間にとって生得的だとされている精神的優越性は、ある強大な動機から人間を他の動物の上に押しあげる文明化の帰結に他ならないこと。その動機とは、人間に支配的な感受性であり、この本質的特性から模倣能力が生まれ、また、人間として新しい欲求の中に新しい感覚を求めさせる永続的な傾向も生まれること。(LF)三 諸器官の教育、とりわけ音声語の習得に向けられるこの模倣能力は、幼児期にきわめて強く活(FF)発だが、年齢の上昇や孤立によって、また、神経の感受性を鈍らせる傾向のあるすべての原因によって急速に弱まってしまうこと。したがって、模倣効果のうち、疑いもなく最も驚くべき、また最も有用な成果である調音は、幼児期をすぎてしまうと無数の障害をこうむってしまうこと。(LF)四 どんなに孤立した野生人でも、最高度の文明状態にある都会人と同じく、観念と欲求の間に恒常的な関係が存在すること。開化した民族における、常に増大するさまざまな欲求は、人間精神の発達の重要な手段と考えられること。そこで、次のような一般命題を立てることができる。すなわち、われわれの欲求の数を増大あるいは減少させる傾向をもつ偶然的な要因は、それが局地的なものであれ国家的なものであれ、必然的にわれわれの知識の領域や科学・芸術・産業の分野を拡大あるいは縮小する力をもっていること。(LF)五 現段階の生理学的知識によれば、教育の歩みは現代医学の光によって照らすことができるし、また、照らさなければならないこと。現代医学は、各個人の器質および知性の異常を検討し、彼に対して教育がおこなうべきこと、社会が彼に期待できることを決定し、あらゆる自然科学のうち最も強力に、人類の完成に協力することができること。」(P.76-77)
第二報告 アヴェロンの野生児の新しい発達および現状にかんする内務大臣閣下への報告書 帝国聾唖学校医師、医学博士 E.M.イタール
学士院歴史・古代文学会終身書記 ダシエ氏より内務大臣閣下への書簡 一八〇六年11月一九日、パリ
内務大臣閣下への報告
「この青年を正しく判断するには、彼自身〔の過去〕としか比較してはなりません。同年齢の青年と比べるなら、彼は不具者にしか他なりませんし、かつて社会の廃棄物であったように、今や自然の廃棄物です。」(P.86)
第一系列 感覚器官の機能の発達
第二系列 知的機能の発達
「つまり、使用法や特性の同一性を生徒に証明することで、対象の同一性を成り立たせ、外見上違っている物がどういう共通の性質で同じ名前に値するのかを理解させる、ひとことでいえば、対象を相違関係でなく共通点で考察させることが問題となったのです。」(P.112)__「違う」ということが「同じ」ということから出てくるのではない。同じが前提となっているのではないし、同じが違うの対立概念でもない。いってみれば、すべては違っている。その「違いの差」が生存上必要なことである。「おいしい、まずい」と「食べられる、毒」の差のように。昨日の私と今日の私は違う。昨日の獲物と今日の獲物が違うように。そこに同一性を見ることは必要ではないのかもしれない。同一性原理。自己同一性。少なくとも、「同じ」という概念は社会的なものである。
「この場合、問題は与えられた形を盲目的に模写する(FF)ことではなく、結果の相違にとまどわず、その精神と様式を再現することにあるのです。それは、生徒が他人のやるのを見てそのまま型どおり反復することではなく、また、物真似をする動物にある程度やらせられるような反復でもなく、その手順・適用のどちらも変えることのできる、知性的で合理的な模倣です。」(P.121-122)__今度は同じことにちがいを見つけること。結果と原因の取り違え。因果関係そのものを問うべき。
「そこで幼児は、青年でさえそうなったりしますが、生まれ故郷を離れると、その国の身振り・発音・語彙を急速に失ってしまいます。しかし、いわゆるお国なまりを作り出している声の抑揚は、決してなくなったりはしません。」(p.122)
「それでもめげずに辛抱し、もっと長期にわたってこの器官の頑固さと闘いましたが、治療を継続し時が流れても何の変化もおきないのを知り、とうとう、話しことばをあたえる最後の試みに終止符を打ち、生徒を不治の啞のままに放置したのでした。」(P.124)
第三系列 感情能力の発達
「閣下は次に、同じく発達の側面でありますが、まず生存本能の欲求の自覚によって目覚めた感情能力(facultés affectives)が、つぎに、それほど利害の関わらない感情、もっと外向的な感動、さらには人間の心情の栄光や幸福を作り出す寛大な感情を生み出すのをご覧になるでしょう。」(P.125)
「彼の目からは、相手は自分を養ってくれる手に他ならず、また、その手はその中身に他ならなかったのです。」(P.125)
「しかし、欲求がしだいに多様化し、そのため、われわれとの関係やわれわれの世話がますます多くなってくるにつれて、マヒした心もとうとう、まぎれもない感謝や友情の感情に門戸を開きました。」(P.127)
「生徒の行為は、まったく正当な復讐行為だったのです。これは、正と不正の感情、この社会秩序の変わらぬ基礎が、もはや生徒の心に無縁の存在ではなくなったことの明白な証拠でした。」(P.134)
「これは申し上げずにはいられないことですが、ヴィクトールは感謝の気持や友情を敏感に感じるようになり、役立つことの喜びを強く感じているようにみえましたが、本質的には依然として利己主義者でした。」(P.134)
「というのも、ふつうの青年の場合、生殖器の興奮はおよそその前に女性への愛があり、あるいは、少なくとも愛を常に伴っていますが、われわれの欲求と嗜好のこのような一致は教育によっても男女の区別をぜんぜん習得せず、ただ本能のひらめきのおかげでやっとその区別を垣間見るものの、自分の現状にはそれを応用しない存在〔ヴィクトール〕には、あり得ようもなかったのですから。(LF)こんなわけで、私は、この青年に思い切って不安の秘密や欲望の目的を暴露すれば数えきれない利点を引き出すことができる、と信じて疑いませんでした。しかし反面、そうした実験を試みることが許されたとしても、われわれの野生児は、この欲求を教えられたら、他の欲求と同じように、自由にまた公然と満たそうとして、言語道断なみだらな行為に及ぶのではないかと、心配せずにはいられま(FF)せんでした。」(P.138-139)
「(一)、聴覚および音声器官がほとんど完全に無能なため、この青年の教育はまだ不完全で、永遠に不完全であるにちがいないこと。(二)、不活動が長かったため、知的能力の発達は緩慢かつ困難であること。この発達は、文明の中で育った子どもなら時間と環境の自然のたまものだが、ここでは、きわめて積極的な教育で成果をあげるにも労力と時間が必要であり、どれほど強力な教育手段もごくわずかの効果をあげるだけで尽きてしまうこと。(三)、感情能力も、その長いマヒから抜け出(FF)るのが遅く、適用のさいは根深い利己心に従属してしまうこと、また、思春期はこの能力を大いに発達させる心か、きわめて判然と発言したのに、次のことを証明したにすぎなかったこと。すなわち、〔一般の〕人間において、感官の欲求と心の感情との間に関係があるとすれば、その共感的結合は、寛大な情念のほとんどと同じく教育によってもたらされたものであることを。」(P.139-140)
「(一)、視覚と触覚の発達、味覚の新しい快感は、われわれの野生児の感覚と観念を増大させ、知的能力の発達に大いに貢献したこと。(二)、この〔知的能力の〕発達を全面的に考察すれば、好ましい変化のなかでも、とりわけつぎの変化がみられること。すなわち、思考サインの規約的価値の認識、この認識の応用による対象の指示、対象の性質や行為の表示、したがって、周囲の人間と生徒との関係のひろがり、自分の欲求を彼らに表現する能力、彼らから命令を受ける能力、彼らと思想を自由に継続的に交換する能力。(三)、野外の自由に対する際限のない趣味、社会生活のほとんどの快楽に対する無関心にもかかわらず、ヴィクトールは、自分の受けた世話には感謝し、あたたかい友情を抱くことができ、良いことをする喜びを敏感に感じ、間違いを恥じ、自分の激怒を後悔すること。(四)、最後に閣下、こうした長期の実験をどのような観点から捉えようとも、自然人の方法的教育と考えるにせよ、自然に疎んじられ、社会に棄てられ、医学(FF)に見放された者の一人に対する身体・精神療法として見るにせよ、後に施された治療もまだ施さなければならない治療も、すでに起きた変化もこれから期待できる変化も、人間愛の声も、これほど完全な遺棄、これほど数奇な運命が引きおこす関心も、あげてこの異常な青年に対する学者の注目、当局者の配慮、政府の保護を呼びかけているのです。」(P.140-141)
付録
付録一 「アヴェロンの野生児」の名で知られる子どもに関する人間観察家協会への報告 医学校教授、〔人間観察家〕協会会員 フィリップ・ピネル
(P.166)__自分の文化(社会)をもたずに育った子ども。「ことばのない世界・・男」は話さないが、文化の中にいた。他文化を自分化の「物語」で解釈する。他人を自分の物語で解釈する。同じ文化に所属するなら、ある程度は同じ。あるいはその単文化を知っていること。
付録二 人間の優位性に関する諸観察 サン=シモン 『人間科学に関する覚え書き』(一八一三年)より
__あの社会主義思想化のサン=シモン。著作集第二巻にこれの翻訳あり。
(クックやラ・ベルーズの研究観察)「今やわれわれは、間断のない一連の観察事実を拠り所にして、当然のことながら万人の中で最も無知であった原始人から、文明においても科学においても先行民族を限りなく陵駕している、現在のヨーロッパ人にいたるまで上昇することができるのである。」(P.172)
(クックの赤裸々な話)「したがって彼は、彼らに、人間は他の動物とは本性(ほんせい)を異にするということをわからせることができなかったこと。」(P.173)__日本人にはまだ分からない。人食いの恐怖は自己喪失の恐怖
「パリに到着した「アヴェロンの野生児」は、シカール神父の手に委ねられた。この神父は、生理学よりも神学に学殖が深く、物理学の原理よりも自分の宗教原理の方をずっと信頼し、人間はいかなる教育の助けも必要とせずに神の存在を認識する高みに到る、という強固な信念をもっていた。(FF)シカール神父は、「アヴェロンの野生児」の観察にはぜんぜん取り組もうとせず、彼を自分の神学=生理学的思想の正しさを公に立証する手段として利用するのに汲汲(きゅうきゅう)としていた。神父は真理に真っ向から挑戦したわけで、当然のことながら、〔すこぶる〕旗色が悪かった。」(P.175-176)
訳者あとがき
一九七八年九月 中野善達


