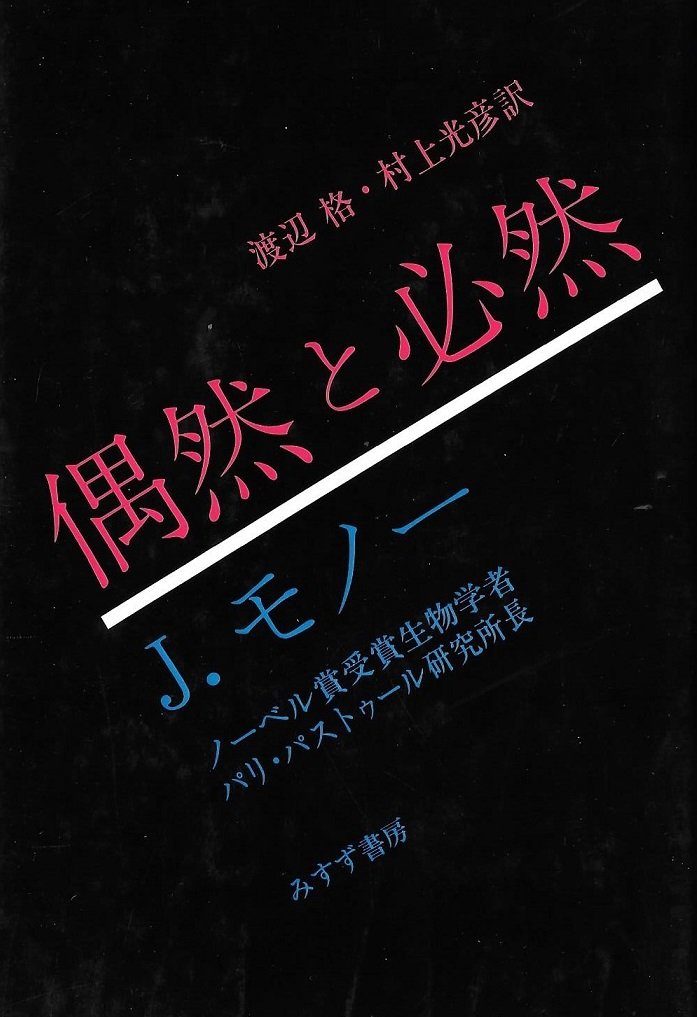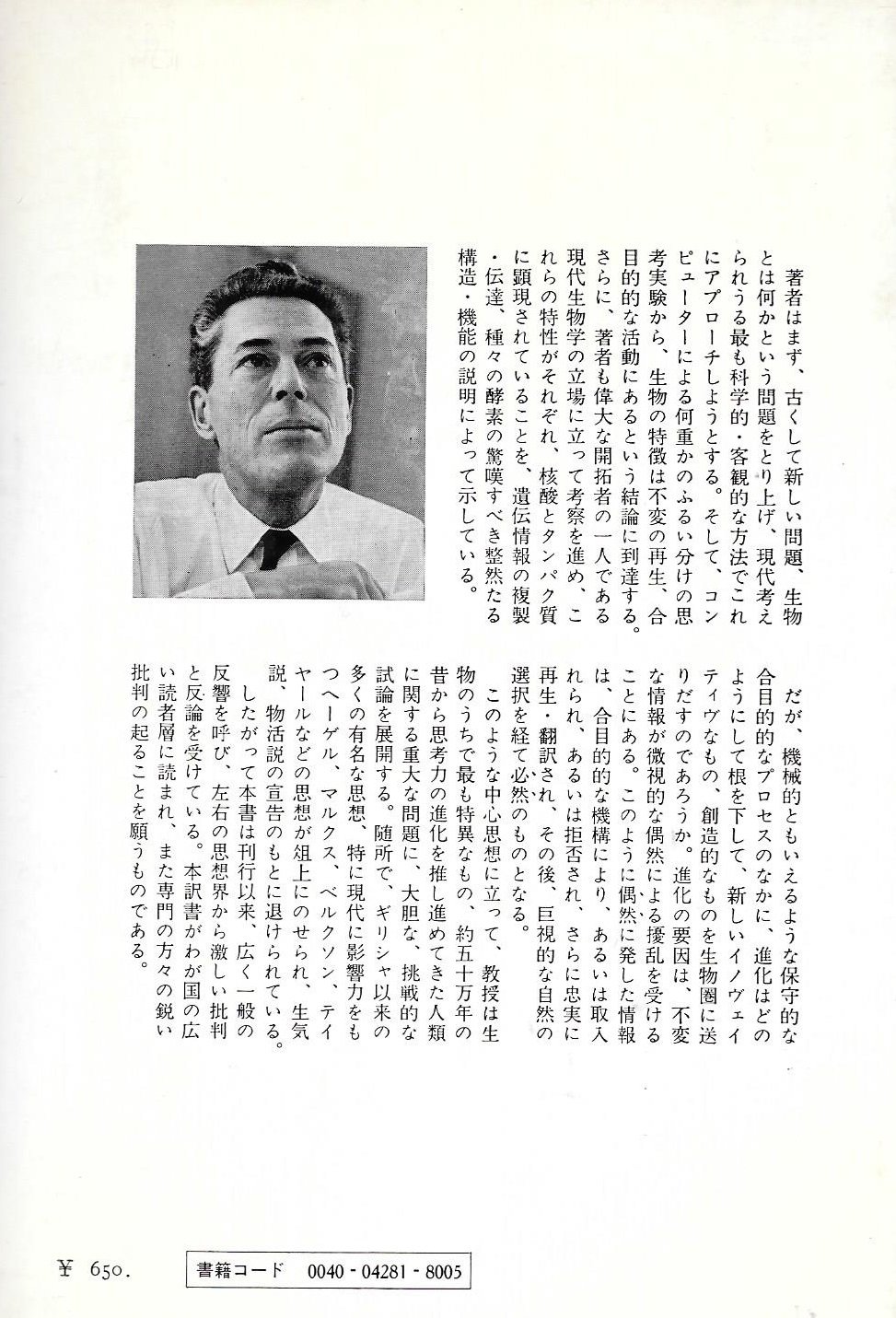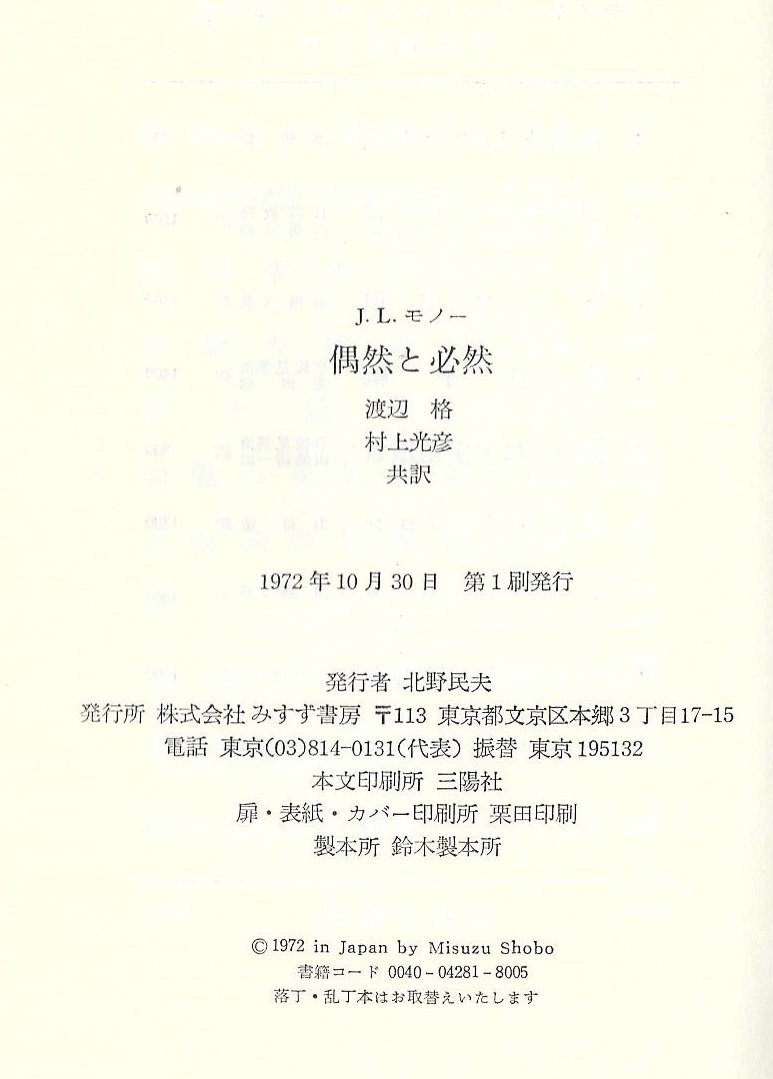〈書抜〉
序
「だが、私が信じているように、あらゆる科学の究極の野心がまさに人間の宇宙に対する関係を解くことにあるとすれば、生物学に中心的な位置を認めなければならなくなる。というのは、あらゆる学問のうちで生物学こそ、《人間の本性》とは何かという問題が形而上学のことばを使わないでも言えるようになるまえに、当然解決されていなければならないような問題の核心に、最も直接的に迫ろうとするからである。」(P.ⅲ)__人間から見ているうちは何も見えない。それで満足するのか。
(P.ⅳ)__人間から自然を見るのを止めたとき、すべてが明らかになる。疑問はなかったと。
Ⅰ 不思議な存在
「したがって、われわれがなんらかの物体について《自然の》ものであるか、それとも《人工の》ものであるかを判断するのは、われわれ自身が意識し、意図をもって行う活動を参考としたうえでのことであり、われわれ自身が工芸品(人工物)の製造者だからである。」(P.2)
「言いかえると、結晶とは微視的構造が巨視的に表現されたものなのである。」(P.5)
「すなわち、ある人工物(それが蜜蜂の蜜カであれ、海狸が築いた堰であれ、旧石器時代人の斧であれ、あるいは宇宙船であれ)の巨視的構造は、その物体そのものの外部からの諸力が、それを構成している物体に加わった結果としてつくられたという事実である。巨視的構造は、ひとたびそれが仕上がってしまうと、もはや物体を構成している原子ないしは分子(それらはその構造にたいして、材料の有する密度・硬さ・可延性などの一般的性質を付与しているにすぎない)のあいだの内的凝集力を表すだけではなくて、それをつくりあげた外的な諸力を示すことになるのである。(LF)自分自身をつくりあげる機械 これにひきかえ、生物の構造は、全然ちがった過程の結果として生じていることを、そのプログラムは記録することになる。ちがっている点というのは、生物が外部の諸力の作用にはほとんどなにひとつ負うておらず、全体的な形からごく微細な部分にいたるまで、すべてそのものに内在する《形態発生上の》相互作用に負っている、という事実である。」(P.10)
「ここで問題になるのは高次の秩序をもった構造を複製する能力であるし、その上、構造の秩序の程度は情報の単位で定義することができるから、われわれはつぎのように言える。ーーある任意の生物種がもつ《不変の内容》というのは、世代から世代へと伝達され、その種にとって特異的な標準となる構造をきめる情報の量に等しい、と。」(P.14)
「ここで問題となるのは、本来の意味での複製と直接に結びついた活動ばかりではなく、種の生存および増殖に対してーーたとえ間接的にでもーー寄与するすべての活動でもある、という事実を強調しておかなくてはならない。」(P.15)
Ⅱ 生気説と物活説
「今日までのところ淘汰理論は、提出されたすべての理論のうち、客観性の原理と両立しうる唯一のものである。それは、普遍性を唯一の根本的特質と見なし、合目的性を普遍性から派生する第二次的特性だとしている。」(P.16)__結果的に、客観性を偶然に委ねている。不変性と客観性そのものから変化は導けない。
「科学的方法は、〈自然〉は客観性をもっているという当然の仮定の上に置かれている。つまり、ある現象を最終原因(コーズ・フィナール)すなわち《目的》の面から解釈することで《真実の》認識に到達できるという考えを、否定しようとする体系なのである。」(P.23)
「それというのも、自然のなかのどこを探そうとも、なんらかの企てなり追求すべき目的なりが存在してはいないということを証明できるような実験は、あきらかに存在することができないからである。」(P.23)
「生物の不思議な性質を説明するために、ほかのいろいろの概念がこれまでにはっきりと提案されたり、あるいは、宗教的イデオロギーや偉大な哲学体系の多くのなかに暗黙のうちに含まれていたり(FF)したが、これらすべての概念は逆の仮説を想定している。すなわち、まず初めに合目的的原理を考え、それによって、不変性が安全に守られ、個体発生が導かれ、進化が方向づけられているというものであり、また、これらすべての現象は原初の合目的的原理の顕在化したものである、という仮説である。この章において、これから、これらの解釈の論理を分析することにする。これらの解釈は、外見は非常に多様であっても、そのすべてが客観性の原則を放棄するーー部分的には全面的にか、認められているか否か、意識しているか否かはともかくーーことを含んでいる。」(P.26-27)
「したがって一方では、生物圏、つまり《生命をもった物質》、の中で明らかに働くと考えられる合目的性の原理を認めるという、一群の理論を定義することができる。私がこれから生気説と呼ぶこれらの理論は、生物と無生物のあいだに根本的な区別をおくものである。(LF)他方、普遍的合理目的的原理にもとづく一群の考え方があって、それによると、この原理は生物圏の進化ばかりか宇宙の進化を支配しており、生物圏の内部ではたんにより精密かつ強烈な仕方で現れているにすぎない、と考えているのである。これらの理論は生物のなかに、普遍的に方向づけられた進化から生じた、もっとも洗練され、もっとも完璧な産物を見ているのである。これらの理論は生物のなかに、普遍的に方向づけられた進化から生じた、もっとも洗練され、もっとも完璧な産物を見ているのである。そして、その進化の(FF)到達点が人間および人類であり、そこまで到達したのはそうなるべき定めにあったからである。これらの見方ーー私はこれを《物活説(アニミスト)》と呼ぶことにするーーは多くの点で生気説よりも興味深い。」(P.27-28)
「他のほとんどすべての生気説や物活説とは反対に、ベルグソンの生気説は最終目標を含んではいない。それは生命の本質的な自発性を、どのような決定論のなかにも閉じ込めることを拒否する。生命の躍動それ自体と同一視される進化は、したがって何ら目的因も作用因も持つことができない。人間は進化が到達した最高の段階のものではあるが、進化はそこまで来ようと、努めてきたわけでも予定していたわけでもない。それはむしろ、創造的躍動の完全な自由さの現れであり、そしてその証拠なのである。(LF)この考えかたに、ベルクソンが根本的なものとみなしていたもう一つの考えかたが結びついている。すなわち、合理的知性は、非生命物質を支配するのには非常に適した認識手段ではあるが、生命現象を把握することはまったくできないという考えかたである。ただ本能のみが、生命の躍動と同質的なものとして、生命現象にかんする直接かつ全体的な直観を与えることができる。」(P.29)
「私はこの哲学を論駁しようとは思わない(もともとこの哲学は論駁するにふさわしいものではな(FF)い)。私は、論理のなかに閉じこもった人間で、全体的直観が貧弱なので、そうする能力がないと思っている。だからといって、私はベルグソンの態度を無意味だとみなしているわけではない。それどころではない。合理性に対して反逆(自覚したものであるか否かを問わず)し、〈エゴ〉〔自我〕を犠牲にして〈イド〉〔本能的自己保存衝動〕に尊敬を払うのが、現代のしるしなのである(創造的自発性のことは言うまでもない)。もしベルクソンがもっと不明瞭な言語と、もっと《深遠な》文体とを用いていたとしたら、彼は今日でも読み返されることだろうに。」(P.29-30)
「生気論者たちは、物理学の法則だけでは胚発生を説明しきれないとか、いずれにせよ、説明しきれないことがそのうちに判明するだろうとか考えているが、彼らの態度は明確な知識や注意の行き届いた観察者によって正当化されているわけではなく、たんにわれわれの現在の無知によって正当化されているにすぎない。」(P.32)__無知によって不正ということもできない。科学的に「知らない」ということが「知ることができる」ことを証明するわけではない。思う《信じる》かどうかの違い。「ない」という証明はできない。
「(私がここで定義するつもりでいるような)物活説の本質的な思考法は、人間が自分自身の中枢神経系の強烈なまでに合目的的な働きについて抱いている意識を無生物の自然のなかに投影することである。言いかえれば、自然現象は究極的には、人間の主観的・意識的で目的を持った活動と同様な仕(FF)方、同じ《法則》によって説明できるし、また説明されねばならないという仮説なのである。」(P.34-35)
「そして、思考が弁証法的に進行するからには、まさしく《弁証法の法則》が自然全体を律するのである。しかし、これらの主観的《法則》をあるがままに保存して、これらを純粋に物質的な宇宙の法則に仕立てようとするのは、物活説的意図をこのうえなく明白な仕方でおこなうことであり、そうすることは、客観性の原理の放棄を始めとして、あらゆる結果をともなうこととなる。」(P.39)
「たしかに、以上の再構成に異議を申し立てたり、それがマルクスおよびエンゲルスのほんものの思想に対応していないと主張することもできよう。しかし、そのようなことは結局において第二義的である。あるイデオロギーの影響は、その信奉者の精神のうちにそれが引き継がれている意義や、亜流がそれに付与する意義によっているのである。」(P.41)
「なおまた、弁証法的唯物論は、マルクスがすでに築き上げた社会経済的な大建築物に、比較的のちになってつけ加えられたものだということを忘れてはならない。これをつけ加えた目的は、あきらかに史的唯物論を自然そのものの法則にもとづいた《科学》にすることであった。」(P.42)__主体ぬきに主体が語れるか。
「周知のとおり、第二期の科学すなわち二十世紀の科学は、認識の源泉へ、その源泉そのものへ復帰することによって、まず準備された。批判的認識論が認識の客観性の条件そのものとして絶対に必要であることが、はやくも十九世紀末期にはふたたび明白になった。それ以後ずっと、この批判に従事するのは哲学者ばかりとは限らず、科学者もまた、これを理論の緯(よこいと)そのもののなかに組み込まざるをえなくなるのである。まさにこのようにして、はじめて、相対性原理および量子力学が発達できたのである。」(P.43)
「他方、神経生理学及び実験心理学の進歩によって、現在、神経系の働きのすくなくともいくつかの側面がだんだんわかり始めてきている。それらのことだけでも、中枢神経系が意識に与えることができる情報は、前もって定められた規範の中で暗号化され、転換され、適合されたものだけである(たぶんそれ以外にはありえない)ということが明らかになった。換言すれば、同化されたものであって、単に再現されたものではないということである。」(P.44)
「これらの誤謬の源泉には、もちろん人間中心主義の幻想がある。太陽中心説〔地動説〕、慣性の概念、客観性の原理などだけでは、この古くからの蜃気楼を吹き払うことができなかったのである。」(P.47)
「しかしながら、われわれが知っているように、(ラプラースや、彼のあ(FF)とを受けた十九世紀の科学および《唯物論》哲学が信じていたこととは反対に)、これらの予想は統計学的なものでしかありえないのである。」(P.49-50)
「一般的にいって、この理論は類別された物体なり出来事なりの存在や性質、あるいは相互作用を予見できても、個別の物体なり出来事の存在とか、それらの特別な性質とかを予見することはできないのである。」(P.50)
「私の言うことをよく理解していただきたい。生物として類別された存在は第一原理からは予見されない、と言うにあたって、私は決して、それらが、これらの原理によっては説明がつかないとか、それがなんらかの仕方で第一原理を超越しているとか、生物にしか適用できない、他の諸原理の助け(FF)が必要だとかいうことを、示唆するつもりはないのである。」(P.50-51)
「現実の、他と比較できない唯一の実在である、いまここにあるこの物体が理論と両立しうると言うだけで十分なのである。理論によれば、その物体は存在する義務を有していないが、存在する権利ならば有している。」(P.51)__名言。
Ⅲ マクスウェルの魔物(デモン)
「これらの合目的的性能は、突きつめれば、すべてタンパク質の持つ《立体的特異性》にもとづくのである。それは、タンパク質が、他の分子(他(FF)のタンパク質をも含めて)をそれぞれの形ーーその形はそれぞれの分子構造によって決定されているーーで《認知》する能力なのである。これは文字どおり、微視的な識別(《認識》とは言わないししても)能力なのである。」(P.53-4)__だれにとっての「目的」か。人間にとって以外にない。つまり科学者「自身」、考える人「自身」にとって。だれが「認知」するのか。人であり個人である。認知、あるいは科学に隠れているのは「人間」であり、「人間」に隠れているのは自分である。
Ⅳ 微視的サイバネティクス
(P.77)__主客は「擬人化」に簡単に結びつく
「自動電子回路に用いられているシステムと比較できる」(P.78)__主語はWe?エネルギー?同じ構造だけど。意図せず主語(形式主語を含む)をつけること自体が主客構造であり、擬人化である。「海は呼ぶ」「春はあけぼの」。AがBの原因となり、Aが運動の主体(意図)をもつ。主客構造に人間中心主義。能動、受動
「(・・・)化学的に必然的な関係はなにもない。この関係は、生理学的には有用であり《合理的》であるが、化学的には恣意的である。われわれはこの関係を《無根拠の》と形容することにしよう。」(P.89)
「このアロステリック相互作用の作動原理によって、そんな制御システムも可能だという意味で、制御にかんする《選択》には完全な自由が許されていることになる。このような制御系は、いっさいの化学的拘束を免れているので、それだけいっそう生理学的要求に従うことができるわけであり、その結果として、それが細胞あるいは生物に与えることのできる今までより以上の首尾一貫性や能率の良さの程度によって淘汰されることになる。このような系の無根拠性そのものが、分子進化の探求と実験にほとんど無限の分野を開いているのである。そして究極的には、分子進化はこの無根拠性のおかげで、莫大なサイバネティクス的相互連絡のネットワークを作りあげていゆくことができたのである。そして、この相互連絡のネットワークによって、すべての生物は自律的な機能単位となり、その働きは科学の法則から免れるとは言わないとしても、それを超越するようなことになったのである。」(P.90)__アロステリック「アロステリック効果(アロステリックこうか)または協同効果(きょうどうこうか)とは、タンパク質の機能が他の化合物(制御物質、エフェクター)によって調節されることを言う。主に酵素反応に関して用いられる用語であるが、近年、Gタンパク質共役受容体 (GPCR) を中心とする受容体タンパク質の活性化制御において、アロステリック効果を示す化学物質 (アロステリックモジュレーター、アロステリック調節因子) の存在が知られるようになってきた。 」Wikki。化学的な説明、たとえば「血液中のヘモグロビンは酸素と結合する鉄中心を持つヘムを四つ持ち、各々の酸素との結合には一定の平衡定数が存在する。しかし、ヘモグロビン中の一つのヘムが酸素と結合を作るとヘモグロビン全体の構造が変化し、他のヘムと酸素との結合が促進される。すなわち、酸素濃度の高い所では単独のヘムよりも効率的に酸素を取り入れることができる。一方で、細胞中のミオグロビンのそれぞれのヘムにはヘモグロビンのような協同効果は無いので、酸素との結合生成反応は酸素濃度に一次で比例するだけである。この結果、ヘモグロビンは酸素の多い肺では酸素を吸収し、酸素の少ない各細胞では酸素を放出することができるのである。」(Wiki)は、「なるほど」と思える見事な化学的成果であるが、「どのようにして」の説明でしかない。それを「なぜそうなっているのか」と問うと「目的」を設定せざるをえない。だから、「結果としてそうなった」、つまり、「原因はない」と言わざるをえない。
《全体論者、還元論者、有機論者》(P.91-)
Ⅴ 分子個体発生
「ある構造が後成的に組み立てられるということは、創造ではなく開示なのである。」(P.101)
(P.104-105)__「進化」という考えそのものが進化(変化)がある目的(意図)を持っているという考えである。科学は目に見えない、理論が先行し、それを見えるように(文字化)する。文字化することによって、実在を与える。しかし、美・前・快「そのもの」を写真や絵にすることはできない。
「しかしながらーーこれが重要な点であるがーーあるタンパク質の三次元的構造全体を規定するのに必要だと思われる情報量は、(FF)配列順序そのもののもつ情報量よりもはるかに大きい。」(P.108-109)
Ⅵ 不変性と擾乱
擾乱(じょうらん)
「これらのイデオロギー的構築物は、先験的(ア・プリオリ)なものとして提示されてはきたが、じっさいには、まえもって抱懐していた倫理=政治理論を正当化するためにつくられた後天的(ア・ポステリオリ)な構造物なのであった。(FF)(LF)科学にとって唯一の先験的なものは客観性の公準であって、科学はこの公準によって、このような論争に参加しないですますことができるし、あるいはむしろそれを禁止されているのである。」(P.115-116)
「むしろそれとは反対で、いろいろの現象を分析するばあいの科学の根本的な戦略は、まず不変なるものをさがすことなのである。すべての物理的法則はーーすべての数学的展開も同様であるがーー普遍的な関係を明確に述べたものである。科学のもっとも基本的な命題は、普遍的な保存という公準である。どんな例を選ぼうとも、そこで保存されている何か不変なものによって表されないかぎり、ある現象を分析することは、じっさいには不可能なのである。そのもっともはっきりした例は、動力学法則の数式化であろう。というのはそれは、不変なものの言葉で変化を定義している微分方程式を発明することを必要としたのである。(LF)たしかに、つぎのような疑問もでてくるであろう。すなわち、化学的論述を織り上げている緯(よこいと)とでもいうべき不変性、保存、対称性などというのは、すべて実在についてのオペレーショナルなイメ(FF)ージを与えるために、実体と置きかえられた虚構ではないと果たしていえるであろうか、と。このオペレーショナルなイメージによると、実体そのものは、部分的に失われてしまうが、純粋に抽象的な、おそらくは単に《約束事》同一性の原理にもとづく論理を受け入れることができるということではなかろうか。ともかく人間の理性はこのような約束事なしにはやっていけないらしいのである。(LF)私がここでこのような古典的問題に言及したのは、その立場が量子革命によって深刻な変化をうけたことに注意したいからである。同一性の原理は、古典的科学においては物理学の公準としてはかぞえられていない。この原理は、古典的科学では単に論理的操作として使われているにすぎず、それがなにか実質的な実在に対応するものだと考える必要はなかった。現代物理学にあっては、事情はまったく異なっている。現代物理学のもっとも基本的な公準のひとつは、同一の量子的状態にある二つの原子は絶対に同一だということになる。同様にして、量子論においては、原子及び分子の対称性は、それが完全であるかどうかではなく、むしろ絶対的な表現とみなされているのである。したがって、今日では、もはや同一性の原則をたんなる精神指導上の規則という立場に極限することはできないように思われる。」(P.116-117)__変化(運動)を不変(数式)で表す。それによって、運動が「実在」していて、それを捉えたと思いこむ。運動の実在が前提にあるのではなく、固定化(数式)が運動を「実在化」する。それ以上分解することのできないものにたどり着けば、そこには実体ではなく論理しかない、ということを言い換えたにすぎないのではないだろうか。古典ギリシャにおいて、アトムが一種類、あるいは数種類の同一なものとされたように。
「ともあれ、科学のなかにはプラトン哲学的な要素があり、それはのちのちまで残るであろう。これを科学からとりのぞこうとすれば、科学そのものを破滅させることになるであろう。科学は、個々の現象の示す無限の多様性のなかから、不変なるものを探し求めることしかできないのである。」(P.118)
(翻訳の非可逆性)「結局のところ、タンパク質の構造と働きが変更をうけたり、またこのような変更がたとえ部分的にもせよ子孫に伝達されるような機構は不可能だということになる。」(P.128)
「したがって、生物というシステムは全面的に極度に保守的かつ自己閉鎖的であり、また外界からの(FF)いかなる教えも絶対に受けつけないシステムであるということになる。このシステムはその特性から言っても、その微視的な時計仕掛けのような働きーーそれはDNAとタンパク質のあいだにも、また生物と環境とのあいだにも一方通行的な関係を打ち立てているがーーから言っても、いっさいの《弁証法的》記述に抵抗し、それに挑戦しているといってよい。それは根底からデカルト的であって、ヘーゲル的ではない。細胞はまさしく機械なのである。」(P.128-129)
「しかしながら、物理学がわれわれに教えるところによれば、(到達できない限界温度である絶対零度以外では)いかなる微視的存在も量子的な乱れをこうむらずにはすまされないのであり、これが巨(FF)視的な系の中で蓄積すると、徐々にではあるが間違いなく構造の変化をきたすことになるのである。(LF)生物は、正確な翻訳を保証している完璧な保存機構をもっているにもかかわらず、やはりこの法則から免れることはできない。多細胞生物の老化と死は、すくなくとも部分的には、翻訳の偶発的な間違いの蓄積ということで説明できる。」(P.129-130)__老化を量子力学で説明?
「その結果、突然変異が次のような原因に帰せられることがわかったきた。(LF)1 ひとつのヌクレオチドの対(ペア)が他の対に置換される。(LF)2 ひとつあるいはいくつかのヌクレオチド対が欠損するか、あるいは付加される。(LF)3 まちまちな長さのDNAが倒置されたり、繰り返されたり、転置されたり、融合されたりして、遺伝暗号のテキストがいろいろなぐあいに《かきまぜられる》。(LF)この変化は偶発的なものであり、無方向的なものである。そして、その変化が遺伝のテキストの変化を起こしうる唯一の原因であり、このテキストが生物の遺伝的構造の唯一の貯蔵物なのであるから、その結果必然的に生物圏におけるすべての新奇なもの、すべての創造の源はただ単なる偶然だけにあるということになる。」(P.131)
「これは観察され実験された諸事実と両立しうる唯一の、しかも考えられる唯一の仮説(FF)なのである。」(P.131-132)
「またこの概念は、あらゆる科学分野のあらゆる概念のうちで、もっとも根本的に人間中心主義を破壊するものであり、合目的性を強く信じてきたわれわれ人間という存在にとっては、本能的にもっとも受け容れがたいものなのである。」(P.132)__それを自分や他人に強要することの違和感。SNSで賛成な人も反対の人もそれを堂々と主張できないから会社や労働組合
(操作上の不確実性と本質的な不確実性)「しかし、このような純粋に機械的かつ巨視的な遊びが《偶然》であるのは、十分な正確さでサイコロを投げたり小さい球をまわしたりすることが事実上不可能であるからにすぎない。」(P.132)
「進化というのは、それがまさしく本質的な予見不能性から起こってきたという事実によって、絶対的な新しさの創造なのである。」(P.135)
「現代の生物理論にとっては、進化はなんら生物の特性ではない。なんとなれば、進化は、生物の唯一の特権である保存機構の不完全さそのものに根ざしているからである。」(P.136)
Ⅶ 進化
「すなわち、単純な《生存競争》の観念である。ついでながら、これはダーウィンではなくてスペンサーが言い出した表現である。それとは反対に、今世紀初頭のネオ=ダーウィン主義者たちは、淘汰についてはるかに豊かな概念を提出し、定量的理論にもとづいて、淘汰の決定因子は《生存競争》ではなくて、種の内部における増殖率の差である、ということを示した。」(P.138)
「したがって、受けいれられる突然変異というのは、合目的的装置の首尾一貫性を低下させたはならないだけではなく、むしろすでに起こっている変化の方向に即してさらにいっそう強化するか、あるいはまたーーそれよりずっと稀なことであるがーーあらたな可能性を開くといったぐあいの突然変異でなければならない。」(P.139)
「注意しておかなければならないのは、その個体だけでは見つけることができないが、性的組み換えによって著しい影響を現すような突然変異は、この数字には含まれていないことである。個々に著しい影響を与える突然変異よりも、このような突然変異のほうが、進化においてより重要な役割を果たしてきたのではないかということも充分考えられる。(FF)(LF)それらを合わせて、現在の約三十億の人類は、各世代ごとに千億ないし一兆の突然変異を生じている。私がこの数字を挙げたのは、ある生物の遺伝情報が偶然に変化する可能性がいかに莫大なものであるかについて、ある目安をつけてもらうためである。複製機構はきわめて厳格に自己保存を一生懸命に行っているにもかかわらず、そういう次第なのである。」(P.140-141)__性による組み換えは、突然変異ではない。
「要するにこの首尾一貫性が、進化において案内役とブレーキの役割を同時に演じてきたのであり、またそれによって自然のルーレットの与えてくれた天文学的数字に達する莫大な機会のなかの、ごくわずかなものだけが受けとめられ、拡大され、組み入れられてきたのである。(LF)複製のシステムは、微視的擾乱によって不可避的に乱されずにはおられないのであり、それはこれらの擾乱を排除できるどころか、逆にそれを記録して、淘汰ということでその働きを判定する合目的的濾過装置にそれをかけるわけだが、その大部分は無駄に終わってしまうのである。」(P.142)__微視的という量子力学的ということであれば、それは「決定できない」ということではないか。猿と人間の遺伝子を比較すれば、その変化の確率を計算することができるかもしれない。しかし、それが0.5であろうと、100億分の一であろうと「でも、それは起こったのだ」で終わらせることができる。
「しかし、二つの種ーーたとえ、きわめて縁が近も(FF)のであろうとーーに分化するといった、著しい進化はすべて、非常に多くのたがいに無関係な突然変異があいついで本来の種のなかで蓄積され、ついでそれらが、性行為によって促進された《遺伝子の流れ》のおかげで、偶然いっしょになった結果なのである。このような現象は、それを生みだすたがいに無関係な出来事の数が非常に多いために、統計的に不可逆的であるということになる。(LF)したがって、生物圏における進化は時間的に方向性をもった必然的に不可逆な過程である。この方向性は、エントロピーの増大法則、すなわち熱力学第二法則の命ずる方向と同一である。これは、たんなる類似をはるかに越えたものである。第二法則は統計学的考察に基づいているが、これは進化の不可逆性を示す考察と同一のものである。じっさい、進化の不可逆性を、生物圏における熱力学第二法則のひとつの表現とみなすことはきわめて正当なことである。第二法則は統計学的予言を述べているにすぎないので、いかなる巨視的大系に対しても、非常にわずかな距離をきわめて短時間だけ動くばあいには、エントロピーの坂を逆にのぼること、いわば時間を逆にさかのぼるようなことを禁止することにはならない。生物にあっては、まさにこのエントロピーの坂を逆にのぼるような運動が、複製機構によってつかまえられ、複製されたすえに、淘汰によってふるいわけられるのである。微視的偶然という膨大な貯蔵庫のなかの、無限にどうでもよい出来事にまじって、貴重な価値のある出来事がごく少し存在しており、それを選び出すことで淘汰的進化がおこるのであり、その意味では進化は一種の時間遡及機械(タイムマシン)だといえる。」(P.142-143)__偶然は可逆的。エントロピーの増大法則からいえば、秩序から乱雑。差から均一。「貴重」「価値」という人間の主観は自然(偶然)にはない。福岡伸一の「さかのぼり」。偶然と不可逆性。正当化進化論のエッセンス。
「しかし、《あらゆる方向》に対する防衛手段を生物に与えられるほど豊かな源は、いま述べた偶然というようなもの以外になにもありえないだろうということは、(経験的(ア・ポステリオリ)に)明瞭である。」(P.145)__いちばん大切なところは「経験的」?
「淘汰説が受け入れられにくいもうひとつの点は、これまでこの説が淘汰の要因として外的環境という条件のみを考えているように理解されたり紹介されたりしてきたことがあまりにも多すぎた、ということである。」(P.146)__日本人が考える「自然環境」という意味か。Natureではないと思う。
「生物が受ける淘汰の圧力の性質と方向を決定している少なくともひとつのことは、生物が《選択する》この特異的相互作用なのである。新しい突然変異が直面する淘汰の《初期条件》の中には、外的環境と、合目的的装置の構造・性能全体が、分離できない形で同時に含まれているといってよい。」(p.146)
「しかし、行動の諸要因に純粋な淘汰が働くことによって、ラマルクが説明したいと思っていたのと同じ結果に到達できることがわかる。つまり、解剖学的適応と特異的な働きとは緊密に結びついているという結果になるのである。」(P.148)__結果論。過程は明らかではない。
「脳の重量は、たしかにその性能とは比例してはいない。しかし、その重量はその性能にある制限を課すものだということは確かである。ホモ・サピエンスが現れることができたのは、その頭蓋の発達のおかげだということも、なんら疑う余地はないのである。」(P.152)__思い込み。人類至上主義。石を落とす鳥も同じ。それは人間には難しい。蜜蜂・蜘蛛。合目的=意識的。でも人間の行動の殆どは無意識的。意識は事後的・結論的といってもいい。象徴化できるか=言語の持つ一般・抽象性。区別が難しい。後天的なものもすべて遺伝子が支配している。動物に言語を教えること。すべての動物に少なからずある先天的と後天的。基準がなければ道具を作ったり選んだりはできない。
「象徴的伝達体系ができあがるやいなや、この体系を使用する才能にもっとも恵まれた個体、あるいはむしろ集団が、他の個体ないしは集団に対して優位を占めることとなった。」(P.154)__個体が言語を作る(使う)ということはありえない。
「幼児はなにひとつ規則を覚えようとしないし、いっこう大人の言語をまねしようとはしない。幼児は、自分のそれぞれの発達段階で、それに適したものを取り込んでいるのだと、言うこともできよう。ごく初期の段階(十八ヵ月ごろ)には、幼児は約一〇語ほどの単語のストックを持つことがあるが、たとえ人真似であろうと、それらを組合せて用いることはけっしてない。」(P.155)__子育てをしていたら、「適した」なんて言えないだろうなあ。
「言語を認識機能と結びつけることを可能としているのは、まさに、この後成的過程の途中で行われる言語の習得であろう。しかも、この結びつきは非常に体質的なものであるので、言語の働きと、それによって明確にされる知識とを、われわれの内容によって切り離すことは非常に困難である。」(P.157)
「しかしながら、ホモ・サピエンスにおいて認識機能がせっかく充実し、また洗練されたとしても、それらの認識機能が存在理由を見いだすのは、言語のうちにすぎず、また言語をつうじてでしかないことは、明らかなことである。この手段を奪われてしまえば、認識能力の大部分は役立たなくなり麻痺したものとなる。この意味から、言語能力はもはや上部構造とのみみなすことはできなくなる。現(FF)代人においては、むしろ認識機能と象徴的言語ーー認識能力によって必要とされ、また認識能力そのものを解明するための象徴的言語ーーとのあいだには、長期にわたる共通の進化の所産としか考えられない、緊密な共生関係があることを認めないわけにはいかない。」(P.157-158)__「明らか」とは言えないが、「言語」は日本語の「ことば」ではない。西欧の「ことば中心主義」は「文字中心主義」である。
「すなわち、話し言葉は、それが人類の系統のなかに出現したとき、たんに文化の進化を可能にしたばかりではなくて、人間の肉体的進化にも決定的な仕方で寄与したということである。」(P.158)
Ⅷ 未開拓の領域
(生命の出現)「このような決定的な出来事は一度しか生じなかったという仮説の可能性は現在の生物圏の構造から見てとうてい排除することはできない。そのことは、生命の出現する先験的な確率はほとんどゼロであったということを意味している。」(P.168)
「現代科学はいっさいの内在性を無視する。運命はそれがつくられるにつれて書き記されるのであって、事前に書き記されているのではない。生物圏において象徴的伝達という論理的体系を使用できる唯一の種である人類が出現する以前にはわれわれの宿命は書き記されてはいなかったのである。人類の出現というのも、もうひとつの唯一無二の出来事だったのであるから、それによって、われわれがいっさいの人間中心主義に陥らぬようにしなくてはならないはずである。」(P.169)
「動物の意識された経験にはわれわれは入りこむことはできず、おそらくいつまでもそうであろう。たとえば、カエルの意識内容に近づくことができないままで、カエルの脳の働きを記述し尽くすことが原理的に可能であろうか。」(P.170)
「すでに述べたように形態発生学において、遠隔的な相互作用がどのようにして実現しているのかという謎がある。」(P.171)
「たとえば、カエルの目の後ろには分析器が(FF)備えられていて、カエルはこれによって、動いているハエ(すなわち一個の点)を見ることができるが、静止しているハエを見ることはできない。そんなわけで、カエルは飛んでいるハエしか捕らえないことになる。」(P.175-176)
「今日なお、一部の動物行動学者は、動物の行動の諸要素は、先天的なものかそれとも学習したものかのどちらかで、この二つは互い(FF)に他方を排除しているという考えを固執している。この考え方がいかに間違ったものであるかは、ローレンツが強く論証している。経験によって習得された要素が行動の中に見られるばあいでも、それはあるプログラムに即して習得されたのであり、このプログラムは、先天的、すなわち、遺伝的に決定されたものである。プログラムの構造が学習ということをひき起こし、それを導くのである。そこでこの学習ということも、種の遺伝的遺産として前もってつくられた《形》の中に書き込まれているのである。」(P.178)
「それは残酷な実験であって、人間に(実際問題としては幼児であるが)そういう実験を行うことは考えられないほどのものである。そんなわけで、人間は自己を尊重しなければならなかったので、自己の存在を構成する構造のうちのあるものを探索することを、自分自身に対して禁じないわけにはいかないのである。」(P.178)__動物ならいいのでしょうか。
「それは認識機能のもっとも奥深いレベルーー言語の基礎をつくっているレベルであるが、それはおそらく言語をもってしては部分的にしか表明できないーーで行われているのである。しかしながら、この機能はただ人間だけにあるとは言えない。」(P.180)
「ところが人間のばあいは、主観的シュミレーションは、なみすぐれた高度な昨日、つまり創造機能にまでなってしまう。言語の象徴性に反映されているのは、まさにこの機能である。言語は、創造機能の働きを置き換えたり、要約したりすることによって、それをはっきりさせる。かくして、チョムスキーが強調しているように、言語というのはごくつまらなく使ったばあいでも、ほとんどいつも革新をもたらしているのだという事実がでてくる。というのも、言語は主観的な経験、すなわちつねに新しい独自のシュミュレーションを、翻訳するものだからである。」「もっとも賢い動物は、おそらくかなり明確な主観的シミュレーションを行う能力はもっているであろうが、《みずからの意識を開放する》手段はやはりなにひとつ持ちあわせていない。」(P.181)
「しかしシミュレートされた経験の意味がはっきりしてくるのは、そのときではなくて、それが象徴的に表現されてからのことである。じっさい、シミュレートするときに使った非視覚的映像は、象徴とみなすべきではなく、むしろこう言ってよければ、架空の経験によって直接与えられた主観的かつ抽象的な《現実》とみなすべきであると私は思う。」(P.182)__ここまで言うと、唯心論に近い。
「いったい、だれが精神の存在を疑うことができるのであろうか。魂のうちに非物質的な《実体》を認めるという幻想を断念することは、魂の実在を否定することではなくて、むしろ反対に、遺伝的・文化的遺産と、意識的・無意識的にかかわらず個人的経験のもっている複雑さ・豊かさ・測りようのない深さを認め始めることなのである。」(P.186)
Ⅸ 王国と奈落
「〈人間〉は、この進化によって、人間より下の世界に対する支配範囲を広げてゆき、その世界が自分らに隠し持っている種々の危険からだんだんとのがれられるようになっていった。かつて進化の最初の段階を導いた淘汰の圧力は、その段階が終わったときに弱められてしまった。少なくともそれは別の性格を帯びることになった。こうなると〈人間〉はみずからの環境を支配できる立場に立つことになり、自分の仲間以外にはこわい敵はもういなくなった。直接的な人類内部の闘争、相手を殺す闘争が、それ以後人類における淘汰の主要な要因の一つとなった。」(P.188)__「弱肉強食」とは違うのだろうか。火星に移住しようとし、宇宙まで支配しようとする西欧人は野蛮だ!!
「ネアンデルタール人が突如消滅したのは、われわれの先祖であるホモ・サピエンスが犯した集団殺戮の結果であるということも大いに可能性がある。それは最後の集団殺戮とは言えない定めにあった。その後の歴史上にもかなり多くの集団殺戮が知られている。(LF)この淘汰の圧力は、人間の進化をどのような方向に押し進めることになったのであろうか。当然それは、知能・想像力・意志・野心などに恵まれた人種の勢力拡張に好適な作用を及ぼした。しかし、それはまだ、個々の人間の勇気よりは団結力や群れの攻撃性のために、さらに自発的よりは部族の掟の尊重のために好適であったにちがいない。」(P.189)__記載された歴史。文字を持つ文化の残酷さ。著者は殺戮の合理性・必然性をどう考えるのだろうか。「人のものを盗んではいけない」は資本主義社会における《掟》ではないのか。
「他のすべての動物のばあいにもまして、人間のばあいにはーーまさしく人間の限りなく高度の自律性のゆえにーー行動こそ淘汰の圧力を方向づけているといえる。そして、行動が主として自動的だった段階を過ぎて文化的なものになってきてからは、文化的特徴そのものが遺伝情報の進化にたいして圧力を及ぼすことになったのである。(LF)もっとも、それはある時期までのことで、その後は文化的進化の速度が速かったために、それと遺伝情報の進化とは完全に分離されてしまった。」(P.190)
(現代社会の遺伝的衰退の危険)「そこでは、淘汰は廃絶されている。すくなくとも、この淘汰には、ダーウィン的な意味で《自然な》ところは、もはやなにひとつなくなっている。」
「知能・野心・勇気・想像力は、たしかに現代社会においてもあいかわらず成功の要因である。しかし、これは個人的成功の要因であって、遺伝的成功の要因ではない。」(P.191)
「だれもが知っているとおり、統計によれば、知能指数(あるいは文化水準)と夫婦の間の子どもの平均人数との相関関係はマイナスである。この同じ統計が、一方では、夫婦の知能指数の間にプラスの高い相関関係が存在していることを証明している。これは危険なことであって、これではもっとも高い遺伝的ポテンシャルが選良(エリート)のほうに吸い寄せられ、しかも選良(エリート)は相対的には子孫をつくることを自制する傾向にあるからである。(LF)そればかりではない。まだそれほど以前ではない時代には、比較的《先進的な》社会においてさえも、身体的に言っても、また知的な面から言っても、不適者の排除は自動的で残酷なものであった。大部分の者は思春期の年齢にまで達しなかったのである。今日では、これらの遺伝的障害者の多くが、子孫をつくれる年まで生きられるようになっているのである。これまでは種を衰退ーー自然淘汰がなくなれば衰退は不可避であるーーから守ってきた機構が、知識と社会倫理の発達のおかげで非常に重大な欠陥をもっているばあい以外に、もはやほとんど作用しなくなっている。」(P.191)__知能をIQだと思うのは、西洋論理に合致するかどうかである。遺伝的障害者は、悪い遺伝子を持っているのだろうか。その価値観が分からない。
「しかし、魂の病にしても、メガトン(級の核ーー引用者)の威力にしても、こうしたことはすべて、ある単純な思想から生じてものである。すなわち、自然は客観的であり、真の知識は論理と経験と組織的に突きあわせて得られる、という思想である。思想の王国の中でも、これほど単純かつ明瞭な思想が、ホモ・サピエンスが出現してから十万年もたった後でなくては白日のもとに現れえなかったのは、どうしてであろうか。たとえば中国文明のようないくつかの最高の文明が、この思想を知らずにきて、西欧から初めて学んだというのは、どうしてであろうか。また、その西欧においてさえ、この思想は実用一点ばりの機械工学のなかに閉じこめられていたのであって、これがついに固い殻を破って解き放たれるまでに、ターレスやピタゴラスからガリレイ、デカルト、ベーコンまでの二五〇〇年近くの歳月が必要だったのは、なぜであろうか。これらすべては理解に苦しむことである。」(P.193)__理解するのは西欧人には難しいが、それこそが問われなければならない。
(思想の淘汰)「生物学者にとって、思想の進化と生物圏の進化とを比較することは非常に心をそそることである。というのは、〈抽象の王国〉が生物圏を超越している度合は、生物圏が非生(FF)物界を超越している度合よりもさらにいっそう大きいにはちがいないが、思想は生物の特性のいくつかを保持しているからである。思想は生物と同じく、みずからの構造を永続化し、増殖させる傾向をもっている。」(P.193-194)__(古い書き込み)科学の思想への無理な適用。アナロジーですらない。宗教の構造の緻密さ。
「浸透力はそれ自体としてははるかに分析しにくい。それは、精神の中に以前から存在していた諸構造ーーそのなかには、文化によってすでに運び込まれていたもろもろの思想が含まれるが、ーーに依存しているが、そればかりか、疑いもなく若干の先天的構造にも依存している。もっとも、これらの先天的構造を同定することは非常に困難である。しかし、自明のことではあるが、最高の浸透力をもった思想は、人間が占めるべき地位を内在的な運命ーーそのふところにいだかれれば人間の不安はときほぐされていくーーのなかに割りあてることで、人間というものを説明するものである。」(P.195)
「おそらくだれかが時として掟を侵犯することはあったであろう。しかし、おそらく、それを否定しようなどと思った者は一人としていなかったであろう。」(P.195)
「この遺産を支えるためには、なんらかの遺伝的な支柱、すなわち精神をして文化的遺産を必要な糧とさせるような遺伝的支柱が必要であった。もしそうでないとしたら、わが人類において、社会構造の基礎となす宗教現象が普遍的であるわけを、どのようにして説明できるであろうか。さらにまた、神話・宗教・哲学的イデオロギーがじつに多様でありながら、そのなかに本質的に同じ《形(たぶん Form−−引用者)》がつねに見いだされるわけを、どのようにして説明できるのであろうか。」(P.197)
「人間の胸苦しい不安を一方では鎮めつつ、掟を確立させる目的で作られた《説明》〔神話的・宗教的説明〕は、どれもこれも《物語(イストワール)》〔歴史の意ともなる〕であり、より正確に言えば個体発生的であることは容易に理解できる。原始的神話はほとんどすべて、多少とも神的な英雄について語っている。そして、彼らの偉業が集団の起源の説明となり、そして集団の社会構造を不可侵の伝統という基礎のうえに築くのである。歴史は作りなおされることがない。」(P.197)__ピダハンには創世神話がない。歴史はいくらでも変えられる。解釈し直される。歴史として残るのは「文献」という客体のみである。主体の(を)喪失した事実(客体)。
「しかしながら史的唯物論は、人類の歴史に限られているし、《科学》の持つ確実性をよそおってはいるが、f依然として不完全なものであった。精神の要求する全面的解釈をもたらすためには、弁証法的唯物論をこれにつけ加えなければならなかったのである。すなわち、そこでは人類の歴史と宇宙の歴史とが、同じ永遠の法則に服従するものとして結びあわされねばならなかった(FF)のである。」(P.198-199)
「この峻厳にして冷静な思想は、いかなる説明も提示せず、しかもあらゆる霊的な糧への欲望を禁じ(FF)断念させるものであるから、とうてい先天的な胸苦しい不安を鎮めることができず、それどころか、ますますそれをかきたてるのである。」(P.199-200)__WhyやWhatではなくHowを示そうとする西欧論理は、無限につづく、ように見える。分析的(部分に分ける)思考。
「それは〈人間〉と自然とのシダの物活説的旧約を告発し、この貴重な絆の代わりに、冷えきった孤独な宇宙のなかでの胸苦しいまでに不安な探索を、あとに残すだけにしたのである。このような思想に味方する者は、清教徒的な傲岸さ以外には見当らないが、いったいそれが受け容れられることができたであろうか。事実それは受け容れられはしなかったし、まだ受け容れられてはいない。」(P.200)__西欧のみが持つ不安感。不満足感。それが世界を覆いつつある。その世界に満足(幸せ)はない。幸せは、その思想の上(sur)・外、越えたところにある。近代科学や哲学は、ユダヤ教徒が生みだしたという説がある。モノーが何教徒かは分からないが、現代でも科学者が、熱心な信仰家であることは西欧では当たり前である。
「三世紀の間に、客観性の公準を基礎とする科学は、社会のなかにそれ自身の地位を獲得した。それは応用面の話であって、魂のなかまで征服したわけではない。現代社会は科学を基礎として築かれている。現代社会の豊かさ、力強さ、さらに、その気になればずっと大きな富と力とがそのうちに〈人間〉のものになるという確信は、科学のおかげで得られたものである。」(P.200)
「知識と真実の源としては物活説の伝統を放棄してしまった一方で、自己の価値を正当化するために死に物狂いでこの伝統にしがみついて、自己の樹立を試みているという、分裂した文明が史上はじめて現れたのである。西欧諸国の《自由主義》社会は、その道徳を基礎として、ユダヤ=キリスト教敵宗教性と、科学主義的進歩主義と、人間の《生まれつきの》権利への信念と、功利実用主義とを、混ぜあわせた胸の悪くなるような代物をいまだに口先で教えているのである。」(P.201)
「これらの体系は、科学を利用したがるくせに、これを尊重したりこれに奉仕したりする気持ちはないのである。絶縁がかくもはなはだしく、虚偽がかくも公然としているので、ある程度の教養を身につけ、なんらかの知性に恵まれ、あらゆる創造の源泉たる例の胸苦しい精神的不安を宿している人間ならばだれしもが、このような絶縁と虚偽に悩まされ、そして良心を引き裂かれる思いをしているのである。」(P.202)__自分の心は「物」じゃないけど、自律して存在しているという事実。物質からいかにして心が発生するのか。
「それは病の徴候と、その根深い原因とを混同しているのである。」(P.203)
「なんとなれば、科学は価値の判断を行わず、価値を無視しなくてはならないからである。」(P.203)
「伝統的な体系はすべて、倫理(FF)および価値を〈人間〉の力の及ばぬところにおいていた。価値は彼に属していたわけではない。価値のほうからおしつけてきたのであり、〈人間〉のほうが価値に属していたのである。彼はいまや、価値が自分だけのものなのを知っている。」(P.203-204)__不安、不完全、不満足。唯一の救いは「発展しているとおもいこむこと」。今日は昨日より良い、明日は今日より良くなる、と信じること。それによって今日を満足するように自分に言い聞かせること。
「ーーまず、言うまでもないことであるが、価値と知識とは、行動においても談論(ディスクール)においても、つねに、そして必然的に互いに結びつけられているからである。(LF)ーー第二に、特に、《真の》知識という定義そのものが、分析を突きつめていくと、倫理的次元の公準にもとづいていることになるからである。」(P.205)__知識人のおごり
「他方、倫理はーー本質的に非客観的なものであるからーー永久に知識の領域から排除されているのである。」(P.206)__「真実を知ってどうなる?だれも幸せにならないだろう」。ガリレオ・ガリレイ「それでも地球は回っている」。でも、今でもだれも目を回さない。
「すなわち、文化史のなかで比類を見ないこの出来事が他の文明の内部においてではなくて、かえってキリスト教を奉ずる西欧において生じたのは、おそらくひとつには、〈教会〉が聖なるものの領域と世俗的なるものの領域とのあいだの根本的区分を認めていたという事実に由来していると思われる。」(P.206)__なぜキリスト教会はそれを認めていたのだろうか。他の宗教にはないのだろうか。理由があるはず。
「客観性の公準は《旧約》を告発しつつ、同時に知的判断と価値判断とのあいだのいっさいの混同を禁止することになる。」(P.207)
《叙説》〔ディスクール、演説という意味もある〕(P.207)
「これに反して客観的体系においては、知識と価値との混同はいっさい禁止されている。しかし(そしてこれが本質的な点であり、知識と価値とを根本で結びつける論理的な結節点であるが)、この混同の禁止という《第一戒律》は、客観的知識の基礎を形づくるものではあるが、それ自体が客観的なわけではなく、また客観的たりえないであろう。ーーそれは道徳的規則であり、規律である。真の知識は価値を無視するが、真の知識の基礎を形づくるには、価値判断、あるいはむしろ価値についての公理が必要である。明白なことであるが、客観性の公準を真の知識の条件として据えるということは、倫理的選択であって、知識による判断ではないのである。なんとなれば、その公準そのものに従えば、この審判者的な選択に先だつ《真の》知識なるものはありえなかったはずであるからである。」(P.208)__公理、公準そのものは問うことはできず、論理的でもない。
「現代社会は科学によって織られ、科学の所産で生きているのであるが、その反面では、麻薬中毒患者が麻薬にすがっているように科学にすがるようになってしまっている。現代社会が物質的に強大なのは、知識の基礎をなすこの倫理のおかげであり、またそれが道徳的に弱体なのは、知識そのものによって掘り崩されているのに、現代社会がいまだに頼ろうとしている、古い価値体系のせいである。」(P.209)__「現代社会」が、いわゆる先進諸国だけをさしていることに注意すること。
「知識の倫理は、説明を与えることはできないが、人間の求めているものはそんな説明ではなく、自己を超克・超越することではなかろうか。」(P.210)
「さいごに知識の倫理は、私の見るところでは、真の社会主義を築くための基礎となるべき、理性的であるとともに、断固とした理想主義的な唯一の態度なのである。」(P.212)
「おそらくほかの数かずの物活説よりも、史的唯物論のほうがさらにいっそう、価値のカテゴリーと知識のカテゴリーとの全面的混同のうえに立っているのである。」(P.212)
付録
Ⅰ タンパク質の構造
Ⅱ 核酸
「最後に、電離放射線(X線や宇宙線)は明らかにDNAの一部分の除去をひきおこしたり、あるいはDNAの鎖を《グシャグシャ》にしてしまう。」(P.222)
Ⅲ 遺伝暗号
Ⅳ 熱力学の第二法則の意味について
訳者あとがき
「個々の生物の自由度は遺伝情報によって限定されているが、集団としての生物の自由度は、タンパク質の性質によって、莫大なものになっているということになる。彼は、オペロン説と、アロステリック・タンパクの概念とを基礎にして、生物の持つ「合目的性」の本体を暴露させたのである。「合目的性」というのは、進化の結果として、生物という分子機構がもつことになった属性にすぎな(FF)いのである。」(P.234-235)
「本書で、もう一つ重要なのは、知識の倫理ということで、倫理は与えられたものではなく、客観的認識のうえに新たな倫理を築くべきことを要請している。」(P.135)
昭和四十七年十月十六日 渡辺格