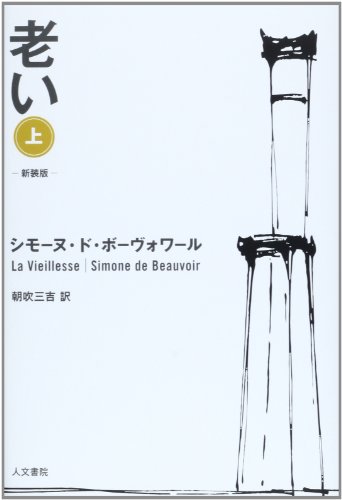
100分de名著
Simone de BEAUVOIR :"LA VIELLESSE", GAllomard, Paris, 1970 の全訳です。
『100分de名著』で上野千鶴子さんが紹介していたのが2021年の7月です。その時買いましたから、約1年間かけて読んだことになります。
とにかく読むのが辛かったです。2段組で上巻322ページ、下巻380ページという大作です。字が小さい上に、ルビが多い。その小さいルビは老人には辛いです。活字がところどころかすれています。私が読んだのは「新装版」ですが、訳者「あとがき」に「一九七二年三月」とありますので、活字の組み換えも行わずに「新装」して、新装前にはかなりの版数を刷ったのだろうと思います。
改めて見てみると、ルビ以外の活字はそれほど小さくないようです。文字の大きさ(読みやすさ)は読み手の気持ちで変わるのかもしれません。
資料
帯に「日野原重明氏推薦「私の大切な資料です」」とあります。本当に「古今東西」といっていいくらいの資料を使っています。古くは古典ギリシャから現代まで、日本も含めて世界中の資料、文学から芸術・政治・文化人類学まで幅広い領域を網羅しています。この本を書くために、そしてこの本を書くまでに、どれほどの本(資料)を読んだのでしょうか。ボーヴォワールは才能だけじゃなく、努力の人だったんだなあ、と思わせます。
内容は少しも難しくありません。伝記や自伝、ニュースなどからの引用がほとんどです。哲学用語も政治用語も出てきません。実存主義的な言葉が一部出てきますが知らなくても大丈夫です。
原書を見たことがないので(見てもフランス語は全くわからないので)はっきりとしたことは言えませんが、素晴らしい訳だと思います。ルビが多いと言いましたが、フランス語を直訳ではなくわかりやすい、文脈に合った日本語にしているだけではなく、場合によってはルビでフランス語(の発音をカタカナで)が付けてあるので、元の単語がわかり、理解をたすけてくれます。また、原書が長文のときは文を分けるのではなく、日本語としては複数のセンテンスで、ただし句点ではなく読点でつなげています。こういう訳のしかたは見たことがありません。翻訳書としての一つの提案だと思うのですが、普及してほしいものです。
一つ大切なことがあります。それは、各種資料〔文献〕を読むときの注意です。
われわれに知られているすべての文明は、搾取階級と被搾取階級の対立によって特徴づけられている。それゆえ老いという語は、人がそのいずれを考慮するかによって、深く異なる二種類の現実を意味するのだ。展望をあやまらせるのは、老齢に関する省察や作品や証言が、つねに上流階級者の身分を反映していることである、すなわち、彼らだけが語っており、しかも一九世にいたるまでは、自分自身についてしか語らないのだ。(上巻、P.248)
文献(文字として残っているのも)は、そのときに生きていた大多数の人のこと(気持ち)が書かれているわけではありません。文字として残し得たのは、その時代の特権階級だけです。また、同じことは現代の著作にもいえます。ボーヴォワールは哲学者であり、作家です。現代社会の大部分を占める賃金労働者ではありません。そのことは、当然その著作にも反映されているのです。
それを認めた上で、ボーヴォワールが感じ、考えたことは、同じ現代を生きるわたしたちと共通するところが多いと思います。
ルビについて
前述のとおり、ルビが多い本です。翻訳物はルビが多いのは当然ですが、この訳書ではいくつかのパターンがあります。
まず、単純な漢字の読み。「咽喉元(のどものと)」「手段(ちから)」「生存理由(いきがい)」「時間(とき)」など。戦後生まれのわたしは基本的には教育漢字しか読めないし、それすら怪しいので助かります。この例は、誰でも読めるんだけど、ちゃんと読んでほしいという訳者の優しさ、それと「訳者の文体(ことばづかい)」で読んでほしいということだと思います。訳書も作品ですからね。
次は、意味をはっきりさせるために原語をカタカナで説明するルビ。「客体(オブジェ)」「体制(システム)」「目標〔終末〕(ファン)」「劇(ドラマ)」「一対(カップル)」など。これで、意味の広がりが生まれます。
次は、あまり馴染みのない単語。「連累関係(コンプリンク)」「老人愛好(ジェロントフィリー)」「固定映像(ステロタイプ)」「不在〔欠落〕(アブサンス)」など。フランス語が分からなくても、なんとなく意味がわかります。「利害的関心物(アンテレ)」くらいになると、辞典を調べる必要が生じてきますが。
原書に忠実に訳しながらも、日本語としてもわかってほしいという訳者の思いが伝わってくるルビです。
「勤人階級(ホワイトカラー)」「姿(イメージ)」などは、フランス語をルビで表示したものではなくて、日本語読みに近いものでしょう。
「老い」の本
読むのが辛かったのは字が小さかったからだけではありません。内容が難しかったわけではないのは前述のとおりです。「老人初心者」の私には「老いがもつ辛さ」が一行一行突き刺さったのです。
定年退職をしたとき、「やっと自由になれた」と思いました。嫌な仕事をしなくてよくなったと思い、数十年飲みつづけていた鬱の薬をやめ、本来の「夜型生活」に切り替えました。「これで好きなだけ本が読める」と思いました。新しいプログラム言語を始めました(BASIC、アセンブラ、COBOL、C、JAVA、そして今回はJavascriptとPHP)。
ところが、すぐに身体に異変が現れました。まずは抗うつ剤の禁断症状です。そんな中で読んだのが、森村誠一さんの『老いる意味』です。「老人性鬱病」という言葉を知りました。でも、森村さんは大都会に住み、蓄えも社会的地位もある老人です。私とは状況が全く違います。それに、その本の記述は「一流小説家」とは思えないものでした。
老いることは「必然」なのでしょうか。さらにその頃に読んだのは、デビッド・A・シンクレア著『LIFESPAN(ライフスパン): 老いなき世界』です。「なぜ老化し、それは必然なのか」という話題のトンデモ本です。トンデモ本ですが、おもしろかった。著者は分子生物学者です。老いのメカニズムを解明し、老いを停止し、さらには若返らせるという内容は素人の私には反論できませんでした。
そのころから、目の調子が悪くなりました。続いて歯が悪くなり、睡眠にも障害が出ています。目医者に生き、歯医者に行き、睡眠薬をもらい、どれも良くならないままなんとか生き続けています。
思い知らされたのは、私が社会と関わっていたのは仕事だけだったことです。退職と同時に人と話すことがなくなってしまいました。折からのコロナ騒動で外出もままなりません。散歩すらしない私は、「引きこもり老人」になりました。引きこもりって辛いんだな、ということを実感しました。(汗)
老いの自覚
誰でも歳をとります。老いるのです。それは間違いなく、「死」に近づくということです。シンクレア氏は「不老不死」を説いているわけではありません(それこそがその本の弱点です)。本書は、「誰もが老い、死ぬ」という前提で書かれています。
ところが若い頃はその事を考えないのです。「知っている」ということは「わかる」ことではありません。それはどこか「他人事」です。老人問題や老人医療・年金の問題も自分の問題ではないのです。私にも親がいます(いました)。でも、老人のイメージは「汚い」「臭い」「役に立たない」「面倒な存在」というものでした。理解しようとせず、自分がそうなることを想像すらしようと思いませんでした。
前述のとおり、老人(退職後)の医療はすぐ身近になりました。そして年金です。37年働いて、もらえる年金は月にして十数万円。家は持ち家ですが、夫婦二人が生活していける額ではありません。退職金は家のローン残額の支払で消えました。今は少ない貯蓄を切り崩して生活しています。
うつや病気(それに運動不足)でやっと自分の老いを受け入れざるを得なくなったのです。この本を書いたときのボーヴォワールは60歳(本文より)。よく言われることですが、ボーヴォワールは「自分のこと・体験」を書きました。『第二の性』と同様です。最近「60歳はまだ老人じゃない」という風潮が強くなりました。そうでしょうか。この「まだ」というのはどういう意味でしょうか。
読むのがつらい
とにかく、読むのがツラい本です。読んでいる最中もそうでしたが、今回書き抜きをするためにちょっと目を通してもとてもつらい内容です。ツラい文章例をいくつか挙げようと思いましたが、書き抜くのも辛い内容なのでやめます。(汗)
老年の悲劇は、人間を毀損する、このような人生のシステム全体への根元的断罪である。このシステムはその構成員の圧倒的多数者にいかなる生存理由(いきがい)をもあたえない。労働と疲労がこの〔生存理由の〕欠如を隠蔽している、そして定年の瞬間にそれがあらわになるのだ。これは退屈よりもはるかに重大である。年を取ると、勤労者はもはや地上に自分の占めるべき場所をもたない、しかし実はそれは、彼が一度としてそのような場所をあたえられたことがなかったからなのだ。ただ彼はそれに気がつく暇がなかったのだ。それを悟るとき、彼は一種痴呆的な絶望におちいる。(上巻、P.319-320)
「労働者」と言っていますが、これもボーヴォワールの実感だと思います。もしそうでないのなら、この本自体が単なる学者の戯言になってしまいます。だから「実感だったんだ」という前提で話をつづけます。
ボーヴォワールには「自分が占めるべき場所」はなかったのでしょうか。サルトルと一緒の人生、(いろいろあったでしょうが)そこにも著者の居場所はなかったのでしょうか。もしそうだったとすれば、著者もサルトルも可哀想です。サルトルは「自由の刑に処せられ」ていました。ボーヴォワールもそうだったと思います。それが二人を結びつけ、また同時にお互いを「居場所」とはしなかった、ということなのかもしれません。
二人のことだから、毎日のように「口角に泡を飛ばしながら」話し合っていた、というような風景を私は想像します。それは「自由の刑に処せられている」二人だからそうしたでしょうし、それがお互いに「居場所」を探すことだった。でも、その「居場所」は「あたえられたことはなかった」。
彼はそれが見つからない。なぜなら、それを捜すことは、すでにそれを失っていることだからだ。(ショーペンハウアーの言葉、上巻、P.234)
「失われた居場所」をどうやって見つけるか。その苦悩がこの本ににじみ出ているように思います。60歳になった著者は、「対自的存在」としての自分、その自分が見つめる「他者のしての老人」の現状は著者を絶望にまで追いやったのかもしれません。
多くの老夫婦の場合、二人は同じ屋根の下に住むが、まったく離ればなれに生きている。そうでない場合は、前述(さき)にみたように、彼らの関係は不安で、要求が多く、嫉妬に悩まされ、たがいに不可欠でありながら、人生を生きやすくするように助け合おうとしない。真の和合を経験する者はごく少数である。(下巻、P.234)
社会福祉(あるいは社会主義)という希望
著者が明るく描く場所が2つあります。一つはサン・アントニオ(アメリカ)にある『ヴィクトリア・プラザ』です(上巻、P.292)。Wikipediaにはそれらしき施設が載っていますが、そのことでしょうか。現在満室のようです(笑)。街の中心近くにあります。価格の見方はわかりませんが、近隣のアパートよりも安いようですね。それでも私のような貧乏人とは縁がなさそうです。
老人たちにとってはたんに施療院や養老院だけでなく、社会全体が一つの巨大な「死のための場所(ムーロワール)」にほかならないのだ。(上巻、P.319)
もう一つは社会主義崩壊前の東欧です。国によって程度が違いますが、ボーヴォワールはそこに希望をいだいているように思います。でも、
社会主義諸国は資本主義諸国よりも少しはそれに近づいているとしても、まだほど遠い。(下巻、P.316)
なぜ社会主義諸国に希望を抱くのか、そもそも「社会主義国」とはなんなのか。最後に考えたいと思います。
ボーヴォワールの性愛観
この本には「私」がたくさん出てきます。「自分」という言葉も多く出てきますが、「自分」というのはほとんどが老人のことです。「私」というのはボーヴォワール自身のことです。ですから、「私」は「老人になった自分」のことで、著者の徹底した自己分析と告白の本なのです。赤裸々に、歯に衣を着ずに語るボーヴォワール。上野千鶴子さんは、ボーヴォワールとは友だちになりたくない、と言っていました(笑)。
この快楽の追求が、一つの機能のたんなる行使に限定されることは稀でしかない。それはふつう、当事者の各々が自己の実存と相手〔他者〕の実存とを独自な様態で実感する、一つの情熱的行為(アヴァンチュール)である。欲望と興奮のなかで、意識は肉体としての他者に到達するために自らを肉体化する、ーー肉体としての他者を魅惑し、所有せんがために。このように相互的で二重の肉化があり、世界の変容がある、すなわち、世界は欲情の世界となるのだ。この所有の試みは、宿命的に挫折する、なぜなら、相手である他者は主体でありつづけるから。しかし終結する以前(まえ)に、この相互性の劇(ドラマ)は、抱擁のなかで、そのもっとも激烈で、もっとも啓示多い相の下に生きられるのである。このドラマが戦いの様相をとるならば、それは敵意を生む。しかし多くの場合、それは必然的に馴れ合いの感情を含み、これが愛情へとみちびく。自己と他者をへだてる距離が消滅するほどの愛をもって愛し合う一対(カップル)にあっては、挫折さえ克服される。
性愛の抱擁において主体は魅惑する肉体として自らを存在させるのであるから、彼は自己に対してある種の自己愛的(ナルシシズム)関係をもつ。彼の男性としての、あるいは彼女の女性としての特質が主張され、確認される。したがって、彼あるいは彼女は自己を価値あるものと感じる。この、自己を価値あるものと感じたいという欲求が、性愛生活のすべてを支配する場合がある。そのとき、性愛生活は誘惑しようという不断の企てとなり、男性的力強さあるいは女性的魅力の絶えざる主張となる。すなわち、自分が演ずることを選んだ人物の高揚、掲示である。(下巻、P.52-53)
こんな面倒なことを考えてセックスするなんて、哲学者は大変。でも、人間は頭でセックスする動物だと言われています。その「頭」とはその大部分が「意識・自己(自我)」のことです。というか、人間は基本的には意識しか意識できないので、「意識的に行為している」という面を過大視してしまいます。
自我とセックス
「気がついたら触ってました」という痴漢の無責任な発言。「忘我の境地に達するエクスタシー(オルガスム)」というセックスの魅惑。セックスや恋愛はどこか「意識と無意識」「人間と動物」の垣根を超えるようなもの、意識的な制御ができないもの、意識を超えたもののようです。でも、意識的に制御できることなんてかぎられています。いちいち意識的に手を制御してコップを持ち上げる人は少ないのです。ところが老人になると、今まで無意識に動かしていた身体がうまく制御できなくなります。
それというのも、老いはサルトルが「実感されえないもの」と呼んだ、あのカテゴリーに属するものだからである。実感されえないものの数は無限である、それはわれわれの状況の裏側をあらわすものなのだから。われわれが他者にとってそうであるところのもの、それをわれわれは対自の様相において生きることはできない。実感されえないものとは、「私のすべての選択を限界づけ、それらの裏側を構成するところの、距てられた私の存在」なのである。(下巻、P.18-19)
「それら多くのささいな疾患は老人というものを実に哀れな存在にする。私の精神が肉体から気を紛らせ、肉体を忘れることに成功することはほとんどなく、これは言いようもないほど仕事のじゃまになる。」(ジィドの言葉、下巻、P.50)
青・壮年期には、自分の肉体、あるいは(場合によっては)自分が属する社会すら「自分の思い通りになる」ものだと考えます。それが「自由」であることだからです。そうできないのは「自分に力がないからだ」と考えます。私も自由を与えて力を与えなかった社会を怨みながら生きてきました。
恋愛やセックスにおいて中心となる「自分〈自我〉」は、〈他者〉である恋愛相手やセックスの相手の前で立ち往生します。「獣(けもの)になれない自分」を悔やみます。「人間としての恋愛・セックス」を貫こうとするのです。
人間だけじゃなく社会性のある動物は、やはり社会・文化(らしきもの)をもたざるをえず、そのなかでセックスしています。文化か遺伝かということではありません。植物の世界には植物の、蝶の世界には蝶の、サルの世界にはサルの社会・文化があり、そこでセックスをしています。有性生物(あるいは私が思うには無性生物も)が持つ社会性を今西錦司は『生物の世界』で描いています。「自我」の存在も社会性の一つの形ですが、自我をもたない(少ない)社会があることを考えたとき、自我は人間のセックス(生きることも含めて)に必然ではないと考えざるをえません。
自我をもった存在(対自存在)としてのセックスと、「生物種である人間としての」セックスは切り離さなければならないと思うのです。「動物と人間」ではなく、「大脳で(「文化」のなかで)セックスせざるをえない人間という種」と「自我意識の壁を乗り越えなければセックスできない人間」との切り分けです。
自我を持ったセックスの悲劇が、前掲の引用文に描かれていると思います。
女性の人権が認められていなかったとき、つまり女性が人間ではなく「物」だったとき、主体(自我)である男は客体(対象)である女性を「所有」する必要がありました。女性が人間となったとき、その関係は闘争となって、「征服・被征服」「勝者・敗者」の関係とならざるをえません。それは男性同士の関係と同じものです。女性が物や被征服者でなく、「第二の性」でもなくなるための試みとその結果がここに描かれていると思います。それは「戦い」と、その結果としての「挫折」か「抱擁の中での馴れ合い」としてしか解決されないのでしょうか。
「女も自立したければ闘わなくては」という人もいるかも知れません。でも、一部の女性を除けば女性は闘いたくないと思っているのではないでしょうか。男性だって、一部の人を除けば闘いたくはありません。「負けたくないがために」仕方なく闘っている人がほとんどだと思うし、闘うことを強制することはできないと私は思います。
対自は存在しない
生きてあること〔実存すること〕、それは人間存在にとっては、己れを時間化することである。すなわち、現在において、われわれはわれわれの過去を乗り越える投企(くわだて)によって未来を志向する、そしてこの過去のなかにわれわれのもろもろの活動は落ち込み、惰性態と化したもろもろの要求を背負ったまま、凝固する。(下巻、P.103)
過去は対自の様態によって生きられたのだが、それでいて即自となった、それゆえ、われわれは過去のなかにおいてこそ、実存がつねに空しく憧れているあの即自と対自との不可能な綜合に到達できると考えるのである。(下巻、P.103-104)
実存主義の、そしてサルトルの基本命題です。私は実存主義の著作もサルトルも読んだことがありません。なので訳者の「あとがき」から引用します。
サルトルの著作の邦訳などに付された用語解を参照していただければ幸いであるが、たとえば下巻四二七頁で即自(存在)、対自(存在)という場合、簡単に言えば、前者は石ころのように「そうであるままのもの」、そのかぎりにおいて完全に充実したものであり、後者は自意識をもった人間存在、すなわち、自由と志向性=投企(くわだて)をもつことを本質とするゆえにつねに現在の自己を否定的に乗り越えて未来(投企)へと向かう実存者の様態を意味し、完全に自足した(即自のような)状態を求めながらも、そうなることはできない存在である。また、本書のたとえば下巻四四一頁に言われている実践的=惰性態という言葉は、実践的な惰性態という意味ではなく、実践の領域に属していたものが凝固して惰性態となったものという。その箇所で言われているように、たとえば人間の実践活動の結果が著作なり制度となって固定し、それを創り出した人間を逆に制約するようになるもののことである。(下巻、P.359)
ページ数は「原書の」でしょうか。過去は記憶のなかで固定され、石ころのように「即自存在」になってしまいます。
たとえ彼らが〔前述した〕自己認知の危機にうち勝ち、自分自身についての新たなイメージーー好人物のおばあさん、定年退職者、老いた作家などーーを受諾した場合でも、内心では昔のままだという確信を持ちつづけている。そしていろいろな思い出を想起して、この安心感を正当化するのである。(下巻、P.104)
記憶はつくられる(再生産される)ものです。だから、予想と同じく〈美化〉され、変形されます。変えることができる経験そのものが全体(欠けた全体)なのです。それでもその記憶が現在の私を形づくっていることは間違いありません。ですから、
近親者、友人たちの死は、たんにその人の存在をわれわれから奪うだけではなく、われわれの人生のなかで彼らとかかわりのあったすべての部分を奪い去るのである。(下巻、P.110)
過去の私が自分を投企した(意志し、企て投げ入れた)未来、つまり現在においても自己は実現(回収)されません。
つまり現在は、たとえ私の期待と完全に一致したとしても、私が期待していたもの、すなわち、実存〔対自〕が空しくも志向する存在の十全性を私にもたらすことはできないのだ。対自は
存在しないのである。そして何人(なんぴと)も「私はすばらしい人生をもった」と言うことはできない、なぜなら人は人生をもつことはないからだ。(下巻、P.112)
なんと寂しい話でしょうか。
死
「老人の性(セックス)」の認識は、まだ広がっていません。年を取るとともに老人は迷いやエログロから自由になる、解放される、いや解放される(されている)べきだ、という風潮が根強く残っています。「老いらくの恋」とか「いろぼけ老人」という否定的な言葉も多く聞かれます。
以上、多くの事例によって明らかだが、老いが心の明澄をもたらすという偏見は徹底的に排除されなければならない。古代以来、成人は人間の境涯を楽観的な光の下で見ようと努めてきた。成人は自分以外の年齢に自分がもっていない美徳を押しつけてきた。すなわち、純真無垢を子供に、明澄さを老人たちに。(下巻、P.248)
子供がたんに無邪気で純真無垢ではないのと同じように、女性は生理が終わっても、男性は勃起しなくなっても性愛欲(リビドー)がなくなるわけではありません。
性愛欲は当人の死とともにはじめて消滅するのである。それはまた、さまざまな感覚やイメージのモザイクを生み出す反射運動の総体とも全く異なるものだからでもある。それは他の肉体をめざす、そして実存の一般的運動に合致するところの肉体によって生きられた志向性なのである。性愛は、それが一つの色情的次元を付与する世界のなかに座を占めている。老人の性愛について問うことは、その性構造において生殖性の優位が消滅した人間の、自己に対する、他者に対する、世界に対する関係がいかなるものとなるかを問うことである。(下巻、P.52)
自己(自我)も死によってはじめて、そしてそれによってのみ無くなります。いや、現代社会においては「自己がなくなること」が死なのです(脳死)。だから、生と性、生きることと愛することは同じなのです。
また私は私の不在について夢想することもできる、しかしその場合、夢想しているのはやはりこの私なのだ。私の死は、私のもろもろの企ての奥底に、それらの不可避的な裏側として、私につきまとっている、が、私はそれ〔私の死〕をけっして実感はしないだろう。私は死ぬべきものとしての私の境涯を実感しないのだ。(下巻、P.196)
実は、死が近づくという観念は誤りである。死は近くにありもしなければ遠くにありもしない、死は
在らないのである。(同)
対自も人生も死も「存在」ではないのです。ボーヴォワールは「実存者としての自己」に疑問をいだいていたのだと私は思います。
習慣・記憶
もしある儀式ーーたとえば英国人におけるお茶の儀式ーーが、その前日私が守り、翌日また守るであろう儀式を正確に反復するのであるならば、現在の瞬間は甦った過去、先取りされた未来であり、私はその両方を対自の様態において同時に生きるのである、すなわち、私は実存者が求めるところの「存在」の次元に到達するのであるーーもっとも〔過去・現在・未来の〕綜合は現実には実現されていないから、それは錯覚なのであるが・・・。(下巻、P.228)
自我の世界に生きている人が、自我のない世界を考えることは「自分の死」を考えることと同じです。それはとても恐ろしいことです。「自分がボケ老人になったらどうしますか」と聞くと「やだあ、自分がわからなくなる前に死にます」と答える人がいます。私がそうですから。私にとっては「私(自己、自我)の喪失は、死」なのです。なぜそれが怖いのかといえば、私は「自我を持った存在」「対自存在」だからです。
それはつねに「未完成」な存在です。過去を乗り越え、未来に投企する存在だからです。「今ここ」に完成はありません。「実存は自己を超越することによって自らを基礎づける」(下巻、P.116)のですから、つねに不安・不満・欠乏をいだいた存在です。現状に満足しない状態であることが実存者の存在理由なのです。
所有もまた一つの存在論的安泰を保証する、すなわち、所有者は彼のもろもろの所有物の存在理由(レーゾン・デートル)なのだ。私のもろもろの所有物は私自身にほかならない。「私の所有物の全体は私の存在の全体を反映する。」(P.230)
獲得した習慣、記憶は誰にも奪うことができない「私のもの」です。でも、私はそれを所有しているわけではありません。所有はその所有物が主体と切り離せる対象(物、即自存在)でなければいけません。そして、所有関係は主体と他の主体(他者)との関係をあらわすものです。通常、植物や動物に対して所有権を主張することはありません。また、無人島にひとりで立って「これは俺の島だ」と叫ぶのは空しいです。人間が存在することと、自我をもつことは同じではありません。同様に、人間の存在が「対自存在」なわけではないのです。存在理由は「自我の存在理由(どうして私は存在するのか)」以外ではありえないし、それは見つかりません。もし見つかるとすれば、それは「社会のある一形態が自我を形成している」という事実だけです。
自分を考察対象とする自我、これが「対自存在」です。存在を全体から切り離して対象とする主体こそが実存であり、それは超歴史的なものでも、普遍的なものでもありません。それは近代西欧が新大陸同様に発見したものです。
老いとは
自分の行動を「括弧に入れ」て活動すること、それは本来性〔真実〕(オータンティステ)に到達することである、そして本来性は虚偽よりも身に引き受けることが困難であるが、それに到達したとき、人はそのことを祝福せずにはいられない。これこそ老齢がもたらすもっとも価値あることである、すなわち、老齢(それ)は物神崇拝(フェティシスム)と空中楼閣とを一掃するのである。
そんなものはもっと早くに厄介ばらいできたはずだ、と人は私に反論するかもしれない。自分を例にとって言えば私は、実存者にとっては存在〔己れ自身で満ち足りた様態〕を追い求めることは空しい努力であるという考えをずっと以前から受けいれていた、つまり、対自〔実存者〕は即自〔存在〕として自己を実現することはけっしてできないであろう、と。私はこの宿命的な挫折を甘受すべきであったのであり、『事物の力』〔邦訳名『或る戦後』〕の終りの部分でその不在を嘆いた、絶対的なるもの(アブソリュ)を夢想すべきではなかったのであろう。しかし、予見すること(プレヴォワール)は知ること(サボワール)でないのと同様、知ることは実感することではない。すべて真実はそうなった〔しかく生成した〕ものなのである。人間的境涯の真実(それ)もわれわれ自身の生成の終わりにおいてしか実現しないのだ。(下巻、P.256)
老いは、永遠と思っていた未来が死によって区切られていることに気づくことであり、蓄積された過去が失われていくことです。対自的存在として客体(即自存在、自然)の上に君臨していた自己に気づく人もいます。もちろん、気づかないで自己の所有物のなかで自己を実現(保存)し続けようとする人がほとんどでしょう。その違いは、その人がどのように生きてきたかに関わっているということもできます。しかし、その自己(自我)そのものはその人が生きてきた文化・歴史・社会がつくり出したものです。それを失うことはまさしく「死」そのものですから、どんなに身体が痛くてもそうたやすくできることではありません。
彼らに対して人が正当に振舞う場合でも、彼らを客体として扱い、主体としてではない。彼らは相談を受けず、彼らの言うことは採り上げられない。彼らに注がれる視線のなかに、彼らは自分が危険にさらされているのを感じとる。彼らは他人(ひと)の視線のなかに悪意がひそんでいるのではないかと疑う。(下巻、P.241)
他人の視線が、老人を即自存在(物)にします。それはボーヴォワールが求めていたものとも言えるし、同時に対自存在としては許せないことでもあります。そしてそれは「終わりにおいてしか実現」してはならないのです。
老人が人間でありつづける社会
人間たちが自己の存在に附与する意味、彼らの価値体系の全体こそ、老年の意味と価値を決定するのである。逆に言えば、ある社会は、老人をどう扱うかによって、その社会の原理と目的のーーしばしば注意深く隠蔽されたーー真実の姿を赤裸々に露呈するのだ。(上巻、P.100)
私たちが生まれ、育ち、作った社会はどういう社会でしょうか。
彼が早くも子供のころから一個の微粒子(アトム)として他の多くの微粒子たちとともに孤立した自閉的な存在にさせられることなく、彼自身の生活と同じように日毎のそして本質的な一つの共同生活に参加するのであるならば、彼は決して流謫の境涯を経験することはないであろう。(下巻、P.316)
私が育った戦後の民主教育は自我・自己というアトム(モナド)を確立することの大切さで満たされていました。ライプニッツのモナドは独立していて窓がありません。独立していて平等だからこそ自由なのです。窓を開けることは自我を侵害される可能性を生みます。独立していて平等で自由だからこそ、他者とは対立関係にあります。つまり、「簡単に心を開いてはいけない」のです。無防備ではいけません。相互の関係は力関係だからです。力のある者は他者を支配することが正当化されます。それは、植物であったり動物であったり、山であったり川であったり、そして人間であったりします。
そのアトムが「ない」窓を開くことが許される(あるいは強制される)ことが一つあります。それが結婚、つまり恋愛です。恋愛が「つらい」のは、その「開けてはいけない」窓を開けるにはとてつもない努力が必要だからです。恋愛というのは制度です。恋愛がこれほど高く評価されるのは、そのせいです(セクシャリティもそのための制度。恋愛や結婚を認めるのは、新しい搾取対象を作るために必要なことです)。
しかしどんな恋愛もその上位の制度、つまり、「儲ける」ということを妨げてはいけません。主体は所有によって自己を確立しようとしますが、主体が観念的であるように所有も観念的になります(それがお金です)。観念化された所有は物の所有と違い限界がありません。そして主体が満たされないように、所有(儲けること)もけっして満たされることはないのです。
自我の絶対性
「対自存在」とは、自らを対象として考察する存在です。対象とされた自分は「対自存在」ではなく、観察される客観物、「石ころと同じ物」、つまりサルトルの言葉でいう「即自存在」になってしまいます。つまり、対自存在は対自存在を対自存在のままで考察することはできません。考察されえない対象は「存在していない」のです。だからボーヴォワールが本書で言うように、対自存在は存在しないのです。西欧社会(哲学)で考察の対象となっている「存在」は「存在そのもの」ではなく、全体としての存在から切り離された対象、「存在者」(ハイデガー)でしかないのです。
本書のなかで度々でてくる「全体」はつねに「欠けた全体」つまり「部分」です。部分を考察し、部分を合わせたものが全体であるというのが西欧哲学、西欧科学の基本です。全体を全体のまま(混沌のまま)考察することはできません。分析すること、分解して分類することが西欧の(アリストテレス以来の)思考法です。部分は、それ自体で「一つの全体(つまり存在そのもの)」ですから、それもさらに分解する対象になります。その無限地獄から抜け出す方法として、「最小単位」「それ以上分解(divide)できない(in)もの」つまり、「individual」、人でいえば個人、物でいえば個物、アトム、つまりモナドを(仮にでも)設定します。
個人を分解することは原理上は許されません。でも西欧的思考はさらにそれを分解しようとします。それが「主体としての私」と「思考の対象としての私」です。精神と肉体(心と身体)を分解します。つぎに、精神を「考える私」と「考えられる私」に分解します。精神を分析する学、精神分析学です。これは西欧的思考の嫡子です。「対自存在」「即自存在」というのは、それを哲学的に表現したものでしょう。対自存在が「ある(存在する)」というのは、証明しようがありません。「我思う故に我あり(Je pense, donc je suis)」と言い切るしかないのです。それが近代的西欧思想の前提です。でも、「私がある(存在する)」「オレはオレなんだあ」と言っても、なんか虚しいですよね。「独り言」「独りよがり」に思えるのです。
私は日本でしか暮らしたことがありません。だから、西欧人がどこまで自我が絶対だと思っているのはわかりません。私にも自我の優位はあります。いや、とても強くあります。同時に『鉄腕アトム』以来の「科学絶対」もあります。つまり「客観の絶対性」です。そこから見ると自我を絶対と考える「エゴイスト(個人主義)」は「わがまま」「自分勝手」に見えます。そして、その個人主義によって被害を受けた人(その人たちを「負け組」といいます。そのなかに私もいます)のことを考えると、「可哀想」だと思うし、「悔しい」とも思います。この世の中を「許せない」と思います。
でも、「可哀想」「悔しい」「許せない」と思っているのも「私でしかない」のです。
社会主義諸国
よりよい社会を作ろう、と多くの人が思っていると思います。いや、そうではないかもしれません。まず、今の社会が良い社会だと思っている人たちがいます。「勝ち組」の人たちです。勝ち組といってもそのなかの多くは「闘い」をしていません。その人たちは生まれたときから「勝ち組」のなかにいます。だから「親ガチャ」という言葉がすぐ一般化します。多くの人は闘わないし、闘いの場に上がることもできません。主体性が絶対ならば、そして自由ならば、闘わないのは「自己責任」です。
そして、多くの人は今の社会を「こういう社会に生まれたんだから仕方がない」と思っているのではないでしょうか。本当に戦って社会を変えた人たちがいます。社会主義国の人たちです。日本では「赤狩り」があり、スターリンの非道な行いをナチスと同じようだと報道され続けました。その後も中国の人権侵害やロシアのウクライナ戦争を「非道」なものと宣伝し続けています。1980年前後に社会主義国が次々と崩壊したとき、それは闘わない人に闘わないことの「言い訳」をあたえた気がします。
社会主義と共産主義はまったく違うし、社会主義とマルクス主義も別物です。ただ、20世紀以降の社会主義はマルクスの『資本論』を信じていただろうことは想像できます。彼らが『資本論』を読んでいたかどうかは別として。
『資本論』は、その名の通り「資本とはこういうものだ」ということを書いた本です。そこには社会主義も、共産主義も描かれていません。当時の労働者の悲惨な状況が描かれている部分はあります。それは労働者の責任ではなくて、資本がもたらしたものだからです。マルクス自身もその資本と闘っていました。でも、原始共産制から資本主義をとおって社会主義、そして共産主義へという歴史観をマルクスがもっていたかどうかは疑問です。マルクスは未来について語ることに慎重だったと思います。それを語ってしまうと、自分が乗り越えようとしているヘーゲルに近づいてしまうからではないでしょうか。
キリスト教の世界観は直線的です。始まりがあって終わり(終末)があるという世界観です。現在は、過去と未来の中間にあります。当たり前だと思うでしょうが、それは西欧的な考えなのです。そしていままで書いてきたように、自己(自我)から始まる考えは「足るを知る」ことがありません。現在は過去を乗り越えたものだし、現在は乗り越えられる「定め」のものです。現在を評価するのは未来です。
生きてあること〔実存すること〕、それは人間存在にとっては、己れを時間化することである。すなわち、現在において、われわれはわれわれの過去を乗り越える投企(くわだて)によって未来を志向する、そしてこの過去のなかにわれわれのもろもろの活動は落ち込み、惰性態と化したもろもろの要求を背負ったまま、凝固する。(下巻、P.103、前掲)
この時間概念そのものが西欧的思考です。そして投企によって未来を志向するのも対自存在としての自己です。それは、過去よりも現在、現在よりも未来を優先します。その社会における所有や価値は、現在よりも未来に向けたものになります。未来のために所有し、価値づけすることで、現在を担保しようとします。対自存在は未来を生きるのです。
社会革命の教訓、形成中の社会における闘争や行動のためのもろもろのスローガン(たとえば「古いものは消滅しなければならぬ、新しいものはその場所をかちとらねばならぬ」)は、世代間の関係に深刻な影響をあたえた。老人たちはこのように警戒の眼をもってみられており、一般的にいって、現在、国内で進行中の革命に組み入れることのできない者とみなされている。(下巻、P.344)
新しいものに価値を見出すのは、まさしく対自存在の権化なのではないでしょうか。
疎外は投企が生み出します。投企は成功しません。未来を生きようとしても、実際に生きるのは現在だからです。成功したと思っても、それは投企した自己とは別のものです。そこにルサンチマンやニヒリズムが生まれるのは必然です。
投企(疎外)とその回収は農業に似ています。今食べずに種を蒔く、秋に実を結べば、今よりも豊富な食料をえられる。でも、農耕文化と主体性の文化は同じではありません。農耕文化は作物を他者とは見るとはかぎらないからです。むしろ牧畜文化が近いでしょうか。牧畜においても、今食べずに育てれば、子供を生む、これは農耕と同じです。でも家畜は他者として食べることができる。家畜を育てるために、家畜をみちびく牧神に近い権力を人間はもっていると想定しなければならない、それがいつしか主体性に変化する、と言えなくもありません。だから、主体性は他者を制御し、所有する権利を持っているし、むしろ制御する義務がある。
社会は進歩べきもので、退歩は許されません。今日は昨日より進歩しているし、明日は今日より進歩している、していなくてはならないのです。その社会で老人が尊重されるでしょうか。老人は乗り越えられた過去でしかないのです。せいぜいノスタルジーとしての過去です。
進歩あるいは退歩という観念は一定の目標との関連においてのみ存在する。(上巻、P.17)
目標はつねに未来にあります。その未来でしか現在を評価することができないのです。だからより新しいものを評価するし、今よりも未来を心配する(「君は心配の権化である」夏目漱石『吾輩は猫である』全集第二巻、P.158、1956/10/12 岩波書店)のです。保険会社が大儲けする社会です(「表紙丈奇麗にして、内容の保險をつけた氣なのかな」夏目漱石『虞美人草』全集第五巻、P.190、1956/10/27 岩波書店)。
時間の直線性と発展性、そこにおける投企した自己の回収、それを想定した上でその回収が現在だということになると、歴史はそこで止まってしまいます。自己意識の具現化、それがヘーゲルの歴史観だと思います(ヘーゲルが西欧において人気がないのはそのためでしょう)。その回収を行わずに投企しつづける自己は、「現在がとりあえず歴史のなかの最前線、進化の頂点としての人間が最高だ、昔の人間より私のほうが進んでいる」と思うことだけが慰めになります。人間中心主義ですし、自己中心主義ですね。人間は、自然(即自存在、他者、存在者)を支配し制御できるし、むしろしなければならない。歴史もその主体が支配し制御できる、あるいはしなければならない。これは資本主義の精神であり、同時にマルクス主義の精神なのではないでしょうか。
老人たちはいかなる経済的勢力をも構成しないので、彼らの権利を主張する手段をもたない。搾取者の利益は、労働者と生産者の連帯を断ち切って、非生産者が何人によっても擁護されないようにすることにある。(上巻、P.8)
経済・生産が「主」になる社会、それは資本主義社会も社会主義社会も同じです。
彼は
プラクシス〔実践〕によってではなく、エクシス〔状態〕によって定義される。時間は彼を一つの目標〔終末〕(ファン)ーー死ーーに向かって運ぶが、それは彼の目標(ファン)ではない、つまり何らかの投企によって措定されたものではない。それだからこそ、彼は現役の人びとにとって、彼らがそのなかに自己を認めない「異種族」のごときものと見えるのである。老いが人に生理学的嫌悪を起こさせることはすでに述べた。人は一種の自己防御から、老いを自分の遠くへ投げ棄てるのだ。しかしこのような〔老いの〕除外が可能なのは、あらゆる企てとの原則的連累関係が老人の場合はもはやはたらかないからこそなのである。(上巻、P.252)
肉体的接触
仕事が強制であったときは、それからまぬがれることは解放である。しかし、実際は、仕事というものはほとんどつねに両義的性格をもつのである、すなわち、隷属や疲労であると同時に、興味の源泉、均衡の要素、社会への統合の要因でもあるのだ。(上巻、P.305)
もう友人と酒をくみかわすことさえできず、自分だけの落ちつく場所も、耕すべき庭の片隅も、新聞を買う手段も、何一つもたない定年退職者は、閑暇の過剰よりも、それを利用することの不可能性と社会的失格とに苦しむのだ。(上巻、P.317)
そこでただ次のように言うにとどめよう、外界との肉体的接触が欠如するとき、人生のある次元が消滅する、と。この、外界との肉体的接触という豊饒さを高齢期まで保持する人は恵まれた人びとである。(下巻、P.90)
人間は社会的動物だ、と言われます。でも、他者との肉体的接触において、他者は対自的存在にとっては即自的存在です。他者は「他の人間」であるのはもとより、動物や植物、土や水でもあります。自分の肉体も他者とみなすことがあります。主体が対象を生み出しているとともに、対象がなければ主体は成立しないのです。
その中でも、他の人間との接触は自我にとっての最大の癒やしなのではないでしょうか。他の主体、対自存在との接触がモナドと化した自己の殻を突き抜ける作用を持つ、と私は感じます。「人のぬくもり」は「自由の刑」に処される前、主客未分離の頃を思い出させてくれるのかもしれません。
ネットの世界や引きこもり、そして新型コロナウィルス対策としての「ソーシャルディスタンス」。それらが締め出した「外界との肉体的接触」によって、どんな次元が消滅したのでしょう。
われわれが保持するもろもろのイメージは、それらの〔現実の〕対象そのもののもつ豊饒さには遠くおよばない。(下巻、P.106)
私も引きこもり老人になったことで何かが壊れたような気がします。でも、これは老人だけの問題ではありません。主客が分離した後にどれだけ「〔現実の〕対象そのもののもつ豊饒さ」に触れるかどうかが大切だと思います。電子書籍ではなくて紙の本、いや『書を捨てよ町へ出よう』(寺山修司)、「Make Love Not War」。そのためには、自分が「対自存在」でなくなることが必要です。でも、相手が「対自存在」に固執しているとき、それは失敗するでしょう。
それは体制(システム)全体にかかわることであり、権利要求は根元的であるほかない、すなわち、人生を変えること、以外にないのだ。(P.316)
それは、対自存在が優先される社会を変えること。
これはまさに戦慄すべき出来事であって、主観性は一旦植え付けられるや、それを根絶することはもはや不可能なのであります。(日下部吉信著『講演集 ハイデガーと西洋形而上学』、P.58)
古典ギリシャ哲学や古代インド哲学が「自我」を発見してから、2500〜3000年経ちます。でも、人類の歴史から見ればほんの一瞬です。デカルトの『方法序説』から約400年、日本に近代西洋哲学が本格的に流入してから約150年、サルトルの『存在と無』が出版されてから、来年で80年。人々の意識が変わるのにはそれほどの時間はかかりません。「セクハラ」が「新語・流行語大賞」を受賞したのが1989年。今年で33年です。その間に人々の意識が大きく変わったのか、あるいは変わらなかったのか。考えていただきたいと思います。
労働者の搾取、社会の細分化、高踏的御用知識人(マンダリナ)の専用と化した文化の貧困、これらが非人間化されら老年という結果をもたらしているのだ。この悲惨な事実は、すべてをその出発点から再検討しなければならないということを示している。それだからこそ、この問題はこのように注意深く隠蔽されているのだ。そして、それだからこそ、この沈黙を破ることが必要なのである。私はそのために読者の協力を求めたい。(上巻、P.13)


