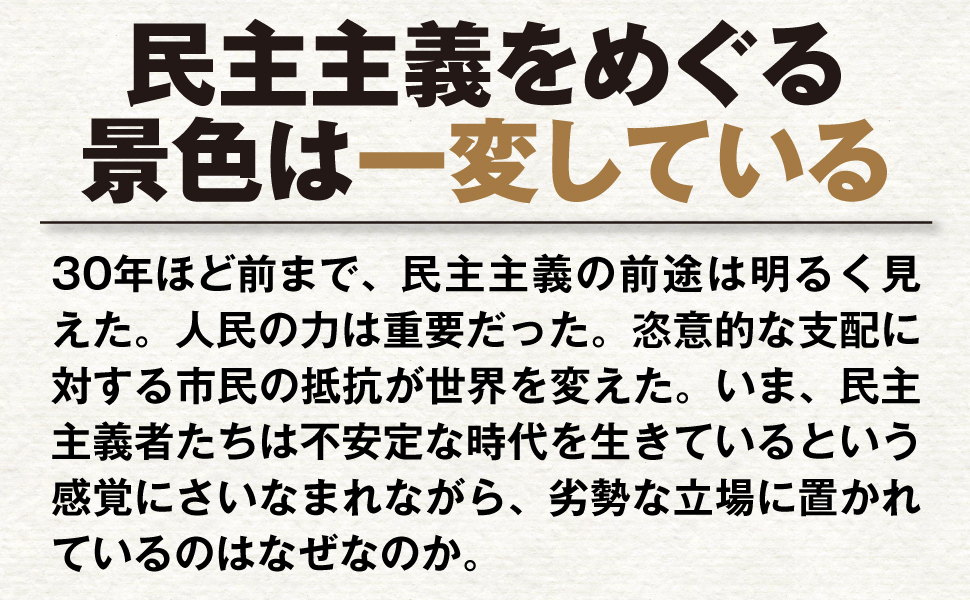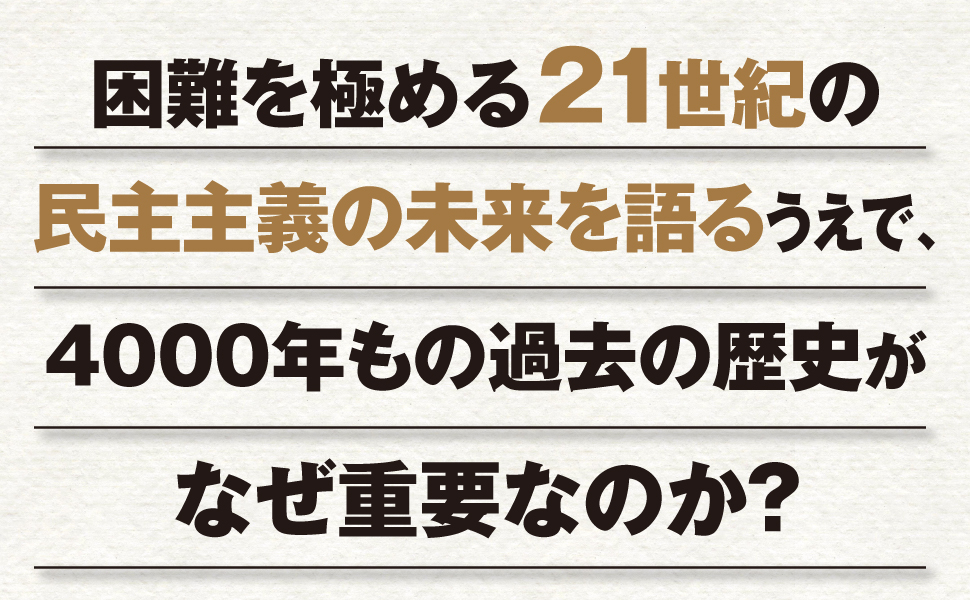『世界でいちばん短くてわかりやすい 民主主義全史 ビジネスパーソンとして知っておきたい教養』
どれが本書の題名で、どれが副題なのかわかりません。原書の題名は『THE SHORTEST HISTORY OF DEMOCRSCY』( by John Keane)と扉の裏にあるので、「一番短い民主主義史」が題名でしょう。
「世界で」「わかりやすい」「全史」、さらに「ビジネスパーソンとして知っておきたい教養」は、本を売るためのキャッチコピーですね。ダイヤモンド社らしいです。
なので、専門書というより、ビジネス書として出版されたのでしょう。
訳について
読みやすい訳だと思います。原書と比べたわけではないので、「正しい」のかどうかはわかりません。
訳注は、本文中に挿入されています。「訳者あとがき」はついていません。原注の文章は翻訳されています。訳者の親切さが感じられます。ただ、ちゃんと見てはいませんが文献の邦訳についての記載がありません。このあたりは、出版社の姿勢の問題でしょうね。
ビジネス書は、「短いこと」、「わかりやすいこと」、そして「それだけで完結していること」が必要です。参考文献を必要としてはいけません。書いてあることを「情報(データ、あるいは雑学、トリビアWiki)」として憶えるかどうかです。それ以上深く知る必要はありません。あとは、使うか使わないか、信じるか信じないか、だけです。
「民主主義」の「歴史」
過去を振り返ることで、我々はより賢明になる。現在の多くの民主主義国家が直面する新たな試練やトラブルの意味を、より正しく理解できるようになる。(P.12-13)
『創世記』を信じるにしても、「ビッグバン」を信じるにしても、歴史(時間)に始まり(と終わり)があり、一方方向に流れる(変化する)というは一つの「考え方(思考方式)」「信念」です。そこに疑問を持ってしまったら「民主主義の歴史」は書けません(笑)。日本には「輪廻」の思想があったので、この西洋的単方向思考、「歴史」にはなじみませんでした。でも、今では当たり前になってしまいました(「西洋」については、デヴィッド・グレーバーの『民主主義の非西洋起源について』を参考にしてください。もちろん「民主主義」についても)。
民主主義は「古典ギリシア(のアテネ)で始まった」という誤った認識を、著者は否定します。それよりはるか昔に古代シリア・メソポタミアでの記録が残っています。またインドにも「集会民主主義」があったという記録があるそうです。でもこれは「記録がある(有史)」ということで、共同体の中で人々が集まって何かを決めるということは「どこでも・いつでも(普遍的に)」あるのではないでしょうか。
むしろ問題は、その「集まって決める・話して(話し合って)決める」という「言語の本質」とも言えることが、「なぜできなくなったのか」ということです。つまり「権力(あるいは利権)」というものが、なぜ、どのように発生したのかということです。
ただ、「権力」言葉(概念)自体が、とても西洋的なのです。もともとは『漢書』にあるようですが、西洋的な「power、authority」の訳語となったのは19世紀後半でしょう。私は「権力」が「power」だといわれても、「powerは力でしょ」というイメージしか持てません。ジョン・レノンが「Power to the people」と歌った時、「人々(人民)に権力を」という意味だったとは思えないのですが、西洋人にとってはどちらの意味もあるのでしょう。
民主主義の種類
まず著者は、「直接民主主義」と「間接民主主義」を区別します。直接民主主義は「集会民主主義」です。それができない(あるいは「代議制民主主義」のほうが優れている)理由は、
領土の関係上、そうせざるをえなかったというのが、歴史家による標準的な答えだ。領土の拡大により、すべての市民が集会で顔を合わせることができない状況の中で、政府が責任を持って権力を行使するための現実的な解決策だった、という考え方だ。(P.118)
しかし、著者はそれだけではないと言います。
公務は専門化と細分化が進み、すべての市民が一体となって行動することはできない。直接民主主義の支持者は、人民が互いに肩を寄せ合い、耳を傾け合いながら協力する姿を想像しようとするだろう。しかし、民主政治には代表者が必要だ。そして、集団を代表してなされる彼らの決断が、結果的に市民の間に緊張関係をもたらす。(P.75)
この「専門化」と「細分化」というのは、この後もずっと民主主義の形態の要素で有り続けます。
学問(科学、知)が細分化されれば、それぞれの学問は専門化せざるをえません。「専門家」でない人、自分の専門以外の学問に関しては、「素人」と言われます。「専門家」がいる社会では、個人の「自己決定」は制限されざるをいえません。新型コロナウィルスが流行しているときに、どんな対策をとったらいいのかは「感染症の専門家」が決めます。もちろん、強制や罰則がなければその対策を実行しなくてもいいのですが、専門家の決定を「否定」することはできません。経済の専門家、土木建築の専門家、医療の専門家・・・、政治家の決定権はどんどんなくなっていきます。政治家に残されているのは、専門家の二つ以上の見解があったときに(場合によっては二つ以上の見解を作って)、どちらにするのかを選択する「選択権」だけです。人民が政治家を選ぶ「選択権」と同様ですね。
そして、代表制(代議制)が優勢になると、
民主主義はいまでは、真の選択に迫られた有権者が、自分たちの利益のために行動する指導者を選ぶ統治形態を意味するようになった。民主主義の定義が改められたのだ。ヘンリー・ブルーム男爵による代表の原則に関する説明が、この点をわかりやすくまとめている。「代表の本質とは、人民が権力を一時的に放棄し、選ばれた代表者に移譲すべきであるということ、そして権力の移譲がなければ人民自身の手で行うはずだった政府の職務を、その代表者が遂行すべきであるということだ」(P.110)
「人民自身の手で行うはずだった政府の職務」の意味はわかりません。
新型コロナウィルス対策も、「明日の天気」を予想するときも、人民は自分で決定することができません。政府広報や、天気予報を見て「知る」ことが「正しい」ことだとされます。
人民が「一時的に放棄した権力」というのは、本当に「一時的」なのでしょうか。難しいですね。夕空を見て明日の天気を考えているときには、明日も同じことができます。でも、天気予報でしか明日の天気を「知る」ことができなくなれば、明日の天気を決める権利は永遠に失われてしまうのではないでしょうか。私が小さい時、転んで膝小僧から血が出ても、母は「なんでもない。だいじょうぶ。ツバでもつけておきなさい」と言いました(笑)。いまはどうでしょう。母親は慌てふためいてスマホで病院を検索し始めるかもしれません。
重要なことは、一時的かどうかよりも、権力(権利)は「移譲」や「放棄」が「できる」という発想です。つまり、私は「明日の天気決定権」「マスクをするかどうかの決定権」等の「人権」の「集まり(集合)」であるという発想です。あるものが分割できる、あるいは分割したものを集めたものが全体である、ということが(近代)西洋科学の(隠れた)原理です。前記の学問の専門化が可能なのも、この原理があるからです。
ひょっとすると、譲渡(放棄)できる権利が「パブリック」で、できない(しなかった)権利が「プライベート」なのかもしれません。そして、その譲渡した権利はなくなってしまうのではなく、「パブリック」として自分がその中に居続けることがでる存在となります。パブリックはプライベート(主体)の意思的構築空間であり、プライベートと対立しない「一つの意思形態」であると考えているのかもしれません(「社会契約論」)。だとすれば、パブリックに参加することは「権利」ではなくて「当然の義務」なのではないでしょうか。
私は、代表選出行為を行った後は「代表される者」は、被支配者のように思えてしまいます。私の自由は保証されるか、代表者は私を代表(代弁)できるのか、と思ってしまうのです。同時に、私は他者を代表(代弁)することなんでできないと思っています。きっと日本的な発想なんでしょうね。
牽制民主主義
集会民主主義の時代は家庭内での力関係や、女性や奴隷の扱いをあくまで個人の問題と見なした。
代議制民主主義の時代には、奴隷制度への反対、そして女性や労働者、植民地の現地人に選挙権を与えようとする動きが見られ、選ばれた政府が医療や教育などの分野に介入した。
牽制民主主義の時代がこれまでと異なるのは、組織化された監視・牽制と恣意的な権力の拒絶が、社会生活全般において可能になったということだ。職場でのいじめ、セクハラ、人種差別、性差別、動物虐待、ホームレス、身体障害者、不正なデータ収集など、あらゆることが民主政治の中心課題となった。(P.216)
「牽制民主主義」という言葉を初めて聞きました。
牽制民主主義とは一体何なのか?なぜ形容詞に「monitory」という単語ーーラテン語の monere(警告する、助言する)を語源とし、もともとは差し迫った危機に対して警告を発するなどの意味ーーが使われているのか?(P.213)
民主主義が「多数派の意思に無制限に従う政治」、もしくは「有権者の票をめぐって争うことで政治権力を得られる制度的な取り決め」ーーしばしば引用される経済学者、ヨーゼフ・シュンペーターの言葉だーーなどと言われていた時代は、過去のものとなった。代議制民主主義の時代は過ぎ去ったのだ。
地方であれ、国であれ、国際社会であれ、非政府組織(NGO)であれ、権力を行使するあらゆる機関が、いまでは議会以外の団体による評価によって公の監視・牽制を受けている。(P.215)
つまり、「NGO」や最近よく聞く「第三者委員会」、つまり政府にとっての「圧力団体」が力を持つ民主主義の形態のようです。科学(知)の細分化(専門化)によって、政治家の知識が追いつかなくなった、決定権を専門家に委ねなければならなくなったことの当然の帰結です。
対照的に、牽制民主主義はマルチメディアで飽和した社会ーーデジタルメディア生態系の中で活動している市民と代表者によって、権力構造が常に監視・牽制られているーーと密接に絡み合っている。
コミュニケーションが飽和した世界は、文章や音、映像を統合するメディア機器によって構成されており、世界中の数億人もの人々がアクセス可能な、モジュール化されたグローバル・ネットワークの中で、複数のユーザー地点を通じたコミュニケーションが可能となった。
牽制民主主義とデジタル化したメディア・ネットワークは切り離せない。もしこの新たなコミュニケーション・ネットワークが突然なくなれば、牽制民主主義もおそらく存続しないだろう。(P.232)
つまり、SNSや監視カメラが中心になった社会、誰もが情報を発信し、受け取ることができる社会です。ゴシップ誌・ワイドショーが支配する社会、「無限の告白」と「あらゆる告発」が必要な社会です。このような社会を日下部吉信さんは次のように言っています。
後期近代世界はなお依然として「正しさ」という観念に呪縛された社会でありつづけているのであって、「人権」、「差別」、「ハラスメント」、「禁煙」、「コンプライアンス」、「説明責任」、「フェミニズム」などに見られる近代社会の告発的性格とヒステリー性に気づかぬ人がありましょうか。あれら非難の諸カテゴリーはいずれも社会主義イデオロギーの変容形であって、主観性の告発的性格に発しています。後期近代社会を広く蔽うあれらの諸現象にわたしは見紛いようもなく主観性の救い難い本性を見るものであります。これらの非難の諸カテゴリーで呪縛された後期近代社会は総じて主観性がヒステリー化した社会であるといって過言でないのではないでしょうか。」(『シリーズ・ギリシア哲学講義』別冊、P.27-28)
自由、平等、平和、民主主義、人権、共生、コンプライアンス、説明責任、これらの近代において過剰に礼賛されている諸原理こそ問われねばならないのであります。(同、P.48)
朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)を筆頭に、中国やロシアなどの「社会主義社会」は民主主義と対立するものだ、という言説がまことしやかに叫ばれています。それらの国に比べると日本は「自由」で「民主主義」的だ、住みやすい国だ、と思っているとすれば(私もどこかでそう思っています)、その人は日本の「支配者」の側にいるのかもしれません。
民主主義の倫理の出発点
民主主義がこうした理想を擁護するのは、すべての女性と男性が生まれながらに平等だからではなく、神や女神、現代化、歴史によって、それらの理想が正式に認定されたからでもない。それどころか、いかなる男女も、その同胞や彼らが住む生態系をしかるべく統治できるほど、完全無欠ではないということを、民主主義が示してくれている。
国、地域を問わず、普遍的価値のある英知と言えるのではないだろうか?(P.263)
本書の最後の文章です。著者の結論だと思います。
一見謙虚な文章にも読めます。私には、著者が神の立場から、神を「代弁」して言っているように聞こえます。それは確かに「倫理的」な問題です。そしてそれは「信仰」のように思います。牽制民主主義(監視カメラ)信仰です。
監視カメラのもとでの「自由」や「平等」、「民主主義」。私には、ジョージ・オーウェルの『1984年』の世界にしか思えないのです。
独裁 vs. 民主主義
これから世界はどうなる?
古代メソポタミアから現代まで
民主主義4000年の歴史を完全網羅
東京大学名誉教授 猪口孝氏推薦!
【そういえば、知らなかった】
「民主主義の国に生まれたから読みたい
世界でいちばん短い民主主義の歴史」
私たちは、民主主義の国に暮らしていながら、民主主義の歴史をあまり知らない。多くの人は、民主主義はギリシャで生まれたと考えているが、実はその起源は現在の中東・シリア、メソポタミアにある。
民主主義は、西欧社会を中心に順調に発展し、自由な普通選挙まで一直線に発展を続けてきたわけではない。ギリシャの都市国家における集会型の直接民主主義が挫折したあと、選挙民主主義の登場まで長く低迷した。
20世紀末に、民主主義国数はピークに達した。世界最大の民主主義国家は貧困と格差が支配するインドであり、イスラム教国のセネガルも民主主義国家と言っていい。
民主主義は時代とともに多様化していて、「アメリカ型の自由主義を背景としていないものは、民主主義ではない」と断じることはできない。一方で、そうした見解を背景に、民主主義は新たな独裁者や専制主義者、ポピュリストたちから挑戦を受けている。
民主主義が生まれ、成熟し、そして困難な状態に直面するまでの出来事は、予測不能で起伏に富んだ一大叙事詩とも言える物語である。その長大な歴史をたどる過程で、緩やかな変化があり、混迷の時代があり、歴史を左右する突発的な大変動が起こる。本書では、民主主義が挫折し、息絶えた過去の出来事に焦点を当てる。
「民主主義」がこれほど注目される時代になったのは、私たちが不安定な時代を生きているという感覚にさいなまれながら、民主主義が劣勢な立場に置かれていると感じているためだ。西欧の価値観に偏りすぎないニュートラルで確かな民主主義の歴史を、オーストラリア・シドニー大学教授の著者が語る本書は、現代を生きるための知的教養を求める読者にぴったりの一冊となる。
【目次】
序章 民主主義の進化を歴史から読み解く
民主主義をめぐる景色は一変している
歴史から希望を見出す
タイタニズムへの反抗
驚きと秘密
第1章 集会民主主義の時代
── メソポタミア〜ギリシャ
民主主義の起源はアテネ?
集会民主主義は東から西へ
ヤコブセンの西洋的な見方
神々の模倣
見過ごされてきた古代シリア・メソポタミア
多元主義的な性質
ビュブロスとパピルス写本
初期のギリシャの集会
集会民主主義国家群
アテネの民主主義の隆盛
宗教色の強いアテネ民主主義
性、奴隷、力
プニュクスでの忌憚のない言論(パリシア)
直接民主主義が理想か
「代表制」の欠落
デマゴーグを追放する
民主主義の敵
プラトンの見解
ヒュブリス
民主主義の瓦解
第2章 選挙民主主義の誕生
── 欧州〜大西洋へ
大西洋に広がった新しい民主主義
民主的かつ代表的な政府
選択という単語
民主主義を再定義する
代表と民主主義
代表者の役割
トマス・ペインの見解
最初の議会
代議政治
被治者の同意
選挙民主主義が生み出した概念
抵抗と勝利
進展
国家と帝国
主権を有する人民という伝説
ポピュリズム
偉大なる民主主義革命
戦争と資本主義
資本主義のもたらす強欲、格差
選挙民主主義の終焉の始まり
さまざまな選挙民主主義への攻撃
第3章 牽制民主主義の未来 ── 挑戦を受ける多様な民主主義
民主主義の蘇生
多くの犠牲の上に
暴力なき成功
ビロード革命
自由民主主義は本当に勝利したのか?
多様な民主主義の台頭
権力を監視・抑制するために
なぜ牽制民主主義なのか?
作家たち学者たちの警告
全体主義に反抗する者たちの言葉の力
牽制民主主義の進展
コミュニケーションが飽和する時代の民主主義
民主主義のグリーン化という新たな課題
困難な時代
新しい専制主義の登場
「まやかしの民主主義」の支配者
それでもなぜ民主主義なのか?
民主主義は多元主義
権力の濫用との終わりなき戦い
抑制のきかない権力を牽制する
民主主義の倫理の出発点