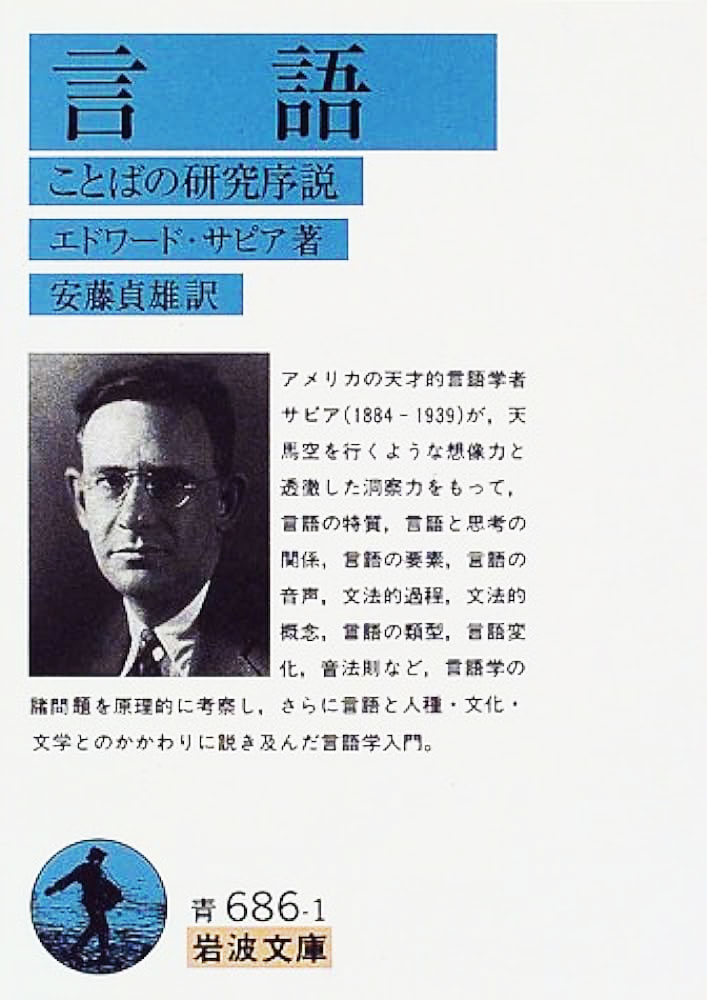
それほど難しくない
買っちゃいました。古本だけど。
原書が「https://www.gutenberg.org/ebooks/12629」で読めることをAmazonのレビューでいま知りました。日本にも「青空文庫」があるけど、Gutenberg、すごいです。頭が下がります。私も写経のかわりに参加しようかな(笑)。当然日本語ですが。
言語学の基本文献なんでしょうね。今では古いところもあるんでしょうが、いい入門書のような気がしました。「言語学概論」といったところでしょうか。内容は印欧語(特に英語)が中心です。日本語訳ですが、英語の勉強にもなるかもしれません。もちろん、サピアは語学の天才ですから、聞いたこともない言語をふくめて、様々な言語が例に挙がっています。
原書が刊行されたのが1921年(大正10年)。約100年前です。『ゆる言語学ラジオ』で本書が紹介されていて、面白そうだったので読もうと思ったのですが、『ゆる言語学ラジオ』を観ていると、この100年間に言語学も大きく発展したようです。言語学そのものがさまざまに細分化され、いろんな学者が、さまざまな考え方(学説)を発表し、自分の考えを表わすのに「新用語」を使うので、専門用語がどんどん増えていきます。私は『ゆる言語学ラジオ』も、半分は理解できていません。もともと外国語も古典も苦手だったので、言語学なんかに興味はなかったのですが。
基本文献といっても、数学を勉強するのに、ユークリッドの『原論』を読む必要はありません。ただ、数学とはなにか、言語とはなにかを知りたいのであれば、読むべきだと思います。そして、多分、数学者や言語学者になるのでなければ、数学や言語学そのものより、そのほうが大切だと思います。
サピア=ウォーフ仮説
サピアやウォーフの本を読んだことのない人でも、「サピア=ウォーフ仮説」という言葉は聞いたことがあるかもしれません。「ひとの思考様式はその言語習慣によって規定されるというもの」(P.422、解説)です。
これはとても魅力的な仮説です。世界を主導している(と言われる)印欧語(インド=ヨーロッパ語族)と、それ以外の語(たとえば日本語)とが文化に与える影響を説明しているように思います。
ただ、サピア自身はそれに無自覚だったか、自覚していたからこそ、それとは違った考え方をしているように思います。たとえば、
ある言語の形式が、国民の気質といささかでもかかわりがあることを示すのは、不可能である。(P.376)
また、わたしには、文化と言語のあいだに、真の意味で因果関係があるとは信じられない。文化は、ある社会がおこなったり、考えたりしている
ものである、と定義することができる。言語は、思考の特定の方法である。選択された経験の目録(社会がおこなった有意義な選択である文化)と、社会があらゆる経験を表現する特定の様式とのあいだに、どのような特定の因果関係が存在することが期待されるのか、理解しがたい。(P.378)
など、サピア=ウォーフ仮説を真っ向から否定しているとも取れると思いませんか。
言語化される以前のもの
ここの原文を調べてみると、
Nor can I believe that culture and language are in any true sense causally related. Culture may be defined as what a society does and thinks. Language is a particular how of thought. (S.233)
「もの」が「what」で、「方法」が「how」ですね。この訳が良いのかどうかは微妙です。
言いかえれば、製品〔思考〕は道具〔言語〕によって増えるのであり、思考は、その発生においても、日常の使用においても、ことばなしでおこなえる、などと想像することはできない。(P.32)
(原文)The product grows, in other words, with the instrument, and thought may be no more conceivable, in its genesis and daily practice, without speech(S.14)
ここでは、「製品〔思考〕」が「product」、「道具〔言語〕」が「instrument」です。
この直前に、
すべての言語の潜在的な内容は、同一である。
すなわち、経験についての直観的な科学である。二度と同一でないのは、外に現れた形式である。(P.377)(原文)The latent content of all languages is the same—the intuitive science of experience. It is the manifest form that is never twice the same,(S.233)
ここで「潜在的な内容」と言っているものが言語以前の思考や感情や経験・感覚(直観)なんだろうと思います。それが「物」つまり「実体」だと言っているのだとすれば、「もの 方法」という訳はいいのかもしれません。
アリストテレスの形而上学 言語化される以前のもの
「潜在的な内容(思考・感情・経験・直観)」が同じだから、それは英語でも日本語でも言語という道具(方法)を使って言えるのだ、とサピアは考えているようですね。「潜在的な内容」つまり「表わしたいもの」は共通で、その「表わし方」つまり「言語」が異なるということです。
言語(ことば)という表現をとる以前のもの、これはアリストテレスのいう「ヒュポケイメノン(ὐποκείμενον、下に置かれるもの、前提されるもの、第一実体、主観)」で、構造化・言語化が「カテゴレオー(κατηγορέω)」、言語化するものが「形相(εἶδος、つまりプラトンのイデア ἰδέα)」です。このヒュポケイメノンがラテン語の「subiectum」、英語の「subject」、つまり「主語・主体・主観」になっていくわけです。ですから、サピアはアリストテレス(あるいはプラトン)以降の西洋哲学(学問・科学)を忠実に継承しているのです。
さて、「潜在的な内容」「感覚・感情」は同じなのでしょうか。ここが分岐点です。サピアは人種や民族、あるいは文化について「平等主義者」であることが随所に現れています。つまり、人種や民族が違っても、「潜在的な内容」「感覚・感情・経験・直観」は同じだと考えているのです。
けれども、本能的な叫び声そのものは、全人類にとってほとんど同じである。それはちょうど、人間の骨格や神経系統が、あらゆる重要な点で、人体の「固定した」特徴、すなわち、ほんのわずかに、それも「偶発的に」、変異するにすぎない特徴であるのと同様である。(P.19)
「潜在的な内容」は「本能的な叫び声」と同様に「全人類にとってほとんど同じ」だと考えているのではないでしょうか。だからこそ、「わたしには、文化と言語のあいだに、真の意味で因果関係があるとは信じられない(前出、P.378)」と言う「信念」が生じているのだと思います。
でも、歴史や文化によって「感情」は異なります。「感覚(何を痛いと感じるか、何がどう見えるか)」すら異なるかもしれません。「何をどう感じるのか」が「言語に影響される」と考えるのが「サピア=ウォーフ仮説」ですから、この点でもサピアの考えとは異なる気がします。
私がどう感じるか、何をどう見ているのか、は、あなたと同じでしょうか。
科学・真理
科学的な真理は、非個人的である。その本質においては、科学的な真理は、それが表現されている特定の言語的媒体によって染めあげられることはない。(P.385)
A scientific truth is impersonal, in its essence it is untinctured by the particular linguistic medium in which it finds expression. (S.238)
つまり、「科学的な真理」は「客観的存在(実在)」だと言うのです。これを疑う日本人は少ないでしょう。
「客観 object」はラテン語の「obiectum」から来ています。このラテン語はギリシア語の「ἀντικείμενον」の訳にも使われたものですが、この語をアリストテレスは『霊魂論』で、感覚に対する感覚対象(外的事物)、思考に対する思考されるもの、という意味で使っています。思考や感覚は「個人的」ですが、その対象は「非個人的」です。客観的存在です。ここでもサピアは西洋哲学(アリストテレス)に忠実だと思います。
事実、科学的な真理の理解は、それ自体が言語的過程なのだ。思考とは、その外部の衣装をはぎ取った言語にほかならないからである。(P.385)
(原文)Indeed the apprehension of the scientific truth is itself a linguistic process, for thought is
nothing but language denuded of its outward garb. (S.239)科学的表現の適切な媒体は、それゆえ、記号代数と定義してもよいような一般化された言語であって、あらゆる既知の言語は記号代数の翻訳である。科学的な文献が過不足なく翻訳できるのは、もとの科学的表現がそれ自体、翻訳であるからだ。(P.386)
(原文)The proper medium of scientific expression is therefore a generalized language that may be defined as a symbolic algebra of which all known languages are translations. One can adequately translate scientific literature because the original scientific expression is itself a translation.(同前)
近代西欧的な「科学(知識)」「真理」観だと思います。思考=言語=科学=記号。科学は言語に合わせて作られるのです。そういう意味では、サピア=ウォーフ仮説に近いと言えるかもしれません。ただし、思考は言語と一致していなければならないし、それは科学(対象・客観)と一致していなければなりませんが。
進化論・定向進化
言語はかならず変化します。そして、その変化には「方向性」があります。それをサピアは「偏流」と呼びます。
個人的変異そのものは、あてどもなく上げ潮につれて前後にゆらぐ海の波のように、でたらめな現象なのである。
言語の偏流には、方向性がある。言いかえれば、一定の方向に動く個人的変異だけが偏流を具現化する、あるいは、運んでゆくのだ。(P.266-267)
(原文)They themselves are random phenomena, like the waves of the sea, moving backward and forward in purposeless flux. The linguistic drift has direction. In other words, only those individual variations embody it or carry it which move in a certain direction, just as only certain wave movements in the bay outline the tide. (S.166)
同じような考え方は主流派(ダーウィン)の進化論にあります。「突然変異」というランダム(偶然、でたらめ)な現象があって、それが進化の原動力となるということです。主流派進化論では、「適者生存」や「自然選択」という要因が絡んでくるのですが、それをサピアは「偏流」と表現します。「自然選択」は外的なものですが、「偏流」は言語に内在的なものです。サピアは「偏流」を様々な例で説明しているのですが、それはぜひ本書で読んでください(多分それがサピアの言語学の中心課題です)。
いずれにしても、「個(個人)」がでたらめな変異(変化)をすることで「全体」が変わると考えているわけです。「偏流に方向性がある」というのは「定向進化」的ですが、あくまでも変化するのは「個」です。今西錦司のいう「個人主義」です。「主体 subject」があって(を前提として)、全体はその集合です。
それが明確に現れているのは次の文章です。
かりに、文芸作家が一人も現れないとしても、それは本来、その言語が道具として弱すぎるためではなく、真に個性的な言語表現を求めるような人物が育つためには、その民族の文化がまだ熟していないためである。(P.399)
(原文)If no literary artist appears, it is not essentially because the language is too weak an instrument, it is because the culture of the people is not favorable to the growth of such personality as seeks a truly individual verbal expression.(S.247)
どの言語も「強弱の差」があるわけではありません。ただ、その文化が十分に「熟していない」だけです。
世界のさまざまな地方で、それぞれ異なる歴史的な先例から、類似した社会的・経済的・宗教的な制度が発達してきているのとまったく同様に、諸言語も、異なる道程をたどりながらも、結果的には類似した形式に収束する傾向があったのだ。
のみならず、言語の歴史的研究が疑う余地のないまでに立証したように、言語は徐々に変化するばかりでなく、整合的に変化するのであり、無意識的にある類型から別の類型に移っていく。しかも、類似の傾向は、地球上の遠く隔たった地方でも観察されるのである。(P.209-210)
(原文)Such a standpoint expresses only a half truth. Just as similar social, economic, and religious institutions have grown up in different parts of the world from distinct historical antecedents, so also languages, traveling along different roads, have tended to converge toward similar forms. Moreover, the historical study of language has proven to us beyond all doubt that a language changes not only gradually but consistently, that it moves unconsciously from one type towards another, and that analogous trends are observable in remote quarters of the globe.(S.128-129)
生物の化石にあたるのが言語史研究です。どの言語も変化し続けます。そしてそれには方向性があり、その頂点にあるのが現在の諸言語です。そしてもっとも「熟している」のが文学をもち、個性的表現ができる言語だというのです。
クローチェの用語を使用すれば、芸術家の「直観」は、一般化された人間の経験
思考と感情から直接に形づくられるのであって、芸術家自身の個々の体験は、そこから高度に個人的な選択をおこなったものにほかならない。(P.386)(原文)The artist’s “intuition,” to use Croce’s term, is immediately fashioned out of a generalized human experience—thought and feeling—of which his own individual experience is a highly personalized selection.(S.239)
たとえば、ハイネの場合、読者は、まるで宇宙がドイツ語を話しているような錯覚に陥る。素材が「消える」のだ。(P.388)
With Heine, for instance, one is under the illusion that the universe speaks German. The material “disappears.” (S.240)
最高の芸術(文学)は、個人の体験が「一般化された人間の経験」となるものであって、それは個々の言語を越え、「宇宙」と一体化するものなのです。壮大な話です。
言語の定義
本書は「ことばの研究序説 An Introduction to the Study of Speech」ですから、「ことばとはなにか」についてまとめておきます。原文を探すのは面倒なので省略です。(笑)
言語とは、意図的に産出した記号の体系によって、思想、感情、または欲望を伝達するための、純粋に人間的で非本能的な方法である。(P.21)
正確に言えば、音声器官など存在しない。言語音を産出するのに、たまたま役立つ器官が存在するだけなのだ。(P.22)
すなわち、どんな器官でも、ひとたび存在するようになり、自発的な制御に従うかぎり、人間によって二次的な目的に利用されうる、ということだ。(P.23)
その音がごく基本的な言語的意義をさえ担うためには、まず、なにか一つ(または一群)の経験の要素、たとえば、一つまたは一群の視覚イメージなり関係の感情なりとさらに連合しなければならない。この経験の「要素」こそ、言語単位の内容、すなわち「意味」である。(P.24)
われわれの言語研究は、具体的なメカニズムの発生や作用の研究ではない。むしろ、言語と称されている、恣意的な記号体系の機能と形式についての探求なのだ。(P.26)
これらの(ことによると、またほかの)連合した経験が、自動的に家のイメージと連合したときはじめて、記号や語、すなわち言語の要素としての性質を帯びはじめるのである。(P.27)
連合は、純粋に記号的なものでなければならない。言いかえれば、家という語が家のイメージを表示し、家というタグを付けなければならない。家という語は、家を指すことが必要であるか、便利である場合は、つねにそれを指すことができるタグの役割をする以外の意義をもってはならない。(同)
事物や関係についてのすべての経験を表わす記号目録を作成できるようになるためには、まずその前に、われわれの経験世界が大幅に単純化され、一般化されなければならない。思想を伝えることができるためには、その前に、この目録が絶対に必要である。(P.28)
伝達されるためには、言語社会によって同一物として黙認される類を指示する必要がある。(同)
言いかえれば、「家」という言語要素は、何よりもまず、記号である。それも単一の知覚の記号でも、特定の事物の観念の記号でさえなく、「概念」の記号である。別な言い方をすれば、幾千もの異なる経験を包含し、なおその上に、幾千もの経験を進んで取り入れようとする、思考の便利なカプセルに対する記号なのだ。(P.29)
雰囲気を感じてもらえたでしょうか。興味が湧いた人は本書を読んでください。
外国語の習得
最後に、外国語の勉強についてサピアの考えを取り上げます。外国語が苦手な私には嬉しいことも書いてあります。
人間の耳は、音声機構の働きの微妙な差異に、それほど敏感に反応するのだ。」(P.79)
日本語でも、語彙ではなく文の一部のイントネーションだけで「方言」と「標準語(共通語)」との違いがわかります。「なまってるな」と感じるのです。
つまり、われわれの耳のほうは、ことばの音に敏感に反応するに対して、音声器官の筋肉のほうは、早くも幼年期に母語の伝統的な音を発音するのに必要な特定の調節および調節方法にのみ、もっぱら慣れてしまっている、ということである。他の調節〔方法〕はすべて(あるいはほとんどすべて)、不慣れのためか、徐々に排除されたためか、ともかく永久に抑圧されてしまっているわけだ。(P.80)
この調音上のこわばりは、大いに必要な記号体系を容易にマスターするために、われわれが払わなければならなかった代価である。(P.80)
外国語の発音が苦手なのは、私だけじゃなく(日本人だけじゃなく)どの言語を母語にするひとでも「当然」のことのようです。だから「発音が悪い」のはあまり気にしないようにしましょう。
ことばのすべての個人的色彩
個性的な強調、速度、個性的な抑揚、個性的な声の高低は、非言語的な事実である。ちょうど、欲望や感情の偶発的な表出が、大部分は言語的表現と無縁であるようなものだ。ことばは、文化のすべての要素がそうであるように、概念的な選択、すなわち、本能的な行動のでたらめさの抑制を要求する。文化の「理念」が理念として実際に実現することがない理念の担い手がなにしろ本能的に行動する生物なのでのは、文化のどの面にもすべてあてはまることである。(P.81)
発音が悪いのは「個性」ということにしておきましょう。
いまファーブルの『昆虫記』を読み始めています。ファーブルは昆虫の行動を「本能」だと書いています。そして「生存競争」や「適者生存」などのダーウィン的進化論をめちゃくちゃに貶しているのが面白い。はたして本能は「でたらめ」で「抑制」しなければならないものなのでしょうか。それが「文化」なのでしょうか。その文化は「実際に実現することがない理念」をもち続けなければならないものなのでしょうか。
私はそれが、個性や主体性に要因があるように思えます。そしてそれはアリストテレス(そしてプラトン)の読み違いに端を発しているように思えます。まあ、プラトンは少ししか読んでいないし、アリストテレスにいたっては一冊も読んだことのない私が言うのもなんですが。(汗)(汗)(汗)
[著者等]
エドワード・サピア(Edward Sapir [səˈpɪər], 1884年1月26日 - 1939年2月4日)
アメリカの人類学者、言語学者。アメリカの構造言語学を主導し、「サピア=ウォーフの仮説」と呼ばれるようになった学説を提唱したことで知られる。
安藤貞雄
広島大学名誉教授。文学博士(名古屋大学)。関西大学専門部中退(1944年)。文部省英語教員検定試験合格(49年)。ロンドン大学留学(73年)。市河賞(76年)。英語語法文法学会賞(06年)。


