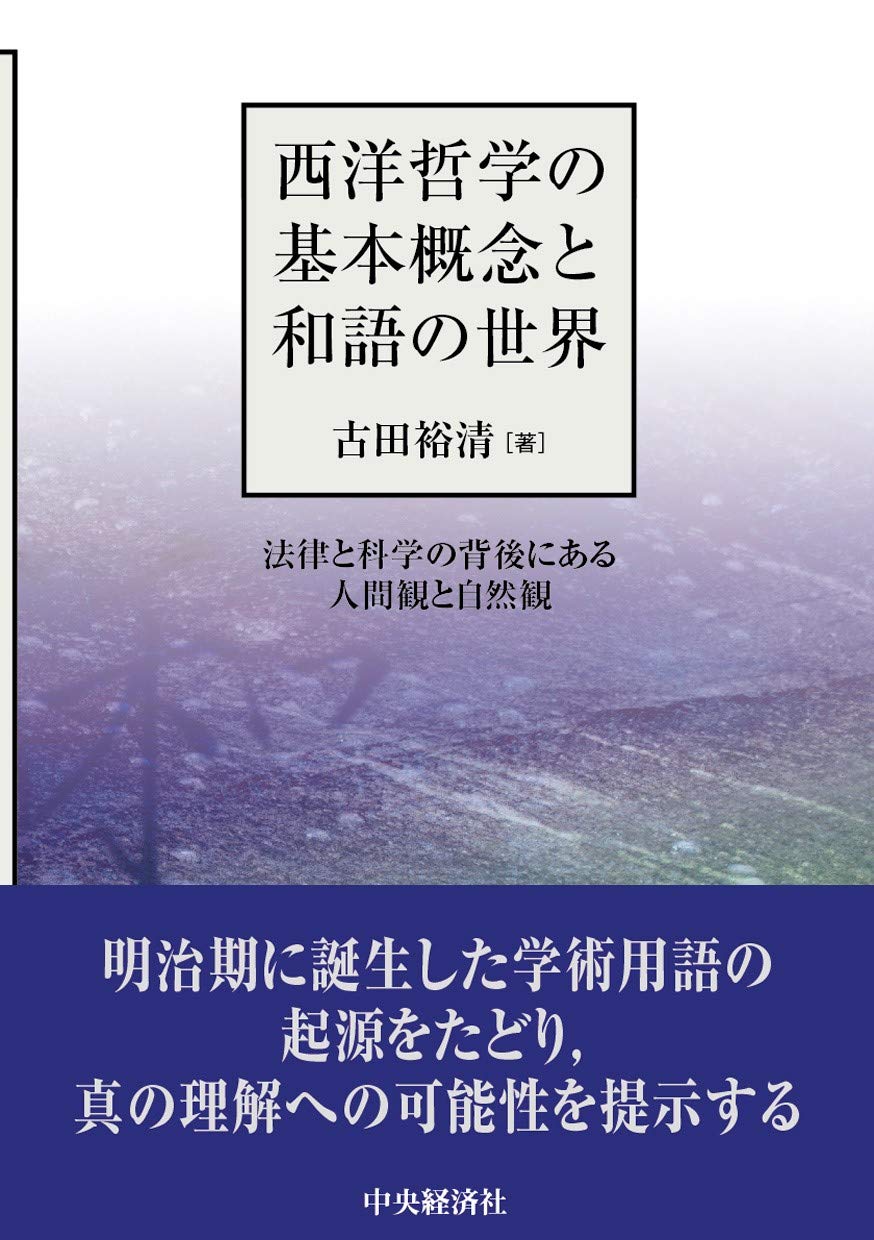まえがき
「欧州由来の学術用語の源泉は大きく見て三つある。ギリシア自然哲学、ローマ法、そしてキリスト教である。」(P.1)
「欧州哲学が他の文化圏における知的営みと違うのは、それが古代ギリシア以来、万学を生み出す母胎となり、同時に日常生活の秩序を研磨する力ともなってきたことだろう。」(P.1)
2020年8月 著者
第1章 主観と客観
西周らの翻訳の試み
(ヘイブン)「心の内部へと向かう心の能力が subjective、外的世界へと向かう能力が objective、と呼ばれた。」(P.2)
subject の語源と来歴 ギリシア・ローマ
subicio=sub「下に」icio「投げつける」。眼下に投げつける、想起させる、自分の下に投げつける、服従させる、目印の下に投げつける、項目別に分類する、本物のかわりに偽物を相手の眼前に投げつける、偽物とすり替える
subiectum=(物理的に)下に投げつけられた、目の前に投げ出された、服従させられた、目で見える所に置かれた、主題となる
アリストテレス ὑποκείμενον
ὑποόκειμαι ὑπό 「下に」κεῖμαι「横たわる」「置かれている」。身近にある、(規則などが)設定されている、前提されている、考慮されている、(支配者に)従属している、担保に取られている。
κεῖμαι <-> τίθημι「置く」「横たえる」 lie <-> lay.
(ベッカーが示すアリストテレスの用法)「一つはいわゆる質料形相説における質料、二つ目は第一実体(個物)、三つ目は述語に対する主語。」(P.3)
「こうした構造化に先立つ所与、という抽象的語彙はアリストテレスの時代、存在しなかった。彼は表現に事欠き、苦し紛れの比喩としてヒュポケイメノン(下に横たわるもの、前提されるもの)という手近な語彙に頼った。(LF)他方、彼は構造化・言語化を指して動詞 κατηγορέω 〔カテゴレオー〕を使った。こちらは前置詞 κατά〔カタ〕(英 toward)と動詞 άγορεύω 〔アゴレウオー〕(アゴラで発言する)の合成型、原意は「アゴラに向かって発言する」。」(P.4)
「すなわち、目の前のリンゴやソクラテスなどは、ヒュポケイメノンの述語とはならず、自らがヒュポケイメノンとなる。」(P.4)
「主語となるが述語にはならない個物は第一実体、個物に宿る「かたち」は第二実体(形相すなわち普遍、第2章及び第10章参照)と呼ばれる。個物には第ニ実体を含む十のカテゴリア全てが属性として宿り得る。」(P.5)
「異常をまとめると、第一の意味は「構造化・言語化以降」に対する「構造化・言語化以前」。第二・第三の意味は構造化・言語化以降における個物、あるいは主語。どの文脈でも、ヒュポケイメノンは我々(主)が世界(客)を認識する際にその下敷きとされるもの。」(P.5)
「自然言語は元来、生活に密着した具体的な語彙しか持たない。抽象的な事柄は、生活に密着した語彙を転用して比喩的に表現するしかない。」(P.5)
(アプレイウス123年頃 - ?)「構造化以前の質量は、形相(かたち)に従属することで構造化される。個物(主語)も普遍(述語)が宿るための従属的土台。」(P.6)
近世以降のsubject
(ホッブス1588年4月5日 - 1679年12月4日)「株主が契約により事業の全権を取締役に委任するのと同様に、人々は弱肉強食の自然状態から脱するために社会契約を通して統治権力を国王に委ねる。これにより支配者(英 sovereign)と臣下(subject)が分離する。後者は subiectum の英語形で「社会契約に従属する人」が原意。」(P.6)
subject、臣下、契約主体
(ライプニッツ1646年7月1日(グレゴリオ暦)/6月21日(ユリウス暦) - 1716年11月14日)「カエサルという主語には、カエサルに述語づけられる行為・属性・関係のすべてが内属する。つまり、カエサルとはこれら述語の束である。subiectum とは、言語的には主語、実在的には個物(主体)。カエサル、プルータス、そして我々は一人一人、それぞれ異なる物理的身体をもち、相互に独立した個人である。各々がカプセルのごとく外界や他者から閉ざされ、各々の視点から物理的世界を眺めて暮らしている。この世界は、感覚を通してそれぞれのカプセル内部に投影された鏡像のようなもの。逆に他者の目から見れば、我々はその他者のカプセル内に投影された物理的世界に(身体を伴って)出現する事物の一つにすぎないはず。こうして我々は相互にお互いを自分の中に映し合って生きている。人間のみならず、サルや石ころなど、この世のすべてが同様の subiectum として存在している。人間のように明晰判明な世界認識はできずとも、それぞれが各々の仕方で世界を映し出している。我々はカプセルの外へは出られない。カプセルにはそもそも「外」が存在しない。ならば、我々が同じ一つの世界に生きている、皆が同じ一つの世界を映し合っている、となぜ分かるのか。人間相互の円滑なやり取りがなぜ可能となっているのか。それは神の予定調和による〔いわゆる弁神論)。晩年、ライプニッツはこうした個物(個体)を「モナド(単子)」と呼んだ(「モナドロジー」)。」(P.7)
(カント1724年4月22日 - 1804年2月12日)「こうした知識を可能にしているアプリオリな制約が、カプセルそのもの(すなわち我々の各自)に内在するはずだ。この制約は科学的認識を可能にする基盤、つまり認識の底に横たわる土台(ヒュポケイメノン)、という意味でも subiectum (独 Subjekt)と形容できる。その詳細な構造分析を行ったのが『純粋理性批判』。カントの Subjekt にはホッブス的な契約主体、ライプニッツ的な個体・主語(モナド)、アリストテレス的な言語化・構造化以前の前提・土台(ヒュポケイメノン)という三(FF)つの含意が存在する。ただし、アリストテレスのヒュポケイメノンは、言語化・構造化以前の所与世界そのもの(質料)だった。カントにとっての Subjekt は言語化・構造化が可能となるための制約(人間自身に内在)、すなわち近世的な主観性。」(P.7-8)
object の源流と来歴
obicio ob=面前にむかって、遮るように。誰かを遮るようにその面前へと投げつける、手渡しして押し付ける、(動物に)餌をやる、目の前に(注意を惹くよう)置く、(危険を)もたらす、(障害物をつかって)妨害する。
obiectum 原意は、眼前に投げつけられた、(価値的な色彩を帯びて)障害物、非難、注意の矛先、念頭にあるもの、注意力が向かう先、目的物
ἀντικείμενον κεῖμαι ἀντί=over, against 原義は、向こう側に置かれているもの、対置されているもの。
「多義的で、アリストテレスはその意味を関係、反対、欠如、否定・肯定の四つに区別している(『範疇論』10章)。」(P.9)
(キケロ 紀元前106年1月3日 - 紀元前43年12月7日)「キケロは obiectum を多くの場合、「我々の眼前に現れて邪魔してくる障害物」(外的事物)の意で用いるのだが、このように内的表象像を指す用例も混在する。(LF)中世スコラ哲学になると、obiectum はもっぱらこの内的感覚像を指す語に転化する(外的事物を指す用法は消失)。」(P.9)
(カント)「彼にとって Subjekt (主観)は世界の認識を可能としている先験的制約(我々自身に備わる)の総称だった。鏡像世界の realitas obiextiva はこの制約下で可能となる。客観を主観に内在させるこの主客対立図式は超越論(先験)的観念論と称される。」(P.10)
カント以降の主客対立図式
(ヘーゲル)「主観も幼少時から共同体において他者から承認され、自己意識を植えつけられることにより、初めて成立する。主観と客観を共に成立させる条件となる共同体的な知をヘーゲルは「絶対精神」「絶対者」などと呼ぶ。「絶対」とは厳しいが、言語は独 absolut。祖型は羅 absolutum、すなわち「解き放たれた」。つまり、ヘーゲルの「絶対」とは「一個人につきまとう限界や制約を免れた」という意味。」(P.11)
「こうして、「subjective=限界ある一個人に関する」「objective=あらゆる個人にアクセス可能な外界事物に関する」という19世紀中葉的な主客対立図式が語圏を超えて成立、自然・人文・社会科学を問わず汎用されることになる。」(P.12)__西欧思想を翻訳語で説明するということは?
「主観」「客観」再訪
(西周、ヘイヴン)「すなわち、人間が主となり、外的事物が客となって向き合う様子を、傍観者が脇から仔細に観察し、主の側で見えてくる面(すなわち主の能力)がsubjective、客の側で見えてくる側面(すなわち客に属する諸特徴)がobjective。こうした趣旨で前者が「主観」、後者が「客(FF)観」と訳された。」(P.14-15)
「他方、漢語は日本への導入以来、非日常的な知識の象徴として「よそ行きの言葉」「たてまえの言葉」と見なされ、本音を語る大和言葉(和語)とは別空間に置かれてきた。初見の一般市民には意味不明ですらある。これに変幻自在性が加わると、一般市民はますます訳が分からなくなる。これが日本で哲学用語の定着が妨げられる一因である。」(P.14)
「実践哲学や法律論におけるSubjekt(行為主体)はホッブスのsubject(契約主体)同様、「観る主(あるじ)」とは訳せない。それゆえ西の時代以降、「主体」「客体」という別の訳語も現れた。」(P.15)
「明治後期からは「対象」という訳語も充てられたが、この訳語でもカントの意図は十分に汲み取れない。」(P.15)
「西は日本語における漢語の「たてまえ」的な位置づけを保持したまま、漢語を訳語にえらんだ。結果的に、哲学用語はたてまえの世界のものとして神棚に祭り上げられ、漢語独特の変幻自在性も手伝って、一般市民を煙に巻く代物と化した。」(P.16)
「これを翻訳借用で和語に再現し、生活で汎用する習慣ができていたら、本音とたてまえの区別自体が破棄され、その後の日本文化は一変していたのかもしれない。実際には、それができないほど日本文化は江戸期までに成熟しきっていた。」(P.16)
哲学と翻訳語
「哲学的問いかけは欧州語を母国語とする人々がこれら用語を繰り返し使うことで自らの歴史的アイデンティティを確認する作業でもある。」(P.17)
「むしろ、西らの訳語創出は、哲学すること自体を日本の日常に移植するのに失敗した。」(P.17)__漢文を読めることは、英語を話せることのようなステータスを維持している。私が哲学用語や英単語を用いるのは、龍之介のドイツ語と同じ。
「哲学(理念信仰)は欧州の土着的な精神活動である、これを和語で再現できたとしても、それが日本に定着する可能性は低い。無理に定着させる必要もない。だが、欧州文化圏が析出させた現代の科学技術や法律を実利的に生活上取り入れてきている我々にとって、その土台となった欧州哲学の基本概念が彼らの生活からどのように湧き上がり、科学や法律の発展に寄与してきたかを適切に理解することは、我々が科学技術や法律を今後どのように使いこなしていくべきかを考える上でも、重要である。本書の目的はその理解を増進させることにある。」(P.17)
第2章 観念と実在
「観念」英 idea、「実在」英 reality
「前者はプラトンに由来、後者は中世スコラ用語。」(P.19)
プラトンのイデア
ἰδέα ὁράω(みる、眼中に入れる)のアオリスト不定詞形 ἰδέιν から派生。
「アリオストは完了でも未完了でもない動作行為そのものを指す動詞の形。ὁράω は現在形で未完了(「見ている」見続け(FF)ている」「見える」「見えている」、英 see に相当)。」(P.19-20)
「他方、アリオストは「見える」(未完了)でなく「見てしまった」(完了)でもなく、そもそも見るということ。ἰδέα はその動作行為の対象(見えたもの)。プラトンはアオリスト1人称単数形 εἶδον 〔エイドン〕からできた名詞 εἶδος 〔エイドス〕も同義で用いる。」(P.20)
「実は、個別と普遍は複数形と定冠詞という文法構造に深く関係している。印欧語にもともと複数形はあったが、定冠詞はなかった。そのなかで、おそらくフェニキア語などセム語系の影響を受けて、初めて定冠詞を持つに至ったのがホメロス時代のギリシア語。「それ」を意味する指示詞が定冠詞に転用され、文法構造として定着した(不定冠詞は数詞「一つ」が転用されたもので、欧州語では比較的遅く中世に登場)。プラトンの時代、定冠詞には特定個体を指示する用法(英語なら the cat で「その特定の猫」)以外に、総称的用法(猫一般)も生まれていた。複数(FF)形と定冠詞を文法的な土台として、プラトンは個別とイデアの対比を顕在化させた。」(P.20-21)
「だが、プラトンはこの「そもそも論」を押し通し、勇気や徳などの定義を求めた。(LF)彼の問いかけは古代ギリシアの一般市民の琴線に触れた。日常使っている定冠詞に沿った問いかけだから、一般人の生活感覚でもついていけた。この問いはプラトンのオリジナルではなく、ソクラテスから継承したもの。ソクラテスはこの問を巷で人々に投げかけ、彼らの答えを吟味し、論駁した。しかし、自ら答えを示すことはなかった。答えられないからである。逆に「勇気とは何か、徳とは何か。誰も答えられないだろう。答えられないということを私は知っている。」(P.21)
「煙に巻くのではなく、答えを示さねば市民に信用されない。プラトンはソクラテスの問いに「それはイデアだ」と答えて示した。」(P.21)
「古代ギリシアにおける普遍への問いは視覚に導かれていた。欧州哲学がこの視覚限定を脱して自然に関する普遍的構造認識(科学的世界観)へと歩みを進めるのは近世以降。」(P.21、注)
魂の輪廻転生(これはプラトンがソクラテスと共にピュ(FF)タゴラス派から借用した世界観)(P.21-22)
「では、イデアとは結局、何なのか。プラトンは最後まで答えられない。表現に窮して比喩的にしか語れないのは、第1章のヒュポケイメノンなどと同じ。」(P.22)
アリストテレスのエイドス(形相)
「アリストテレスはイデアを師の専門用語、エイドスは自分の哲学用語として使い分けた。」(P.22)
「アリストテレスはイデアをこうした文脈で捉え直し、エイドスあるいは μορφῆ 〔モルペー〕と呼んだ。後者は「かたち」の意、とくに彫刻像について使われた古代ギリシアの日常語彙。プラトンもイデアを指(FF)して使った。(LF)アリストテレスによれば、自然界における動き変化の原因はエイドスに留まらない。たとえば彫刻家は像の形(エイドス)を頭に思い描き、大理石を彫り込んで像を制作する。大理石が像へと変化するプロセスには、原因が次の四つの文脈で介在する。まず、彫刻家が思い描く像の形が、像の制作を引き起こす原因となる(形相因)。次に、像を彫り込む彫刻師自身が、像の制作の原因である(始原因)。また、原材料となる大理石も、像の制作には不可欠な原因である(質料因)。更に制作が目指すべき終着点、すなわち像の完成した姿も、像の制作プロセスを牽引する原因となる(目的因)。」(P.22-23)
「魂は形相を感覚から引き離して記憶・想起する能力、想起された形相に依拠して思考する能力、更に形相を宿した個物(前述の建築物など)を自ら作り出す能力も持つ(『霊魂論』、後段第9章参照).」(P.23)
species(スペキエス)と forma(フォルマ)
「プラトンの ἰδέα をキケロは species、forma、あるいは figura と羅訳した。翻字した idea という語形をつかう箇所もある。species は動詞 specio(「見ている」「見えている」)の名詞形、「見ていること」「見えているもの」が原意で、「(特定の)外見」「姿かたち」「見世物」「上っ面」「空想物」「言い訳」「(ものが配列された)様子」と意味が広がるラテン語の日常語彙。ローマ法では特定のものを広く指した(個別、種別など)。ラテン語はギリシア語と違いアオリストを持たず、完了と未完了しかない。動詞 specio は未完了形。species には「今見えている特定のもの」という連想が働き、ἰδεά にある「真相を観た」という語感がない。逆に真実性のなさが含意される。これはギリシア語なら別の語( φἀντασμα〔パンタスマ〕、第10章参照)に伴う含意。」(P.24)
「forma の原意は「かたち」「外見」。」(P.24)
「figura は動詞 fingo (粘土をこねて形を作る)から派生した名詞、「(具体的な)形」「形作られた粘土像」が原意。」(P.24)
「聖書によれば、神は自らに似せて人間を創造した。父・子・精霊という神の三つの位格は、知性・記憶・意志という人間の3つの能力に対応する(『三位一体論』)。」(P.25)
「その結果、プラトンにおけるイデアと個物の対立はキリスト教的な三重の対立(神と被造物の対立、神と人間の対立、人間精神の内と外の対立)へと複相化される。」(P.26)
デカルトの観念
「デカルトの idea は、スピノザに代表される欧州大陸と、ロックに代表される英国の系譜に分岐して継受される。二つの系譜には根本的な違いがある。(LF)オランダのユダヤ人スピノザは idea(観念)を心の中の感覚像と捉えるのに反対する(『エチカ』)。」(P.28)
reality の源流と来歴
「reality (「実在」)の鼠径は羅 realitas、中世スコラ哲学者ドゥンス・スコトゥスが res (「もの」)から作った新造語。res は生活上の必要に迫られて相互に区別・知解されるもの一般を指す。動詞形は reor (解する)、別の名詞形に ratio(理性)がある。民法総則の「人(persona)」と「物(res)」はローマ法以来の対概念。」(P.30)
「神による創造は人間の知解能力と無関係であり、被造物は人間の知解能力とは独立に存在する。(LF)この教義をトマスも継承する。彼はアリストテレスに従い、神が個々の被造物を創造する際の決め手(個体化の原理)は質料だと考えた。すなわち、神は類に種差を加えて種(forma、形相)を創造し、最後に形相が質料を取り込んで個体化が起きる。」(P.30)
(スコトゥス)「つまり、被造物は共通本性、「これ」、質料の三者からなる合成対(天使の場合、質料はない)。共通本性と、「これ」、は質料とは無関係で、被造物(res)の形相に備わる二側面。この(FF)二側面を指してストトゥスは realitas (もの性)と呼んだ。つまり、被造物は共通本性と「これ」という二つの realitas を持つことになる。(LF)キリスト教義に従うと、この二つの realitas は人間の ratio から独立した被造物(res、ens)の形相的特質であるということになる。」(P.30-31)__「これ」=指示代名詞が独立して、一般化したもの。フロイトの「エス」。
(リード)「大聖堂は観念ではなく、観念の object(対象)である。objective reality を持つのは観念でなく、大聖堂そのもの。この新語法は、ロック的な観念の理解(心の内部にある心理的単位)に基づき、objective reality の在処を観念から外的事物へと転換させたもの。しかも、知識は観念でなく言語により獲得される、というホッブズ説(後段参照)の影響下にある。」(P.31-32)
「その idea もどきの曖昧さゆえ、米国人クワインは「命題」という言葉そのものに反対した。音声や活字として客観的に確定できる「文( sentence )」で十分、と言うのである。クワインが考える objective reality は、各個人が受ける感覚刺激を通してその真理性が社会的に保証される文の総体によって提示される。クォークなど数理的に構築された科学的実在も、こうした文で記述(FF)される限りの存在と解される。クワインはリードの常識実在論を科学的に洗練させた。彼にとっての reality は各人が受ける感覚刺激に合わせて改変の余地を永遠にのこす一元論体系であり、社会的分業により維持される。」(P.32-33)
「なお、res の日本語訳である「もの」は、元来、平穏無風の状態を打ち破って登場する存在一般、周囲の注意を惹く新奇性を備えた存在一般のこと(「ものものしい」という表現が象徴的)。」(P.33)
観念と実在の対立
「イデア(普遍)と個物の対立ならプラトンの時代からあった。プラトンにおけるこの対立はキリスト教的な内外対立とは異なり、根拠(イデア)と根拠づけられるもの(個物)との対立。」(P.33)
「キリスト教義はプラトン的なイデア・個物の対立を神・被造物の対立に読み替え、他方で被造物の世界(外的個物)と人間精神(概念把握)との内外対立を表面化させた。」(P.33)
「原子論者は人間精神を物質へ還元しようとする「唯物論者( matérialiste )」、デカルト系の人々は「観念論者( idéakuste )、と形容したのはライプニッツ(1702年のベール宛書簡)。」(P.34)
「だが、そもそも世界を経験科学的に把握しようとすること自体、そして正義を希求する法の支配を進めようとすること自体、実はプラトンのイデア論に動機づけられた営みである。」(P.35)
「観念」と「実在」その後
「「観」は見る、「念」は思う。仏教語ではなく漢語としての「観念」は「見て思う」という人間の所為一般を指す。これが使われ得る文脈は idea と比べてより広く、辺縁も不明確。こうした曖昧さは訳語としての「観念」が日本語話者の生活中に定着しないことと表裏一体。」(P.35)
「日本人の日常空間はこうした翻訳語彙を必要としていないのだろう。」(P.36)
「他方、「観念」「実在」という翻訳語は日本人にとってたてまえの領域に属する神棚の上の語彙であり、日常生活(本音の世界)に響いてこない。」(P.36)
「ゲルマン語によるラテン語の翻訳借用は古代(FF)末期という時代に発生し、両者が同じ印欧語であることも手伝って成功したが、日本語は印欧語と系統が異なり、明治初期には同様の翻訳借用を行うことが不可能なまでに成熟を遂げた後だった。(LF)日本語に定冠詞や複数形がないことも ἰδέα や εἶδος の翻訳導入の困難さを増幅する。上述の通り、プラトンによるイデアへの問いはギリシア語の文法構造と表裏一体の問題提起である。それゆえ、子供でも身近に感じられた。複数形はあるが冠詞を持たないラテン語(古代ローマ)はこの問いの咀嚼に時間を要したが、欧州中西部の印欧語はキリスト教の聖書(元来、古代ギリシア語で編集された)を翻訳する過程で中世には定冠詞を備えるに至る(これを通してラテン語は仏語やイタリア語などへと分岐していった)。こうして、プラトン的な問いが生活レベルで再現可能となった。」(P.36-37)
「普遍と個別の区別はギリシア・欧州に土着的な世界理解の枠組み。科学や法律など有益な知識の枠組みとして極めて利用価値が高いのは確かだが、唯一無二の真実性を主張できるものではない。身近な和語の世界は今もこの枠組みを寄せつけない仕方で維持されている。」(P.37)
第3章 帰納と演繹
「前者は英 induction 、後者は deduction の訳語。」(P.39)
アリストテレスのエパゴーゲー
「英 induction の祖語は羅 inductio、更に遡ると希 ἐπαγογή 〔エパゴーゲー〕。動詞は ἐπάγω、前置詞 ἐπί (英 upon)と ἄγω(導く、英 lead に相当)の複合語。「上へ導く」が原意の日常語で、「戦へと軍隊を導く」「犬をけしかけて獲物へと仕向ける」「歩くペースを上げる」「相手を説き伏せて考えを改めさせる」「捕虜を捉えて連行する」(FF)「食料を補給する」など雑多な文脈で用いられる(英語の lead on に類似、ただし意味の広がりは異なる)。ἄγω はたの前置詞とも結びつき多彩な複合語を作る。たとえば κατά 〔カタ〕(下へ、向かって)を前置した κατάγω 〔カタゴー〕(「下へ導く」が原意)は「引きずり下ろす」「川を下る」「船から陸地へと降り立つ」「家に帰す」「減らす」など、σύν 〔スュン〕(一緒に〕を前置した συνάγω 〔スュナゴー〕(「共に導く」)は「一緒になる」「くっつける」「結論づける」など、と意味が広がる(ユダヤ教会を意味するシナゴーグはこの語が由来)。ちょうど英語の lead から lead off や lead with などが作られるのと同じ。(LF)前置詞プラス ἄγω ( ἀγωγέ )はどれも古代ギリシアの頻用表現。その中で、アリストテレスはエパゴーゲーを次の意味の専門用語に転用した。すなわち、個物についての言明(たとえば「アリストテレスはいつか死ぬ」「プラトンはいつか死ぬ」など)から、普遍的な言明(「人間は皆いつか死ぬ」)への移行である。この移行は今では枚挙的帰納(英 enumerative induction )、すなわち個別事例を根拠に普遍的一般的結論を導出するステップ、と解されている。」(P.39-40)
「だが、アリストテレスの考えたエパゴーゲーは第一義的には推測ではない。彼はこの語の第一義的意味と派生的意味を区別する。前者におけるエパゴーゲーはそもそも結論導出ですらない(後者については後段参照)。それはアリストテレスがプラトンと共有するイデア論の文脈にある。人間は身の回りの個別的事物と関わる際、これら事物に宿るイデア(形相)を直感的に把握済みである、と両者は考える。第一義的なエパゴーゲーとは、この文脈における個別的事物からイデア(形相)への視点転換である。」(P.40)
「彼にとってイデアは個別的事物から離れて天上界に自存するものではない。むしろ地上で個別的事物に寄り添い、個別的事物とともにある限りのもの(形相と言い換えられた)。だが、彼は形相を個別的事物の根拠と見なす点で師プラトンを継承する。」(P.40)
「この目線転換は、すでに把握済みの形相に目を凝らすだけなので、推測でありえない。」(P.40)
「「太郎に人間という形相が宿る」とは、現代風に言えば、太郎がホモ・サピエンスという自然種に属するということ。」(P.41)
「形相(自然種)、これを包摂する類、自然種を相互に区別する種差、これらは上述の意味で我々の日常を成立させている土台であり、間違いであり得ない。こうした真理(及びそのわれわれによる了解・把握)を彼はエピステーメー( ἐπιστἠμη )と呼ぶ(『ニコマコス倫理学』6巻3章など)。この語は ἐπί 〔エピ〕と動詞 ἳσταμαι 〔ヒスタマイ〕(「立つ」)の複合語で、上に昇って立つ、が原意。上から全体を(見間違いなく)見渡す、統括する、と意味が広がる。アリストテレスは、エパゴーゲーで上に登ると見渡せる真なる知識、の意で用いている(つまり「間違ったエピステーメー」は形容矛盾)。このニュアンスは可謬的経験知という含意のある英語の knowledge や science では表現できない(現代欧州語でエピステーメーに匹敵する語彙は独 Erkenntnis くらい)。形相説(イデア論)はこうした「誤りでありえない知識内容」を(定冠詞に沿って)理念的に措定し、そうした知識内容を少なくとも部分的には獲得済みと見なす思考の枠組みであり、その全面的獲得を希求する目的論と一体である。」(P.41)
「他方、根拠からの結論導出をアリストテレスは συλλογισμός (シロギスモス)と呼ぶ。これは σύν と λόγος 〔ロゴス〕(第9章参照)の合成形。「数と数を結びつけ計算する」「文と文を結びつける」「説得的な流れを作る」などと意味が広がる。」(P.41)
「出発点となる真理は他のシロギスモスの結論か、上記のエパゴーゲーによるものしかない。」(P.42)
キケロとセクストス
「「懐疑」は英語で skepsis。祖語は希 σκέψις、こちらは「探究」の意。」(P.43)
「セクストスにつけられたあだ名「エンペイリコス」は「経験」( έμπειρια 〔エンペイリア〕)に由来。アリストテレスは経験を重視しつつも、普遍及びこれが示す類種ヒエラルキー構造をプラトンと共に躊躇なく永遠不変の真理と見なした。」(P.43)
「これは、アリストテレスにおいては一体だった質料形相説(自然学)と論理学が、トマスにおいて分断されたことを意味する。」(P.44)
「論理学は世界のあり方と無関係な形式論理へと転換し、現代に至る。この変質は論理が形而上学から解放される喜ばしき発展とされるが、アリストテレスから見れば嘆かわしき誤解である。誤解の源泉はエパゴーゲーを結論導出と解したキケロのローマ法的な目線にある。」(P.45)
エパゴーゲーと懐疑の融合:ベーコン以降
(ベーコン)「彼はエパゴーゲー(induction)とシロギスモス(syllogism、三段論法)というアリストテレスの二つの方法を対比し、アリストテレスとスコラは後者重視だと避難する。そして、induction こそ科学的真理を探求する道だ、と主張する。これはアリストテレスの誤解である。アリストテレス本人はベーコン同様、シロギスモスよりエパゴーゲーを重視したからである。」(P.45)
(ベーコン)「目標到達の困難さは、キリスト教的な内外対立に付随する外界の不可知性(第2章参照)が形を変えて現れたもの。欧州哲学(科学)はこのシンプルな構造を維持しつつ脱皮を繰り返してきた。他方、漢語文化圏では多様な思想が別の漢字で提起され、構造は一枚岩に収斂せず複雑化するばかり。これは別個の漢字が相互に独立した文字媒体であることと軌を一にする。」(P.46)
「20世紀になると帰納概念は細分化され、今では狭義の帰納(枚挙からの一般化)と広義の帰納(アナロジーや仮説形成を含む)が大別されている。フレーゲやラッセル以降の分析哲学の系譜では、確率論を使って帰納の論理を形式化する試みがなされたきた。(カルナップら)。」(P.47)__直感的認識をイデアから論理学に移行した?
「工学的アプローチにできるのは、帰納プロセスを観察してそこに一定の数学的構造を読み取り、この構造に基づく自動機械を作成して工学的に再現すること(AIを作ること)。他方、再現される帰納プロセスそのものは、さしあたり生身の我々各自の「今」「ここ」「私」(アリストテレスのエパゴーゲーはまさにこれを足場に我々(FF)の各自が行うべき普遍へのジャンプだった)に委ねられたまま。」(P.47-48)
「全体を見ると、アリストテレスが披瀝したエパゴーゲー構造は、結論導出という文脈に移し替えられながら、科学的真理の追究を支える枠組みとして継承されてきたことが分かる。こうした構造を日常語の反省を通して析出させ、継承し、人類を席巻する科学的世界観の屋台骨へと涵養する。これが欧州文化圏の強み。漢語文化圏に同様な所産は生み出せなかった。」(P.48)__脳が意識を作っているという機械論的思考では何も解決しない。西欧はその他の地域の犠牲の上に成り立っていることを忘れるな。
「しかし、法律はギリシア・ローマで正義の女神に喩えられ、理念化もされてきた。この意味で法律は地に足をつけつつも、現実を導くべき理念的正義を見据えつづける。」(P.48)
演繹(deduction)の淵源と来歴
「アリストテレスのシロギスモスも演繹の一種。こうした意味での deductio の用法はトマスまで遡る。」(P.49)
「deductio の動詞形は deduco、前置詞 de(英 from)と duco (導く、英 lead)の合成語。追い出す、遠ざける、導き去る、運び去る、連れ去る、背ける、そらす、とうとうと意味が広がる日常語彙。」(P.49)
「6世紀、ポエティウスがアリストテレスの ἀπαγωγή を deductio と訳した。言語は前置詞 ἀπό 〔アポ〕(分かれて、離れて、遠ざかる)と前述の ἂγω の複合語。離れて導く、引き離す、連れ去る、分離させる、引き返す、などと意味が広がる。」(P.49)
「カントは deductio を考える文脈を二つに大別する。スコラ的な形式論理学における deductio と、先験的文脈での deductio である。前者は一般命題から特殊命題を演繹的に導出するステップで、inductio (特殊命題から一般命題を機能するステップ)の逆。カントにとって一般命題は経験知であり、経験知に必然性はない(将来的に覆されうるし、懐疑にも開かれている)。」(P.52)
「経験知と違って懐疑不能で必然的な知は確かにある。それはデカルト的なエゴ、しかも経験知が可能となるための制約としての我々自身についての知である。」(P.52)
日本語の中の「帰納」と「演繹」
「しかも、漢語を翻訳語に選んだことで、哲学は身構えて臨むべき知識だ、と西は解釈したことになる。原語が生活感覚からにじみ出る本音を語る日常語彙であり、同時に日常を変革する役割を果たすのとは対照的。」(P.54)
「シロギスモスはエパゴーゲーが獲得した永遠不変の真理を拡張する。エパゴーゲーとシロギスモスはこのように神々との一体化にほかならない。この一体化はギリシア語圏からラテン語圏へ、さらに定冠詞を備えた現代の西欧諸国語圏へと継承される。これら欧州語の話者は、定冠詞として構造化されたイデア界に生活の中で全面的に身を委ね、思考する限り神的なものの眼差しに(FF)曝されて立ち尽くす。この構造に思考が制約され、生活の中で神に絶えず見張られた緊張感を感じ続けることになる。正義を実現する「法の支配」もこうした神の臨在への確信と密接に結びついた文化現象。近現代の帰納的な経験科学の発展も同様である。法律から科学技術の最先端に至るまでを一貫して動機づける欧州精神文化のおおもとがエパゴーゲーだと言える。」(P.54-55)__『トゥルーマン・ショー』。お天道様が見ている。
第4章 総合と分析
総合 synthesis、分析 analysis
「「総(總、綜)」は糸でまとめ結ぶ、合は合わせる。神仏が糸で結び合わされる、の謂。」(P.59)
「原著者ヘイヴンはカントやミルの意味で synthesis と analysis をペア語彙として用いた。西もこれに沿って訳語選択した。両語彙は元々ギリシア語(希 σύνθεσις〔スュンテシス〕と ἀνάλυσις 〔アナリュシス〕)。元来は対語でなかった。」(P.59)
ギリシアにおける総合と分解
「シュンテシスの動詞形は συντίθηπι 〔スュンテイテーミ〕、σύν 〔スュン〕(英 with)とτίθημι 〔ティテーミ〕(置く)の複合形。τίθημι は κεἶμαι 〔ケイマイ〕(置かれている)とペアをなす日常語(第1章参照)。様々の前置詞と複合形を作る。συτιθημι はその一つで、複数のものをまとめて置く、の意。」(P.60)
「ペアを成す σύγκειμαι 〔スュンケイマイ〕は複数のものがまとめて置かれている、の意。」(P.60)
「アナリュシスの動詞形は ἀναλύω 〔アナリュオー〕、前置詞 ἀνά 〔アナ〕と λύω 〔リュオー〕の複合形。λύω は「緩める」「ほぐす」「溶かす」の意。様々な前置詞と結合する日常語彙。反対語は δέω 〔デオー〕(縛る、締めつける)。ἀνά は「(何かに)沿って」「合わせて」「抵抗して」「最後までやり通す」と意味が広がる。英語で一対一対応する前置詞はない。たとえば ἀναλογία 〔アナロギア〕(英 analog「アナログ」や analogy 「類推」の祖形)は「ロゴス(比例、法則性)に従う」。ἀναχρονισμός 〔アナクロニスモス〕は「時の流れに抵抗する」すなわち「時代錯誤」。ἀνατομή 〔アナトメー〕(英 anatomy)は「切り離す」「切開」「解剖」。アナリュシスの ἀνά はこのうち anatomy の ana、つまり「やり通す」「し尽くす」の意。ἀναλύω は「縛りから完全に解き放つ」「ほぐし切る」「溶かし切る」、転じて「魂が肉体から解き放たれる(死ぬ)」。反対語はシュンテシスでなく ἀναδέω 〔アナデオー〕(縛り上げる、締め上げる)。」(P.60)
幾何学における総合と分解(分析)
「本来は対語でないシュンテシスとアナリュシスは幾何学で対語化された。」(P.61)
「幾何学は個別的な三角形でなく理念的な三角形、三角形のイデアに関わる。」(P.61)「作図問題のアナリュシス(分析)とは、その作図があたかも可能だと仮定して、既知の作図(よりシンプルな作図)を組み合わせてその問題が解けるかどうかを見極めること。」(P.61)
「他方、作図問題のシュンテシス(総合)とは、既知の作図を一定の順序で組み合わせて作図問題を実際に解いてみせること。『原論』は幾つかの用語の定義、上記の二等辺三角形の作図、そして角の二等分線の作図を組み合わせ、円に内接する正五角形を作図していく。このプロセスが総合。(LF)」『原論』には作図のみならず命題の証明も含まれる。証明も作図に準ずる。命題の(FF)アナリュシス(分析)とは、その証明が可能だと仮定して、既知のどんな真理を組み合わせればこの命題が証明できるかを探ること。」(P.61-62)
「総合は論理の流れを事後的に整理した結果。実際の思考現場では分析が欠かせない。」(P.62)
プラトンにおける総合(合成)と分析(分解)
「これとの類比で、この世界が刻一刻と変化していくのも、何らかの要素がその形や場所を変えていくプロセスに他ならない。その要素とな何か。タレスは「水だ」、アナクシメネスは「気だ」、そしてピュタゴラスは「数だ」と答えた。」(P.63)
「どのような答え方をするにせよ、イオニアの伝統における要素は同時に ἀρχή 〔アルケー〕であると理解されていた。この語は「始まり」「始点」の謂、「支配」という含意もある。つまり、アルケーとは単なる始まりでなく、先頭に立って後に続く全てを支配するもの(たとえば政治的支配者)、全てを従わせ統括するもの、全てを通底する原理。反対語は τέλος (テロス、すなわち目的・終わり・終点)。」(P.64)
(プラトン)「彼にとってアルケーは詰まる所、イデアである。彼は四元素も三角形などのイデアへと還元してしまう。人間精神も政治的支配も善のイデアに導かれる。イデアは万物がそこへと向かって収斂していくテロスでもある。」(P.64)
アリストテレスにおける総合と分析
「アリストテレスはシュンテシスをやはり要素からの合成(要素単独では持ちえなか(FF)った強度を備えた合成)というイオニア的な意味で多用する。」(P.64-65)
「森羅万象は複合物、しかも要素にはなかった独特の強度を備えた複合物だとする世界観が基盤にある(第10章参照)。要素への分解を指す語はプラトン同様 διάλυσις 〔ディアリュシス〕が多い。」(P.65)
ラテン語圏における分析と総合
近世における分析と総合
(デカルト)「イオニア的な要素への分解ではない。『原論』的な分析でもない。『原論』的な分析は、作画問題が解けると仮定した上で、何らかのシンプルな作図を組み合わせて問題が解けないか探る手続き、つまり問題を解くための十分条件(既知の原理の束)を探し出す手続きだった。『省察』の分析は違う。それは真実性が保証された認識(コギト)から出発し、この認識に含まれる必要条件(エゴの存在、神の存在など)を次々と導出する論理分析、すなわち演繹(第3章参照)である。換言すれば、出発点に前提される必要条件を論理的に明示していく分析(『省察』の分析が成功しているか否かは別問題、実際にあちこちで破綻している)。」(P.68)
「これに対し、スピノザは総合という方法に徹底的にこだわった。」(P.69)
「自然研究においてニュートンは原子論者であるのみならずベーコン的な帰納の徒でもある。自然を単純な要素(原子)へと分割し、運動を引き起こす力(機械論的に把握された始原因、すなわち作用因)を帰納により一般化したのが古典力学。イオニア的な要素への分解を体現する考え方である。その成功は形相因と目的因を自然学から駆逐した(第6章、第7章参照)。しかし、残る質料因(原子)と始原因(作用因、力)が何であるかについて、古典力学は数値化可能な法則性があるという以上のことを教えてくれない。前者の探究はボイルの元素説を経て化学へ、後者の探究は理論物理学へとつながり、現代でも続いている。両者は突き詰めると素粒子論に収斂する。」(P.70)
デカルト的な分析・総合の系譜
「19世紀も半ばになると、科学技術の発展と軌を一にして分析は総合より圧倒的優位に立つ。」(P.72)
「「分析」「総合」の用語法もミル流で、人間の分析能力は演繹に、総合的能力は一般化・帰納・反省に関わる、とされる。この analytic・synthetic ペアを西が「分解」「総合」と訳した。」(P.73)
その後の総合と分析
「西の時代以降、欧米では論理学が『原論』の総合的方法で公理系化される。立役者はフレーゲ。」(P.73)
日本語における分析と総合
「第3章で述べた通り、定冠詞を持つ欧州の話者は、神の眼差し(イデア)から逃れられない。中でも哲学者たちは神の眼差しを突き詰める。彼らの言葉は概して「私は真理を語っているのだ」という神を体現するかの如き圧倒的な確信に満ちている。これを受け止める日本の哲学関係者の多くは、納得しながらも「その立場が全てではない」と相手を突き放してしまう視線を心中に感じてしまうらしい(少なくとも本書の著者はそうである)。」(P.76)
第5章 実体と属性
アリストテレスとそれ以前
「アリストテレスは「実体」を οὐσία 〔ウシア〕と呼んだ。これはギリシア語の be動詞 ἐιμί 〔エイミ〕の現在分詞 οὖσος 〔ウーソス〕に由来、「存在するもの」から転じて「財産」「所有物」「(誰々の)もの」の意で当時、日常的に使われた語。プラトンは、個物が宿すイデアとはその個物のいわば本当の内実、値打ちだ、という趣旨でイデアを指す語に用いた。」(P.80)
「アリストテレスはカテゴリアを十個、識別した。たとえば「太郎は人間だ」における「人間」は、太郎に宿るウシア(実体、形相)。「太郎は身長170cmだ」における数170は、太郎に備わる量( ποσόν 〔ポソン〕、英 how much )。「太郎は浅黒い」における浅黒さは、太郎に備わる質( ποιόν 〔ポイオン〕、英 what kind of )。「太郎は次郎の先輩だ」における「先輩」は、太郎と次郎の関係( πρός τι 〔プロス ティ〕、英 in relation to)。「太郎は今、自宅にいる」における「自宅」は太郎のいる場所( ποῦ 〔プー〕、英 where)、「今」はその時間( πότε 〔ポテ〕、英 when)、「太郎は寝転がっている」と言えば、これは太郎の姿勢( κεῖσθαι 〔ケイスタイ〕、英 be in a position、置かれた状態)。「太郎は部屋着を身につけている」は太郎の所持( ἒχειν 〔エケイン〕、英 having)、「太郎は次郎を殴った」という言明は太郎の能動( ποεῖν 〔ポイエイン〕、英 doing)、そして次郎の受動( πάσχειν 〔パスケイン〕、英 being affected)。」(P.80)
「第1章でアリストテレスのヒュポケイメノンに言及した。それは構造化される以前の所与世界すなわち質料、構造化された後の個物・主語、大きく見て二義的な用語だった。これと連動してカテゴリアも二義的となる。すなわち、構造化以前と対置される範疇(構造化以後の十の要素),及び構造化後における(個物・主語に(FF)対置される)述語。更に連動して、ウシア(実体)も二義的となる。第一実態(個物)と第ニ実体(形相、普遍)である。第一実体は主語になるが述語にならない(『形而上学』7巻3章)。第ニ実体は主語にも述語にもなる(たとえば「人間は動物である」「ソクラテスは人間である」などのように)。「主語」「述語」は西が英 subject・predicate に充てた新造翻訳語。それぞれ原語はヒュポケイメノン・カテゴリアである。」(P.80-81)
「定義( ὅρος 〔ホロス〕)とは境界・境目が原意。本質( τί ἦν εἶναι 〔ティ エーン エイナイ〕〕とも言い換えられる。「本質」はアリストテレスの造語。「それはいったい何だったのか」「そうか、そうだったのか」という日常表現が哲学用語化したもの(抽象的語彙に事欠いて苦し紛れに案出された典型例)。たとえば「人間」の定義・本質は彼によれば「理性的動物」。特有性( ἴδιον 〔イディオン〕)は当該事物にしか備わらない性質(原意は「自分だけのもの」、英 own に相当。反対語は κοινόν 〔コイノン〕「共通性」)。」(P.81)
その後のギリシア語圏とラテン語世界におけるカテゴリア
「オッカムは subiectum と praedicatio が言語記号としての主語と述語、substantia と praedicamentum が実在としての実体と属性、とする用語法を確立した。」(P.83)
ローマ社会における attributum
トマスにおける proprium と proprietas
「トマスにおける proprium・proprietas・accidens は、実体( substantia )と共にキリスト教の内外対立における「外」(外界の被造物)の位置に置かれている。どんな個物も substantia に proprium・proprietas・accidens が宿った状態で神が創造した。」(P.86)
スコラからデカルトへ
「デカルトによれば、このような仕方で他の観念に依拠せず、理詰めでその明晰判明さが証明できる概念は、何であれ実体( dubstantia )として存在する。」(P.87)
「これを踏まえると特定のスコラ用語群、中でも「実体」に対するデカルトの偏愛が明らかに浮かび上がる。この偏愛は、実体概念がアリストテレス以来、かくも根深く欧州人に沁みついており、何を考える際にもつい頼ってしまう手軽な概念装置であることを(ハイデガーはこれを『存在と時間』で「存在忘却」と形容した)、そしてキリスト教の強力さを、示していると思われる。」(P.88)
(デカルト)「これらの語彙をそもそも採用し続けた(FF)こと自体、彼の限界だが、哲学的思考は伝統的概念を全て否定することはできない。何かを残さないと思考は始められない。伝統に連なる、とはそういうことである。」(P.88-89)
ホッブズと英国経験論
スピノザと大陸合理論
その後の実体、属性、範疇
日本における実体と属性
「全てを口に出して実在を余すところなく完全に言語化し、その知見を生活に活かして自然を支配し使いこなそうとする(社会も制御していこうとする)欧州文化とはかなり異質な面がある。アリストテレスもこの点で典型的な欧州人。(LF)「こと」は「こ」(話者に物理的・心理的に近いものを指す指示詞、「子」や「来」と同語源と推測される)と「と」(内側に対する外側、「外」「戸」「門」「跡」などの漢字が充てられる)の複合系と考えられる。すると、「こと」とは自分の身近、しかも自分から見て向こう側に、新たに出現した事象一般を指すことになる。「新たに」という部分を強調すると、「ことなる(異)」。この「こと」に潜む普遍的な内部構造を言い当てる語彙(ウシアやカテゴリアに相当する自前の語彙)を和語は持たない。「こと」が要素となって「できごと」や「ことば」などの複合語はできるが、「こと」の内部構造に和語は関心がない。」(P.96)
「和語の世界では言は事の写し絵でなく、事と未分化。「こと」は、身体を持つ我々各自にその都度出現する世界の断片。その世界はウシアのような普遍的構造を持たず、絶えず「浮き世」として動きの中にある。」(P.97)
「「私」とはこうした世界が転回していく言わば場のようなもの。「私」の身体はこの転回に絶えず居合わせ、そのつど「そと(外)」「こと」「うち」の相互の境目を成す。これに対して、その都度の「こと」に囚われず、「こと」の動きの一切から己を脱却させることで開けてくるのが無であり、空である。「私」とは、その真相を見極めれば、実はこうした無であり、空そのもの。日本語生活者には空を観ずる心根が宗教のみならず芸事や武道、日常生活に至るまで根を張っている。日本の芸事や武道は、どのような道であれ、「こと」の動きを、身体の動きを、無の開けの中で制御し、陶冶し、反復する作法に他ならない。「無」や「空」は漢語であり、和語の世界にとって外来かつ後発的な視座だが、相性がとてもよかったようである。それは「私」が「こと」を脱却して向かうべきテロス、欧州ご生活者にとってのプラトン的イデアに類似する位置づけを多くの日本語生活者において占めている。両者の違いは、後者が構造化と言語的認識を強く希求するのに対して、前者は全ての構造を飲み込み、無効化し、超越すること、そして言語化を拒否すること。」(P.97)
「理論と実践の区別はアリストテレス由来で、カントが近代的な刻印を付与して流布させた。」(P.97)
第6章 原因と結果
「世界のすべての事象には hetu(梵語で「元になるもの」の意。「原因」「理由」「動機」などさまざまに訳出可能)があり、これが何らかのきっかけ(梵 pratyaya)を得て、果(梵 phala)を結実させる。」(P.99)
「とはいえ、現代の我々が用いる「原因」「結果」の直接的源泉は仏典ではなく欧州哲学である。英 cause の祖語は羅 causa)、ローマ法用語。キケロが希 αἰτία (アイティア)の羅訳語に使った。effect の祖語は羅 effectum、やはりローマ法用語。こちらはギリシア語に対応概念がない。」(P.100)
ギリシアにおける原因への問い
「これら近代的な区別(自然と価値の区別と総称できる)は古代ギリシア人に無縁だった。」(P.100)
「自然界は神々と人々が交流し、時にせめぎ合う場。人間どうしの交流や争いも神々の名において行われた。ホメロス時代のギリシアでは自然と人為、そして神々を相互に峻別せずにアイティア(せい、責め)の所在が問い求められた。」(P.101)
アリストテレスの四原因説
「すなわち、動き変化を起動させる始原因(アルケー)、動き変化の到達目標(目的因、テロス)、動き変化が生み出すものの形(形相因)、及びその素材(人為を被る材料・基体、質料因)。」(P.102)
「natura は古代ローマで希 φύσις 〔ピュシス〕(英 physics 「自然」「物理」の祖語)の訳語として使われた。この語は動詞 φύω 〔ピュオー〕「(父が子を)生み出す」「生まれいずる」の名詞形、「生まれ」「育ち」「成長」「変化」の謂。世界は動き変化に満ちており、留まることを知らない。これを和語ははかなみ、「浮き世」と呼ぶが、ギリシア人ははかなむことなく全面肯定しピュシスと呼ぶ。動き変化はアイティア(FF)(原因)により引き起こされる。この解明究明が『自然学』の課題。アリストテレスは人為との類比で次のように考える。自然界の動き変化もなんであれアルケーにより動かされ、レロスへと収斂する。素材が基盤(ヒュポケイメノン)となってイデアを宿すことで、自然界の生成変化が起きる。」(P.102-103)
「だが、彼はアイティアについてアリストテレスのような理論を提唱していない(アイテイアはイデアを名指すためにプラトンが援用した日常語の一つ)。」(P.104)
古代ローマ
(アウグスティヌス)「それでも悪を為すものが絶えないのは、彼らに信仰がないから、あっても神への愛が足りないからである。」(P.107)__愛は能動的。「聖アウレリウス・アウグスティヌス(ラテン語: Aurelius Augustinus、354年11月13日 - 430年8月28日[26])は、ローマ帝国(西ローマ帝国)時代のカトリック教会の司教であり、神学者、哲学者、説教者。ラテン教父の一人。テオドシウス1世がキリスト教を国教として公認した時期に活動した。正統信仰の確立に貢献した教父であり、古代キリスト教世界のラテン語圏において多大な影響力をもつ。カトリック教会・聖公会・ルーテル教会・正教会・非カルケドン派における聖人であり、聖アウグスティヌスとも呼ばれる。日本ハリストス正教会では福アウグスティンと呼ばれる。母モニカも聖人である。名前が同じカンタベリーのアウグスティヌス(イングランドの初代カンタベリー大司教)と区別して、ヒッポのアウグスティヌスとも呼ばれる。 」(Wiki)
スコラ:トマスからオッカムへ
「スコラ学(スコラがく)とは、ラテン語の「scholasticus」(学校に属するもの)に由来する言葉で、11世紀以降に主として西方教会のキリスト教神学者・哲学者などの学者たちによって確立された「学問のスタイル」のこと。このスコラ学の方法論にのっとった学問、例えば哲学・神学を特にスコラ哲学・スコラ神学などのようにいう。 」(Wiki)
「普遍をスコトゥスはトマス同様、概念上は実在すると考えた。オッカムはこれが理性による構築物だと主張した。すなわち、普遍は個物を知解するために人間が創出した概念装置。実際に存在する(神の被造物である)わけではない。こうした知と信の峻別が近世への扉を準備する。」(P.109)
スコトゥス「ヨハネス・ドゥンス・スコトゥス(Johannes Duns Scotus、1266年? - 1308年11月8日)は、中世ヨーロッパの神学者・哲学者。トマス・アクィナス後のスコラ学の正統な継承者。アリストテレスに通じ、その思想の徹底的な緻密さから「精妙博士」(Doctor Subtilis)といわれたフランシスコ会士。盛期スコラ学と後期スコラ学をつなぎ、スコトゥス学派の祖となった。ドゥンスのジョン(John of Duns)とも呼ばれる。」(Wiki)
オッカム「オッカムのウィリアム(英: William of Ockham、1285年 - 1347年[1])は、フランシスコ会会士、後期スコラ学を代表する神学者、哲学者。通例オッカムとのみ言及されるが、これは下記のように姓ではなく出身地で呼んだものである。哲学や科学における節約の原理「オッカムの剃刀」の提唱者として知られている。」(Wiki)
「オッカムの剃刀(オッカムのかみそり、英: Occam's razor、Ockham's razor)とは、「ある事柄を説明するためには、必要以上に多くを仮定するべきでない」とする指針。14世紀の哲学者・神学者のオッカムが多用したことで有名になった。 」(Wiki)
近世:ベーコンからニュートン・ライプニッツまで
「デカルトによれば、神はその能力の無限さゆえに、自分自身が存在する原因にもなる、つまり神は自己原因( causa sui )である。アウグスティヌス、トマスラはアリストテレスに倣って神が自己原因であることを否定した。創造主である神は被造物の始原因(作用因)だが、もし神が自己原因であるなら、神は自分自身に先立って存在し、作用を加える原因であることになる。これは自己矛盾である。デカルトは自己原因を形成因と捉えて矛盾を回避する。」(P.110)
カント以降
(カント)「他方、我々は物理的世界の認識にとどまらず、善悪を判断し、目的を持って行動し、他者と関わる意思の主体、すなわち人格でもある。人格とは手段(道具)ではなくそれ自体が目的であり、尊厳を持つ。尊厳を守る最低限のルール(法律)を構築して社会生活は営まれるべき。目的は社会規範を扱う世俗知(社会科学や社会政策)に不可欠な概念。カント以降、社会科学は自然科学から独立・自立する学問領域として自覚的に発展する。その発展(FF)が、目的概念を因果関係から分断し、物理的世界とは異なる次元に置くプロテスタント的な態度により促されたことは、思想史的に見て興味深い。哲学においては、ヘーゲルの絶対者(理念)、フッサールの生活世界、初期ハイデガーの道具関連など、目的因を作用因に優越させようとする様々な立場が提起されるが、どれもカントの強い影響下にある。」(P.113)
「発生する事件を当事者の知(自白、不知)と意思(故意・過失)、及び機械論的な因果関係に沿って事実認識し、これを法規範(大陸では法典、英国では判例)に当てはめて判決する、という方法論が18世紀から19世紀にかけて確立する。」(P.113)
「物理的世界で因果関係が一般に成立する、という主張は帰納であり、ヒューム的な懐疑がつきまとう。ポパーはこれを逆手に取り、現在正しいと見なされている理論は反証されていないだけで、絶対正しいとはそもそも言えない、科学理論は本質的に仮説形成でしかなく、反証できても確証は不可能だ、と考えた。では、科学における仮説はなぜ因果関係に依拠してしまうのか(量子力学は例外としても)。カントの言うように、因果関係を使わないと我々は整合的に世界を理解できないのか。これは観念論と実在論の対立。答えはない(第2章参照)。」(P.113)
「ニュートン以降の物理学は形相因を放逐したが、生物学では19世紀まで形相因が生きていた。すなわちアリストテレスの自然種(英 species )である。これをダーウィンの進化論が崩壊させた。」(P.113)
「ゲノムの全塩基配列が形相(情報)、タンパク質の元になるアミノ酸は質料(物質)とも言えるが、そうまでしてアリストテレスの用語の延命を図る必要はない。塩基配列は様々な要因で突然変異を起こし、これが生物の進化につながる。またヒトゲノムは約0.2%分の塩基配列に個人差を許容する曖昧さを含み持つ。やはり質料形相説は敗退した。」(P.114)
「この意味で、我々が生きている世界は作用因の世界と目的因の世界の重ね合わせ。つまり、我々はライプニッツ・カント的な二世界説を地で生きている。眼鏡をかけかえるように二つの世界を使い分けながら、今後もやっていくしかない。」(P.114)__近代化(西洋化)した日本では、そう言ってもいいかもしれない。でも、そこまでわかっていて、それが他者(非西洋の世界、西洋世界によって虐げられている世界、あるいは環境、自然)にとってはけっしていいことではないということに目をつぶってもいいのか。西洋は勝手に西洋していればいい。でも、それならば他者には関わらないでほしい。
和語の世界と因果関係
「「原因」と「結果」の背後にはギリシア自然哲学、ローマ法、キリスト教、そして近代の機械論的自然観が折り重なる。ギリシアにおけるアイティアの決定論的な厳しさ、ローマ法の causa に備わる神判の厳しさは、キリスト教の神の厳しさ、そして自然法則の厳しさに置き換えられ、今でも生きている。」(P.114)
「和語でアイティアの原意に近いのは「せめ(責、攻)」。その能動・受動両面を指す。「せい」と同様、因果関係を直示する語彙へと脱皮することはなかった(いわばホメロス時代のアイティア概念のまま)。」(P.115)
「いじめ自殺や過労死自殺も「せめ」の結果。明治以降導入された欧州的な近現代法は、厳密な因果関係の立証によらず責めることを許容しない。こうした法律観は現代の日本社会にかなり浸透したものの、人々の日常的な意識に根を張るには至っていない。」(P.115)
「因果関係に対する和語の意識は総じて薄弱。暗黙知の対象でしかなかったのだろう。漢訳仏典の「因」「果」「縁」が因果関係を直示する日本初の語彙だったと思われる。これらは言語化されるべき法則性というより諦念して順応すべき理の象徴として日本で受けとめられ、輸入概念ながら日常生活に根ざしていく。ここに19世紀半ば以降、欧州思想が流入して「原因」「結果」などの翻訳語が考案され、「ため」「ゆえ」などが因果関係の明示表現へと転用された。英 cause の動詞形は「引き起こす」などと訳された。この表現は江戸期まで「体を引っ張り起き上がらせる」の意で、因果的法則という含意はなかった。」(P.116)
「和語は元来、語彙貧困だった。漢語導入は和語の語彙を分身させた。「よる」が「寄」「因」「拠」「依」へと分岐したのはその例。これは和語彙の原風景消失を助長した。「寄」「拠」「因」などの漢字の意味に引っ張られ、「よる」の原意が見失われがちになるからである。」(P.116)
「そこには、万物を支配する厳しい理念的法則性を信じ、それを言語化してえぐり出し、応用しながら自発的に行動し、世界を変革する、という欧州土着的な理念信仰(イデア論的な自己理解と自己制御)はない。」(P.117)
「法の支配の定着はまだ不十分。いじめの根絶、環境破壊の抑止、一人一人が大切にされるよりよい社会の実現のために、和語の世界にまどろむ余地を残しつつも、外来の道具である法の支配を更に使いこなし、根づかせていくのが望ましい。それが我々一人一人の利益を最大化する道だろうからである。」(P.117)__加藤尚武『現代倫理学入門』
第7章 可能と現実
可能 英 possibility δύναμις
現実 英 actuality ἐνέργεια
古代ギリシアにおけるデュナミストエネルゲイア
「デュナミスは力、強さ、能力、特質、(お金の持つ)価値、と意味が広がる名詞。動詞形は δύναμαι 〔デュナマイ〕、強さ(価値)がある、何かを意のままにできる、(社会的地位が)高位である、などの意。英 can に相当する助動詞でもある日常語。(LF)エネルゲイアはアリストテレスが ἐν 〔エン〕(英 in)と ἒργον 〔エルゴン〕から新造した語。エルゴンは一定の社会的地位(市民、兵士、男性、女性など〕に特有の働き・仕事(ホメロスでは「戦功」の意が多い)、あるいはその働きの結果(制作物や作品)のこと。英 work と同語源で、日常頻用語だったはず。動詞形は ἒργω 〔エルゴー〕(働く)。エネルゲイアは「働いている最中」の意。」(P.119)
「ある能力(例えば建築術)を他の能力(例えば医術)から区別する必要はあるが、能力とその行使を区別する必要はあまりない。建築家が実際に建築していようといまいと、その能力に変わりはない。プラトンのイデア論もこうした文脈にあった。」(P.120)
能力とその行使(働き):アリストテレスの区別
「能力とその行使(働き)を明確に区別したのはアリストテレス。」(P.120)
「メガラ派はソクラテスの弟子だったメガラのエウクレイデスが始祖。」(P.120)
「メガラ派は能力(デュナミス)とその行使(エルゴン)を混同している。アリストテレスは能力行使中の状態を指してエネルゲイアという新造語まで作った。」(P.121)
(パルメニデスに対し)「これにプラトンは「そうだ。動き変化はまやかしだ。不動なるイデアをつかめ」と迎合し、個別から目を背ける。だが、アリストテレスは違う。動き変化はまやかしではない。プラトンの態度は現実逃避である。では、動き変化とは何か。彼の答えはこうである。たとえば建築とは、建築家(始原因)が素材(質料因)に働きかけ、設計図(形相因)通りに建物の完成(目的因、テロス)へ向けて仕上げていく一連の動き変化のプロセス。建物が完成するとプロセスは終結する。建築という動き変化は、換言すれば、建築家の能力と、素材の能力が、建物の完成目指して共に発現中の(エルゴンの内にある)状態。より一般化すれば、デュナミスが発動されエネルゲイア化することこそが動き変化に他ならない。」(P.121)
デュナミスとエネルゲイア:その多義性
(デュナミス)「(1)働き変化の能動能力(始原因、建築家に備わる建築術など)、(2)動き変化の受動能力(質料因、建築材料の適材性など)、(3)単なる能動・受動のの力でなく、うまく能動・受動する能力(高い建築能力、高い適材性など)、(4)悪化や破壊に抵抗する能力(材木が折れれずに持ちこたえる能力など)、(5)論理的可能性(たとえば否定形で「正方形の一辺は対角線と通訳的でありえない」(FF)という際の「あり得ない」)。エネルゲイアとペアを成すのは(1)to(2)。」(P.121-122)
(エネルゲイア)「(1)能動能力が発動され動き変化が発生している状態(建築家が建築中である、など)、(2)受動能力が発動され動き変化が生じている最中(建築加工中の素材、同11巻9章参照)、(3)受動能力が発揮されて動き変化が生じた末、テロスに達した状態(彫刻が完成した暁のヘルメス像、訓練の末に大成した笛吹など、未完だったものが完成した状態)、(4)動き変化と無関係なエネルゲイア(感覚・思考・幸福などの能力の発動。すなわち、エネルゲイア化しても動き変化は生まれず、即テロス即達状態となるもの)、以上四つの用法に言及する。同12巻では(5)発動されないことがありえないエネルゲイア(発現しっぱなしの恒常的エネルゲイア)にも言及される。これは天球の恒常的働きのこと。」(P.122)
エネルゲイアとエンテレケイア
「エネルゲイア(3)は ἐντελέχεια 〔エンテレケイア〕とも呼ばれる。これもアリストテレスの造語、「テロス到達状態にある」が原意。」(P.123)
(ゼノンのパラドックス)「言い換えれば、二次元をどれだけ分割しても一次元には至れない。逆に、一次元をどれだけ集積しても二次元には至れない。一次元の集合体として二次元を捉えることは論理的に不可能。一次元と二次元は本質的に違う。」(P.124)
「ここでアリストテレスはデュミナスとエンテレケイアの区別を導入する。ゼノンが無限に存在するとナイーヴに仮定する一元(点)は、エンテレケイアとして存在するのかデュミナスとして存在するのか。」(P.124)
「つまり、ゼノンが構成(FF)していく無限の点は、想定できるという意味で可能(デュミナス)的に存在するが、現実に(テネルげイア的に)存在はしない。一次元と二次元を混同してはならない(『自然学』8巻8章)。」(P.124-125)
ローマと初期教父の時代
「 δύναμαι に相当するラテン語は possum (できる、力がある)。やはり英 can のような助動詞になる。」(P.125)
「名詞形は potentia (支配力、能力)や potestas (特権、力、武力など)。形容詞形 possibilis (英 possible の祖形)は紀元後に派生(羅訳聖書で使われた)。(LF)エルゴンに相当するラテン語は ops (労働、制作物、作品)あるいは fuctum ( facio 「作る」の受動完了分詞)など。」(P.125)
「ボエティウスはデュミナスを potestas、エネルゲイアを actus (動詞 ago からの派生語)と羅訳した。 ago の原意は「駆り立てられる」「仕向ける」。」(P.125)__ボエティウス「アニキウス・マンリウス・トルクアトゥス・セウェリヌス・ボエティウス(Anicius Manlius Torquatus Severinus Boethius、480年 - 524年か525年)は、古代ローマ末期のイタリアの哲学者、政治家、修辞学者。著作に『哲学の慰め』『音楽綱要』『エイサゴーゲー註解』など。 」(Wiki)
(アウグスティヌス)「神の似姿である人間は、神の potentia (理性など)の一部を共有する。他方、神の actus とは創造行為や救済行為など。人間の actus は贖罪行為や善行・悪行など、被造物としての分相応な行為。」(P.125)
スコラ
「必然はギリシャ語で ἀνάνκη 〔アナンケー〕。締め付けて無理強いする、が原意。」(P.126)
「アリストテレスにとって偶然と必然は対立しない。彼は偶然をαὐτόματος 〔アウトマトス〕、 τϋκη 〔テュケー〕、 συμβεβηκός 〔スュンべべーコス〕という三つの概念で捉えた。前者ニ者は因果関係の文脈にあり、それぞれ「他の原因に左右されるのではなく、自分自身が原因となること」「原因が不明瞭」の意。どちらもアナンケー(無理強い)と対立しない。三つ目は偶有性。『形而上学』はこれを存在(ある)の意味の四義に数える。自体性( καθ᾽ αὑτό 〔カタハウト〕)が対立概念。」(P.127)
近代科学 古典力学の成立
「典型はホッブス。彼にとって作用因は能動力( potentia activa )、質料因は受動力( potentia passiva )。この二つの力が発動(actus 化〕され、運動が発生する。つまり、 potentia は原因、 actus は結果、両者の関係は因果関係そのもの。」(P.129)
「デカルトはこの二つの potentia をビュリダンの発想で融合し、アリストテレスの「能力( potentia )の発現( actus )」という概念図式を「力( potentia・vis )の作用( actus )」という図式へと変更したことになる。変更前の図式では「発現していなくても能力はある」と言えた。変更後の図式では、作用しない力( vis )はあり得ない。神がいったんかけた力は永久に作用しつづける。つまり、力とは作用そのもの。」(P.130)
「すなわち、運動を無限分割して得られる点はデュミナス的に存在するが、エンテレケイアとしては存在しない。ライプニッツは発想を逆転させる。エンテレケイアとして得られるところまで分割を続けよう。極限まで分割して得られる運動の最小単位をエンテレケイアと呼ぼう(微分的発想)。このエンテレケイアは作用する力そのものであり、ホッブズのコナトゥスにほぼ相当する。ライプニッ(FF)ツはこれを活力( vis viva )、後にモナドと呼んだ。モナドは物理的運動の分割の極限に想定される形而上的な一次元(点)。彼はニュートンが幾何学的に表現した古典力学法則を微分方程式で表現し直した。人の感覚や知性の源は活力である。物体は活力が原因となって運動する。物体に作用する活力は、その物体の重さと速度の二乗の積である、とライプニッツは考えた。これは今日の運動エネルギーに相当する。活力を初めてエネルギーと呼んだのは19世紀初頭の物理学者ヤング。運動エネルギーは他の物体に対して仕事(その物体に働く力✕物体の位置変化)をする能力と定義される。仕事(英 work、すなわちエルゴン )という概念を導入したのは19世紀半ばのヘルムホルツ。位置エネルギーをポテンシャル( potential )と呼んだのは19世紀前半の物理学者グリーン。これらは全てアリストテレスのデュミナス・エネルゲイア、エルゴンに由来する用語だが、力と作用を同一視するデカルト図式にしたがって意味変更されている。」(P.131-132)
能力とその発現 その後
「とりわけカントはスコラ・ライプニッツ的な「必然・可能・不可能」を人間の能力(主観性)に内在する様相性範疇(可能・現実・必然の三つ組)として位置づける。可能とは、論理的無矛盾性や主観による経験可能性。現実とは、主観が感覚制約下で目の当たりにする眼前存在性。必然とは、論理的必然性や認識の先験的諸制約(主観性にアプリオリに備わる)。」(P.133)
「ヘーゲルはカントの「可能・現実・必然」を個人の主観性から共同体という文脈に移す。」(P.133)
「ハイデガーは若い頃、生物学者ユクスキュル(環境世界に置かれた生物が目的論的(FF)な行動をする、という視座を基本とした)から強い影響を受けた。ライプニッツのモナドよろしく、それぞれの生物種がそれぞれに固有の仕方で環境世界を解釈し、能力を発現して生きている、という思想である。ロレンツらが開拓した生物行動学の基盤にも能力発現という視点がある。」(P.134-135)
「様相論理は20世紀、ルイスを経てクリプキにより可能世界意味論として展開された。公理的な統語論体系(述語論理など)を意味論解釈(存在領域すなわちオントロジーの対応付)する際、解釈に無限のバリエーションを与え、ここに必然・現実・可能を位置づける。すなわち、一つ一つの意味論解釈が可能世界を成し、現実世界はこれらのうち現実化しているどれか一つとされる。必然はあらゆる解釈において正しい文。ライプニッツのアイデアに沿った理解だが、神は出てこない。様相論理は必然・現実・可能を神から分離し、単なる形式科学上の特性と見なす。こうした形式科学的な発想は一般にAIなど現代の技術革新を推する原動力となっている。」(P.135)
和語の世界
「「できる」は「いでく(出で来)」の変形。原意は「出てくる」「出現する」「現れる」。自分が何かをするのではなく、何かの自発的な現出を我が身に引き受ける、その現出を見届ける、の意。欧州的な主体の能動的行為能力とは無縁。これが明治以降、英 can の翻訳語に充てられた。can はゲルマン語で「学んで知っている」が原意。中世から近世にかけて論理的可能性及び主体的能力を表す語彙となった。」(P.136)
「「あたう」は「あつ(当つ)」(命中する)と「あふ(会合遭)」の合成語。的を射た状態(肯定的評価対象)に遭遇する(我が身に引き受ける)、転じて正鵠を射ており理に適う、納得がいく、の意。」(P.136)
「「〜し得る」中の動詞「得る」はどうか。祖形は「う」。入手する、我が身で受け止める(受身)、が原意。自発・可能の意もある。和語の世界で重要な役割を果たす語(詳細は第8章で)。can のような主体に備わる能力を指す語ではない。can と同様、(FF)論理的可能性を意味し得るが、「得る」の「可能」は元来、恩恵を我が身に受けるという利害関係。」(P.136-137)
「総じて、デュナミスや can に発想レベルで対応する和語はない。それゆえ、明治期に漢語新造語で訳したのは理に適っている。だが、翻訳者たちが can を再現する語彙として「能力」「可能」を提案し流布させても、能力を発動する主体という欧州的自己意識が日本に定着するわけではない。」(P.137)
「エルゴンはどうだろうか。」(P.137)
「「す」は「する」の古形。元来は「香ぞす(香りがする)」のように周囲に漂うものを感じ受け止める、の意(指示詞「そ」と近縁、第8章参照)。つまり、能動的な働きかけではなく、むしろ受け身を指す。中古以降、人の動作の意が生じ、明治以降は英 do の訳語にもされたので、「する」は主体的能動を表すと思われがちだが、実は背後に受け身性が共鳴している(話者が主体的に為すのではなく、為されたことに話者が触れ、引き受ける、という発想)。「仕事」も労働や作品そのものというより、それを人による所業と感受する受け手(話者)の心を含意する語彙。和語の世界は能動性に乏しい。」(P.137)
「エネルゲイアに相当する発想の和語もない。」(P.137)
第8章 能動と受動
「「能動」は英 active 、「受動」は英 passive の翻訳語。初出は田中義廉の『小学日本文典』(1874年、英文法書に倣って編纂された日本語文法教科書)。」(P.139)
「active・passive の源泉は二系統ある。一方は古代ギリシアの動詞ペア ποιέω 〔ポイエオー〕・ πάσχω 〔パスコー〕。もう一方はディオニュシオス・トラクスの文法用語 ἐνέργεια 〔エネルゲイア〕・ πάθς 〔パトス〕。
古代ギリシアの用語
「ποιέω 〔不定形 ποιεῖν 〔ポイエイン〕)の原意は「制作する」。」(P.139)
「プラトンの時代からは「する」(英 do に相当)という広義でも使われた。名詞形は ποίησις 〔ポイエーシス〕(制作行為)や ποίημα 〔ポイエーマ〕(制作物)。(LF)πάσχω (不定形 πάσχειν 〔パスケイン〕)の原意は「被る」「受ける」「(何らかの目に)遭う」。」(P.139)
「名詞形 πάθος も元来は降りかかる不幸(病気など偶発事)、受ける仕打ち、境遇などを指したが、後には外的原因による心の可変的状態(FF)一般、価値中立的な状態一般をも指した。ポイエイントパスケインは元来、「食べる」「歩く」と同様、それぞれ数ある動作行為状態の一種。相互に独立で対立しない。能動(する)・受動(される)という対立語(上部概念)として使われ始めたのは紀元前5世紀。」(P.139-140)
アリストテレスのの用法
アリストテレスから文法学へ
「アリストテレスは言葉が事物の名前だと素朴に考え、文法に立ち入らなかった。」(P.142)
(ディオニュシオス)「彼は能動を ἐνέργεια 〔エネルゲイア〕、受動を πάθος 〔パトス〕、中動を μεσότης 〔メソテース〕と呼んだ。前者二つはアリストテレス用語。能動は「人が肉を着る」や「比嘉木材を燃やす」などにおける動詞の語形(不定形で τέμνειν〔テムネイン〕、κάειν 〔カエイン〕)、アリストテレス的に言えば人や火(始原因)を主格としてその能動能力の発動を表現する語形。受動は「肉が切られる」「木材が燃やされる」など、肉や木材(質料因)を主格としてその受動能力の発動を表現する語形(不定形は τέμνεσθαι 〔テムネスタイ〕、καίεσθαι 〔カイエスタイ〕)。」(P.143)
古代ローマ
「倫理学については、アリストテレスが制作(ポイエイン)と行為( πράττω )を峻別した。前者はその始原因(制作者)が目的因(制作物)の外にある。後者はその始原因(行為者)が目的因(成されるべき行為)の内にある(自分自身の行為が目的)。制作は技術と自然学の問題、行為は倫理学の問題とされた。トマスはこれを踏襲、制作を factio、行為を actio と呼んで区別する。」(P.145)
「こうした actio・passio の用法は概してトマス以降のスコラ哲学者たちにも継承される。文法的な能動(主格)・受動(対格)が、自然学的な能動(始原因)・受動(質料因)、倫理的な能動(行為者)・受動(目的・客体)、そして神学的な能動(神)・受動(被造物)を覆うように、スコラ的世界観の軸を形成する。」(P.145)
近世以降
「デカルトは思考実体(魂)と延長実体(身体)を分離し、この二つの実体間の能動・受動(橋渡し)が因果関係にほかならないと考えた。スピノザはこの二世界説を却下する。自己原因である神のみが実体である。」(P.146)
「ニュートンの第三法則は通称、作用( actio )・反作用( reactio )の法則。人が壁を押すと、壁は力を受ける( passio )のみならず、人へと逆向きで同じ大きさの力を反作用させる(二つの力は釣り合う)。デカルトも物体の運動・静止をこうした力の衝突や均衡で説明した。actio・reactio ペアは自然(物理)学に浸透、やがて actio (能動)・passio (受動)ペアに代わり標準語彙と化す。」(P.147)
トマス・ホッブズ(Thomas Hobbes, 1588年4月5日 - 1679年12月4日[1])
ルネ・デカルト(仏: René Descartes、1596年3月31日 - 1650年2月11日)
バールーフ・デ・スピノザ(Baruch De Spinoza [baːˈrux spɪˈnoːzaː]、1632年11月24日 - 1677年2月21日[1])
ジョン・ロック(英語: John Locke FRS、1632年8月29日 - 1704年10月28日)
サー・アイザック・ニュートン(英: Sir Isaac Newton、ユリウス暦:1642年12月25日 - 1727年3月20日[注 1])
ゴットフリート・ヴィルヘルム・ライプニッツ(ライブニッツ、Gottfried Wilhelm Leibniz ドイツ語: [ˈɡɔtfʁiːt ˈvɪlhɛlm fɔn ˈlaɪbnɪts][1][2][3]あるいは[ˈlaɪpnɪts][4][5] 、1646年7月1日(グレゴリオ暦)/6月21日(ユリウス暦) - 1716年11月14日[6])
イマヌエル・カント(Immanuel Kant ドイツ語: [ɪˈmaːnu̯eːl ˈkant, -nu̯ɛl -]、当て字は「韓圖」[1]、1724年4月22日 - 1804年2月12日)
ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル(Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770年8月27日 - 1831年11月14日[1])
フェルディナン・ド・ソシュール(Ferdinand de Saussure、1857年11月26日 - 1913年2月22日[1])
エトムント・グスタフ・アルブレヒト・フッサール(Edmund Gustav Albrecht Husserl ドイツ語: [ˈʔɛtmʊnt ˈhʊsɐl]、1859年4月8日 - 1938年4月27日[1])
マルティン・ハイデッガー(ドイツ語: Martin Heidegger, 1889年9月26日 - 1976年5月26日)
エイヴラム・ノーム・チョムスキー(Avram Noam Chomsky、1928年12月7日 - )
「実は、能動・受動は印欧語の一部に特有の、しかも後発的に(数千年程度前に)備わった構造。世界には能動・受動の対立を欠く自然言語も存在する。たとえば和語である。」(P.149)
「能動」「受動」「中動」と和語
「印欧祖語は能動・受動ではなっく、能動・中動の区別を基本とした。比較言語学的にそう強く推測されている。古代ギリシア語は中動と受動が併存状態で、前者が後者に置き換わりつつあった。」(P.149)
「中動態とはなにか。バンヴェニストは古代ギリシア語に棹差してこう特徴づける。(『一般言語学の諸問題』)。能動態は、主格から出発してその外部で進行する動き変化を表現する形態(「燃やす、καίω 〔カイオー〕など)。中動態は、主格を場として進行する動き変化や状態、すなわち主格がその動き変化・状態の内部にあることを表現する形態(「横たわる、κεῖμαι 〔ケイマイ〕」など)。中動態における主格は、当該の動き変化・状態が成立するために必要不可欠であり、その動き変化・状態をまさに被りつつある当のもの。中動態は、主格が外部から独立に自己の内部で完結させる(あるいは主格自身が受益する)動き変化・状態とも形容できる。主格から発出する動き変化であっても、主格がその動き変化に内在するなら、中動態が用いられる。(「自分の体を洗う、λούομαι 〔ルーオマイ〕」など)。(LF)他方、受動態は、自らが発出源でない動き変化・状態に、主格が巻き込まれることを表現する形態。主格は外的な他者が発出させた動き変化・状態を被ることになる。受動態の κεῖμαι は「横たえられる」、λούομαι は「洗われる」。つまり、能動・受動の対立は、動き変化・状態の発出源が主格かそれ以外かの対立。能動・中動の対立は、主格が動き変化・状態に外在的か内在的かの対立。両対立において能動の特徴づけは違ってくる。受動と対立する能動は、主格が発出源となる動き変化。だが、これは λούομαι のような中動態の一部についても言えるので、中動と対立する能動の特徴づけとしては的外れ。中動と対立する能動は、その主格が動き変化・状態の外部にあることの表現である。」(P.149)
「自然的事物も人も神もこの全体の中に部分として位置づけられ、その位置を自らの運命として受け入れる。これは後にプラトンやアリストテレスが θεωρία 〔テオーリア〕(神の目線で見た光景)と呼んだもので、ギリシア自然哲学の母胎となり、近現代物理学へもつながった世界観である。同じ印欧系でも、アーリア人のヴェーダやペルシア人のアヴェスタが一方的に神々を崇拝するのみであるのと対比すると、極めて特徴的と言える。こうしたアイティアへの問いの浸透と軌を一に、中動態から受動態への転換が進んだ可能性がある。」(P.150)
「こうした変遷を貫いて変わらぬ文法的特徴が欧州語には二つある。一つは、受動に対する能動の優位。」(P.151)
「主格の能動という文法構造は、ギリシア自然学とキリスト教を貫いて欧州の精神世界に深く根ざし、哲学のみならず心理、学術、そして法律を規定してきた。19世紀以降、欧米発の科学が徹底的な世俗化の推し進めた後も、自由意思を備える個人(主格)の能動という図式は人々の思考や行動を強く規定している。」(P.151)
「もう一つは、能動・中動・受動を通じた主格の遍在。印欧語の文は主格を前提し、その人称(一人称〜三人称)や数(単数・総数・複数)に合わせて動詞が形態変化する(英語は変化をかなり喪失した)。能動・中動(受動)はそれぞれ別の変化をする。神や人を含むあらゆる事物が動詞の主格となり得る。主格が能動的・中動(受動)的に関与する動作行為状態関係の総体が、欧州語にとっての世界。中動から受動への移行も、主格主導を保ったままのものだった。(LF)この能動・受動のキリスト教・近代バージョンが、安土桃山期に、そして江戸末期以降は本格的に、日本に導入された。」(P.151)
「だが、能動・受動という形での世界解釈は和語から自生したものでなく、和語の世界を反映していない。日本語話者の実生活に定着してもいな(FF)い。「学ぶ」「学ばれる」の対立は学校で学ぶが、実生活で「学ばれる」とは口に出さない。」(P.152)
「る」「得(う)」「す」における自発・可能・受身
「古形「(せ)らる」の原意を確認したい。これは「す」の未然形と助動詞「らる」の複合形。「らる」は「る」の別形。「る」は四段活用動詞などの未然形に、「らる」は下二段活用動詞などの未然形に、後置される。「る」「らる」〔現代語形「れる」「られる」、以下「る」で代表)は学校文法で用法が自発・可能・尊敬・受身へと区別される。」(P.152)
「つまり、「る」は子音 r と「得」の合成形と解せる。「得」は手に入れる、(獲得済みで)秀でる、できる、と意味が広がる。話者に未獲得だったものが手に入る、未実現だったものが実現される、という利害関係を指す語。その獲得・実現は、話者の努力や働きかけによる場合もあるが、成り行き任せの自然発生であることも多い。何れにせよ、話者は身を以てその獲得・実現を引き受ける(利害に与る)。これが「得」の諸用法に通底する含意であり、そのまま「る」の通底含意でもある。」(P.152)
「「る」の用法の一つである受身(うけみ)は、現代欧州語の受動(能動と対立)とは違う。「る」が含意する受身(我が身への引き受け)に、引き受けさせる側の能動者は存在しない。」(P.152)
「「る」の受身は古代ギリシア語の受動(自らが発出源でない動き変化を主格が被る)とも違う。和語の動詞はそもそも主格を要求しない(和語の格助詞はおそらく漢文の影響で接続助詞から派生した後発的なもの)。「る」「得」は受身の当事者(話者、聞き手、それ以外の明示された人や物)の視線を前提するが、その当事者を明確に名指す必要はなく、ましてやその主格としての表示は文法的に求めない(現代語では格助詞による主格表示が可能だが)。また動き変化の発出源か否かという対立は、「る」「得」の意味成立に無関係である。」(P.153)
「中動態は、主格が動作行為状態に内在することを(人称変化パターンを伴って)表示する形態。「る」「得」は当事者(明示される必要はない)が動作行為状態に内在することを表現する語彙。発想は似るが、ギリシア語は主格を明示した言語化(言わば θεωρία 化)を文法的に求めるのに対して、和語は「る」の当事者の言語化を文法的に求めず、実際の使用局面でも言語化を回避しがち。また、中動(主格の内在)は能動(主格の外在)に対立するが、「る」「得」の当事者内在性(自発・可能・受身)は必ずしも外在と対立しない。」(P.153)
「和語には能動・中動・受動という印欧語的な対立はなく、代わりに次の動詞グループ分けが存在するように思われる。一方は、四段・ラ変に分類される動詞群(グループAとする)。「たつ」「置く」「思ふ」など欧州語で自動詞、他動詞、中動態動詞などと分類される動詞が区別なく含まれる。変化形は四段型活用(上代特殊仮名遣いでは未然から順にa、i甲、u、u、e乙、e甲)。もう一方は、上二段、下二段・上一段・下一段・カ変・サ変・ナ変に分類される動詞群(グループBとする)。「切る」「責む」「恐る」など、やはり欧州語で自動詞・他動詞・中動態動詞などと分類される語彙が区別なく含まれる。全て語幹に「得」が後置された形で、変化形は「得」に準ずる。「立つ」などはA・B両グループに属する。Bの「立つ」は「立つ」プラス「得」の短縮形、現代語では「立てる」と語形変化している。」(P.153)
「Aの「立つ」は四段活用。立つという動き変化を端的に指す。Bの「他つ」(「立つ」プラス「得」)は下二段活用、何かが(FF)立つという動き変化が話者目線から見て実現し、その(自発的)実現を話者が我が身に引き受けること(つまり、何かが立った状態が話者の眼前に実現されること。誰がその状態を出現させたか、話者なのか第三者なのか、は不問)。」(P.153-154)
「こうした「得」の論理、能動・受動の対立とはまったく異なる自発・可能・受身の論理は、古典的な和語だけでなく、現代日本語の翻訳文体の背後にも空気のごとく漂っている。欧州語の能動を翻訳再現したつもりで、実は古来の「得」の論理に支配されている。」(P.155)
「得(う)」の論理と日本の共同体倫理
「能動・受動、自動詞・他動詞という枠組みで和語を解釈できないわけではないが、それは優れて後知恵的。漢文訓読や欧文和訳を通して和語が表層的に変化を遂げた結果である現代日本語の、表層部分に対する後付け解釈でしかない。」(P.155)
「能動・中動・受動という文法構造は主格を明示する思考を話者に強要する。アリストテレスの自然学的なポイエイン・パスケイン、そして実体概念も、その産物。これが因果関係と手を携えて現代の自然科学発展につながり、また自由で平等な個人(人格)を基礎とする現代の法秩序も生み出した。」(P.156)
「だが、主格思考は日本に広まらない。文法的にこれは仕方ない。能動・受動を翻訳しようにも、手持ちの道具は主格を求めない「得」の論理に従うものばかり。」(P.156)
「欧州的な法の支配(主格的な個人の能動・受動が基盤をなす)が日本になかなか定着しないのもこれが一因だろう。のみならず、「得」の論理は、ときには話者の目線共有を聞き手や周囲に強要する無言の圧力を醸し出す。同調圧力や雰囲気に流される生き方(いじめが根絶できない原因)が強固に根を張ることになる。この空間に、能動・受動、実体・属性、原因・結果などの概念を土台に個人(法的人格)という理念を掲げ、これを実現すべく社会を改善してきた欧州思想のダイナミズムを植えるけるのは至難の業(「得」の論理は話者が個人すなわち主格となることを構造的に求めない)。それ以前の問題として、我々には「得」の論理の強靭さを自覚することすらそもそもできていない。明治以降、欧州由来の概念(特に科学技術や法的思考)が曲がりなりにも導入され、我々一人一人を取り巻く生活環境は劇的に向上してきた。その恩恵を更に享受し続けることを日本の一般市民は願っているはず。そのためには、まずは「得」の論理の遍在を自覚し、その長所・短所を見極め、欧州由来の概念装置の力を今後とも借りて短所を地道に除去していくしかない。」(P.157)__科学技術、自由・平等概念の代わりに失ったものは何か。それは失っていいほど「必要ないもの」か。一人一人が選択することなのか。
「欧州語はこれら幾つもの概念ペアを文法構造(人称変化や格支配)と組み合わせて独特の構造的世界観を析出させた。対する和語の文法構造は極めて原始的。しかし、両者の違いは優劣の差ではなく、生活戦略の差である。実際、和語の受容能力は極めて高い。欧州語の言説と知的産物の導入を和語は漢語の並行利用によりこなしてはきた。本書が指摘したいのは、この導入に際して発生する摩擦、無理、そしてひずみ。」(P.158)
第9章 理性と感性
「「感性」は西が英語の sensibility に充てた訳語。」(P.159)
「「理性」は西の新造語。原語 reason は名詞にも動詞にもなる日常語。『和英語林集成』は「道理」「ことわり」「みち」「ゆえ」「せい」「わけ」、動詞では「考える」「分別する」などと日常語で訳した。西は哲学における reason を専門用語と見なし、新造訳語を考案してこれに充てた。(LF)「理性」の類義語に「悟性」がある。明代に「利口な性質」の意で用例があり、これを西周が英 understanding の訳語に転用した。」(P.159)
「「感」は心の動き、「理」は物事に備わることわり。漢語文化圏では「理」を巡って様々な思想が展開されたが、これを「感」と対立させた思想は自生しなかった。欧州で理性と感性を初めて明確に対立させたのがプラトンとアリストテレスのイデア論。」(P.159)
古代ギリシア
「mind や soul に相当するギリシア語は ψυχή 〔プシュケー〕。原意はいのち、転じて身体から分離可能な魂や自己意識。」(P.160)
「reason に相当するギリシア語は λόγος 〔ロゴス〕や νοῦς 〔ヌース〕。前者は動詞 λέγω 〔レゴー〕の名詞形。この動詞はもともと(果実や花などを)「摘む」「選択的に摘み取る」「数える」の意だが、紀元前6世紀以降、転じて「意図的に何かを選んで口に出す(話す)」という意味で使われ始めた。この当時のロゴスは次の意味でμῦθις 〔ミュートス〕の対立概念だったことはよく知られている。すなわち、ミュートスは人前で公式になされる言明(神を称える祝詞や演説、詩の朗唱など)で、ステータスは恣意的な私的発言であるロゴスより高い。これが紀元前5〜4世紀になると逆転する。ロゴスは森羅万象を支配する真なる法則性を選りすぐって表現する語であり(ロゴスに元々あった「数える」「数で表せる比率」などの含意が幾何学の隆盛と共にこの意味を際立たせかのかもしれない)、対するミュートスはただの作り話だ、という理解が広まる。これを広めたのは自然哲学の系譜にあるプラトンとアリストテレス、そ(FF)してソフィストたち。」(P.160-161)
「ヌースはホメロスにおいて感覚や判断、理解など心の作用を広く指す。動詞形 νοέω 〔ノエオー〕も目で見る、耳で聞く、心でつかむ、判断する、などの意。日常語だったはず。これをプラトンが感性と対立する理性(イデア直観能力)を指す語に意味限定した。この限定的な語法はアリストテレスに受け継がれる。(LF)感性はギリシア語で αἲσθησις 〔アイテーシス〕。動詞形はαἰσθάνομαι 〔アシスタノマイ〕。中動態でのみ使われ、能動態はない。感覚置換する、五感で察知する、の意。語源は άἶω 〔アイオー〕(聞く、見る、覚知する)。この語は詩に使用例が残るのみ。ここから変形して αἰσθάνομαι ができたと推測される。」(P.161)
プラトンのプシュケー(魂)
「我々は感覚を信ずることなく、イデアを把握するよう務めねばならない。プラトンはこの把握を νόησις 〔ノエーシス〕、把握されたイデアを νόημα 〔ノエーマ〕、イデア把握能力をヌースと呼ぶ。」(P.161)
アリストテレスの『霊魂論(魂について)』
「すなわち、生まれながらに手足などを具備し、生きる能力(デュナミス)を持つ物体(身体)が、生命が(FF)維持された状態(エネルゲイア(3)つまりエンテレケイア)にあること。魂は睡眠中の身体にも宿る。その定義にはエネルゲイア(3)が相応しい。」(P.162-163)
古代ローマ
「デポネント動詞 reor は人の精神作用を表現する語彙のうち最も生活に密着した古来のもの(第2章参照)。「考える」「思う」が原意。「分別する」「計算する」「判断する」と意味が広がる。res はその名詞形(考えられたもの、の意)。完了分詞 ratus から別の名詞 ratio (英 reason の祖形)が派生、ロゴスの羅訳語に転用された。類義語に動詞 scio がある。こちらは原意が「割る」「割く」「分ける」。和語で古形「分く」から「分かる」が派生したように、 scio からは「理解する」「知る」の意も派生する。名詞形 scientia (英 science の祖形)はエピステーメーの羅訳語となった。」(P.167)
キリスト教から中世スコラへ
「七十人訳で「似姿」は εἰκών 〔エイコーン〕や ὁμοίωσις 〔ホモイオーシス〕。これらはプラトンがイデア(原型)に対する個物を形容して使った語彙である。羅約するとそれぞれ imago と similitudo。アウグスティヌスによれば、ちょうど個物がイデアの似姿であるように、人間は神の似姿であることになる。」(P.167)
「res は被造物、ratio は神の言葉(ロゴス)と解され、 intellectus は神に備わる理性、そして神の似姿たる人に備わる理性として捉え直される。spiritus は神の聖霊へと転義する。神が父・子・精霊という三つの位格( persona、原義は「声が響き渡ること」、転じて仮面劇で役者がかぶる仮面、劇中の登場人物などの意)をもちながら実体としては一つであるように、人間も意志・記憶・理性という三つの位格を持ち実体としては一つである、とされる(『三位一体論』13巻20章)。」(P.168)
近世における魂と心
現代における心の問題
「このような物理的・生化学的モデルで人の心が完全に説明し尽くせるか否か、見解は割れている。説明し尽くせないとする立場が持ち出すのがクオリア。これは、わくわく感や頭痛、色など、各自が主観的に体感する質感のこと。」(P.173)
「しかし、私も、友人も、コウモリも、そのりんごの赤さのクオリアを体感しているはず(各々モナド的に)。」(P.173)
「将来的に、我々の自己意識を完全に情報化して身体から機械へ移し替え、我々が自己意識の上で死ねなくなる(情報空間場で永遠に生きつづける「人格」と化す)可能性が開かれ得る。可死的な身体を医学的に延命するより、このほうが技術的にも簡単となる時代の到来が予想される。そうなれば無痛社会への欲求は完全に充足される。」(P.173)
和語の世界
「和語で生命や精神を指す語は幾つもある。「いのち」は「往ぬ」(過ぎゆく、過ぎ去る)と「うち(内)」の合成語と推測される。」(P.174)
「「たま」は美しいもの、かけがえのないもの(玉)が原意。転じて、かけがえのないものとして命を比喩的に表現する(霊、魂)。」(P.174)
「「たましひ」は「たま」と「強ひ」の合成語。「強ひ」は「強ふ」の使役の「しむ」(下二段、他者が我が意に服した状態の可能・自発・受身が原意)と類縁。上代の「たましひ」は「たま」から溢れ出る強さ、分別、才能や機転(特に対人関係で発揮される力)を指した。これが明治以降、プシュケー系の欧州語彙(理性・感情の二分を伴う)の訳語に転用され、語源の忘却につながった。(LF)「こころ」は「くくる(括る)」の母音交代形。括られ閉ざされた内面の思い、が原意。謎かけをする落語家に「そのこころは」と問うのは、閉ざされた意図を明かしてほしい、という懇願。」(P.174)
「分(別)かる」は古形が下二段「分(別)く」、分(別)かれた状態の自発・可能・受身(「得」の論理に従う語彙)。ここから理解の意が派生した。道が分かれる、血筋が分かれる、などが原意に沿った用例。主体の能動を表現する語彙ではそもそもない(漢語の「分」「別」は物理的分離の意。「分別」は「理解する」の意で、「理解」も「悟り知る」の意で古来漢籍に用例あり)。」(P.176)
「「知る」は何かを了解している、制御できる、支配する、が原意。暗黙知も含意す(FF)る。普遍的なエピステーメーやその能動的獲得を指す語ではない。漢語「知」は認識の意。「知解」(認識すること)、「知性」(或る人のさとい性質)、「知識」(世の道理を知ること)、「知覚」(知り悟ること)は古来漢籍(主に漢訳仏典)で用いられた語彙。」(P.176-177)
和語の世界と共同体の倫理
「しかし、理性・感性という概念的二極分化は和語の世界に根づかない。人格概念も宙に浮いたまま。喜怒哀楽に浸り、人との関わり「たましひ」を示しつつときに疲弊し、またあるときには閉じた心を開いて美しきものを愛で、歌を詠み、技を磨き、小宇宙的な世界に耽溺する、万葉以来の日常がひたすら繰り返されている。外来の翻訳概念の流通を輸入業者(翻訳者)が試みても、一般市民は概して関心を示さない(一時的に流行することがあってもじきに忘却される)。生活の具体的改善に役立つもの、便利なものなら飛びつくが(16世紀の鉄砲、現代のコンビニやスマホなど),そうでないものに食指は動かない。我々の日常はかくも啓蒙拒否的、保守的である。保守されているのは、「得」の論理に守られている共同体(家族、学校、地域、職場、国家、等々)で自発する価値規範。」(P.177)
「ムラ社会的な価値規範を備えた共同体において、人は「人格」として平等ではなく、共同体中で自発偶発する地位と同一視され、地位で値踏みされる。」(P.177)
「第8章で敷衍した「得」の論理が支配する和語の世界には、こうした同調圧力に身を置く心はあっても、ギリシア自然学的な魂、ローマ法的な人格、キリスト教的被造物としての人格、近代欧州が掲げた自由で平等な尊厳ある人格(法的に守られるべき(FF)存在)はない。」(P.177-178)
「啓蒙というより実利的な観点で、つまり自分自身や大切な人々の身を守るために、こうした浸透を進める努力、法的文脈で人格概念を道具的に使いこなす努力を我々は地道に続けたほうがよい。」(P.178)
第10章 普遍と特殊
「「普遍」は『哲学字彙』が英 universal に充てた訳語。「あまねく」を意味する古来の仏教語の転用。原語の淵源はアリストテレスの論理学用語 καθόλου 〔カトルー〕。κατἀ μέρος 〔カタ メロス〕(英 particular )、καθ´ ἓκαστον 〔カタ ヘカストン〕(英 singular )と三組をなす。西周はこの三つをそれぞれ「全称」「特称」「単称」(いずれも新造語)と訳した。(LF)『和英語林集成』は universal を「一般」と訳した。「一般」は一様な、一切合切、などの意で江戸期以来の日常頻用語。『哲学字彙』は「一般」を general (genus 「類」の形容詞形)の訳語に充てた。類は種(英 species、形容詞形は special )と対語。アリストテレス論理学で類種ヒエラルキー(ポルピュリオスの樹、第4章参照)をなす。」(P.179)__ポルピュリオスの樹(ぽるぴゅりおすのき、ラテン語: Arbor porphyriana、英語: Porphyrian tree)は、プラトン派のポルピュリオスが考案した樹形図[1]。古典的な認識論的分類システムの一つ。範疇論の古典として知られるアリストテレスの『範疇論』とその入門書であるポルピュリオスの『エイサゴーゲー』は、その両方がポルピュリオスの樹を基礎として議論を展開した。更にそれらの起源は、プラトンの「ディアイシス」の概念まで遡る。(Wiki)
καθόλου、κατἀ μέρος 、καθ´ ἓκαστον
「καθόλου は前置詞 κατά 〔カタ〕と ὃλος 〔ホロス〕(FF)の合成語。κατά は「下へ(に)」(英 downwards )から転じて「〜にむかって」「〜に合わせて」「〜に関して」「〜について」と意味が広がる。これと用法が完全に一致する前置詞は羅独仏英に存在しない。(LF)ホロスは英 whole と同語源、「まるまる全部」「まるごと」の意。」(P.179-180)
「メロスは「分前」が原意、 μόριον 〔モリオン〕「一部」や μόρος 〔モロス〕「運命」と同根。神々が各人に振り割った運命的なもの、という含意がある。動詞形は μείρομαι 〔メイロマイ〕、「(名誉などみずからの正当な分け前を神々から)割り当てられている」の意。」(P.180)
「ホロスとメロスは対立語になることが多い。数の1がホロスなら2分の1はそのメロス。(中略)我々一人一人、宇宙やポリス(ホロス)の中に部分(メロス)として位置づけられる。これが我々にとっての運命(メロス)である。メロスはホロスを前提する。プラトンが希求したイデアは、我々が逃れがたい運命、すなわちホロス(不死なる魂)の中にあるメロス(個々のイデア)として、定冠詞に読み入れられた。」(P.180)
「自分の意志で左右できない運命を甘受する思想は、航海民族的なものかもしれない。第3章で言及した神の眼差しの下での立ち尽くし、第4章で述べた帰依を迫る一神教的な厳格さ、第6章で敷衍した因果関係の厳格さはどれもイデアの中動態的な運命論に淵源があると考えられる。」(P.180、注)
καθ´ ἓκαστον は κατά とἓκαστος 〔ヘカストス〕の合成語。後者は英 every に相当。ἑκάς (離れて、それぞれ)あるいは形容詞 εἳς (一つの、英 one に相当)から派生したと推測される。ホロス・メロスと関係づけるなら、ヘカストスはホロスをメロス以(FF)上に分割し、行き着いた単位(個別、要素)。メロスを更に細分化して初めてヘカストスに至る(メルスが個別の集合体である)場合、メロスがそれ以上細分化不能でそのままヘカストスとなる(メロス自体が個別である)場合、どちらもあり得る。」(P.180-181)
プラトンにおける全体と部分
「すなわち、難題を抱えているが、イデアはやはり一つの全体であり、同時に自らを個別者の数だけ分身させている、と言わざるを得ない。イデアのこの二重性格を名指すために、後にアリストテレスは καθόλου (普遍)という語彙を新造した。「普遍」という語に長年親しんでいる我々は、普遍という事象を指すのに「普遍」とひとこと言えば足りる。しかし、プラトンはこの語彙を持たなかった。「個別」についても同様。彼は普遍と個別の対立を定冠詞と複数形に棹差して自覚し、ホロス以外にもエイドスやうシアなど様々な日常語に訴えて四苦八苦しながら、人々に理解させようとした。」(P.181)
アリストテレスにおける全体と部分
(『形而上学』)「5巻25章はメロス(部分)に次の5つの用法を区別する。(1)量的なものを分割した結果(たとえば数2は数3のメロス)。(2)その分割の果に到達される単位・要素(FF)(この意味で、3のメロスは2でなく1である)。(3)形相に関して、類を分割して出てくる種(この意味で、人間は動物のメロス)。(4)個物(形相質料結合体)を形相と質料へ分割したとき、そのうちの質料(この意味で、青銅像のメロスは素材としての銅)。(5)形相に関して、その本質・定義を構成する要素(この意味で、人間のメロスは「理性的」と「動物」)。(5)の意味では類が種のメロス、(3)の意味では種が類のメロス。」(P.181-182)
「続く26章はホロスの用法を二つに大別する。(1)メロスが欠落なく全部揃っていること(たとえばクラスの全員の出席)。(2)多くのメロスが集合してまとまりをなすこと。」(P.182)
「総じて、アリストテレスは全体が部分に勝る(たとえばポリスは個人に勝る)、部分は全体の中で初めて意味を保つ、と考えた。プラトンのイデア論も同じ考え方。アリストテレスはイデア論を個体重視で修正しただけ。両者とも古代ギリシアの中動態的な運命論(全体の中で自らに割り振られた運命を引き受け、自らを全体の中に位置づけることで初めて自らの意味を見出す、という世界観)の体現者。」(P.183)
古代ローマ(ラテン語圏)
「ラテン語はギリシア語より早く中動態を失った。ローマにも法と神々に身を委ねる運命論的な発想はあるが、運命を前にした意思の無力さという中動態的な世界観はない。」(P.186)
ポルピュリオスとキリスト教
スコラ
「教義上、個物と普遍はどちらも被造物であり、その区別は神による被造性という観点では霞んでしまう。より重要なのは、そもそも唯一神が世界(普遍と個物)を無から創造したこと。このような創造は元来、セム系の人々に特徴的な考え方で、印欧語族に元来は希薄だった。ギリシア自然哲学もこれと無縁(制作という観点はあるが、無からの創造はない)。」(P.189)
近世における普遍と個別
近現代の論理学
「欧州語における定冠詞や複数形という文法的特徴がこうした構造的な世界観を生み出した。この所産に匹敵するものを、ギリシア・欧州文化圏以外の地域は生み出すことができなかった。(LF)他方、古代ギリシア由来の普遍・個別ペアが近世の機械論や現代の形式科学により相対化され、その原型(形相を宿す個別というビジョン)が破棄されたのも事実である。」(P.194)
和語の世界
「端的に言って、和語は普遍・個別という相の下に世界を見ない。明治以降、この対立の所産が欧州から日本に大規模に流入した。日本語生活者はこれを巧みに漢語翻訳語で写し取り、生活に活かし、国土の風景を一変させていった。これは和語の世界にこの対立が定着したことを意味しない。この対立は知識として理解されてはいても、和語の世界を全く侵食していない。」(P.194)
「欧州語の定冠詞はもともと和語なら「そ」(「それ」「その」)に相当する指示詞だった。」(P.194)
「何れにせよ、「そ」は状況(話者)依存性が高く、発話行為現場に縛られる語彙。他方、プラトンのイデアはこうした依存性から独立し自存する普遍的存在(今風に言えば客観的実在)。ギ(FF)リシア人はこうした存在を中動態的な宿命( θεωρία 〔テオーリア〕)として投影し、元来は状況依存性が高い指示詞をその徴表(定冠詞)に転用した。」(P.194-195)
「ホロスに相当する漢語「全体」「全部」の「全」は、玉の境地に入ること(完全無欠性)。「全体」は体の全て、「全部」は何巻にも及ぶ書物の一揃え全て。和語の「すべ(全)て」は下二段「すぶ(統)」の連用形と接続助詞「て」の合成語。「すぶ」は(複数のものが)まとめられた状態の自発・可能・受身が原意(「得」の論理)。転じて、支配統治の意にもなる(「すめらみこと」)。四段「すむ(澄、清)」と同語源。こちらはまとまることで動きや混濁が消失する、が原意。転じて、乱れた状態をなくす、従わせる、の意も生じる。「すぶ」には(まとめられるべき)全体が前提されるが、この全体とはまさに無秩序・騒乱状態。これを指す和語彙はない。」(P.195)
「しかし、「ひと」も「まる」も部分から構成されるという含意はない」(P.195)
「量子力学のような確率論的世界は要素還元思考の行き詰まりを示す。とも指摘されるが、確率論も数学的構造というイデア的法則性の追究結果である点に変わりはない。こうしたイデア追究的な世界観は、そもそも和語の世界と親和的ではない。全体と部分を対立させ、部分を支配する全体を観照( θεωρία )し、この全体の中に自らを主格思考により位置づけて自己制御に活かす。これが科学技術と法の支配に共通する発想である。ギリシアの全体主義的な美徳は、同調圧力に屈するという和語の世界の美徳に外見上、似ている。だが、和語の世界には主格思考(個を前提する)がない。日本における同調圧力への迎合は、各自の部分(個)としての自己意識に因るものでなく、「得」の論理に支配された無私の自発・可能・受身である。」(P.196)
「何れにせよ、我々は主格思考が根づきにくい和語の限界を自覚し、その限界を踏まえつつ法の支配を一層定着させ、一人一人の尊厳がより守られる環境整備(地球環境の保護を含めて)を今後も地道に続けるしかないだろう。」(P.196)
あとがき
「だが、所産を生み出す原動力である理念信仰(欧州哲学)そのもの、そしてその母胎である欧州語の文法構造(主格思考、定冠詞、能動態・受動態など)は、日本語に導入できるものではない。実際、導入されておらず、導入する必要もない。和語の世界に生きる人々は文法構造上、イデアの民であり得ない。今後もイデアの民でないままだろう。これは価値評価でなく事実問題である。」(P.198)
「それをそれぞれが自覚し、欧州の理念信仰が培ってきた科学技術と法律を道具だと割り切って使いこなしていけば、世界の未来は多少、明るくなるだろう。」(P.199)