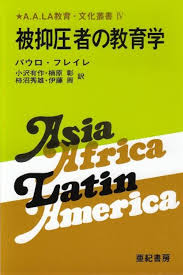日本語版読者へのメッセージ
一九七九年冬 パウロ・フレイレ
序章
(P.2)__自由・不正・進化。人間にはなぜ翼がないか。
(ヘーゲル『精神現象学』)「そこで自由を保証してもらうためには、生命を賭けねばならない。・・・敢えて生命を賭けなかった個人は人格とは認められようけれども、自律的な自己意識として承認されているという(FF)真理には達してはいない(樫山欽四郎訳 河出書房新社 一一八頁)。
だが、自由への恐怖を公然と認める人間はまれである。」(P.3-4)
「しかし、かれらは自由を現状維持と混同している。」(P.4)
「右翼セクト主義者にとって、今日は過去と結びつけられており、それはすでに前もって与えられている不変なものなのである。左翼セクト主義者にとっては、明日は前もって布告され、すでにうごかしようもなくさだめられてしまっているものである。」(P.7)
「未来とは受け取るべく与えられるものではなく、人間にとって創造されるべきものであ(FF)る。」(P.7-8)__たしかに「時間」や「歴史」は人間が作り出したものである。でも、いつまでこのようなことを言わなければならないのだろうか。
「ジャーナリストのマルシオ・アルヴェス Marcio Moreira Alves は、かつて私に「かれらは両方とも疑い欠乏症にかかっている」といったものだ。」(P.8)
Ⅰ なぜ被抑圧者の教育学か?
一 なぜ被抑圧者の教育学か? 人間化の課題をめぐって
(P.16)__日本でオンロトジーが広まらないのは、当たり前だから。日本でオントロギーが進むとは西欧化が進んでいること。
「この闘いは、非人間化が具体的歴史的事実ではあるけれども、けっして与えられた運命などではなく、むしろ抑圧者のなかに暴力を呼びおこし、(FF)その暴力がさらに被抑圧者を非人間化するような不正な秩序の産物であるからこそ、可能なのである。」(P.16-17)
二 抑圧者ー被抑圧者の矛盾とその克服
「自分たちの寛大さを見せびらかす機会を確保しつづけるために、抑圧者は不正をもまた同時に行い続けていかなければならない。
不正な社会秩序がこの寛大の永遠の源泉であり、それはし、絶望、貧困によってはぐくまれる。」(P.18)__政治そのもの。
「こうした現象が生ずるのは、それは被抑圧者が日常経験のある時点で、抑圧者にたいして同化しようとするする態度をとるからである。
このような環境のもとにあって、被抑圧者は自分を対象化できるほど明瞭に、 つまり、自分がその環境の外側にいることを発見しうるほど明瞭には、自分自身について考察することができないのである。」(P.19)
「抑圧の現実に埋没しているために、かれらは自らを被抑圧者として自覚できないのである。」(P.20)__自覚(意識)できないものが存在するか。対象と考えれば存在する。
「かれらが農地改革を望むのは、人間を解放したいからではなく、土地を獲得して地主になりたいからである。」(P.20)
「被抑圧者は、自由を受け入れるのを恐れるが、抑圧者は、抑圧する自由を失うことを恐れる。」(P.21)
「抑圧者と被抑圧者のあいだをつないでいる基本的要素のひとつが命令 prescription である。一人の人間の選択を他人に強制することはどのような命令にも見られることである。それによって、命令される人間の意識は命令者の意識にしたがうものへと変えられてしまう。」(P.21)
「被抑圧者は、抑圧者のイメージを内面化しかれの指針に身をゆだねているので、自由への恐怖を感じている。自由は、かれらがこのイメージを放棄し、それにひきかえて自律と責任をもつことを要求するだろう。」(P.22)
「自由は人間の外側におかれた理想ではなく、また、神話となる観念でもない。それは、人間の完成を追求するうえで不可欠な条件である。」(P.22)
「とはいえ被抑圧者にしても、かれらを呑み込んでいる支配構造に順応してあきらめきってしまい、闘いが要求する危険を冒すことができないと感じているかぎり、自由を求める闘争に立ち上がることはとてもできるものではない。
そのうえ自由のための闘いは、抑圧者だけではなく、さらにいっそう大きな弾圧を恐れているかれら自身の抑圧されている仲間をも脅かす。自由になりたいという熱望を自らの内に見いだすとき、かれらは、この熱望が現実のものとなりうるのは、それは同じ熱望が仲間のあいだにも呼びさまされるとき以外にはないということを知らせるのである。
だが、自由への恐怖に支配されているあいだは、かれらは他者に訴えたり、他者の訴えに耳をかしたり、あるいは自らの良心の訴えに耳を傾けることさえ拒んでいる。かれらは、真の仲間同士のつながりあいよりも、烏合の衆でいる方を望む。
かれらは、自由および自由の追求そのものから生みだされる創造的な親交 communion よりも、不自由な状態のままでいられる従属の安全性の方を好む。
被抑圧者は、かれらの内面がもっと奥深いところにできあがってしまった二重性に苦しんでいる。かれらは、自由がなければ確固として生きてゆくことができないのを発見する。だが、かれらは確かな存在を求める一方で、それを恐れている。かれらは、自分自身であると同時に、抑(FF)圧者でもある。それは、かれらが抑圧者の意識を自分のものにしてしまっているからである。」(P.23-24)__自縄自縛。自由が近代西欧的概念であることは確実である。日本にはなかった。それは抑圧がなかったからではない。それは身分制に隠れていたのか。抑圧・被抑圧構造の違い。近代西欧においても、自由を求めたのはブルジョアである。民衆(農業を含めた一種のギルド)はいまよりも抑圧を感じていなかった。ブルジョアが感じた「自由」とは、経済の自由である。信仰の自由(キリスト教内であるが)はその一面に過ぎない。ユダヤ(商人であり金融)という失われた民族の欲望である。
「被抑圧者が自らの解放の闘いに取り組むことができるためには、かれらは抑圧の現実を、出口のない閉ざされた世界としてではなく、変革しうる有限の状況として認識することが必要である。」(P.25)
「抑圧者が被抑圧者との連帯を示すことができるのは、かれが被抑圧者を抽象的範疇としてみなすことをやめ、たえず不当に扱われ、声を奪われ、だまされながら労働を売ってきた人間として見すえるとき、つまり、かれがいかにも敬虔な、感傷的な、個人主義的な思わせぶりをやめて、愛の行為に自らを賭けるときだけである。真の連帯は、この愛の行為の充足のなかに、その実存性のなかに、その実践のなかにのみ見いだしうる。」(P.27)
「主観性を欠いた客観性など考えられない。」(P.27)__Nota Bene!!
「客観性(FF)を主観性から切り離すこと、現実を分析したり現実に働きかけたりするときに、主観性を否定してしまうことは、客観主義である。」(P.27-28)
「ここで提出されているのは、客観主義でも主観主義でもなく、また、心理主義でさえもなく、たえざる弁証法的関係のなかにおかれている主観性と客観性である。」(P.28)
「マルクスが批判し科学的に論破したのは、主観性ではなく、主観主義と心理主義であった。」(P.28)__主観性と主観主義。
「この目的を達成するためには、被抑圧者は批判的に現実と対峙すると同時に、現実を対象化しそれに働きかけなければならない。
こうした現実への批判的介在をともなわないたんなる認識は、客観的現実の変革にいたることはないだろう。それはまさしく真の認識ではないからである。」(P.30)
「勝手に理屈づけられた真実をかかえもつ事実は、否定されはしないがその客観的基礎は失われている。それはもはや具体的存在であることをやめて、認識者の階級を防衛するためにつくられた神話となる。」(P.31)
「不信をもたらすのは、愛されることのない人びとではなく、自分をしか愛さないがゆえに人を愛することのできない人びとである。」(P.37)
三 抑圧の具体状況と抑圧者
(P.40)__七〇年安保のとき、学生運動の頃、資本に大切だったこと、郊外報道を減らすこと、金儲け。
「抑圧者にとっては、自分たちだけが人間であり、他者は物にすぎない。また、かれらにとって、権利はひとつしかない。つまり、かれらが平和に暮らすための権利である。それは、必ずしも承認されているわけではないのだが生きのびるためにあてがわれている被抑圧者の権利とは、まったく対照的なものである。かれらがこうした権利を被抑圧者にあてがう理由にしても、ただ被抑圧者の存在がかれらの存在に欠かせないからにすぎない。」(P.41)
「人間性とは物であり、かれらはそれを誰にも譲りわたせない権利として、世襲財産として所有する。」(P.43)
「所有階級として持つことを利己的に追い求めている内に、自分の所有のなかで窒息してしまい、もはや生きているのではなく、たんに持っている存在でしかないことに、かれらは気づかない。かれらにとって、より多く持つことは、奪うことのできない権利、すなわち、自分だけの努力によって、勇気をふるい危険を冒しながら獲得した権利である。
ほかの人びとが多く持たないのは、それはかれらが無能で怠惰だからである。」(P.43)__いまでは被抑圧者も「持つことが生きることだ」と思い、借金をしても闇バイトをしても「持つ」ことにこだわる。その反面、持つのは「物(物質・実体・手で触れるもの)」ではなくて「データ」になりつつある。
(フロム『人間の心』)「サディズムの目的は人間を物に、生物を無生物に変えてしまうということである。かくして、完全かつ絶対的統制によって、生き物は生命の本質 すなわち、自由を失うのである。」(P.44)__自由とは生命であること。それなら納得できる。
「対象物としての、物としての被抑圧者は、抑圧者によって命じられた目的以外の目的をもつことはない。」(P.45)__ロボット、パソコン、AI。
四 抑圧の具体状況と被抑圧者
「したがって、自らの抑圧者を、ついて、自らの内側の意識を具体的に発見するまでは、かれらはつねに状況に対して宿命的態度をとる。」(P.47)
「現実のなかに埋没しているために、被抑圧者は抑圧者の利益に奉仕しているこの秩序をはっきりと見分けることができない。それほどまでにかれらは、抑圧者のイメージを内面化しているのである。」(P.48)
「その反面、被抑圧者は現実経験のある時点で、抑圧者の生き方にたいして、抑えがたい魅力を感じている。」(P.49)__それこそが抑圧者意識の内面化。現代でも「物を欲すること」それも「生活と関係が薄い奢侈品・贅沢品・高級品」を。そして、模造品を買ってすぐゴミにする。
「自己卑下は被抑圧者のもうひとつの性格であり、それは抑圧者がかれらにくだす評価の内面化から生まれる。」(P.50)__Nota Bene!!
「かれらは自分を無知な者と呼び、「教授」は知識のある人、自分が耳を傾けるべき人であると言う。」(P.51)
「自分たちもまた物事を知っているということ、つまり自分たちもまた世界と他者との関係のなかで学習をしてきたのだということが、かれらにはまるっきり理解できない。
かれらの二重性を生みだした環境を考えてみれば、かれらが自分自身を信用しないのも無理からぬ噺である。」(P.51)
「かれらはよく、自分と動物とはひとつとして違うところがないと言い張る。違いを認めるときでさえも、動物の方をたてる。
「やっこさんたちは、われわれよりも自由なんだから。」」(P.52)
「かれらは、抑圧者が不死身で強大な力を有しているという広くいきわたった呪術的信仰にこりかたまっている。」(P.52)
「まことに、ボスはかれらの内部にいたのであった。
被抑圧者は、抑圧者にもさまざまな弱点があることを見出さなければならない。そのことによって、これまでのものとは反対の確信がかれらの内部に育ち始めることができるのである。この確信が生まれるまで、かれらは気力を奪われ、恐れおののき、うちのめされつづけるだろう。」(P.53)__抑圧者の弱点は抑圧者であること。つまり被抑圧者を必要としているということ。被抑圧者に依存していること。
(農民とのインタビューから)「かれはボスといっしょにいるときはうっ憤をはらしたりしない。」(P.54)
五 抑圧からの相互解放 省察と実践の共有をとおして
「被抑圧者の解放行為への思慮深い参加なしにかれらの解放をこころみることは、かれらを、燃えている建物から救い出さなければならない客観物として扱うことである。」(P.56)
「しかしながら、最善の意図をもってする指導 leadership でさえ、自立を贈物として授けることはできない。被抑圧者の解放は人間の解放であって、物の解放ではない。
したがって、自分一人の努力だけで自分を解放できる人もいなければ、他者によって解放される人もいない。人間的現象である解放が、亜人間 semi-humans によって成し遂げられることはありえない。」(P.57)
「同様に、被抑圧者は(もしかれらに確信がなければ闘争に関与しないし、そうした関与が行われなけれ(FF)ばこの闘争に必要な条件を満たすことはできないのであるが)、客体としてではなく主体としてこの確信に到達しなければならない。」(P.58-59)__「無痛文化論」。誰に向かって書かれたものか。大衆向けなら理解不能だ。著者の自己満足にすぎない。学者に向けて書くしかないし、その場合の学術用語を前提すべきではない。あるいは日本語(翻訳語)を。
(フロム『人間の心』)「・・・創造し、建設し、疑い、冒険を企てるための自由。このような自由は、個人が奴隷やたらふく食わされた機構の歯車であることをやめ、活動的で責任ある人間であることを要求する。・・・人間が奴隷でないというだけでは十分ではない。社会条件が人造人間の存在をいっそう助長するとすれば、その結果生まれてくるのは、生への愛ではなく死への愛である。」(P.60)
「人間性を取り戻すために、かれらは物であることをやめ、人間として闘わなければならない。こ(FF)れは根源的な要求である。かれらが客体として闘争に加わり、その後で人間になるなどということはありえない。」(P.60-61)__主体性=人間。
第二章 銀行型教育と課題提起教育
一 預金行為としての教育 非人間化をもたらす教育
「語りかける内容が、価値についてであろうと現実に関する経験的事柄についてであろうと、それらは語りかけられる過程で生気を失い、硬直してしまう。教育は、一方的語りかけという病に陥っている。
教師は、現実があたかも不動で、静止していて、明確に分類された、予言可能なものであるかのように語る。」(P.65)
「こうして、教師の言葉は具体性を失い、空虚な、阻害されまた阻害する饒舌となる。」(P.65)__饒舌=じょうぜつ。
「一方的語りかけ(それはつねに語りかける人である教師によるものであるが)は、生徒を語りかけられる内容の機械的な暗記者にする。さらに悪いことには、かれらはかれらはそれによって容器、つまり、教師によって満たされるべき入れ物に変えられてしまう。
入れ物をいっぱいに満たせば満たすほど、それだけかれは良い教師である。入れ物の方は従順に満たされていればいるほど、それだけかれらは良い生徒である。」(P.66)
「だが結局は、人間自身がこの(よくできても)誤った方向に導く制度のなかでは、創造力、変革の可能性、知識を喪失し、磨り減らされてしまうのである。探求から引き離され、実践から切り離されては、人間は真に人間になることはできない。知識は創造 invention と再創造をとおしてのみ、また、人間が世界のなかで世界とともに、相互に追求する不断の、やむにやまれない、永続的で、希望に満ちた探求をとおしてのみ、生まれてくるものである。
銀行型教育にあっては、知識は、自分をもの知りと考える人びとが、なにも知っていないとかれらが考える人びとに授ける贈物である。他者を絶対的無知としてみなすのは抑圧イデオロギーの特徴であるが、探究の過程としての教育と知識はそれによって否定される。
教師は、生徒に対して必然的な対立物として自らを演ずるようになる。生徒の無知を絶対的なものとみなすことによって、かれは自分自身の存在を正当化するからである。
ヘーゲルの弁証法における奴隷のように疎外されている生徒は、教師が存在するのは自分たちが無知だからと考える。だが、ヘーゲル弁証法の奴隷とは違って、自分たちが生徒を教育するということにはけっして気がつかない。」(P.67)
「それどころか銀行型教育は、抑圧社会を全面的に反映している次のような態度と実際上の行為によって、矛盾を維持しあまつさえ刺激しているのである。
1 教師が教え、生徒は教えられる。
2 教師がすべてを知り、生徒はなにも知らない。
3 教師が考え、生徒は考えられる対象である。
4 教師が語り、生徒は耳を傾ける おとなしく。
5 教師がしつけ、生徒はしつけられる。
6 教師が選択し、その選択を押しつけ、生徒はそれにしたがう。
7 教師が行動し、生徒は教師の行動をとおして行動したという幻想を抱く。
8 教師が教育内容を選択し、生徒は(相談されることもなく)それに適合する。
9 教師は知識の権威をかれの職業上の権威と混同し、それによって生徒の自由を抑圧する立場に立つ。
10 教師が学習過程の主体であり、一方生徒はたんなる客体にすぎない。」(P.68)__銀行型教育の10の特徴
「生徒の創造力を最小限に抑え、摘み取り、かれらの軽信をあおりたてる銀行型教育の機能は、世界を解明したいとも思わなければ、それが変革されるのを見たいとも思わない抑圧者の利益に仕えるものである。」(P.69)
「この目的を達成するた(FF)めに、抑圧者は銀行型教育概念と合わせて温情主義的社会活動装置を用いる。その装置のなかで被抑圧者は、福祉受領者という婉曲ないいまわしの称号を与えられる。かれらは個人的ケースとして、つまり、立派に組織された正しい社会の一般形態から逸脱した周辺人 marginal men として取り扱われる。被抑圧者は健全な社会の病理とみなされるのである。」(P.69-70)__「お上の世話」「福祉や行政、法律が助けてくれるんだから」。独立することは不可能。
「かれらはつねに内側に、かれらを他者のための存在にした構造の内側におかれてきたのである。解決策はかれらを抑圧構造に統合することにあるのではなく、かれらが自分自身のための存在になれるようにその構造を変革することにある。」(P.70)
「現実との関係をとおしてかれらは、現実がたえず変革しつづけている過程であることを感じとるであろう。」(P.72)
二 銀行型教育 教師ー生徒、エリートー民衆の矛盾
「銀行型概念では、暗黙裡に人間と世界の二分法が仮定されている。すなわち、人間は世界や他者とともに存在するのではなく、たんに世界のなかにあるにすぎない。人間は再創造者ではなく、傍観者にすぎないのである。
この見解によれば、人間は意識的存在 corpo consciente ではなく、むしろ意識の所有者、現実についての預金を外界の世界から一方的に受け入れるべく開いている空虚な心にすぎない。」(P.73)
「そして、人間が世界を受動的存在として受け入れるのであるから、教育は人びとをいっそう受動的にし、世界に順応させるべきだ、ということになる。教育のある人間とは順応した人間のことである。」(P.74)
(フロム『人間の心』)「・・・経験より記憶が、生きることよりは所有することが、ここでは重要なのである。ネクロフィラスな人が客体 花や人 とかかわりあうことができるのは、かれがそれを所有するときだけである。したがって、自らの所有に対する脅威は、自分自身にたいする脅威である。もし所有物を失うとすれば、かれは世界との接触を絶たれるのである。・・・かれは支配を愛し、支配することによって生命を抹殺する(フロム『人間の心』)。」(P.76)__バイオフィリー(生命への愛)、ネクロフィリー(死せるものへの愛)。記憶は(原則)変化しない。(認識も?持続する。)実践だけが記憶を動的なものにする。
(同)「(自分の)行動能力を回復すること。だが(かれらに)それが可能だろうか。可能ならどのようにして。ひとつの方法は、権力をもつ個人や集団に服従し一体化することである。(人間は)このような象徴的な参加によって自分が行動しているという幻想をもつのであるが、現実には(かれらは)、行動する人びとに服従しその一部となるにすぎない(フロム前掲書)。」(P.77)
「支配権をにぎるエリートが考える治療手段は、いっそうの支配と抑圧であり、それは自由、秩序、社会平和(エリートの平和にすぎないが)の名のものとで実行に移される。」(P.78)
三 課題提起教育 世界への介在
「したがって、課題提起教育の実践は、なによりもまず最初に、生徒―教師の矛盾の解決を要求する。そうでなければ、認識者が協力して同じ認識対象を認めるさいに不可欠な機能、つまり対話関係は、成り立つことはできない。」(P.81)
「対話をとおして、生徒の教師、教師の生徒といった関係は存在しなくなり、新しい言葉(ターム)すなわち、生徒であると同時に教師であるような生徒と、教師であると同時に生徒であるような教師 teacher-student with students-teachers が登場してくる。」(P.81)
「ここには、誰かを教えるだけの者も、自分一人で学ぶだけの者もいない。
人びとはお互いに教え合う。世界によって媒介され、また、銀行型教育では教師によって所有される認識対象によって媒介されながら、相互に教えあうのである。」(P.82)
「自由の実践としての教育は、支配の実践としての教育とは反対に、人間が抽象的存在で、世界から孤立し、独立し、切り離されているという考えを認めない。それはまた、世界が人間とはかけ離れた実在であるという考えも否定する。」(P.84)__他者の否定。
「我は非我なしには存在できない。反対に非我は我の存在に依拠している。」(P.85)
(フッサール『純粋現象学及現象学的哲学考察』)「この紙の周囲には書物、鉛筆、インク壺等々が、ある仕方でやはり『知覚』されて、知覚的にはそこに、『直観の野』に在る。けれども私が紙に注意を向けているあいだはそれらはいかなる注意も把捉も たんに第二次的なるそれといいども 受けていない。それらは現出はしたのであるが、しかし取り出され、それ自身として措定されはしなかったのである。」(P.86)__知覚しないでも世界があるということは、知覚(自覚)しなくても我があるということである。
「人間と世界の弁証法的関係は、この関係がどれだけ知覚されているかということとは無関係に(あるいはそれがまったく知覚されていようといまいと)存在するけれども、人間がとる行動形態は、かれが世界のなかでどれだけ自分自身を知覚しているかに応じて大きく機能を変える。」(P.87)
(P.88)__注意する・指向することによって、あるいは言語化し、単語化する、すなわち「話す」ことによって明らかになる。->対象化の別名だけれども、必要な気がする。壊すためには。
四 歴史的使命としての人間化
第三章 対話 自由の実践としての教育の本質
一 対話 自由の実践としての教育の本質
「言葉の中にはふたつの次元がある。省察と行動がそれである。それらは一方が一部なりとも犠牲にされれば、他方もただちにその影響をこうむるほど、根源的に相互作用しあう関係にある。同時に実践とならない言葉は、真の言葉とはいえない。したがって真の言葉を話すということは、世界を変革することである。」(P.95)
「対話とは、世界を命名するための、世界によって媒介される人間と人間との出合いである。」(P.97)
二 対話と対話的教育
「しかし対話は、世界と人間にたいする深い愛がなければ存在しえない。創造と再創造の行為である世界の命名は、愛の息吹を吹き込まれないかぎり不可能である。」(P.98)
「さらにまた、対話は希望がなければ存在しえない。希望は、人間が未完成だからこそ生まれるのである。」(P.102)__対話の不可能性ではなく、対話の不完全性。すべてを語ることはできない。なにかが欠けている。相手が必要だから。デジタル化で、データの増加とともに、その欠損はどんどん増えていく。
「閉ざされた思考の持ち主にとって重要なことは、この標準化された今日への順応である。批判的に考える者にとって重要なことは、人間をた(FF)えまなく人間化するために、現実をたえまなく変革することである。」(P.103-104)__「人間」を対象として、概念として考えると、その「完全」なることが必要になる。たんに存在として考えたとき、「不完全な個体(個別)」(つまりアイデンティティがない)というものは矛盾である。
「閉ざされた思考にとっての目標は、この保障された空間にしがみつき、それに順応することにほかならない。こうした時間性の否定によって、閉ざされた思考はその思考自体をも同時に否定するのである。」(P.104)
三 教育プログラム編成の基礎としての対話
(毛沢東「文化運動における統一戦線」選集第三巻、邦訳第七巻)「大衆に結びつくには、大衆の必要と自発的意思に従わなければならない。大衆のためのすべての活動は大衆の必要から出発すべきであり、たとえ善意ではあっても、個人的願望からは出発すべきではない。多くのばあい、大衆は、客観的には、ある種の改革を必要としているが、かれらの主観においては、なお、そのような自覚がないのであり、大衆が、なお決意をくださず、なお改革を望まないかぎり、われわれは辛抱づよくまたなければならず、われわれの活動を通じて、大衆の多数が自覚をもち、決意をくだし、自ら改革の実行を望むようになるのをまって、その改革を行わなければならない。さもなければ、大衆から遊離することになるであろう。」(P.107)
「すなわち革命指導者が民衆を訪ねるのは、救いのメッセージをもたらすためではない。それは民衆との対話をとおして、かれらがおかれている客観的状況とそれについてのかれらの自覚、つまり自分と世界、自分がそのなかで、それとともに存在するところの世界についてのさまざまな知覚の水準に精通するようになるためである。」(P.109)
四 生成テーマとその教育プログラム内容
(メモ)__何ものも命名するのを避けること。「新語」をつくらないこと。命名することで、その全体性が失われる。それは個物としての特性を失い、範疇(カテゴリア)となってしまう。
「対話的教育の目的が解放にある以上、探求の対象は(人間がまるで解剖学的断片であるかのように)人間であるはずはない。対象は、人間が現実に言及するために用いる思考 言語、かれらがその現実を知覚する水準、生成テーマの源泉であるかれらの世界観である。」(P.111)
「動物はその活動から自己を切り離すことができず、それゆえに自己省察ができない。この一見表面的な区別のうちに、その生活空間内のそれぞれの行動を限界づける境界線が横たわっている。動物の活動は自己の延長であるから、その活動の結果もまた自己と切り離すこと(FF)ができない。」(P.112-113)__境、界、縁なのか、その中なのか。なんか重大な意味がありそう。日本語の語源からいうと、坂(さか)のようなので、縁(坂)で区切られた内部ということではないか。それが内部とともに縁をも指すようになったのではないか。
「英語では、生きる live という用語と存在する exist という用語は、語源とは反対の意味をもつようになった。ここで使われれいるように、生きるの方はより基礎的な用語であって、ただ生き延びることだけを意味し、存在するの方は、転成する becoming 過程のなかにより深くかかわることを意味している。」(P.114)
「人間は、自己を世界から切り離して対象化し、自分の活動からも自己を切り離す。」(P.115)
「生物の活動の所産であって、その刻印を受けてはいるが物質的身体には属さない生産物だけが、状況に意味の次元を与えることができる。この状況はこうして世界となる。このような生産の可能な生物は、必然的に自分自身を自覚する自分自身のための存在であり、自分の関係する世界のなかに介在することなしには、けっして生きることができない。まさにこの生物が存在しなければ世界も存在しないのと同様である。」(P.117)__Nota Bene!! そうなんだけど、そのことがけっして自己の存在を正当化するものではない。なぜ生きなければならないのか、その言い訳としてなぜ種は生き延びようとしたと思うのか。その答えは「神がそう定めた」と思う以外にあるのか。
五 生成テーマの探求とその方法
「自由への恐怖が、かれらに根本的なものを覆い隠す防御機制と合理化とを生ぜしめ、偶然性を強調して具体的現実を否定させる。」(P.123)__自由の刑との矛盾。自由であるが、だからこそ自由であること、理性でコントロールされ予測される自由からはみ出すことの恐怖。その意味での自由や出合いを無痛文明は許さない。
「部分から全体へ戻る必要がある。さらにその主体は、客体(コード化された具体的な生きた現実状況)のなかで自己を認識し、その客体を、他の主体といっしょになって、そこに自己を発見する状況として認識する必要がある。」(P.125)
「解読のすべての段階で、人間は自己の世界観を客観化する。」(P.126)__P.23-24 抑圧者の内在化。客観的に世界を見、主体を確立させることが、被抑圧者の解放につながるのか。その結果、解放された世界は主客構造に支配されないか。支配者がなく、被支配者だけがいる世界。支配者は存在として必要か。それは神でもいいのか。主従、支配・非支配関係を主客関係と同一視してよいか。
(P.127)__健康は維持するものから管理するものになった。
「こうしてテーマの探求は、現実にめざめ自己にめざめるための共通の努力になり、それが教育の過程あるいは解放をめざす文化行動のための出発点になるのである。」(P.128)
六 生成テーマの探求と意識化の実践
「変化を否定はしないが望みもしないという人は、変化のなかに、生の兆候ではなく、死と衰退の兆候をみる。」(P.130)
「人間はその埋没状態から脱却する。そして現実のヴェールがはがされるにつれて、そこに介入する能力を獲得する。現実への介入は、歴史的自覚にほかならず、脱却からの一歩前進を意味している。それは状況の意識化の所産である。」(P.131)
(P.133)__ウガンダの青年がいる村には井戸の技術がなかったのだろうか。そうは考えられない。失われたのだろうか。どうしてそれは伝わらなかったのだろうか。「商品」に囚われた(侵された)途端、伝わらなくなったのではないか。
「訪問中、探求者は研究地域に批判的にねらいを定めるのであるが、それはまるで地域が、巨大で独特な、解読されるべき生きた記号 code であるかのようである。」(P.134)
(P.137)__real エネルゲア、potential デュミナス -> 可能ではあっても、制御できることではない。
「農民が議論に興味をもつようになるのは、コード表示がかれらの切実な要求と直接結びついているばあいだけだということである。」(P.142)
第四章 文化行動の理論
一 反対話的行動理論と対話的行動理論
「動物は世界を考察せず、そのなかに埋没している。これと対照的に人間は、世界から脱却し、それを対象化しつつ、労働をとおして世界を理解し変革することができる。」(P.159)__本当にそうなのか。そういう思い込みをしているだけではないのか。「世界から脱却し」ているなんで、妄想と思い上がりではないのか。実際世界がなければ、人間は一秒たりとも生きていけないのではないか。世界から独立していて、世界を制御(支配)できると考えるのが、支配者の思考なのではないのか。被抑圧者(解放者)はそれを内在化しているのではないのか。あなたは世界、あるいは他者から脱却しているのか。
「人間の活動とは理論と実践 practice であり、省察と行動にほかならない。」(P.159)
「支配者が支配を行うためには、民衆に真の実践を許さず、民衆が自分の言葉を話し、自分の頭で考える権利を否定する以外に道はない。」(P.161)__プラスチック・ワード。
「抑圧者は被抑圧者に入り込み、被抑圧者に宿っているのだ。」(P.162)
「民衆のために革命を行うことは、民衆なしで革命を行うことに等しい。なぜなら民衆は、自分たちを抑圧するために用いられるのと同じやり方で、その過程にひきずりこまれるからである。
すべての真実の革命に必要不可欠なのは、民衆との対話である。」(P.163)
「交流を妨げることは、人間を物の状態に還元することである。」(P.164)
「すなわち、私が実践を擁護するとき、そこには、この実践を、先行する省察の段階とそれに続く行動の段階に分割してしまう二分法はまったく含まれていない、ということである。行動と省察は同時に生起する。」(P.164)
「批判的省察もまた行動なのである。」(P.165)
「革命過程における親交の拒否、民衆を組織し革命の力を強化するとか、統一戦線を確立するとかの口実のもとで行われる民衆との対話の回避、これこそまさに自由への恐怖にほかならない。それは民衆にたいする恐怖、もしくは民衆への信頼の欠如である。」(P.165)
「人間的ではない歴史的現実などは存在しない。人間なしの歴史もなければ、人間のための歴史もない。あるのはただ、マルクスが指摘するように人間によってつくられ、逆に人間をつくる、人間の歴史だけである。多数者が支配され疎外されるようになるのは、かれらが主体として歴史に参加する権利を否定される、まさにそのときである。」(P.168)
「革命指導者は、民衆なしで考えることも、民衆のために考えることもできない。なしうるのは民衆とともに考えることだけである。
支配者としてのエリートは、逆に、民衆なしで考えることもできるし、現にそうしている。」(P.169)__官僚。
「したがって一見エリートと大衆との対話や交流とみえるものはすべて、実はコミュニケを預ける行為であり、その内容は感化して手なづけるように目論まれている。
支配者としてのエリートは民衆とともに考えないにもかかわらず、なぜ気力が衰えてしまわないのだろうか。それは、民衆がかれらの対立物、つまりかれらの存在理由そのものだからである。(LF)(FF)
そしてエリートは自分たちと民衆との縦の関係こそが自らの存在を証明するものであることを知る。革命過程にあっては、出現しつつある指導者が存在証明を獲得する道はひとつしかない。すなわちかれらは、被抑圧者をとおして、かれらとともに生れかわるために、死ななければならない。
抑圧過程では誰かが他の者を抑圧する、といいきってよい。革命過程では、誰かが他の者を解放するとか、誰かが自己解放を遂げるなどということはできない。親交のなかにある人間同士が互いに解放しあう、といいうるだけである。」(P.169)__Nota Bene!! 西欧の思考は西欧でケリを付けてもらう。他文化はそれぞれ独自の方法がある。日本において社会主義(無政府主義)がエリートの学問だったことは間違いない。それが学校で教えられるかどうかに関わりなく、文字の思想である。アイデンティティが西欧化しているように日本も西欧化している。商品文化。日本の闘争は日本の支配者層にたいするものだし、それは自分たちの商品文化に対するものである。
「抑圧者の非道にも、革命的ヒューマニズムにも、ともに科学が用いられる。前者に役立つ科学と技術は、人間を物に還元するために使われる。後者に役立つとき、それらは人間化を促進するために用いられる。だがそれでも、被抑圧者は、自分たちがたんなる科学的興味の対象として見られ続けることがないように、後者の過程の主体にならなければならない。
科学的な革命的ヒューナニズムは、革命の名において被抑圧者を分析対象としたり、その分析にもとづいて、行動命令を与えられるべき対象としてはならない。もしこれを行えば、無知の絶対化という抑圧者のイデオロギー神話のひとつに陥ることになろう。」(P.173)__ナイーヴすぎる。科学が客体化だから主体になる必要がある。しかし、それは矛盾であろう。精神が肉体の主人だとでもいうのだろうか。たとえそこに「無意識」や「潜在意識」を持ってきても説明にはならない。
(革命指導者は)「なるほどかれらは、その革命意識のおかげで、民衆のもつ経験知の水準とは別の革命的知識をもっていると、自認することができよう。それでもかれらは、自らとそのもてる知識を民衆に押しつけることはできない。かれらはスローガンで民衆を引きまわしてはならないのである。むしろ民衆との対話に踏み込まなければならない。そうすれば現実についての民衆の経験知は、指導者の批判的知識によって豊かにされ、しだいに現実を根源的にとらえる知識に変わってゆくようになる。」(P.174)
「ときとしてこの言葉は語られることさえないのである。民衆のなかに宿っている抑圧者を脅かすことのできる者(それは必ずしも革命集団のものとはかぎらない)が現存するだけで、民衆が破壊的立場を取るに十分である。」(P.175)
「しかし革命は、解放がなければ革命ではないという意味で、不可避的に教育的性格を有するものであるから、権力の掌握とは、それがいかに決定的であろうとも革命過程における一契機にすぎないのである。過程として考えれば、革命以前なるものは抑圧社会のなかに位置し、革命意識にとってのみ見えてくることである。
革命は抑圧社会の内部で、社会的実体として生まれてくる。だからそれが文化行動であればあるほど革命は、それを生ぜしめた社会的実体の、潜在する可能性に、必ず一致せざるをえない。すべての実在は、その矛盾の相互作用によって、それ自体の内部で発展し、あるいは変革される。外的諸条件はもちろん必要であるが、それが有効に働くのは、その潜在する可能性と一致するばあいだけである。」(P.177)
「革命のきざしは、古い抑圧社会の内部で芽生える。権力の掌握は、連続的革命過程の決定的な一契機にすぎない。革命を静的にではなく動的にながめるかぎり、権力の掌握を境とした絶対的な革命以前や革命以後などないのである。
革命は、客観的諸条件に起因し、人間の社会を連続的解放過程のなかに引き入れることによって、抑圧状況を廃棄しようとする。革命の教育的対話的性質は、革命を同時に文化革命たらしめるところのものであって、革命のどの段階にも存在していなければならない。この教育的性質は、革命が反革命的官僚制のなかで制度化されたり、人を序列化したりするものに変わることを防ぐ、もっとも有力な手段のひとつである。このようにいうのは、反革命というものが、反動化した革命家によって実行されるからにほかならない。」(P.178)
二 反対話的行動理論とその特徴
(1)征服
「この目的のために抑圧者は、世界の考察者としての人間の資質を破壊しようと務める。だが抑圧者は、この破壊を全面的に成し遂げることができないので、世界を神話化しなければならない。抑圧者は、被抑圧者や非征服者がものを考えるときの材料として、かれらの疎外と受動性を強めるように仕組まれた欺瞞の世界を提供するために、一連の方法を開発する。それは、世界を課題として提示することをまったく排除し、むしろ固定した実在、与えられたもの、人間がたんなる傍観者としてそこに順応しなければならないものとして世界を説明する方法である。」(P.182)__Nota Bene!!
「以下にその神話を例示しておこう。
抑圧者的秩序を0とする神話。
だれもが自分の働きたい場所で自由に働き、もしボスが気に入らなければかれのもとを離れて別の仕事を探すことができるという神話。
この秩序は人権を尊重するがゆえに、尊敬に値するという神話。
勤勉であれば、だれでも企業家になれるという神話。(FF)
さらにひどいのは、街頭商人は大工場主と同じくらい立派な企業家であるという神話。
小学校に入学したブラジルの子どもたちのなかで、大学までいくのはほんの一握りであるにもかかわらず唱えられる、普遍的な教育権という神話。
「誰に向かって話しをしているのかわかってんだろうな」といったいい方が、いまだに私たちのあいだにはやっているというのに主張される、すべての人間の平等という神話。
唯物論者の野蛮から西洋のキリスト教文明を守る守護者としての抑圧階級の英雄的行為なる神話。
階級として実際に行っていることが、選択的善行(それは結局、ローマ教皇ヨハネ二十三世が国際的レベルで厳しく批判した公正無私の援助という神話へと巧みにつくりあげられる)の奨励であるにもかかわらずいわれる、エリートの慈悲と寛大という神話。
「支配者としてのエリートはその義務をわきまえており、民衆の向上をうながしてくれるのだから、民衆は感謝の念をもってエリートの言葉を受け入れ、かれらにしたがうべきだという神話。
反乱は神に背く行為だという神話。
個人としての人間の発展(抑圧者だけが真の人間だというかぎりで)にとって基本的なものとされる私有財産なる神話。
抑圧者は勤勉で被抑圧者は怠惰で不正直だという神話。
同様に生まれながらにして被抑圧者は劣等で抑圧者は優秀であるとする神話。」(P.182-184)__Nota Bene!!
「被抑圧者を服従させるためには、これらすべての神話(読者のあげるものも含めて)を内面化させることが不可欠である。これらの神話は巧みに編成されたプロパガンダとスローガンによって、(FF)大衆伝達媒体をとおして、こうした疎外状態がまるで真実の交流をなすかのように、かれらに提供されるのである。」(P.184-185)
「私が批判するのはメディアそのものではなく、その使われ方である。」(P.185)
「征服の内容と方法は歴史的に変化する。支配者としてのエリートが存在するかぎり変わらないものは、死体愛好症的な情熱である。」(P.185)
(2)分割統治
「統一、組織、闘争などの概念は、たちまち危険であるというレッテルをはられる。」(P.186)
「抑圧的な文化行動の特徴のひとつで、献身的ではあるが理解の浅い専門家当人にはほとんど意識されていないものに、問題を全体性の次元からみるのではなく、部分的なものの見方を強調する、ということがある。コミュニティ開発計画のなかで、ひとつの地域ないし地区がより小さな地域社会に分割されるばあい、これらの地域社会が全体の一部として研究されることなしに分割されていけばいくほど、疎外はいっそう大きくなるだろう。」(P.186)__最終的には「個人」。それは全体(関係性・対話)から切り離されている。
「それらは、被抑圧者の弱みのひとつであるが衣食住の不安定を、直接関節に利用する行動形態である。被抑圧者は、抑圧者を宿している存在としての自らの二重性において不安定なのだ。かれらは抑圧者に抵抗する一方、かれらの関係のある特定の場面では、抑圧者に魅せられるのである。」(P.191)__衣食住を desire 渇望に変える社会。
「職を失ってブラックリストに名を連ねること、それは他の職業からも閉め出されることを意味するが、これなどは良い方である。かれらの生活の不安定は、このように、労働の奴隷化と直接結びついている(それはスプリット司教が強調したように、まさにかれらの人格の奴隷化を意味している)。
人間がどれだけ己を全うできるかは、ひとえにかれらがどれだけ(人間の世界である)自らの世界を創造し、どれだけそれを変革的労働によって創造するかにかかっている。人間の人間としての完成は、それゆえ、世界の完成にある。仕事の世界にいることが、人間にとってまったく依存した不安定な状態にあること、常時脅かされていることであるならば、つまりかれらの労働がかれらのものでないならば、人間は己を全うすることはできない。自由でない仕事は、すでに自己実現の追求たりえず、非人間化の有力な手段となる。」(P.191-192)
「だからこそ、抑圧者は、農民を都市労働者から孤立させておかなければならないのである。ちょうど、両者を学生から孤立させておかなければならないように。」(P.192)
「すなわち、学生は無責任(FF)で無秩序であるということ、工場労働者と農民が国家の発展をめざして働かなければならないのと同様に、学生の本分は勉学にあるのだから、かれらの証言は偽りであるということを。」(P.192-193)__学生(非労働者)は一人前の人間ではないということ。日本の60-70年代も同じだった。現在はそれが十全なものとなっている。戦前、戦中は中学(旧制中学)生は大人だった。現在は大学生でも子供。バイト(闇バイトを含む)は昔以上にしているが。
「人間は、個人としても階級としても、己自身で己を救うことはできない。そのことは救いの理解のしかたと無関係である。この点にこそかれらの誤りがある。救いは他者とともにのみ成し遂げられる。」(P.193)
(3)大衆操作
「一定の歴史的条件の範囲内では、大衆操作は、支配階級と被支配階級との協定、表面的には階級の対話という印象を与えかねない協定によって成し遂げられる。だが現実には、こうした協定は対話ではない。真の目標は、まぎれもなく支配者としてのエリートの利害関係によって決定されるからである。つまるところ協定は、支配者が自らの目的を達成するために用いるものである。」(P.196)__インディアンとの協定。儲けるものがいれば損するものがいる。「みんなが大家さん」なら「店子」は存在しえない(「大家さん」は名前だけのものになる)。儲ける・損する、搾取する・される。みんなが儲けたように見せるための「成長」「発展」「株価」。
「大衆操作をとおして、支配者であるエリートは、民衆を偽りの組織化へと導くことができ、これによって、すでに出現しつつある民衆の真の組織化という、恐るべきもうひとつの道を回避することができる。
大衆操作という行為から生まれる組織化においては、民衆は、たんに指導されるだけの対象として、操作者の目標に順応させられる。真の組織化においては、各人は組織する過程で能動的であり、組織の目標にしても他からの強制ではない。第一のばあい、組織化は愚民化 massification の手段であり、第二のばあいは解放の手段である。
歴史過程に踏み込むとき、民衆にはふたつの可能性しかない。解放のための組織化を行うか、エリートによって操作されるか、このどちらかである。」(P.197)
「しかしながら、とくに国のなかでもずっと産業化の進んだ中心地においては、被抑圧者の大部分を、都市プロレタリアートが占めることがある。この部分は、ときとして反抗的ではあるものの、革命意識に欠けており、自分たちを特権者とみなしている。一連の欺瞞と約束をともなう大衆操作は、通常ここに格好の土壌を見い出す。」(P.198)__Nota Bene!! 都市には末端の労働者も多い。かられは、「都市に住んでいる」ということで、自分の優位さを感じている。それがなければ生きていけないからだ。それで闇バイトに手を出しても都市で生きようとする。それは、食べるためでもあるが、都市で生活することそのものが大変だからだ。都市における遊びや服装は高額である。交流そのものにお金をかけなければならない。だから「孤独」である。商品に囲まれていかざるをえないこと。生活手段が「商品」しかないのだ。お金がないことが孤独を強い、交流をはばむ。都市においては賃労働者であるしかないし、それが優越感でもあり、地方に帰ることは逃げることである。親も友人も羨ましい(支配者の意識を内包している)から、帰ってきた彼らを歓迎できない。それは自分の内なる支配者を否定することになるから。せいぜい地方の支配者である「親」の仕事を継ぐことが免罪符になるだけである。親の仕事を継いでも、やはり地方では他者(支配者)なのではないだろうか。おごることによってしか自分を認めてもらえない。そしてそれが地方の仲間の内なる支配者意識を強化する。ドラマの影響でそう思うのかもしれないが、それが意識を代表するように見えて意識を形づくる。マスコミの「大衆操作」である。それを製作する人の意識はやはり「都市の優越性」をもっている。ただ、それが「エリート意識」や「大衆操作」だという認識はないだろう。「良いものを作ろう」という思いそのものが「エリート意識」「優越感」なのだ。テレビ局に努めているということそのものが「すごいこと」なのだ。
「大衆操作の状況のなかでは、左翼はほとんどつねに、急いで権力を回復することに心を奪われ、被抑圧者といっしょになって組織を鍛えあげることの必要性を忘れて、支配者としてのエリート(FF)とのかなわぬ対話のなかへさ迷い込む。そのあげく、これらのエリートによって操作されるところとなり、自らエリートの術中に陥ることが少なくない。そしてこれを、左翼は現実路線と称するのである。」(P.198-199)
「ポピュリスト指導者は、たんに操作を行うだけで、真に人民の組織化のために闘うことをしない。だから、この種の指導者がまがりなりにも革命に貢献することなどほとんどないのである。曖昧な性格と二面行動をやめ、断固として民衆の側につき、こうしてポピュリストたることに終止符を打つことによってのみ、かれははじめて大衆操作と縁を切り、組織化という革命的任務に献身するのである。この時点でかれは、民衆とエリートの仲介者たることに終止符を打ち、エリートと矛盾するものになる。するとエリートは、彼を押さえつけるためにただちに力を結集する。」(P.200)
「なぜならば、大衆操作の道具としての福祉計画は、究極的には征服の目的に一役かっているからである。それらは麻酔の役割を果たし、被抑圧者の真の原因とそれらの解決策から、被抑圧者の目をそらせてしまう。」(P.203)__福祉に依存する民衆をつくることは、民衆を自立(自主性)できなくしてしまう。
(4)文化侵略
「慇懃であろうと乱暴であろうと、文化戦略は、このように、常に侵略される側の文化に属する人びとへの暴力行為である。」(P.204)
「侵略者は雛型をつくり、侵略される人びとはその鋳型にはめられる。侵略者が選択し、侵略される人びとはその選択にしたがう、あるいはしたがうように期待される。侵略者が演技し、侵略される人びとは、侵略者の演技をとおして、演技の幻想のみを抱く。」(P.204)__親が子に演技し、教えることは侵略か。
「侵略とは、つまるところ、一種の経済的文化的支配である。侵略は中心社会 metropolitan society が依存社会 dependent society にたいして行うこともあれば、(FF)同一社会内におけるある階級の別の階級への支配に内在することもある。
文化的征服は、侵略される人びとの文化の真正さを喪失させるにいたる。かれらは侵略者の価値や規範や目標に感応し始める。」(P.204-205)__依存社会は、中央にたいする地方でもあり、資本にたいする消費者でもある。
「文化戦略においては、侵略される人びとが、自らの目ではなく侵略者の目で現実をみるようになることがどうしても必要である。なぜなら、かれらが侵略者をまねればまねるほど、侵略者の地位はますます安定したものになるからである。
文化侵略が首尾よく成し遂げられるためには、侵略される人びとが本来的劣等生を確信するようになることが肝心である。」(P.205)
「侵略者の価値は、こうして被侵略者の手本となる。侵略が強化され、侵略される人びとが自らの文化の精神と自分自身から疎外されればされるほど、ますます侵略者のようでありたいと思うようになる。つまり侵略者のように話したいと願うのである。
侵略される個人の社会的我 I は、すべての社会的我と同様に、社会構造における社会 文化関係のなかで形成される。」(P.206)__若者と・年寄の対立、子供と大人の対立、子供を支配する大人と支配される子供。福祉や慈悲・愛情の名を借りて。その対立はまさに現代社会を反映し、現代社会を再生産しているのだ。支配―被支配、宗主国―植民地、そして学校における教師―生徒。大人―子供。
「文化侵略は、一方では支配の手段であり、他方では支配の結果でもある。したがって支配の性格を帯びた文化行動は、他の反対話的行動形態と同じように、巧妙に計画されたものであると同時に、別な意味では抑圧的現実のたんなる産物にすぎない。
たとえば、硬直した抑圧社会の構造は、必然的にこの構造内の育児と教育制度に影響を及ぼす。(FF)これらの制度は、構造様式にならってその機能を定め、その構造についての神話を伝達する。家庭と学校(育児室から大学まで)は、抽象のなかにではなく、時間と空間のなかに存在する。それらは、支配構造の内部で、将来の侵略者の養成機関として機能するところが大きい。家庭における親子関係は、通常それをとりまく社会構造の客観的文化的諸条件を反映する。家庭に浸透してくる諸条件が権威主義的で硬直した威圧的なものであれば、家庭には抑圧の空気が広がるだろう。」(P.206-207)__親が子供に教育(育児)という名で、制度を押しつける。しかし、そこにはヴァナキュラーなものも潜んでいる。そのヴァナキュラーな部分を子供は「古い」とする。そしてそれに反抗するわけであるが、その反抗そのものが「人として生きる(コンヴィヴィアリティ、ヴァナキュラー)」という部分を含み、その表現形態は社会的な構造を含んでいる。親もその表現形態の内側をどこかで感じているが、それを認めることは今まで生きてきた「我」を失うことである。もっとも、それらがマスコミによって植え付けられていることは否定できない。それらも環境の一部だから。
「若者はしだいに両親と教師の権威主義を、自分たちの自由を妨げるものとみるようになる。まさにこの理由から、かれらは、かれらの表現力を萎縮させ、自己肯定を妨害する行動形態に、ますます反抗するのである。このきわめて積極的な現象は、けっして偶発的なものではない。それは、第一章で述べたように、実は私たちの時代を人類学的なそれとして特徴づける歴史的徴候である。だから若者の反乱を、(そう考えることで個人的利益にあずかるのでないならば)伝統的な世代間の違いのたんなる一例とみることはできない。ここにはもっと根深いものが含まれている。若者たちは、反乱のなかで支配社会の不正なモデルを告発し、非難しているのである。そうした特別な位相をもつこの反乱は、しかしながら、ごく最近のことである。社会はあいかわらず権威主義的な性格を帯びている。」(P.207)
「家庭の雰囲気は学校にもひきつがれる。生徒は、まもなく、何がしかの満足をえるためには、そこでも家庭にいるときと同じように、上から与えられた訓戒にしたがわなければならないことを発見する。これらの訓戒のひとつは、考えてはならないということである。」(P.208)
「主人を宿しているからこそ、かれ(FF)らは自由を恐れるのである。」(P.208-209)
「世界観を有するものは専門家だけだというわけだ。同様にまた、かれらは、教育行動のプログラム内容を編成するときには必ず民衆に相談しなければならない、という主張をばかげたことだと考える。」(P.209)
(専門家)「すなわち、かれらは侵略を断念しなければならないと考えるのだが、支配の様式があまりに深く自己の内面に食い込んでいるために、それを断念することは、ほとんど自分自身の存在を脅かすほどのことなのである。」(P.210)
(P.212)__ペチャパイ -> 客観的描写、貧乳 -> 価値的表現。微乳と美乳 -> 価値的。
「専門家にせよニューヨークのスラムの討論参加者にせよ、この歴史的過程の能動的主体として、自ら語り行動することはない。かれらのなかには、支配についての理論家やイデオローグはひとりもいない。逆にかれらは支配の結果であると同時に、次には支配の原因となるのである。」(P.212)
「革命社会は、技術を以前の社会がしたと同じ目的に役立てることはできない。」(P.214)
「こうした文化的残滓をとおして、抑圧者の社会は侵略を続行する。今度は、革命社会そのものを侵略するのである。
この侵略がとくに恐ろしいのは、それが支配者であるエリートとして再組織された者によってではなく、革命に参加した人間によって実行されるからである。」(P.215)
「以上の理由から私は、革命過程とは、ひとたび権力が掌握されれば、文化革命へと延長されるところの対話的文化行動である、と考える。そのいずれの段階においても、真剣かつ深い意識化の努力が必要である。それは、人間が真の実践をとおして客体たる地位に別れをつげ、歴史的主体の地位につくためには、ぜひとも必要な手段である。」(P.216)
「文化侵略は、侵略される人びとの行動にかんする最終決定権が、かれらにではなく、侵略者にあることをも意味している。そして決定権が、決定すべきものの内にではなく外にあるとき、かれらが抱くのは決定の幻想だけである。二重の反動的な被侵略社会において、社会経済的発展がありえない理由はここにある。発展が起こるためには、次のことが必要である。第一に、探求者に決定権のある探求と創造の運動がなければならないこと。第二に、この運動が、空間のなかだけでなく自覚的探求者の現に生きている時間においても生起すること。したがってあらゆる発展には変化がともなうが、すべての変化が発展につながるとはかぎらない。適切な条件のもとで発芽し成長する種子に生ずる変化は、発展ではない。同様に動物の変化も発展ではない。種子と動物の変化は、自らのものではない時間のなかで、それらの属する種によって決定される。なぜなら時間は人間のものだからである。」(P.217)__Nota Bene!! 「発展」の考え方。それでも、著者は「発展」の優位性(価値)を信じているように思える。
「社会を生き物とみなせば、自律的存在である社会だけが発展しうることは明らかだ。」(P.218)
「近代化と発展とを混同しないようにすることが肝要である。近代化は、衛星社会 satellite society の一部の層には影響を与えるかもしれないが、ほとんどのばあいつねに、押しつけられたものであるから、そこから本当の利益を引き出すのは中心社会にほかならない。」(P.218)
「二重社会の主要矛盾は、それらの社会と中心社会との依存関係にある。ひとたびその矛盾が廃棄されれば、主に中心社会を潤していた援助によって、これまで引き起こされてきた変化は、真の発展に変わり自律的存在の利益となる。」(P.219)
「それは、まるで中心社会が「民衆が革命を実行しないうちに改良を実施しよう」といっているかのようである。」(P.219)
「階級的必然性と階級意識とは別なものである。」(P.221)
「支配された者の意識は、、二重で、曖昧で、恐れと不信に満ちている。」(P.226)__フロム編『社会主義ヒューマニズム』「人間主義的精神分析のマルクス主義理論への適用」。
三 対話的行動理論とその特徴
(1)協同
「反対話的行動理論では、その第一の特徴である征服は、他人を征服して物に変える主体の存在を当然の前提としている。」(P.227)
「マルチン・ブーバー Martin Buber の言葉で(FF)いえば、反対話的で支配する側の我 I は、支配され征服される側の汝 thou を、たんなるそれ it へと変形する。しかしながら対話的我は、自らの存在を出現させたのがまさに汝(非我 not-I )であることを知っている。かれはまた、かれ自身の存在を出現させる汝が、同時に別の我にほかならず、その我のなかに汝があることも知っている。我と汝は、こうして、弁証法的関係のなかでは、ふたつの我になると同時にふたつの汝になる。
対話的行動理論は、征服によって支配する主体や支配される客体の存在を前提とはしない。そのかわりに、世界を変革するために出合い、世界を命名する主体が存在する。」(P.227-228)
(P.232)__ゲバラ。スローガン・キャッチフレーズ・標語、ナチスのプロパガンダ。
(2)解放のための団結
「さらに、支配それ自体がすでに客観的には分割をはらんでいる。それは抑圧されている我に、全能で抗しがたいものに思われる現実への密着の立場をとらせ続け、同時に神秘的な力をもち出してこの権力を説明することによってかれを疎外する。抑圧されている我の一部は、かれが密着している現実のなかにある。他の一部はかれ自身の外部、つまり神秘的な力のなかにあり、かれは自分が抗うことのできない現実をそこに帰着させて考えるのである。かれは一体化している過去、現在、希望なき未来のなかで引き裂かれる。かれは自分を転成する者として認識することのない個体である。それゆえかれは、他者との団結のなかで築かれるべき未来をもつことができない。だが自分の密着を断ち切り、現実から脱却してそれを対象化するにつれて、かれは客体(現実)に立ち向かう主体(我)として自己を統合し始める。この瞬間にかれは、引き裂かれた自己の偽りの統一から離れて、真の個人となるのである。」(P.237)__Nota Bene!! 。ここに問題の本質があるような気がする。「自立・独立・自主」、つまり現実(大地)との一体化から離れて、自己と客体を分離したうえで、「我」(主体性)となれというのである。それは「私」や「自分」ではない。近代的な自我 ego である。自分が大地や隣人や自分の肉体から独立できないように、「自立・独立・自主」としての「我」などというものははなからないのだ。それは支配者も同じである。被支配者のいない支配者などというものはないのだから。「みんなが「我」」というのは「みんなが大家さん」ということと同じだ。
(LF)(FF)「被抑圧者を分割するには抑圧者のイデオロギーが欠かせない。逆にかれらの団結をかちとるためには文化行動の形態が必要である。この行動をとおして、かれらは、現実への密着がなぜ、どのようにして起こるのかを知るようになる。すなわち団結をかちとるためには脱イデオロギー化が必要となるのである。それゆえ被抑圧者を統一するための努力にとって、たんなるイデオロギー的なスローガンの利用は不要である。そうしたスローガンの利用は、主体と客観的現実のと正しい関係をゆがめることによって、分割しえない全人格からその認識や、感情や、行動の諸側面を切り離す。
対話にもとづいて解放をめざす者の行動目標は、被抑圧者を神話的現実から解き放って別の現実に縛りつけることにあるのではない。逆に対話的行動の目標は、被抑圧者が自らの密着を認識することによって不正な現実の改革を選びとることができるようにすることにある。」(P.238)
「そして自己発見とは、何よりもまず自分自身を、ペドロ、アントニオ、あるいはジョセファとして発見することにほかならない。この発見によって名称の意味のとらえ方が当然変わってくる。つまり世界、人間、文化、木、仕事、動物等の言葉が、その真の意味をとり戻すのである。」(P.239)__多分「命名」。
「農民は単一で小さくまとまった抑圧的決定中枢をもつ閉ざされた現実のなかで生きている。都市の被抑圧者はあらゆる方向に広がっている関係のなかで生きており、そこにおける抑圧命令中枢は多元的で複雑である。農民は抑圧機構を体現するひとりの支配者の統制下におかれている。都市地域では、被抑圧者は非人格的抑圧 oppressive ipersonality に服従させられている。どちらのばあいにも抑圧権力はある程度目に見えないのである。すなわち農村地帯ではそれが被抑圧者にとって身近であるために、としてはそれが分散しているために。」(P.240)
(3)組織化
「証言は、それが生ずる社会的状況の一部となる動的な要素である。一部になった瞬間から、証言は社会的状況に影響を与えずにはいない。」(P.243)
「支配者であるエリートにとって組織化とは、自分たち自身を組織することである。革命指導者にとって組織化とは、自分たち自身を民衆とともに組織することである。第一のばあい、支配者であるエリートは、支配と非人格化をより効果的に進められるように、その権力をますます体系化する。第二のばあい、組織化は、それ自身が自由の行使を本質とするかぎり、その本質と目標にしたがうだけである。したがってどんな組織にも必要な規律を画一的管理 regimentation と混同してはならない。」(P.243)
(P.244)__「食べ物が必要だから」->「おいしいものが必要だから」、明晰さ。「食べ物が必要」と「お金が必要」との差。金権政治、政治にはお金が必要である以前に、生きるにはお金が必要だということを批判できるか。
「対話的行動理論は権威主義にも自由主義にも反対することによって、権威と自由を肯定するのである。権威のない自由は存在しない。自由のない権威もまた存在しない。」(P.245)
「真の権威は、たんなる権力の移譲によってではなく、代表委任もしくは心からの同意によってそれと認められる。」(P.245)__納得=明晰さ。
「権威が自由と衝突を避けることができるのは、ただ自由にふさわしい権威であるばあいにかぎられる。一方の肥大症は他方の萎縮症を引き起こす。権威は自由なしに、自由は権威なしに存在しえないのと同様に、権威主義は自由を否定せずに、自由放任は権威を否定せずに存在することができない。」(P.245)
(4)文化総合
文化総合 cultural synthesis
「すなわち指導者は、一方で高い給料を望む民衆の要求を自分のものとしてとらえると同時に、他方でその要求そのものの意味を課題として設定しなければならない。」(P.252)
「抑圧者は民衆を欠いたまま行動理論をつくりあげる。それはかれらが民衆と対立しているからである。民衆は、踏みにじられ抑圧されて、抑圧者の像を内面化しているかぎり、自分たちだけで解放行動の理論を構築することはできない。民衆と革命指導者との出合いのなかで、両者の親交、両者の実践のなかで、はじめて、この理論は構築できるのである。」(P.253)
解説 パウロ・フレイレの人と教育思想
ノルデステの飢餓体験
パウロ・フレイレは、一九二一年九月一九日にブラジル東北部(ノルデステ)ペルナンブコ州の州都レシフェで生まれた。
多くのブラジル人にとって、東北部で生まれるということは、ただちに、旱魃、飢え、渇き、過重労働、病気、貧困のまっただなかに生みおとされることを意味している。」(P.256)
「フレイレは、しかし、内陸部のカアティアンガではなく、海岸都市のレシフェに生まれ、搾取される農民ではなく公務員の息子として生まれたために、ある時期までは、そのような悲惨さとは無縁な環境で育てられた。」(P.256)
「幼年期に文字を学べるということ、このこともまた、大多数の住民が文字を奪われたまま放置されていた東北部では(一九五五年でブラジルの識字率は五〇%を割っていた)、まれにみる幸運な経験であった。」(P.257)
ブラジルにおける教育・文化の実践
「フレイレは、しかし、生きながらえることと人間として生きることがまったく違うものであること、人間が人間になるためには文字を獲得しなければならないことを、農民自身が自覚し、その自覚を深めてゆくように導いていった。」(P.264)
<文化サークル>運動の学習方法
「スラムがひとたびコード化されて、絵や写真などのコード体系として表されると、それはもはや、民衆が生きているスラムの現実そのものではなく、理論的な検討と批判を加えるために文化サークルという場において抽象化されたひとつの表現となる。
したがってスラムのコード表示は、民衆がおかれた生(なま)の現実(具体的な場)と、それを対象化し検討する討論の場(理論的な場)とを媒介するものである。」(P.273)
「このようにして、かれらは、文字を獲得することと、現実世界を読みとることを同時に体験する。」(P.274)
ポピュリスモ批判とクーデター
「このような政府の積極的な方針と民間運動(労働運動、農民運動、そしてフレイレらの識字教育運動)の盛りあがりにたいして、ブラジルの「共産主義化」を恐れる地主や資本家および軍部は、一九六四年三月三一日の深夜から四月一日にかけてクーデターをおこし、ゴラール政権もろとも在野の運動をもつぶしてしまうのである。」(P.279)
「ところでラテン・アメリカでは、ポピュリスモとは本来、依存経済によって規定されているラテン・アメリカ諸社会が、一九二〇−三〇年代の経済恐慌を克服していく過程で現れてきた政治形態のひとつであると考えられている。それは、各国ごとにさまざまな特性をそなえており、ひとことで定義することは困難であるが、おおむね、労働者階級に依拠するという外観を保ちながら結局は大土地所有制を基盤とした寡頭政治体制を存続させる方向へと動いていく傾向をもっている。」(P.280)
「ポピュリスタは、支配者としてのエリートと、登場しつつある労働者とのあいだにあって、あらゆる運動を自分たちの勢力拡大のために利用しようとする。」(P.281)
「フレイレはこのように、大衆操作と民主化への契機というポピュリスモの二面的性格をみすえながら、ブラジルでの敗北を教訓に変え、みずからの思想を深めていくのである。」(P.281)
チリにおける実践
「フレイレの批判的姿勢は、亡命先のチリにおいても貫かれている。」(P.282)
「海外から援助のためにやってくる専門家たちは、農民を無知で遅れたものとみなしている。かれら専門家には、農民もまた毎日の農作業のなかから、経験的・実践的な知識を身につけてきた、(FF)ということが理解できない。それは、かれらが、自分たちの知識だけが真の知識であると信じ込んでいるからである。
しかし、農民がおかれている現実の条件を無視しながら専門家によって一方的に押しつけられるどんな知識も、農民にとっての真の知識となりうるはずがない。なぜなら、知識の獲得、すなわち、知るという行為は、客体の受け身の行動ではなく、主体の積極的な仕事だからである。
専門家たちは、教育と技術の援助と称しながら、実は、主体としての農民を客体にかえ、対話と交流を否定し、技術による救済(メシア)信仰を植えつけることによって、まぎれもなく、文化侵略を遂行しているのである。」(P.285-286)
「孤立した抽象的な人間が存在しないように、孤立した思考も存在しない。主体としての人間は、(FF)世界という客観的対象を媒介にして関係している。同時に、人間は、観念の領域においては、言葉を媒介にして相互に関係を結ぶ。
したがって、「わたしが考える」は、考えられる対象と、考えるさいの言葉とが媒介となって、それぞれの主体どおしを結びつけ、そこに共同関係を成り立たせているのだから、もはや、「わたしが考える」ではなく、「わたしたちが考える」であるはずだ。
「わたしが考える」は「わたしたちが考える」という共同性を前提としてはじめて成り立つのであって、その逆ではない。この「考える」という行動において、各主体が相互に関係し、参加しあうことが〈交流〉である。
〈交流〉は情報の一方的なおしつけを意味する〈伝達〉や〈コミュニケ〉の対極にあるものである。」(P.288-289)__言語は思考の道具ではない。言語がなくても思考はできる。野生児を見よ。言語で思考することはほとんどない。それは文字的思考、あるいは論理的思考のためのものである。もちろん、コミュニケーションの唯一の(最大の)手段でもない。ただ、そうでないこともない。
アメリカ合衆国における省察と行動
「真の識字学習は、疎遠な言葉を暗記することからではなく、学習者が、自らをとりまく具体的な現実を、つまり世界を〈命名〉することから始まらなければならない。」(P.291)__「命名」-> 具体的なものと観念(言葉)を結びつけて「概念」あるいは「範疇」とすることか。
(P.294)__人間、あるいは人間性という幻想。
「被抑圧者の教育学」への模索
(P.296)__テレビはその基本に文字があることを覆い隠す。自動車はその基本に人間が歩くということを否定する。
ギニア・ビサウにおける教育実践
「このばあいにも、もっとも重要なことは、民衆自身が、文字を獲得すると同時に現実世界を〈読みとり〉、それを変革しながら現実を〈書きかえていく〉ことである。(P.299)__文字が〈読み取り〉になるのか。覆い隠し抽象化するのか。「文字の輸出」は、それが民衆自身が選択したとしても(そのように見えても)「開発」「啓蒙」ではないのか。
「この「理解しにくい考え方」が、理論のうえで解明され実践されることによって検証されるとき、また、見えない関係が見えはじめ、関係を変えるための行動が生み出されるとき、わたしたちは言葉の疎外がつくりあげたふたつの〈沈黙の文化〉 ひとつは文字を奪うことによって、もうひとつは偽りの言葉を植えつけることによってつくり出された〈沈黙の文化〉 を克服し始めるだろう。」(P.304)
(一九七九年二月 伊藤 周)
〈終わり〉
〈メモ〉
言葉と言葉になる前のものを同じく「有る(在る、存在する)」とする契機となるのは「言葉」を「文字」と同一視することである。それは言葉の単語化、単純化であり、アルファベットという記号にすることで「外在性」が確固たるものとなる。
質料、大工の形相(イデア)。ある人(可能態)が学習(訓練)して大工(現実態)となるためには、大工のイデアを学習するわけだから、現実帯よりも可能態(イデア)が先行する。
日記に代表される文字化は、自己(の内面)の外在化。ここで生じるのが、自己が客観的に存在するということ。「我あり」。自己も客体も客観的に存在する=>唯物論。客観も自己のなかに存在する=>観念論。記憶も自己も存在する、というのは「ムネモシュネ―」とは違う。
聖書のなかに、神も歴史も存在する。記憶は存在する。客観的に、聖書として。
観念論者も文字(書物)を否定しないし、そこから学ぶ。本は記憶・歴史・主体そのもの。
言葉で考えているのではなく、文字で考えているのだ。その「考え」を表明するときに言葉が介在せずにはおかない。
言葉と文字の混同(取り違え)=>主体と客体の混同(取り違え)。
言葉で表現するもの「である」と、言葉「がある」との取り違え。
言葉が客体的構造として存在すると思うこと(チョムスキー、生成文法)は、である(意味する)とがある(構造が存在する)との混同。それが言葉(ロゴス、論理、調和)でできている以上、理屈はいくらでも付けられる。日本語で日本語を説明するのと同様、言葉で言葉を説明するというのは、言葉の存在(構造化)を前提しているのだ。
言葉は論理化できる。ただし、西欧(印欧語)文法(ロゴス、構造、制度、理論、理性、法)で。そして西欧文法とは言語そのものであり、論理そのものである。
法を守れという法はない。それは法(つまり印欧語文法で言う言葉)を超えたものだ。言葉を説明する言葉も同様だ。
農作物(とそれをつくる道具)の改良で、暮らしのスピードは速くなったけど、それが幸せに結びついたかわからないが、通常(以前)より早く多くつくることが、「生」を、つまり、前と同じものを速く多く作っているという道理がわからない。
天然ダイヤと人工ダイヤ。イノシシと豚。
間隔や感情があって、アメリカ人なら「 This flower is red 」と言い、日本人なら「この花は赤い」という。この場合、心にあるもの(存在)が言語化されるが、それは赤い花そのもの、外部に在る存在ではない。表されているのはあくまでも「心」だ。言葉や文字は、自然(外在)を映す鏡ではなく、心を表す道具である。
いつの時代にも「経済」はあった、「恋愛」はあった、「コンピューター」はあった。おかしい。
自然との物質代謝、食べたり排泄したり。
農民は文字を知らない無知な存在だ。文字が知識を与える。
エリート、左翼、革命家、革命指導者、専門家、支配者、抑圧者
エリートとしてのマルクスとエンゲルス
自律性の障害 おっぱいが大きいことが価値となること
対話的行動理論と反対話的行動理論
我と汝
命名
中央と地方、都市労働者と農民、労働者と学生、の分離
福祉政策(医療・就業支援・子育て支援)とコンビニと(電動)自動車