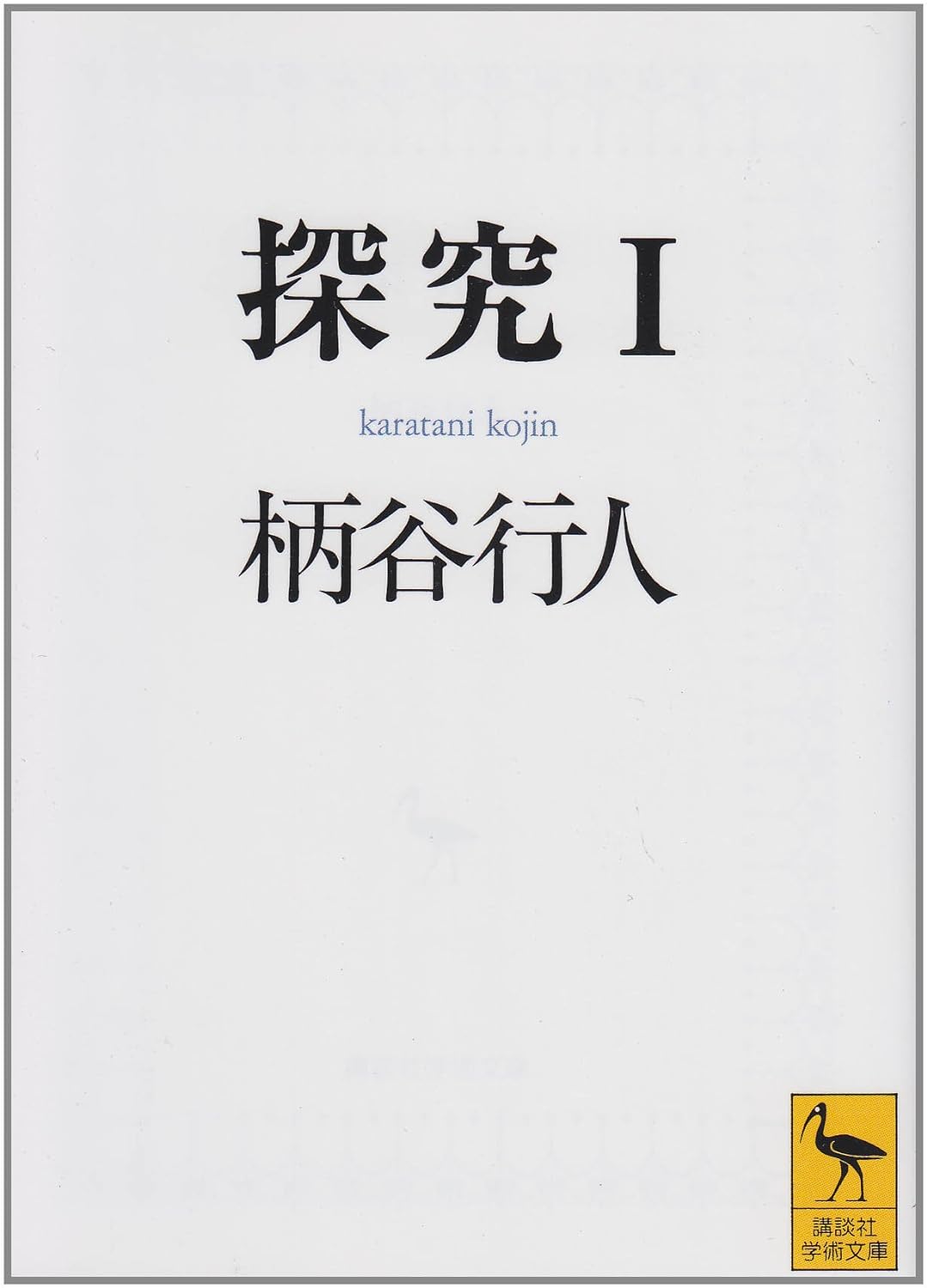
再読
20年以上前に、一度読んでたんですね。その頃はなんにもわかっていなかったはずなんだけど、短い感想ですが、結構的確な感想だなあ、とわれながら嬉しいです(笑)。
柄谷氏の本を最初に読んだのは『マルクス その可能性の中心』の文庫本あたりだから、40年近く前だと思います。今回、浅見克彦氏の『批判のエロス』を読み直したところ、取りあげられていたので、読んだことも忘れて読み直しました(汗)。
これがとてつもなく面白い。といっても、理解できたかどうかといわれれば、ほとんど理解できていません。まあ、20年前よりはいくらか分かる部分が増えているのですが、一文を「〜〜は〇〇」まで読んで、「ふむふむ」と納得したつもりになると、文末に「ではない」とひっくり返されることが何度もあって、眩暈ばかりしていました。でも、カイヨワの言う通り「眩暈」も「遊び」の要素のひとつなので(『遊びと人間』)、それがまた気持ちがいい。
当時私は、「評論(批評家)なんてくそくらえ」と思っていたし、「宇野弘蔵はわかりやすいけど、浅い」なんてうそぶいていたので(意味があってるかなあ)、労働価値説を否定するかのような柄谷氏の本は面白かったけど、資本論解釈には使えないと思っていました。当時は「ニューアカ(Wiki)ブーム」。わかりもせずに浅田彰氏や中沢新一氏の本を読んでいました。そのなかで、柄谷氏だけはその後もつづけて読んでいました。
氏が「NAM(地域貨幣の一種)」を提唱したときは共感したし、「アソシエーション論」をいい出したときは、「いまさら?」と思いながらも、読んでいました。
素直な力作
その数多い著作の流れを分からずに追いかけていたのですが、今回、その変遷の意味がいくらかわかりました。それについては、後で述べることにします。「あとがき」にこうあります。
これまで私は、いつも何かここで決着をつけようというような緊張と焦燥をもって仕事をしてきたのに、そんな気持ちが消えうせたのである。(P.254-255、あとがき)
当時、著者はまだ40代中頃です。その境地に達したことがすごいです。私は定年退職後、人生の終りが近づいたことを感じてしまって、かえって焦っています。でも、変な緊張がはいっていないからこそ、自由な発想で、縦横無尽に書き綴っていると思います。あくまでも精緻で、作者に寄り添い、ときには斬新な(新奇な)発想も飛び出します。渾身の著作だと私は思います。
「「学術文庫版」へのあとがき」ではこう言っています。
そして、私は、私の「真意」が伝えられることを期待していない。そんなものはありえないのだから。(P.256-257、「学術文庫版」へのあとがき」)
最近やっと、同じような気持ちになりました。でも、「わかってもらえないけど書く」というのはとても辛い作業です。
独我論
『トランスクリティーク』の序文にこうあります(序文の日付は「二〇〇一年五月」)。
しかし、八九年以後に私は変わった。それまで、私は旧来のマルクス主義的政党や国家に批判的であったが、その批判は、彼らが強固に存在しつづけるだろうことを前提していた。彼らが存続するかぎり、たんに否定的であるだけで、何かをやったような気になれたのである。彼らが崩壊したとき、私は自身が逆説的に彼らに依存していたことに気づいた。私は何か積極的なことをいわなければならないと感じ始めた。(P.11)
当時は、ヒトラーと同じようにスターリンを批判すればいい、とか資本家(資本主義体制)を批判すればいい、公害(環境破壊)を批判すればいい、という風潮がまだ残っていました。「ベルリンの壁崩壊」とともに、「社会主義(共産主義)の敗北」という言説が流れ、労働運動(組合運動)はその力を急速に失いました。
急進勢力は分裂し、「新自由主義」が大手を振って世界を支配し始めました。その流れは今も続いています。明日から「G7外相会合」が東京で開催されます。ウクライナ情勢やイスラエル・パレスチナ情勢などが話し合われるそうです。ウクライナやイスラエルを支援している国の外相の集まりです。とりあえず「戦争は悪いこと」ということのようですが、それなら支援しなければいい、という声は聞こえません。
先日、性同一性障害特例法の違憲判決が出ました。性差別や障害者差別はいけないということになっています。とりあえす、「差別をなくそう」と言っておけばいい。ジャニー喜多川の性加害は、芸能人の浮気と同列に「いけないこと」だといわなければなりません。戦争とは何か、とか、差別(平等)とは何か、を問われることはありません。それは「真理(規則)」として前提されています。この本で多用されている言葉でいえば、G7は「同じ言語ゲームを共有する国」の集まりです。そこでは「テロリスト」「ロシア」「中国、北朝鮮」は、その中に入らない「他者」ということになっていますが、それは著者のいう「他者性をもった他者」(以後、《他者》と表記)ではありません。同じ言語ゲームを共有する「他者」であり、その批判は「批判のための批判」であり、結局は「モノローグ」です。なぜなら、どちらの側も「正しい(真理)のは自分(まちがっているのは相手)」であり、自分は人間の代表であり、自分が正しいと思うことは、人類一般(普遍)的に正しいと考えているからです。
私が独我論とよぶのは、けっして私独りしかいないという考えではない。私にいえることは万人にいえると考えるような考え方ことが、独我論なのである。(P.12)
他者性
日本には「勝てば官軍」ということわざがあります。「官軍」というのですから、このことわざができたのは明治維新以後です(「官軍」という言葉自体は大昔からありました)。私はこの言葉が日本人の中に残り続けているのは、それが日本人にとっては異質だったからではないかと思っています。私はこの言葉には「本当はそうじゃないんだけど、そういう事になっちゃうんだよなあ」という、気持ちが含まれているように思います。これの英訳はふつう「Might is right.(力は正義なり)」とされています。このようなストレートな気持ちが、このことわざにはないと思うのです。第一、「right(正義)」なんて概念(考え方)はそれまでなかったのですから。「right」には「権利」という意味もありますよね。正義と権利が同じというのは、多分近代法がもたらしたもので、西欧では「善・悪」「快・不快」など、感覚や倫理(道徳)にかかわるものと、論理にかかわるものが対立してきたその流れのなかで出来上がったものです。そこにはつよい「自己意識」があります。そしてそこに「他者」が現れます。権利(法)というのは、「権力」同様、自己と他者の関係です。著者は明言していませんが、翻訳語としての正義、権利、権力、(そして義務、)などの翻訳語(翻訳のためにつくられた語、または従来の漢語を翻訳のために転用した語)は、その概念を表す「実体(現実)」が日本にはありませんでした。「鰯(イワシ)」という漢字は中国にはありません。理由は簡単で、中国(漢字が生まれた黄河の流域)にはイワシがいないからです。
この本におけるキーワードはいくつかありますが、その殆どは(程度の差はありますが)日常会話で使われることがありません。普段一番使う単語は「教えるー学ぶ」でしょうか。でも、「teach - learn(?)」と「教えるー学ぶ」は当然異なります。私は外国語が苦手ですが、学者は外国語がわかるからこそ(外国の実体を知っているからこそ)、その実体を(無意識に)日本語に当てはめやすいのではないでしょうか。それは「事後的に」日本の中に発見(あるいはその不在を発見)されるのです。それは「イデアの実在性」の問題ではありません。哲学(この本でいう「哲学」は西欧哲学。西周の造語)の問題でもありません。そしてこれこそが「言語ゲーム」や「他者性」の問題なのだと思います。
哲学は、こうした実践的な乖離を直視するかわりに、それを無視したところに確実な根拠を求めるところからはじめる。いいかえれば、それは「内面」から始め、《他者》を抹殺してしまうのである。(P.60)
哲学は、いつも「我」(内省)から出発し、且つその「我」を暗黙に「我々」(一般者)とみなす思考の装置なのである。デカルトがわれわれに記憶されるのは、自己意識の明証性から出発したことによってではなく、「私」が「一般者」であるという暗黙の前提を疑い、それを証明すべき事柄とみなしたことによってである。(P.241)
ちなみに、「我々(わたしたち)、We」というのは「おれたち、あたしたち」とはちがいます。
教えるー学ぶ
著者は、ウィトゲンシュタインを引用して「教えるー学ぶ」と「話すー聞く(書くー読む)」の違いを説明します。「話すー聞く」は、同じ言語ゲームの共有が前提にあります。外国人(だとおもわれる人)に話しかけるとき、小さな子供と話すとき、あるいは動物と話をするとき、日本語で話しても通じません。日本人は、外国人を見ると英語で話しかけますが、海外ではどうなのでしょうか。日本人は英語が話せるひとが少ないといいますが、英語圏以外でもそうなのでしょうか。
話すことを聞くのは「私」です。書いたものを読むのも「私」です。何を言っているのか、何を書いているのか、まず理解しようとするのは私なのです。そこで、私が話したこと、書いたことは、私にとって「客観的」に「あるもの」として存在すると前提しなければなりません。そしてそれを私が「言いたいこと」「書きたいこと」と比較します。そこでいつも感じるのです。「言いたいことが言えているのか」「書きたいことが書けているのか」「別の言い方や書き方はないのか」と。もちろん、それは「言いたいこと、書きたいことが他者に伝わるのか」といういみです。でも、その他者は「伝わるべき他者」、つまり同じ言語ゲームが成立する他者です。その「言いたいこと」と「言ったこと」のずれは同じ言語ゲーム内での自己と他者のずれです。
ロラン・バルトは、「書く」という動詞は他動詞ではなく、自動詞だといったが、「話す」という動詞も同様である。つまり、ひとは何か考えを話すのではなく、たんに話すのだ(たとえば、幼児は、〝意味もなく〟たんにしゃべる)。だが、それをわれわれ自身が聞くとき、その言葉が何かを意味していると思うのみならず、まるで前もってそのような「意味」が内的にあったかのように思いこむ。
デリダが、明証性を「自分が話すのを聞く」ことにあり、そこで〝差延〟が隠蔽されるのだというのは、いわばこのことである。結局「話す」立場に立つというとき、われわれは実際は「聞く」立場に立ってしまっている。私が「教える」立場という言葉を用いるのは、そのためであって、それは「話す=聞く」立場とはまったく異なる。(P.33-34)
柄谷氏が「教えるー学ぶ」という関係をもちだすのは、その言語ゲームが成りたたない《他者》との関係を明確に示すためです。「伝わること」を前提とするのではなく「伝わらないこと」を前提とする関係です。
実は同じことは、自己との関係にもいえます。自分が言いたいこと、あるいは「自分そのもの」が「わかる」かどうか。それは「自分が言いたいこと」あるいは「自己」そのものが客観的に在って、それが「理解可能(わかるはずだ)」という前提そのものを疑うということです。それは「他者」あるいは「事物」が客観的に在って、それは理解できるはずだという「科学的な発想」に対する疑問です。
我思う故に我あり
デカルトの「方法」、そしてその行き着いた先の「我思う故に我あり」(Je pense, donc je suis、デカルトは『方法序説』をフランス語で書きました。Cogito ergo sumというのは第三者がそれをラテン語に翻訳したものです)について、
デカルトにとって、〝精神〟とは、「考える」ことではなく、「疑う」こと、すなわち外部的であろうとする実存である。(P.16)
と捉えてます。つまり、「我疑う故に我あり」ということです。デカルトにとって、「他者」も「事物」も「自己」も「自分が言いたいこと」も疑うこと、それが大切でした。
プラトンのイデアやアリストテレスの質料と形相は、それらが「ある」「理解可能」ということが前提です。それに比べてソクラテスは、「無知の知」という言葉で「それらがあるかどうかが問題で、私はその答えを持ち合わせていない」と言っています。だからこそ、それらは「対話 διάλογος」のなかで事後的に見つけられるものです。「産婆術」はその「見つけ(気づき)」を助ける方法です。でも、ソクラテスはそのものを「事前にあったものを発見する」と考えていたのか、事後的に生まれる(発明する)と考えていたのかは、私にはわかりません。プラトンの「対話篇」がどのくらいソクラテスのことばを正確に(?)伝えているのかはわかりません。もちろん、それはプラトンの「創作」なのです。でも、私が読んだ数作品ではソクラテスは「答えを用意していて、それを提出して解決する」ということをしていません。多分、ソクラテスにはそんなつもりはなかったのでしょう。でも、プラトンやアリストテレスは、「書く」という行為でそれを「客観的に存在するもの」だとしてしまいました。存在する以上、それは「分かる(説明できる、伝えられる)可能性があるもの」だと。
ソクラテスは「書かなかった」人である。彼は対関係における他者との対話に終始し、プラトンのように、それをこえた「実在」(イデア)にはけっして至らなかった。まさにそのために、彼は「共同体」のルールを危うくする者として処刑されたのである。(P.251)
でも、それ(伝えられるもの、意味)は、あるのではなく、事後的に成立する(発明される)ものにすぎません。
だが、誰でも自国語のなかで考えているかぎり、意味が積極的に在るという実感をぬぐい去ることはできない。事実、現象学はこの明証性から出発するのである。(P.24)
その明証性に対する疑問は、デカルトでは「神の存在」となり、ソクラテスの「文字に対する非難」となったのです。
社会(ゲマインシャフトとゲゼルシャフト)、民主主義
柄谷氏がいう「社会」というのは、「個人と社会」などというときの「社会」とは異なります。
それは、つねに現存するが、共同体(システム)のもとでは隠蔽されてしまうような場所である。
私の考えでは、マルクスは、共同体と共同体の「間」において存在する関係を、社会的とよんだのである。(P.19)
これはテンニースのいう「ゲゼルシャフト」ですね。
柄谷氏が引用している『資本論』の「社会的過程」は原書では「gesellschaftlichen Prozeß」(Das Kapital Erster Band,S.59)となっています。日本には「social」に相当する「社会」は存在しませんでした。明治以降、日本にパブリック、「社会」が持ち込まれたのです。
ゲゼルシャフトは他者(他者性)がいること、あるいは疎遠なものがいること、異質なものがいることです。ゲマインシャフト(共同体)とのちがいはそこにあります。異質なものを異質とするのは自己です。そこにパブリックとプライベートが生まれます。
デヴィット・グレーバーは『民主主義の非西洋起源について』で、民主主義が発生したのは「「あいだ」の空間、spaces in between(P.69)」だと言っています。そこは「言語ゲームが成りたたない場所」です。共同体の中で民主主義が発生するのではありません。逆に、共同体の中では言語の内外での「システム」が成立していますから、システムの一部としての「階級」が自然発生的に成り立ちます。それは「支配・被支配」とは別なものなのですが(能動・受動という対立も日本語にはなかった)、民主主義(商品交換)は「共同体の中」に浸透していきます。
商品交換は、共同体の果てるところで、共同体が他の共同体またはその成員と接触する点で、始まる。しかし、物がひとたび対外的共同生活で商品になれば、それは反作用的に内部的共同生活でも商品になる。(『資本論』第1巻、大月書店、118)Der Warenaustausch beginnt, wo die Gemainwesen enden, an den Punkten ihres Kontakts mit fremden Gemeinwesen oder Gliedern fremder Gemeinwesen. Sobald Dinge aber einmal im auswärtigen, weden sie auch rüchschlagend im innern Gemeinlaben zu Waren. S.102
『資本論』の2巻、3巻
柄谷さんの『資本論』読解は特別です。その意味がすこしわかりました。ある著作をどのように読もうか、それは読む人の勝手です。もし、柄谷さんの読解が正しいとすれば、マルクスは第2巻、第3巻を出せなかったのではなく、出さなかったのかもしれません。エンゲルスはマルクスの草稿をもとに第2巻、第3巻を出版しましたが、それは第1巻の出版(フランス語版、1872-1875年)より前に書かれたものです。「売り」が《他者》と対峙するときの「命がけの飛躍」だとするならば、第2巻、第3巻は同じ言語ゲームを共有する文化圏を叙述しているだけで、たんに独我論にすぎません。そこに《他者》はいないのです。
なぜいかにして「意味している」ことが成立するかは、ついにわからない。だが、成立した
あとでは、なぜいかにしてかを説明することができる規則、コード、差異体系などによって。いいかえれば、哲学であれ、言語学であれ、経済学であれ、それらが出率するのは、この「暗闇の中での跳躍」(クリプキ)または「命がけの飛躍」(マルクス)のあとにすぎない。規則はあとから見出されるのだ。(P.50)
学校で文法を習うことを考えてみればいいのです。すでに「ことば」を使っていた人があとから文法を知るのです。それは先生も例外ではありません。文法を学んだあとに、「文法(システム)」は「つねに/すでに」存在するという「発見」があるのです。
第1巻を書き終えたマルクスにとって、「つねに/すでに」ある「なぜいかに」は自分が解明するものではなかったのではないでしょうか。
柄谷の視点(西洋と東洋)
柄谷氏の視線は、現代社会、近代以降の西洋社会にあることは間違いありません。取りあげられている題材からして、近現代の思想家です。彼にとって日本(非西洋)はどういう役割を果たしているのでしょうか。取りあげられている日本の哲学者は西田幾多郎だけです。結果的に近代西欧を一般化した印象があります。近代批判を近代思想で行うのは意味があるし、ある種、近代日本は近代西欧だから日本で学者として生きるためには仕方ないともいえますが。
私は、ヴァナキュラーな視点をはなれて(つまり、西洋的視点を一般化して)の、変革はあり得ないと思います。それは柄谷氏も同意すると思うのですが。ヴァナキュラーを再生すること。コミュニズムとはその運動にしか結果しないのではないでしょうか。そこにしか、コミュニティ(共同体)の可能性はありえません。「世界共同体(世界共和国でもいいけど)」などというのはありえないのです。世界(西欧、自分)に当てはまることは日本(自分)に当てはまる、それこそが唯我論(モノローグ)なのです。
西洋と東洋の思想に関わりのある部分を、ちょっと長いですが引用します。
しかし、東洋哲学も結局「哲学」である。これもまた、対関係としての他者を排除するところに成立している。どこでも、内省
すなわち自己対話=弁証法から出発する思考は、その結果がイデアであろうと空であろうと、独我論(モノローグ)であるほかない。いうまでもないが、東洋のブッダも孔子も、そのような独我論をイロニカルに否定することによって、あるいは主客未分の純粋経験といった神秘主義をイロニカルに拒否することによって、ひとを《他者》に向かい合わせようとした。単純にいえば、彼らは「他者を愛せ」といったのだ。真理を愛することは、結局、それを可能にしている共同体(コミュニティ)を愛することである。ところが、《他者》は、そのようなコミュニティに属さない者、言語ゲームを共有しない者のことである。そのような他者との対関係だけが、彼らの関心事であった。しかも、彼らはソクラテスやイエスと同様に書かなかった。書かないということは、音声的なコミュニケーションの直接性を優位におくからではない。書くことは、われわれを一般的他者との関係に、「事象の根拠」を問う弁証法に向かわせてしまう。だが、彼らは、そのような弁証法=哲学体系を拒否するために、他者との一対一関係にのみ終始したのである。
むろん、ブッダにせよ孔子にせよ、彼らのいうことは、まもなく「共同体」に回収されてしまった。そして、それは以前からある「神秘主義」に吸収されたのである。神秘主義は、私と他者、私と神の合一性である。それは《他者》を排除している。いいかえれば、〝他者性〟としての他者との関係、〝他者性〟としての神との関係を排除している。そこにどんな根源的な知があろうと、私と一般者しかいないような世界、あるいは独我論的世界は、他者との対関係を真理(実在)を強制する共同体の権力に転化する。西田幾多郎やハイデガーがファシズムに加担することになったのは、偶然(事故)ではない。(P.249-250)
「弁証法(希: διαλεκτική、英: dialectic)」は前記の「対話 διάλογος」、つまり「二つの(二人の)ことば」です。それに対するソクラテスとプラトン(アリストテレス)の態度は、ある意味180度ちがいます。
後者には「意味(答え)」は言語化される(された)ものだという前提があります。言語化されない(される前の)意味(感覚、感情、存在)というものをアリストテレスは形相化(言語化)される前の実体、第一実体としました。プラトンはそれをほぼ無視しましたが、アリストテレスはそれを明確な「存在(実体)」と捉えました。木材という質料に「机」という形相(イデア)が結びつくように。
要するに、ウィトゲンシュタインは、「言語ゲーム」によって、われわれのコミュニケーションが何らかの規則(コード)によっていることをいいたいのではなく、その逆に、そのような規則とは、われわれが理解したとたんに見出される〝結果〟でしかないといいたいのである。そのような規則は、ある記号で何かを「意味している」ことが成立するそのかぎりで、たちまち「でっち上げられる」。そして、このような規則の変改を規制するような規則はありえないと、ウィトゲンシュタインはいう(「哲学探究」八四)。(P.44-45)
意味は、「了解される」ことによって発生する、というのが柄谷氏(ウィトゲンシュタイン)の考えです。でも、ほとんどの行為(感情、感覚)は言語化されないのです。意味されるものが在って、それを表すのが「言語」だというのは、「翻訳可能性」の基本です。でも、意味される(翻訳される)ものなどというのはないのです。それが「ある」ということこそが、アリストテレス以来の西欧的思考の「主客構造」です。その構造を「印欧語文法」に求めても結局は意味がないでしょう。むしろ、それによって生じるのが「外部(《他者》)」です。「外部(《他者》)」の設定そのものが主客構造です。共同体の間で発生したもの(貨幣、商品)が内部化されるというマルクスの論理も、外部を前提としています。その点でマルクスをとらえるなら、それは西欧的思考でのみ意味を持ちます。
地域貨幣
柄谷氏が一時期注目していた地域貨幣は「地域(ヴァナキュラー)」ですが、「貨幣」です。つまり「数字・経済」です。貨幣が流通する社会は、依然として社会(ゲゼルシャフト)です。だから、地域貨幣で貨幣(社会)はなくなりません。それは、「外部(国家)」があるせいではありません。もちろん、社会主義社会でも貨幣(商品、経済)はなくなりません。
では、国家や資本を揚棄すること、すなわち、交換様式でいえばBやCを揚棄することはできないのだろうか。できない。というのは揚棄しようとすること自体が、それらを回復させてしまうからだ。唯一可能なのは、Aにもとづく社会を形成することである。が、それはローカルにとどまる。BやCの力に抑えこまれ、広がることができないからだ。ゆえに、それを可能にするのは、高次元でのAの回復、すなわち、Dの力によってのみである。
ところがDは、Aとは違って、人が願望し、あるいは企画することによって実現されるようなものではない。それはいわば〝向こうから〟来るのだ。(P.395)
そこで私は、最後に、一言いっておきたい。今後に、戦争と恐慌、つまり、BとCが必然的にもたらす危機が幾度も生じるだろう。しかし、それゆえにこそ、〝Aの高次元での回復〟としてのDが必ず到来する、と。(『力と交換様式』P.396)
定式化するということ、概念化し、区別すること。世界(地域、文化)は、あるいは「歴史」はどれかにあてはなると考えること、これは「探究Ⅱ」における「固有名」あるいは「特殊と普遍」にかかわってきます。
詳細はそちらに譲るとして、ヴァナキュラーなもの(ここでは「ローカル」と表現していますが)は「普遍に対する特殊」ではありません。「社会に対する個」「全体に対する部分」でもありません。そんなものは200年前の日本にはなかったのですから。それを、「(意味されるものとして)在ったけど、概念化(言語化)されていなかった」とか、「日本は意識が低かったけど、近代化によって進歩した」と考えるのはどうなんでしょうか。国家貨幣を地域貨幣にして、さらに、家庭の中にまで貨幣関係(経済)を持ちこむことを「高次元でのAの回復」とどう結びつけるのか、私にはわかりません。むしろ、「高次元・低次元」などと考える「思考方法」そのものが問われなければならないのではないでしょうか。
[著者について]
柄谷行人[wiki(JP)]
1941年兵庫県生まれ。東京大学経済学部卒。同大学院英文科修士課程修了。現在法政大学教授。漱石論により群像新人文学賞、『マルクスその可能性の中心』で亀井勝一郎賞受賞。著書に『畏怖する人間』『意味という病』『批評とポスト・モダン』『日本近代文学の起源』『内省と遡行』『隠喩としての建築』『反文学論』など。


