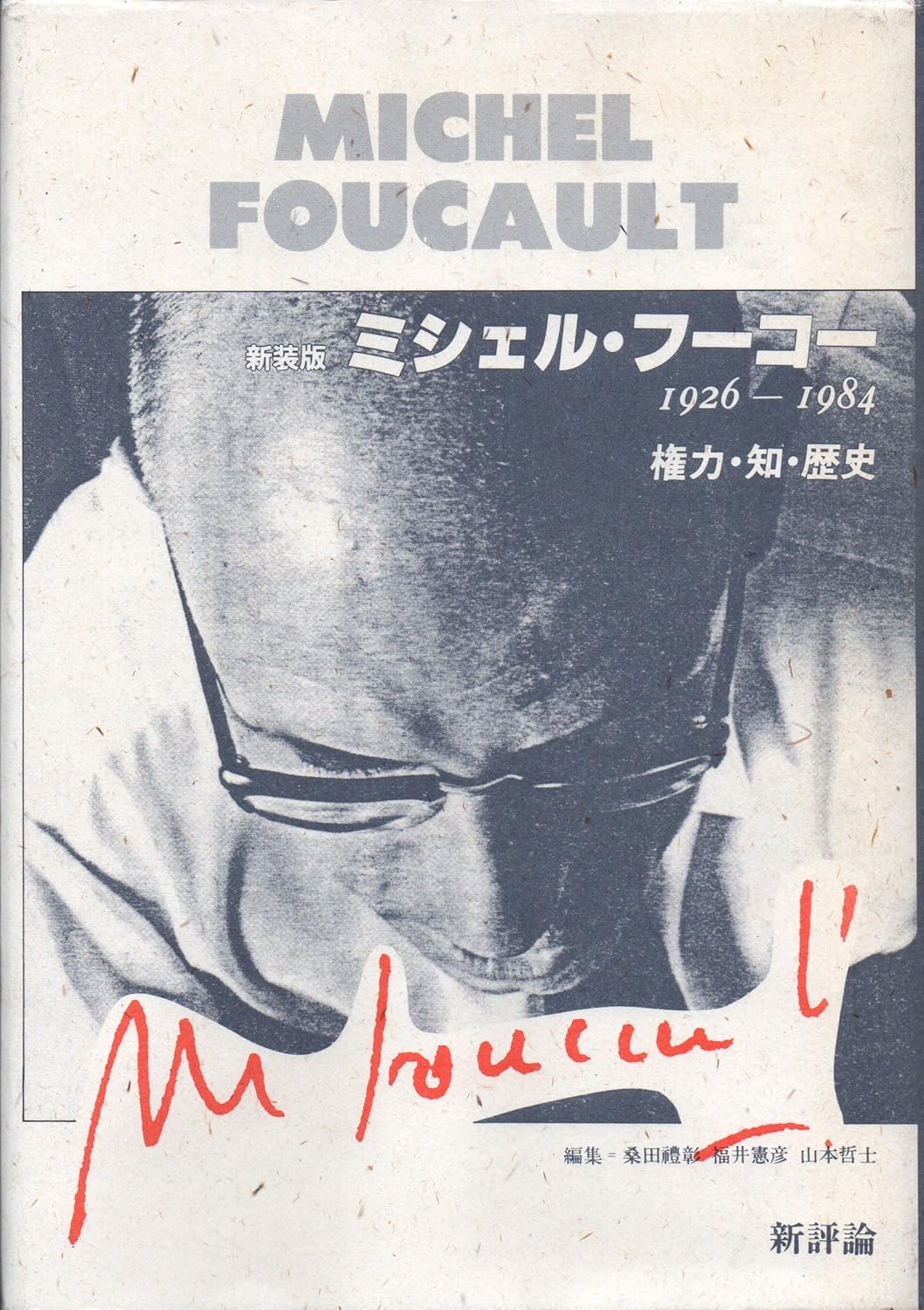追悼 ミシェル・フーコー はしがきにかえて
「真理や科学そのものが、じつは権力をはらむものであり、教育や(FF)医療など「社会の向上」をもとめる行為が同時に権力の網の目を構成するものであることを、白日のもとにさらした。そして権力の問題を、抑圧と禁止の問題のみに還元してしまってきた既成の権力観を、根底においてくつがえしたのである。
この〈権力〉は、けっして一枚岩をなすものではなく、歴史上のさまざまな〈事件〉を通じて、複雑な網の目のごとく交差しながら編制されてきた。」(P.1-2)
一九八四年九月 桑田禮彰・福井憲彦・山本哲士
●フーコーは語る●
権力について 『狂気の歴史』から『セクシャリテの歴史』まで
(聞き手)ピエール・ボンセンヌ (訳)桑田禮彰
一九七八年のインタビュー
『狂気の歴史』
『言葉と物』
『監視することと処罰すること』
『知への意志』
「厳密にいえば「権力は実際にどのように行使されているのか。あるものが別のものに権力を行使する場合、具体的にどのように事態は運ぶのか」という問題です。そうして問題意識のなかで、やがて、性の領域がどんな社会の中でも とりわけわたしたち西欧社会で 強力に規制されているかぎりにおいて、性こそ、権力のメカニズムのポイントをおさえるのに適した領域だ、と思うようになりました。」(P.25)
ピ「「権力にとって、セックスを禁止するより告白させたほうが都合がよかった」ということを示してみせたわけですね。」(P.26)
「実際は、性に関する言説は、ある特定のいくつかのコードをと関連しながら、あるしかたで組織だてられているのです。」(P.26)
権力の分析
ピ「「だれが権力を実際に行使しているのか、そして、どこでそれを行使しているのかということは、いまのところぜんぜん明らかにされていないんだ。なるほど、だれが搾取し、どこで利潤があがり、それがだれの手をわたり、どこにまた投資されているかということなら、すでにおおむね明らかになっている。」(P.27)
権力の戦略ネットワーク
「具体的にどのような経緯をへて、一八世紀末ごろ、監獄をいちばん重要な懲罰様式として選ぶことに決まったのかを調べてみますと、実際には、それに先立って、人びとの行動範囲を一定の場所に限定する技術、人びとを一定の場所に定住させる技術、人びとにある特定のいくつかの仕事や習慣を強制的に押しつける技術な(FF)ど、こうしたさまざまな技術が長いことかかって入念に仕上げられていたことがわかります。ひとことでいえば、それは、文字どおり人びとを「調教する dresser 」技術です。」(P.30-31)
「つまり、大作業場の場合、これらの新しい管理技術が生産という経済上の必要性に応じていたことはもちろんです。でも、兵営の場合は、これらの技術は、実際上の、同時に政治上の問題に密接に結びついていました。」(P.31)
「いいかえれば、わたしは終始、こうした調教の方法の経済的ないしは政治的起源をを示しましたが、だからといってすべてを権力で説明しようというのではなく、わたしは、こうした新しい調教技術の特殊性が存在する、と考えているんです。つまり、個人の行動を操作する具体的なやり方にまで利用されるさまざまな手順は、ひとつの論理を持ち、ある型の合理性に従い、相互に支えあいながら、ある特殊な層をなしている、と思うわけです。」(P.32)
権力と知
「しかし、一般的にみれば、「社会が科学的観察の対象になりうる」というような事実、「ある一定の時期から人間行動が、分析し解決しなけりゃいけない問題になった」というような事実は、とにかく権力のさまざまなメカニズムに密接に結びついている、とわたしは思うんです。ある時期に、まさにこれらのメカニズムが、そうした対象 社会、人間、等々 を切り抜き、解決しなきゃいけない問題として、それをつきつけてきたのです。だからこそ、人文科学の誕生は、権力の新たなメカニズムの成立と、期を一にしているわけです。」(P.33)
「「科学とは、命題を反証したり、誤謬であることを証明したり、神話を暴いたりすることができる手続きの総体である」というだけでは不十分です。科学は権力を行使するということを忘れてはなりません。科学は文字どおりひとつの権力であって、あなたにある特定のいくつかのことだけを強制的にいわせようとします。そしてその指示にしたがわないと、あなたはまわりの人から、「思い違いをしている人」とみられるだけならまだしも、「ペテン師」というレッテルをはられかねないのです。科学は、大学組織を通じて、また、実験研究設備のシステム、まさしく強制的なシステムを通じて、権力として制度化されました。」(P.34)
「真理とは権力の一形式である、といったっていいでしょう。まさにこの点では、要するに西洋哲学が「なぜわたしたちは真理にひかれてしまうのか。なぜ嘘よりも真理に、なぜ神話より真理に、あるいは、なぜ錯覚より真理に」という問をたてるかぎりで、わたしは西洋哲学の根本問題のひとつを取り上げているだけのことです。(FF)でもわたしは、真理を誤謬に対置しながら「真理とは何か」を知ろうとするのではなく、ニーチェがつきつけた、「具体的にどのようなぐあいに、わたしたちの社会のなかで、『真理』にこんな特別な価値が認められるようになり、そうした価値のせいで『真理』がわたしたちにとって絶対的な強制力をもつようになったのか」という問題を、深刻にうけとめなければならないと思います。」(P.34-35)
「なんでも知っている知識人」と「特定領域の知識人」
(P.35)__専門家は、全体をいうことはなく、それを担うのはタレントになった。知識は蓄積されてきた。でも個人の「存在」が大きくなったのではない。全体を「知っている」人は、先進国にはひとりもいない。専門家とエキスパートの違いを「プラスチックワード」で確認せよ。
「いいかえますと、なにか仕事をやっているまさにそのとき、わたしはいまなにをやっているのか、と問うことです。一五年ほど前から少しずつ目立ってきましたが、現に、精神科医、医者、弁護士、判事たちは、自分たち自身の職業を批判的に検討しています。こうして彼らは、知的生活の本質的要素である「疑う」という仕事を行っているわけです。」(P.36)
マスコミとベスト・セラー
《 Du pouvoir : un entretien inédit avec Michel Foucault 》, L'Express, 13, juillet 1984. ©1984, L'Express
Ⅰ
セックスと権力
(聞き手)ベルナール=アンリ・レヴィ
(訳)桑田禮彰・福井憲彦・山本哲士
セックスと真理
「西洋の歴史は、「真理」が生産され、その「真理」がみずからもたらす結果を刻み込む、その様式と分かち難いものだということを、今度も彼らは理解することになるでしょう。「どんなことでも、やがては皆にわかってもらえる」ものです。」(P.49)
「「真なる」言説(これはたえず変化するものでもあるのですが)を備え付けることは西欧の基本問題のひとつなのです。「真理」の歴史 真理として受け入れられた言説に特有の権力の歴史 、これをいまこそまるごと書くべきなのです。」(P.49)
性の抑圧と子どものセクシュアリテ
「問題は、そうした苦悩を、基本的な禁止あるいは経済状況と相関関係にある禁制(「働け、恋愛に耽ってはならぬ」)によって否定的に説明すべきなのか、それとも、はるかに複雑で積極的な手続の結果によって説明すべきなのか、を知ることなのです。」(P.51)__性欲の歴史、食欲の歴史、排泄欲の歴史、・・・。「必要 needs」と「渇望 desire」と「欲求」「意図」との関係。恋愛したい、恋愛しよう、恋愛しなければならない、どうして恋愛できないのか。恋愛の苦悩と性欲の苦悩。恋愛が性欲という物質的(対象)としてあらわれること。能動としての恋愛と受動・中動としての恋愛。性欲という本能をどう取られるか。本能は客観的存在(対象)か。
「後の巻でとりあげようと思っているものにこんな麗があります。世紀初頭、突然、子どものマスターベーションがひどく重大視されるようになり、いたるところで「全人類を腐敗させかねない突発性のおそろしい疫病」として迫害されるようになります。
「子どものマスターベーションが、発達中の資本主義社会によって突如として受け入れがたくなった」と考えるべきでしょうか。これは最近の「ライヒ主義者」の説ですが、わたしはこれだけでは不十分に思えるのです。
当時重要課題とされていたのは逆に、大人や両親や教育者と、子どもとの関係の再組織化であり、家庭内の関係の強化でした。両親にとっても「投資金(アンジュ)」になってきた子どもたち、そして将来の国民を育てる苗代としての幼少年期、(FF)そうしたものが重視されるようになったのです。身体と魂、健康と道徳、教育と調教、それらが行き交う場である子どもの性は、権力がむかってゆく標的であると同時に、権力を行使するための道具にもなったのです。たえず監視する必要のある、特殊で一時的ではあるが危険な「子どものセクシュアリテ」なるものが構築されたのです。
そこから幼少年期や青年期の性的苦悩が生まれてきました。わたしたちくらいの年代になってもその苦悩からはまだ解放されていないわけです。しかし、権力は、こうして苦悩をもたらすことを目標として追い求めていたわけではありません。禁止するのを狙っていたのでもありません。そうではなくて、突如として重大性をもち、秘密めいたものになってきた子どものセクシュアリテを通じて、子どもにたいする権力の網の目を築くことを狙っていたのです。」(P.51)__「子供の誕生」を参照。「子ども期の延長」「学校制度」と関わるのかも。
「そして、だからこそ彼らは、わたしたちに恐るべき罠をしかけていることになるのです。彼らはこんなことをいいます。「諸君には性衝動(セクシュアリテ)がある。性衝動は欲求不満を起こして黙り込んでいる。偽善的な禁止のために抑圧されている。だったら、わたしたちのもとに来たまえ。そしてわたしたちにすべてを語り、すべてをさらけ出し、不幸な秘密を打ち明けるがいい」、と。
このようなたぐいの言説は、実際には統制と権力のおそろしい手先なのです。いつもながら人び(FF)とのいっていることや、感じていること、望んでいることを利用しています。幸せになるためには言説の敷居を踏み越え、いくつかの禁止を取り除くだけでいい、と信じたがっている人びとの気持ちを悪用しているのです。そして、その実、反抗と解放の運動を押しもどして、警備を強めてしまうわけです。」(P.52-53)__Nota! 解告。これはセクシュアリテだけでなく、ほかの運動全般に言える。「〜ハラ」も同じ。中国の言論統制。
性の解放 同性愛者と女性のセクシュアリテ
「「あなたは、そもそも病気のかたまりなのだ」というのです。そして、こうした古くからの動きは一八世紀に突入すると、女性を病理学の対象とするにいたったのです。女性の身体は医療をほどこすべき典型的なものとなります。」(P.55)
アンチ・セクソ
「なんでもかんでも性ということになると性の比重がゼロになってしまうわけです。」(P.57)
「事物やまわりの人間たちや身体にたいして実にさまざまな多型的諸関係をとっていることこそ、幼児期でなくて何だというのでしょう。この幼児の多形にみちあふれている状態を、大人はみずからを安心させるために自分たちの性の単彩色で塗りたくって、倒錯とよんでいるにすぎないのです。」(P.58)
「一般にこういっておきましょう。禁止、排除、禁制、こういったものは権力の本質的な形態であるどころか、その極限的な状態であり、粗野で極端な形態にすぎない、と。権力関係はまず第一に生産的なのです。」(P.60)
権力諸関係のとらえ方
(これを理解するのに長い時間がかかりました)「第一に、西欧の権力はもっとも積極的にみずか(FF)らの姿を見せつけるものであり、それゆえ、かえってもっとも巧妙に姿を隠していたからです。一九世紀以降、「政治生活」と呼ばれているものは、権力が代表として与えられる仕方(王政時代の宮廷を扱う場合のように)をいいました。だが、権力関係は、たぶん、社会体の中のもっとも隠された事象の中にあるのです。
第二に、他方、一九世紀以降、社会に対する批判は本質的には、あらゆることを規定するという、経済が持っている性格から出発して行われるようになりました。たしかにこれは、それまで過大視されていた「政治」の健全な規模縮小だといえましょう。だが、それはまた、経済諸関係を構成する要素となる権力関係をないがしろにする傾向でもあったのです。
第三の理由というのは、いくつかの組織や党など革命的な思想や行動の流れ全体に共通しているのですが、権力をもはや国家形態や国家諸装置の中にしか見ようとしない傾向です。
このため、個々人に目を向けるときでも権力を彼らの頭の中に(思想の表現や受容、内面化といった形で)しか見出そうとしない結果になってしまいます。
では、それに直面して何をなさろうとしたのですか。
フーコー 四つあります。権力諸関係の中にありうるもっとも隠されたものを探し求めていくこと。権力諸関係を経済的な下部構造の中でまで捉え直すこと。国家という形式にあらわれた権力諸関係を追求するだけでなく、国家の下位にあったり、国家をこえでたり(FF)する形式においても追求すること。権力諸関係をそれらの物質的作用の中で再発見することです。」(P.61-62)
革命と政治
「キリスト教の初期の数世紀の思想は、つぎのような問いに答えなければなりませんでした。「現に過ぎ去っていくのは何なのか。われわれ人間のものであるこの『時間』とは何なのか。われわれに約束されている神の再来はいつ、いかにして起こるのか。余計なものとして存在しているこの『時間』をどうすればいいのか。そして、われわれ、この移ろいゆくものでしかないわれわれとは何なのか」。
革命がめざされているに違いないが未だ到来せずにいる、この歴史の中腹にあって、わたしたちは同じ問を発しているのだといえるでしょう。「過ぎ去るべきことが過ぎ去らずにいるこの時代にあって、余計なものでしかないわれわれとは何か。近代思想の全体は政治と同様、革命の問題に支配されてきたのです。」(P.65)
権力と戦略
「そして、そのため、知識人は「何が起ころうとしているか」を述べるという自負をもたないばかりではなく、立法者としての機能も持っていないと思います。彼らは長い間立法者になることを願っていたのですが。「ほら、これがしなければならないことで、あれが正しいことだ。わたしに従いたまえ。諸君全員がまきこまれている動揺の中にあって、このわたしのいる場所が固定点なのだ」というふうに。ギリシャの賢人、ユダヤの預言者、ローマの立法者らが今日語ったり書いたりするのを職業とする者たちに、相も変わらずつきまとうモデルです。しかしわたしは、あたりまえなことや何にでもあてはまることを破壊する知識人を夢みます。」(P.70__あたり前のことをいう必要はない。
《 Non au sexe roi 》, Le Nouvel Observateur, 12 mars 1997.
©1977, Le Nouvel Observateur
sふぁ
真理と権力
(聞き手)M・フォンタナ
(訳)北山晴一
科学とイデオロギー
権力の体制
構造と事件
真理の系譜学的アプローチ
「あなたのおっしゃる構成の問題についてですが、わたしはそれを構成主体に送り返すのではなく一つの歴史的枠組の内部で解決するにはどのようにしたらよいのか、みきわめたかったのです。構成主体をお払い箱にすることによって主体そのものからも自由になる必要があります。いいかえれば、主体がどのように構成されるかを歴史的枠組の中で明らかにすることができるような分析に到達する必要があるのです。それが、わたしが系譜学と呼ぶものの中身なのです。」(P.83)
「イデオロギーという観念は、用いることがたいへんむずかしいのではないか、と思います。それには三つ理由があります。第一の理由は、望もうと望むまいと、この観念は、ある種の真理といってもよい何物かにたいして、つねに潜在的に対置されているからです。ところが、だいじなことは、ひとつの言説のなかで、科学性とか真理の領域に属するものと、それ以外の領域に属するものとの間に分割線を設けることではなくて、それ自体は真でも偽でもない言説の内部に、どのようにして真理としての効果が生じてくるのか、を歴史的にみきわめることなのです。第二の不都合は、イデオロギーという観念が、わたしのみるところ、主体のような何物かに必ず準拠している、ということにあります。そして第三の理由は、イデオロギーが、そのイデオロギーの下部構造ないしは経済的・物質的決定因などとしての役目を果たしている何物かにたいして、一歩退いた位置にあるからです。」(P.84)
「もし権力が、ただたんに抑圧するばかりでしかなかったら、「否」ということ以外何もしないものであったなら、はたして人は権力にいつまでも従っているものでしょうか。そんなことがほんとうに可能だとお考えですか。ところが現実には、権力はしっかり立っているし、人びとに受け入れられているのです。その理由はしごく簡単です。それは、権力はたんに「否」を宣告する力として威力をふるっているわけではなく、ほんとうはものに入りこみ、ものを生み出し、快楽を誘発し、知を形成し、言説を生み出しているからなのです。権力は、社会体の全域にわたってはりめぐらされた生産網なのだ、と考える必要があります。」(P.85)
(一七、八世紀以降の技術的離陸)「何にもましてだいじなことは、今なら権力の新しい「経済学」と呼びうるような何物か、すなわち、権力が及ぼす作用を連続した、途切れのない、対象にあわせた「個別化された」やり方で社会体の全域に行きわたらせることのできる技術がそのころ確立されたことなのです。」(P.86)
新しい知識人の役割
普遍性から特定性へ 大作家時代の終わり
「「普遍的」知識人とは、法律家−名望家からわかれて出てきたものであり、すべての人がそこで自己の像を認めることのできるような、意味と価値の保持者としての著述家となることで、十全な自己表現を見出したわけです。これにたいして「特定領域の」知識人はまったく別の人間像から、すなわちもはや「法律家ー名望家」ではなく「学者ー専門家」から派生したものです。」(P.91)__『プラスチック・ワード』エキスパートと専門家。「〜がこういっていた」とはいえるけど、その人のようになりたいわけではない人間像。人間像ではなく、単なる「知(の権力)」が人の姿をとったもの。偶像。アイドル。コメンテーター。
「もはやそれは永遠を歌いあげる詩人ではなく、生と死の戦略家なのです。すなわちわれわれはいま、「大作家」消滅の時代を生きているのです。」(P.93)__学問の細分化と、科学優先が原因だと思う。
真理と権力作用
「思うに、重要なことは、真理は権力の外にも、権力なしにも存在しない、ということです(真理は、自由精神への報酬でも、長い孤独の産物でも、自己解放をなしとげた人びとの特権でもありません。真理をそのようなものとみなす神話はありますが、そうした神話の歴史や果たす役割は、再検討されねばならないでしょう)。真理はこの世のものなのです。真理は、この世の数々の制約があればこそ、生みだされたものなのです。真理は権力(FF)作用、それも調整ずみの権力作用を手中に収めています。どの社会も固有の真理体制を、すなわち真理についての固有の「一般政策」をもっています。具体的にいえば、その社会が真なるものとして受け入れ機能させる特定の言説タイプ、言語表現に真偽の区別をあたえるメカニズムとベクトル、真と偽のそれぞれにたいする取り扱いの処方、真理の獲得に有効とされる技術と手続き、何が真であるかを決定する権限をもつ人間の地位、などがその内容です。
われわれの社会のような諸社会において、真理の「政治経済学」を特徴づける要素は、歴史的重要度という点からすれば、五つ考えられます。第一に、「真理」は科学的言説の形式とその言説を生みだす諸制度とを、その中心軸としています。第二に、「真理」は不断の経済的、政治的要請に従属しています。(経済生産と政治権力はともに真理を必要としています)。第三に、「真理」は、さまざまの形で、巨大な流通と消費の対象となっています(「真理」は教育や情報の諸機構のなかで流通し、ひろまります。これらの機構の社会的広がりは、たしかにある種のきびしい制約を受けてはいるものの、かなり大きなものです)。第四に、「真理」の生産と伝達は、いくつかの巨大な政治・経済機構(大学、軍隊、文字表現、メディア)の支配的な 独占的な、ではない 統制のもとで、行われています。そして第五に、「真理」はあらゆる政治論争、あらゆる社会対立(いわゆる「イデオロギー」闘争)の争点となっています。」(P.94-95)
「いいかえれば、知識人は三重の特定性をその本質としています。第一は、彼の階級的位置の特定性(資本主義に奉仕するプチ・ブルジョワ、プロレタリアの「代弁者」たる知識人)。第二は、生活と仕事の条件 しかも知識人としての立場に結びついた条件(研究分野、研究所内の地位、あるいは大学や病院その他の場所で彼が甘受し、ないしは意義をとなえている経済的、政治的強制)。第三は、われわれそれぞれの社会の、真理政策の特殊性です。知識人の存在が一般的意味をもつ地点があるとすれば、それはまた知識人の局部的で特定された闘いが、職業や領域の枠を超えた作用や影響を生みだす地点があるとすれば、以上のような地点においてなのです。」(P.96)
「闘いがあるとすれば、それは「真理のための」、あるいは少なくとも「真理をめぐって」の闘いです ここでもう一度念をおさせていただければ、いうまでもなくわたしが真理という語で意味していることは、「発見すべき、あるいは人に認めさせるべき真なるものの総体」ということではなく、「われわれが真と偽を見分け、真なるものに特定の権力作用を付与するときに使う、もろもろの定規の総体」のことです。」(P.96)
「「真理」は、それを生み出し支える権力システム、および、真理に誘発され、ついで逆に真理を誘導する権力作用に、循環的に結びついています。これが真理の「体制」です。
この体制はたんにイデオロギー的、上部構造的なものではありません。それは、資本主義の成立と発展の条件だったのです。多少の修正は受けたものの、今日の社会主義諸国の大部分で機能しているのも、この体制です(中国については知識がないので、問題を白紙にしておきます)。」(P.97)
「真理をいっさいの権力システムから解放せよといっているのではありません 真理はそれ自体が権力なのですから、これは幻想です。真理がいまのところその内部で機能せざるをえないでいるさまざまなヘゲモニー形態(社会的・経済的・文化的)から、真理の権力をひき離すことが課題なのです。
結局のところ政治的問題とは、失敗でも幻想でも、疎外された意識でも、またイデオロギーでもありません。それは真理それ自体のことなのです。」(P.98)
《 Vérité et pouvoir 》, L'Arc, n˚70, 1977.
©1977, Michel Foucault
権力と戦略
(聞き手)グループ・レヴォルト・ロジーク
(訳)大木憲
強制収容所問題
権力と精神分析的理解
「ファシズムにたいする分析が行われなかったことは、過去三〇年におけるもっとも重大な政治的事実のひとつです。」(P.108)
「すなわち、権力の手続きを、ものごとを禁止する法に還元してしまうという問題です。この法令への還元は、三つの主要な役割を果たしています。
①どのようなレベルであれ、またどのような領域であれ、つまり家族であれ国家であれ、あるいは教育関係であれ生産関係であれ、権力は同質なのだという図式の主張を可能にする役割。
②権力というものを拒否、障壁、検閲といった否定的な用語だけでしか考えないことを、可能にする役割。権力とは、つまるところ否をいうものだ、というわけです。そのように理解されると、権力と衝突することは、侵犯としてしかありえないようになってしまいます。(FF)
③権力の基本的な作戦は言葉を発する行為にある、とみなす考え方を可能にする役割。」(P.109-110)__「 oui 」という法律。福祉国家。please じゃなくて do という法律。「 oui 」に対する反抗。食べない、好きなことをしない。してもよい。してはならない。しなければならない。するほうがよい。するべきだ。
「権力に関する唯一で同一の「定式」(つまり禁止ということです)が、こうしてあらゆる形式の社会に、またあらゆるレベルの隷属について適用されるわけです。さてしかし、権力を禁止の決定機関とみなすことによって、ひとは二重の「主観化」にみちびかれることになります。権力を行使する側では、権力は禁止をはっきりと言明する一種の偉大で絶対的な「主観」として、理解されます。それが現実的存在だろうと想像であろうと、純粋に法制上のものであろうと、そんなことはどうでもよいわけで、たとえば父親とか君主とか、一般意志だとかの最高権力がそれにあたります。権力が行使される側についても、どの点で禁止の受容が成立するか、どの点で権力への「承服」と「反対」とが表明されるかを定めるということにおいて、やはり「主観化」されるということになります。だからこそ、最高権力〔主権〕の行使を説明するために、自然権の放棄とか、社会契約とか、支配者の愛だとかが想定されたりするのです。古典主義時代の法学者がうちたてた体系から、現在の考え方にいたるまで、つねに問題はおなじ関係のもとに提起されているように思われます。つまり一方に禁止するのがその役割である君主がいるのにたいし、他方に、その禁止(FF)になんらかの形で「了解」と言わざるをえない臣下がいる。」(P.110-111)__主客構造の投影。
(西洋社会における「法」)__東洋における法との違い。中村元。
「他方、特に一八世紀において法は、王権に対抗して戦うための武器でもありました。かつては王権の方が、その力を確立するために法を用いたわけですが。そして最後になりますが、法はまた、権力の主要な表象様式でもありました(ここで表象とは、おおいとか幻想として理解されてはならず、現実の行動様式と理解されねばなりません)。」(P.111)
権力関係の分析
「 権力とは、社会体と、外延を同じくするものである。権力という網の、目止めの間に、さまざまな基本的自由の場が広がっているわけではない。
権力関係は、他のタイプの関係(生産関係、婚姻関係、セクシュアリテの関係)の中に本質的に含まれており、そこで、条件づける役割を演ずると同時に、また条件づけられた役割をはたす。
権力関係は、禁止とか懲罰という唯一の形式に従うわけではなく、実にさまざまな形式をもつ。
権力関係どうしの交錯が、支配の一般的な諸事態を描きだす。」(P.113)
「 権力関係は、実際「役に立つ」。」(P.114)
「 抵抗をともなわない権力関係は、存在しない。抵抗は、まさに権力関係が働くその場に形成されるものであるからこそ、いっそう現実的で効果的になる。」(P.114)
「以上が、わたしの仮説です。」(P.114)
道具箱としての理論
(P.115)__権力の網の目と目の間をつけば(犯罪としても、抵抗としても)そこが権力の弱点(影響が不十分であった点)であることを教えることになる。権力は、そこを利用し、福祉や禁止を行う。権力は「苦」をつくり出すと同時に「快」をつくり出す。何を「快」と感じるかも社会(体)がつくり出す。
「道具箱としての理論とは、つぎのことを意味します。
体系ではなく、ひとつの道具を構築することが問題なのだ。権力の諸関係に固有な、そしてそれら諸関係をめぐって引きおこされる闘争に、固有な論理を構築することが問題なのだ、というのが第一点です。
この追求は、一定の与えられた状況についての考察から出発して、一歩一歩進むかたちでしかなされえないこと(この考察は、その考察諸次元のいくつかにおいて、必然的に歴史的考察となります)、これが第二点です。」(P.118)__フーコーの方法論。フーコーの諸著作はこの原則に基づいている気がする。
《 Pouvoirs et stratéfies 》,Les révoltes logiques, n˚4, hiver 1977.
©1977 Michel Foucault
Ⅱ
健康が語る権力
(訳)福井憲彦
「病気はつねに、個人的な不幸とか苦痛より以上のものなのだ。「私的な」医療は、病気に対する集合的な反応の一様式なのである」(P.123)__病は気から。
(「健康保全の政治」)「1 ある種の目標の移動、ないし、少なくとも目標の拡大。すなわち、病気が出現したところで、その病気を抑えつけるばかりではなく、病気を予防することがまた問題となる。さらには、どのような病気であれ、すべて可能な限り予防すること、が。
2 健康という観念の二重化。すなわち(病気の反対としての)伝統的な規範的意味のほかに、状態を描写する意味作用が加わる。そうして健康は(さまざまな病気の頻度、それぞれの病気の重さと継続期間、病気を惹起しうる諸要因への抵抗、といった)諸データの全体を観察してえられた結果となる。
3 一集団ないし集合体に特徴的な諸変数、すなわち死亡率、平均寿命、それぞれの年令に応じた余命年数、ある地域に住む人々の健康状態の特徴をなす流行性ないし風土性の病気の確定。
4 治療上の干渉でもなく、あるいは厳密な意味での医療上の干渉でもないような型の干渉の発展。つまり、生活条件や生活様式、食料、住居、環境、子どもの育てかた、などに関するものである。
5 最後に、社会の合理化をめざす経済的政治的管理に、医療行為が少なくとも部分的に組みこまれたこと。医療はもはや、集合体がけっして無関心ではありえない諸個人の生と死における、重要な技術というにとどまらない。医療はさらに、全体にかかわる諸決定の枠のなかで、集合体の維持と発展にとって本質的な一要素となるのである。」(P.124)
「このような貧困の実利的な解体のなかにこそ、病気という固有の問題が、労働という至上命令と生産の必要とへの関係のなかで、たちあらわれはじめるのである。
健康保全の政治の登場は、また、はるかにいっそう全般的なある過程と、関係づけられねばならない。すなわちそれは、社会の「福祉」が、政治権力の本質的目標のひとつとされた過程である。」(P.126)
「静穏さとよき秩序をこえて、さらにこの「公益」を保証するために作動させられるべき諸手段の総体こそ、おおまかにいって、ドイツとフランスで「警察 police 」とよばれたものにほかならない。」(P.127)
「この同時代には他方で、市民社会の法的規定や形式を考えることが求められていたのであるが、警察は、いわばこの市民社会の物質的ことがらを担当するのである。
ところで、この物質的ことがらの中心に、一七、一八世紀を通じてその重要性がたえず確認され、増大し続ける一要素が、たちあらわれる。すなわち人口 populaion である。すでに伝統的にこの語は、居住可能な面積に応じた住民数という意味で了解されていたが、さらに、相互に共存関係をもち、そういうものとしての諸個人の総体、という意味でも理解されるようになる。そうして人口は、みずからの増加率をもち、また死亡率と罹患率をもつことになる。」(P.128)__平均寿命が上がろうが下がろうが、あなた(わたし)の寿命が変わるわけではない(関係ない)。
「以上が、一八世紀にはっきりとしてくる「健康保全の政治」の、二つの主軸である。つまり、病人をそれとして担当することのできる装置の構築(健康が、回復すべき状態という意味をもち、また到達すべき目標という意味をもつのは、まさにこの装置のためなのである)。そしてまた、住民たちの「健康状態」を常時観察し、改善しうる装置の整備。この装置にあっては、病気は一連の多数の要因に従属し(FF)た一変数でしかない。」(P.129-130)
1 幼少年期の優位化と家族の医療化
「もはやたんに、最適数の子どもを産むことのみが問題なのではなく、人生のこの年齢段階を、しかるべく管理することが問題とされているのである。」(P.130)
「そのとき家族は、より狭い範囲で切りとられることによって、物質的な容姿を持つことになる。すなわち、子どもをとりまく身近な環境として組織だてられ、子どもにとっての、生存と(FF)発達の直接の枠組となっていくのである。これは、締めつけの強化という結果をもたらす。あるいは少なくとも(親子集団という)狭義の家族を構成する諸要素や諸関係の強化を、もたらす。」(P.130-131)
「新たな「結婚のあり方」は、むしろ両親と子どもたちとを結合させるものなのである。狭く限局された形成装置としての家族が、伝統的な大きな家族=姻族関係の内部で、強化される。そして同時に、健康 なにより子どもたちの健康 が、家族がもっとも配慮せねばならない目標のひとつとなる。両親と子どもたちが形成する四角形は、いわば一種の健康自動安定状態を、保証せねばならないのである。」(P.131)
「家族は、よき健康という「指摘」な倫理(両親と子どもの相互の義務)を、衛生という集合的統制と接合し、そしてまた、個人と家族の要請にもとづいて、国家によって推薦された有資格の医師たちの職業集団が保証する治療の(FF)科学的技術とも、接合することを可能にしたのである。」(P.132-133)
「しかしこのことは、医療化されるとともに医療化の担い手となった家族、という、一八世紀に形成された中心要素を考慮に入れないならば、理解することはできない。」(P.133)
2 衛生の重要性と社会統制の審級としての医療の作動のありかた
「生活の規則としてと同時に、予防医療の形式としても理解されていた、節制 régime という旧来の観念は、その範囲を広げはじめ、全体としての人口の集合的な「体制 régume 」となってゆくが、そのさい目標は、三つあった。すなわち、大疫病流行の消滅、罹患率の低減、平均寿命の延長、である。住民たちの健康保全体制としての衛生は、医学によるいくつかの権威的干渉と統制の掌握とを、ふくんでいる。
それはまず第一に、都市空間全般に対して、なされる。というのは、人口にとってのおそらくもっとも危険な環境をなすのは、都市空間にほかならないからである。」(P.133)
「一八世紀と一九世紀はじめにおいて、医者に政治的に優越した地位を保証するのは、その治療者としての威信であるよりも、まさにその衛生学者としての役割なのである。」(P.135)
3 施療院(病院)の危険と有用性
「荘重な建物ではあるが、病気の外部への流出を妨げることもなく、内部では病気を増殖させてしまうという、不手際な建物。」(P.135)
「というのも施療院が施す救援は、けっして貧困の減少を可能にしないし、せいぜい貧困者のいくらかが生きのびることを可能にするばかりだからである。ということは、貧困者の数を増加させ、彼らの病気をひきのばし、ひいてはあらゆるたぐいの感染が結果する可能性がある、というわけである。」(P.136)
「したがって、医学的知識と治療上の有効性とが、施療院(病院)において接合させられねばならない。そうして一八世紀において、特定の医療を行う施療院(病院)が出現する。かつても、狂気の者や性病患者のための施設はいくつか存在した。だがそれらは、医療看護の特定化のためであるよりも、排除の手段としてであり、あるいは危険を恐れてのことであった。」(P.139)
《 La politique de la santé au XVIIIe siécle 》, M. Foucault et al., Les machines à guérir, Bruxelles, 1979.
©1979, Pierre Mardaga.
歴史と権力
(訳)尾崎浩・桑田禮彰・福井憲彦
なぜ監獄か
「わたしが監獄を研究対象にとりあげるのが正当だと思ったのは、ふたつの理由によります。第一に、監獄がそれまでのいろいろな分析のなかで、かなり無視されていたこと。」(P.144)
「監獄を研究しようとした第二の理由は、こういうことです。道徳の系譜学というテーマを、再びとりあげること、ただし、いわば「道徳のテクノロジー」とでもよべるものの変容の系をたどりつつ行うこと。なにが罰されるのか、なぜ罰するのかをよりよく理解するために、どのように人は罰するのか、という問いかけをすること。この点では、わたしは狂気にかんする研究のさい歩いたのとまさにおなじ道を、たどっていたわけです。すなわち、ある一定の時期に、なにが狂気とみなされ、なにが非=狂気とみなされたか、なにが精神病とみなされ、なにが通常の行動とみなされたか、と問うよりも、むしろ、どのようにして人はその区分をしたか、を問うてみることです。」(P.144)
「反精神医学のテーマが問題化されたのは、一九五八年から六〇年にかけてのことなのです。強制収容所の経験との関係は、明らかです。」(P.145)
「ほかの仕事の場合もそうですが、監獄にかんするこの仕事の場合も、標的というか、分析の攻撃地点は「制度」とか「理論」、あるいは「イデオロギー」ではなく、「実践」でした。それは、ある所与の時点でこれらの実践をうけいれ可能なものとする諸条件を、とらえるためです。わたしのたてた仮説によると、実践の諸類型は、たんに制度によって指揮され、イデオロギーによって規定され、あるいは周辺状況によって導かれるような そのそれぞれの役割がどんなものであろうとも ものではなく、ある程度まではそれら固有の規則性や論理、戦略、自明性、「理性」をもっている、というものでしたから、問題は「実践の体制(レジーム)」を分析することにあります。もろもろの実践とは、人がいうことと行うことが鎖のように結びつき、また、みずからに課した規則とみずからに与える理由づけとが、そして投企と自明性とが結びつきあう、そういう場とみなされるからです。
「実践の体制」を分析することとは、つまり行為のプログラミングを分析することです。そうした行為のプログラミングは、行うべきこととの関連で命令の効果(「法の強制」 juridiction という効果)をもち、同時にまた、知るべきこととの関連でコード化の効果(「真理の強要」 véridiction という効果)をもっているわけです。」(P.145)
「問題なのは、それにまつわるいつわりの自明性をぐらつかせ、その根拠が不安定であることを示すことです。」(P.146)__ソクラテスみたい。
「わたしは、いわば「異様な現象」としての変異であるこの非連続から出発して、それを消しゴムで消してしまわずに、説明するように努めたのです。だから問題は、隠された連続性を再発見することではなく、このひどくあわただしい移行を可能にした変換作用がなんであったかを、知ることなのです。
ご承知のように、わたしほどの連続論者もそういないのですよ。非連続を突きとめること、それはつねに解決すべき問題の存在を認証することにほかならないのですから。」(P.146)
事件化すること
「では、事件化とはなにを意味するか、といえば、まず自明性を断ち切ることです。
問題は、一般に歴史的に恒常的なものとか、直接的な人類学的特徴とか、あるいは、すべての人にたいしておなじように押しつけられる自明性とかに準拠される傾向のあるところで、あえて「特異性」を浮びあがらせることです。それが「さほど必然的なこと」ではなかった、と示すことです。狂人が精神病者として認定されることは、それほど自明のことではありませんでした。犯罪者にたいしてなすべき唯一のことといえば、閉じこめることだということも、それほど自明のことではありませんでした。病気の原因は、個人の身体の検査に求めるべきである、ということも、やはりそれほど自明のことではありませんでした。こうしたさまざまな自明性を断ち切ること。われわれの知、われわれの同意、われわれの実践が基盤をおいている自明性を断ち切ることです。これが、事件化とわたしがよんでいるものの、第一の理論的=政治的な機能なのです。
さらにじけかとは、のちに自明で普遍的で必然的なものとして機能することになるものを、ある時点で形成したいろいろな合流、衝突、援護、封鎖、力のゲーム、戦略などを、再発見することでもあります。ものごとをこのようにとらえることによって、われわれはいわば因果関係をいくつにも割ってゆくことになるわけです。」(P.147)
「(a) 因果関係の分割とは、事件の分析を、その事件(FF)を構成するさまざまなプロセスに従って行うことです。」(P.147-148)
「(b) したがって因果関係の重さを軽減するには、プロセスとして分析される特異な事件の周りに「多角形(ポリゴーヌ)」、あるいはむしろ「理解可能性の多面体(ポリエードル)」を、作り上げることです。」(P.148)
「そして、分析すべきプロセスを内部から分解すればするほど、外部に理解可能性の諸関係を作ることができるようになるし、またそうしなければならなくなる、と考えねばなりません(具体的にいえば、刑罰実践の「監獄化」のプロセスをそのもっとも小さな細部にまでわたって分析すればするほど、よりいっそう学校化とか軍隊の規律といった実践にも、関係をもたざるをえなくなるということです)。プロセスの内部的分解と、分析上の「張りだし」の増加とは、対をなすものなのです。
(c) したって、こうしたやり方をとりますと、分析が進むにつれて、以下のように多形性が増大するということになります。
関連づけるべき諸要素の多形性。すなわち、「監獄」から出発して、教育学的実践、職業的軍隊の養成、(FF)イギリス経験論哲学、火気を扱うテクニック、労働分業の新たな手順なども考察に引きこむことになります。
記述される諸関係の多形性、それは(監視用の建築など)技術的モデルの移転にかかわるものかもしれないし、特定の状況(暴力行為の増加、公開処刑が引き起こす騒擾、あるいは追放刑が有効でなくなること)に対応する戦術的計算にかかわるものかもしれない。また(理念の発生や記号 シーニュ の形成、行動の功利主義的概念などにかんする)理論的図式の適用も、問題でありうるわけです。
準拠する諸領域における多形性(それらの領域の性質、一般性など)。ここで問題となるのは、細部についての技術的変化であると同時に、資本主義経済において、その資本主義経済の諸要求に応じて、作動させられるべく追求される権力の新たなテクニックでも、あるわけです。」(P.148-149)
「もうだいぶ前から歴史家たちは、事件をあまり好いておられないようで、「非事件化」を、歴史の理解可能性の原則としておられるようです。」(P.149)
「理解可能性の面ではあふれるほど多くのものがあり、必然性の面では欠落している(FF)わけです。
でもわたしにとっては、そこにこそ、歴史的分析と政治的批判とに共通する賭金があるのです。われわれは、単一の必然性の星のもとにいるわけではないし、そうした場に身をおくべきでもない、と思います。」(P.149-150)
合理性の問題
「ただそうした合理性の体制を、理性=価値で測るのではなく、わたしとしてはふたつの軸にしたがって分析したいと考えています。ひとつはコード化=規定化の軸(つまり、規則、処方、ある目的にたいする手段などからなる総体がここに形成される)で、もうひとつは真・偽の定式化の軸(つまり、それについての真の命題と虚偽の命題とをはっきり分けうるような諸対象からなる領域が、この軸で規定される)であります。」(P.151)
「もっとはっきりいいますと、私にとっての問題とは、いかにして人びとが、真理の生産を通じて(自分自身および他者を)統御するか、を知ることにあるのです。」(P.152)__Nota Bene !!日本にもあてはまると思うけど「真理」ということばは、一般的ではない。オウム真理教。日本語の何に当たるのだろう。「道理」「真実」「事実」「正義」「正しいこと」・・・。
「(1)監獄や、施療院(病院)や、あるいは精神病院の合理的図式は、歴史家だけが時代を遡った解釈を通じて再発見できる一般原則などではありません。それらは、明白なプログラムなのです。」(P.153)
「(2)もちろん、このプログラミングは、それが直接に活用する形式よりはるかに一般的な合理性の形式に、属しています。」(P.154)
「それはさまざまに異なった諸テクニックの全般化と相互関連化であって、そのテクニックのそれぞれは、もっと局部的な目標(学校での知識習得、銃の操作可能な部隊の養成)に答えることを、要請されているものなのです。
(3)これらのプログラムは、決してそのままの形で諸制度のなかにとりこまれたりはしません。そのなかのあるものは選ばれて、その他のものははずされます。」(P.154)
「プログラム、テクノロジー、装置 そのどれひとつとして「理念型」ではありません。わたしは、たがいに連関しあうさまざまな現実の織りなすゲームと展開とを、見すえようと努めます。あるプログラム、それを説明する結びつき、それに拘束的価値をあたえる法律など、これらすべては現実なのです。それは(別の様式に基づいたものではありますが)、プログラムに形を付与する諸(FF)制度、あるいはそれに多かれ少なかれ忠実に参加する人びとの行動とまったくおなじように、現実なのです。」(P.154-155)
「また、とくにフランスのような国で目立つことですが、国家の機能全体との関係で、司法の実践や司法関係者にみられるそれまでの自立性や島国根性を、減らそうとする試みがそうです。」(P.155)
「つまり、人びとが自分自身および他者を、「方向づけ」、「統御し」、「行動に導く」さいに、真なるものと虚偽なるものとを分割して示すという効果が、それです。それらの効果を、歴史的事件としての形式においてとらえること しかも、(まさに哲学の問題にほかならない)真理の問題にとってそれが意味するところのものをも、とらえること 以上が、だいたいにおいてわたしのテーマなのです。」(P.156)
「すなわち、「歴史とは、もしそのなかでたえず真・偽の分割が生産されているとすれば、いったい何なのであろうか」ということですね。そのさいわたしは、四つのことをいおうとしています。
(1)真・偽の分割の生産と変容は、どういう点で、われわれの歴史性を特徴づけ、また決定づける要因となっているのか。(2)この関係は、形式はつねに変化しつつ価値は普遍的な科学的知を生産してきた「西欧」社会において、どのような特定のやり方で作動してきたのか。(FF)(3)歴史が真・偽の分割を生産し、その分割に歴史的知が依拠しているなら、この歴史についての歴史的知とは、どのようなものでありえるのか。(4)もっとも全般的な政治的問題とは、真理の問題ではなかろうか。真・偽を分割する方法と、自分自身および他者を統御するやり方を、いかにして結びつかるか。その双方の基礎をまったく新たに、その一方を他方によって築きなおそうとする意志(つまり別の統御の仕方によってまったく別の分割を発見し、別の分割の仕方から出発してまったく別の形で統御しようとする意志)、それこそ「政治的精神性」ということではないでしょうか。」(P.156-157)
麻痺効果
「ところでわたしの計画はといえば、そんなおおがかりなものとはほど遠いところにあります。なんらかの形で、狂気、正常、病気、犯罪、処罰にかんするいくつかの「自明とされること」や「常套句」がはげ落ちるように手助けすること。ほかにもいろいろありますが、とりわけある種の言葉が、もはやそうかんたんには口にされなくなるように、ある種の身ぶりが、少なくともいくらかの躊躇なしにはもはや行われなくなるようにすること。知覚のあり方、行動の仕方において、なんらかの変化が起こるように貢献すること。感受性の形態や許容度の敷居を、困難ながらも動かすことに参加すること。ざっとこんなところで、それ以上にやれる力が私にあるとは思えません。」(P.258)__過去の著作を見直すと、自分でも知らなかったことが書いてある。
「人びとの皮膚が恒常的にヒリヒリしているということは、わた(FF)しを勇気づけるものなのです。」(P.158-159)
「少なくとも一九世紀いらい、麻酔と麻痺との区別は、はっきりつけられるようになっています。
(1)麻痺。」(P.159)
「つまり監獄の問題とは、わたしの眼からみれば、「ソーシャル・ワーカー」の問題ではなく、囚人たちの問題なのです。」(P.159)
「(2)しかし麻痺は麻酔と同義ではない。その逆です。」(P.160)
「しかしわたしの考えでは、「今後なすべきこと」は上から、予言者的、あるいは行政的職能をもつ改革者によって決定されるべきものではなく、長期にわたる往ったり来たりの作業、意見交換、熟考、試行、さまざまな分析などの仕事を通じて、決められるべきもののように思えます。」(P.160)__ソクラテスに似ている。ゆさぶつこと。立ち止まってちょっと考えること。
「批判は、すでにある法にたいし、さらに法をつくるようなものであってはならない。それは、プログラミングの一段階ではなく、現在あるものにたいする挑戦なのです。」(P.160)
「変革が起こるのは、この現実にかかわりのある人たち、そうした人たちのすべてが、お互いどうし、また自分自身ともぶつかりあい、ゆきづまりや当惑、不可能性に直面し、紛争や対立をのりきったときであり、批判が実際に行使されたときのことであって、改革者たちがみずからの考えを実現したときのことではないでしょう。」(P.161)
「一方、わたしの全般的テーマといえば、社会なるもの一般ではなく、真・偽をこれだと示す言説なのです。」(P.162)__一つの発言には様々な可能性(言い方・恣意性・偶然性)がある。聞く方にも同様に様々な解釈がある。真(論理的)なる言葉は、つねに可能性がつきまとい、不定だ。
「歴史形が客観的に所与だとみなしたこれら諸要素の、「客観化」の歴史を書くこと(あえていえば、種々の客観性の客観化)、こうしたたぐいの循環こそ、わたしが尋ね歩いてみたい道なのです。ようするにこれは「もつれ」であった、そこから抜け出るのは容易ではありません。」(P.163)__マルクスの批判は、西洋においてのみ、もっというとドイツでのみ有効なものであって、ロシア、中国、日本では有効ではない。言葉(単語)そのものが違うからだ。言葉が社会(文化)によって成り立つ以上、それはやむを得ない。日本において、それを有効だというのは、日本文化が完全に西洋化しなければなならないと言っているのだ。
「ポール・ヴェーヌが正しくも見ぬいたように、それ自身が歴史学的分析を通じて形成された唯名論的批判が、歴史学的知にどんな効果をおよぼすか、それが問題なのです。」(P.163)__分析し、分割し、名付けることで、存在させること。知の細分化はだれも捉えられない。
《 Table ronde du 20 mai 1978. Débat avec Michel Foucault 》, M. Perrot et al., L'inpossible prison, Paris, 1980.
©1980, Ed. Le Seuil.
身体をつらぬく権力
(聞き手)リュセット・フィナス
(訳)山田登世子
「それまでのわたしは、権力についての伝統的な考え方を受け入れていたような気がします。つまり権力を本質的に法的なメカニズムの如きものとして考えていた。そのような権力は、法をもうけ、禁忌をつくりだすもの、排除、廃棄、妨害、否認、隠蔽、等々、一連の否定的効果を及ぼしながら、否(ノン)をいうものです。」(P.165)
「刑罰のケースを研究してからというもの、わたしは、法とのかかわりなどはさほど問題ではなく、むしろ問題なのはテクノロジーとのかかわりであり、戦術や戦略とのかかわりなのだと、そう確信するようになりました。」(P.165)
「権力が言説に対してもっぱら希少化という否定的メカニズムを及ぼすように述べているところがあれば、そういうとらえ方はいっさい放棄したい。」(P.165)__イリイチ批判か。「否定」をなぜ「希少化」と言い換えているのかがわからない。
「一九世紀に入ってから、何より根源的な現象が起こった。権力の二大テクノロジーの歯車が噛みあって作動しはじめたのです。すなわち、セクシュアリテを織りあげるテクノロジーと、狂気を分割するテクノロジーとが。狂気に否定的にかかわっていたテクノロジーは、積極的なものに変わりました。こうして心理的なるもの(プシュケ)についての一大テクノロジーが生誕するのであり、それが、われわれの世界の一九(FF)世紀と二〇世紀の基本的特徴のひとつをなしております。このテクノロジーによって、性は、理性的意識の隠された真理ということになり、同時にまた、狂気の解読可能な意味ともなってしまう。かくて性は、理性的意識と狂気の双方に共通する意味(サンス・コマン)というわけであり、したがってそのいずれにもおなじ様態で働きかけることができるというわけです。」(P.166-167)__フロイト。
身体権力の網目
「思うに権力の問題は、一六世紀と一七世紀の法ー哲学思想によって規定されたモデルに従って、たいていの場合は、主権の問題に還元させられているような気がします。」(P.169)
「家族は、今日にいたってもなおそうですが、国家権力のたんなる反映、その延長ではありません。家族は子どもにたいして国家を代表するわけではない。女にたいして男が国家を代表するわけではないとのまったくおなじです。国家が国家として機能しうるためには、男の女にたいする、あるいは大人の子どもにたいする、まったく特殊な支配関係が存在しなければならない。固有の位置をもち、相対的自律性をそなえた支配関係が存在しなければならないのです。
権力の分析にしきりと登場して邪魔をしている、あの代表という考え方、これはいっさい警戒してかかる必要があると思っております。諸個人の意志がいかにして一般意志によって、あるいは一般意志において、代表されうるのか、長いあいだ、それを知ることが問題になっていました。」(P.170)
権力の多様性
「一般的にいって、わたしは、権力が「意志」(個人的であれ集合的であれ)から発しては成立しないと思っていますし、権力が利害関係から生じるとも思っていません。」(P.170)
(ジャック・ドンズロ)「(ドンズロが明らかにしているのは、家族の内部で行使されるきわめて特殊な権力形態が、学校化の展開を通じて、いかにして国家タイプのより一般的なメカニズムに浸透させられていったのかということ、しかもまた、国家タイプの権力と家族タイプの権力とがそれぞれの特殊性を保持しつつ、おのおのの権力メカニズムが尊重されたかぎりにおいて真に両者の歯車がかみあったのはいかにしてか、ということです)。」(P.171)
セクシュアリテと政治
快楽のエコノミー
「あらゆる快楽の法則、それは、少なくともひそやかには、性である、と。だからこそ快楽は抑制されねばならないのであり、またそうして快楽を操作しうる可能性もそこから生まれてくるのだ、と。あらゆる快楽の根底には性があり、性のその本性を鑑みるに、性はもっぱら生殖に専念し、生殖に限定すべきだというこの二つのテーマ、これはもともとキリスト教からきたものではなく、ストア哲学からきたテーマです。キリスト教は、ローマ帝国の国家構造に同化しようとして、これらのテーマをとりあげざるをえなかった。ストア哲学はローマのなかば普遍的な哲学でしたから。こうして性は快楽の「コード」となったのです。」(P.174)
「そうして、この装置はわれわれに信じこませるのです。われわれは、ついに性を見出したのであり、この性の語彙を用いてあらゆる快楽を「解読する」ときにこそ、われわれはみずからを「解放(FF)する」のだ、と。むしろ必要なのは性の真理から解き放たれることであり、性によって規範化されないような快楽の一般的エコノミーをめざすことであるのに。」(P.174-175)
精神分析と精神医学
政治の創出
《 Les rapports de pouvoir passent à l'intérieur des corps 》.
Quinzaine littéraire, 15 janvier 1977.
©1977, Michel Foucault
●フーコーを読む●
フーコー・歴史・権力 追悼にかえて
福井憲彦
(アリエス)「生まれ、成長し、死に、病にかかる、これらは一見すると、なんとも単純で、なんとも変わらざるものであるかのようにみえる。だが人びとのそれらに関する態度は、複雑で変化を示すものとして展開してきたのであり、そうした変化する態度は、それらに与えられる意味を変えるばかりではなく、もたらされる結果をもときには変えることになるのだ。」(P.184)
「フーコーもまた、慣習的行為とその変化についての考察を、彼の考察作業全体の一出発点にしている。すなわち、ある時代、ある社会において、明々白々で自明なものとして、その根拠を何ら問われずに担われている行為、それらが、じつは自明のことでも不変のことでもないことを示し、つまりそれらの行為の自明性を断ち切り、そしてそれらが自明だとされていることの根拠を問うこと、これが、フーコーにとって、少なくとも歴史を素材とした考察作業の標的のひとつであった。」(P.185)
「いずれにしてもフーコーは、歴史の推移のなかで、ある断絶や急速な変化をその前後に生みだした切断面としての「事件(出来事)」に着目した。」(P.185)
「歴史学が、王侯貴族だの、議会や政策、政治事件や組織の年代的変遷をもっぱら対象にすえていた(FF)かつての伝統的政治史学を、事件史と規定して批判し、こんどは逆に長期的に持続する歴史的要素の研究に、もっぱら熱をあているかにみえたとき、フーコーはむしろ、事件という語に新たな意味を与えて、歴史研究における「事件化」の手法をうちだしたのであった。」(P.185-186)
「このことは究極的には、なにが真理であり、なにが誤っているのかということを、言語表現として生みだす体制、すなわち「真理と誤謬の生産体制」にかかわっている。
フーコーが究極において問うた問題は、知と権力の問題、真理と権力の問題であった。歴史家は、みずからの歴史研究による過去の再構築があたかも現実であり、これこそほんとうだ、これこそ真実だ、と言語表現してきたし、している。だがそうした真理と誤謬の分割を保証する作業は、学校・大学・書物・マスメディアなどの知的正統化の制度装置をとおして、じつはあるモラルや秩序規範を押しつけ、新たな自明性を押しつけ教えこむテクノロジーに属してはいないか、と彼の仕事はつきつけてくる。
そもそも人文科学はその生成の時点において、社会と人間を観察の対象とし、そしてそれらについての真理を生産するものとして成立していったのだが、それはまさ(FF)に同時期にはじまる権力の新たなメカニズムのはじまりと、背中あわせの関係になっている。真理の生産もまた、権力のテクノロジーから自由ではないということを、フーコーによる人文科学の考古学は暴きだす。」(P.187-188)
フーコー〈権力〉論の全貌 権力理論のための第一草稿
山本哲士
(『臨床の誕生』)「本書でフーコーは「この本の問題は、空間、ランガージュ、死に関するもの、それはつまり、まなざし regard に関する問題である」という文から出発している。邦訳では、「この本の内容は空間、ことばおよび死に関するものである。さらに、まなざしに関するものである」というように、空間、ランガージュ、死、まなざしが併存したニュアンスでとらえられてしまっている。〈空間、ランガージュ、死〉を《まなざし》としてそこからとらえるという微妙な違いを、つまり、フーコーのエッセンスをとりのがすという邦訳は、仕方がないといってはすまされない重要な問題を、いつのまにかどこかへ捨ててしまうのだ。この《眼差し》がやがて《視線》の権力、パノブティク(一望監視体制)の《監視》へとつながっていく、こんな単純な筋さえ見逃されてしまうのだ。」(P.192)
(『言葉と物』)「ここでフーコーは、
(1)もろもろの文面(エノンセ)
(2)叙述のための体制(ディスクール)
(3)理論形式・パラダイム・体系性
を区別して、(2)と(3)を混同していたと反省している。この混同が、実は「権力」の問題が中心にあることを見きわめなかった根拠であった、と。
"enincé"を言表、"discours"を言説などとやるからわけがわからなくなるのであって、"enoncé"とは、文書に記されている文面、述べられたことであって、法律の条文、判決文、証文の文面 これらはいかに書くか、その叙述法・書き方がたいへん重要になる といったもの、数学では「与件」である。そこにすでに、平常のものとして記されたもの、発表されたものだ。"discours"とは、演説、口頭弁論、間接話法などの話法、そして論文、序説などをいうが、"énonce"に結果するうえでの「叙述の仕方」と言える。(3)と(2)が違うというのは、論としてなりたった形式や体系性やパラダイムではなく、書かれたものとして編成・形成されているその仕方である。文面(言表)にたいして、叙述の仕方(=ディスクール)がそれを支配・統括するように働きかけている。その働きかけ、仕方がひとつの体制となってつくられているのだ。」(P.193)__わからない。
「「知」 savoir は、この「エノンセ」と「ディスクール」とがなす一大装置である。《エピステーメー》はひとつの特別な「ディスクール的装置である」と「装置」概念にいずれかかわっていく問題がそこにはある。
「知 savoir 」と「言説 discours 」のなかに新しい「体制 régime 」がつくられた。」(P.194)__わからない。
「それは、ソヴィエト社会主義の権力は全体主義だと非難し、西欧資本主義は支配者階級の権力に操られているという、ともに、権力を敵の側、他者の側におしつけて、非難して、満足しているというあり方からの脱却である。」(P.194)__両方を敵に回して満足しているようにみえる。
一 〈権力〉論の問題設定 「権力とノルマ:ノート」について
「権力分析をする際に、既存の四つの把え方から解放されねばならないというのが、この論考の内容である。
(1)「権力の(一方への)領有」という理論シェーマ。ある限られた者が権力を所有し他の者が所有しない。権力を所有する階級のある社会という観方。それはブルジョアジーだ というように、「権力は所有されるものだ」という考え。
(2)権力が(あらゆる局面にあるのではなく)ある特定の場に局在するという範疇。政治権力はある限定された要素に局在化する。とくに国家諸装置に局在化する。これは、政治諸構造と権力諸構造とを結びつける考え。
(3)生産様式へ権力は服属するという考え。権力は、生産の維持・継続・再生産つまり生産様式につねに従属しそれを保証するという考え。
(4)権力はイデオロギー的な諸効果しか発揮しないという考え。」(P.195)
「医学、精神医学、臨床といった学問、そして、監禁や処罰、また〈科学〉の権力性と政治性を議論しうるためには、これら権力範疇から解放されねばならないのである。」(P.196)__
「(1)「奴らは権力をもっている」という表現図式は、政治的に価値はあったにしても歴史分析としては意味がない。」(P.196)
「限られた諸個人が出会うとき、その瞬間また継続的に、限られた形式において、権力は貫かれている。」(P.196)
「(2)権力のシステムを国家諸装置だけでなく政治諸構造からも切り離すべきだというフーコーは、一九世紀の処罰の装置がディシプリンの体系と結びついていた状態を例証にあげる。国家装置からはなれて、諸個人は処罰諸装置の方針に従ってその対象となるべく圧迫されていた。
国家諸装置をコントロールしようとまた破壊しようと、権力形式は消滅しないし転換もしないという見解にフーコーは立つ。」(P.197)
「ここで、フーコーは、”局在化 localization ”なる彼自身のひとつの用語を使っているが、国家諸装置が全体的なものでなく局在的なものとみなされている、西欧の、市民社会世界が前提にすえられている点が推測しうる。」(P.197)
「ロシア・マルクス主義的な局在、全体とは逆転した視座である。ただし、このとき、いわゆる〈合意〉があるというグラムシのレベルでの理解を想定してはならない。権力の行使のされ方を論じているのだ。
(3)権力は確かに生産様式を構成する一要素であり、生産様式の核心部で機能するが、生産様式を保証するた(FF)めの権力とみなすだけでは不十分だとして、フーコーがとりあげるのは、生産様式を構成する第一義的なものとしての「差し押さえ(あるいは強制保管)の手段」「隔離の手段」である。恒常、銀行、監獄、収容所といった場所がそうであるが、とくに問題にとりあげているのは、「時間」を生産時間へ服属させることにおいて編制された状態である。
(ⅰ)生産機構の過程に諸個人を固定させる。
(ⅱ)そして生産のサイクルへ服属させる危機・失業・エコノミーがその手段となっている。
(ⅲ)さらに、労働力が有益となるまでは、生産装置に労働者を束縛するためのみがきあげと局所コントロールのシステムに彼らをいれる。
こうした事態は、生産様式を保証するという以上の機能構成をもっているメカニズムがあるのを意味している。ここでは、もはや純粋な〈時間〉というものはなく、生産時間・労働時間として、諸個人の時間を生産諸装置へ統合している。
これは労働力が買われた八時間なら八時間という時間にとどまっていない時間である。つまり、労働力を「生産的な力」に変容する経済構造がある一方で、諸個人の生活時間を差しおさえ、強制保管して労働力へ仕上げるという権力構造が定められているのだ。これは資本蓄積とよばれる経済の一部に対応している「強制保管」「隔離」の権力形式である。
人間の具体的存在を〈労働〉にみることは偽りであるとするフーコーは、快楽、不安、婚姻、休息、必要(欲求)、事件、欲望、暴力行為、盗み、等が、人間の生活であり時間でもあるとみなす。そして、資本はこの爆発的で瞬間的で非連続的なエネルギーを、継続的につねに市場へと提供される労働力へ変容する。資本は生活を労働力へと統合してしまうものであり、そのとき差しおさえ=隔離という強制処置を使う。学校へ子どもを生徒として差しおさえ強制保管=隔離する、というケースを考えれば容易のわかるだろう。
この収容は、一七・八世紀に貧しい者を怠け者とみなし、また主権が行使される地域から逃亡させないために収容した古い制度と、対象を直接に諸個人全体として社会諸装置へ結びつけ、資本主義的生産様式に合うものへとつくりあげたのだ。(フーコーは、ここに、権力形式をみたがイバン・イリイチはここに、シャドウ・ワーク(FF)の経済様式をみている点は面白い!)
(4)権力は、力あるいはイデオロギーとしてとらえられるべきではない。権力が行使されるところには同時に、〈知〉が形づくられている。知が統制されているすべての断片は、権力行使を許し確証させる。つまり、言われたこととなされたことの間に対立はないのである。
一七・八世紀に、つぎのような知の型があった。
(a)管理の知 国家装置を管理するものは反乱、観察、体験から管理するうえでの知を発達させた。またいかに税を課すべきか、いかに徴税を見積もったらよいかを知り、いかなる集団から塀を徴集したらよいかを知っていた。
(b)調査(証拠調べ)から生みだされた知 地域の人口移動、職人の技術、農業技術、健康な集団などを調べる上での知識があった。
(c)異端審問に属する知 諸個人の行状が報告される知識のあり方。
これは、一九世紀になるとつぎの二つの大きな原理へと集約された。
a、権力行使にともなって、その代表者・代理人が文書化し、所有し、使用する知の体系がつくられた。
b、各代理人と監督者の相互関係でなされる報告が統合され制度的な性質をもつようになったのは、権力と知の諸関係の歴史である。抽象化、一般化、統計といった一連の特殊な手段が、この報告の具体的な確実性として用いられる。
精神的労働と肉体的労働の分割によって、こうした知識は、権力をともない、社会のなかで機能しなければならぬものとなる。また知の水準が、学校装置によって測定され、評価され、真実化されることから、知が権力を行使する力をもっている事実がはっきりしてきた。」(P.197-199)__学問を代表する〈知〉そのものが、資本蓄積。〈知〉ではなく、それが「正しさ」となるところに問題の中心がある。西洋的正義・真理。それは、文字として蓄積され、蓄積された〈知〉が再検討されることは稀である。再検討していたら蓄積されないから。
「生産や欲望ないし、経済や無意識はたいへん重要な問題領域であるが、そこに権力の戦略を見いださねばならない。とりわけ、刑罰システムは、ディシプリン体系をもち、一九世紀以降、諸装置の影の部分で、ディシプリンの製造、義務のおしつけ、監修の形成が、「社会的規範(FF)としての慣習」の維持のために奉仕する権力装置として発展してきたのだ。
一九世紀では、人びとが〈慣習〉 habitude の主体とならねばならなくなったため、〈契約〉の性格もかわる。諸個人が自己の所有から離れるときに設定される関係が、〈契約〉であり、(自らが所有する労働力を雇用者へ売るとき契約を結ぶ)生産諸装置へ諸個人が束縛されていないければならないのが〈慣習〉である。つまり、自分が所有していない装置へ、何の所有もなく自己を束縛させることだ。」(P.199-200)__Nota Bene!!
「かつて、権力とは自らを誇示し、ディスプレイするものであったが、現在ではその姿を隠し、日々の規範の形をとっている。自らを隠しながら、しかし、自らが現実性・具体性であると表示するのが、強制のシステム、ディシプリンのシステムである。規格を設定し、監視に参与し、正常なものと異常なものを区別する 教師、医者、精神医として精神分析者のディスクールを通じてこれはなされている。規範化のディスクールが、人間を対象とした人文諸科学となっている。
このようなフーコーの考察は、決してマルクス主義を擁護するわけではないが、実にマルクス的であると評価したい。」(P.200)
「というのも、とくに、” dispositif ”という装置論が、「セクシュアリテ」を論じる際に、総括的な視座としてフーコー自身によっていずれとりあげられてくるからであり、この批判的にとりあげられた装置が経済から権力形式の場を切りはなそうとしている四点にたいして、再介入が見受けられてくるからである。もちろん、土台がまったく地盤がえされたのことである。」(P.201)
「フーコーは、経済機構そのものを問題対象としてのではないだけのことだ。資本主義的生産様式、資本蓄積の様式という歴史的現存性を当然ふまえたうえで、一九世紀の歴史的切断が、科学や知の「叙述世界」のうえで、どのように生起したのかを、経済関係としてではなく、《権力関係》の「形式」として論じたのだ。」(P.201)__フーコー・マルクス、権力関係と経済関係の相互作用。
二 〈個人化〉と〈主体化〉の権力形式
「フーコーのメインテーマである権力概念が直截に明確に叙述されたのは、〈個人化〉 indicidualisation と〈主体化〉 subjection の存在様式をつかんだときである。単純にいえば、個人がバラバラに個別化されて、各人がそれぞれ違うと差異づけられて、自覚的な主体をもって行為している状態におかれているときの権力編制である。これは、通常、諸個人にとっては好ましい状態であると判断されていたことであるが、フーコーはこの個人化・主体化を《隷属の状態》であるとみなし、そこに、権力の新しいテクノロジーが編制されていると考える。
いいかえると、個人化とは規格化されることであり、主体化とは服従するということである。
個人化=規格化は、監獄の一望監視体制の歴史記述のなかで明らかにされたが、主体=服従はセクシュアリテの史的考察のなかで明らかにされた。」(P.202)
「これらはすべて、〈身体〉を対象としている点で統合されているのであるが、当初、フーコーは、〈排除の歴史〉 ネガティブなものを設定する と〈境界づけの歴史〉 ポジティヴな面での編制 とがパラレルな歴史として描かれうると思っていたと述懐している。」(P.202)
「ともかく、同時進行していた、
(1)権力形式
(2)アルケオロジー( archéokogie )
(3)叙述法( discours )
の”知 savoir ””真理 vérité ”総体が、〈歴史〉の文脈において系譜学的に論じられていたのである。
フーコーは、「主体と権力」におさめられた自ら英文で記したという「なぜ権力を研究するか 主体の問題」において「私の課題は、人間 human beings を諸主体につくりあげる異なった諸様式の歴史を創造することにあった。わたしの仕事は、にんげんをしょしゅたいに変容する三つの客観化の様式たずさわってきた」として、
(1)調査の諸様式
ア 語る主体の客観化である一般文法・文献学・言語学、イ 生産主体の客観化である富と経済学の分析、ウ 生きてある事実分野の客観化である自然史・生物学、が科学の座になろうとしている様式。
(2)分割する慣習行為の客観化(FF)
自己自身内での分割、他者からの分割。狂気と正気、病者と健康者、犯罪者と善人。
(3)人間が彼と彼女を主体へ転換する
セクシュアリテの領野を対象に、人がいかにして自らをセクシュアリテ主体として認識していくか。
である。
これを総じてフーコーは、自らの研究の一般主題が権力ではなく主体にあるのだとのべているが、権力をテーマとしてきたことに何の変更もない。いいかえると、
・権力の関係
・権力の形式
・権力のエコノミー
・権力の行使のされ方
を、探求してきたのである。」(P.203-204)
(1)個人化 ディシプリンの権力
「政治的には、法律的枠組におさまらない反法律的なものであり たとえば、、法律のもとで人びとは平等であるが、ディシプリンのもとで人びとは不平等・不均斉である 、処罰権力を、監視のディシプリンへとねじ曲げているのもである。」(P.205)
「学校では、頑健な身体へむけて鍛錬(健康の要請)、有能な士官を手にいれる(資格認定の要請)、従順な軍人の養成(政治的要請)、放蕩・同性愛を防止(道徳上の要請)というように、教育中心の軍隊的要請が、訓練のなかで組織されている。」(P.205)
「多様で、自立的で、匿名の権力、いたるところにあり、つねに見張っている。監視者も常に監視される。どのような影の部分もなく徹底して取り締まるフジックな権力である。
ディシプリンの権力のもとでは、処罰の技法がとられているが、それは抑圧をめざすものではなく、次の五つの操作を用いている。
(!)個別的な行動・成績・行状を、比較・区分によってある総体へと関連づける。
(2)各個人の相互比較を一般規則との関連で差異づける。
(3)各個人の能力・水準・性質を量として測定し価値として、この差異を階層序列化する。
(4)この価値中心の尺度に適合するよう束縛を働かせて同質化する。
(5)この規格にあてはまらない逸脱は、排除する。」(P.206)__監視者は見えないから、いなくてもよい。見られていると思う「自己」「主体」こそが問題。
「つねに《ノルム》を基準にたて、等質的な社会全体へ帰属するように、分類化、階層秩序化、序列配分などをするのだ。
視られるものは末端のひとりひとりであり(強制的な客観化がなされている)、その個人性は記録文書の分野(FF)の対象となるよう分析可能な個人としてくみたてられ、事例として仕立てあげられる。」(P.206-207)__Nota Bene!!!ノルマ、ノーマル
「かつて排除された者たちは、排除空間におしこまれて集団的に扱われていたが、いまや、それは個別的に取り扱われるようになった。一望監視体制の技法の導入である。そこでは、つねに自分は視られているのだと自覚し、かつ、服従強制にたいして自発的にその強制を自らに働きかけるのだ。個々人の配分・逸脱・系列・組合せを分析する機構であり、しかも、個々人を可視化し、帳簿に記入し、差異化し、比較するための道具を使用する機構である。」(P.207)__ID。個別化し、差異化するが、「人間」という名のもとに均一(平等)が原則となる。「プライバシー」とは何か。
「ディシプリンの権力は、①流浪民の増大 これを定着させること。②生産装置の増大 複雑さから収益を高めること、この二つの歴史状況において双方を調整させるべく働きうる。そのとき、人間の多様性を秩序づけ安定させるという権力体系において、ディシプリンの権力に固有の目標が三つ設定された。
(1)権力行使をできるだけ経費がかからぬようにすること。
(2)この社会権力の効果が、最大限の強烈さに達し、失敗なく隙間なく可能なかぎり遠くまで広がるように措置すること。
(3)この権力体系を構成する要素が従順に効果を増大させ、経済の増大と権力装置の成果を結びつけること。」(P.207)__不特定の個人が匿名性をもたないようにすること。
「権力のエコノミーとは、
a 多様性のなかで生じる事態を少なくするために、ディシプリンは、多様なものを定着させ、動きを停止し規制し、混乱や不確かな流通によって密集した人びとを、計量的に配分し、順次解決する。
b 多様性から生じる反権力的な効果を、可能なかぎり完全に流通を防止した区分を同一平面に導入して、緊密なヒエラルキー的網の目に定めピラミッド型にする。
c 身体から最大限の時間・力を抽出すべく、時間割、集団訓練・教練・統括的で詳細な監視という一糸乱れぬ方法でもって、個別的効果を増大させる。
d 配分、身体、身ぶり、リズムの相互調整を行い、能力を差異化し、装置・課題を相互に整合しうる戦術を明確に定めて、多様性の総和以上の効用をつくりだす。
e これを、多様性の上部においてではなく、織目そのものの中で、もっとも慎重に、費用を安く、流動させる。
相手を客体化し、相手に関する知を形成し、多様性は成員相互の関係が好ましくなったとき、ディシプリンの水準へと達しているのだ。こうして人びとの多様性を役立たせる服従を編成する生産装置から、資本の蓄積の動きをはやめるそれが、経済的生産装置と統合されるのだ。
ディシプリンとは、身体が、最低の費用で、政治の力としては小さなあり方で、役立つ力としては最大の効用を発揮するという、統一的な技法である。
さらにディシプリンは、個々人の間に、私的絆をつくりあげ、ひとつの拘束関係となり、強制される仕方、その働く機構において逆転不可能な従属関係を形成し、共通の規則に従う別々の成員の不平等、いつも同じ側により多くの権力が固定される、という反法律的なものである。法は普遍的ノルムにもとづいて共通の法主体を定めるのに、ディシプリンは、人びとを個別化し特定化し、極端には、その資格をうばいとり無効にさえする。」(P.208)__日本になぜ法主体がないか。西欧においては生まれながらに法主体だ。多様性や個性化、個人化、主体化などというのが日本にふさわしいのか。マルクス主義の二の舞いを起こしてはいけない。西洋の闘い、西洋の理論は西洋でしか通じないのだ。日本にそれを広めようと「学問的(科学的)」言説をのべても、明治以降の「法律」「民主主義」と同様に、根がない。ヴァナキュラーなものがなくなるのと、日本がなくなるのとどちらが先か。
「こうしたキリスト教的伝統の内部においてこそ、神の手に偶然的に委ねられていた自然が〔神という根拠を失ったことで〕死んだ後、生命なるものが管理されるべき対象として、また人工知能のように製造されることさえ可能な対象として現れるような文化的空間が生みだされるのです。わたしがこのことを非常に強く実感したのは、つい先日あるセミナーに参加したときのことです。そのセミナーには、情報工学やコミュニケーション科学やシステム管理といった分野を専門とする多数のドイツ人学者にまじって、情報工学を専門とする二、三名の日本人学者が招かれていました。〔そこにおいて〕ドイツ的な教養を培った同僚たち、つまりゲーテを愛読するような同僚たち〔ドイツ人学者たち〕はみな、かれらがやろうとしてい(FF)ることにある特別な意義を見出そうとしていました。それに対して日本人学者たちは、かれらがおこなっていることによって脅かされたり、促進されたりしている事態の意義にまったく気づいていない様子でした。」(イリイチ『生きる意味』、P.402-403)
「二十五歳から三十歳までの人びとは、自分たちより上の世代の人間が相変わらず驚異の念をもって受けとめていることがらを、かれら自身はあたりまえのように受けとめているということをはっきりと自覚していました。たとえばハイパーテクストなるものについて、上の世代の人びとは幻惑されるような思いを抱いています。それは過去六世紀の間にもたらされたいかなる概念とも似ていない、まったく異質な概念だからです。しかしながら、そうした上の世代の人間のことをおかしく思う若い世代の人びとも、次のような事実に気づいてます。それは、かれらの生徒たちの世代、すなわち、かれらが「コンピューター世代の子どもたち」と呼ぶ、十七歳から二十三歳くらいまでの若者たちのほうが、かれらよりはるかに平然と、何の疑いももたずに、こうしたことがらを受け入れているという事実です。かれら三十歳くらいのドイツ人研究者たちでさえ、なおも、こうした(FF)新しい認識形態が自分たちの想像力や感覚や空想力に与えたインパクトについて意識せざるをえないのです。ヨハネス・ベックは、中産階級に属する とはいえ、ここドイツにおいて中産階級に属さない人間がいるでしょうか? 現在三十歳の人びとと、現在十八歳の子どもたちとの間のジェネレーション・ギャップに驚いています。というのも、現在十八歳の子どもたちはほとんど日本人と変わるところがないからです。」(同書、P.407-408)__いま、自分の家の近くを流れる雨雲の様子がパソコンの画面に表示されているけど、これがどれほど暴力的な画面なのかを考えることは難しい。
(2)主体=服従 牧人の権力
「これは、”牧人の権力 pouvoir pastoral ”であり、そのキリスト教会への制度化が司祭の権力のあり方として出現し、その現代版が、教師や医師や精神分析医の権力のあり方となって明示された。」(P.209)
「牧人型権力は、四つの特徴を持つ。
(1)多様な移動する群の中の諸個人におよぶ。(王・皇帝のように領地におよぶものではない。)
(2)この羊の群を養い、よい牧草をあたえ、泉まで導いて水を飲まし、個人と集団の生活を保証し、守っている個々人の幸せをはかる。(征服して、富や奴隷をえる勝利者の敵を痛める権力ではない。)
(3)己が羊のために自らを犠牲にする本質的に献身的なもの。(王のために一身をなげうつよき臣下でも、都市のために行政者の命をうけ自己を犠牲にするのでもない。)
(4)集団内の個々人を個々人として扱う〈個人化をめざす〉。群全体の救済を考えると同時に、構成員一人一人の救済を保証する。(王や行政官は領地内の住(FF)民総体を救う。)」(P.210)
「〈牧人=司祭〉という制度化された権力のもとで、羊の群たる信者たち個々人は、西欧世界特有の権力体制下にくみこまれる。
(ⅰ)自らを救う義務がある。
救いはもはや選択の余地がなく、諸個人はことごとく救いをえるために全力を尽くすことが強制される。
(ⅱ)他者の権威を受けいれねば自らの救済はありえない。
自分のためにする救いは、自らの行為を他者=司祭に知られてはじめてなされる。司祭は救済のために個人の行動のすべてを知り、それを監視し、絶えざる監視と管理(断罪・有罪化)の力を個人の行動すべてにおよぼしる立場にある。
(ⅲ)絶対の服従が要求される。個人に対して自らの決断をもって自らの意志を強要することができる司祭のもとでは、信者は「よく服従する」ということ自体が、絶対的な価値として目的となっている。何かのために服従するのではなく、服従そのものが普遍化されたシステムとなっている。」(P.210)
「ここで肝心なことは、こうした、〈牧人=司祭権力〉のもとで、はじめて〈主体〉の成立が可能になるという点である。そしてこの主体の確立とともに、真理を生産する技法が確立される。」(P.211)
「そしてキリスト教徒たるものは、己が頭の中で起こるすべてのことをいう義務がある。 「告白の義務」である。これらを、フーコーは、主体の内部における主体的な「真理の生産」とよんでいる。
この〈主体〉への転化を、「真理の産出」と結びつけて構成したのがセクシュアリテにたいするキリスト教のあり方であった。」(P.211)__日本ではどうであったか。主体の形成がないのだからありえない。主体の内部にあるもの(告白の対象となるもの)を「(客観的実在)現存・ある」ととらえる契機は何であったか。言語構造か。
「すなわち、主体性 subjectivité の形成によって、自己の弱さ、誘惑と肉体をたえず意識して、自己の身体、肉体にたいして、内面化の技術、自覚、意識下の技術でもって、つねに自己自身に目覚めさせることである。肉体 chair とは身体 corps の主観性であり、それに目覚めていること、つまり、個人が個人に、主体的に隷属する assujettissement こと、その内部でセクシュアリテがとらえられるようになったというのである。」(P.211)
(3)国家の個人化からの解放
「個人を識別する日常生活に直接関わり、個人の個性を烙印し、アイデンティティを付与し、自他ともに真理と認められるものを強いる つまり、諸個人を諸主体に変容する権力形式を、〈歴史ー現在〉において明確につかんでいるのだ。」(P.212)
「したがって、フーコーは、国家の諸制度から個人を解放せよというのではなく、
国家全体と、
国家に結合した個人化と
の双方から、自分たちを解放することであると主張する。
そして、現在の個人化・主体化を拒否し、「新しい主体性の諸形式」をプロモートすべきである、という。」(P.213)
三 〈現在〉の権力世界
「搾取・抑圧の只中にある民族構造が、まったくの演劇的文化叙述の世界に転じられてきたことをはじめとして、〈政治〉や〈国家〉や〈権力〉は論じられなかったのではなく、文化論的に需要ないし、切断・排除されてしまったのだ。
エスニックなレベルでの文化という翻訳不可能な情況・現実があることを地盤にして、記号論的・構造論的に一般化して論じうる土壌が豊かに肥やされる一方、もっと根源的で資本主義的・政治経済的に一般化されうる現実の土壌が構成されているのでar.実は、この二つは別のものではなく、相即して、複雑な世界編成 普遍化の支配体制 を構成している。これが、相対的に一般化=普遍化されないためには、《歴史のメトドロジー》が根元的に問われているのである。」(P.215)__学問すること、哲学することそのものが〈普遍化=一般化〉ではないのか。それぞれヴァナキュラーなものである文化を学問の対象とすること。文化内、文化外を含めて。そこに共通するものがあるとは思うけど、それを「人間一般」として抽象的にとらえることの問題点。日本には日本の文化、対象(対象となりうるもの・あたりまえじゃないもの・何を当たり前と思うか・アスペクト盲)。
methodology
名
〔学問・研究領域の〕方法論
・The researchers' methodology was the best way of solving problems. : その研究者たちの方法論が最良の問題解決法だった。
《哲学》方法論研究、方法学
〔一般的な〕手段、方法、技法◆【用法】この用法を認めない人もいる。(英辞郎)
「その叙述世界は、日本の一九七〇年代から現在までの十余年の中で、政治運動停滞にみあった消費志向安定の日本高度資本主義の多様化=画一化に対応した叙述世界(ディスクール)そのものである。これは、同時代的な知の革命的転換が、〈政治〉論においてあった地方の叙述世界(危険なもの)を排除するほどの力をもってしまった。そこで旧態依然の政治主義的叙述世界が温存されてしまったのだ。
わたしは〈日本〉を、大ざっぱに、消費志向の高度資(FF)本主義を制度化した産業的生産様式において、世界に画一的に参与し、同時に先進諸国の一員である民族国家として新帝国主義関係を、アジア・アフリカ・ラテンアメリカに対して構造化し、そのうえで、みずからのエスニシティを天皇制へと象徴統合しているととらえている。文化としての使用価値が日本の伝統性へとパイプをつなぎ、商品としての使用価値が世界資本市場へとパイプをつなぎ、その象徴統御と現実統御が〈政治ー帝国主義〉へと構造化されているのだ。」(P.216)__日本論。日本の伝統性をどうとらえるのか。「アメリカはこうなっている」と「アメリカのだれそれはこう考えている(言っている・書いている)」との同質性。
しょう‐ひんシャウ‥【商品】
〘 名詞 〙 商売で売る品物。売買を目的とした財貨。あきないもの。
[初出の実例]「且巨艦と雖とも岸上より直に商品を積ことを得べし」(出典:西洋聞見録(1869‐71)〈村田文夫〉前)
「生産者、卸売商人及び小売商人が売却したる産物及び商品の代価」(出典:民法(明治二九年)(1896)一七三条)(精選版 日本国語大辞典)
「フーコーは、権力を、身近な諸形式そのものの中にみた。文字通り、何事かが可能となっているところに” pouvoir ”をみたのである。そして、彼の複数形で語られる諸概念は、消費多元化の編制を正確につかまんとする。解釈の多元性を遊ばせているものではない。
イバン・イリイチは、消費者の生活上の諸必要を決定・作成・修正・解体している専門家のサービス権力をみた。人びとのためになることそれ自体の権力性である。
ピエール・ブルデューは、恣意的な諸々の意味を正当化する象徴的な分類・統御に象徴権力をみた。(FF)
彼らはいずれも〈国家権力〉を論じていないが、〈支配する権力〉〈決定的な権力〉つまり、現代人の生活様式において行使されている〈権力〉をそれぞれ固有に論じたのである。
ここで、わたしは、彼らが〈権力〉を論じるうえで、自らが考察の土台・地盤にすえている対象のきり方との関係をつかみ直しておきたい。
フーコーは、権力を論じるとき〈 régime 〉を立てている。
イリイチは、〈 institution 〉をたて、ブルデューは、〈 système 〉をたてる。もちろんこれらの用語を、三者とも使用しているが論の基軸にそれを置いている。それを、彼らのそれぞれのキイワードから簡略化すると、
権力形式 体制 discours
専門権力 制度 services
象徴権力 システム pratiques
がうかびあがってくる。
これらは、いずれも、イデオロギー的な働きかけおよびその効果を論じたものではなく、日常生活世界の諸個人の行動・関係に直接にうめこまれている関係様式を論じたものだ。
①個人化
②他律化
③正統化(分類化)
が、権力の働きかけた結果として想定されている。」(P.216-217)__複数形。日本人にはわからんだろう。外国語で考える難しさ。複数形や不定形、定冠詞がもつ意味を日本人はいちいち考えなければならない。西欧人はそれを無意識に肌で感じているのだろう。日本語の視点だから見えるものも当然あるのだが(金谷)。私にはそれができない。多分殆どの日本人にはできないだろう。たしかに日本は「資本主義社会」として西欧と同じ仕組みの中にいる。当然共通するものもあるかもしれない。でも、西欧と別の眼(日本語の眼)で見、日本語で考えるときにまったく違う見え方がするはず。それがヴァナキュラーな思考。日本語が英語している中で、若い世代はどんどん西欧的思考になってきてはいるが、そこに残っている日本的なもの(ヴァナキュラーなもの)があるとすれば、それが唯一の「希望」である。まずは残っている「ジェンダー」をはっきり見つめること。そのときに「自由・平等・個人」意識が邪魔をする。それをこえて見える「ジェンダー」、言ってしまえば「日本的女らしさ」。それは「日本人らしさ」「日本語らしさ」と同様に、西欧人でさえ否定できないものではないだろうか。私は「西欧らしさ」を認める。だから「日本らしさ」も認めたい。もしそれでも西欧が日本的なものを潰そうとするなら(対話にもかかわらず、インディアンを見よ)、西欧が「人類を滅ぼした」ということで、仕方ないのかもしれない。「人類」も西欧が作り出したものだから。
「つまり、学校教育として構造化された体制が支配的であれば、そのもとでの〈生徒ー教師〉関係であるならば問題はとわれない体系的な次元における考察である。
生徒は、ある文化的恣意性を〈真理〉として正当化されるよう他律的な教育学的行為(=サービス行為)のもとで、それを教えられ、その真理を身につけ、その処置の仕方を身につけ、個人として主体化され差異化される。」(P.218)__Nota Bene!!!「寺子屋」との(あるいはそれ以前にはなかった教育制度)差を考えよ。山本さんの熱気について行くのは疲れる。どうして日本人の思想家が出てこないのか。フーコーの本だからしようがないけど。出てきても吉本隆明くらいか。
四 知の編成における権力形式
「まず、フーコーはいわゆる進歩的政治にたいする三つの批判的な操作をする。
(1)思想を限界づけること。それには、a 境界をもたないよう広がっていく大きな解釈公準を疑い、b 主体のかかわりを疑い、c 起源をはてしなく求めるあり方にたいして誕生と消滅の閾をはっきりさせること、である。
(2)ほとんど反省をくわえられていない二分対立という問題のたて方を消しさること。たとえば、逆行的なものと適応的なものを分割する進化論、惰性的なものと生きたものを分離する生物学、運動と不動を対立させる力学、の三重のメタファーから思想史を解放する。対立ではなく、a 同時的な差異(分散状態)b 継続的な差異(変移の総体、ヒエラルキー化、依存関係、その水準を規定する差異)といった「差異の歴史」を語ること。
(3)叙述世界を固有のものとして扱うためになされている「否認」をとりのぞくこと。a 叙述をたんなる表現の場としてしかあつかわず、差異や原生的法則を認めない、b ひとりの著者の心理、意味論的主題・思想、修辞学的な文体があるとしか認めない、c 言われていることをいう以外のことはしないとする。(FF)
そうではなく、叙述世界は、ひとが言おうとのぞんだところのものではなく、ある時代に正確に人びとが言いうるであろうことと、実際に言われたこととの差異に構成されるものだ。「言われた物 choses dites 」の歴史を考えねばならない。
(4)諸学間の総体を、その不確実な規格から解放すること。a 境界確定の困難さ、b 対象の性質を規定する困難さ、c 思考された事実と歴史的分析の諸領域との間の関係づけの困難さ、においてあまりに不確実である。」(P.223-224)
「フーコーは、〈言うこと〉と〈物〉とが別のものではないという科学的言説の世界をおさえたことから、” discours (叙述の仕方)”と” pratiques ”は別のものではない、「政治的実践 la pratique politique 」と「科学的言説の、地位、行使条件、機能の仕方、制度化」とは別のものではないといっているのである。ここでいう” pratiques ”とは明らかに意図的実践 praxis ではなく、ある時代のなかで慣習化された行為様式である。」(P.224)__政治は科学的でなくてもいいのか。
「病気についての人びとの知覚の変化と経済的・社会的・政治的な変化との関係である。
(ⅰ)人びとは病気についての政治的結果を認識した 健康に欠陥のある一定地域住民の不安、不満・反抗。
(ⅱ)人びとは経済的な関連項目を認識した 健全(FF)な労働力を自在に使いたいという雇用主の欲望、公的扶助の負担を国家に委ねたいという権力ブルジョアジーの願望。
(ⅲ)経済的関連事項に自らの社会についての考え方をみた 施療院は貧しい階級のものであり、自由競争的な医療行為は豊かな階級のものであるというはっきりと二分された適用の場をもつ、ただ一つの医学。
(ⅳ)人びとはそこに世界についての自分たちの新しい考え方を転写した 屍体の非神聖化による屍体解剖の可能・労働の手段としてある生きた身体の重要性、救済を気づかうことから健康への配慮の転移。」(P.224-225)__欧米で、採用時の健康診断はあるのか。
「つまり、政治的行為が医学的叙述世界の存在様式を変形したということである。これは、
a 医学的な対象を変形したのではなく、医学的叙述に可能となる対象を提供する体系が変形された。
b 分析方法が変形されたのではなく、分析方法が編成される体勢が変形された。
c 諸概念が変形されたのではなく、諸概念が編成される体系が変わった
のである。つまり、「医学が編成される諸規範」が変形されたのである。」(P.225)
五 セックスとセクシュアリテ
「まず、大きくみて、フーコーは「結合の仕組み」から「セクシュアリテの仕組み」への変容をみている。これは、セックスからセクシュアリテへの移行である。フーコーは、〈セックス〉と〈セクシュアリテ〉を対照させる。
〈セックス〉とは家族上のものである。」(P.226)
「セックスが「結合」から離れてきたとき、「セクシュ(FF)アリテ」という個人的な事態が仕組=装置となってきた。それは、隠された私的な快楽、身体の危険な過剰物、秘密の幻想であり、個体的人間の本質であり、個人的アイデンティティの核となってきたのである。医者や精神科医など、個人の私的な考えや行動を告白されたものが知りうる身体・精神となった。この・個性化・医療化、セックスの意味化が、フーコーのいう「セクシュアリテの装置」である。
セクシュアリテに関する叙述が生産され増殖されるにあたって四つの大きな戦略が一九世紀以来個々別々に発展していったとして、①女性の身体のヒステリー化、②子どものマスターベーションの教育方法化、③生殖行為の社会化、④倒錯的快楽の精神医学化、をフーコーはあげている。
女性のヒステリー化の過程において、男女ともに共通していたセックスは、女性の身体特有の混乱したものがあると病理学によって固定化され、社会体と生殖にかかわる器官的なコミュニケーションが考えられるようになった。身体のどこかに神秘的でしみわたっているセクシュアリテがあり、その神秘的な出現が医学の分析的叙述世界へと記述される。女性の個人的アイデンティティと人口の将来的健康とがリンクされて知と権力と身体の物質化とが結びあった世界で考えられるようになった。セックスの戯れは自分と他者のものとに分割され、このヒステリー化の戦略のなかで、「すべて」は、部分、原理、欠如となったのである。
子どもの教育方法化、それは同時に、子どものセクシュアリテ化 sexualisation であるが、」(・・・)(P.227)__個人の確立とセクシュアリテ。セックスは「社会的」「結合」。セクシュアリテは「個人的」「独立」したもの。イリイチの「ヴァナキュラーなジェンダ」と「経済的セックス」と逆のように見えるが、セックスが「個人」の中に閉じ込められて「セクシュアリテ」と認識されるとともに、セックスが担っていた「社会的なもの」つまり「ジェンダー」が失われ、科学=経済=物質としての「セックス」のみが「身体の一部(部分)」として残った。
「生殖行為の社会化は、結婚したカップルが医学上・社会上の責任をもつよう、国家の眼のもとで、身体政治に(FF)たいする義務を課せられたことである。病理的影響から守り、人口の増減に注意を払うよう、性交の中断が、現実の法則と快楽のエコノミーとのあいだで提言された。」(P.227-228)
「性的本能の規範化と病理化にそってすべての行状が分離されるようになる。身体、新しい科学、規範化と監視の要請とが、やがて結びつき、深層に偏在する、意味あるセクシュアリテをとり扱うようになる。
こうした、ヒステリー、オナーニズム、性交の中断、フェティシズムの四つの大きな戦略が、セックスを「セクシュアリテの装置」へとかえていったのだ。」(P.228)
「こうした戦略が、権力と快楽を結びつけてきたのである。」(P.228)
「医療上の検査、精神医学的探査、教育学的報告、ファミリー・コントロールは、すべてを語るように仕向け、セクシュアリテはもはや理不尽で非生産的なものではなく、「性の科学」を産出するものとなり、また、権力と快楽の合体を可能ならしめる装置となったのである。
セクシュアリテについての文化的・社会的・科学的・(FF)理論的な知が過剰に産出され、同時に、他方では自己の性的欲望にたいする否認が個人のレベルでは広がっている。” ars ”(技芸)を発達させた東洋や多くの文明とちがって、〈知〉を発達させた西洋とは、「結合の装置」から「セクシュアリテの装置」へと展開しながら、主体化の権力形式を〈快楽ー権力〉の関係の中でうちたててきたというのが、フーコーの探求の基軸におかれている。」(P.228-229)__権力は、苦(監視、処罰)と快楽を実現する装置となる。権力に従うこと、科学に従うこと、権力が科学(知)であること。権力(社会の規範)に従わなければ快楽を得られないということ。権力に従うことが快楽となるということとの差。規範に則った行為の安心感と規範に逆らうことのワクワク感が同居する。認められたセックスでありながら、セックスそのものが反社会的色彩を帯びていることで両立する。反社会的でなくなったセックス(夫婦間のセックス)は、面白くない。権力(権利)と自由との関係。権力と知(科学)は一体に「なった」のか、「もともと」一体なのか。どうして夫婦以外の性行為はこれほど非難されるのか。
『知の考古学』を読む 「歴史化フーコー」のイメージ
桑田禮彰
書評1 『狂気の歴史』
正常と《狂気》 狂気の発明
R・D・レイン
「狂気とは、悪しき遺伝子、悪しき血、悪しき脳ミソ、悪しき親、悪しき生活、悪しき社会に由来するという考えは、今日でさえほと(FF)んど疑われていない。」(P.238-239)
「事実はもっとはるかに曖昧なものであるのだ。監禁された者の集団から「異常なもの」を分離することは、ある程度の広がりをもって、「正常」な人びとのためになされた。身体的拘束があきらめられた(あるいはほんの部分的なものになった)のも、「道徳的」な強制の方が、もっと効果的な恐怖政治を遂行できることが発見されたためである。いずれにしても抑圧するという形態以外の何ものも、人びとは想いついていない。狂人がしたりいったりしていることを、哀れみや恐怖ではない、他の何らかの感情でもってとらえた者は誰もいなかったのだ。」(P.239)
「この書からわかることは、理性ある者が理性なき者をいかに取り扱ってきたかである。勝利は、社会の権力構造を握った者に属する。もう一方の側の歴史は、とりかえしがつかないほど失われている。」(P.230)
「この本自身はまったく正常者のことばのなかにあるが、正常性それ自体の根本にあらかじめすえられている諸々の前提を、掘りおこしている。真の狂気を規定するということは 狂気以外の何ものでもないのだ。」(P.240)
(Laing, R. D., "Sanity and 'Madness'.... The Invension of Madness." New Statesman, 73, No 1892 [16 June 1967]より抄訳)(山本哲士・福井憲彦訳)
書評2 『監視することと処罰すること』
監視と処罰
ヘイドン・ホワイト
「「臣民」の概念が「市民」にオキカエられたとき、一九世紀初頭において、学校、軍隊組織、病院、精(FF)神病院、監獄といった再組織化に、不平を言いながらも産業社会の要請に応える市民としての自己規範化が反映されたのである。これら新しいディシプリンの諸制度の目的は、「すべてを平等に抑圧する」という同じものであった、とフーコーは論じる。」(P.244-245)
(White, H., Review of Surveiller et punir, American Historical Review, 82, june 1977 より抄訳)(山本哲士・桑田禮彰訳)
書評3 『セクシュアリテの歴史 1』
自白による証拠 『知への意志』をめぐって
アンドレ・ビュルギエール
「検閲の言説と反検閲の言説とは、おなじ泉で喉をうるおし、対立しあうと称してお互いに強めあっているのである、と。」(P.246)
「というのも、反検閲の言説は、フーコーがいうところの「発言者の特典」を、さらにおまけに、みずからのものとしているためだ。ただたんに、禁止にたいして侵犯するという楽しみをわがものとしているばかりではなく、前衛という位置に快適におさまり、その陰でもって、語る楽しみを手に入れているのである、と。」(P.246)
鍵穴をとおして
「あの、子どもの発する「ボクの生まれるまえには、なにがあったの。どうして世の中は、いまあるようになったの」、という問に発していることを。ひきだしのなかを漁り、鍵穴をとおしてのぞきたいという欲求、ようするに、知への意志である。」(P.267)__普通の景色でも、穴を通してみると見え方が異なるのは一般的ではない(知への意志のある者のみ)のか。
「しかし、いつもは性の解放を説いている先駆者たちも、このエロチシズムの波には、いやな顔をしている。商品となったこのセクシュアリテは、資本主義体制によって完全に操作され、疎外化の道具に変えられてしまったものなのだ、と彼らは考える。」(P.248)
(フーコーは断言する)「性とは、ほかのどの部分よりもいっそう、懸念と関心とをよびおこした、まさにブルジョアジーの本質的要素なのである。(中略)ブルジョアジーは、みずからの身体にたいする神秘的かつ無限定の権力を性に付与することによって、みずからの身体を性に従わせたのであった。」(P.248)
「服従を拒む者も、法を尊重するものと同様に、法を愛しているのだ。というのは、服従も反抗も、権力に正当性をあたえているという点では、おなじだからである。」(P.249)
肉欲の世界
「この「肉欲の世界」は、責任性に強く刻印されている。なぜならこの世界こそ、罪の主たる棲み家だからであった。そしてまた、この世界は真理でもあった。なぜなら、この世界はたえず自白されねばならなかったからである。」(P.250)__「真理」という言葉が含むキリスト教性。多分、「善」とか「正しさ」とは異なる。「責任」も。
格好の標的
「抑圧は、もはや牢獄も家計も必要としない。というのも、碁盤目状の衛生網によって、外的な行動を統制するには、科学で十分であり、内的な行動の統御は、科学が意識に染みこませた原則をもってできるのであるから、やはり科学で十分なのである。」(P.251)
「性交渉においては、いわゆる「宣教師」の体位(このよび方は、男性上位の体位を強要されて肝をつぶしたアフリカの人びとが、その体位につけることになる名称である)のみが、承認されている。分娩の技術においては、一七世紀の産婆たちが、しゃがんだりひざまづいたりする姿勢を禁ずるよう、要請される。それらの姿勢は、けだものの分娩をあまりに想起させる、というのである。自然なもの、と、獣的なもの。この対比は、正常なものと病的なものとを対置する最初のやり方ではないだろうか。」(P.252)__自然から独立した人間という意識。
金銭と引きかえに貸しだされる耳
「精神分析は、西洋的感受性の歴史をつらぬいている自白の長い連鎖の、最も最近の環のうちの、ひとつにすぎない。自白し、みずからの身体について語りたいという欲求、それが、もっとも不作法な、またもっとも言いよどんだような言葉のやりとりをつくりだし、もっとも演劇的な情熱のメカニズムを支配する。」(P.254)
「自白に価値を与えるのが性なのであろうか、それとも、自白が、性に価値を与えるのであろうか。西洋世界は、各人はみずからの真理をこの悪魔のごとき結びつき、「ファウスト的契約」のなかにさがさねばならないと、決定的に決めてしまったのだ そしてわれわれは、自分を自分自身の精神構造から放逐しないかぎり、この西洋世界の選択を認可するしかない。」(P.254)
(福井憲彦訳)
Anfré Burgière, 《 La preuve par i'aveu 》, Le Nouvel Observateur, 32 janvier 1977. ©1977, Le Nouvel Observateur
書評4 『セクシュアリテの歴史 2・3』
ミシェル・フーコー、快楽、そして道徳
フレデリック・ゴーサン
「セクシュアリテとは、近代の発明品であって、それは、宗教・教育・道徳・心理学・医療・裁判・家政・生物学等を通じて、わたしたち全員を統治している。それは、一番隠されることのない秘密であって、だからこそ、たえ(FF)ずわたしたちは、自分についてほんとうのこと〔=真理〕を語ってもらおうと、セクシュアリテに問いかけるのである。」(P.255-256)__「セクシュアリテ」は「ジェンダー(あるいはセックス)」と名前を変えて、表通りを歩き続けている!!
「こうした指導はすべて、ただひとつの目的へと収斂していく。つまり、自由人 道徳的・哲学的思索の対象になる唯一の身分 に、自分の存在を抑制し、自分を導き集団的仕事を指導する能力を、すなわち他の人びとの模範という適性を与えようと指導するのだ。生活スタイル、行動の節度、バランスのとれた人柄などが重要なものとみなされているのである。
だから性に関して問題になるのは、「男に向かう欲望と女に向かう欲望」という欲望の二元性ではなく、「恋愛の対象すべて 少女、女、少年 に、おなじように見事に、対応しなければ(FF)ならぬ」という点なのである。セクシュアリテは、同性と異性とに分けられるのではなく、他動的振舞い(成人男子に割り当てられる役割)と受動的振舞いに分けられる。」(P.258-259)
「難しいのは、「どうしたら同性間で恋愛関係を持てるか」ということでは全然なく 若くて美しい存在に恋愛感情をおぼえることは、当時はまったく正当とみなされていた 、「ひとりの男が、彼の生涯のある時期に、女や奴隷と同じような関係の中に存在しうるという事実」なのである。」(P.259)
禁欲への傾向
「二世紀のストア主義者とともにこの動きは勝利を収めた」(P.260)
「しかし、厳格な生活へと向かうこの傾向は、のちのキリスト教の場合のように、肉を忌み嫌うということからきているのではない。そうではなくて、「個人に無駄な消もうをいっさいさせたくない、自己についての認識にうち込ませてやりたい、自分自身の享楽だけを気にかければいいようにさせてやりたい」という欲望を、究極まで押し進めたことからくるのだ。
このようにして、ミシェル・フーコーは、古代ギリシャ人のセクシュアリテと、二世紀の古代ローマ人のそれとのあいだに、こうした個人的自律の道徳が成熟することに基づいた、長い連続性をはっきり描き出す。彼にとって、この道徳は、やがてキリスト教とともに構築される道徳、つまり支配諸機構によって言明された超越的な規則へ服従することに基礎をおいた道徳とは、対立するものである。」(P.260)
「つまり、彼がひとつのプログラムをしっかり提示しているのだというには、彼のペシミズムはあまりにも深く、懐疑的な態度はあまりにも徹底している。しかし、彼は、たんにそれをにおわせているだけであるにせよ、彼は、私たち現代の状況と類似点をもっていると彼の眼に映ったある状況を記述しているのだ。すなわち、超越的な法も勝ち誇ったイデオロギーも(FF)ないある世界の状況である。つまるところ、この世界では、個人は自分自身へと帰り、自分と他人、自分と快楽、自分と美、自分と芸術という関係の中へ、自らを全面的に投げ込むことができるのである。」(P.260-261)
(桑田禮彰訳)
Frédéric Gaussen, 《 MIchel Foucault, les plaisirs et la morale 》, Le Monde, 22 juin 1984.
●フーコーを憶う●
『ル・モンド』紙にみるフーコー追悼 ドロワ、ヴェーヌ、ブルデュ ー
桑田禮彰
「はじめに、「絶対的相対主義」と題されたロジェ=ポル・ドロワの文章をとりあげよう。」(P.264)
「古典主義時代初めに行われる「狂人」のトジコメ一八世紀に現れる人間の新しい顔、一九世紀における、病人の身体についての新しい見方の出現、古代ギリシャにおける西洋的性道徳の構成。」(P.267)__古代ギリシャは一度忘れられた。
「しかし、言説それ自体は、なんの価値ももたない〔=真でも偽でもない〕。わたしたちは、絶対的相対主義に直面しているのである。ここには哲学がある。
これこそ、まさにニーチェの哲学である。フーコーは「ニーチェ以後になにをなすべきか」という問いに、ありとあらゆる仕方で答えようとしている、とわたしは思う。「ニーチェ以後」とは、「真理という観念そのものの決定的な破壊のあとで」ということだ。このとき可能なのは、歴史学的遠近法だけである。」(P.267)
「マルクスは、真なるものと科学をまだ信じていた。」(P.268)
「それは、ふたつの階級〔ひとつは、権力を保持している階級、もうひとつはそれを奪いとろうとしている階級)の対立をひき起こすのではなく、あちらこちらで行われるさまざまな局地的闘争において、抵抗する側と同時に、抑圧する側にも、もろもろの効果をおよぼす。だから、そうした闘争において、言説は賭金であり武器なのである。この権力ネットワークは、なるほど〔抵抗する側を〕鎮圧するが、それとおなじだけ扇動も行う。」(P.268)
「そこでフーコーは、性的主体の出現を問題にし、古代文明と倫理という道をたどって、現存在についての美的な見方を再検討しながら、自分は「自分自身をなくすこと」をめざしているのだと主張する。彼は「自分自身をなくすこと」が、知識人の任務だと考えているのである。」(P.269)
「ミシェル・フーコーという名は、歴史家という言葉にも、また哲学者という言葉にも、おきかえることはできない いや、「ミシェル・フーコー」という言葉にさえ、おきかえることはできなないのだ。なぜなら、この名は、決して自己に同一化することはないのだから。この名はそれ自体、同義語によるおきかえを拒否する。これは、『セクシュアリテの歴史』二巻、三巻の裏表紙にあるルネ・シャールからのあの引用文に、はっきり表現されている。「人間の歴史とは、おなじひとつの聖なる名称をさまざまな同義語につぎつぎとおきかえてできたものである。それを否定することは義務なのだ」。」(P.269)
「それでは、現代の歴史家たちにとってフーコーとはいったいなんだったのか、なんでありつづけるのか。この点については、歴史家ポール・ヴェーヌの言葉に耳を傾けたい(表題「二五〇〇年続いた形而上学の終焉」)。」(P.270)
「「歴史の連続性は偽りである」というテーゼを究極まで追求するなら、いっさいの合理主義の終焉(いわゆる「真理の死」)に、また、主体なるものがもっていたいっさいの特権の廃棄 つまり、二五〇〇年間続いた形而上学の終焉 に、たどりつくのである。それはまた、知的にのみ理解できるようないっさいの因果性の終焉でもあった。すなわち、知性が確信をもてるように保証をあたえていたひとつの包括的な方向性〔=意味〕が消え、そのかわりに、多角形状に配置されるようないくつかの偶然的な原因が現れたのである。」(P.270)__「一人前」の知識の習得が長引き、「子供時代」が現れる。知が「確信」をもって発言するのはなぜか。顔の洗い方、手の洗い方、髪の毛の洗い方、歯の磨き方・・・、わたしが知っているだけでも三回も四回も変わっている。その時々で「正しい洗い方」だと発言した専門家や学者がいる。彼らが謝ることも、責任を取ることもない。なぜか。「その時の知識では正しかった」。当時の専門家も、現在の専門家も言うだろう。つまり、いまの学説もいつか「正しくない」といわれるということだ。学者(研究者)は、過去の実験を体験したことがない。それ自体が「正しいもの」だと思われている。それらが再検証されることは稀だ。つまり、学者のほとんど、人口の99.99・・・%は、その学説が正しいものだということは、「そう信じている」だけであるということだ。医学生のうちヒポクラテスを読む人はどのくらいいるのか。古典ギリシア語が分かる人はいないだろうし、翻訳でもよんでいないのではないか。『ヒポクラテスたち』大森一樹監督、1980年。一般的に学者(研究者)や専門家が求めているのは「旧来の知」ではなく「新しい知」である。ヒポクラテスが生涯をかけて得た知を自ら得るためには、それ相応の才能と「生涯」という時間がなければならないだろう。東洋医学と健康保険。どうして西洋医学(西洋的知)が優先されるのか。
「さいごに紹介するのは、ピエール・ブルデューである(表題「知の快楽」)。」(P.272)
「しかしその際、彼は、「一切でなければ無だ」と「無でなければ一切だ」という一切か無かの二者択一〔それ自体〕をしっかり避けていたのである。」(P.272)
「だからといって、彼は、逆に一人称の思考に籠もりそれを盲信するようなことも、もちろんなかった。
真理の様々な作用は権力の作用であること、そして、権力・特権は、さまざまな権力・特権の真理を発見しようという努力の原理そのものになっていること こうしたことをフーコーはほかのだれよりもよく知っていた。」(P.272)
「心理学、臨床医学、生命の科学等の学問研究は、自由主義的改良主義の啓蒙的悟性が、人間行動をコントロールするために、新たにつくりあげたものであった。」(P.275)
ミシェル・フーコー文献
〔ミシェル・フーコー 略歴・主要著作解説〕
(『言葉と物』)「ともかく、ひとつのことがたしかなのである。それは、人間が人間の知に提起されたもっとも古い問題でも、もっとも恒常的な問題でもないということだ。比較的短期間の時間的継起(クロノロジー)と地理的に限られた裁断面 すなわち、十六世紀以後のヨーロッパ文化 をとりあげることによってさえ、人間がそこでは最近の発見であるという確信を人々はいだくことができるに違いない。知がながいこと知られることなくさまよっていたのは、人間とその秘密とのまわりをではない。そうではなくて、物とその秩序に関する知、同一性、相違性、特徴(カラクテール)、等価性、語に関する知を動かした、あらゆる変動のなかで すなわち、《同一者》のこの深い歴史のあらゆる挿話のなかで 一世紀半ばかり以前にはじまり、おそらくはいま閉ざされつつある唯一の挿話のみが、人間の形象を出現させたのである。しかもそれは、古い不安からの解放でも、千年来の関心事の光かがやく意識への移行でも、信仰や哲学のなかに長いこととらわれてきたものの客観性への接近でもなかった。それは知の基本的諸配置のなかでの諸変化の結果にほかならない。人間は、われわれの思考の考古学によってその日付の新しさが容易に示されるような発明にすぎぬ。そしておそらくその終焉は間近いのだ。」(新潮社版、P.409)
〈終わり〉
〈メモ〉
アリエスが言うように子供時代はなかったのだから。自我の目覚めとはまったく別な事です。
同様に、自我の目覚めと性の目覚めもまったく違うことなのです。戦後の日本に生まれ育った私には、想像することしかのですが。レヴィーストロースのいう熱い社会しか体験したことがないのです。
るのは一般的ではない(知への意志のある者のみ)のか。
__「セクシュアリテ」は「ジェンダー(あるいはセックス)」と名前を変えて、表通りを歩き続けている!!
思春期、自我の目覚め、「若きウェルテルの悩み」、成人の通過儀礼
事物やまわりの人間たちや身体にたいして実にさまざまな多型的諸関係をとっていることこそ、幼児期でなくて何だというのでしょう。この幼児の多形にみちあふれている状態を、大人はみずからを安心させるために自分たちの性の単彩色で塗りたくって、倒錯とよんでいるにすぎないのです。」(P.58)
東洋医学と健康保険。どうして西洋医学(西洋的知)が優先されるのか。
「 genre 」には多分、近代においてフーコーのいう「セクシュアリテ」