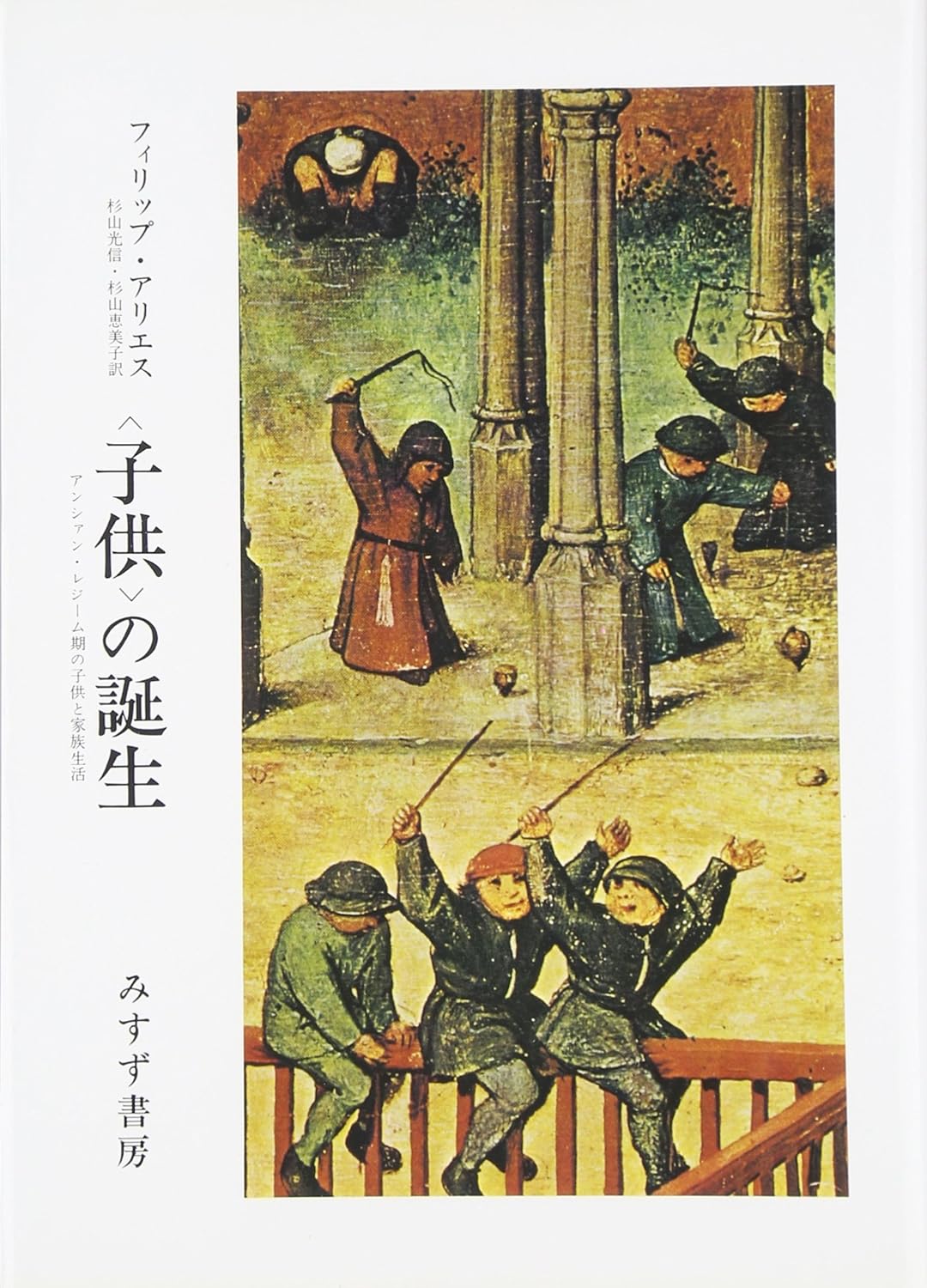日本語版への序
「一九四〇年にナチス・ドイツによってフランスが軍事的敗北を喫したことが、ときとしてフランスの人口の減少と出生率の低下によって説明されることがあった。これは政治現象を政治でも経済でもない原因によって説明することであり、当時としては異例のことであった。」(P.ⅰ)
(人口学の諸データ)「事実、現代の人びとが故意に目を向けようとしないでいたか、あるいは注意深く秘密のものとして保ちつづけようとしていた行動について、これらのデータは詳細な情報を含んでいることを、私は発見したのである。その行動とは、生と死にたいする態度ということであり、それ以後になると、生、死、性、出生といったこの領域の全体が、感嘆させられている私の眼に立ち現れてきたのである。これらの現象は生物学的なものと考えられ、従って文化以前の自然の性質に属し、変化しないものとみなされていたために、現在にいたるまで歴史家に採り上げられないでいたのである。だが、私はこれらの現象も動き変化することを知ったのだ!生物学に属していると同時に社会的な意識のあり方( mentalité )にも属し、自然に属すとともに文化に属してもいるこれらのカテゴリーの現象に、私が自分の研究をささげたのはこの理由からであった。」(P.ⅰ)
〔一九七九年六月〕
序文
「第一のテーゼは先ず、私たちのかつての伝統的な古い社会に関係している。この社会は「子供」をはっきりと表象していないし、少年にかんしては、なおのことそうであると、私は論じた。子供期に相当する期間は、「小さな大人」がひとりで自分の用を足すにはいたらない期間、最もか弱い状態で過ごす期間に切りつめられていた。だから身体的に大人と見做されるとすぐに、できる限り早い時期から子供は大人たちと一緒にされ、仕事や遊びを共にしたのである。ごく小さな子供から一挙に若い大人になったのであって、青年期の諸段階を過ごすことなどない。」(P.1)
「ちょうど動物と戯れるように、小さな淫らな猿でもあるかのように、人びとは子供と戯れたのであった。往々にして生じたことだが、子供が死亡したばあい、一部の人々は悲嘆に暮れはしたが、一般的には子供にたいしてあまり保護はなされず、すぐに別の子供が代わりに生まれてこようと受けとめられていたのである。子供は一種の匿名の状態からぬけ出ることはなかった。」(P.2)
「だが(この点が重要なのであるが)夫婦のあいだ、親子のあいだでの感情は、家族の生活によっても、その均衡のためにも、必要なものとはされていたのではなかった。」(P.2)
「感情の交流や社会的なコミュニケーションは家庭の外にあって、隣人、友人、親方や奉公人、子供と老人、女性や男性から構成されているきわめて濃密かつ熱い「環境」によって保証されていたのであり、そこで愛情関係をもつことにはたいした拘束もなかったのである。それで結婚生活における感情は薄められていたのだ。」(P.2)
「私の第一のテーゼは伝統的な社会を解釈しようとするひとつの試みであり、第二のそれは今日の産業社会のなかで子供と家庭とが占めている新しい地位を示そうとするものである。」(P.2)
「二つの異なったアプローチからその変化をとらえることができよう。教育の手段として、学校が徒弟修業にとって変わった。つまり、子供は大人たちのなかにまざり、大人と接触するうちで直接に人生について学ぶことをやめたのである。」(P.3)
「こうして開始された子供たちを閉じ込める長期にわたり存続していく過程(ちょうど、狂人、貧民、売春婦たちの「閉じ込めの過程」のような)は、今日まで停止することなく拡大をつづけ、人はそれを「学校化」とよんでいる。」(P.3)
「この意識・感情の変化が、私が強調したく思っている現象への第二のアプローチなのである。家庭は夫婦のあいだ、親子のあいだに必要な感情の場となったのであるが、以前には家庭はそのようではなかった。この感情はそれ以後に教育において認められ、そこで表現されるのである。」(P.3)
「こうして家庭は、子供をめぐって組織され、子供たちを以前に置かれていた匿名の状態からぬけ出させ、重要なものとし始める。以前の時代には子供を亡くしてもそう悲嘆に暮れることもなく別の子供によって埋め合わせられたのであるが、そのようにしばしば子供を生み直すということはされなくなり、よりよく面倒をみるために子供の数を限定するのがよいとされるようになる。」(P.3)
「その結果についてはこの本で考察する時期をこえ出ることになり、私は他のところで展開しておいたが、それは十九世紀の社会生活を家庭の極をめぐるものと職業の極をめぐるものに両極化させ、(モーリス・アギュロンやミシェル・ヴォヴェルなどの歴史家が示している南仏プロヴァンスを除いて)古い人間関係の結ばれ方を消滅させたのであった。」(P.3)
「実のところこれら若者からなる社会は単身者たちから構成される社会であって、下層民衆の階級では今日でもそうであるが、これらの時代には人びとはしばしば遅い年齢で結婚し(FF)たのであった。だから対置されるのは、結婚しているものと結婚していないもの、自分の家を有しているものと家をもたず他人の家に起居するもの、より安定したものとより不安定なものとのあいだでなのである。」(P.7-8)
「第一に、私はしだいによく知られ始めた非常に重要なひとつの現象に、すなわち十七世紀末葉にいたるまで大目に見られていた嬰児殺しの現象に関心を向けていたであろう。それはローマでの聖体顕示のように公認されて行われていたことではない。嬰児殺しは厳しく罰される犯罪であった。しかしながら、この犯罪は秘密裡に行われ、たぶんかなり普通にみられたのであり、事故の形をとって偽装されていたのである。」(P.8)
「死亡率の減少の理由は、その対策など考えられないでいた子供を死ぬにまかせない、ないし子供の死を促進することを止めた、ということしかないのである。」(P.8)
「本当の子供を裸の姿で表現することが好まれるようになるのは、十七世紀になってからのことでしかない。それより前の時代では、産衣か上着をつけていた。その一方、中世以来、魂は裸の子供として形象化されていたのはよく知られている。」(P.12)
「十三世紀―十四世紀の宮殿は、防衛のための塔、一階にあって街路に向かって開いているロッギアによって特徴づけられる。このロッギアに家族たち、友人たち、それに客人たちが、この市街とこの都市の公共的活動に参加するために集まったのである。」(P.13)
「十五世紀になると、宮殿はその設計、性格、意味を一変させた。第一に、宮殿はモニュメントとしての統一性をもつものとなり、隣の建物とは区別され、巨大な建物となった。そこに含まれていた数々の商店や関係のない間借人たちも、立のかされていった。こうして区分された空間は、ほとんど拡大されることのない家族のためのものとなった。街路に開かれていたロッギアは閉ざされたか、取り除かれた。宮殿が以前よりもこの一家族の権勢をよりよく誇示するものとなったとしたら、それは外部に向かって開かれているのをやめたからである。日常生活は、街頭の騒音や無遠慮さからへだてられ、外皮となる壁にそって、四辺形に仕切られた建物の内部に集中されるようになった。」(P.14)
メゾン=ラフィットにて 一九七三年
第一部 子供期へのまなざし
第一章 人生の諸時期
「アフリカの未開の土地では、年齢はいまだにはっきりとした観念となっていず、ほとんど重要なことではなく、それゆえ忘れてもかまわぬものなのである。だが、今日の技術文明の世にあってはどうして自分の正確な生年月日を忘れることができるだろうか。」(P.18)
「そして彼が初めて仕事に就くとき、彼は自分の名前と並んで登録番号の記入されている社会保険証を受けとることになるだろう。つまりそのことは、かれがポール某であるよりも性別や生年月日で始まるひとつの番号と化してしまうことだといえよう。すべての市民が登録番号をもつ日がいつかやって来ようが、それこそ身分証明書業務の目ざすところなのである。そうなれば私たちの市民としての人格は姓名よりも出生の座標によって一層正確に表現される。こうした傾向の極限においても、姓名はやはり消滅することはないかもしれないが、多分に私生活のうちにのみとどまるものとなろう。これにたいし公的慣行においては身分証番号が姓名に入れ替わり、生年月日がこの番号の構成要素となることだろう。」(P.18)__マイナンバー
「けれども、個人名と姓名とは、聖人たちのいる空想の世界(個人名のばあい)に、あるいはまた伝統の世界(姓のばあい)に属している。これにたいして年齢はほんの数時間の内に法律的に定まった仕方で確認しうる数量であり、厳密性と数字の世界という、まったく別の世界に由来している。今日私たちのもつ戸籍の慣行は二つの異なる世界に属しているのである。」(P.18)
「個人の位置よりも、家族の構成員としての座標配置が問題にされているのであり、日付を明記することで家族生活にたいしひとつの歴史を与えようという欲求が示されているのである。」(P.20)
「肖像画や家具などの上に年齢や日付を記銘することは、家族にたいし、さらに歴史的な一貫性をあたえようとする同じ意識に対応しているのである。」(P.20)
(子供 enfant )「中世末期には、その意味は特殊な仕方で拡大されていった。それは「幼児」( putto )(十四世紀の人びとは裸の幼児たちのフレスコ画の描かれている部屋、幼児〔 putti 〕用の部屋を呼ぶのに「子供の間」( la chambre aux enfants )と言っていた)を指すとともに、他方で青少年、とくに憂慮すべきいく分年長の少年、不良少年までも意味していた。」(P.28)
「十六世紀の人生の諸時期の暦表によると、二十四歳で「子供は逞しくかつ勇敢」であり、「十八歳ともなれば子供たちはそのような状態になる」とされていた。」(P.28)
「十七世紀を通じて一つの変化が生じ、古い慣習は最も従属的な社会階級のなかだけに保存され、他方ブルジョアジーにおいては新しい別の慣行が出現するに至るが、そこにおいては「子供」という語が近代的な意味に限定されるのである。一般的用語法にみられるような子供期を長期間にとる用法は、この当時、まさしく生物学的な現象が関心を払われぬままにあったことに由来している。子供期を性的成熟によって上限を区切るという思考法は見られなかったようで(FF)ある。子供期という観念は従属・依存の観念に結びつけられていた。息子、下男、少年という語もまた、封建制ないしは領主制的従属関係を示す語彙に属する語である。依存から、少なくとも従属関係の最低の位置から抜け出ることでしか、子供期から脱出することはできなかった。」(P.28-29)
(十八世紀)「私たちが青春期と呼んでいるものの観念は存在しなかったのであり、この観念は長い時間を要して形成されることになる。」(P.31)
「いつの時代であれ恋愛小説の読者になんらかの本当らしさを感じさせるためには、まだ口髭も生えていない少年と娘との間の類似が存在しているという最小限の本当らしさが要求される(それに私の想像では、この時代にごく丁寧に髭を剃ることなど不可能であったに違いない)。しかしながら、当時、こうした類似は青春期の特徴、この時期固有の特徴として表現されていたわけではない。柔和な風貌をもった口髭のないこうした男性は、青年に達していないとはいえすでに命令を下したり戦闘したりする一人前の男性として行動しているのである。」(P.31)
「近代の青年の最初の典型例は、ワグナーの「ジークフリート」である。ジークフリートの音楽は、青年をこの二十世紀の、つまり青年の世紀の主人公になさしめていく、(束の間の)純粋さ、身体的な力、自然さ、自発性、生きる喜びなどの混じりあったものとして表現する最初のものである。」(P.32)
「反対に、青年の意識は一九一四年の大戦のときに、前線の兵士たちが一団となって後方の老人世代に対立したのを承けて、普通にどこにでも見られる現象になった。」(P.32)
「青年期は子供期をごく幼い年齢へと押しもどし、成熟性をさらに年齢を重ねてからのものにするだろう。それ以後には結婚はもはや「身をかためること」ではなくなり、結婚によって青春期がさえぎられてしまうことはなくなる。既婚の青年の存在は現代の最も特徴的な類型の一つである。彼は自分の価値、自分の欲望、自分の慣習を主張する。このようにして、青年期なしの時代から青年期が好ましい年齢とされる時代へと移行する。人びとはそこに少しでも早く到達しようと望み、そしてそこに少しでも長くとどまっていようと願うようになるのである。(LF)この進化は、その方向は逆であるが、老年期の進化と並行して生じている。昔の社会では老年期が早期に開始したことは周知の事実である。」(P.32)
「古い時代のフランスでは老人はほとんど尊敬されていない。」(P.33)
「ちょうど二十世紀が青年たちに代表されているように、十七世紀はあの軍人の若者たちに代表されているのである。(LF)今日では、逆に、老年期( veillesse )という言葉は少なくとも口語からは消え去ってしまった。口語では「老いた」( vieux )という語は、隠語的、侮蔑的ないしは保護者ぶった意味あいを帯びて残っているのである。この進化は二段階でなされた。第一段階では尊敬すべき年寄り、銀髪の先人、賢明な助言を与える長老、経験豊かな家長がいた。(中略)彼はなお敏捷であるというわけには行かないが、もはや十六世紀・十七世紀の老人のように老けこんではいない。老人に対するこの敬意は、何らかの形で今日なお社会一般に受け容れられている観念の中に残っている。だが、実をいえば、これが第二の段階であるが、古い老人のイメージの時代は去り、このような老人への敬意はなんら実体を持ち合わせないものとなっているのである。」(P.33)
「若さの維持というテクノロジー的な観念が、生物学的であるとともに精神的でもあった老年期の観念に置き換えられているのである。(LF)こうしてみると、各時代ごとに、特別に重視されていた年齢と、人生にかんする特殊な時期の区分とは完全に対応しているかのようである。十七世紀に特別に重視されたのは「若者期」であり、十九世紀には「子供期」、二十世紀は「青年期」である。」(P.34)
「人間の寿命が短かった時代には、今日のような長寿の時代にもまして、特別に尊重される人生の時期の観念が重要であった。これから繙かれる頁では、わたしたちは子供期のあらわれに注目していくことにしよう。そして古い時代に知られる「若者期」の偏愛との関係では、子供期というこの表象がいかに相対的なものであるか忘れないことにしよう。この期間は現在いうところの子供、少年、老人のいずれのものでもない。それは「若い人間」の時期なのである。」P.34)
第二章 子供期の発見
「ほぼ十二世紀までの中世芸術では、子供は認められていず、子供を描くことが試みられたこともなかった。だが中世芸術における子どもの不在は器用さが欠けたため、あるいは力量不足のゆえであるとは考えられていない。それよりはむしろ、この世界のなかに子供期にとっての場所があたえられていなかったと考えるべきであろう。」(P.35)
「このことは疑いなく十世紀・十一世紀の人びとが子供期のイメージを持つには至っていなかったことを意味している。子供期はかれらの関心をひくものではなく、またなんら現実と対応するものでもなかったのである。」(P.36)
「十三世紀には、近代的な感覚にやや近いいくつかの類型の子供が出現する。」(P.36)
「十四世紀になると、周知のように、イタリア芸術がこの感情の発展と普及に貢献するのだが、それは母親の優しさに結びつけられているのである。」(P.37)
「裸の子供がその翼でもってやって来て、女性の口のなかに入りこもうとしているからである。「自然による人間の魂の創造」なのである。」(P.37)
「まず第一に、子供たちは日常生活の中で大人たちと混在しており、仕事や散歩あるいは遊びといったあらゆる集まりに、子供と大人の双方が合流していたことである。第二に、人びとは子供を描くことに惹きつけられていたのであり、(逸話を絵画の題材にする趣味は十五世紀・十六世紀に発達し、幼児期を可愛らしいとする感覚に符合していた)、家族や群衆を描くときに好んで子供を強調したのである。」(P.39)
「生き残ることさえおぼつかない子供があまりにもたくさんいたのであった。そのうち幾人か生き残ればよしとして子供を多数もうけるという意識は非常に強固であっ(FF)たし、長い期間にわたり存続した。」(P.39-40)
「今日私たちが普通に考えるように、子供というものがすでに一人前の人間のあらゆる体裁をそなえているとは考えられていなかったのである。」(P.40)
「こう見てくると、今日の私たちの子供期の概念と、近代の人口革命以前の時代ないしはそれに先立つ時期の子供期の概念との間には深い溝が存在することが理解できよう。この無感覚に驚いてはならない。それはこの時代の人口学的条件のなかでは当然にすぎることでしかない。」(P.40)
「子供の生命を必然的な浪費と考える思想は、ようやく十八世紀になって、マルサス理論の誕生と中絶法が実践されることで、消えていくことになろう。」(P.41)
「子供の人格に与えられたこの重要性は、たしかに一層深いところで習俗がキリスト教化されたことと関係している。」(P.44)
「子供期の発見は疑いなく十三世紀に始まる。そして十五世紀と十六世紀の芸術と図像記述の歴史に、その進化の里程標をたどることができる。だが、その進化を証言するものがとくに多数となり重要となるのは、十六世紀の末から十七世紀にかけてである。」(P.47)
第三章 子どもの服装
「幼児は産衣を外されると、つまり幼児の身体に巻きつけられていた帯状の布をはずされるとすぐに、自分の属する身分の他の男性や女性と同じ服を着せられていた。」(P.50)
「ともかくも、一九〇〇年―一九二〇年代に少年たちが大きくなってもなお子供期に特有の服装をさせられていたのにたいして、中世にはどんな年齢区分とも無関係(FF)な服装がされていたのであり、服装によって配慮がなされたのは社会的ヒエラルキーのどの段階にいるかを明示することだけであった。」(P.50-51)
「しかしながら十七世紀になると、貴族であれブルジョワであれ、少なくとも上流階級の子供は、大人と同じ服装はさせられていない。」(P.51)
「こうして、以前には大人と同じ服装をしていた子供たちを大人から区別するために、大人たちが久しい以前に着用しなくなっていた古風な服装の特徴が、専ら子供たちだけの慣習として保存されたのである。」(P.56)
「服装への支出は非常に嵩み、奢侈取締令によって衣裳が贅沢になるのを抑えようと努力されたが、贅沢な衣裳はあるものを破産に陥れる一方、他のあるものにはその身分や出自を実際とは違ったものに見せることを可能にした。」(P.57)
「社会的身分の微妙な千貝が服装という記号で表示されていた。十六世紀の末葉に、その頃から認識されるようになった子供期がそれに固有な服装を持つことが、慣行上求められたのである。」(P.57)
「男児に女性の服装をさせる慣習は一九一四年の大戦以後に、ようやく廃止されることになろう。それは同じ時期に女性のコルセットがすたれていくことと関係づける必要がある。この服装革命は習俗の変化を示しているからである。大人から子供を区分するという配慮が男児に特に限定されていたことは、さらに興味深い。」(P.57)
「男児たちは特異化された最初の子供たちであったのだ。」(P.58)
「十七世紀にはまだ庶民特有の服装はなく、また地方独特の服装もなかった。貧民は施しをうけた衣服や古着屋で買ったい服を着ていた。今日庶民の乗りまわす自動車が中古車であるのと同様に、庶民の衣裳は中古服であった(過去の時代の衣服と今日の自動車との比較は、外観的なレトリックで言ったいるのではない。自動車はかつて衣服が有していたが今日では完全に失ってしまった社会的意味を継承したのである)。」(P.58)
「衣裳の考証の範囲でいえば、子供期の特殊化は長期にわたって、少年のみに限定されているといえよう。また、この特殊化がブルジョワないし貴族の家庭にのみ保持されていたことも確かである。」(P.60)
第四章 遊びの歴史に寄せて
(十七世紀)「この時代には子弟の養育にあたって、早い時期から音楽と踊りとが導入されていたことに注目されよう。このことは子供時代のモーツァルトのように、今日私たちが神童と呼んでいる人びとが音楽家など専門家の家系に頻出したことを説明する。」(P.61)
(ルイ十三世の頃)「こうしてみると、当時は今日見られるような子供用の遊びと大人が行う遊びの間に厳密な区別は存在していなかったように思われる。同じ遊びが、大人と子供の双方に共通であったのである。」(P.65)
「近代になって幼児の独占物となっていくものは、古代には少なくとも死者と共有されていたのである。そして人形とも模擬品ともつかぬこの曖昧な性格は中世に至るまで、田舎ではさらに長く存続することになろう。人形はまた、魔術師、呪術師の用いる危険な道具でもある。日用品や人間を実物より小さい縮尺で形象することへのこうした嗜好は、今日では子供特有のものであるが、かつては子どもの慰みとしても、また大人を満足させる目的でも製作された大衆芸術ならびに職人仕事の中に見出されるものなのである。」(P.67)__内に向かう日本語思考、トランジスタ。
「これらの遊びが専ら子供たちに特殊なものになるとしても、一六〇〇年頃には幼児についていえる範囲を超えることはない。三歳ないし四歳を過ぎると、子供だけの遊びはみられなくなり消え去る。それより年長の子供たちは、時には子供たち同士で、また時には大人と一緒に、大人と同じ遊びをするのである。」(P.69)
「逆に、大人たちは今日子供のものとされている遊びで遊んでいた。」(P.69)
「古い社会では、労働は一日のうちに今日ほど多くの時間を占めていず、世論の上でも重要視されることはなかった。つまり一世紀ほど前から私たちが労働に認めている生活上の価値は、有していなかった。労働が今日と同じ意味をもっていたとはほとんど言い難いのである。反対に遊びや娯楽は、私たちがそれらに割りあてているような人目を忍ぶような時間ではなく、それをはるかにこえて拡がっていた。遊びや娯楽はひとつの社会がその集合体として結束を締め直し、一体感を確たるものとして感じるために行使する主要手段のひとつを構成していた。」(P.70)
「楽器を演奏したりすることがごく親近にまた一般的に行われることが、エリザベス朝時代のイギリスで最も先んじていたのは事実であるが、またフランスや、イタリアやスペイン、それにドイツでも中世の古い慣行に従って広まっていたのである。この慣行は趣味の変化の過程を通じつつ、また技術的な(FF)完成を達成しつつ、地域によって早い遅いの差はあるにしても、十八世紀、十九世紀に至るまで持続していた。それは今日ではもはや、ドイツ、中部ヨーロッパ、ソヴィエトにしか残存していない。」(P.76-77)
「これら乞食の子供たちという画題は十七世紀には非常に広くみられるものである。」(P.77)
「さて、ここで古い社会にこれほど大きな位置を占めていたこうした遊びにおいて、伝統的な精神態度がどのようなものであったかを問題にしてみよう。この態度は相互に矛盾した二つの側面を有しているように思われる。一方では、遊びは社会の大部分の人びとからなんの留保も蔑視も受けることなく、完全に認められていた。他方、これと並行して、権力につきまた開明的である、厳格な規律を重視(FF)する少数の人々は、ほとんど完全な否認に等しいほどに遊びを非難し、ほとんど例外を認めることなくその不道徳性を告発した。圧倒的多数派の道徳的無関心と、教育による強化を推進しようとするエリートの不寛容とは、長期にわたって共存していた。十七世紀・十八世紀を通じてひとつの妥協が成立し、それが古い態度とは根本的に異なる、遊びに対する近代的な態度をうち立てるのである。このことはまた子供期についての新しい意識の出現をも証言しているという意味で、私たちの主題にかかわってくる。すなわちそれ以後悪い遊びを子供に仕向けて、子どもの道徳性を保ち、また教育もしようとする、以前には見られなかった配慮が生まれるのである。」(P.78-79)
「私たちは相変わらず賭けごとに手を出したりはするものの、その裏でやましさを感じているのである。十七世紀にはまだこうではなかった。この近代のやましさの意識は、十九世紀の社会を「生まじめな人びと」の社会にした深部からの道徳化の結果なのである。」(P.79)
「一八三〇年ごろになっても依然として、イギリスのパブリック・スクールでは、公然と富籤が行われ、多額の金が賭けられていた。」(P.81)
(十六世紀のパリ)「禁止規則の厳格さは、その効果が見られないからといって改正されることは一度もなかった。原則よりも効果を問題視する私たち現代人の目から見ると、驚くべき頑固さである。」(P.85)
(十七世紀)「彼らは選択し、規定し、統制するという留保のもとで、逆に遊びを吸収し、プログラムや規則の中に公然と導入することを提唱した。このように規制されて、健全であると判断された遊びが許可され推奨されるにいたり、それ以後学問と同様に尊重すべき教育手段とみなされるに至ったのである。」(P.85)
「私たちは遊びがどの年齢にもどの身分にも共通であった社会状態から出発した。強調しなければならない現象は、こうした遊戯が上級の社会階級の大人の間ですたれていき、逆に、庶民と同時に上流階級の子供たちの間に残されていくことである。イギリスでは本当のところ、フランスのように貴族が古い遊戯を見捨てることをせず、改変してしまった。彼らは近代的に面目を一新した形態で、十九世紀にブルジョワジーと「スポーツ」を確立したのである・・・(ママ)(LF)古い遊びの共同体が時を同じくして子供と大人、大衆とブルジョワジーの狭間で崩壊したのは、実に注目に値することである。この符合は、すでに子供期の意識と階級意識の間の関係を垣間見せてくれるのである。」(P.96)
第五章 猥らから嗜みへ
(十七世紀)「十四歳の男子の結婚は恐らく稀になり始めていたことと思われる。十三歳の女子の結婚は当時なおごく普通であった。」(P.99)
「性的なことを前にしての態度、そして多分性的なことそのものが環境と共に変化するのであり、したがって時代と感情意識に応じて変化しているのである。」(P.99)
「子供の性器を素材にしてたわむれるこうした風潮は、ごく広汎に見られる伝統的なものと考えられるのであり、今日でもなお回教徒の社会には現存しているのである。」(P.99)__祖母によく「すずめ」と言われた。
「たしかに宗教的性質のものであるに違いないけれども、性にまつわ(FF)る施術に何の懸念もなく子供たちを同席させていたばかりではなく、子供が思春期、すなわちほぼ大人の世界に達するやいなやただちに禁止されることになる仕草や身体接触が、常識的に公然と許されてもいたのである。これには二つの理由がある。まず第一に、適齢期に達していない子供は性には部外者であり無関心であると考えられていたからである。したがって仕草やほのめかしは子供には何の影響も残さず、その性的な意味を失って無性化されたわけである。第二に、実質的に曖昧な低意が抜かれているとはいえ性的なものへの言及が子供の無垢を穢し得かねないという感覚が、実際の面でも世論の中にもまだ存在していなかったということがあげられる。この無垢というものが、本当に存在するのであるという観念はもたれていなかった。(LF)(LF)少なくともこれが、人びとが共有していた見解であった。だが、モラリストたちや教育者たち、少なくとも彼らのうちでも最もすぐれた人びとの見解は、当時にあってはほとんど影響を与えることがなかったとはいえ、これとはちがっていた。今日から見て彼らが重要視されるのは、時の経過とともに彼らの観念が社会一般の観念にたいして勝利するに至ったところにある。今日の私たちの性にたいする態度はそこに由来しているのである。」(P.102)
(十五世紀)「ジェルソンは淫蕩について論じる待降節の第四日曜の説教において、この問題に立ちもどる。子供は他人が自分に触れたり接吻することに抵抗しなければならず、もしそれを怠ったばあいには、どんな場合でもそれを告解しなければならない。「ソノヨウナ全テノ場合」とされていることは強調する必要がある。というのも通常は、こういうことが悪いことだとはみなされていないからである。彼はもっと先の個所で、夜には子供を別に寝かせるのが「よいであろう」と論を進めている。」(P.103)
(十七世紀)「基本的観念が押しつけられる。子供は無垢であるという観念である。」(P.106)
「子供を天使になぞらえることは啓蒙の上で常套的なテーマになっていくのである。」(P.107)__日本では戦後。
「実際、子供のかよわさや幼稚さについて本当に語られるのは、この時代になってのことである。」(P.107)
「ここでは、いかなる身分においても大人たちが幼児を相手に遊ぶことを好んだ、ということに立ち戻ろう。これが非常に古くからのことであるのは疑いないが、この時代以降になると、子供らしさに対して苛立ちの感情が出現することが注目されていた。子供らしさを前にして苛立つという、子供に対する現代的感覚とは正反対の感情が、このようにして発生したのである。」(P.108)
「神は「ご自身の完全無欠性にきわめて近い」かれらの純粋無垢の故に、子供たちを加護のもとに置くのである。子供たちには情念もないし、悪もないのである。」(P.109)
「いくつかの一般的原則はこの教義に由来しており、この時代の文献の中に共通する地位を占めている。例えば、子供がひとりのままで放置されることは決してないだろう。」(P.110)__第一の原則。
「第二の原則は、子供におもねることを避け、ごく早期に厳格に躾けようというものである。」(P.111)
「第三の原則は自制である。物腰の「大仰な慎み」。」(P.111)
「第四の原則はこうした品位、「慎ましさ」の配慮のもう一つの適用にすぎない。すなわち旧来の親密な関係を消滅させ、日常生活の中でもごく慎み深い物腰と言葉でもって、それにおきかえることである。」(P.113)
「以上のとおり、子供が純粋無垢であるという理解は、子供期に関する二重の道徳的態度に帰着する。ひとつは生活の穢れから、ことに大人においては黙認されるか、さもなければ許容された性的なことから子供の無垢を保護することであり、もうひとつは、性格と理性を発達させながらそれを強化することである。ここには矛盾があることが見てとれよう、というのも一方では子供期は維持され、他方ではそれを衰えさせようととしているからである。だがこうした矛盾は、私たち、二十世紀の人間にとってしか存在しない。子供期を原始的なもの、非合理的なもの、ないしは論理以前のものと関係させるのは、現代の私たちの子供期にたいする態度によって性格づけられたことなのである。」(P.114)
「最も集団的な祭りが最も早くに消え去ってしまったのである。」(P.120)__盆踊りとクリスマスや誕生会。
「初期聖体拝領は、十七世紀から十九世紀の間に、子供期の意識の最も可視的な表示となった。それは子供期の無垢ならびに聖儀によるその理性面の評価という、相容れない二つの相を同時に祝しているのである。」(P.122)
結論 子供期への二つのまなざし
「私たちが出発点として取りあげている中世の社会では、子供期という観念は存在していなかった。このことは、子供たちが無視され、見捨てられ、もしくは軽蔑されていたことを意味するのではない。子供期という観念は、子供にたいする愛情と混同されてはならない。それは子供に固有な性格、すなわち本質的に子供を大人ばかりか少年からも区別するあの特殊性が意識されたことと符合するのである。中世の社会にはこの意識が存在していなかった。」(P.122)
「小さな子供は死去する可能性があるゆえに数のうちに入っていなかったのである。」(P.123)
「子供はその生存の可能性が不確実な、この死亡率の高い時期を通過するとすぐに、大人と一緒にされていあのだった。」(P.123)
「この変遷は、すなわち十六世紀・十七世紀の社会の上層階級では、子供や幼児に、大人たちと区別する特別の衣裳を与えるまでになるのである。」(P.123)
「子供のいたずらは、常に母親や乳母、「お守役」に結びつけられていたには相違ないが、説明のつかない感覚の、漠たる領域に属していた。」(P.124)
「ここで注意されていること、つまり激昂するという感覚もまた、可愛がりと並んで新しいものであり、かつ中世社会にも見られた年代に無頓着に生活を共にする習俗の観点からみれば、一層かけ離れたものである。」(P.126)
「ところで肝心な点は、十七世紀には、こうした可愛がりは上流階級の人びとだけに見られたのではなく、逆にかれらはモラリストの感化を受けて、可愛がりを放棄し始めていた、ということである。」(P.127)
「子供の将来ばかりでなく、その現在の姿や存在そのものに関心が向けられるようになり、こうして子供は家庭のなかに中心的な地位を占めるに至ったのである。」(P.129)
第二部 学校での生活
第一章 中世における幼い生徒と大人の学生
「中世の学校の特殊な性格を理解するための手段は存在している。中世の学校の起源を研究することである。だが、起源のみではなく、歴史が展開するなかで生じてきたものを理解しなければならない。その理由は、ある歴史現象はその起源によって性格を規定されるより、それが直接に規定しているほかの一連の現象の連鎖により性格づけされるからである。」(P.132)
「学校の構造でいえば、古代の学校と中世の学校とのあいだには、根底的なところで断絶が存在している。中世の学校は聖職者を補充する必要から生まれるのである。」(P.132)
「ヘレニスム的な学校は古代文化の崩壊の過程にまきこまれ、都市的生活様式によって荒廃させられていった。」(P.133)
「聖務日課に定められているほとんどすべての祈禱を、聖職者たちは記憶のみを支えとして唱えることができた。この理由から、書物を読むことは認識にとって必ずしも不可欠な手段というわけではなかった。読むということは、失念したり、思い違いしたりするばあいに、記憶の支えとして役立つにすぎなかった。読み方は既知のことを生徒に「追認」させるだけであり、決してなんらかの新しいものを発見させるわけではない。だから、読み方の重要性はきわめて限られていたのである。」(P.133)
「しかし、ここにはひとつの新しい要素が付け加えられている。その要素とは古典ローマ世界の自由学問であり、ヘレニスム文化から継承されてきたものである。世俗学校において絶えることなく教授され伝えられていたこの自由学問はイタリアから、学問の伝統が修道院のなかで保たれていたイギリスとアイルランドを経由して、ガリア地方にもたらされるのである。これ以後には、詩篇集と聖歌の教育を主眼とした中世の学校に、「形式科」の三学(ラテン語文法、修辞学、論理学)、「実質科」の四学(幾何学、算術、天文学、音楽)が加えられ、最後に神学教育によって完全なものとされることになる。」(P.134)
(十二世紀)「さらに、新しいひとつの現象が中世の教育に、決定的な構造をあたえることになる。それは進学と法学とが専門分化していくことで(FF)ある。」(P.134-135)
(十三世紀)「自由学問はそれ自体では不十分なものであり、他の教育への準備を行うにすぎないとされていたからである。」(P.135)
「古代の学校と中世の学校とのあいだを明白な断絶がへだてているというのなら、中世の学校から今日の私たちの教育の形態までのあいだは、反対になんらの断絶もなく、感知されないような修正をつみかさねてくることによって移行してくる。」(P.135)
(相違の第一)「幾世紀にもわたり久しく、ラテン語は教養の言語としてよりも生きた言語として教育されたのであり、聖職者、法律関係者、財産管理の関係者には必要であったのである。」(P.136)
「中世の学校と現代の学校の相違の第二は、中世の学校には初等教育にあたるものが存在しなかったことである。」(P.136)
「しかし、中世や近世初期には、これら初歩的知識、経験的知識は学校教育の対象とされていないのである。これらの知識は家庭あるいは職業について見習うことで習得されるものなのだ。」(P.136)
「中世の学校と現代の学校のあいだの第三の相違は、中世の学校制度のうちには、文学と自然科学の高等教育は存在していなかったことである。」(P.136)
「論理学は学校での科目名としては長期にわたり存続していくものとして弁証術と入れ代わり、それ以後は論理学は哲学の同義語となる。」(P.137)
(イギリス)「フランスのラテン語学校と完全に類似したこれらの学校は、もっと後になると「グラマー・スクール」とよばれることになる。」(P.137)
「階段化されたプログラムの欠如、難易性のちがう学問を同時に教育していたこと、さまざまな年齢の生徒・学生が一緒にされていたこと、それに生徒の放任などである。」(P.140)
階段化されたプログラムの欠如
「時代が進むにつれ、文法はより初等の教育に位置づけられていった。古代においては、これとは全く反対に、文法学はひとつの学問であり、現在の文献学に対応するようなきわめて難解な学問であった。」(P.140)
難易性の異なる学問の同時教育
年齢の無視と学生の放任
「パリの大学に編成されている諸学校では、十二世紀と十三世紀には、長期の学業課程が慣行化し、学生たちはそこに遅い年齢になるまで、二十歳あるいはそれ以上の年齢までとどまるようになった。」(P.146)
「生徒全体の年齢が低下するにつれて、自由学問の教師たちはその思想の独創性で有名な学者や思想家、弁証論者や論理学者であることはなくなり、ほとんど尊敬されることのないただの教育家、教師、博識家、たんなる知的職人となっていった。この進化は十五歳前後で学業が終了されることになる短期課程が勝利したことで、中世末期に始まるのである。」(P.146)
「じっさいには、中世は年齢と学業段階のあいだの対応関係を全く知らないでいる。諸々の文書のうちで生徒の年齢への論及を認めることはきわめて稀なことである。」(P.147)
「このような人口統計学的構造にとって本質的な心理的要素は、その構造を構成している人々の年齢にたいする無関心であり、今日私たちの有しているような年齢への関心は十九世紀に生じているのである。」(P.147)
「だが、人びとが年齢の現象にかくも無関心でいたときに、相違する年齢の人びとが混然と一緒になっていると感知することができるであろうか。(LF)学校に入ったその時から、子供は直ちに大人の世界に入るのである。」(P.149)
第二章 新しい制度:学寮
「中世の大学にみられた雑多な学生人口の構成から、最初に分離されていくのは幼い生徒たちである。」(P.155)
(P.156)__文法学が諸学の基本?
「つまり私がそこでいいたいことは、十二世紀・十三世紀においては、十歳の子供たちと十五歳の少年たちとは大人の学生と一緒にされていたのにタイして、十五世紀以後、とくに十六世紀になると子供たちを少年たちとは分離しようとする試みにもかかわらず一緒にされたままでいるが、学寮の構内に閉じこめられることによって、全体としては大人の学生たちからは分離された、ということなのである。(LF)このような年齢による分離は学寮においてのみ存在していた。同じ時代の社会において、十三歳から十五歳の少年たちはすでに一人前の成人であり、人びとはそのことになんら奇異の念を抱くことなく年長の人びとと生活をともにしていた。」(P.157)
「大人たちから十分はっきりと生徒たちを区分するために、いささか年齢が上であっても、かれらの少年たる性格を誇張しなければならなかったようである。教育者たちのもとで通常みられるようになる傾向、教師という職業に固有な心理の本質的部分を形づくっていくようになる傾向の起源を、私たちはここに認める。ひき続きこの傾向は拡大していくが、十九世紀より以前には、親たちまで達することはないであろう。(FF)それが勝利する十九世紀に、たしかにこの傾向はまた、恐れられていた性的成熟( puberté )の時期をもっと遅い年齢に思いたがるひそかな欲求と対応したものとなるであろう。」(P.157-158)
(P.160)__禁止するということは、それに反する行為が多かったということ。「〜する困った連中がいる」という文献より、そちらを読むこと。日本史。現在はどうか。禁止によって見えなくなることはあるだろうし、ないかもしれないが、今も同じではないか。
「それゆえ、国王委員会の委員たちは、生徒たちにたいし給費生たちと一緒に居住することを禁止し、学寮から教師に属する生徒たちをひき離そうと考えたのであった。つまり、それ以前には、教師に属している生徒と給費生とは一緒に生活していたわけである。」(P.160)
「古くからの給費生の施設であり、授業を行っていた学寮にたいして、近代的な教育施設の性格をあたえるのは、この外来生なのである。」(P.160)
「外来生の制度の発展は、その起源において影響力を有していた規則正しい精神をそこから取り去って、それよりも権威主義的な規律によって置きかえていくことになっていく。」(P.161)
「いまやこれとは反対に、学院の学則は一日中、学院の授業に出席することをかれらに要求する。この慣行はどこででも課されたが、それというのも、生徒たちの家庭や教育家たちの眼にとって学寮の優秀さは、とりわけ学寮を支配している規律正しさと映っていたからである。」(P.162)
「これら規則のどれひとつとして、学業と関係しているものはなかった。これらの規則は大人にたいして適用される宗教上の規則に示唆をうけたものであった。だからそれら規則の本性からいって、大人と子供とのあいだで区別を設けようとするものではなかった。」(P.163)
「だから、これらの規則は慣行によって、より権威的な方向へ修正されていき、命令的な秩序が確立されるにいたる。」(P.163)
「こうして、道徳と生活様式とを指導する原則をあたえる規則から、一日の各々の日課を厳格に規定する規則へ、同僚たちによる管理から権威にもとづく体制へ、教師と生徒とからなる共同体であったものから教師による厳格な生徒の支配へ、移行がなされる。」(P.164)
「規律規則の最終的な確立は、たったひとつの講義の部屋からなり立っていた中世の学校から、教育のみでなく少年たちを監視し枠にはめこむ複雑な制度である近世の学院へと達する進化を完成させるのである。」(P.166)
「この生活様式のおかげで、生徒である青少年は社会ののこりの部分から隔てられたのである。社会全般はといえば、異なる年齢の人びとのみでなく、男性も女性も、異なる身分の人びとも、一緒に混然となったままであった。これが十四世紀の全体を通じての状況であった。」(P.167)
第三章 学級の起源
「公立学校であれ私立学校であれ、少なくとも中等教育に親しんでいる今日の人びとの共通の言語のなかで、学級(=学年)は子供あるいは少年・少女の置かれている位置を性格づけるような本質的な単位であると思われる。あまりに一般的にしか規定しないから、自分の息子がリセに行っているとは表現されない。かれはリセの第五学級にいると言われるであろう。少年たち自身もかれらの日常の生活空間のなかでの位置を、かれらが属している学級によって示している。」(P.168)
「だがそれなしには学院の生活が理解されないであろうこの学級という構造は、せいぜい十六世紀か十五世紀の末の時期にまでしかさかのぼれるものでしかなく、それが最終的な形態を獲得するのはようやく十七世紀初頭になってのことなのである。」(P.168)
「難易性の異なる学問を同時に教え、またいく度もくりかえし聴講する中世の方式は、たえざる混淆をひきおこし、年齢ごとにあるいは能力ごとのカテゴリーに編成しようとしうすべての試みを禁じたのであった。」(P.168)
「かつての時代には、人はもっとずっと長い期間にわたって人生のひとつの時期を保ち続け、少年期という生活期間はこのように短い時間の幅でいくつにも分断されることはなかった。だから学級が、幼児の時期と少年の時期との分化の過程の決定的な要因となったのである。」(P.169)
「固有の用語によって指示されるようになって、学級は教育の理論家たちによって、たとえばバデュエルによって、学級組織の本質的要因と認められるようになっていく。」(P.172)
「それにひきかえ、古い時代には「異質な生徒たちがごたまぜにされていた」。だが学級が出現してからはこれとは反対に、「学校は生徒の年齢や発達にしたがっていくつもの学級に区分されていこう」。これはもはや経験にもとづくものでなく、なんらかの根本的かつ必然的なものである。」(P.172)
「もし他の学校において、たったひとつの部屋に集められた生徒たちのあいだでの区分である学級がひとつの有機的な単位となっていったとしたら、そのことはこの学級を担当している教師に負っているにちがいないのである。」(P.173)
「長い期間にわたって、教師たちとかれらに属している生徒たちは、ひとつの教室のなかに集められ、この部屋は「スコラ」(学校)と呼ばれていた。学校ごとにひとつの学業の部屋しか存在せず、それゆえ「スコラ」という言葉には、部屋の意味と制度の意味とが同時に含意されていた。」(P.176)
「じっさいには、人びとの注意が向けられていたのは年齢の方ではなく、つねに発達の程度であった。」(P.180)
「最も知的な領域、すなわち教育の領域において近代的意識の誕生したことを告げる分析や区分の新しい欲求は、ひるがえって、労働の領域では分業を、年齢の表象の領域ではあまりにも異なる年齢の人びとを混淆させることの嫌悪を、というように、それと同一の欲求や区分方法を生じさせていった。」)P.180)
第四章 生徒たちの年齢
「この章では、アンシャン・レジーム期の数世紀を通じて、生徒たちの年齢がどうであったか、人びとが年齢にあたえている意味とその意味の進化について、ひとつの懸念をあたえるように試みよう。」(P.180)
「これは口誦による伝達が、書字によるコミュニケーションに優位していた時代のさいごの名残なのである。」(P.182)
「中世の末期にいたるまで、そして多くのばあいそれ以後においても、宮廷人、軍人、行政官、商人、労働者など、いかなる職業であるにせよひとつの職業に入るためには、その職業に入るに先立ってその活動に必要な知識を学ぶことが必要とされたのではなく、その職業に先ずは直接に入り、そしていったんその内部に入ってから、すでに経験を積んでいる大人と一緒に仕事をしたり、生活上の共同体のおかげで、日常的な活動のなかでこれらの知識を身につけていたのである。」(P.184)
「少年たちのあるものは早熟的な熟練ぶりを示すことがあり、それなしには、年齢の区別なく職業上の資質を高めていくのがつねである技術的な環境から、技術をぬすみとることはできなかった。」(P.186)
「上級の諸学部の衰退と学院の威信が高まることとの間の符合は、必ずしも偶然のことではない。専門の教育があまり技術的ではなくなり、中世末や人文主義のすべての知識に通じることを理想とすることからへだたってきた時期には、学院がただひとつの人間形成の手段となり、個人授業を受けるところまで行かずとも、人は教育をより完全にするため学院で学ぶ時間を長くしようとする。」(P.193)
「会話によりラテン語を教えることは十七世紀末には消滅するであろう。」(P.203)
「「ここには学問をする」という近代的な表現とともに、かつては専ら父親のものであった子供の教育、社会的上昇、職種の選択などにかんして母親とその役割が家庭でも影響力をもってくるという近代的、ないし「十九世紀」的なものを認めうる。」(P.207)
「回想録から抽出されてきたという理由から、私たちがざっと眺め経歴を書き出してきたこれらの諸例は、例外的ではないとしても、少なくとも平均を上まわるものとみるべきであろう。普通の平均的な人びとは回想録など残さないからである。したがって、ときには絢爛たるともいうべき、社会的成功を得た人びととかかわっている。」(P.208)
「私たちは十歳から十四歳の年齢の修辞学の学級の生徒と出会った。これはまた、十六世紀から十八世紀までのイギリスの著作家たちによって、グラマー・スクールを出て大学に入る年齢とされていたものなのである。」(P.210)
「十七世紀末以来、時代の相違をこえて、ブルジョワや貴族に割りあてられている職業につくことによって上流階級に入っていくという欲望も、教育と学校とによってこの上昇を達成するその手段もなんら変化していない。変化したのは教育に年齢制限が付されたことである。今日では野心的な父親はすぐに息子を中等教育に入れようとしよう。だがもしその年齢制限を逸してしまえば、賭けは終わっていて、規定の年齢をこえた少年はリセへの入学を認められないであろう。」(P.214)
「この年齢制限という観念は十七世紀十八世紀には全く知られていなかった。」(P.214)
「人びとの人生は今日より短かく、さまざまな年齢が密に重畳していたとはいえ、人生における新規巻き直しにかんしては今日よりずっと柔軟性があった。」(P.214)
「このような年齢は、現代の人びと、少なくとも私と同じように一九四〇年以前に中等教育を終えた人びとによっては、かなり遅いものと思われよう。というのは、すぐその後でバカロレアを一種の競争試験に変形した――むしろ堕落させたといってよい――競争のせいで、あらたな高年化を観察することになるからである。」(P.223)__就学率はどのように変化したんだろう。
「早熟はある時代には社会的成功と結びついていたのである。とはいえ遅くとも十八世紀になると、世の人びとはこれら神童を感嘆の対象としなくなる。早熟ということへの嫌悪は、青年期に対して無関心でいた状態への最初の亀裂のあらわれである。」(P.225)
「それゆえ、早熟さにたいする反発は、子供期の最初の段階を十歳ごろまでひきのばさせる、学院による最初の学齢区分という分化を意味している。」(P.225)
「十八世紀末にいたるまで生徒を年齢ごとに区分する観念はもたれない。」(P.226)
「1年毎に進級するサイクルの正規化、一部の学級のみを過ごさせるかわりに、学級の全過程を過ごさせる慣行、より少数で年齢のそろった生徒から構成される学級と適合的な新しい教育方法、こういったものが十九世紀初頭に、年齢と学級とのあいだにしだいに厳格化する対応関係をうち立てさせるのである。こうして教師たちは生徒の年齢という側面から自分たちの学級を編成するのに慣れていく。さらにかつては混合されていた年齢も、生徒たちが年齢に応じて学級に分けられていくに従って区分され始める。というのも、十六世紀末以来、学級は構造的単位として認められていたからである。学院やこのような生きた細胞をなしには、ブルジョワジーは子供たちのさまざまな年齢の段階を、かれらが今日示しているような配慮と結びつけることはできなかったであろうし、またこの点で民衆の社会での年齢にたいする相対的な無関心から区別されることもなかったであろう。」(P.226)
第五章 規律の進化
「近代人の生活はときとしては相互に競合的である職業生活と家族生活に分割されていて、残りはすべて付属的なものとなっている。たとえば宗教と文化の生活は、たいていのばあい楽しみであり息ぬきである。友人たちとの会話、食事は、すばやくのみこまれる食物と同じように有機体にとって必要であるたんなる息ぬき、骨やすめといったものとされている。だが、このことは生命の本当の有機体にとってはそうみなされてはいず、ちょっとした余分、贅沢であり、それが無視されることはないが、恥ずかしいものとされはしないとしても重要なものとは考えられていない。中世においては全く反対であり、今日では全く個人に属するものとされ狭いところに押しこめられているこの社会的な余暇は、集合体の生活において本質的な位置を占めていたのである。私たちにとって、それらの起源が地中海的な酒神祭にあるのか、ゲルマン的な饗宴にあるのかということが重要なのではない。重要なことは、ときとしては酩酊と結びついている一同に会しての食事により支えられているこの結社を、友愛関係を公然と認知するような風土なしには理解しえない、ということなのである。このばあいの(FF)酩酊は、たんにその状態のうちに見出しうる感官上の快楽ということ 人間は仲間たちとうまく調理されたものを賞味するよろこびをやめたことがない のためのみではなく、この快楽はそのことをさらに乗り越えて、ちょうど今日の私たちの社会生活が公私の法的制度の上で営まれているように、すべての社会生活がその上で営まれている宗教的かつ法的な参加、誓約されたものの感覚的かつ物理的な形象化物となっているためでもある。近代的な生活様式はかつては融合していた要素の間での乖離の結果として生じたのである。」(P.231-232)
「中世の生徒たちの共同体は、今日の人間社会、とくに子供や青年の社会の組織についての私たちの有している観念からへだたっている。これらの共同体はなんら権威主義的でなく、いかなる首長もひとりで意思決定を下すことはない。意志の決定はほとんどの場合共同体の全員による多数決 全員の一致によることがよくある によってなされていた。とはいえ、共同体は民主主義的ないし平等主義的であったのではない。というのは共同体は一部のものの特権を認め、旧来からの生徒と新入り生徒の間で格差づけによる差異を保っていたからである。そして、これら共同体は功利的な目標よりも、具体的な人格関係の上に、成員間の友愛関係の上に基礎を置いていた。権威の観念、というよりも権威の委託の概念、つまり権威の委託者が規律が遵守されるようにその役務を果たすという規則にかんする近代的観念は、かれらにとっては無縁のものであった。とはいえ、ヒエラルヒーや指揮命令という近代的原理が存在せずにいたことから、生徒たちが一種の無政府状態にいると推論するなら、それは誤っていよう。反対にこの時代の社会の構造を構成していたこれら共同体によって枠組をはめられていたのである。」(P.232)
「十五世以来、これら秩序の側に立つ人びとは学生組合的連帯という学生の慣行に対してたたかうとともに、これら開明的な人びとの組織は子供とその教育について新しい思想を普及させようとした。」(P.239)
「ここで、二つの新しい観念が出現する。ひとつは子どもの「弱さ」( infirmié )の観念であり、教師は子供たちの道徳について責任を有しているとする意識である。」(P.239)
「ここから中世には思われもしなかったような、近世の学院での密告の制度が重要性を持つことになる。密告は相対的に過大となっている生徒人口をごくわずかな担当教師によってコントロールするために必要であったにちがいない。」(P.241)__人員削減が「密告」制度を産む。相互不信が増える。雇用側が監視するだけなら、被雇用者は相互に助け合う。
「というのも、生徒たちはこれ以後になると、自分ひとりで行動を処していくことのできぬもの「弱キ者」とみなされるからである。」(P.241)__労働者や、個人は「弱キ者」だろうか。自分で行動を処しできないものだろうか。さらに「自己統御」「自助」の観念が生まれていく。
「十六世紀になると、すでに完全に実効を失っているか、古い文書によってはじめて記憶に思い返されるかするにすぎない伝統的な罰金の罰は、笞うちの罰によって置きかえられた。体罰はすぐれて「学校でなされる罰」となった。」(P.245)
(P.245)__100年で大きく変わり、忘れられる。
「十五・十六世紀には、体罰は社会全体における権威ないし絶対王政的ヒエラルヒーの観念と並行して一般化していった。とはいえ、中世においては程度の差でしかなかったところの子供の規律と成人の規律との間に本質的な差が生じているのが認められる。」(P.247)
「だから、幼年期と少年期とを画す線はひき下げられ、同一の規律に服させることで青年は児童の方へ押しやられようとする。」(P.247)
「すべての身分を通じて、子供たちはすべて農奴のものであり品位を傷つける制度のもとに置かれる。子供期の特殊性、またその大人の世界から区分される差異の感情は、子供は弱いものというごく基本的な感情から始まり、もっとも下層の社会階層の水準まで普及していくのである。」(P.247)
「フランスにおいては、世論はこの学校規則の体制に対してはっきりと嫌悪の念を表明し、一七六三年までには消滅してしまうことになった。」(P.248)
「これとともに、従来からの密告の制度も放棄された。」(P.249)
「しかしながら、監視の廃止は教師団体の改革をもひき起こした。モニターの存在なしでは、教師たちは従来のような少数にとどまりつづけられない。」(P.249)
「諸々の学院では教師団の規模が増大していったし、その内部でのヒエラルヒー化が進行していった。このような構図のうちで一七六六年に教授資格試験の制度が創設され、教師たちの世界のヒエラルヒーでの最下層は、これまでモニターであったのだが補助教師によって置きかえられた。これが自習監督の起源をなすものであり、今日では復習教師とか監督教師とよばれていようが、「操行の教師」なのでもあった。(LF)このような学校規律のシステムの変革は、子供世界において、たんに自由思想の進歩の表現にとどまるものであったろうか。そのような説明は単純にすぎるし、また一般的すぎる。というのは、笞刑が学院から放逐されたとしても、それは代わりに軍隊のなかで根をおろすことになるからである。」(P.249)
「さらにまた、初期の工業の工場は、体罰を欠いていたとしても、かなり冷酷非情なものであったのである。」(P.249)
「子供は大人と対立させられるよりは(いかに習俗の上では大人と区別をされるにしても)、大人の生活への準備をするものとされる。」(P.250)
「じっさい、早期からのこの指揮の慣習をもつことは、未来の紳士たち、つまり未来の指揮官のもとで権威と責任の感覚を強化すると理解されていよう。とはいっても、もし教師たちに密告するという権限をうばわれていたら、モニターは仲間たちに対していかにしてその権威を押しつけることができたであろうか。これが古い慣行では決してモニターにあたえられることのなかった罰則の直接の実行の権限が、あたえられるようになった理由である。」(P.251)
「十九世紀初め以後には、アンシァン・レジーム末期と大革命の時期にさえみられたこのリベラリスムの伝統を、学校規律は放棄してしまい、いな革命期からすでに軍隊的な方法、つまり、兵営の様式を採用するようになる。そしてこの様式はもっと後まで、十九世紀の末まで持続するのである。」(P.251)
「一八九〇年になって、ひとつの新しい学則が独房にとじこめる懲罰を廃止し、こうしてほぼ一世紀近く続いたナポレオン体制は終わったのである。ルイ・ル・グランの歴史を著したデュポン=フェリエが注目したように、学校は十八世紀のロランの体制へと復帰するのである。」(P.252)
「したがって、ナポレオン的学制によるリセの出現に先立って、少(FF)なくとも今日の中等教育に対応する学校が軍隊化するということがあったのである。このことは、軍隊が社会のなかで自己主張を始めたことに対応しているのは疑いない。」(P.252-253)
「いまだいかに萌芽的であるにせよ、子供に対する感性様式とは区別される新しい感じ方が、青年期を青年期として感知する様式が出現する。私は他のところで徴兵された兵士について同一の性格に注意を喚起しておいた。」(P.253)
第六章 通学学校から寄宿学校へ
「今日、私たちは教育について三つのカテゴリーしか知らない。ひとつは十九世紀のブルジョワの時期に今日よりはるかに普及していた家庭教師による個人教育であり、あとの二つは、通学生および寄宿生を対象とする集合的教育の形態である。十八世紀に至るまではこれら三つのカテゴリーは存在していなかった。というよりも、教育はそれらの具体的意味とは対応していなかったのである。」(P.254)
「しかしながら、教育理論の論議のなかでは、個人教授よりはせいぜい十人ほどの生徒に限定しての小さな集団での教育のほうが好ましいとされていたのであった。」(P.254)
「理論的な著作と現実との間にこのばあいはいかなる関係も存在していないことを殆ど考慮に入れることなく、近代の歴史家たちは書物のなかの例を額面どおりにうけとったのであった。」(P.254)
「この家庭教師という言葉は、ひとつは具体的な意味で、他は漠然とした意味でというように、二つの意味で理解されていた。(召使=近習はほぼ同年齢で、ときとしては乳飲み兄弟であったのとは反対に)家庭教師は本人よりも少し年上のひとりの仲間であり、金持ちの家族は学院で子供にともなわせるために選ぶものであって、生活や勉学をともにし、金持ちの子供たちを監視し、保護し、援助するものであった。」(P.254)
「けれども、同じ家庭教師という言葉は、その子供たちを寄宿生としてあずけている学院の担当教師たちに対しても用いられていた。」(P.255)
「十八世紀末以来の寮制度の発達は、子供期と社会のなかでそのさしこまれているその位置について、全く異なるある観念が生じたことを示している。これ以後になると、子供たちは社会において他の年齢の人びとから隔離されるようになる。少なくともブルジョワ市民にとって、子供を別の世界、つまり学校の寮の世界にとじこめることが重要なこととなる。学校はこの幽閉のための手段なのである。かくして、学校はすべての年齢の人びとが区別なく入りまじっている社会に対して置きかえられる。そして、ここで人は、学校が子供たちをある理想の人間類型のモデルに従って教育することを求めるのである。」(P.269)
「そして今日、青春期という新しい年齢階級のおかげで子供期はそれに固有の特殊性の一部を失いかけているのである。」(P.269)
第7章 「小さな学校」
「技能は学校で教えることのできるものではない。もっと先に至ってみるであろうように、能書技能の独占は親方=筆匠の職業団体に属しているものである。」(P.275)
「これは印刷術の発明される以前であったことと紙の稀少かつ高価であったことを原因としていて、今日よりもはるかに記憶が拠りどころとされたのである。すっかり暗記する必要があったのである。それで、書字はこの努力を避けさせる疑わしい手段とみなされていた。」(P.275)__親方という独占職業=カースト=社会的分業。貴族はテーブルを拭くことを禁止される。「やらない・できない」ではない。パンチャーという高級(高給)な職業がなくなったことを見よ。
「この時代に、十七世紀中頃のイギリスにおいて、J・エヴラルトの『速記術概要』などの速記術の教科書が存在していたのである。そこまでいくことなく、書字は筆記体の変形にとどまっていて、それ自身いくつかの変種、丸味がかったり、折衷的であったりする変化字体を有していた。」(P.276)__日本の草書。書くための書体。というか、「書体」は書くこと。「書くため(とき)の字体」。
「このさいごの「手書き文字」体は当時は「儀礼作法の活字」とよばれていたのである。」(P.276)
「この仕事は印刷術の普及によってすたらされずにはいないし(モニター、官報などの印刷された書式は十八世紀末に始まる),また一七八九年の革命の法律・政治的な大変動によって滅んでしまう。それ以後には歴史家にとってのみ役立つよう残された古文書を、大革命は無効にしたのである。共通に利用しうる書字体にかんしては、ゼロから再出発することになる。」(P.279)
「勘定することは、すべての人に可能なことではなかったのである。」(P.279)
「今日では相互補完的と思われている読み方と書き方が、長期にわたって独立なものと考えられ、別々に教えられていたことが、ここからわかるだろう。一方は文学的・宗教的教養と結びつけられ、他方は手先の技能と実業活動と結びついていたのである。」(P.280)
「というわけで、この時期に金持は貧乏人と机を並べるのを嫌うことはなかった。」(P.289)
「この点で私たちは、十七世紀の社会と、私たちの社会、少なくとも十九世紀の社会という二つの社会のあいだにある大きな相違に具体的にふれている。一方の社会は非常にヒエラルヒー的に構成されているが、決して各々に分離されていないひとつの空間のなかで人びとがとなりあわせている。そして今日の社会はといえば、全く平等になっているが、各々の境遇の人びとはそれぞれごとに区画されている空間のなかに分離されているのである。(LF)私たちは、今日のブルジョワ的な中等教育の起源としての学院もまた、部分的には民衆的な社会層から生徒を編入してきたことを知っている。起源にあっては、学寮の基金は貧しい給費生のために用意されたものであった。じっさいのところは、給費生の資格も往々にして、官職と同じように金銭によって購買される特権たるにとどまっていた。だから、貧乏人の子供たちがラテン語学校に入ったのは、必ずしも給費生の制度によるのではなく、むしろ無償教育と(FF)通学生の制度のおかげなのである。」(P.289-290)
「十八世紀を経るうちで、ある新しい精神が出現し、それが十九世紀の状態を準備する。この精神は啓蒙哲学を生気づけたのと同じものだ。この精神は、民衆にぞくする子供たちが中等教育に入ってくるのを拒否する。この時期以後になると、教育は富裕者のみ約束されているものでなければならぬ、というのも、貧民たちにまで拡大されると教育内容はねじ曲げられ、子供たちは出来そこないになるから、と考えられるようになる。社会においてはどこでも、有用な肉体労働者の不足と、非生産的人口の過剰に苦しんでいた。」(P.292)__「リソース」としての人間。
(P.292)__出生届を出さない子供は存在しない。文字(数字)化されない歴史は存在しない。
「ラテン語学校は、ちょうどのちの中等教育がそうなるように、農民、労働者、従僕たちに対しては閉ざされるようになった。」(P.293)
「民衆の子供たちを編入することは切りすててしまい、学院は完全にブルジョワのものとなるのである。」(P.294)
「こうして、パブリック・スクールは十九世紀のイギリス社会を形成し、それに貴族主義的な性格をあたえることになる。」(P.295)
「十九世紀のジェントルマンは、十八世紀ないし十九世紀初めのイギリス人とは身体的特徴においてさえも異なっていて、つまりピックウィック氏とは異なっていて、これはパブリック・スクールの教育の産物そのものなのである。」(P.295)
「とはいえ、もしフランスとイギリスとにおいて進化のメカニズムが異なっているとしても、この現象は基本的に同一のものであろう。ある限られた地域から生徒を編入する通学生の学校から、より広く、ときには全国から生徒を集めてくる寄宿生の学校へ、さまざまな社会カテゴリーの生徒により構成される学校から、貴族主義的ないしブルジョワ的に編入の限定される学校への変化は瞭然たるものであり、かつてはきわめて開放的であった中等教育は、階級により独占されるものとなり、ある身分とその選別の手段を表示するものとなる。」(P.295)
第八章 生徒=幼児の粗暴さ
「十七世紀の社会と今日の私たちの社会と、この二つの社会のあいだにある習俗のちがいは、大人たちのうちでは部分的にすでに消滅したアルカイックないし中世的なものが、子供や青年のあいだでは非常に長くにわたって保存されている点にみられるのである。私たちはさきの頁において、学院やその他の教育制度を通じて、子供たちが近代的な意識をもつようになる足どりを研究してきた。秩序、明晰さ、権威と結びついていた一部少数の人びとが、古くからの習俗のうちにある無秩序な衝動的なものとは対立する新しい生活様式を、教育によって社会に浸透させようと努力するのである。だが、子供の世界は長いことそれに抵抗を示し、フランスでは十九世紀の初めまで、孤立したアルカイスムの小島のような形で残りつづける。そのあとで、子供の世界は社会を近代化して(FF)いく原動力となるのだ。」(P.296-297)
「十八世紀は静穏な時代になるだろう。そして十九世紀の前半になって、リセにおいて学生の反抗の発生を再びみることになるが、それはポーランドの独立を支持するかしないかとか、ジェスイット会に反対するというように、政治的な動機のものとなる。これは今日の私たちの有しているのと同様のものであって、十七世紀の反抗とは別の種類の意識状態に根ざしている。」(P.299)
「これとは反対に、イギリスのばあい、十八世紀はこのような学生反乱に特有の時期を認めることはできない。学生の反抗は、フランスでのように衰退し消滅していくどころか、十八世紀の終わりから十九世紀の初めに、その頻度と激しさを増大させるのである。あらゆるところで無規律と反抗とが認められるようになる。」(P.300)
「これらの決闘は十九世紀の初めになるとレスリングやボクシングの試合に変形され、パブリック・スクールの改革よりも前の時期から、教師たちにより尊重されるものとなる。」(P.301)
「今日でもアメリカにおいて十一月のある日には、子供たちは家々の戸口をまわって、お菓子などささやかな贈り物を求めている。かつて家族たちから多かれ少なかれ離れていた子供たちのもとで、食物の必要と対応していたこれらの慣習が、形をかえて存続しているのである。」(P.306)__七夕。
「新しい道徳の観念が子供たち、少なくとも学校にかよう子供たちを区別させたにちがいなく、教育された子供たちを別扱いにさせた。このような観念は十六世紀にはほとんど存在していず、十七世紀に形成されてくるのである。」(P.308)
「このよい教育をうけた子供とは、フランスでは小ブルジョワである。イギリスではジェントルマンであるが、ジェントルマンという社会類型は十九世紀までは知られていなかったものであり、脅かされていた貴族社会がパブリック・スクールのおかげで、民主主義化の圧力から自らを防御するために創出したものである。」(P.309)
「中世的な古くからの騒乱を好む傾向は、先ず子供たちのもとで放棄され、さいごに民衆階級のもとでも放棄される。そして今日では、かつての放浪者、乞食、「アウト・ロー」、十六世紀から十七世紀初めの生徒といったものたちの最後の継承者である不良少年のもとで存続しているのである。」(P.309)
結論 学校と子供期の長さ
「この本の第一部において、私たちが区分した子供期にかんする二つのまなざしの誕生と発展とを、私たちは研究してきた。そのひとつは、広く普及をみている「甘やかし」( mignotage )の感覚であり、これはごく幼い年齢に限られ、またごく短期間の幼児期の思想と対応している。もうひとつは、子供の無垢と弱さの自覚とかかわる感覚であり、従って子供を保護し防衛するのは大人の義務という感覚である。」(P.309)
「だがまた、放縦といわないとしても、道徳的ないし教育的な配慮から全く自由であった。生まれて以来はじめての五、六年間をすごしたあと子供はなんらの移行期もなく、大人たちの間に溶けこんでいく。」(P.309)
「それゆえ、アンシャン・レジーム期にははっきりと区別されないでいた少年期は、十九世紀には、正確には十八世紀末に、徴兵制によって、ついで兵役制によって、区別されるようになったのである。」(P.310)
「中世の学校は決して子供のためのものではなく、聖職者に必要な知識をあたえるための一種の実務学校であり、ミショーの書物がのべているように「老いも若きも」共存していたのである。」(P.310)
「ルネッサンス期の人文主義者たちも、かれらの敵である伝統的スコラ学者たちとこの立場を共有していたことに注目されよう。中世の神学教授と同じように、かれらは教育と教養を同一のものとして考え、教育を人生のすべてにわたる期間にまで拡大し、いかなる年齢のときに教育をうけるかを特定化することがなかったのである。」(P.311)
「ルイ十四世の治世の終わりごろ、十四歳の中尉が軍隊には存在した。」(P.311)
「中世の学校と近世の学院とのあいだの本質的なちがいは、規律の導入という点にある。」(P.313)
「私たちが今日、初等・中等・高等というように列挙する教育をほとんどすべて学院が担当していた時代に、学校にかようことは、今日よりもはるかにある特定の社会身分と結びつくことは少なかったのである。」(P.314)
「しかしこのような状態は持続しない。十八世紀を過ぎると、エコード・ユニークとして存在していたものは、複線的な教育体系によって置きかえられる。ここで各々の分岐は年齢に対応するのではなく、社会的身分と対応するものとなる。すなわち、リセないしコレージュはブルジョワのための中等教育、小学教育は民衆のための初等教育とされるようになる。」(P.315)
「人びとはもはや、出発点において最後の課程にまで修了し、ゲームの規則をすべて受け入れようと決めている生徒をそうでないものと共存させるほど寛容ではなくなった。というのは、学校であれ宗教団体であれ、閉ざされたひとつの集合体の規則というものは、すべて同じようにそのゲーム以外のすべてを放棄させるからである。長期の学業課程を規則として課そうと考えられたときからその身分、親の職業、財産によって、その過程を続けることができないか、最後まで終えると保証できない子供たちのための余地は、なくなったのである。」(P.315)
(繊維産業などの)「児童労働は、大人の世界へごく早い時期に入っていくという、中世社会の性質を保存していた。ブルジョワと民衆階級とにおいて学校での子供の扱い方が異なってくることによって変化をうけたのは、生活すべてにおける色調なのである。(LF)したがって、近代的な年齢階級と社会階級とのあいだには、注目すべき同時性が存在している。つまり、その両者とも、十八世紀末という同じ時代に、ブルジョワジーという同じ環境で生まれているのである。」(P.316)
第三部 家族
第一章 家族の肖像
(十三世紀の写本)「街路は、今日のアラブの諸都市に見られるように、仕事場つまり職業生活の本拠であると同時に、お喋り、会話、見せ物、遊びなどの本拠でもあった。ながいあいだ芸術家に無視され続けてきた個人生活以外は、すべてのことが街路で行われていたのである。それでもなお、田園から着想を得て描かれていた暦の場面では、街路の情景はいつまでも無視されていた。」(P.320)
「こうした中世の街路は、今日のアラブの街路と同様に、個人生活の親密性に対立してはいない。それは個人生活の外への延長なのであり、仕事と社交の身近な地域なのである。芸術家たちは、個人生活の描写を比較的遅ればせながらも試みるにあたって、家の内部に追い求めるより先に、街路でそれを把握することから始めるであろう。もっとも、この個人生活は家の中と同じくらいかあるいはもっと多く、街路で送られてもいたのではあるが。」(P.320)__井戸端会議。今は個人は家に(あるいは室内に)閉じこもり、通りを監視する。不審者を見つけるために。今、用事もないのに街路にいれば通報されかねない。交流の場ではなく、移動の手段になってしまった。高速道路や自動車と同じように。
「ところで周知のように、遊戯は当時単なる余暇ではなく、共同体もしくは集団への参加の一形態であった。それは家族、隣人、各年代、各教区の対抗で行われていたのである。(LF)最後に、十六世紀になって、新しい画材が暦のなかに登場する。それは子供である。」(P.320)
「十六世紀のフランドルの最後の写本では、子供たちがはしゃぎまわっている。子供たちに向けられた芸術家たちの偏愛ぶりが窺われるのである。」(P.321)
「このようにして、一年の月々の続き絵に、女、隣人仲間、最後に子供という具合に当たらな人物が登場してくるのである。子供は、まだ正確には家庭生活とまではいかないにしても、身近な生活や一家団欒という、かつては認識されていなかった欲求に結びつけられるのである。(LF)十六世紀のあいだに、暦の月のこの図像記述は私たちの関心から見てきわめて有意義な最後の変遷を経ることになる。それは家庭的な性格をとるようになっていくのである。これはもう一つの伝統的アレゴリーの象徴主義である人生の諸時期に結合されて、家庭的になっていくことであろう。人生の諸時期を表現する方法はいくつかあったが、そのうち二つは他を圧していた。そのうちのひとつ、広く民衆の間に普及していた方は、版画の形式で存続していったのであるが、それは人生を出生時から成熟期までは上りに、ついで老齢期と死期までを下りにというピラミッド型の階段で表現するものである。偉大な画家たちは、このあまりにも素朴な構図を嫌った。そのかわりにかれらは通常、子供、青年 大概は夫婦 ならびに老人の形をかりて人生の三つの時期の表現につとめた。」(P.321)
「異なった世代が三つないしは四つの人生の諸時期を象徴しているような一つの家庭内に、それらをまとめようという考えはもたれていなかった。芸術家たち、そしてまたかれらが代弁している世論は、年代の個人主義的概念に忠実にとらわれていたのであり、すなわち同一の個人がその運命の異なる時々の姿に描かれていたのである。」(P.322)__核家族にはそれがない。個人主義が貫徹する。大きな家族は、毎日人生を観ている。
「もはやありえない死は描かれておらず、家族の意識という新しい意識が形象化されているのである。」(P.324)
「十六世紀から十七世紀にかけて、こうして迸り出る家族意識は子供期の意識と不可分である。私たちがこの本の最初に分析した子供機に向けられた関心は、このさらに普遍的な意識である家族意識の一つの型態、一つの個別の表現にすぎない。」(P.330)__普遍性ー>プラスチック・ワード。平和と開発。桃源郷とカッパと一緒にいた。
「現代の核家族は、中世末期に系族と財産の共有制度の傾向を弱めたと思われるある進化の結果生じたものであろう。」(P.331)
「十世紀には、夫も妻も各々に自分の相続財産を管理していたのであり、一言の相談もなく別々に取得し、かつ売却していたのである。」(P.331)__多分日本も。
「村落共同体は、農民においては貴族における系族の役割を演じていたと言えよう。(LF)十三世紀中に、状況はいま一度変転を見る。貨幣経済という新たな様式の出現や動産の拡大、取引の頻繁か、また同時に君主(カペー王朝の王もしくは大公国の首長)の権威ならびに公的保障の発達が、同一系族の人びとの連帯の緊密性ならびに家産の共有性の放棄を惹き起こしたのである。夫婦単位の家族は再び自立性を取り戻した。とはいえ、貴族階級では、十世紀にみられた連帯のゆるやかな家族に戻ることはなかった。父親は、十一世紀・十二世紀に共有の家産の統括を維持する必要性から賦与された権限を保持したばかりか、それを拡大さえした。他方、周知のように、中世末に端を発して、女の分限は絶えることなく減少していった。」(P.332)
「ジョルジュ・デュビィは次のように結論を下している。「実際、家族というものは、脅かされている個々人が国家の衰退の期間、庇護を求めてやって来る第一の避難所である。だが政治機関が十分な保障を可能にするとたちまちに、個人は家族的制約を避け、血の紐帯は緩和される。系族の歴史は、政治秩序の変化に応じて周期的に変わる、緊密と弛緩の連続なのである。」」(P.332)
「十四世紀に端を発して、近代的家族が形成されていくのが見られる。顕著なこの変化を、P・プトーは次のように明確に要約した。「十四世紀以後、家政における妻の地位が、漸次剥奪されていくのが見られる。妻は、不在の、あるいは気が狂った夫の代替を務める権利を失う・・・最終的には、十六世紀になると、既婚婦人は無能力者となり、そして彼女が夫もしくは司法による許可を得ずになす行為はいかなるものも、基本的に無効とされたようである。」(P.333)
「だが、実際には、聖別は婚姻をかろうじて合法的なものにしたくらいの意味しかもたなかった。結婚は長い期間にわたって、契約(諾成行為)としてなされていた。」(P.333)
「性的結合は、結婚によって祝福されたときに、罪であることをやめたのであり、それだけのことだったのである。」(P.334)
「肉体ばかりか家族にも結びついている自然的な制度が崇拝の対象になるためには、世俗的身分の復権が必要であった。家族意識の進歩と世俗の人間の地位が宗教的に向上していく進歩とは平行していた。なぜなら、近代的家族意識は 中世的な系族意識とは異なって 共通する信仰心の奥深く浸透していったからである。」(P.334)
「左手には介添の少年たちを伴った花婿が、右手には介添の少女たちを伴い冠を被った花嫁(とはいえまだ白い衣装ではない。愛を象徴する色は依然として祭服に使われる赤であ(FF)る)がおり、コルヌミューズ(風笛)の調べが流れて、一人の娘が花嫁の前に貨幣を投げている。」(P.334-335)
(聖ニコラ祭・クリスマス)「それはともかくとして、これはもはや大がかりな集団的な祝祭ではなく、一家団欒のなかでの家族的な祭りである。それがこのように家族に縮小されたことは、家族が子供たちを中心に凝縮することにつながっていく。家族の祭りは子供期の(FF)祭りになっていくのである。」(P.335-336)
(十七世紀のオランダ絵画、十八世紀のシャルダン)「図像記述上のテーマは、信仰心、子供期の意識(最年少の子供)、家族意識(食卓での集まり)という三つの情念の力を喚起して一つの統合体にまとめあげていた。食前の祈りは、いわゆる家族礼拝のモデルになっているのである。それ以前には私的な礼拝というものは存在しなかった。」(P.337)__Nota Bene!!。信仰(礼拝)は社会的(公的)なものであった。」(P.337)
「すなわち人びとは家族にたいして十分な価値を認識してはいなかったのである。同様に、この長い沈黙の時期に続く十五世紀、ことに十六世紀以降の図像記述の開花期にたいしても、家族意識の誕生とその発達という注目に値する意味を認めなければならない。この時を画して、家族は、秘めやかに息づいているばかりではなく、一つの価値として認識され、かつあらゆる情念の力によって高められるのである。」(P.340)
「この家族は、家族そのものとはいわないまでも、少なくともそれを描いて讃えたい人びとが望んだときに作りあげられた思想は、現代の私たちのそれに酷似しているように見える。その意識は同じものなのである。(LF)この家族意識はまた、子供期の意識としっかり結びついてもいる。」(P.340)
「エラスムスは、子供が家族を結合するのであり、親子が身体的に似ているということがこの深い結合を生み出しているという、あのきわめて近代的な思想をすでに有していた。こうしてみるとかれの結婚論が十八世紀になお版を重ねたことは驚くに値しないことだろう。」(P.341)__デジデリウス・エラスムス(Desiderius Erasmus Roterodamus,
1466年10月28日 -
1536年7月12日)は、
ネーデルラント出身の人文主義者
、カトリック
司祭、神学者、哲学者。
ギリシャ語新約聖書「公認本文」の著者。ラテン語名には出身地をつける当時の慣習から「
ロッテルダムのエラスムス」とも呼ばれる。なお、名前の「エラスムス」は洗礼名で
カトリック教会の
聖人である
フォルミアのエラスムス (Erasmus of Formiae) からとられているが、「デジデリウス」は1496年から自分自身で使い始めた名前である。
「この後は、親たちの生きた肖像たる子供によって目覚めさせられる情念こそが、とりわけ重視されていくのである。」(P.341)
第二章 中世の家族から現代の家族まで
「子供は実地で学んでいた。この時代だけでなくその後も長い期間にわたり、職業と私生活の間には境界がなかったのであるから、この実習は職業から一線を画するものではなかった。」(P.344)
「少年(garçon )という語は、十六世紀ならびに十七世紀の用語では、ごく若い男を指すと同時に若い奉公人を指していた。今日、それは喫茶店の給仕人の呼称として残っているのである。十五世紀・十六世紀以降に、家庭奉公の中味が下働きの奉公と高級な職務とにさらにはっきりと区別されるようになっても、食卓で給仕をするのはやはり家族の息子たちに落ち着くのであって、雇われた使用人にではない。育ちが良く見えるためには、今日のように食事作法を覚えるだけでは充分ではない。さらに食卓での給仕の仕方を覚える必要があったのである。」(P.344)
「こうした見習いによってある世代から次の世代へ直接に伝授がなされていた時代には、学校の占める余地はなかった。」(P.344)
「学校はじっさいに例外的なものだったのであり、それは後世になって徐々に普及して社会全体に拡まったのであるから、学校を通して中世の教育を記述するのは誤りであろうし、例外から慣例を作ることになろう。万人に共通な慣例は、見習修行だったのである。」(P.345)
「奉公は、貧乏な学生たちのばあい、学寮であたえられる給費に置きかえられていった。こうした給費生のための基金がアンシャン・レジーム期の学院の起源であることは、すでに見たとおりである。」(P.345)
「一般的なやり方では、ある世代から次の世代への伝授は、子供たちが大人の生活に日常的家族的に参加することで保証されていた。」(P.345)
「こうした状況のもとで、子供はごく早期に自分の生まれた家族のもとをはなれていたのであり、後に大人になってそこに戻ることがあったにしても、それも常にそうだとは限らなかったのである。したがって、この時代に家族は、親子の間で深い実存的な感情を培うことはできなかった。このことは、親たちがその子供を愛していなかったことを意味するのではなく、親たちは家庭の設立にあたって、共同作業におけるこうした子供たちの協力にたいするのに比べれば、自分たち自身にたいして、また子供たちがもたらす愛着にたいして、それほど意を払わなかったのである。家族は、感情的というよりはむしろ、道徳的かつ社会的な現実であった。非常に貧しい家族たちのばあい、家族とは、村落、農園、主人や領主の「邸の敷地」や「城館」など、より広い環境のなかで、夫婦が物質的な拠点をもっている以上のことではなかった。」(P.346)__子供たちだけ集める学校で社会や人生を学ぶことはありえない。彼らが学んでいるのは何なのか。究極的には文字だ。読み書き算盤だ。それを科学とか学問とかいう。
「それは教育者の側からの道徳的厳格さにたいする新たな要請、すなわち若者を生まれたばかりの無垢のなかにとどめておくために、大人たちの穢れた世界から隔離しようという配慮、あるいはまた大人たちの誘惑にたいし十分に抵抗するように若者を仕込もうという考えと符合するものであった。だがそれはまた、自分たちの子供をもっと身近で監視し、自分たちのもっと近くにとどまらせ、たとえ一時的であろうともはや他人の家族にはまかせない、という親たちの欲求にも一致していた。学校が見習奉公に置き替っていくことは、かつては分離されていた家族と子供たちの接近を、すなわち家族意識と子供期の意識の接近をも表明しているのである。」(P.347)__大人が穢れているという認識が、大人自身の変革ではなくて、子供(他者)への矯正(強制)につながっているのは西欧的。操作・支配・保護・変革。
「市の日になると、お金と食料が届けられる。生徒とその家族との間の絆が強まるのである。」(P.347)
「長子相続の慣行は十三世紀に、すでに系族の連帯が衰退し、反対に富の流動性が大きくなることによって脅かされ、家産の統合がもはや共有制度によっては保護されなくなり、細分化の危機が生じたとき、その危険を避けるために普及したように思われる。」(P.348)__「貧」の字は、相続によって財産「貝」を「分」けることによって生じる。
「じじつ、母乳が充分出なくなった場合に、乳児たちの教育にあたって生ずる支障を想像してみるがよい。牛乳に頼ろうというのだろうか。それは貧民の行うことであった。」(P.351)
「それではなぜ、とりわけ学級担任教師や下級官吏などのような小ブルジョワの家庭で、乳児を田舎に預ける習慣がみられたのであろうか。この比較的新しい手段を、私たちが子供に関して特別な関心を認めた他の諸現象とも引合にしうる保護手段、すなわちあえて言うならば衛生手段として解釈する必要はないだろうか。」(P.351)
「街路での生活、あるいは仕事、遊び、祈禱など共同体のなかでの生活が比重を占めるにつれて、こうした共同体は個人の時間ばかりかその精神までも占有するようになり、かれの感受性のなかで家族の占める場所は減少していく。反対に、もし仕事や隣近所、親戚のつきあいが枯れの意識に負担をかけることが少なくなり、かれを家族から遠ざけることをやめるならば、家族意識が忠誠や奉公などの他の意識に置き替わり、優勢に、ときには排他的なまでになっていく。家族意識の進展は、家が部外者にたいしてあまりに開かれている時には発展していない。それは最小限秘密を要求するからである。」(P.352)
「十七世紀の社会は、フランスでは、弱小なものたち、「特殊な貴族」が大貴族たちの下に組み込まれていく、階級化された保護関係の社会である。こうした集団の形成には、日常的かつ耳から口への感覚的な全体的関係のネットワークが必要であった。すなわち、私たちの言葉で具体的に言えば、想像を絶するほどの量にのぼる訪問や会話、会合、交流といったものである。物質的成功や社会的協約、相変わらず集団的な娯楽などは、今日のように分断された活動に区別されておらず、もとより職業生活、私生活、社交ないし社会生活の間に区別がなかった。本質的なことは、自分が生まれた集団総体と社会的関係を保つこと、ならびにこの網の目のような関係を巧妙に運用して自分の地位を高めることであった。成功するということは、富や地位を獲得することではなく、少なくともそうしたことは二次的なものである。それは何よりもまず、全構成員がほとんど毎日互いに目にし、耳にし、出会うひとつの社会の中で、少しでも名誉ある序列を手中にすることなのである。」(P.352)__Nota
「昇進は唯一、「名声」にかかっているのである。」(P.353)__日本の平安時代はどうだったか。同じだったかもしれない。
「こうした手引の忠言は、途方もなく瑣末主義に堕していく。」(P.353)__マニュアルの詳細化。文字文化の定め。
「「言わんとすることを頭の中で考える前に口に出してはならない」。」(P.353)__文字文化の影響。文字という言語の内面化。主体の明確化は、主体を客観視(外在化、文字化)することで生じる。
「「市民的」( civil )という言葉は、現在私たちが使っている「社会的」( social )という言葉とほぼ同義語だったのであり、「市民で(FF)あること」は「社会的であること」なのである。礼儀作法( civilité )という言葉は、今日、社会意識とでも理解されるものにほぼ該当するのであろうが、両者の相違はすでにきわめて大きい。」(P.357-358)
「十六世紀から十七世紀にかけて大きな変化も見せずに流布しているような礼儀作法集の起源は、かなり複雑である。それは非常に古い起源を持つ三つのジャンルに大別される。まず第一に、本来言うところの「クルトワジー」を説くもの。」(P.358)
「『バラ物語』は部分的には作法書なのであり、婦人たちに向けて、一種のコルセット(鯨のひげや金属製の胴なしのもの)の使用を推奨し、化粧や衛生、入念に剃り落としておかなければならない「ヴィーナスの家」の清潔さなどについて助言を与えている。」(P.358)__この頃はパイパンが主流。
「礼儀作法集の第二の起源は、中世に大カトーなる人物によって作られたとされる末期ラテン語格言集、カトーの二行詩のなかに含まれるような道徳的通念である。『バラ物語』のこれを引き合いにしている。」(P.358)
「礼儀作法集の第三の起源は、寵愛の技法ないし恋愛の技法で、(中略)『バラ物語』はこの種の典型的なものである。」(P.359)
「礼儀論、道徳律、恋愛術は、同じ結末に凝集している。それは、青年(時には婦人)に、万事が人との接触や遊戯と同様に重要なものである会話の中で行われる、社交を中心とした社会生活、すなわち僧房の外での唯一想像しうる生活形態を手ほどきすることである。(LF)このかなり複雑な錯綜した中世の文学は、十六世紀になると変貌し、単純化していった。そこから、礼儀作法集ならびに成功術ないしは「追従術」( courtisans )という二つの、根柢では似通っているものの形式上は異なったジャンルが引き出されていったのである。」(P.359)
(数種類の活字)「ローマ字体、イタリア字体、ゴシック字体のほか、筆記体もあり、これはこの種の本以外には印刷されることがなかったので、礼儀作法集の活字体とも呼ばれていた。これらの教育的目的は、礼儀作法の本に、絵のように美しい活字の体裁を備えることである。また数カ国後の本文が一度に、それぞれ異なった字体で縦に並べて印刷されることもあった。フランス語、ラテン語は言うに及ばず、イタリア語、スペイン語、ドイツ語も使われていた(英語は決して使用されなかったが、それは当時ごく少数の読者しか解さなかったからであり、文化的価値のない言語だったからである)。人びとはこれを使って、学院では教えられない生きた言語を学んでいたのであった。」(P.360)
(P.361)__ティッシュがないときに鼻をどうかんでいたのかを忘れている現代人。
(十八世紀)「他の面と同様、服装の面でも、一人だけかけ離れていることは反社会的な罪になるのである。決して自分自身の欲求を押しつけることなく、つねに仲間の欲求に歩を譲らなければならない。肉料理の準備が整い、手を洗い終わった時になって、書きものを頼んだり、尿瓶を要求してはならない。ぶっきらぼうであっても、慣れなれしくても、陰気であってもならない。奉公人たちに対しては相応しい威厳を保たねばならず(「尊大な」人びとは「絶えず自分の奉公人たちに向かって小言を言ったり叱りつけたりして、家族全員をいつまでも悩ますのである」)、街路にあっては、足どりは性急であっても遅すぎてもならず、通行人たちの注視を浴びてはならない。」(P.361)__街の作法。
「明らかに田舎じみた粗野な住民を教育の対象にしていたのであり、あらゆる種類の公権力と警察の管理のもとにおかれている今日の社会よりも、当時は作法の訓練が重要だったのである。国家が、学校、交通、軍務・・・など、個人の訓育にあたって作法に取って代わったのは、この後のことであった。また当時の人びとは、社会生活においては瑣事など存在しないという意識を抱いていたのであり、社会的伝達の行為さえもそれ自体が本質的なものだったのである。」(P.362)
「バルタザール・カスティリョーネの『宮廷人論』は、エラスムスが礼儀作法論の型を定着させたように、寵愛を得て成功する術という一つのジャンルを生み出したのである。それは行儀作法の手ほどきの範囲にとどまっていない点で、礼儀作法集とは区別される。」(P.362)
「この素材は、「野心と名誉」という二つの本質的な着想に還元することができる。野心も一つの価値なのである。」(P.363)
「この「出世」をどのようにして実現するのか。その唯一の方法は名声、評判である。」(P.363)
(M・ド・グルナイユ『礼儀正しい少年』)「「あゝ、名声を求めてのみ情熱を傾けるひと、偉大さを渇望している君よ、あらゆる人をして君を知らしめよ、だが誰一人として君を理解させてはならぬ。こうした手管をもってすれば、凡庸が偉大に見え、偉大が無限に、無限がそれ以上のものに見えるのである」。」(P.364)
「野心と出世というルネッサンスの理想は、宮廷人が教養ある紳士に、宮廷が世間に置き替えられると同時に消え去る。あまりにあけすけに富や威信を渇望することは、もはや上品なことではないのである。まさに中流を、上品な中庸を探し求めるという、騎士メレがその著作を通して培った新しい理想が台頭してくる。」(P.364)
「アンシャン・レジーム期の緊密な対人関係は、もろく、貧弱な世俗趣味に縮小されていくだろう。」(P.364)
「昔は慣例は成文化されていなかったとはいえ、尊重され真摯に扱われる点においては礼儀作法集に劣るものではなかった。十七世紀後半になると、礼儀作法集は、その伝統的側面を温存してはいるものの、徐々に教育的助言や生徒の行動などといった、大人を除外し子供だけを対象とする助言で占められるようになる。」(P.365)
「今や礼儀作法集は学校生活に大きな関心を向け、それに順応し、かつそれを拡張しているのである。これは学校が発展したことと、子供期が特殊化されてきたことから生じた結果である。」(P.365)
「これらの著作は、伝統的な礼儀作法集の抜粋のように見える会話や食卓での行儀作法に関する章を含んでいるとはいえ、両親にたいする警句という意識をもって書かれているのである。」(P.366)
「これらは、明らかに、伝統的な礼儀作法集とは大きな隔たりを感じさせる。というのも、大人の慣例を子供たちならびに無知な大人たちを対象に執筆することはもはや問題にならず、家族それ自体にその義務や責任を指示し、また子供たちにかんして実践のなかで助言を与えることが主題になっているからである。エラスムスの礼儀作法集と、クステルやヴァレの教育論との間に見られる相違は、他家での見習修業という中世の習慣が存続していた十五世紀末の家庭と、すでに子供を中心にして構成されていた十七世紀後半の家庭との間の距離に見合うものである。」(P.366)
「十九世紀とかぎらず今日もなお、少なくとも男たちはしばしばカフェに集まる。フランスの現代文明は、もしカフェにその地位を認めないならば、理解し難いほどなのであり、カフェはいついかなる時にも、習慣のように規則的にも利用可能な、人と会う唯一の場所である。イギリスではそれは、パブリック・ハウス、すなわちパブであろう。十六世紀ならびに十七世紀の社会は、カフェ抜きの社会であった。」(P.367)
「個人の家、もしくは少なくともそのうちのあるもの、すなわち田舎風であれ都会風であれ「大きな家」(グランド・メゾン)以外には、公的な場所はなかったのである。」(P.367)
「十七世紀ばかりでなく十五世紀、十六世紀においては、「大きな家」は常に多くの人々を居住させていて、「小さな家」(プチット・メゾン)よりも人口を密集させていた。」(P.367)
「「大きな家」は、ホテルという名前こそつけられていなかったが、各階にいくつもの室があり、通りや中庭ないし庭園に面していていくつかの窓が並んでいるものであった。そこの中だけで正真正銘の社会的グループが形成されていたのである。」(P.368)
(「大きな家」)「最初の近代的な家族は、こうした有力者たちの家族である。」(P.369)
「教育者のモラリストたちが書き残し、学院が増設されたのも、これらの家族のためである。これらの家族のためとは、このような家族が形成する集団全体、すなわち、夫婦単位の家族の他に親族は含まれず(族長的な家族形態は非常に稀であったはずである)、せいぜい何人かの独身の兄弟が一緒にいる程度で、他方、家中に奉公人たち、友人たち、被保護者などを抱えていた集団全体のためということである。」(P.369)
「要するに、客の来訪が、その家の生活を支配し、食事時間でさえも決定しているその応対は、ひとつの積極的な仕事のような観を呈していたのであった。」(P.369)
「台所以外はどの部屋も、とくに用途は定まっていなかったのであり、しばしば最も大きな室の暖炉(FF)で料理が作られてさえいたのである。」(P.369-370)
「人びとは多目的用との室のなかで暮らしていた。人びとはそこで食事をとっていたが、専用のテーブルを使用していたわけではない。まさしく「食堂用テーブル」などというものは存在していなかったのであるが、食事の時には、アブラハム・ボスの版画に見られるように、折り畳みの台にテーブル・クロスがかけられ、飾りつけられたのである。」(P.370)
「長いこと寝台もまた組み立て式であった。」(P.370)
(十七世紀)「組み立て式寝台が耐久家具へと変換したことは、疑いなく団欒の進展を示すものである。」(P.371)
「しかしながら寝台のある室は、寝台があるからといって寝室であるわけではなかった。それは公的な場所でもあった。それだからこそ、居住者の団欒を擁護するために、随意に開け閉めするカーテンで寝台を囲い込む必要もあってたである。というのも、当時はひとつの寝台に一人で寝るのは稀なことであって、もちろん自分の妻や、また同性の他人と一緒に寝るのが普通だったからである。」(P.371)
「とはいえ、世間の介入を拒否するものとしてではなく、社会の中心すなわちきわめて稠密な社会生活の団欒の中心として、すでに近代的な家族意識が生まれていたこれらの家族について、想像をめぐらさなければなるまい。それらを核としてその周囲に、外へ向かうに従って徐々にゆるやかになっていく、求心的な身分関係の環、すなわ(FF)ち親戚、友人、客、被保護者、債務者等々の環が同心円状に確立されていたのである。」(P.371-372)
「他者への「従属」状態にあるという事実は、後世になって見られるような屈辱的な性格を、まだとってはいなかった。人はほとんど常に誰かに「所属していた」のである。」(P.372)
「奉公人に賃金を支払ったのではなく、報いたのであり、その関係は公正なものであるよりも庇護や憐憫に基づくものであり、子供たちにたいして体験されているものと同一のものであった。」(P.373)
「歴史家たちは、かなり前から、国王は決して一人になることがないことを指摘してきた。だが事実は、十七世紀末までは、だれもが一人でいることはなかったのである。社会生活の密度が高かったことから孤立は不可能だったのであり、そしてまた、かなり長い間「個室」ないしは「執務室」の中に閉じこもることのできた者たちは、類い稀なる行為として褒めそやされたのだった。」(P.374)
「こうした社交によって、個人生活の機会が少なかったために、長い間、家族意識の形成が妨げられていたのである。」(P.374)
「伝統的な社交と新しい家族意識との結合は、田舎であれ都会であれ、貴族であれ庶民であれ、農民であれ職人であれ、有力者の家族という限られた家族の中でのみ生じたのであった。」(P.374)
「十八世紀以後、家族は社会とのあいだに距離をもち始め、絶え間なく拡大していく個人生活の枠外に社会を押し出すようになる。家族の構造も、世間に対する防衛という新たな配慮に応じるのである。」(P.374)__社会が「防御」しなければならないものとなる。多分「他者」も。
「住み心地の良さはこの時期に始まる、と言われてきたが、また同時に一家団欒、プライヴァシー、孤立も生じたのであり、住み心地の良さはこうした現象の一つの現われなのである。」(P.374)
「まず最初にブルジョワジーと貴族において、住居の各室がこのように用途ごとに分化していったことは、たしかに日常生活の最大の変化の一つである。それは孤立という新たな要請に対応するものなのである。」(P.375)
「人びとは、かつては公衆の面前で体面をとりつくろって暮らしていたのであり、あらゆることが口頭で、対話で伝えられていた。だがこの後、人びとは、社交生活、職業生活、私生活をそれぞれ分離させるのである。そしてそのそれぞれに、応接室、事務室、個室といった相応な部屋が割当てられるだろう。」(P.375)__個人も分裂した生き方をする。「建前と本音」、「パブリック」と「プライヴェート」等。個人の分裂には、個人の対象化(文字の影響)と、その分析(分割)がある。個人の確立と分裂は同じ。絶対的自己矛盾的統一。人は社会を作りながら、社会に適応するように生きていく。
「古い作法は、公共の場で体面を保って暮らす術であった。新しい礼儀(ポリテス)は、他人のプラヴァシーの厳守と尊重を義務づけている。道徳上強制されるところが変わったのである。」(P.375)
(一七六〇-一七八〇年、マルタンジュ将軍の手紙)「「マダム」のような旧い呼称は消失した。マルタンジュは妻に宛てて、「私の愛しいママン」「私の愛しい子」「私の愛しいひと」などと書いているのである。夫は妻に、子供たちが呼び慣わしているのと同じ呼称「ママン」を好んで用いる。」(P.376)
「愛称の使用がますます普及していくことは、家族間の親しみが一層大きくなっていくことや、また特に他人とは異なった呼び方をする必要性、つまり一層の内密な言語によって、親子の絆の強さと他人からわけ隔てる距離とを強調することに対応しているのである。」(P.376)__夏目漱石。他者との秘密の共有が関係を強くするという考え方の発生。
「この文通の中では、健康と衛生の問題が大きな位置を占めている。かつては人びとは、重病に頭を悩ますことはあったが、こうした気(FF)遣いを毎度口に出すことはなかったし、風邪や一過性の小さな病気を心配することはなかった。」(P.376-377)
「ほんの一世紀前に認められたような、子供を一人失ってもまた一人別な子供をもうければよいという希望で気を休めるということを、当時の人びとはもはや行うことはなかったのである。この小さな存在はかけがえの無いものであり、かれを失うことは取返しのつかぬことである。そして母親は、自分の子供たちにとりかこまれて喜びを見出すのであり、子供たちはもはや実在と非実在との中間の位置に属しているのではない。」(P.377)__「自己(自我)」の子供への投影。それを可愛がり、失うことを恐れること。家庭というミニチュア社会の尊重。
「健康と教育、これこそこの後の親たちの主要な心配事となるものである。」(P.378)
「十七世紀においては子供は、気晴らしの主人公でなければ、社会にあって家族の地位の向上を図るための結婚ならびに職業上の投機の道具であった。マルタンジュの書簡では、こうした配慮は副次的な地位に堕しており、教育的関心ははるかに無私無欲に見える。日々の悩みや喜びを分かち合うこのような子供たちと家族のあり方は、最も鮮明な意識の領域に到達するための基本的慣行から出現してきた。孤立することのうちに幸福を見出し、家族以外の社会の残りの部分には無関心なこうした親子のまとまりは、友人、顧客、奉公人たちにたえず介入され世間に開かれていた十七世紀の家族ではもはやない。それは近代的家族なのである。」(P.378)
「この後、十八世紀末には、子供たちの間の不平等は許容しがたい不正という様相を現してくるだろう。長子の権利を抑制していったのは習俗であって、市民憲章でも大革命でもない。」(P.379)
「中世末期から十六・十七世紀にかけて、子供は親にたいしひとつの地位を獲得していった。それは、子供を他人に委託する風習が盛んであった時代には、熱望してもかなわぬことだった。このように子供が家庭に戻ったことは大きなできごとであり、中世的家族と一線を画する主要な特徴を、十七世紀の家族に与えているのである。子供は日常生活に欠かせない要素となり、人びとはその教育や就職、将来を思いわずらう。子供はまだ社会機構全体の軸ではないが、以前と比べてはるかに重要な登場人物になるのである。とはいえ、この十七世紀の家族は近代的家族ではなく、社交に大きな比重を残していることで区別される。家族が存在しているところ、すなわち「大きな家」の中では、家族は社交関係の中枢であり、家長が命令を下す複雑で階層的な小社会の首都なのである。(LF)近代家族は、反対に、世間から切り離されており、孤立した親子からなる集団として社会に対立している。この集団の全エネルギーは、何らの集合的野心もなく、子供たち、ことに子供たちそれぞれの向上に費やされるのであり、家族というよりはむしろ子供たちが中心なのである。(LF)こうして、中世的家族が十七世紀的家族へ、そして近代的家族へと進化していくといっても、それは長いあいだ、貴族やブルジョワ、富裕な職人、富裕な勤労者に限られていた。十九世紀においてもなお、人口の大部分を占める最も貧しく最も人数の多い層は、中世的家族のような暮らしをしていたのであり、子供たちが親元に留まることはなかった。家とか「自宅」、家庭といった意識は、こうした人びとには存在していなかったのである。
結論 家族と社交性
「それは群衆であるが、現代の人口過密都市の雑踏の中での匿名の群衆ではなく、街路やあるいは(教会のような)公共の場所での隣人たちや善良な女たち、子供たちといった、数が多くても互いに顔見知りの人びとの集まりであり、今日のアラブ諸都市の(スークとよばれる)市場、あるいはまた、夕方の散歩どきの、地中海沿岸の諸都市の広場に活気を与えているものに酷似した親しげな雑然とした集まりである。」(P.380)
「事実上ほとんどいかなるプライヴァシーも存在せず、四六時中来客の無遠慮にさらされている家の中で、主人も奉公人も、子供も大人も、各自がそれぞれ混じって暮らしていた時代にあっては、このようなことで気を損なうことなどなかったのであろう。社会的に稠密であったために、家族の占める場所などなかったのである。家族というものが、生きられた実体として存在していなかったのだから、逆説ながら家族を認め得ないのである。家族は意識や価値としては存在していなかったのである。」(P.381)
「過去何世紀かの変革は、しばしば家族意識も含めて、社会的拘束に対する個人主義の勝利として言われてきた。夫婦のエネルギー全体が、自発的に数少なくしか作らない子孫の出世に向けられたこの近代的な生活にあって、いったいどこに個人主義が見えるのだろうか。個人主義はむしろ、アンシャン・レジーム期の家族の、多産な家系の快活な無関心の側にあるといえはしないだろうか。」(P.381)
「勝利を収めたのは個人主義なのではなく、家族なのである。」(P.381)
「家族意識と古い社交関係のあり方とは相容れないものであり、互いに他方を犠牲にすることでしか発展できなかった、と考える誘惑にかられるのである。」(P.382)
結論
「宮廷風(ないし貴人の)恋愛の神話は結婚を軽蔑するものであり、子供を他の家庭へ見習に出すという現実は、親と子どもとのあいだで感情上の絆を緩和していた。」(P.384)
「本質的なことは、中世文明が教育という観念をもたないでいたことである。」(P.384)
「私たちの世界は、子供についての生理的、道徳的、性的な諸問題に、強迫観念のようにつきまとわれている。(LF)中世の文明はこのような関心、配慮を知らないでいた。というのは中世文明にとって、大人に完全に庇護されている時期から、あるいはその少し後から、子供は大人の当然な仲間たるものにならねばならなかったゆえに、これらの問題は存在しなかったのである。新石器時代の年齢階級、ヘレニスム文化にあった教育(パイデイア)などは子供の世界と大人の世界のあいだの差異や移行を想定していたし、その移行は入門儀礼によって、あるいは教育のおかげで達成されるものであった。中世文化はこの差異を理解しないし、従ってこのような移行という観念をもたなかった。(LF)それゆえ、近世の初頭においての重要な出来事は、教育的配慮が再び出現したことである。この配慮は十五世紀にはいまだ稀であっ(FF)たが一部の教会、法曹界、学問の世界の人びとを動かし、十六世紀と十七世紀になるとしだいにその数も影響力を増し、宗教改革の支持者たちと合流するのである。それはかれらが人文主義者であるよりは、モラリストであったからである。人文学者たちは人生の期間全体にひろがる人間の教養ということに執着するにとどまっていて、子供たちだけを対象とする教育にはほとんど関心を払わなかった。」(P.384-385)
「家族は財産と姓名とを伝えていくようなたんなる私権の制度であることをやめ、道徳的かつ精神的な機能を主張するようになり、家族が魂と身体とを形成する。」(P.385)
「十八世紀以後に社会を支配していくことになる愛の感情がつきまとっている。感情生活のうちにこのように子供期のことが入っていくことが、今日ではマルサス主義としてよく知られている出産コントロールの現象を生じさせたことも、容易に理解される。この現象は、家族が子供を中心に再編成され、家族と社会とのあいだに私生活の壁が形成されるのが完了したまさにその時期に、出現したのである。(LF)近代の家族は、子供たちだけではなく、大人たちの大部分の時間と関心をも、共同の社会生活からひき戻していった。近代の家族は、親密さとアイデンティティの欲求に対応している。」(P.386)
「数世紀にわたる期間、同じ種類の遊びが、諸々の異なる身分の人びとのもとでも共通に行われてきた。近世の初頭以来、ある選別がそれらのあいだで生じたのである。一部の遊びは高貴な身分の人びとのために取り置かれ、他のものは子供と民衆のものとして放棄された。」(P.386)
「遊びと学校とは、どちらも初めは社会全体に共通のものであったが、それ以後は階級システムのうちに入っていく。これらはすべてあたかも、非常に拘束が多いが多様な側面をもつひとつの社会体が解体してしまい、家族という小社会からなる塵の集合によって、また階級というある大規模な集団によって、置きかえられたかのようである。」(P.387)
「人びとは際立った対照のうちで生活していた。高い身分の者、あるいは富裕者は貧民と隣りあわせでいたし、悪と徳、醜聞と献身も一緒くたに存在していた。」(P.387)
「親密さの探求と、それが生じさせた快適さへの新しい欲求(というのは親密さと快適さのあいだには密接な関係が存在するからである)は、民衆とブルジョワジーとの物質的な生活様(FF)式の対立を、いっそう強調していった。」(P.387-388)
「家族の感情、階級の感情、そしておそらく他のところでは人種の感情は、多様性にたいする同一の不寛容の表明として、画一性への同一の配慮の表明として、出現するのである。」(P.388)
訳者あとがき
マンテリテ( mentalité )
(右翼の人びと)「かれらは連続性を強調しその違いを過小にみようとし、アリエスがアルカイックなものをフランス社会からすでに失われたものとして語るのに反発していたのである。」(P.393)
「そのことはアリエスが以前から抱いてきた近世・近代を通じての家族モデルの変化への関心ともかかわっており、かれは近代的家族の形成を、古代的・地中海的な開放的で濃密な人間関係の結ばれ方( sociablité )の衰退との関係でとらえようと考えるに至った。この問題関心は『狂気の歴史』や『監獄の誕生』におけるミシェル・フーコーのそれと方向を同じくしている。」(P.393)
「いいかえると、近代の社会は、居住空間や市街の再構成と閉鎖的な近代的家族とによって、「温和な仕方でだが、権力の関係によって枠組がつくられてしまっている」。私生活化が管理の強化をともなうのはその理由によるのである。しかし、「私たちはわずかであるにせよ、(何者にも規定されていない)空白の余地を残したところで生活をすることが絶対に必要なのではないか」というアリエスの発言は、フーコーの関心と深くかかわっているし、『〈子供〉の誕生』が一九六〇年代のアメリカで歓迎されたことを説明していよう。」(P.394)
一九八〇年八月 訳者
<おわり>