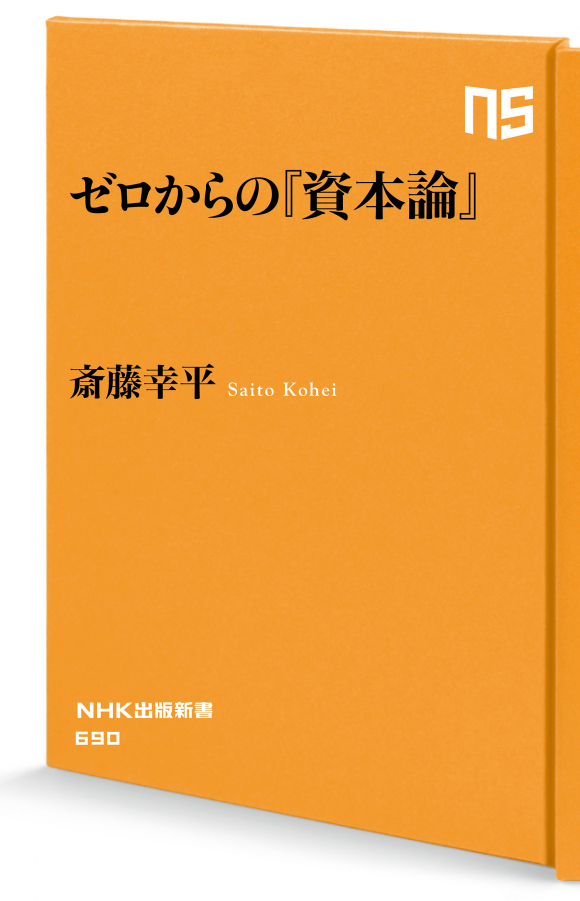
この本は、私を四十数年前に引き戻します。ちょっと辛いです。
マルクスの『資本論』が出版された当時から、数限りない批判書や解釈本がでてきました。そして「入門書」も。
いつからでしょうか。どんどん厚くなっていた「マニュアル」がだんだん薄くなってきて、その代わりに「入門書」がどんどんでてきました。「初心者でもわかる」「カンタン」「めっちゃやさしい」「誰でもわかる」などのキャッチコピーが入ったタイトルです。ひどいのでは「サルでもわかる」というのもありましたね。問題は「サルを馬鹿にしている」ということではなくて、「サルが(日本語を)わかっているか」どうかを「人間(日本人)がわからない」ということなのですが、多くの人が「自分はサルよりマシ」だと思っていたということです。
同じように、日本は「原始時代よりマシ」とか、「中国や北朝鮮よりマシ」とも思っていました。実際には「 made in Japan 」の商品は「 assembled in Japan 」になって、部品のほとんどは東アジアや東南アジアの「商品」に置き換わりました。そして、最近では「 made in China 」の商品を避けることが困難な状況です。
「自分のほうが上」「自分が一番」という意識がいつからあるのかはわかりません。少なくとも「自分」というものがなければなりませんから、「自分」をどうとらえるかによって意味が変わってきます。「自分で考えなさい」という言い方からもわかるように、日本語における「自分」は「 I 」も「 you 」も表します。近代的自我がデカルトから始まるとすれば、ヨーロッパにおいても「自分(私)」の意味は変わってきています。「自分が可愛い」とか「自分が良ければいい」という意味(感覚)も、決して「永遠不変」なものではなくて、時と場所によって違います。
本書は、「NHK100分de名著」において2021年1月・12月に放送された「カール・マルクス『資本論』」のテキストを底本として、加筆・修正し、新たに書き下ろした章を加えたものです。(本書、末尾)
「NHK100分de名著」というのもある意味で「入門番組」ですが、それをきっかけにして「名著」そのものを読まなければ、結構「指南役」の講師の捉え方(考え方)を「名著そのもの」と誤解してしまうこともあるでしょう。
50年前と比べて、今は「商品」と「物・財」とが同じような意味で使われるので、言うほどのことではないのですが一応言っておくと、「商品」には2つの価値があります。「使用価値(有用性)」と「価値(交換価値)」です。「食べられる」とか「飲める」とか「着れる」などの「使う価値」は必ずありますが、「1000円」などの価値はそれとは異なります。「お米1kg」の使用価値は、それが「1000円」だろうと「10000円」だろうと変わりません。去年からお米の価格が急上昇していますが、「お米そのもの(の使用価値)」が変わったわけではありません。自分の田んぼや畑で取れた米や野菜は、天候などによって豊作・不作はあっても、価格変動はありません。
私が子どもの頃、飲料水は「商品」ではなく、水道からタダで飲めるものでした。ペットボトルに入った水が「ミネラルウォーター」という「商品」として定着したのは、ここ30年くらいのことです。(P.27)
私は自動販売機で「お茶」が売られ始めたとき、それを「買う」のはとても馬鹿らしいことに思いました。お茶っ葉は「買う」ものでも、「お茶」は「自分でいれる」か「誰かが出してくれる」ものだったからです。
当時、東京がどうだったのかは知りませんが、私が住んでいた地域では「水道水」が「まずい」と感じたことはありませんでした。自然の「湧き水」はとても美味しかった記憶がありますが、だからといって「水道水」がまずいとは思わかなかったのです。
お茶っ葉と同じく、水道水も「タダ」ではありません。水道料金がかかる、ということでもありますが、それ以上に「税金」が投入されているからです。図書館も「タダ」で本が借りられますが、それも税金で賄われています。
これこそが、福祉国家の研究者であるイエスタ・エスピン=アンデルセンが「脱商品化」と呼んだ事態です。つまり、生活に必要な財(住宅、公園)やサービス(教育、医療、公共交通機関)が無償でアクセスできるようになればなるほど、脱商品化はすすんでいきます。これらの財やサービスは、必要とされる人に対して、市場で貨幣を使うことなく、直接に医療や教育といった形で現物給付されるわけです。(P.170)
そこでは誰が財を作り、誰がサービスをするのでしょうか。それらの人には「支払われない」のでしょうか。その支払は「税金」ではないのでしょうか。
(義務)教育、医療、自動車こそイヴァン・イリイチが批判したものです。それらは誰が作り、誰が利用し、誰が負担するかの問題ではありません。義務的・強制的に「儀礼」に参加すること。人々が「痛む技術(生きる技術)」を失うこと。「歩く技術・経験」を失うこと。コンビニができることやそこで商品を買うこと以前に、コンビニに行くまで「自動車」を使ってしまうことを批判したのです。財やサービスが「商品化されている」以前に、それらに依存していることを批判しているのです。
ウォシュレット(商品名)ができたのは、私がおとなになってからです。はじめは「高嶺の花」でしたが、今ではそれがないと排泄しにくくなった自分がいます。私の子どもたちが物心ついたときには、家のトイレは「洗浄機付きトイレ」でした。彼らはそれなしに排泄できるのでしょうか。
なぜ依存してしまうのでしょうか。イリイチはそれを「 scarcity (邦訳では”稀少性”)」と呼びました。
資本主義は、人工的に「希少性」を生み出し、人々の暮らしを貧しくするシステムといってもいいでしょう。(P.31)
著者の『人新世の「資本論」』ではもっと「希少性」が強調されていました。
貧相な生活を耐え忍ぶことを強いる緊縮のシステムは、人工的希少性に依拠した資本主義の方である。私たちは、十分に生産していないから貧しいのではなく、資本主義が希少性を本質とするから、貧しいのだ。これが「価値と使用価値の対立」である。(中略)資本主義の人工的希少性に対する対抗策が、〈コモン〉の復権による「ラディカルな潤沢さ」の再建である。これこそ、脱成長コミュニズムが目指す「反緊縮」なのだ。(『人新世の「資本論」』、P.268-269)
「生活に必要な財(住宅、公園)やサービス(教育、医療、公共交通機関)」は、「生活 life 」に必要なものですが、「生存 subsistence」に必要なものではありません。動物や植物はもちろんのこと、人類のほとんどの時代、そして現在の多くの地域では、それらの「財」は存在しません。なのに、それらは「必要 needs 」で、それらがなければ(単純にいえば商品・お金がなければ)「生きていけない」と思わせるのが「資本主義社会」です。
私が子供の頃には、毎日お風呂に入ったわけではありませんでした。記憶に自信がありませんが、「今日はお風呂沸かそうか」ということばがあった気がします。少なくとも私の家族が住んでいた公営アパートにはお風呂がありませんでした。お風呂がある家では、「お風呂を焚く(沸かす)」必要がありました。今のように蛇口を捻ったら「お湯」が出るわけではありませんですから。ライター、マッチの前はどうやって火を付けていたのでしょうか。
「火をつけることができない」というのが「富(豊かさ)の喪失」です。
資本主義の終わりなき運動は、一部の国の一部の人達が有利になるような独占的な形(=「大土地所有」)で、世界中を商品化していきます。グローバル化の結果、一国内の「都市と農村の対立」は、国境を超えて拡大していくのです。しかし、資本主義は価値の増殖を「無限」に求めますが、地球は「有限」です。資本は常にコストを「外部化」しますが、地球が有限である以上、「外部」も有限なのです。(P.137)
私のもっている本のほとんどは「古本」です。新本は高くて文庫本や新書でも買えません。私の街の古本屋はほとんど残っていません。「Bookoff」も店舗が無くなり、残った店舗も「古本」の面積はどんどん小さくなっています。私の子供はマンガが大好きですが、部屋にはマンガがほとんどありません。どうしてか訊くと、「ネット(デジタル書籍)で読んでるから」と答えました。なるほどね。「古本屋」が成り立つはずがありません。「古本」がないのですから。
「古本」「古着」などを売る店が多くなりました(多分)。ゴミとして捨てるよりもずっと「エコ(エコロジー)」です。買う方は「エコ(経済的、エコノミー)」ということになります。最近盛んにテレビCMをやっているのは、貴金属やブランドバッグなど「なんでも」買い取るという店です。私の家の近くにもできましたが、そこでは「販売」はしていません。買ったものはどうなるのでしょう。多分、「都市」で売られんでしょうね。地域の「財」が都市に流れているのです。買い取ったお金は地方に残ります。でも、そのお金はすぐに無くなるでしょう。都市で出来た「商品」を買うから、結局それも都市に行ってしまいます。
イリイチは南米で、資本(商品)がなだれ込んでいく姿を見ました。それは「開発」と呼ばれていました(それは「啓蒙」の変形です)。そこで「生きること」と「生活すること」が混同されていく姿を見みました。だからこそ「生きること subsistence 」を強調しなければならなかったのです。都市と農村(地方)との対立は、南北問題であり、環境問題であり、生存と生活の対立でもあります。
なぜマルクスは将来社会像を具体的に描かなかったのでしょうか。著者はこう言います。
ここには、そのような社会を具体的に想像するのが難しいという自明の理由がありますし、『資本論』が未完のままに終わってしまったという理由もあります。
けれども、別の理由もあります。それは、将来社会を想像する際に、現在の価値観や常識を無批判に投影してしまうというリスクがあるということ。つまり、今の社会の欲望とか、ジェンダー観とかをベースにして、将来社会の働き方や自由・平等を構想してしまうという誤りを犯す可能性がある。未来社会はその時々の人々が自分たち自身で作り出すものだと考えたから、マルクスはあえて具体的に描かなかったのです。(P.186)
私は生まれてから今まで、日本で(日本語で)生活してきました。自分では「常識人」だと思ってきました。「平等」や「民主主義」に反することに腹を立てる「価値観」をもって生きてきました。マルクスも少しは読んだし、労働組合にも関わりました。その間、ひとつの疑問をもっていました。「社会はこうあるべきだ」とどうして「私」が言えるのか、ということです。その疑問は、棚上げするしかありませんでした。分からなかったし、そこで立ち止まったら何にも出来ないと思っていたからです。
男女平等は「当然のこと」でしたが、それが「ジェンダー平等」と名前を変えたとき、「ジェンダーってなんだろう」と思いましたが、それも棚上げにしました。
定年退職してから、急に「老い」という問題がでてきました。それまでは「一日でも早く仕事をやめたい」としか思っていなかったからです。仕事(不自由・強制されること)は大嫌いだったし、仕事をすることが「他の人」のためになるとはどうしても思えなかったのです。自分が退職するまでは、「何の役にもたたない老人」をバカにしていたのですが、自分がそうなったわけです。
それまでは「正義」や「真理」とともに「自分」も「変わらないもの」だと思っていたのです。ところがそうじゃなかったのです。現実にわたしは「年を取って」いたわけです。「IDとパスワードを入力してくだい」と言われても思い出せないことも増えました。私は変わったのに「IDとパスワード」は変わらないのです。多分。
私はちゃんとマルクスを読んでいなかったのです。「弁証法」が「運動(変化)」だということを理解しようとしていなかったのです。
1970年代、日本で「アイデンティティ」という言葉が流行りました。そのままでは何のことか一般の人にはわからないので、「自己同一性」という漢字の訳語も当てられましたが、どちらも浸透しませんでした。明治以来、日本人(日本語)の欧米化は激しいのですが、それでもこの言葉がすんなり浸透するような「考え方」は成立していなかったのです。ところが、それが「 ID 」に変わった途端、それは「ことば」から「記号(符号)」に変わってしまいました。まさしく「サイン sign 」です。「印鑑文化」は「署名」が「サイン」になる前に「デジタルサイン」になってしまいましたが、「 ID 」とはまさしく識別記号です。国民総背番号制度は大きな抵抗をうけましたが、「マイナンバー」と呼び名が変わった途端に抵抗が少なくなったのと似ています。
私は「12桁の数字」になりました。そこにはわたしの「個性」のようなものはありません。わたしは「数字」として「情報(データ)」として処理されます。「平均寿命」(P.31)という統計で、私は1億2000万分の1として計算されます。私の「70歳」と誰かの「70歳」は同じでしょうか。違うんではないでしょうか。私(消費者)のもつ「100円」と、誰か(資本家)のもつ「100円」は同じでしょうか。マルクスは、そこにある違いを表現しました。
- W - G - W
と、
- G - W - G'
です。前者の「 G 」は、私(消費者、労働者)の持つお金(100円)です。後者の「 G 」は資本家の持つお金(100円)です。そうすると「商品( W )」の意味も変わってきます。前者における「 W 」は、多種多様な個別の商品です。後者の「 W 」は、一般的な商品です。その個性は資本には関係ありません。むしろ資本にとっては余計なものです。「 G - G' 」が理想なのです。「 G - W 」(買い)は簡単ですが、「 W - G 」(売り)は「命がけの飛躍」が必要ですから。どちらの「 G・W 」も実在としては同じです。ですが、前者は「使用価値」が優位(有意)です。いままでの話の流れで言えば前者は「生存」に対応します。後者は「価値」が優位(有意)です。「生活」に対応するといってもいいでしょう。「70歳の私」は前者の W です。「70歳の1人の老人」は後者の W です。
アイデンティティは「一般化された個人」です。それは後者に属します。これを著者は「「複雑さ」の破壊」と呼んでいます。
貨幣というのは、あらゆるものに値札をつけることで、すべてを比較可能で交換可能なものにしてしまいます。それは便利でもありますが、そのような単純化はしばしば極めて暴力的なものとなります。本来、比較不可能な富や使用価値を、価値という1つの抽象的な尺度で測ってしまうのですから。(P.138)
スーパーやデパートに行って、「どれを買おうかな」あるいは「何を買おうかな」と迷ったことはありませんか。そう思ったときに選んでいるのは「生活手段としての商品」です。「じゃがいもがほしい」と思って買いに行くとき、それは「生存手段としての商品」です。使用価値に対する欲求から始まっているからです。「お金がほしい」という欲求も使用価値に対する欲求ではありません。お金は食べられませんから。少なくとの直接的な(肉体的な、個人的な)欲求ではありません。
食べ物は作りすぎると腐ってしまいますし、いかに強欲な王も、巨大な宮廷を100も200も欲しがったりはしません。(P.35)
なぜこうした事態になるかというと、資本主義社会では「人間の欲求を満たす」ということよりも、「資本を増やす」こと自体が目的になっているからです。(P.37)
「人間」というのは前者の「 W 」なのでしょうか、後者の「 W 」なんでしょうか。「人間は、モノじゃない。その価値も測ることはできない」と言ってしまうと、冒頭のように「自分(人間)が一番」になってしまいます。「自分」は「 I ( ego )」と同じになってしまいます。
前述したように、商品に頼らずに生きていくことは、現代社会ではもはや不可能です。(P.51)
著者もウォシュレットがないと排泄できないのでしょうか。ライターがないと火が起こせないにしても、ウォシュレットがなくても排泄できる(やろうと思えばやれる)と思っていると思います。
どんどん記憶がなくなっていくような年齢になったので、昔のことはなかなかはっきりとは思い出せません。何をやっても三日坊主なので、日記をつけるのは小学校で諦めました。それでも私の中には「経験」があります。記憶という「知識」は失われても、「経験」は残ります。私の父母にも「経験」があり、私の祖父母にも「経験」がありました。それらの一部は「同じ時・同じ場所」で経験したものです。その時父母が何を言い、どう行動したのかは忘れても、なぜそうしたのかを「今の私」はいくらか想像することができます。私も父母も祖父母も資本主義経済の中で生きてきました。でも、「お金・商品がなければ生きてはいけない」という感覚は異なっていると思うのです。自分の畑も家すらもないところから始めた祖父母、戦後の「物がない時代」に生きた父母、高度成長の中で育った私は、それぞれ「物」や「お金」に感じることが違うのは当たり前です。
テレビ(CMばっかりだけど)の報道を否定するのは難しいのです。それは経験したことではない「知識( Wissenschaft、科学、学問 )」だからです。
ウォシュレットは、ウォシュレットがなくても、水洗便所でなくても、トイレットペーパーがなくても排泄できるということが基本になっています。医療は「自分が治癒する」ことがなくては成り立ちません。医者や薬はそれを「助ける」だけです。
輸送システムは、車まで歩いていき、そのドアを開けるための足が人びとにないかぎり機能しません。病院というシステムが意味をもつのは、人びとがいまなお、まったく他者に頼ることなくおこなう活動、すなわち生きるという活動に従事しているかぎりでの話しなのです。(イリイチ『生きる意味』、邦訳 P.359-360)
使用価値は、富の社会的形態がどんなものであるかにかかわりなく、富の素材的な内容をなしている。われわれが考察しようとする社会形態にあっては、それは同時に素材的な担い手になっている
交換価値の。(『資本論』第1巻 S.50、邦訳 大月書店 P.49)
生きること、食べること、痛むこと、学ぶこと、歩くことなどは「知識」ではありません。たとえ「知識」だとしても、そこには「生きてきた・生きている」という経験があります。経験できないことはたくさんあります。歩けない人もいるし、話せない人もいるでしょう。ただ、自動車、医療、教育などが成り立つのは、それ以前に「生きている経験・現実」があるからです。商品が成り立つのは「使用価値」があるからであるように。
商品(お金、ウォシュレット、トイレットペーパー、ミネラルウォーター、水道水、電気、自動車、医療、教育、あるいは図書館、公園・・・)がなくても生きていけるか、という問いはどこか「ズレ」ている気がします。それらがなくても生きていけるからそれらがある、からです。
ただ、井戸を掘る技術がないと水は飲めません。ライターなしに生きるためには火を起こす技術が必要です。それらは「経験」です。商品は、それらの技術を奪います。私の経験は知識で置き換えられます。私は私のからだから切り離され、他者から切り離され、「希少性を欲望する主体」としてのみ認められます。その私が「こうあるべき」「こうするべき」というのも、どこか「ズレ」ています。
つまり、私たちはみな、日常においてはコミュニストなのです。会社でも同僚を助けませんか?その意味で、資本主義でさえコミュニズムなしには成り立ちません。(P.214)
マルクスは資本主義に特徴的な、無計画の分業に基づいた商品生産のあり方を「私的労働」と呼んでいますが、そのような指摘労働をなくして賃労働を廃棄するのが、アソシエーション社会の目標です。
これは一見すると、分業が複雑化した現代社会においては実現不可能に思われるかもしれません。けれども、それが現実のものとなる余地は、ICT(情報通信技術)やアルゴリズムが発展している現代社会において、むしろ飛躍的に拡張していきます。(P.210-211)
ITなどの現代技術は、まさに「経験(言い換えれば時間と空間)」が「知識」に置き換わったものです。そして経験よりも知識を重要視(尊重)するのが現代社会です。使用価値と価値との関係と同じです。
たしかに、「人間」は「文化(伝統)」の中で生きています。他者に依存しない文化とは何んでしょうか。自分が自律していること、家族が自律していること、共同体が自律していること、「人間(人類)」が自律していること。「自律している」ためには「他者」が必要です。「自律」は「不可能」なのではなく、それは「他者」とセットで存在している(他者との関係性を基礎としている)だけです。
だからこそ、西ヨーロッパの資本主義がもたらした鉄道や電信などの果実を、ロシア社会がしっかりと取り込むことの重要性をマルクスは唱えたのでした。(P.220)
マルクスがそう唱えたのかどうか、今は確認する気はありませんが、なぜ取り込めなかったのでしょうか。何か「新しい技術」を取り込もうとするときに、常に抵抗があります。それが既得権益を持つ者の抵抗と言われることもあります。それともロシアには取り込むだけの資本がなかったのでしょうか。わかりません。ただ、その「抵抗」は「反動的」「保守的」なだけではないような気がします。私は年を取り、「セルフレジ」に抵抗があります。この間も同じ商品を二回スキャンしてしまって、店員さんを呼びました。この抵抗は、それが「私の経験」に反するものだからです。ですから、経験を重ねればその抵抗は薄れていくんだろうと思いますが、それは過去の経験を「なかったこと」にすることで、それで何かが失われているような気がします。「ICT(情報通信技術)やアルゴリズム」は、それに代わる何かが失われているのではないでしょうか。それは自分の経験や父母の経験、他者の経験を「なかったこと」してしまうのではないでしょうか。
新しい技術を取り込むこと自体への反感は、そこに根ざしています。むしろお互いの経験を「分かち合うこと conviviality 」、それこそが「コミュニズム」なのではないでしょうか。
[著者等]
著者について
東京大学准教授。1987年東京生まれ。ウェズリアン大学卒業、ベルリン自由大学哲学科修士課程・フンボルト大学哲学科博士課程修了。大阪市立大学准教授を経て現職。著書に『大洪水の前に――マルクスと惑星の物質代謝』(堀之内出版・角川ソフィア文庫)、『人新世の「資本論」』(集英社新書)、『ぼくはウーバーで捻挫し、山でシカと闘い、水俣で泣いた』(KADOKAWA)など。


