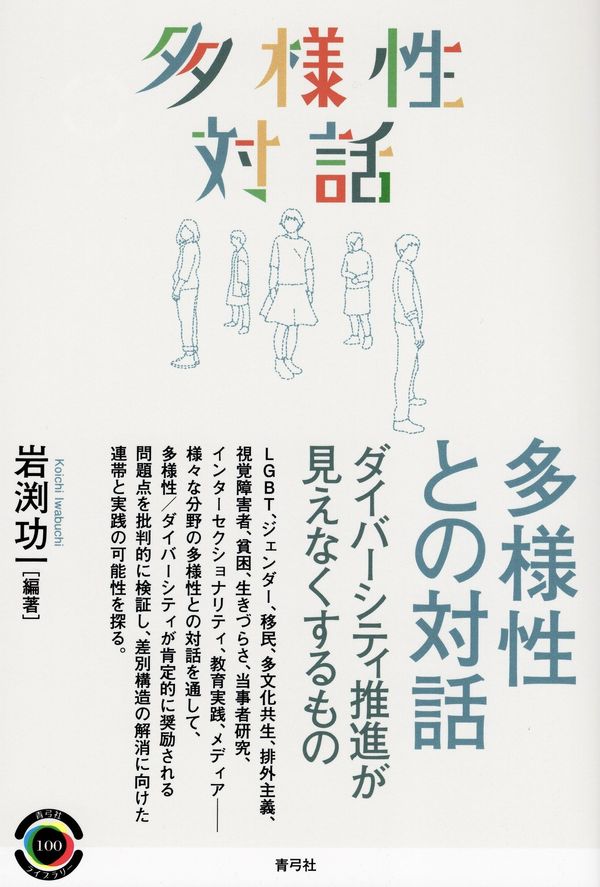
ラクマ914円(送料込み)。『最新アイヌ学がわかる 佐々木史郎、北原モコットゥナシ監修・執筆、 坂田美奈子・マーク・ハドソン著 』で引用されていたので読みました。
同書の感想にも書いたのですが、
167ページに「マイノリティ性・マイノリティ性チェック」図があります。
マジョリティ性 マイノリティ性
日本人 <> 非日本人(外国人)
高学歴 <> 低学歴
健常者 <> 障がい者
男性 <> 女性、ほか
異性愛者 <> 同性愛者、ほか
シスジェンダー<> トランスジェンダー、ほか
高所得 <> 低所得
大都市圏在住 <> 地方在住
私は日本人です。私は和民族です(多分)。一応大学を卒業しているので、高学歴です。健常者といえるかどうかはわかりません。病院には複数ヶ所通っていますが、障害者の認定は受けていません。男性です。異性愛者ですが、「愛」という言葉はわかりません。同性愛者ではありません。シスジェンダー・トランスジェンダーというのは「ジェンダー」という言葉の意味にもよりますが、シスジェンダーです。所得申告をしても所得税を払っていないほどの低所得者ですが、ヘビースモーカーだし(これはいまではマイノリティ?)ビールも飲むし、消費税も払っているので、高額納税者です。地方在住者です。
ほかにもいろいろな「マジョリティ性・マイノリティ性」の対は考えられるでしょう。私は「大人 < > 子供」を付け加えたいと思います。私は大人です。
カタカナ語が多いです。20年くらい前までは、「漢字が多い本」が「難しい本」でした。カタカナ語を原語に置き換え(ほとんどが英語)、漢字・ひらがなを「ローマ字」に置き換えれば、そのまま外国人にも読めそうなくらいです。10年くらい前でしょうか、「ダイバーシティ」という言葉を聞いたときには全くわからず「ダイバー(潜水)するシティ(都市)ってなんだろう?」と思いました。「バーチャル」なんて言葉は意味も調べずに使っていました。
本になるくらいなんだから、著者たちは勉強して分かっているんだと思うけど、読者は必ずしもそうではありません。少なくとも私はここにでてくるカタカナ語で抵抗なく「意味がわかる」ように思えるのはほんの一部分です。アルファベットの略語も同様です。
去年、「ジェンダー平等」に関する講演に出席させられたのですが、「私がおとなになるまでジェンダーという言葉はありませんでした。どういう意味ですか?」と質問すると、講師の大学教授に「その質問自体がアウトです」と言われました。分かっているんだから教えてくれてもいいのに。「多様性」あるいは「ダイバーシティ」って何?、と聞いても同じような答えが帰ってきたような気がします。確かに説明は難しいでしょう。
「ジェンダー gender」について、私の考えていることを書きます。「社会的性役割」と解説されたりしていますが、間違っているわけではないけど、その意味は誤解されていると思います。ジェンダーが日本で使われたのは「男性名詞・女性名詞・中性名詞」の「性(文法性)」としてです。御存知の通り、「男性名詞」は「生物学上のオス」とは違います。オス・メスがないもの(動植物以外には基本オス・メスはない)でも「男性名詞」がありますし、同じものが言語によっては「女性名詞」だったりします。フランス語で「genre ジャンル(古フランス語 gendre)」と言われるように、それは「種類」を指します。日本語の「性(さが、性質・性格などの性)」に近いかも知れません。「種(-)類」という単語もいろいろな意味があります。「人種」と「人類」という言葉が何を意味するのでしょう。genderはラテン語の「genus 」、ギリシャ語の「ゲノス γένος 」が語源とされます。印欧語根の接頭辞「gen-」は「命を与えること、子孫を作ること、繁殖・家族に関すること」に関係しています。接尾語「 -gen 」は「生成物」です(アレルゲンとか)。「生成(ゲネシス γένεσις )」は『エヴァンゲリオン』で有名になった気がしますが、これは日本語の「〜がなる(が生まれる)」と「〜になる(〜に変わる)」の両方の意味を持ちます。まさしく「生」と「成」です(「生」は、「生まれる born 」と「生きる live 」の意味があります)。
ラテン語の面白い例を一つ挙げます。
- sermō「会話」(男性名詞)
- lingua「舌, 言語」(女性名詞)
- verbum「言葉」(中性名詞)(Riku「no+e」より)
verbum は「 verbal (口頭で)」とか「 verb (動詞)」として英語に残っています。 lingua は「 language 」などとして残っています。 sermo は「説教 preach」ですが、それが現代英語の何に当たるのかはわかりません。speech? say? 英語(外国語)は苦手なので。
英語には名詞性(文法性)がなくなったと言われるけど、私の知る限り猫はオスでもメスでも「 she 」という代名詞で受けるし、犬は「 he 」で受けていました(今はそういうことがないのかなあ)。いずれにしても、文法性( gender )と生物学的性( sex )は同じようで違います。それは「文化の違い(ものの味方の違い)」です。万国共通( universal 普遍的)なものではありません。
先程書いた教授は、(さすがに申し訳ないと思ったのか)講演の最後に「ジェンダーはその人がどう生きたいかということです」と付け加えました。なるほど、とその時は思いました。
「男女平等」と言えば「戸籍(法)上の」(生物学上の、とは違う)性別の差別をなくすという意味で了解できます。「ジェンダー平等」は、本書に何度もでてくる「 LGBT/SOGI 」も含んだ概念でしょう。
(1)ここではLGBTとは Lesbian(レズビアン)、 Gay(ゲイ)、 Bisexual(バイセクシュアル)、 Transgender(トランスジェンダー)の四つのアイデンティティを指し、SOGIとは Sexual Orientation and Gender Identity (性的指向と性自認)を指す。(本書、P.53 注)
SOGI は教授のおっしゃった意味に近いですね。
この「アイデンティティ」も私が若い頃にはなかった言葉です。
エリク・エリクソンの心理学用語「アイデンティティ (ego) identity」の訳語として「自己同一性」とか「自我同一性」という訳語が使われたこともありますが、普及しませんでした。「私が私と同一であること」「私が私であること」なんて、「当たり前のこと」あるいは「証明しようのないもの」だと、私は思っていました。歳をとっても(時間が違っても)、状況(場所)が違っても「同じ私」はあるようなないような。
「忖度」という単語は昔からあったのでしょうが、私はおとなになるまで知りませんでした。
そん‐たく【忖度】
〘 名詞 〙 ( 「忖」も「度」もはかる意 ) 他人の心中やその考えなどを推しはかること。推量。推測。推察。(精選版 日本国語大辞典)
そん‐たく【×忖度】
[名](スル)他人の心をおしはかること。また、おしはかって相手に配慮すること。「作家の意図を忖度する」「得意先の意向を忖度して取り計らう」(デジタル大辞泉)
他人の心を推し量るというのは大切なことです。マスコミが「悪いこと」のように使ったのは、忖度した末の行動が、上司や権力者の得になり、それが自分の保身や利益になり、結果として他の多くの人の不利益になる、というような意味でしょう。それが「社会正義」に反するということです。その原因とされたのが「アイデンティティのなさという日本人の特徴(気質)」だった気がします。日本人の多くはどう思ったのでしょうか。「悪いことかも知れないけど、仕方ないんじゃない」と思ったに違いありません。その後も何も変わっていないことは「フジテレビ問題」でも明らかになりました。
私は「正義の味方(月光仮面)」「ヒーロー(鉄腕アトム)」「勧善懲悪物(水戸黄門)」を見ながら育ってきました。ヒーローは力を持っていますから、必ずといっていいほど勝ちます(勝つことが決まっている、連続物では勝たないと続かないし)。ただ、簡単には勝ちません。必ず挫けそうになったり、負けそうになったりします。「自己犠牲」も強いられます。その困難を乗り越えて勝つのがヒーローです。
「忠臣蔵」は江戸時代の話なので、近代の作品とも言えますが、そこでの「赤穂浪士」は自分のために戦ったのでしょうか。多分違うでしょう。月光仮面、鉄腕アトム、水戸黄門はどうでしょうか。私はそこに「エゴ・アイデンティティ(自我同一性)」はないと思うのです。
ちなみに私は無神論者で無宗教です。これはマジョリティでしょうか、マイノリティでしょうか(日本的にはマジョリティだけど世界的にはマイノリティ?)。新約聖書の「ルカによる福音書」に「善きサマリア人」という話があります。追いはぎに襲われて半殺しになったユダヤ人をユダヤ教の祭司やレビ人は見捨て(素通りし)、サマリア人が助けた、というイエスの譬え話です(「ルカによる福音書」10-30〜10-37)。この話に対してイバン・イリイチはこう言います。
あのサマリア人があのように行動するのは、彼の行為が善だからであって、この男を助けることができたり、できなかったりするからではありませんし、この男が医療介護を必要としているからでも、食物を必要としているからでもなく、その男が、自分がそのサマリア人であるとして言うのですが、わたしを必要としているからなのです。(『生きる希望』邦訳、P.375-376)
サマリア人は「いいことをしよう」としているわけでもないし、「助けることができる」と思っているわけでもありません。「自己犠牲」ですらありません。ただ単に「求められている」と思ったのです。なんか「忖度」と似ていませんか。つまりそこには「近代的自我」も「アイデンティティ」もないのです。少なくとも、イリイチは近代的自我を通す(近代的自我から見る)ことを避けて聖書を解釈しようとしています。
私は戦後民主教育で「自主的(自律的)」で「独立」した「主体性」を持つことを教わりました。すると「人助け」も「自己犠牲」すらも「自分のため」と見てしまいます(「情けは人の為ならず」?)。「自分のために人助けをすること」、これは「偽善」です。その強い自我は「アイデンティティ」なんて言葉では表現できません。それを「煩悩」という人もいるでしょうが、多分違います。それを「アイデンティティ」という言葉で簡単に表現できる人は、逆にうらやましいと思っています。
内容が多岐にわたっているので、章と「論点」に沿って書こうと思います。
この章は、全体の導入部で、各章をまとめながら本書の意図を岩渕さんの考えを踏まえて書いてあります。
二〇〇一年の九・一一アメリカ同時多発テロ事件以降、集団的な差異の過度な受け入れは社会を分断するとして多文化主義へのバックラッシょがいっそう高まるとともに、移民やエスニックマイノリティを、社会の支配的な規範と価値と共有する役立つ個人として社会に統合させる政策が進展した。そのなかで多様性/ダイバーシティ( diversity )は差異( difference )に代わって積極的に語られるようになる。(中略)この変化は市場の自由競争によって経済の最大効率化を目指す新自由主義の浸透が推し進めてもいて、多様性/ダイバーシティ推進は経済的な生産性を向上させる人的資源の管理として促進されるようになった。(P.15)
簡単に言えば(経済的に)プラスな(利益になる)のが多様性(ダイバーシティ)で、マイナスになれば差異(差別)だということです。物には必ず両面があります。
多様性/ダイバーシティの奨励をより建設的に前進させるためにも、多様性の包含をめぐる問題に真摯に向き合い、様々な経験に目を向け耳を傾けて、構造化・制度化された差別・不平等の複雑な作用を理解して、それを乗り越えていく方途を考え続けること、つまり、多様性と対話していくことが必要不可欠なのである。(P.20)
本書の主題ですね。
唐突かも知れませんが、デカルトの言葉を引用します。
最後に、われわれは談話をするために、われわれのあらゆる概念を、それを表現することばと結びつけ、それぞれの概念を必ずことばとともに記憶に託するものである。そして、あとになると、事物を思いだすよりも、言語を思いだすほうが容易であるから、われわれはいかなる事物についても、ことばの内容からまったく切り離せるほどに判明な概念をもつことがとうていできず、ほとんどすべての人々の思惟は、事物そのものよりもむしろ言葉をめぐって動いているのである。したがって彼らは、きわめてしばしば、理解してもいないことばに同意を与えるはめに陥るが、それは、彼らが、かつて自分はそのことばを理解したことがあるとか、だれかほかの正しく理解している人から聞いたことがあるとか、思いこんでいるからなのである。(デカルト『哲学の原理』Ⅰ、74、世界の名著22 P.367)
「ジェンダー」も「ダイバーシティ」もみんなが使っていると、「なんとなく分かっている」気になります。「男女(平等)」も「多様(性)」も「辞書」を調べることなく(最近は辞書を持っている人が少なくなってきているでしょう。ググることは当たり前になっていますが、それも面倒です)意味がわかると思っています。「男女」も「多様」も「平等」も「目に見え、手に触れることができる」ものではない「概念」ですが、「言葉が地についている」「経験している」という意味では、漢語よりもカタカナ語のほうが「より離れている」ような気がします。漢字が「表意文字」だからでしょうか。
「本(文字)を読む」つまり「ことば(体験)ではなく文字が前提となっている」こととも関連していますが、「理解してもいないことばに同意を与えるはめに陥」っていないかは常に考える必要があると思ます。
四元と千羽(元電通総研の四元正広と千羽ひとみ『ダイバーシティとマーケティング』・・・引用者)の主張に耳を傾けるなら、日本のLGBTマーケティング戦略の特徴として挙げられるのは、LGBTという特定の消費主体をあえて立ち上げることなく、LGBTの生き方や活動に賛同する支援者であるアーリーアダプターを含めてターゲットを緩く広くすることだといえる。(P.48)
「バリアフリー」なら自分の親や、自分の将来として思い浮かべ、「消費主体」になることができます。マイノリティについてはどうでしょうか。自分が将来「障害者(老齢)になるということ」とも、「身近に障害者がいるということ」とも違うのではないでしょうか。「自分がLGBTになる」「自分が外国人になる」というのはあまり考えません。カナダがアメリカの51番目の州になれば、「旧カナダ人」は「旧土人」になるかも知れませんが。
このように同性婚だけを取り上げても、多数決によってある人の婚姻の権利を認める/認めないという認識自体が誤っていて、その権利が憲法に保障されているのであれば、憲法に基づいて同性間の婚姻は認められるべきものになる。LGBT/SOGIの人権問題が多数決によって左右されるもので、それこそが民主主義だという四元と千羽の主張は危ういものである。(P.52)
「マジョリティ・マイノリティ」という問いは、その始めから「多数派による民主主義に対する問い」だと思います。アイデンティティも民主主義も「法 law 」も定着しているとは思えなかった戦後の義務教育で行われた「話し合いと多数決による決定」という「民主主義」の根幹に関わる問題なのです。
そのためにはやはり、彼・彼女らの日本における「移民」としてのシティズンシップを、公式に承認することが必要である。排外主義への歯止めになるオルタナティブな多文化共生理念・施策は、そこから構想されうるだろう。(P.65)
経済的利益にならなれば異人も受け入れるが、利益にならなければ排除する。それは現代日本に特徴的なことではありませんが、いつから始まったのでしょうか。「村八分」という日本文化(?)とは違うと思います。
シチズン(市民)とブルジョアの違いはよくわかりません。自分が「シティズン」だと思おうこと自体が、自分が「マジョリティ」だと思うことではないでしょうか。なぜなら「市民社会」だから。シティズンシップ(市民権、公民権、公民の身分)というのは、「よそ者」や「奴隷」ではないということですが(「身分」:ある意味では納税者であること)、「権 right 」というのは「法 law 」同様、自我(アイデンティティ)や「人間」(あるいは「自然」「神」)から発生してくるものですから、「シティズンシップ」は「市民性」とでもするべきかも知れません。でも「移民の市民性」と言ったら分けが分かりません。でも「移民のシティズンシップ」と書かれれば分かったような気がします。
つまり社会正義を構想する際、それは「誰」にとっての正義かという点、またその正義や「誰」は「いかに」決定されるのか、という点が重要だと(ナンシー・フレイザーは・・・引用者)主張する。このうち後者の「いかに」は、決定プロセスに誰がどのような形で関わるのか、という問いである。本性では、これを「誰による」と表記する。つまり本章で検討したいのは、「誰にとっての多文化共生か」と「誰による多文化共生か」という二つの問いである。
これら二つの「誰」をめぐる問いは、これまで様々な議論が繰り広げられてきた「多文化共生とは何(であるべき)か」に対するメタレベルの問いである。というのも「誰」に関わる問いは、「何」に関わる問いが問われる場自体を設定するからである。(P.73)
柄谷行人は、
失恋の傷から癒えることは、結局この女(男)を、たんに類(一般性)のなかの個としてみなすことであるから。(『探求Ⅱ』、講談社学術文庫 P.15)
と言いました。「男(女)なんで世界に何十億人もいるんだから」とは、失恋した友達を慰めるときの言葉です。「〇〇さん(固有名)」を「単なる一人の男(女)」とみなすことで失恋の傷から癒え、次の恋は「一人の男(女)」を「✗✗さん」と呼ぶ(あるいは命名する)ことで始まります。「✗✗さん」は「私にとって」「私が恋する男(女)」となります。
柄谷は単独性( singularity )と特殊性( particularity )を区別しています(同書、P.11)。この辺がわかりにくいのですが、柄谷はこの辺の関係を「〈概念〉…一般性(類) 特殊性(個)」という軸と、「〈観念〉…普遍性 単独性」という軸に整理しています(同書、P.150)。失恋と新たな恋は、「単独(固有)から普遍・普遍から単独(固有)」ということですね。
別の面から考えてみましょう。「何であるか」というのは、「そのものの本質(定義)」です。「ソクラテスは人間(あるいは障害者)である」という「主語(個物)+述語(形相・普遍・カテゴリー)」が定義です。ただし、これは逆にはなりません。「人間(あるいは障害者)はソクラテスである」というのは変です。
アリストテレスは、質料(ソクラテス)と形相(人間・障害者)が別々に存在するのではなく、「ソクラテスという人間(障害者)」が存在するのだといっています。つまり、「何であるか」と「何が存在するのか」は同じことなのです。それらを混同しているのではなく、分けれれないことを一生懸命説明します。「〇〇がある」というのは(それがあるかないかは)、その本質を定めなければならない(定義しなければならない)からです。
誰が定義するのでしょうか。プラトンはそれを「知者」と言ったりしますが、むしろ「(生成・消滅・変化する)個物とは別に不変なイデアとしてあらかじめある」と考えていたようです。アリストテレスがどう考えていたのかはわかりません。「ソクラテスが」とか「私(アリストテレス)が」とは考えていなかったような気がします。
誰にとっての問題か、誰が問題だと決めるのか。誰が決めるかによって「問題の有無」は左右されます。でもそこには「主体性」が設定されていると思います。「私はマイノリティである」「私は差別されている」「私はセクハラされている」ということを「主体性(自我)」抜きに考えることはできません。
共同体性を失い、個別化することで、だれもが「マイナー」という不安(あるいはリスク)を抱えています。つまり、障害者(病気の人)だけでなく、健常者(健康な人)もマイナーになりました。障害者に慈悲を感じてなどいられないのです。「ひとごと」ですらありません。みんなが特殊なのだから。
筆者が使っている「多文化共生」は何の訳なんでしょうか(あるいは外国語にするときには何と言うのでしょうか)。ググったら、「multicultural symbiosis、 multicultural coexistence」という英語がでてきました。私は「 con-vivial (宴会・共に生きる)」というイリイチの用語を思いだすのですが、意味は全然違います。
フーコーの「生権力の誕生 The birth of biopolitics 」やハーベイの「新自由主義の起源の概要 A brief of neoliberalism 」がでてきてとても興味深いです。
そして、家族主義が加わることでその「責任」の範囲画家拡大し、「自己」「自家」への責任だけで手いっぱいになり、シティズンシップの行使、つまり社会的なものを多様な人々とともに作ることへの参加が困難になる。(P.102)
新自由主義とナショなリスムが増幅しあい、個人主義は「自己責任」「自家責任」「自国責任」となります。
貧困を社会問題として可視化したうえで、一人ひとりの「生」が多様で社会的なものであること、そして「人間らしく生きる」ことは国籍などの諸条件にかかわらず、すべての人の権利(人権)であることをどのように社会の共通認識にしていくのか。(P.109)
著者は「新自由主義・保守主義ナショナリズム」のことをいっているようにも思えるし、「自由主義・ナショナリズム一般」のことをいっているようにも思えます。ひょっとしたら「人間一般」のことをいっているのかも知れません。「現代日本」に独特な問題でもあるかも知れません。
「何を見るか」「誰が見るか」とともに、「どこから見るか」ということも大切です。「事例(この章では生活保護言説)」を挙げると、「そこから」ものを見てしまいます。「現代日本」から「近代先進国」「人類一般」に視点を広げるとき、「現代日本(あるいは自分)」というフィルターを通して見ているということを忘れてはいけないと、私は最近思っています。「権利 right・人権 human right 」というのは何でしょうか。それらの西欧観念が「当然あるもの」「尊重されるべきもの」であるとしても、それを「現代-日本-語」から見ている限り「社会(日本?世界?)の共通認識」にはならないのではないでしょうか。
「国籍 nationality 」と「シティズンシップ」はどう関係しているのでしょうか。国籍の「国」は近代国家です。「お国ことば(方言)」の「国」ではないし、「お国」は「東京(江戸)や京都」などの大都会から見た「地方」を指します(東京・京都を指してもいいんだけど)。シティズンシップは都会から見た人間関係です。今は地方の人もテレビや本を「通して」東京からの視線を持っているでしょう。自分が標準語(共通語)で「本を書」いているという自覚を持たないと(常に問わないと)、ナショナリズムが忍び込みます。
メディアの画一的な生産現場と画一的なコンテンツという二つの問題は、資本主義がもたらした社会での支配・被支配の関係に基づいた広く社会的な文脈から議論し、ステレオタイプの再生産やコンテンツの平準化について批判的に議論をすべきなのだ。(P.119)
最近のドラマはおもしろいものが少ないですね。同じような主題や設定が何度も繰り返されます。同じクールでも、別のドラマで「闇バイト」や「ネット詐欺」が登場します。相変わらす「失敗しない医師」が登場し、「政治家」は賄賂を受け取り、「警察官」は「忖度」します。
〇〇ハラスメントや法令遵守(コンプライアンス)で、放送できる内容が制限され平準化(事なかれ主義)していきます。
つまり、現代社会では男性優位なマスメディアが情報空間を支配してきた時代とは異なり、サイバー空間の広がりによって女性やマイノリティを含む一般市民たちが手軽に意見を述べたり、表現活動を披露したりできるプラットフォームが存在している。それによって、マイノリティの活動は以前と比べて格段に可視化され、また活発化もしている。つまり情報媒体自体の多様化によって声の多様性が実現している、と考えられている。
しかしながら、他方で、サイバー空間は、特に女性にとってミソジニーを具現する惨酷な女性処罰の空間でもあることを忘れてはならない。(P.119-120)
つまり、AIを機能させるために学ばせる機械学習のデータ群は、前述のミソジニーやマイノリティへのヘイト的空間も含んだ、男性優位のネット空間から引き出されてくる可能性が高く、それを深層学習したAIを利用することによって、マイノリティ差別がさらに強化されるというのである。特に画像認識パターンを機械に学習させる深層学習は、ステレオタイプを再生産するだけでなく強化する恐れがある。AIの利用が社会に普及していくいま、データの公正性はいっそう問われるべき重要なテーマであり、対策に向けた不断の調査努力が必要である。」(P.120-121)
台風が来るのは「仕方がない」と考えるとしても、私が不思議なのは「交通事故(自動車、列車、飛行機)」の悲惨さが報道されるとき、「だから自動車(列車、飛行機)に乗らないようにしよう」と報道されないことです。マスメディア、サイバー空間(インターネット)自体を使わないためにはどうすればいいか、が検討されることは(ほとんど)ありません。それは「生きる条件」であり、進化の産物として「(自国の・現代文明の)よさ」として前提されています。それを前提にした上で、「悪いところ」「悪くなったところ」を修正しようとするのです。
それは宗教改革的文化論であり、その中心にあるのは宗教的進化論です。それは「考え方」「ものの見方」の問題であり、独特の文化です。ではどうすれば、その文化の中にいてそれを問うことができるのか。私はそれを知りたいのです。そしてそれは多分、その前提そのものを「疑う」ことによるしかないのではないでしょうか。
生きづらさという表現が使われるようになった背景として、私はかつて自著のなかで、以下の二点を挙げた。第一に、「問題の現れ方が個別化・複雑化していて、集合的な属性や状態では捉えきれなくなっている」こと(個人化)、第二に「特定の「漏れ落ちた人」だけでなく、すべての人が潜在的に問題を抱えるようになってきている」こと(リスク化)である。(P.126-127)
不登校を経験しても個人の裁量で不確実性を乗り切り「自立」を果たす可能性が生まれる傍らで、学校に適応してきた大学卒の者であっても、雇用不安に直面するリスクを抱えることになった。このような状況では、排除は「学校に行っている/行っていない」という状態によってではなく、個人が主観的に感じる生きづらさとしてしか表現できなくなる。
実際には、排除は個人に対してランダムに降りかかってくるのではなく、特定の集団のうえに色濃く表れる。(P.127)
結局「自己責任」(それを増幅する自家責任、自国責任)が向かう先は、「他者攻撃」か「自己死(自殺)」です。そこに至るまでは(至ったあとも)、誰もが「生きづらさ」を感じています。『なんで私が神説教』(日本テレビ)、とってもおもしろいです。生きづらさをかかえているDMに対する静先生の投稿「辛かったらいつでも逃げ出していいと思う。自分の人生なんだから好きなように生きるべきじゃないのかな?」。たしかに「生きるか死ぬか」を考えている人には前半しか見えないんだけど、後半の「生きるべき」というのに注目してほしかったな。「(音)声」として聞いたら、きっと後半が届いたんだろうけど、文字にすると後半が見えなくなるんじゃないかという気がします。文字は「言葉を表す」し「何度でも読める」と思われているけど、それは幻想です。
先週の「先生を続けていいかは生徒が決めることです」というセリフはどうなんでしょうね。先生が生徒を選んだり、生徒が先生を選んだり、親が子を選んだり、子が親を選んだり。まるで商品を選ぶようです。
「〈名前のない生きづらさ〉/〈名前のある生きづらさ〉」。名前をつける(命名する)とそれが存在するように思えます。「定義」と「存在」の混同(取り違え)です。命名するというのは「定義する」ことです。それは固有名をつけることとは違います。固有名には定義がありませんから(あってもいいんだけど)。「一般」が「普遍」化することです。アリストテレスが「実体は主語になって述語にならない」というとき、その実体(基体といってもいいけど)として想定されているのは定義される前の「ソクラテス(固有名)」なのではないでしょうか。
〈名前のない生きづらさ〉が定義されないのは、それが「その人独特のもの(固有名・単独性)」だからです。「病名」のように一般的な名前をつけるとき、その病気は「特殊」になります。それはその人独特のものではなくて、考察(科学)の対象となり、その人とは別の「存在(イデア)」であると取り違えられます。
アリストテレスがプラトンをあんなに批判したにも関わらず(そして西欧はアリストテレスを信奉してきたのにも関わらず)、見ているのは「イデア(普遍)」です。「神」の代わりに「科学」を置いただけなのです。
本を読んで「知る」のではない、あるいは「客体(対象)」として研究するのではない「当事者研究」。
当事者研究を始めとする対話的な場の実践は、矛盾や葛藤を含む渾沌とした当事者のニーズに言葉を与え、「私はこうしたい」と語ることを可能にすることで、当事者を支援される客体から支援を「使っていく」主体へと変化させる基盤になりうる。(P.141)
「客体」でいることの気持ち悪さ、「客体(お客さん、外部の者)」でいることの気楽さは何でしょうか。私は「主体」という言葉に、私が義務教育で受けた「自立(独立)した」「自主的」な個人という「胡散臭さ」を感じてしまいます。
本章の知見からいえるのは、そうした場合には、一つの運動の物語に多様な個人を押し込めることで統合をはかるよりも、個々の差異や違和感を積極的に表明できる場や関係性を生み出しつづけるプロセスのなかに、新たな連帯の形式を見いだしうる、ということである。それは、多様性と自由とを、分断と孤立ではなく、異なる他者との出会いや共生に向けて開いていくための一つの道だろう。(P.142)
それが「つながれなさを通じてつながる」(P.136)道なんだろうと、私も思います。そしてそれは「文(テクスト)」ではなくて「対話」でのみ可能になるのでしょう。
ただ、その分断と孤立が「自由と多様性」や「主体と客体」の日本型変種に根ざしていることには忘れてはいけないと思います。
〈女性〉というカテゴリーの同一性を問い直し、フェミニズムの政治に〈女性たち〉の複数性を意識的に取り込もうとすこのような観点を、一九八〇年代の終りにキンバリー・クレンショーは「インターセクショナリティ」と名づけた。(P.151-152)ここで提唱されているのは、黒人の経験のなかでもとりわけ黒人の女性の経験に、黒人女性の経験のなかでもとりわけ黒人のレズビアン女性の経験に、黒人のレズビアン女性の経験のなかでもとりわけ黒人のレズビアン障害女性の経験に、という具合に、いわばより周縁化された、より少数の集団へと焦点を絞り込み続ける作業
ではない。そうではなく、黒人の経験というときに視野から外されがちだった黒人女性の経験を、黒人の男性の経験とは異なる、しかしあくまで黒人の経験として取り扱うとを要請するのが、インターセクショナルな観点である。(P.156-157)
「黒人であること( A )」と「女性であること( B )」があり「黒人女性であること」を「 A ∩ B (共通集合・共通部分)」だとし、個人の経験を「 A ∩ B ∩ C ∩ D....」としていくと、結局は「定義だけの・実体のない孤立した個人」に、ライプニッツのモナドのようなものになります。それは固有名とは全く別物です。。広がりも(窓も)ない実体は、「存在ではない」のです。
黒人男性とは異なるものとして黒人であること、そして白人女性とは異なるものとして女性であることを経験する黒人女性は、〈黒人であること〉の男性中心主義的な同一性と、〈女性であること〉の白人中心主義な同一性との双方に疑問を投げかける。交差点の比喩は、縦に走る一本の道路と横に走るもう一本の道路、それぞれ独立した別々の二本の道路があるような印象を与えるかもしれない。けれども交差点の存在が示すのは、その二本の道路がそもそもバラバラに独立して存在しているわけではなかったということだ。(P.156)
道路を「直線」とみなし、その交点を「点」とみなす(名付ける)ことはできます。でも、広さのない点(ゼロ)をいくら集めても線(大きさのある存在)にはならないのです。
「黒人女性であること」は「黒人であること」と「女性であること」の和( A + B )でもないし、共通部分( A ∩ B )でもないのです。問題としているのは共通部分ではなくて、「同一性 identity 」そのものです。
つまり、トランスジェンダーにたいする差別に反対する論文でシスジェンダーの女性であるアーメッドが最初におこなうのは、自分はトランス女性の経験を共有してはいない、自分が経験してきたハンマーとトランス女性たちの存在を削ってきたハンマーとは同じではない、と確認することである。その確認のうえではじめて彼女は、双方が経験したハンマーの「類縁性」を見いだそうと試みるのであり、そしてそれこそがインターセクションナリティなのだ、と彼女はいう。(P.158)
inter - section 、切られたもの(限定されたもの、定義されたもの)どうしの接点、定義を無効化するようなその接点は「同一性」そのものの否定です。同じではないけど、全く違うわけでもありません。プラトンのイデアのもとにある西欧人には「同一性の否定」は困難です。「私が私であること」の否定だからです。プラトンはソクラテスの言葉を借りてこう言いました。
いや、そればかりか、そのようなもの〔決して同一状態にないもの〕は、何者によっても認識されえないことになるだろうね。なぜなら、認識しようとする者がそれに近寄った瞬間に、それはもう別のもので別の性質のものになっているので、それがどのようなものであるのか、あるいはどのような状態にあるかは、もはや認識されえないだろうからね。そして、いかなる認識も、それが認識しようとする対象がいかなる一定の性状をももたないならば、これを認識することはないだろうからねえ。(プラトン『クラテュロス』439,プラトン全集第2巻、P.168)
それで考えたのが「変化することのない実体としてのイデア」です。でもそれは今でいう「イデアル(理想的、空想的、観念的)」なものです。アリストテレスは「それは可能性(可能態、デュナミス)であり、現実(現実態、エネルゲイア)ではない」と言いましたが。
この現実態としての交差点は「アイデンティティ」ではなく「固有名としての私」です。それは「固有名としてのあなた」とは「似ているけど同じではない」のです。
連帯は、私たちがお互いの同じではない経験、同じではない壁、同じではない抵抗を互いに認めるところから、複数の「ハンマー」の同一性ではなく類縁性を見いだし獲得するところから、始まる。(P.161)
「同じでないことの連帯」(P.158)。これは「つながれなさを通じてつながる」(P.136)と同じなのでしょうか。どこか違う気がするのです。
「私」でも「あなた」でもないけど、「私とあなたに共通するもの以上」のもの、部分の集まり以上の全体、それが類縁性でしょう。全体を改めて「種」として定義すると、その種を包摂する「類」を想定します。「ぽち」と「たま」を「猫」と定義すると、それを種とする「動物」という「類」を想定しなければならないように。「黒人という形相(定義、エイドス)」「女性という形相(定義、エイドス)」との同一性を拒否し続けながら、類縁性を見つけ出そうとする、そこに「希望」を見いだすのです。
自分の歩みを押しとどめ存在を削り取る「ハンマー」の経験がほかのハンマーの経験の「自動的」な理解へと結び付かない以上、ハンマーの類縁性は意識的に獲得されなくてはならない「私たちはそれを手に入れるべく努力するのだ」。(P.160)
それは可能なのでしょうか。
私のマイノリティ性、たとえば「低所得の地方在住者」は、「低所得」と「地方在住」の交差点です。同様に、「大卒の日本人」というマジョリティ性も「大卒」と「日本人」の交差点です。そして「大卒・日本人」と「低所得・地方在住」は「まったく別のこと」であって「まったく交差していない」のでしょうか。例えばですけど、「大卒の地方在住の日本人」だから「低所得」でも生きていられる、なんてこじつけることだってできそうです。
イリイチの言葉を借りれば、獲得する未来を予測して努力し、それを「期待」するのではなく、
制度には未来がある・・・しかし人々には未来なんかない。人にあるのは希望だけだ(前出『生きる希望』邦訳、P.25)
現実(性・態)は「現在」にしかないのです。
論点3 みえない「特権」を可視化するダイバーシティ教育とは? 出口真紀子
差別には大きく分けて個人的差別、制度的・構造的差別、文化的差別の三種類が存在するが、個人だけを変えるのでは、制度的・構造的差別は撤廃できない。(P.172)
「制度」は古くからある言葉です。「 institution 」は「制度、法令、慣例、学会、協会」などの意味があります(weblio)。イリイチが言う「制度」は、
わたしがはじめの頃の本を数冊書いていた時、わたしはこの分水嶺(道具 tool の時代からシステム system の時代に変わったこと・・・引用者)に気づいていませんでした。そしてわたしは、わたしの本を真面目に読んでくれた何人かの善良な人々に対して、学校というシステムを学校という道具、あるいは医学の確立された制度をある装置として納得させてしまった点で、誤っていました。(前出『生きる希望』邦訳、P.145-146)
「はじめの頃の本」とは『脱学校の社会』(1971年)、『コンヴィヴィアリティのための道具』(1973年)、『脱病院化社会』(1975年)など、彼が「第二の分水嶺」と呼ぶ「1980年代」以前に書かれた本のことです。法を守れという法(あるいは制度を守れという制度)を作り始めることは、自己矛盾(無限ループ)です。制度や法はどんどん細分化され、複雑になっていきます。人は良心・正義の外在化としての法(制度)を守る(ごく一部の人は作る)ために生きざるを得なくなります。
そして、「構造 structure 」は、
すなわち、連続的で境界維持的、かつ多様に連関した諸部分の集合である「システム」と、それらの構成要素がある特定の時点でとる「構造」とを混同してはならない。構造にはシステムの「特殊化」としての側面があり、それだけに、要素、要素間関係の総体としての全体性、その目的性についても具体的なバリエーションを示すのである。すなわち、一定の命題を証明しようとする仮説は、これを構成する諸概念の論理的な整合関係としてある種の構造をもっているし、また、適応、生存を維持する生物有機体は、その諸器官の機能的な秩序関係として、いわゆる解剖学的・生理学的構造を有するわけである。(中野秀一郎「日本大百科全書(ニッポニカ) 」)
システムは「全体」であり、動的概念ですが、構造はその「一部」、静的概念です。つまり、「構造」は「システムのある断面」です。私が見ること(認識すること、あるいは作ること)ができるのは、「現実」であり「現在という断面」でしかありません。個人(あるいはアイデンティティ)にしても、文化にしても、同様です。「私が変われば世界は変る」。そうかも知れません。でも変えられるのは、「現在の個人・制度・構造・文化」であって、「未来」ではないのです。全体は部分の集合ではないからです。ソクラテスの言う通り、認識には有限の時間が必要ですから。
同時に筆者がとりわけ学生との関係性を通して抱いているのは、「共生」という言葉が、「道徳的に正し」く、「目指すべきもの」「そうならなくてはならないよきもの」として認識されているのではないかという感触である。そこでは、「共生」する「相手」としての「他者」の「異質性」(例えば”民族的マイノリティ”や”生活困窮者と名指されるような人々など)が過度に強調されることで、かえって「われわれ」の同質性が安定的なものとして意識される、というような発想や態度が発生しかねないのである。(P.177)
「われわれ」と「共生する相手としての〈他者〉」とを「別なもの」と「定義」し、そのなかに自らを置いて同一化することで、その「特殊性」がより「安定的(普遍的)」なものになってしまいます。
それ垣間見られるのは、例えば、いままでいわゆる「共生」の実践とは距離が遠かったり、逆に「支援するんだ!」といった気負いをもちすぎたりしていた学生たちが、学習支援の現場の子どもたちを「〇〇人の子」「〇〇な家庭の子」ではなく、ファーストネームやニックネームで呼ぶようになっていくプロセスである。(P.192-193)
つまり、実践によって、相手を「定義」や「種別(ジェンダー)」ではなく、固有名で呼ぶようになるということでしょう。
〈名前のない生きづらさ〉と〈名前のある生きづらさ〉と似ていますが、〈目に見えるマイノリティ〉と〈目に見えないマイノリティ〉があります。視覚障害者は、まさしく〈目が見えない〉わけです。「見えない」人に「見えたもの」を説明することができるのでしょうか。
いざ他者に説明するとなると、自分は目が見えているはずなのに、言葉で表現することができず、見えているにもかかわらず、見えていなかったのだなと感じた。(文学部現代社会学科二年・・・引用者)(P.209)
人によって見える見え方は異なるのだから、全盲の人にも弱視の人にも、それぞれの見え方があるのだろうと考えることができるようになった。(文学部現代社会学科二年・・・引用者)(P.210)
人間は五感しかありません。視覚を聴覚で説明すること、あるいは聴覚を視覚で説明することはとても難しいことです。特に視覚が重視されるようになった近代以降は、目に見えるもの(たとえそれが幻覚や夢であっても)が重要です(そしてこれは本がテクストとなったことと大きく関係していると私は考えています)。
視覚や嗅覚が味覚に大きく(あるいは完全に)影響することは明らかです。それらを分類した(部分として捉えた)とき、その全体性は失われます。それでも人は「見えたもの」を「見えない人(見えるけど見なかった人も含めて)」に一生懸命伝えようとします。自分が見たものを完全に伝えることができないことが分かっていても、どれだけもどかしくとも。
そしていくらかでも伝わったと感じたときに、とても嬉しく感じます。
社会が多様性を帯びていくことは、同時に社会がより複雑になっていくことでもある。(人間生活学部人間生活学科二年・・・引用者)(P.212)
社会は「単純」だったのでしょうか。そうかも知れませんが、その単純さですら、無限の要素から成り立っています。分割することで個々は単純化し、数は増えます。複雑さというのは、「複雑だ」と思わせられている、あるいは「単純化して思考することに慣れている」可能性はないのでしょうか。あるいは、その全体を理解しよう、伝えようと思ったときに、「複雑性」というのが生まれてくるのではないでしょうか。
批判は批判として有効です。でも批判のあとに具体策があるのかというと、ないことが多い。(P.226)
そうなんだけど、具体策がないから批判できないということでもないし、具体策だけ(実行だけ)を行なうということは、彼の運動のように体制を強化・継続することになり、マネジメントがマーケティングになってしまう気がします。
具体的な行動を取ろうと思うとき、そこに感じるのは「自分の能力のなさ(無能力感)」です。物理的な力や「お金」でしょう。
(禁欲的に養われた此処の感覚に対する渇望・・・引用者)この渇望は、テクノロジーで生産された今に対する関係にただようどうしようもない無能力の気分から生じています。(イリイチ『生きる希望』邦訳、P.306)
わたしが自分自身に、友人たちと共に、養いたいのは無能力感ではなく、無力感、あのユダヤ人とサマリア人の間にある今・此処を注意深く見守る態度を忘れない無力感です。(同、P.307)
「無能力感」は impotence 、「無力感」は powerlessness です。「今・此処」という感覚が、「(未来への)期待」にすり替えられています。計画し、予測してその結果を「期待する」こと、それが「道具の時代」であり、それが「システムの時代」に繋がっています。そして「(未来に)何かができる」と考えます。それは「制御できる」という思いであり、「支配できる」という「責任」と「期待」です。「できる・できない」ということではないのです。今・ここで「いくらかでも」話すことができること、伝えることができること、知ることができること。必要とすること、されること。そして無力であること。それが「希望」であるとイリイチは言いたいのではないでしょうか。
この本を読むのは、ひどく辛い作業でした。はじめに書いたように、私のマジョリティ性は高いのです。そしてそれに気づかないことを非難され、あるいは「そうであること」を否定されているように思えたのです。著者たちがそういうこと(非難・否定すること)に反対していることが十分にわかっていても、です。いや、分かっているからこそ辛いのです。マジョリティ性が高い私は、それを認めたくないのです。理解しようとしない自分がいるからです。だから、いろいろ考えました。
結局イリイチの力を借りたし、デカルトの「事物そのものよりもむしろ言葉をめぐって動いている」文章のほうが(つまり実践よりも理論的な文章のほうが)楽に読めてしまいました(「簡単だ」という意味ではありません)。
私自身の体験を話すのは恥ずかしいのですが、不特定多数の人はこの文章を読んでいないだろうし、家族すら読んでいないと思うので、まあ日記のようなものとして残しておきたいと思います。
性の話が中心になるし、今の日本では子供は親の性の話なんか聞きたくないと思うので、読まなくてよろしい。昔は(地方によって違うけど、戦前としておきましょう)長屋なんて一間(ひとま)の家が多く、子供部屋はもちろんのこと、寝室なんてありませんでしたから、ご飯を食べるのも、勉強するのも、寝るのも、セックス(以降、「性交」の意味です)するのも同じ部屋でした。「ウサギ小屋」とばかにされましたが、西欧だって多くの賃労働者の家はそうだったと思います。『ロミオとジュリエット』よろしく、「夜這い」も当たり前でした。それは慣習、あるいは制度としてあったのです。「秘密」はありましたが、「プライバシー」はありませんでした。西欧においてさえ、「プライバシー」というのは、「私たち(市民)」が王権に対抗するために考えた主張で、市民(ブルジョア)が「所有権」を主張し始めたときにできた言葉です。そして「私」は常に「私たち(市民)」のことでした。それが「エゴ」の「アイデンティティ」と結び付いたとき、今の「プライバシー」の概念(のようなもの)が出来上がりました。セックスは、邪魔されるのは嫌だけど、秘密にするものではありませんでした。もちろん、それを含めた関係性は自分や相手を取り巻く社会(共同体)に影響を与えますから、何をしてもいいわけではありません。他人の畑の野菜を突然(何の了解も慣習もなく)踏み荒らしてはいけないようなものです。王様(領主)はそういうことを度々やるので、それに対抗するのが「プライバシー(プライベート)」です。
戀 愛戀愛は唯性慾の詩的表現を受けたものである。少くとも詩的表現を受けない性慾は戀愛と呼ぶに價ひしない。(芥川龍之介『侏儒の言葉(遺稿)』岩波書店、旧全集第9巻、P.346、「青空文庫」にもあります)
私は性欲が強いほうだと思います。性欲、食欲、睡眠欲など、「欲」が「desire 」かどうか分かりませんが、まさしく「渇望」でした。異性は恋愛の対象である前に性欲の対象でした。残念なことに私はまったくモテませんでした。内気で、異性に触ることも、話すこともできませんでした。話そうとすると顔が真っ赤になって、何も話せなくなりました。それこそが、私が性欲の強い証拠だと思います。求める気持ちが強すぎで、何も行動を起こせないのです。
同じ異性愛者(シスジェンダー)というマジョリティでも体験(経験)は全く異なると思います。単に私が「変」だったのかも知れないし、たまたま私と気が合う異性が現れなかった(会う機会がなかった)だけなのかも知れませんが。
そこに「セクハラ」という言葉が登場してきました。「ハラスメント」なんて聞いたこともない単語です。手持ちの辞書を調べると「嫌がらせ」と書いてありました。そうかあ、と思ったのですが、どうもそういう意味では使われていないようでした。「 harass 」は他動詞です。「〇〇が✗✗を悩ませる(に嫌がらせをする)」、つまり〇〇(主体)は「意図」をもって✗✗(客体)に嫌がらせをする(能動)わけです。私が使っていた「嫌がらせ」はそういう意味です。主体(性)の存在を徹底的に信じる教育を受けてきたわけですから、能動態は主体が客体に自らの意思で働きかけるものだったのです。文部省の意図にもかかわらず、そう思っていた日本人は少数者だったのかも知れませんが。意図(動機、故意・未必の故意・過失)は犯罪( crime )の構成要件です。動機はそれの善悪(正しいか間違っているか、行為を認めるか認めないか)とは別に、第三者(それの代表が裁判長)が論理的に理解しうるものです(被害者にとっても同じです)。そこには加害者も被害者も裁判官も「人間(もしくは市民)」であるという共通点(同一性、あるいは連続性)が前提されています。すべてがわからないにしても、すべては認めないにしても、すべてが正しいと思わないとしても、そこには何か「同じもの」「つながり」があるからこそ犯罪は成立するのです。そしてその他の人も、有罪と考えるか無罪と考えるかとは別に、動機が明らかになることでホッとするのでしょう。どこか自分自身の中にも同じものがあると思うからかも知れません。ハラスメントは、加害者が何を意図したかではなくて、被害者がどう感じたかです。ここに加害者と被害者の間の同一性(連続性)はありません。行為という客観的事実だけが加害者と被害者を関係づけます。「辛かったらいつでも逃げ出していいと思う。」という文章が、結果として自殺に結びついたとしても、そこにはまだ加害者と被害者のつながりが(ねじれや誤解があったとしても)あります。でもはハラスメントは「つながりがないこと」こそが犯罪の構成要件なような気がするのです。ハラスメントが成立するためには「つながらないこと・つながりを拒否すること」が必要なのです。
人と関わる「不安」は「リスク」になります。マネジメントはマーケティングの視点でのみ認められます。「リスク」や「マーケティング」のみが強調されますが、それを支えているのは「不安」や「マネジメント」であることは隠されます。ハラスメントを支えているのも「つながりの存在」であることは見ようとしません。
異性と話ができない私はさらに混乱しました。いままでそんな状況があるとは思わなかったし、異性にも同性にも優しく接しようと思っていたし、それにどう対応していいのかも分かりません。分からないものには対応しようがないのです。
私の親の世代は、ちょうどお見合いと恋愛結婚の割合が逆転した世代でしょう。私は民主主義と自由恋愛は「当然のものだ」「そうしなければならないものだ」と日本が変化する、その真っ只中に育ったのです。
都市部と農村部ではだいぶ違うでしょうが、文部省が示した学校教育は同じです。それまでは恋愛と結婚と(多分セックスも)は別なものだったのです。そして結婚も出産も育児も個人ではなく「社会」が行っていました。もちろん反発する人もいましたが、「家制度」というものがありました。家制度は、もとからあったものを戦後に学者が西欧文化と比較して説明したものに過ぎませんが。家族もありませんでした。社会も society という意味ではありませんでした。「自由・平等・独立」をベースにした個人(近代自我)がないのですから、 society もないのです。「農村共同体 community 」というのとも共通点はあるでしょうが違います。
それは日本という地域に特有なものです。このその土地に特有な文化をイリイチは「ヴァナキュラーなもの」と名づけました。「ヴァナキュラー」とは古くからある言葉で「その家で採れた、作ったもの」というような意味です。私は「土着性」という日本語が近いと思っています。
結婚において「性・性格の相性」などは問われません。子供ができなければ「家」は養子をもらいます。離婚の条件にもなりました。性欲の強弱という相性も問われません。子供を作るのに性欲は必須の条件ではないですから。誰の子供であるか、ということさえ本質的な問題ではないのです。夫婦のいる「家」で生まれた子供はその夫婦の、つまりその家の子供なのです。母性愛というものがあったとしても、それは「個人の個人に対する愛情」というより、家や社会の子供に対する必要性なのです(サマリヤ人のように)。
性欲は、夜這いや売春という別の仕組みが補完していました。NTR(ねとり)・浮気は「異例なこと」ではなく、慣習というよりもむしろ「制度」と呼んでもいい存在でした(赤松啓介『非常民の民族文化』)。村落と都市部ではその表れ方が違ったようですが、性欲の強弱は結婚制度とは別の制度が補完していたのです。
補完制度が制限される(イリイチの言葉で言えば罪の犯罪化)と、子作り、出産、子育ては家制度のなかで解決されなければなりません。マイホーム主義(家族制度)や自由恋愛(恋愛結婚)はその補完物の代用としてできたものなのですが、その地盤(個人主義)がない日本ではいびつな形になっているのは、週刊誌やネットニュースが示しているとおりです。
男性、あるいは父親による「暴力、横暴、力ずく」な行為はありました。
家父長制(父権制、パターナリズム)は、父が権力を持っているということではなく、父の行動が社会という、うまく説明できないものの意思を伝えるものでした。そこには父の「私(個人・自我)」などというものは(ほとんど)なかったのです。司祭が神の言葉を伝えるように、父親は社会の声を伝えていたのです。父は社会・家の象徴でした。今の天皇と同じです。
家長は「家」を維持するのですが、むしろ属していたのは社会だといったほうがいいのではないでしょうか。
女性も出産育児、家事だけでなく家を維持する労働をしていました。そして、地域の女性に属していました。男性と女性が同じだったということではありません。それぞれに性役割(ジェンダー)がありました。男性と女性は着る服が違うように、立ち入ることができる場所、使う道具、触っていいものなどが厳格に決められていたようです。これをイリイチは「経済的セックス」に対する「ヴァナキュラーなジェンター」と呼んでいます。
たしかに生物学上の区別が作用をおよぼす可能性はあるだろう。しかし、ジェンダーにもとづく独自化は社会的に動機づけられており、限りなく多様である。それは社会的な基本法則である。くらしの経済における男女関係をいいあらわす共通分母、それは「非対称の相互補完性」、「両義的な対照補完性」である。(ウヴェ・ベルクゼン「補論 ディノザウルスの最後のあえぎイヴァン・イリイチのジェンダー論とは何か」、イリイチ『ジェンダー』岩波現代選書、P.411)
わかりにくいですね。異性をセックスの対象としてみている私には、より分からないのかも知れません。一応イリイチの言葉で補足しておきます。
ジェンダー同士のあいだの対照的補完性は、非対称的であると同時に両義的である。非対称性は、大きさ、価値、力、あるいは重さの不均等であることを意味しているが、両義性はそうではない。非対称は相対的な位置を指しているが、両義性は、二つのものが同じものとなって適合することのないという事実を指している。(『ジェンダー』、P.157-158)__ The complementarity between genders is both asymmetric and ambiguous. Asymmetry implies a disproortion of size or value or power or weight; ambiguity does not. Asymmetry indicates a relative position; ambiguity, the fact that the two do not congrruously fit. (原書、P.75)
男性と女性は「同じ」もの「わかり合える」ものでもないけど「補い合うもの」、と言ったら単純すぎて誤解を招くかも知れません。「共通する定義された性質」「同一性・同質性」ではなく、「違う(自分とは違う)」「分かり合えないけど類縁性はある」、「お互いがお互いを必要としされる」・・・、やっぱり説明できません。
セックスは、厳密な科学的枠組において研究することができるが、ジェンダーは謎に包まれ、非対称的な補完性を示す。暗喩のみが、ジェンダーを顕在化しうるものといえる。(イリイチ「フランス語版への序」『ジェンダー』P.ⅻ)
ジェンダーはヴァナキュラーなものですから、時代によっても、地域によっても同じではありません。また生物学上の、あるいは戸籍上の「性別」である必要もないのです。
子供ができない女性(妻)は家の役割を果たしていないのですから、追い出されることもあります。長男は家督を次ぐ役割がありました。次男以降は分家するか、本家にとどまって居候したり、家主を手伝ったりする役目でした。長男が家長の役目を果たせないなら、家督相続人になることもあります。個人よりも役割があって、それに個人がはめ込まれるとも言えます。これが社会的性役割、ジェンダーです。身体(肉体)という枠組みがあって、そこに精神があるように。プラトンは枠組みと中身を別に考えたけど、アリストテレスは一緒にしか存在しないと言い直したのでした。西田幾多郎はそれを「限定」という言葉で表現したと思います。
しかしヘーゲルなどのいったように、真の個人性というのは一般性を離れて存するものではない、一般性の限定せられたもの、 bestimmte Allgemeinheit が個人性となるのである。一般的なるものは具体的なるものの精神である。(西田幾多郎『善の研究』日本の名著、P.214)
ソクラテスの哲學もギリシャ時代に於て懐疑的自覺の立場に於て始まり、自己自身を限定する實在の原理はプラトンのイデヤに於て把握せられた。しかしギリシャのポリス的世界の時代に於ては、いまだ眞の個人的自覺と云ふものはなかつた。それは働くものの世界ではなかつた。(西田幾多郎「四 デカルト哲學について」『哲学論文集 第六』旧全集第十一巻、P.156)
個人はその役割をこなせばいいだけで、それ以外のことをさせないように采配するのが家長の役割でした。封建時代は身分制度で、農民やその妻や子供が耐えられないような生活をしていたというのははっきり言って嘘です。現代社会のフィルターを通して過去を見ているだけです。過去をどう見るかによって、その時の「現在」がどのくらい「生きづらいか」がわかるような気がします。寒い地方に住む人を見て「寒いだろうな」と思い、暑い地方に住む人を見て「暑いだろうな」と思うのと同じです。
男が年齢(だけじゃないけど)を基準として男組・若者組・子供組などを作っていたように、女性は女衆を作っていて、自分たちの役目(今なら権利)と言われるものを守るために男衆と対抗(対立)することもありました。もちろん普段はそんなことはありませんでしたが。
どの道具が女性のもので男性が触れてはいけないかというのは厳密に決められていました。それは「差別」ではなくて「きまり・掟」です。女性が子供を生むのも「きまり」です。差別ではありません。
男性の力仕事は、機械によって女性や子供でも行えるようになりました。労働そのものは男性・女性に関わらずできます。できるけどあえてしないことで、掟が守られていたのです。掟(ジェンダー)を破棄することで、売春や出産以外の性差は経済セックスとなりました(売春する・男性と関係するのは女性とは限らないのですが)。「男・女という種(種差・ジャンル)」は「人間という類(人類)」を設定することによって平等(同じ)だということになったのです。その「後」で「人類」に種差を持ち込むことで「人種」ができました。
民主主義が「実現しなければならないもの」であるのとまったく同様に、恋愛は「しなければならない(しなければ一人前ではない)もの」でした。自由で独立した主体的な個人として。
そして私の現実はそうではなかったのです。「叶わなかった」とも言えます。しかしそれは「自己責任」でした。そうなるように(星飛雄馬のように)努力しない自分が悪いのです。
性欲に注目したフロイトは、理解できないけど魅力的でした。「性が抑圧されている」というウィルヘルム・ライヒの本にはホッとしました。性は解放しなければならないものでした。「生権力」というフーコーの本もさっぱり分からなかったけど、私の味方のように思いました。
「抑圧・搾取されている労働者を解放しなければならない」という思いで労働組合運動もやりました。「自由・平等」という立場では男女平等も目指しました。でも、男女平等は「ジェンダー平等」に変わってしまいました。
その頃はもう、毎日毎日新しいカタカナ語が現れて、辞書を引く前に(辞書には載ってなかっただろうけど)新たなカタカナ語が専門家によって、そしてマスコミによってばらまかれました。一つの単語すら理解する前に、です。
それらのカタカナ語は、日本語になることもなく「空虚なまま」で流通していますから、評価や批判されることも難しいのです。それらの言葉は「知ったふり」をして、時には自分で使わなければなりませんでした。
退職して時間ができたので、いくらか調べようとしたのですが、その説明のほうが難しいのです。それはそうです。いままで日本語になかった考え方(ものの見方)から出てきた言葉だからです。
本当に日本語でわかろうとすれば、古典ギリシャまで遡り、中世におけるキリスト教(ラテン語)的変遷を知り、近代における科学的(論理・理論的)広がりを見、コンピューター(システム)における使い方まで知らなければ理解できないのです(私は体質的に外国語が苦手です。心が拒否してしまいます)。その上、それまで知っていると思っていた日本語(あるいは漢語)すら、ちゃんと分かっていないことが分かってきました。かといって「やまとことば」すらまったく身についていません。逆にどんどん自分の使っている言葉がわからなくなっていきます。
専門家は「当然のこと」「すでに/つねに認められたもの」のように話します。それまでの日本がそうだったように(仏教や中国文化を受け入れたように)、西欧の受け売りです。学者と言われる人は、西欧的思考(見方)で理解していた(している)んだろうと思いますが、それを西欧的思考がない人に分かりやすく伝えることができるのでしょうか。英語がわからない人に英語で説明することや、視覚障害者に絵を説明しようとするのと同じなのではないでしょうか。伝わらないわけじゃないけど、自分の考えを「そのまま」つまり「丸ごと」伝えることはできないと思うのです。「必ず伝わるはずだ、同じ人間なんだから」と思うこと自体が近代西欧的な、特殊歴史的な、いわばヴァナキュラーな考え方(ものの見方)なのだと思います。
結局、私の体験は書けませんでした。それでも何も書かないよりはマシだと思いたいのです。それくらいの希望は私も持ってもいいのかな、と思いますが、残念ながら未だにその希望も持てません。
[著者等]
※執筆者(以下、執筆順)
岩渕功一/新ヶ江章友/塩原良和/髙谷 幸/河合優子/林 香里/貴戸理恵/清水晶子/出口真紀子/小ヶ谷千穂/村田麻里子/松中権(インタビュー)
岩渕 功一(イワブチ コウイチ)
関西学院大学社会学部教授。専攻はメディア・文化研究。著書にResilient Borders and Cultural Diversity(Lexington Books)、『トランスナショナル・ジャパン』(岩波書店)、編著書に『〈ハーフ〉とは誰か』(青弓社)など。
LGBT、ジェンダー、移民、多文化共生、視覚障害者、貧困、生きづらさ、当事者研究、インターセクショナリティ、教育実践――様々な分野の多様性との対話を通して、それらが抱える問題点を批判的に検証し、差別構造の解消に向けた連帯と実践の可能性を探る。
解説
多様性の時代だと言われる。多様な背景をもつ人材の活用が革新的な創造性を高めるとして、企業、政府、地方自治体、教育機関、NGO/NPO、市民団体で多様性/ダイバーシティを奨励する動きが活発化している。
多様性/ダイバーシティの推進は女性、LGBT、障害者などの社会的なマイノリティの存在に目を向ける一方で、有用で受け入れやすい差異を選別化することで、いまだ続く差別・不平等を見えなくするとともに、新たな包摂と排除を生み出してもいる。
多様性/ダイバーシティの推進により建設的に取り組むには、構造化・制度化された差別・不平等の複雑な作用を理解して、様々な差異を平等に包含する方途を考え続けること、つまり、多様性と対話することが必要不可欠である。
LGBT、ジェンダー、移民、多文化共生、視覚障害者、貧困、生きづらさ、当事者研究、インターセクショナリティ、教育実践――様々な分野の多様性との対話を通して、それらが抱える問題点を批判的に検証し、差別構造の解消に向けた連帯と実践の可能性を探る。
目次
第1章 多様性との対話 岩渕功一
1 BLMとD&Iの取り違え
2 「多様性/ダイバーシティ推進」が見えなくするもの
3 日本での多様性/ダイバーシティ推進
4 多様性との対話
5 誰もが生きやすい社会に向けた横断的連携
6 インターセクショナリティと連帯の可能性
7 学び(捨て)の実践
第2章 ダイバーシティ推進とLGBT/SOGIのゆくえ――市場化される社会運動 新ヶ江章友
1 ダイバーシティ推進とは何か
2 経営学におけるダイバーシティ・マネジメントとは何か
3 ダイバーシティ・マーケティングとLGBT/SOGI
4 LGBTマーケティングと人権問題への意識
論点1 多文化共生がヘイトを超えるために 塩原良和
第3章 移民・多様性・民主主義――誰による、誰にとっての多文化共生か 髙谷 幸
1 多文化共生をめぐるこれまでの批判
2 多文化共生をめぐる問い――「何」から「誰」へ
3 誰にとっての多文化共生か
4 移民にとっての多文化共生か、地域にとっての多文化共生か
5 誰による多文化共生か
第4章 生活保護言説における「日本人」と「外国人」を架橋する 河合優子
1 生活保護制度の歴史と現状
2 生活保護言説と「日本人」
3 生活保護言説と「外国人」
論点2 メディア研究における「ダイバーシティ」の現在 林 香里
第5章 「生きづらさからの当事者研究会」の事例にみる排除の多様性と連帯の可能性 貴戸理恵
1 「個人化・リスク化した排除の苦しみ」としての生きづらさ
2 当事者研究での個別性・多様性と共同性のつながり
3 多様性に立脚したつながりとは何か
第6章 「同じ女性」ではないことの希望――フェミニズムとインターセクショナリティ 清水晶子
1 「#トランス女性は女性です」
2 インターセクショナリティ
3 「交差」の誤解
4 同じではないことの連帯
論点3 みえない「特権」を可視化するダイバーシティ教育とは? 出口真紀子
第7章 共生を学び捨てる――多様性の実践に向けて 小ヶ谷千穂
1 「共生のフィールドワーク」という授業について
2 体当たりの邂逅――「正しい共生」のプレッシャーからの解放?
3 距離をとられる、という経験――自らのまなざしに気づく
4 ミックス・ルーツの学生の経験――自分自身を問い直す
第8章 アート/ミュージアムが開く多様性への意識 村田麻里子
1 多様性の砦としてのアート/ミュージアム
2 多様性の奨励とその課題
3 アート/ミュージアム実践が投げかける問い
論点4 批判にとどまらず具体的に実践すること 松中 権[インタビュー聞き手:岩渕功一]
あとがき 岩渕功一


