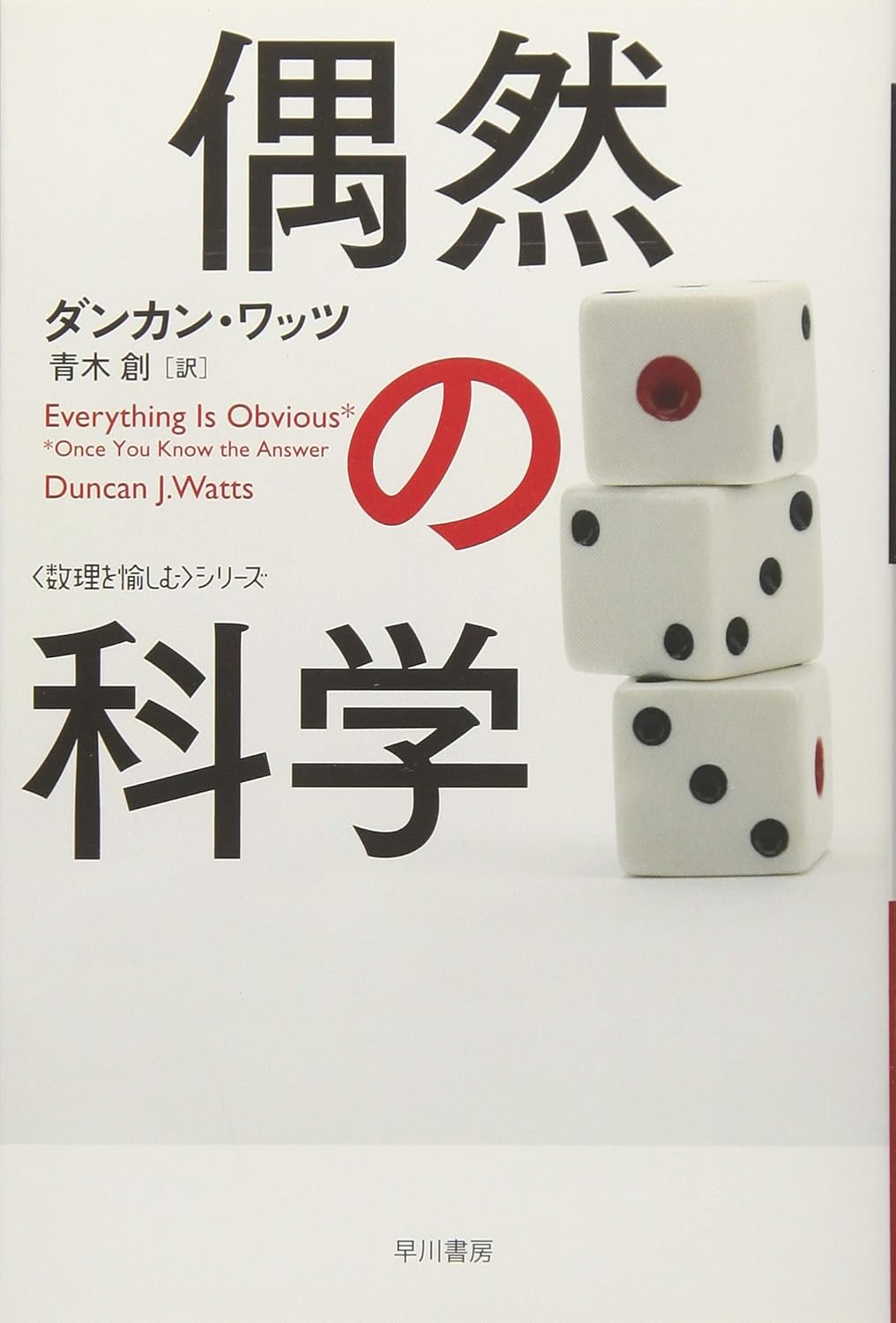
EVERYTHING IS OBVIOUS, Once You Know the Answer, Duncan J. Watts, 2011
の訳です。いま、「INTERNET ARCHIVE」を見たら、ありました。タイトルは、「 Duncan J. Watts Everything Is Obvious Once You Know The Answer Crown Business ( 2011 )」。表紙の写真では、「 Everything Is Obvious* *ONCE YOU KNOW THE ANSWER How Common Sense Fails Us 」。
どうして読もうと思ったのか、忘れました。社会学(者)の本です。全体として「偶然の科学」について述べていますが、「偶然とは何か」などの定義はありません。確率の本でもありません。表紙を直訳すれば「すべては当然(、答えを知っちゃえば。)ーどうして常識は役に立たないのか」でしょうか。「 Crown Business 」はわかりません。
初めて或る「出来事」を知ったとき、「どうして?」と疑問が湧いても、「〜〜だから」と説明があると(特に専門家から)、「そりゃそうだ」とその出来事を「当然のことだ」と納得してしまいます。どうして納得するのでしょう。「当たり前」だからです。つまり「常識だろ」というわけです。
どう感想を書こうか迷ったのですが、せっかく章立てしてくれてるんですから、その順番で思いついたことを書いていきます。
だが、
常識に基づく推論の欠陥にはめったに気が付かない。むしろ、「そのときは知らなかったが、あとから考えれば自明のこと」でかるかのようにわれわれの目には映る。このように、常識の矛盾とは、世界に意味づけをするのに役立つにもかかわらず、世界を理解する力を弱めてしまうことだ。(P.13)
「社会学者の謝罪」は、「この本には自信がある」と言っているようにも取れます。そりゃ、学者だからね。
なんと言っても、人間世界では、何物にも頼らない直観がはるかに有効だからだ。そのため、科学的方法を用いる必要をわれわれはめったに感じない。(P.34)
「科学的方法」は言い換えれば(この本では多くの「言い換えれば」が使われている)「論理的」「理性的」であるということです。そして「論理(ロジック)」という単語が「ロゴス(比率、言葉)」という古典ギリシャ語から来ているように、「言葉で考えている」ということです。
でも、ほんとうに「言葉で考えている」のでしょうか。ホームに着いた電車を見て、「空いてる。座れる。」と思ったとき、その言葉(たとえば日本語)で考えているのでしょうか。隣に一緒に電車を待っていた友人がいて、その人に「空いてる。座れるね。」と言うことはできます(その人も日本語がわかるとして、ですが)。声に発する前に、頭のなかで「空いてる。座れるね。」という言葉を作って、「その後で」声に発することもないことはないですが(それほど親しくない人の場合など)、私はほとんどの場合、「声に発する前の言葉」を作らず、「声を発すること=言葉にすること」です。著者(たぶんアメリカ人)はちがうのでしょうか。
「声(言葉)にする前のもの(感情や感覚や意図)」があって、それはどの文化でも同じで、それを声(言葉)にするとき、日本人なら日本語を使い、アメリカ人なら英語(米語)を使うのでしょうか。
たくさんの面白い実例があげられているので、こういう本の感想は「興味を引く」ような書き方をしたいと思っていました。でも、だんだんそういう書き方ができないことに気づいたので、また七面倒臭いことを書きます。
論理は「ロジック logic 」です。これは古典ギリシャ語の「ロゴス λὀγος 」です。詳しくはわかりませんが、もともと「比率、類比」のような意味があったようで、ラテン語の「ラティオ ratio」も同様に「比率」という意味があったので、そう訳されました。
なお、ついでながら、「言葉をもつ」というのが英語で rational(理性的・合理的)と訳され、ラテン語の ratio は「理性」、そして英語の ratio は「比」「割合」を意味するように、もともと λόγος も、古くから「比」「割合」の意をもっていた。「言葉をもつもの」は物事を比較し、類比的に( ἀναλόγως )考えるものだからであろう。(出隆『形而上学』旧アリストテレス全集第12巻 訳註、P.539)
ロゴスは、言葉とか論理という意味を持つようになります。自然界も「類比」で説明できるし、言葉や論理を扱うのは人間だからです。同様に「理性」をもつのも人間だけで、自然を「類比」で考えるのも人間だけなので、ラティオには「理性」の意味をもつようになります。ギリシャ語と並行して意味が膨らんだ気がします。
そして「ロゴス」は日本語で「論理」、「ラティオ」は日本語の「理性」に訳されたようです。「論理的 logical 」とか「 rational 理性的」とか。
日本は中国経由で儒教や道教や仏教が入ってきたので、これらを表す語(漢字)は「理(ことわり)」とか「道 tao」とか「法(のり dharma)」とか。
「道」は「武士道」とか、「(人の)あるべき姿」という意味が強い気がするし、「理」は「理科」など「(人というより世界の)あり方」という感じがします。「法」は「定められた世界の姿」という感じでしょうか。仏教思想が絡んでいるので、そこには「梵(ブラフマン、世界)」と「我(アートマン、人・個人)」が絡んでいて、「道」や「理」もその影響を受けて変化してきたのだろうと思います。
同じ印欧諸語であっても、古典ギリシャとイタリアとインドはやっぱりとらえ方がちがうと思います。それが近代西欧語の訳語としての「論理」や「理性」となったとき、もともとの道・理・法などと融合しているのでますますわからなくなります。
日本語には「直観」と「直感」という2つの単語があります。私が普通に使うのは「直感」で「どうしてわかったの?」「直感さ」という感じです。これは「 feeling 」に近いですね。「直観」は「 intuition 」で、ラテン語の「 intueri 熟視する」のニュアンスが強くて、「感じる」よりも「見つめる」に重点があります。だから「直感さ」を「 it's ( by ) intuition. 」と言うと誤解される可能性があります。著者が使っているのは「直観 intuition 」です。裏表紙の紹介文で「世界は直感や常識が意味づけした偽りの物語に満ちている。」とあるのは「直観」の誤りだと思います。パソコンの変換ミスかもしれません。
著者は「常識は直観的に生まれる」と考えているようなので、「言葉にする前のもの」があって、それが「直観的」なものと「論理的(科学的)」なものとに区別されると言っているような気がします。
「頭を掻く」ときとちがって「文章を書く」ときには、たしかに頭の中に浮かんだ言葉を「文字」として表すことが多いと思います。西欧では中世までは、本を読んだり書いたりするときに一旦「声」にしていました。いまは「黙読」と「黙書」がほとんどですが、そのときにも「省略された声」はあると思います。それが「頭の中の声」(「心の声」と言ったりすることもあります)です。文字が前提の社会では、文字を読んだり書いたりしなくても(文字を知らなくても)「頭の中の声」が当たり前になります。ドラマや映画では「頭の中の声」がアフレコで流れても不思議に思いません。さらに「ひとりごと」で状況や感情をセリフとしている作品も増えています(私はそれを声に出さずに演じることが役者だと思っています)。
それに伴って、「頭のなかで言葉にしないと話せない」つまり「考えないと話せない」という状況が強まっています。「考えなしに話す」と「それセクハラよ」とか「それパワハラだ」と言われかねないからです。結果として「対話」は「交渉 negotiation 」にならざるを得ません。
それは私は、西欧においてもとても近代的なことだと思うのですが、この本は現代のことを書いているのですから、「声や言葉にするしないにかかわらず、なにかがあって、それが直観的(常識的)であったり、科学的(合理的・論理的)であったりする」という前提にしておかないと次に進めません。
いろいろと面白い例が載っています。一例を挙げます。「ヨーロッパで臓器提供に同意している国民の割合」は、ドイツで12%、オーストリアは99.9%です。なぜそんなに差があるのでしょう。
答えは実のところ、ばかばかしいほど単純だ。オーストリアでは、臓器提供者になるのがデフォルト(標準)の選択肢だが、ドイツでは臓器提供者にならないのがデフォルトだからである。この政策のちがいは些細なものに見えるが(簡単な用紙に記入して郵送する必要があるかないかのちがいでしかない)、同意率を一二パーセントから九九・九パーセントに押しあげるにはそれでじゅうぶんなのである。(P.41)
「な〜んだ、そりゃそうだ。当然だ」と思いませんか。日本ではどのくらいの人が「臓器提供の意思表示」をしているのでしょうか。運転免許証やマイナンバーカードには「臓器提供意思表示記入欄」があります。記入がなければ「意思不明」ということになりますが、「提供する」がデフォルトで、「提供しない」人がその「意思を表示」することにすれば、同意率はぐんと跳ね上がるでしょう。
つまり「同意率」というのは、「同意している人の割合」でもないし、「臓器移植を認めている人の割合」でもないのです。こういう「政策」はよくあります(マイナンバーカード自体も含めて)。
この例はむしろ特別(社会学的というより政策的)ですが、「 A という事柄」があって、「それは B だからだ」と説明されて、「そりゃそうだ」と思った後に、「いやちがった、C だったからだ」といわれると、やっぱり「そうだよねえ、そう思った」となることは結構あります。
あるいは「 D になってほしい」と思っていて D になったとき、「やっぱりそうだろう」と思うこともあります。
また、 E を聞いたことがある、あるいは経験したことがあるということが、あるいは「 前には E だった」ということも、E は「当然のこと」だと思えます。
毎日のように闇バイトや詐欺(・特殊詐欺)のニュースが流れます。ニュースを観る人は「なんでそんなことで騙されるんだろう」と思いますが、騙された人が特別「常識がなかった」ということではないでしょう。
これらの心理学の実験が明証していることを一言でまとめるとこうなる
われわれの行動にきわめて現実的、具体的な影響を与えるにもかかわらず、もっぱらわれわれの意識しないところで働く関係要因は実に数多くある。(P.54)だがどういうわけか、なにを無視しているのか自覚することさえなく、こうした事柄をすべて無視して、かぎられた重要な事柄に注目することができる。(P.56)
ロボットに(つまりプログラムで)何かをやらせようとします。たとえば「あの部屋に行って爆弾を処理せよ」とか。これが簡単なようで、とても難しい(あるいは不可能)なのです。つまり、「〜〜(爆弾)に注目せよ」と言うことは「〜〜(爆弾)以外のものを無視せよ」ということだからです。爆弾の特徴は、ある程度プログラムすることは可能です。でも「爆弾以外のもの」をプログラムすることはできないからです。逆に「爆弾」の特徴もやはりそのすべてをプログラムすることはできません。形や仕組みはもちろんのこと、「爆発するもの」が爆弾だとしても、実際に爆発するかは爆発させてみなければわかりませんから。
私は〈モナ・リザ〉が好きではありません。実物を見たことはありませんが、写真で見る〈モナ・リザ〉の顔が怖いのです。
われわれは芸術作品をその特質に基づいて評価しているように思えるが、実は反対のことをしている。つまり、まずどの絵が最高かを決めたうえで、その特質から評価基準を導き出している。こうすれば、すでに知っている結果を一見すると合理的かつ客観的な形で正当化するのに、この評価基準を引き合いに出せる。(中略)だが本当のところは、〈モナ・リザ〉が有名なのはそれがほかの何よりも〈モナ・リザ〉的だからと言っているにすぎない。(P.76)
私は漫才をやっていたころの「ダウンタウン」が大好きです。同じネタを何度見ても面白いし、知らないネタでも笑ってしまいます。そのうち「面白いからダウンタウンなのか」「ダウンタウンだから面白いのか」の違いがなくなります。ダウンタウンにも面白くないネタはあるし、無名の芸人でも面白いネタはあるんでしょうが。
どの例でも、われわれはXが成功したのはしかるべき特質を備えているからだと思いたがるが、われわれの知っている特質はXのもつ特質にかぎられる。だから、そうした特質がXの成功の理由にちがいないと結論する。(P.78)
だから事実上、われわれはこう言っているにすぎない。「Xが起こったのは人々がそれを望んだからだ。人々がXを望んだとなぜわかるのかというと、Xが起こったからだ」(P.79)
著者はこれを「循環論法」だといいます。
「ダウンタウンは面白い」という「経験や記憶」「贔屓目」「フィルター」「バイアス」が「ダウンタウンを面白く観る」ということになります。
階層がちがってもある程度は同じ法則があてはまらなければならないが(物理学の法則に反する化学などありえない)、下の階層を支配する法則から、上の階層にあてはまる法則を引き出すのはまず不可能である。(P.81)
「階層」は「スケール scale 」です。似たような言葉で「レイヤー layer 」とか「レベル level 」とかがあります。それらの違いはわかりません。「次元 dimension 」も同じように使われることがあります。
病気の原因を知るには、その手足や内蔵、体重、体温、血圧、などの部分に分けて調べることが当たり前になっています。病院に行けば、まずは検査、検査、検査。で、数値が基準以上だったり以下だったりすれば、「病気です」ということになります。でも、生まれながらに体温の低い(高い)人、血圧の低い(高い)人がいるじゃないですか。この本に従っていうなら、問題なのは「体温が低い(高い)」「血圧が低い(高い)」ということだとはかぎらないということです。つまり、なにかに注目するのは結構ですが、注目しないことに病気の原因があっても、それが考慮されない恐れがあるということです。
病気を痛みやかゆみ、体重、体温、血圧などの「症状」つまり「部分」を測定することで「病気そのもの」つまり「全体」が分かるわけではないのです。
「ミクロ・マクロ問題」とは、「全体と部分」との問題です。全体を部分に分けることはできます。でも、部分を集めたのが全体ではないのです。西欧で「全体主義」と「個人主義」がせめぎ合っているのはこの「全体と部分」が根本にあります。
たとえばわれわれは、一遺伝子のように働くものとしてゲノムを論じないし、個々の神経細胞のように働くものとして脳を論じないし、個々の生物のように行動するものとして生態系を論じない。そんなふうに論じるのはばかげている。
にもかかわらず、社会現象に関しては、われわれは
たしかに家族、企業、市場、政党、人口階層、国民国家などの「社会的アクター」が、それを構成する個人のように行動するものとして論じる。つまり、家族が休暇中の行き先を「決める」とか、企業がビジネス戦略を「選ぶ」とか、政党が議案の成立を「推し進める」といった言い方をする。同じように、広告主は「ターゲット層」への訴求力を語り、ウォール・ストリートの証券会社は「市場」の心理を分析し、政治家は「人々の意思」を語り、歴史家は「社会をとらえた熱病」として革命を述べる。(P.82-83)
進化論(ダーウィン進化論、正統派進化論)は、個が変われば(生存闘争で、自然選択で)種が変わるといいます。ダーウィン以後、その変化は DNA の変化と言い換えられ、DNA の変化は量子力学における不確定原理に言い換えられていきます。
自然淘汰で適者が生存するとするならば、生存しているものはみな適者であり、生存競争の勝利者であるという理屈が、とおらぬわけでもあるまい。私にこの話をして、はじめて進化論にたいする眼を開いてくれたのは、旧制第三高等学校の同級生で、いまは亡き言語学者の三上章であった。(今西錦司『主体性の進化論』中公新書、P.43)
今西とダーウィンはちょうど逆の言い方をします。ダーウィンは神の意志のかわりに自然の意志(自然選択)を主張したのでした。そして彼が言わなかったのが個人(主体)の意志です。それは「生存競争」として「人間が受け入れねばならない(必然)」として暗に語られています。スペンサーはそれを露わにした(社会進化論)だけです。
今西が「主体性」というのは、むしろ自然の意志(客観性、必然性)の否定で、かつ個の否定です。その主体は自然でもなく、個人でもなく「種」です。そして種の意志というのは、社会の意志ではないのです。「主体性」という言葉は「種体性」の洒落かもしれません。
変わらないというのは、言葉を変えたら、自己同一性(アイデンティティ)を保っているということであるから、私も種も、自己同一性を維持しながら変わってゆく、ということだろう。そして、自己同一性をもちながら、変わるべくして変わってゆくもの、あるいは自己運動によって変わってゆくようなもののことを、ここであらためて主体性をもったもの、と定義しよう。しかし、変わるべくして変わるということは、この空間的・時間的な世界に存在するあらゆるものについて、いえることではないか。そうすると、私はこの世界に存在するあらゆるものに主体性を認めよう、としていることにならないだろうか。(個体に主体性を認め、種に主体性を認めるのであったならば、もろもろの種によって、くわしくいうなら種社会によって、構成された生物全体社会にたいしても、やはり主体性を認めないわけには、ゆかなくなるのでないだろうか。(同書、P.209)
「変わるべくして変わる」(「変える」のでも「変えられる」のでもない)のなら、そこにあるのは「人間的な」意図や、目的や、意志とはまったく「次元」が異なるものです。それをあえて「人間の言葉(ロジック)」で表そうとするなら、「主体性」という表現をせざるをえないのです。
犬を見て「お腹が空いてるんだ」と思ったり、植物が「水を欲しがっているんだ」と思うのは、きっとどの文化でも同じでしょう。これを擬人化と言ったりしますが、その内実はだいぶ異なります。自分と犬や植物が「別のもの」と思う文化(つまり、主体と客体が明確に分離している社会)では、犬や植物に見ているのは自分の姿の投影です。でも、「別のもの」だと思わない文化では、それは自分の姿の投影ではなく、擬人化ともいえないものです。ダーウィンと今西との差はそれだと思います。
大体6ステップを踏めば、世界(ワールド)中の人と繋がれるというような話しで、「スモール・ワールド現象」の一例です。「世界は人が思っているひど大きくない」ということです。タモリさんの「友達の友達はみんな友達」でしょうか。
「6」というのはいい加減な数で、さまざまな実験で様々な数字がでています(Wikipedia「
六次の隔たり」「スモール・ワールド現象」参照)。著者(ダンカン・ワッツ)もネットワーク理論からスモール・ワールド現象を説明するための実験を行っています。インターネット(SNS)を使えば、大規模な実験を安価な費用で実施できるというわけです。
私達が日々ネットで検索をしているのは、情報を得ると同時に、その大規模な実験に参加している(情報を提供している)ともいえます。
ただ、私が思うに、SNSがこれだけ流行るのは「必要」や「好奇心」からだけではありません。わたしたちの「欲望」は「必要を満たす」ことではなくなっているからです。検索をするとたくさんの広告に出会います。その中には興味がありそうな商品だけでなく、興味を引きそうなネットニュースもあります。なにかが必要でスーパーやコンビニに行ったとき、目的のものだけではなく沢山の商品や広告が目につきます。「美味しそう」とか「便利そう」とか、つい買ってしまうこともあります。そしてほとんどは食べてみて(使ってみた)「まあこんなもんだな」ということになるのですが。
これは「必要を満たす」ということを超えているのです。むしろ、消費者やユーザーは「情報や必要を求めている」のです。「欲望を欲望する」ということです。「なんか刺激がほしい」「なんか面白いことないかなあ」「なんか美味しいものがないかなあ」というわけです。最近、「名物料理」や「名所」の番組がやたらと多いのですが、セットを作る必要もなく、スタッフも少人数で安く番組が作れます。実際にそこに行く人の割合は少ないでしょうが、それでも番組としては成立します。
必要なものを求めているのではないのですから、この欲望は満たされることがありません。それは欲望を超えた「渇望」となります。
インターネットはその「渇望」の社会の中で生まれました。なので、インターネットによる実験というのは、そういう「ものの見方・考え方」をもった人々を対象とした実験なのです。インターネットによって、
それでも、観察データが飛躍的に得やすくなり、かつては想像しがたかったほどの規模で実験がおこなえるようになったおかげで、社会学者もほかの分野の科学者がずっと慣れ親しんできたのと同じ形で、人間の集団行動を測定、理解し、うまくすれば予測可能な世界を想像できるようになってきている。(P.329)
その通りなのですが、その対象となっている世界(あるいは社会)が「特殊」であることを「意識」せずに、「人間とは、社会とは、あるいは世界とはこういうものなのだ」と言うことはけっして「理性的」なことではありません。
しかしながら、われわれがシミュレーションから知ったのは、こうした個人に特別なことなどほんとうはまったくないということだった。われわれがそのように設定したからである。(中略)
したがって、われわれの結論をいうと、エネルギーや人脈によって本をベストセラーにしたり製品をヒットさせたりできるほどの影響力の強い人物は、十中八九タイミングと状況の偶然によって生まれる。いわば「偶然の重要人物(インフルエンサー)」なのである。(P.125)
だが、「Xが起こったのは少数の特別な人々がそれを起きしたからだ」と主張するのは、循環論法を別の循環論法で置き換えるのに等しい。(P.137)
最近、「ユーチューバーになりたい」という子ども(大人も)が増えているようです。フォロワーが多いと結構な収入になるそうで、なんか楽しそうに好きなことをやって儲けているように見えるからでしょう。でも、ユーチューバーが増えると段々と収入を得るのが難しくなっていくように思えます。
企業は(インターネット広告にも)莫大な広告費を出しているのですが、それが実際の売上につながっているのかどうかは別のことです。「売上を上げる」と「売上が上がる」が全く別なように。
「影響を与える」と「影響を与えられる」という「能動と受動」について考えてみます。最近ではそのふたつが「反対のこと」だと思っている人が日本でも増えているように思います。
「欲望を満たす/欲望が満たされる」(あるいは「欲望する/欲望される」)は「反対のこと」でしょうか。「気を使う/気を使われる」はどうでしょうか。日本語にも主語や補語(あるいは目的語)らしきものがありますが、英語ができる人は英訳してみてください。多分、別の主語(や目的語・補語)がでてくるでしょう。「愛する/愛される」はどうですか。みんな「〇〇は✗✗に」という名詞や代名詞が出てくると思います。
「見る/見られる」はどうですか。日本語には「見える」という文があります。これは能動でも受動でも、または「可能 can, possible 」でもありません。「見えた」というのは過去形でもありません。英文法的にはそう整理するしかないのですが、ぜんぜんちがうのです。英語以外の多くの印欧諸語には「中動態」というのがあります。主体的・意識(意志)的にではなくて、そういう状況に陥る(遭遇する)というような意味です。
「見える」というのは「見ることができる状態・状況にいる」ということで、実際に「見ている、見えている」こととも違います。「愛している」は「好きだ」と同じで、「愛している・好きな状態状況にある(陥っている)」ということです。「気を使う/気を使われる」も能動・受動的なものと受け取られていますが、本来は「気を使ってしまう/気を使われてしまう」ような状況になることをいうのではないでしょうか。
「影響を与える/影響を与えられる」という「対立」を前提とした著者の論述は、ある意味でとても西欧的です。
ちなみに、「売る/買う」という対立も「売る/売られる」「買う/買われる」という対立と同じく西欧文法的です。
経済や政治や文化の事柄、つまり多数の人々が時間をかけて影響を与え合うような事柄についてフレーム問題とミクロ‐マクロ問題がともに教えているのは、いかなる状況も、これまでに観察した状況とは重要なちがいがあるということだ。したがって、現実には同じ実験を二回以上おこなうことはけっしてできない。(P.141)
すなわち、われわれは実際に起った事柄を必然としてとらえる傾向があるのだ。
心理学者が「遅い決定論」と呼ぶこの傾向は、「あと知恵バイアス」というもっと有名な現象と関係がある。あと知恵バイアスとは、事が起こったあとになって「はじめからわかっていたのに」と思う傾向のことである。(P.143)
「歴史は繰り返す」という言葉があります(トゥキュディデスの言葉のようです)。人間だれでも親から生まれ、歳を取って死んでいくのですから、繰り返すといえば(輪廻とは関係なく)その通りです。実際は、政治の世界でも経済の世界でも「同じようなこと」が繰り返されているように思えます。半世紀以上を生きていると、否が応でもそういうことを感じるのです。
でも、誰かYoutubeで人気が出たからといって、私が同じことをやっても人気は出ないでしょう。画期的な商品は、最初に作ったから画期的なのであって、同じものを作っても画期的ではありません。「昨日と同じ今日はない」という言葉もあります。たしかに、私は昨日より1日歳を取っています。1年前、10年前と比べれば、その違いは明白です。私の世代と私の親の世代、私の子供の世代とは考え方もちがっていると思います。変わっていく個別のものと変わらない(普遍)普遍なものを考えるとプラトン的(イデア論)になってしまいますが、学問(科学・知)は基本的に変わるものの中に変わらないもの(法則)を見つけ出そうとします。
いまの世の中で変わらないものがひとつあります。それは「お金に価値がある」ということです。「商品(知識も)は変わるけど、お金(価値)は変わらない」、それが現代のイデア論であって、その表現型はプラトンのイデア論とはまったくと言っていいほどちがうものです。
事実、予測の奇妙な点のひとつは、われわれは未来についての見解を熱心に発表したがるが、それに負けず劣らず、立てた予測に説明責任を持ちたがらないことである。(P.174)
しかし、専門家は一般の人々に比べて予測を立てるのが上手ではないにしても、おそらく下手でもない。(P.175)
要するに、予測の真の問題とはそれが上手か下手かではなくて、自信を持って立てられる予測とそうでない予測とを区別するのにわれわれが長けていないということである。(P.177)
天気予報をはじめとして、いまの世の中は数え切れないほどの予測で成り立っています。予測が世の中を動かしている観すらあります。昔は「天気予報は当たらない」ことが当たり前でしたが、最近は「よく当たる」ようです。ただ、「天気予報が当たったかどうか」を確かめる人は少ないのです(天気予報にお金を出している人だけじゃないでしょうか)。専門家が「株の予測」から「新型コロナの流行予測」まで、あらゆる「予測」を立てますが、それらが検証されることは殆どありません。もし「当たらなかったじゃないか」と責めても、「それは別の要因があったから」と言われればそれまでです。たしかに専門家は素人よりは「その要因」に詳しいかもしれません。でも専門家が注目する要因はけっしてすべての要因ではないのです。最近は「警報級の」という言葉が多用されていて、「それじゃあ、素人でも言えるじゃない」と私は思うのですが。
昔は数少ない観測所からの情報で、手計算で地図上に等圧線を引いて予測したのですが、いまは数え切れないほどのデータをコンピュータで処理させています。株の予測も処理するデータは膨大になっています。データをさらに増やして、処理速度を速めれば確実な予測ができるのでしょうか。
複雑なシステムでは小さな要因のひとつひとつが予測できない形で増幅されるのであれば、モデルが予測できることはかぎられている。このため、複雑なシステムのモデルは単純なものになる傾向がある。単純なモデルのほうが好結果を出せるからではなく、どのみち大きく誤る可能性が残っているために、改良してもほとんど意味がないからである。(P.181)
3章で論じたとおり、社会システムをそもそも「社会」たらしめているのはこうした相互作用である。相互作用によって、人々の集まりは単なる人々の集まり以上のものになるからだ。だがその過程で、途方もないほどの複雑性が生じる。(P.182)
データを増やすことによって、予測精度が増すのだとしてもデータの数が増えれば増えるほどその精度の向上は難しくなります。10箇所の観測所からのデータに基づく予報と20箇所の観測所からのデータに基づく予報では精度は上がるでしょうが、10000箇所からのデータと10010箇所からのデータによる予測精度の差は殆ど無いと言っていいでしょう。
「降水確率〇〇%」と予報されますが、窓から外を見て雨が降っていればそれは「雨」であって「〇〇%の雨」ではありません。
確率の面から未来を考えようとするときに出くわす困難は、別の可能性に目をつむって既知の結果を説明したがるわれわれの好みを映し出している。前章で論じたとおり、過去の振り返るとき、われわれは出来事の連続しか見ていない。(P.185)
しかし、現在とちがう成り行きになったかもしれないのだといくら自分に言い聞かせても、起こったことが起こったという事実は変わらない。四〇パーセントでも六〇パーセントでもなく、一〇〇パーセントそうなったのである。だから、未来を考えるときも、もっぱら実際に何が起こるかをおのずと気にかける。(P.185-186)
別の言い方をすれば、未来について不確かであることと、未来そのものが不確かであることはちがう。実際のところ、前者は単なる情報不足、つまりわれわれが何かを知っていないということだが、後者は情報が原則として知りえないことを意味している。(P.188)
コインを二枚投げて両方とも表が出る確率は1/4です。いま実際に二枚のコインを投げて両方が表だったとき、それは「25%の現実(=75%の非現実)」ではないのです。
どんな予測を立てるべきだったかも、あとになってみないとわからない。(P.189)
何が関係しているかはあとにならないとわからない。つまり、最も立てたい予測を立てるためには、未来に起こるかもしれないすべての出来事のなかで、どれが関係するものかをまず特定し、それにいまから注意を払わなければならない。(P.190)より大きな結果を生むことになんら役立たない予測は、われわれの興味を引かないし、価値もない。繰り返すと、われわれは重要な事項を気にかけるが、最も困難なのは、未来についてのこうしたより大きくより重要な予測にほかならない。(P.193)
前章が言わんとしているのは、常識からすれば立てられそうな予測も、実際には立てられないということだ。それはふたつの理由による。
第一に、常識はたったひとつの未来だけが起こると教えるので、それについての明確な予測を立てたくなっても無理はない。しかしながら、われわれの社会生活と経済生活の大部分を構成する複雑なシステムでは、ある種の出来事が起こる確率をなるべく正しく見積もることくらいしか望めない。
第二に、われわれはいつでも予測を立てられるが、常識は興味を引かない予測や重要でない予測の多くを無視し、重要な結果に注目するように求める。だが現実には、どの事件が未来に重要になるかを予想するのは原理的にも不可能である。(P.204)
不可知論というのではないのです。平均寿命(あるいは平均余命)から「私が明日死ぬ確率」を算出することはできるでしょう。でも、その確率には「隕石に当たって死ぬ」という死亡要因は含まれていません(多分)。私にとって、「明日死ぬかどうか」はとても重要なことなのですが。
とっても面白い話です。よくわかります。私はそこに生きていましたから。どう書いているかは、あえて引用しません。
書かれていない話をします。私が学生時代にソニーの「ウォークマン」が発売されました(1979年、イリイチが「第二の分水嶺」と捉えた時代)。スピーカーも録音機能もないカセットレコーダー、いや再生専用機です。私はこんなスピーカーも録音機能もないものが売れるわけがない、と思ったのですが、飛ぶように売れました。今まで部屋で聞いていた「自分が好きな音楽」が外で聞けるのです。ほしかったのですが、貧乏学生には買えませんでした。しばらくして、別のメーカーが同じようにポケットにはいるカセットレコーダーをウォークマンよりずっと安く出しました(録音機能もついていたと思う。その分、当時の最新型のウォークマンより大きくて重かった)。私はそれを買いました。好きな音楽を入れたカセットを入れ、外で歩きながら聞いたときの衝撃をいまだに忘れられません。「世界が違って見えた」のです。自分の好きな音楽が聞こえる、それもあらゆる方向から。つまり、スピーカーから聞こえる音楽は「スピーカー」という「聞こえてくる方向」があるわけです。でも、歩きながら聞く音楽は、頭を動かしても、自分が動いても音楽が「そのまま」追(つ)いてくるのです。「見ている風景」と「聞こえてくる音」が違うのです。身体感覚と認識が分離するのです。ほとんど「めまい」がしました。車酔いのような、「吐き気」がするような感覚です。
生まれたときからそういう経験をしている人にはわからないでしょう。そのとき怖かったのは、音楽以外の音、車の音や人の話し声が聞こえないことです。いつ車に轢かれるか、いつ人に殴られるかも「その気配」がしないのです。そこにあるのは、世間(世界)と切り離された「自分の存在」です。モナドの中から世界を覗いているような感覚です(ライプニッツは未だに読んでいないけど)。いまの若い人は、生まれたときからそういう「世界」と「自分」の関係にいるのかもしれません。
iPod(2001年〜)は、ウォークマン同様の再生専用機です。カセットテープを入れない分、小さくなりましたが、当初はハードディスクでしたから、大きさの割にずっしりとしていました。ウォークマンの成功がなければ iPod はなかったかもしれません。少なくとも、「世界観」を変えるようなものではなかったでしょう。
ZARA(スペインの衣料品会社・・・引用者)は客がつぎのシーズンに買うものを予測しようなどとはせず、むしろそんなものは見当もつかないと認めているに近い。そのかわり、いわば「測定-対応」戦略を用いている。(P.237)
「つぎのシーズンの予測」ではなくて、「今売れているもの(消費者が今欲しがっているもの)」を短時間で作るという戦略です。
要するに、計画者は未来に何が役立つかを正しく予測しようとするのではなく、現在役立っているものについて知る能力を向上させなくてはならない。(P.238)
来年の天気を予想するより、明日の天気を予想することのほうが簡単です。今の天気は「窓から見ればいい」のです。
肝心なのは、世界の状態を測定するわれわれの能力は増したのだから、計画に対する従来の考え方も改めるべきだということだ。対象が広告だろうと製品だろうと政策だろうと、われわれは人々の行動を予測し、消費者に特定の反応をさせるための方法を立案しようとするかわりに、可能性全体に対して人々がどう反応し、それに基づいてどう対応するかを直接測定できる。
言い換えれば、「予測とコントロール」から「測定と対応」への変化は、テクノロジーのみにかかわるのではなく
テクノロジーは必要だが心理にもかかわっている。未来を予測する自分たちの能力はあてにならないと認めてはじめて、われわれは未来を見いだす方法を受け入れられる。(P.247-248)
真の問題は、広告主が知りたがるのは、広告が売上の伸びの原因になっているのかどうかという点にある。だが、広告主が測定するのはほぼ決まって、両者の相関関係でしかない。もちろん、理屈のうえでは、相関関係と因果関係がちがうことはだれしも「知っている」が、実際には両者は混同されやすく、現にしょっちゅう混同されている。(P.250)
因果関係と相関関係を区別するのは、概して多大な注意を要する。だが少なくとも原理上は、簡単な解決策がひとつあり、それは「処置」、つまりダイエットや広告キャンペーンをおこなう場合とおこなわない場合の実験を実行することである。「対照」群に比べ、処置をおこなったほうが、(体重の減少や売上の伸びなどの)関心のある結果を著しく生じやすければ、その処置が結果の原因になったと結論できる。そうでなければ結論できない。(P.251)
「タバコを吸う(原因)とがんになる(結果)」というのは本当に「因果関係」なのでしょうか。たしかに研究者は(その人が厚労省や WHO に資金提供されていようと、いまいと)「対照群」を設けて「数値」を出します。(その数値が有意なのか、母数はどうなのかは知りませんが)その数値を基に「キャンペーン」がなされます。でもそれが「相関関係ではない」と言えるのでしょうか。
「タバコを吸っていてがんになった人」「タバコを吸っていなくてがんになった人」の人数は数えることができます。でも、「タバコ吸っていなくてがんになった人」がいるということは、「タバコを吸っているのが癌の原因で、がんはその結果であるとは言えない」ということです。
癌の原因としては様々な学説があります。NHKスペシャル『シリーズ人体』で「ジャンクDNA」(ヒトゲノムのうち役割がわかっている2%以外のゲノム)の中に「トレジャーDNA」があるという話がありました。その中に「カフェインを速く分解するDNA」の話が出てきます。「喫煙によるがんを防ぐDNA」の話があったかどうか確認できませんが、そういう「トレジャーDNA」をもっているかどうかは、たぶん「偶然」です。そういうDNAが発見される(された)かどうかも偶然です。そしてその人が喫煙するのか、さらに喫煙していてがんになるのか(ならないのか)も偶然です。
因果関係は「より強い(?)相関関係にすぎない」のではないでしょうか。だからこそ著者にとってはそれが「偶然の科学(ロゴス)」なのでしょう。
タバコを吸ってがんになった(ならなかった)というのは「偶然」なのでしょうか。それを「がんを防ぐ DNA をもっているかどうか」に置き換えてもやはり「偶然」かどうか、です。
実力主義の社会では、成功した人々はあまり成功していない人々より才能があるか、努力をした少なくともうまく好機に乗じたにちがいないとわれわれは信じたがる。(P.290)だがどの個人の物語も独自のものなので、自分の目にした結果はその個人の独自の特質がなんらかの形でもたらしたものだと、われわれはいつだって自分を納得させることができる。(P.291)
物質的な富以外の報酬を気にかける賢明な人もいるという明白な理由からでなく、才能は才能であり成功は成功であって、後者は必ずしも前者を反映しないからである。(P.292)
「偶然(偶有性)と必然(自体性)」「可能(ポテンシャル)と現実(アクチュアル)」、あるいは「運」「運命」「宿命」などの考え方は、どの文化・その時代にもあると思います。でも、それをどう捉えるか、どう感じるのかは文化・時代によって異なります。
同じ西欧においても、古典ギリシャ語の時代や古典ラテン語の時代、中世ラテン語の時代で異なるでしょう。それはイリイチのいう「第一の分水嶺」(13世紀前後)、あるいはグーテンベルク(15世紀)、デカルト(17世紀)を経て変化します。そして1980年代、私が感じたあの「めまい」を若い人に伝えることはむずかしいと感じています。
著者は1971年生まれです(本書カバー)。ウォークマンが発売されたときにはまだ8歳です(ちなみに訳者は年生まれ)。彼に私のめまいはわかるのでしょうか。それを「認識」や「理解」できるのでしょうか。
言い換えれば、社会学の提供するものの多くが常識のように思えるとき、それはひとたび答えを知ってしまえば人間の行動のすべてが自明に見えるからだけではない。この問題には、社会学者もほかの人と同じく社会生活に参加していて、よく考えさえすれば人々の行動の理由が理解できるように感じていることも関係している。だから、社会科学の説明の多くが、合理性の事後主張、代表的個人、特別な人々、因果関係と相関関係の混同といった常識に基づく説明に広くみられる欠点を共通して持っていても不思議ではない。(P.318)
これは、日本語で「分かる」というのと同じ意味なのでしょうか。日本語の「分かる」自体も変わってきているのかもしれませんが。
変化するものとは別に普遍(不変)なものがあるのか、あるいは普遍(不変、抽象的)なものの具現化(具体化)として変化するものがあるのか。私にはわかりません。ただ、古代ギリシャ人は古典ギリシャ語で考えるしかないし、私は(現代)日本語で考えるしかありません。でも、その事自体の中にしか答えはないし、その事自体(つまり問い自体)が答えなのかもしれません。
われわれは最後の最後までけっして知りえない。それに、すべて自分次第で決まるわけではないのだから、最後の最後になってもわからないかもしれない。
言い換えれば、人生には明確な「結果」があり、そのときになればある行動の意味を最終評価できるという考え方そのものが、都合のいい作り事に等しい。(P.164-165)
[著者等]
著者について
アメリカの社会学者。マイクロソフトリサーチ主任研究員。1971年オーストラリア生まれ。コーネル大学で理論応用力学の博士号を取得。オーストラリア海軍士官、コロンビア大学社会学部教授、ヤフー・リサーチ主任研究員を経て現職。サンタフェ研究所およびオクスフォード大学ナフィールド・カレッジにも籍を置いた。1998年、S・ストロガッツと共にスモールワールド現象(わずか数人の知人をたどれば世界中の人間がつながるという説)をネットワーク理論の見地から解明した論文で一躍脚光を浴び、現在ネットワーク科学の世界的第一人者として知られる。邦訳書に『スモールワールド・ネットワーク――世界を知るための新科学的思考法』『スモールワールド――ネットワークの構造とダイナミクス』がある。
「『社会科学を本物の科学に! 』 この社会学党宣言こそ本書のコアだ」
ダン・アリエリー(イグ・ノーベル賞受賞者、『予想どおりに不合理』)
「世界認識を変える本が現れた。耳が痛くても、“間違う理由"は知る価値あり」
世界は直感や常識が意味づけした偽りの物語に満ちている。ビジネスでも政治でもエンターテインメントでも、専門家の予測は当てにできず、歴史は教訓にならず、個人や作品の偉大さから成功は測れない。だが社会と経済の「偶然」のメカニズムを知れば、予測 可能な未来が広がる……。より賢い意思決定のために、スモールワールド理論の提唱者が最新の科学研究から世界史的事件までを例に解き明かす、複雑系社会学の話題の書。



