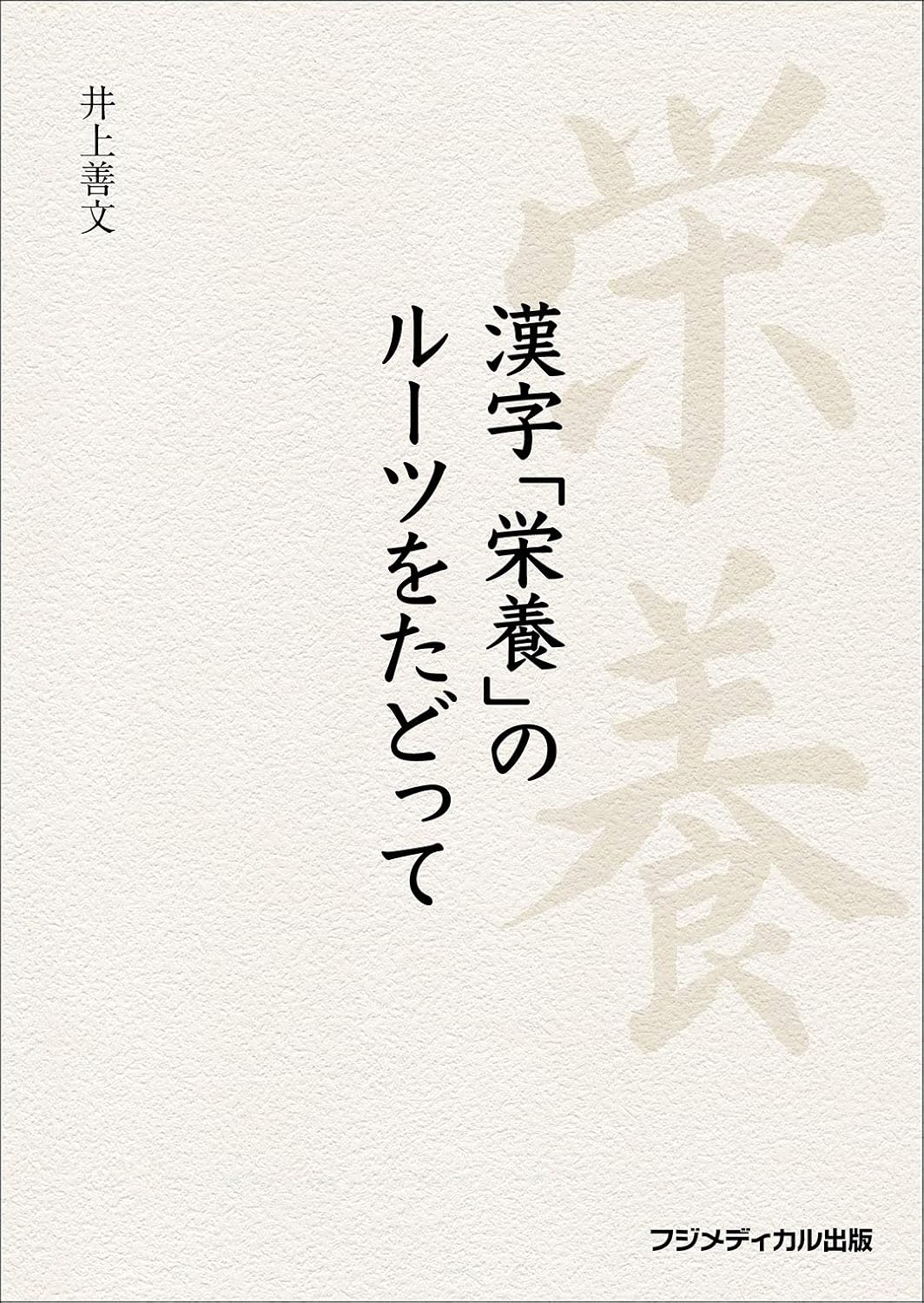
図書館から借りてきました。B5サイズ、108ページ。最後にはメモ用のページもあります。
地図や写真がふんだんに掲載されていて、臨場感があります。「栄養」という単語(漢字)がいつから使われていたのか、誰が作ったのかを様々な文献、あるいは「その場所」に行って訪ねる内容です。一緒に旅をしているかのように楽しかったです。
著者は、「栄養」の専門家(医師)です。
医師である。外科医である。静脈栄養、経腸栄養という方法での『栄養』の専門家なのである。外科医として手術を中心とする診療をしながら、安全に手術するため、手術の合併症を予防するため、手術後の回復をサポートするため、できるだけ早く社会復帰していただくため、また、食べられない患者さんの栄養状態を維持するための栄養管理として、『栄養』に関する仕事をしている。医療としての『栄養』に関する仕事をしている。(P.4)
「栄養」というと、すぐにビタミンとか、炭水化物とかを思い浮かべます。栄養士や管理栄養士という職業(資格)もあります。栄養士は、「ビタミンを〇〇グラム摂るために、リンゴを〇〇グラム・・・、を食べる」という「食べる」栄養の専門家です。それに対し、著者は「食べられない患者さん」のための栄養の専門家です。私の義母はもう何年も静脈栄養だけで生きていますから、その技術(学問)には感謝しています。
しかし、医学部では『食』についはほとんど学んでいない。講義にも、もちろん、ない。いわゆるグルメの医師、美食家はたくさんいるが、食における『栄養』については詳しくない方が多いはずである。サプリメントなどの使用についても、『医師に相談すること』となっているが、それは無理である。勉強していない、習っていない、知識も経験もないのだから。(P.4)
「栄養って何か」なんて考えたこともなかったし、実はこの本にも「栄養とは何か」という学問的なことが書かれているわけではありません。あくまでも「栄養」という「漢字」のルーツを探す旅が描かれています。2017年、『榮養寺』に行った際には道後温泉へ行って「じゃこかつ」を食べた話も記載しています。
最近有名になっている『じゃこかつ』を食べたが、300円もした。地元、宇和島や八幡浜では100円だが。(P.34)
著者の地元、愛媛県の伊予市に『榮養寺(えいようじ)』というお寺があって、それを知ったことが「漢字「栄養」のルーツを探る旅」の始まりです。
本山に残る江戸時代の記録によると、榮養寺の開山は余戸村(現 松山市余戸)出身の傅誉上人となっているが、寺伝では苦厭(求厭)上人としている。「浄土本朝高僧伝」によると、苦厭上人は豊臣秀頼の子、国松丸(一説には国松丸の弟)で、元和元年(1615年)大阪夏の陣の時にわずか二才であったが、家臣の手によって難を逃れ、後に出家して念仏行者となったという。苦厭上人が榮養寺の前身、妙音寺を建立したという伝説もあり、跡地には苦厭上人の墓所も残っている。(P.96)
「豊臣秀頼」とか「大坂夏の陣」とか、歴史ファンにはたまらないでしょう。
「源義経」の墓とかが全国にあり、「チンギス・ハーン」の墓とかが日本を含めて各国にあります。「ゴータマシッダールタ(仏陀)」の遺骨は、全世界の寺院に納められています。「骨」は「カルシウム」などの物質(栄養素)の塊です。でもそれは「カルシウム自体」が持つ意味とは異なります。カルシウム、ビタミン、ミネラル、炭水化物などの「意味」は、「人間にとって」の意味です。人間にとってどういう「関わり」があるかということです。人間にとって大切なのは、むしろ「関わり」の方です。
愛媛県と『榮養寺』ゆかりの(「ゆかり」の意味については本文を読んでいただきたい)佐伯矩(さえきただす)は「栄養学の父」と呼ばれる人です(Wikipedia「佐伯矩」も参照)。1918年、文部省に「営養」の表記を「栄養」に統一するよう建言しました。今から約100年前です。それが定着して、今でも「栄養」という漢字が使われています。それまでは「営養」だったのです。
著者は、みずからの専門である「栄養」が100年前から使われたものだ、『榮養寺』も何か関係があるにちがいない、ということから、文献を調べ、その現物を探し確認します。
その過程で、須藤憲三、森鴎外、貝原益軒、杉田玄白、高野長英などと遡っていきます。「蛮社の獄」などの歴史的事件も登場します。
結論を言ってしまうと(ネタバレ注意)、
いずれにせよ、高野長英がオランダ語の『 Voeding 』(英語では mutrition または feeding )を『栄養』と訳し、生理学の中の用語として用いられ、それが森鴎外、須藤憲三、佐伯矩へとつながり、現在、『栄養』が『 nutrition 』の意味で使われるようになった、これが『栄養』のルーツであると結論づけることができるはずである。(P.75)
高野長英が天保3年(1832年)に書いた『西説医原枢要』が最初ではないか、というのです。これは当初、筆者が考えていた仮説とは異なります。筆者は、その発見を喜んだとともに困惑したでしょうね。何しろ、『榮養寺』の住職、髙橋宏文さんと「漢字『栄養』100年イベント」を開催しようと決めていたのですから。
2018年11月25日に、松山市で開催されました。各種の講演がなされ、参加者は103名。記念品は『榮養寺』にある佐伯矩の書『栄養』をデザインしたマグカップ。150個作ったそうです。いい字です。ほしいなあ。
そこで著者は、開会の挨拶と閉会の挨拶をします。「漢字「栄養」のルーツ探しの旅の結論」の発表は、その閉会の挨拶でなされました。一種のどんでん返しですね。イベントそのものが「ルーツ探しの旅」の再現そのものです。著者の人柄が浮かんできます。
江戸時代以前には、日本は漢籍にある漢語を輸入していました。文化そのものがその漢字とともに日本に入ってきたからです。明治以降(前後)、西洋文化という「非漢字」文化を取り入れる時に、その外国語(アルファベット)の多くは「漢字熟語(翻訳語)」として、漢籍にある語や、漢字を使っての造語がされました。それは漢字という「字」そのものが意味を持っていたからです。「栄」は「さかえる」、「養」は「やしなう」というように。「 nutrition 」は「 a, b, c, ., i, n, o, r, t, u, ... 」を知っていても意味がわかりませんが「栄養」と書けば(=読めば、「聞けば」ではない)、意味がわかります。
というか、「わかったような気に」なります。「栄養は nutrition のことだよ」というのは説明になっていません。つまり、「 nutrition 」とは関係なく、「栄養」という言葉は流通していきます。なので、結局誰も(ほとんどの人が)「栄養」の意味を知らないのです。
近年は「 energy 」を「エネルギー」というカタカナ語で流通させます(格好をつけて「エナジー」という英語読みにする人もいます)。「PCR検査」とかは、アルファベットそのもので流通しています。多くの人は「きっと専門家はその意味がわかっているんだろう」と思っていますが、それが怪しいのです。
この本の著者に「栄養ってなんですか」と問うとどう答えるのでしょう。「むずかしいですね。むずかしいから勉強して、研究しているんです」と言うでしょうか。さらに問えば、「学問的には・・・」と説明してくれるでしょう。それを理解できるのは「医学会員」だけかもしれません。
この本を読んでいて、途中から「営養」でも「栄養」でもいいじゃないか、と思い始めました。少なくともそれが意味しているのは「営(営養)」でも「栄(栄養)」でもなくて「 nutrition 」だらかです。
ここからは、私が考えたことです。ちなみに、私は医学知識はゼロで、外国語は苦手なので、語学の知識もほぼゼロです。ネットでググった知識くらいしかありません。
「食べる栄養(学)」は英語で「 dietetics 」、つまり「ダイエット diet (食事)」です。それに対して著者の栄養学は「 nutrition 」(ニュートリション)、聞いたこともない単語です。元はラテン語の「 nutritio 」です。「nutrio 」は、
○ 意味乳を飲ませる、母乳で育てる、養う
○ 語源についての解説
印欧祖語 sneh-|流す|が 詳細な語源。
英語 nurse|看護師|などの派生語がある。( Goeiji 「nutrio 意味と語源【ラテン語】」)
ついでに「 nutrition 」は、
○ 意味
栄養摂取
栄養学
栄養素
○ 語源
ラテン語 nutrio|乳を飲ませる、養う|
ラテン語 -tio|こと、行為の結果|
○ 覚え方
nutrio|乳を飲ませる
-tio|こと
乳を飲ませての栄養摂取
栄養学(同「nutrition 意味と語源【英語】」)
それに対し、「 diet 」は、
○ 意味飲食物
ダイエット
に食べ物を与える
○ 語源についての解説
「日常の食事|diaeta|」が 語源から分かる 最適な覚え方。
中期英語 diet, dyet, diete|飲食、食物摂取|⇒ 古期フランス語 diete|飲食、食物摂取|⇒ ラテン語 dieta, diaeta|食事、住居、集会|⇒ 古代ギリシャ語 diaita|生活様式、住居、食物|⇒ 古代ギリシャ語 diaitao|人生を送る、生活する、取り扱う|⇒ 古代ギリシャ語 dia-|中を通って|+aitao|?|⇒ 古代ギリシャ語 ainumai|取る、つかむ、握る|の 反復動詞形 ⇒ 印欧祖語 hey-|取る|が 詳細な語源。
英語 dietary|食事の|と 同じ語源をもつ。(同、「diet 意味と語源【英語】」)
古代ギリシア語がでてきましたが、邦訳旧アリストテレス全集では「栄養」は「 τροφἠ 」の訳語として出てきます。一例を挙げます。
したがって、もし燕が巣を作り、蜘蛛が網を張り、また植物が、その果実のために葉を生やし、栄養をとるために根を上にではなく下におろしなどするのが、自然によってであるととともになにかのためにでもあるとすれば、自然によって生成し存在する物事のうちにこうした原因〔目的因〕の存することは、明白である。(アリストテレス『自然学』199a、邦訳旧全集P.76)
アリストテレスの用法は、ものが体内に入ってきて、排出される、つまり「流れる」という意味が強い気がします。その流れによって「成長」が起こるその原因です。
食べる、とか、養う、とか、成長する、とか、生活する、とか、名詞や自動詞や他動詞など広い意味がありますが、「さかえる」というニュアンスは感じません。むしろ「いとなむ」に近いのではないでしょうか。
高野長英が師事したシーボルト(Philipp Franz Balthasar von Siebold、1796年2月17日 - 1866年10月18日)が日本に来たのは、1823年です。
本来はドイツ人であるシーボルトの話すオランダ語は、日本人通辞よりも発音が不正確であり、怪しまれたが、「自分はオランダ山地出身の高地オランダ人なので訛りがある」「山オランダ人」と偽って、その場を切り抜けた。(Wikipedia「シーボルト」)
オランダのほとんどは干拓地なので「山地」はありません。
シーボルト本人がどういう思想の持ち主だったかはわかりませんが、当時のヨーロッパの学問風土を持っていたでしょう。それは「開発」「啓蒙」などの言葉で表される、「学問は(国や自分が)栄えるための礎」だという風潮です。
鳴滝塾の塾生たちも、内容は違っても同じような気風を持っていました。なので、「蛮社の獄(Wikipedia)」という事件が起きます。
本書のはじめの方に、『漢字雑談』(高島俊男著、講談社現代新書)からの引用があります。又引します(後で確認します)。『晋書』にこうあります。
趙至は、歳十三の時、師について学問をはじめた。父が畑で牛を追う声を聞いて、書を投げ出して泣いた。師がいぶかって問うと、『吾小未能栄養、使老父不免勤苦』と答えた。師は甚だ異とした。ーという話である。
その趙至少年の立派なセリフは、「私は年が小さくて(親を)栄養することができず、父に苦労をさせております(それで泣いてしまいました)」ということ。聞いた師は、これは並の子供ではない、小さいながら学問の目的をはっきりつかんでいる、と感にたえたのである。(本書P.29、原書P.24-32「営養、栄養」)
この「栄養」には、「養う」とともに「栄える(豊かになる、栄誉・地位を得る)」の意味がありそうに思えます。単に「入って出ていく流れ(代謝)」ではありません。流れ(代謝)そのものよりも、その結果としての「成長」「繁栄」の方に重きを置くとすれば、「営養」よりも「栄養」が適訳だし、当時のヨーロッパや鳴滝塾の塾生の思いに近いのではないでしょうか。
「新陳代謝」、食べて消化し、吸収し、そして排出することは、「 metabolism 」です。「メタボ」は「メタボリックシンドローム(代謝異常症候群)」。口から食べたものを胃や腸の消化器官で、消化吸収します。人間(動物)の体は、ちくわのようなもので、口から肛門までの「ちくわの穴」を食べ物や飲み物が通過します。その流れのなかで、体(ちくわ本体)が「必要なもの」を吸収します。なんでも吸収するわけでもないし、必要量だけ吸収するわけでもありません。それでも、身体は種類も量も「選択」して吸収しているはずです。「食べない」と死んでしまいますが、「食べ過ぎ」て死ぬということはめったにないでしょうから。
栄養士が選んだ食事を食べてすぐ死ぬ、ということはないと思います。でも、静脈栄養や経腸栄養は、その危険性が高まります。「選択吸収する」という身体の機能を経ないからです。極端な話、毒や「味が変なもの」、「食べすぎ・飲みすぎた時」などに「吐き出す」ということができないからです。NHKスペシャル『人体』を観ると、さまざまな臓器が複雑に関係しあっていることがわかります。血液は栄養や酸素を運ぶだけではありません。それを人間が「コントロール」しようとしているのが、現代医学や科学です。
それが「可能か」どうかの話ではありません。はじめに書いたように、義母はそれで何年も生きています。義母はもう「お腹が空いたと言う」ことはないでしょう。お腹が空いているのでしょうか。
人間は(少なくとも私は)「栄養を取るため」に食べているのではありません。「お腹が空く」から食べています。お腹が空くのは不快なことだし、苦しいことでもあります。いま、ガザ地区の人たちは「飢え」に苦しんでいると報道され続けています。では、彼らに「ビタミン剤」や「栄養剤」を送ればいいのでしょうか。そういう考えは「家も土地も与えるから、パレスチナ人を移住させる」と言うトランプ大統領の発言に近いと思います。
お腹が空いているから、食べたときの「満足感(満腹感)」があります。
「子どもたちが飢えを知らない社会を」
そういう社会が作れるのでしょうか。飢えを知らない子どもたちは、「リンゴやパンの代わりにビタミン剤や栄養剤でいい」と思うかもしれません。その子どもたちは、食べたときの「満足感」があるのでしょうか。
彼らも、お腹は減るし、満足感もあるでしょう。
どうして おなかが へるのかなけんかを すると へるのかな
なかよし してても へるもんな
かあちゃん かあちゃん
おなかと せなかが くっつくぞ
どうして おなかが へるのかな
おやつを たべないと へるのかな
いくら たべても へるもんな
かあちゃん かあちゃん
おなかと せなかが くっつくぞ(『お腹のへるうた』)
私の好きな歌です。今の子どもだって、トランプ大統領だってわかると思います。でも、その感じ方は私とはちがうかもしれません。私が「家と土地があれば、ガザに住んでいようとリビアに住んでいようと同じだ、とは思わない」ように。なにかが違うのです。人々が忘れつつ、失いつつあるなにかが。
著者なら、「食べられないなら、静脈栄養も仕方がない」と言うでしょう。私はそれを否定できません。否定できないけど、全面的に同意もできないのです。「自動車にガソリンを入れる、ガソリンではなく充電でもいい。火力でなく、原発でもいい、太陽発電が望ましい」。そうではないのです。人間は「歩ける(歩く能力・技術がある)」から、自動車に意味があります。自動車があれば歩けなくてもいい、というのではないのです。栄養を摂取できれば食べなくてもいい、ということではないのです。もちろん、著者がそう言っているのではありません。でも、社会の風潮全体が、そういう方向に進んでいる気がしてならないのです。「歩く力」「食べる力」はイリイチのいう「生きる技術」です。それは「痛む技術」や「病気になる技術」とともにあります。「お腹が減る技術」というのもあるのです。
それらが「自動車」や「静脈栄養」に置き換えられること、私はそういう風潮が向かう先が「いい」とは思えないのです。そういう私は、今は医者に通っています。前歯でしかかむことのできない生活が何ヶ月も続いています。今、とてもお腹が空いています。つまり「生きて」います。
読書中のメモが見つかりました。メモしたことも忘れる今日このごろです。いつも持ち歩いて、目につくところにあるのに。悔しいので、重複する部分もありますが、補足として書いておきます。どうせ忘れるのだから。
この本を読んでいて、自分も一緒に「栄養のルーツ」を探している気分になりました。
日本人が「栄養」をどう考えた来たのかということは、「エネルギー」と同じで、「本」をどのように考えてきたか、桜をどのように考えてきたか、山をどのように考えてきたか、ということことを探すことが、「栄養という言葉」を探す本来の意味です。ここに見つけた、あそこにあった、というのはそのための基礎に過ぎません。
同じことは動作にも言えます。見ることをどのように考えてきたか、歩くことをどのように考えてきたか。それは時代・地域によって変わるのです。「富士山が見えた(富士山を見た)」という言葉は同じでも、江戸時代の人、平安時代の人、縄文時代の人、あるいはシーボルトが心の中に思ったことは異なると思います。それは「 I see Mt.Fuji. 」でも「 I can see Mt.Fuji. 」でも「我能看到富士山」でも、「可以看到富士山」でも、「 μακρὰν ὁρῶ τὸν Φουτζι 」でもないのです(中国語・古典ギリシア語はGoogleさん)。
言葉は心の中を表すものではなく、心そのものを形作るものです。自然や自分をどう感じてきたかは言葉によって形作られるのです。
もっと言うと、思いとは別に、見るとか歩くとか栄養とかがあったわけでありません。そう考える文化もあった(ある)でしょうが、考えなくとも歩くし、栄養をとる、つまり食べるのです。だからそれを翻訳することはできません。言葉とは別に物や行動(動作)があったわけではないのですから。
この感覚を取り戻すのは不可能に近いのです。言葉を使う限り。言葉を一度使ったときから、もうそれを否定することができなくなるのです。
でも、「実際には」つねにそれを行っているのです。言語とは別に(言語化せずに)行っていることがほとんどだからです。栄養をとることも。
趙至が nutrition の意味で「栄養」を使っているのではないように、高野長英が思っていた「栄養」は、著者が考えている「栄養」とは違うと思います。佐伯矩が「営養」ではなく「栄養」としたのも、「 nutrition 」を彼の思いに近づけるためのものです。
重要なことは、どのように違うのか、なぜ違うのかであって、そのことから見えてくる「自分はなぜそう考えるのか、感じるのか」ということです。ルーツに自分の考えを押し付けたり、自分の考えに近いルーツを見つけるのは、自分の思いを強固にすることはあっても、「自分の思いのルーツ」からは遠ざかってしまうのです。
[著者等]
著者について
●愛媛県出身。昭和55 年大阪大学医学部卒業。大阪大学第一外科、国立呉病院外科にて外科研修後、大阪大学小児外科 岡田正教授に師事し、外科代謝、がん患者の栄養管理、栄養評価、カテーテル管理、在宅医療などの研究を行う。平成元年米国Duke University Medical Center 外科に留学、John P. Grant に師事し栄養管理チーム(Nutrition Support Service)に所属、グルタミン輸液と腸管機能に関する研究を行う。平成3 年11 月米国 University of Florida 外科に留学、Wiley W. Souba に師事し、肝細胞膜および腸管粘膜細胞膜におけるアミノ酸輸送システム、特にグルタミン輸送の解析に関する研究を行う。平成5 年大阪府立病院消化器一般外科、平成9 年大阪大学第一外科助手、平成13 年大阪大学大学院医学系研究科臓器制御医学専攻機能制御外科講師、平成14 年日本生命済生会付属日生病院外科部長、平成17 年医療法人川崎病院外科総括部長、平成25 年より現職。
●一般社団法人 静脈経腸栄養管理指導者協議会(リーダーズ)代表理事、血管内留置カテーテル管理研究会(JAN-VIC)代表世話人、関西PEG・栄養とリハビリ研究会代表世話人ほか
「この書で改めて医学で使う言葉というものの重みを感じた。そして栄養という言葉の歴史を辿る旅の中で、わが国の医学や医療の黎明期に貢献した偉人にも会える楽しさも揃えている。医療分野で活動されている多くの方々に、「栄養」という言葉のルーツを辿りながら、わが国の医療の歴史の一齣を読み解いてほしい」
(松田 暉:大阪大学名誉教授/日本外科学会名誉会長)
「読みながら、栄養の歴史を切り開いた先人の偉大さ、歴史的認識の誤解、人間臭さ、さらにnutrition(栄養)とdietetics(食事)の違い、医療や臨床栄養のこれからの方向性等、幅広く学ぶことができる。以前にも、このような栄養のルーツを目指した人はいたが、これほど徹底的に調べたものは見たことがない。全ての栄養関係者が読むべき本である」
(中村丁次:日本栄養士会会長/神奈川県立保健福祉大学学長)
<まえがきより>
私はもう40年以上、外科医としての診療に加え、『栄養』の正しい普及のために、学会活動、論文執筆、講演に力を注いでいる。『食』としての『栄養』ではなく、静脈栄養、経腸栄養という『人工的な栄養』管理である。(中略)
『栄養』という漢字は、おそらくはほとんどの人が、その語源やルーツなどを考えることなく使っている。なんとなく『元気の源』『身体にとって大事なもの』『生きていく上で絶対に必要なもの』などの意味で使っている。(中略)この『栄養』という漢字は、使われるようになって、わずか100年なのである。100年前は、江戸時代ではない、明治時代でもない、大正時代である。昭和の前である。平成が終わってしまったので、昭和の前の大正ははるか昔のことと思われるかもしれないが、100年前である。
その『栄養』という用語、漢字のルーツをたどる必要が出てきた。そのルーツを突き詰めなければ、『栄養』の専門家とは言えないと思ってしまったのである。私の、その「漢字『栄養』のルーツをたどる旅」におつきあいいただきたい。(井上 善文)


