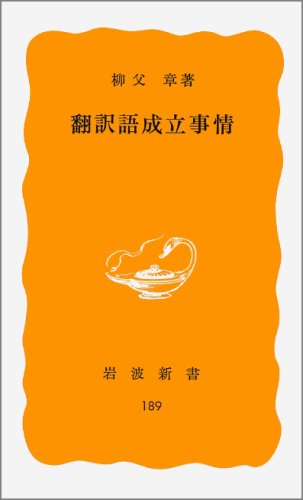
日本には「社会」も「個人」も「恋愛」もなかった?
ふだん、日本語を読んだり、聞いたり、話ししているときに「違和感」を感じたことはありませんか。なにげなく使っていることばでも、「社会って、どういう意味?」と聞かれたとき、「社会は社会だろ」と投げやりになるか、「社会とは・・・」とうんちくをたれるかするだけで、「ほんとうの意味は漠然としか分かっていない」ということは多いのではないでしょうか。
かつてsocietyということばは、たいへん翻訳の難しいことばであった。それは、第一に、societyに相当することばが日本語になかったからなのである。相当することばがなかったということは、その背景に、societyに対応するような現実が日本にはなかった、ということである。(P.3)
「鰯(イワシ)」という漢字は中国にはありません。理由は簡単で、中国(漢字が生まれた黄河の流域)にはイワシがいないからです。
でも、社会・個人・恋愛はどこの国にも、どの時代にもあったはずです。しかし、「society」「individual」「love」に相当することばも「現実」も、日本にはなかったのです。
私の違和感
「自由」や「民主主義」は「正しいこと」で「そうある(する)べきだ」という信念で、私は生きてきました。だから、私は「他人に強制されること」に反発してきました。
それは同時に、「他人に強制すること」「他人に押し付けること」を否定することでもあります。上司に逆らい、労働組合運動でも、「それはおかしい」と強硬に自分の意見を主張しながら、「他人が納得しない」ことに憤りと、諦めとを感じていました。
それを感じていないように「正義を振りかざす人」(SNSでもそういう人が多い。「賛成」の人にも「反対」の人にも)を「羨ましい」そして「馬鹿だな」と思っていました。それはそのまま自分に向い、「自己嫌悪」そのものになっていました。
その「自由」や「民主主義」に対する「違和感の正体」をいまも探っています。
翻訳・輸入文化
日本の文字は、漢字の輸入から始まりました(たぶん。それ以前に日本独特の文字があったという人もいますが)。それに日本語(やまとことば)の読みをつけました。漢字の基本は表意文字です(それ以上に表音文字でもあります)。だから「山」に「やま」という「やまとことば」の意味とその音を当てることができます(訓)。ですが、漢字といっしょに中国の「文化・思想」が輸入されました。やまとことばにない単語は、そのまま中国語の音で発音されます(音)。それは一種の「翻訳文化」です。
幕末以降、西欧の文化・思想が流れてきました。その多くは、日本になかった物、日本になかった考え方です。そして、明治の知識人は、それを漢字で表現しようとしたのです。生活に必要なものは、当然日本にもありましたから、それを新しい造語で表す必要はありません(ないはずです)。ですから、そこでつくられたり、当てはめられたりした翻訳語は日本になかった物や、思想、あるいは考え方です。その「物」が「本当に必要なもの」だったかどうかは色々な考え方があるでしょう。日本になかった思想・考え方は、生活に直結するものではありませんし、目に見えるものでもありません。つまり、抽象的なものです。
翻訳語は、先進文明を背景にもつ上等舶来のことばであり、同じような意味の日常語と対比して、より上等、より高級という漠然とした語感に支えられている。(P.20)
このころつくられた翻訳語には、こういうおもに漢字二字でできた新造語が多い。とりわけ、学問・思想の基本的な用語に多いのである。外来の新しい意味のことばに対して、こちらの側の伝来のことばをあてず、意味のずれを避けようとする意識があったのであろう。だが、このことから必然的に、意味の乏しいことばをつくり出してしまったのである。そして、ことばは、いったんつくり出されると、意味の乏しいことばとしては扱われない。意味は、当然そこにあるはずであるかのごとく扱われる。使っている人がよく分からなくても、ことばじたいが深遠な意味を本来持っているかのごとくみなされる。分からないから、かえって乱用される。文脈の中に置かれたこういうことばは、他のことばとの具体的な脈絡が欠けていても、抽象的な脈絡のままで使用されるのである。(P.22)
ことばはもともと、話す人と聞く人(書く人と読む人)の暗黙の了解で成り立ちます。「いぬ」ということばは、犬のすべてを表しているわけでありません。それでも、同じ日本の文化で育った二人なら伝わるはずです。それは、「いぬ」ということばが日本の生活にすでにとけこんでいるからです。
もっとも、「すれ違って」いることもよくあります。いまは、TV等の影響で、全国での差は縮まっていますが、「シカ」とか「クマ」ということばで描く動物の姿は、南北で違っているのではないでしょうか。ことばは、ことばだけで成り立つものではなくて、文化といっしょになって初めて意味を成すのです。
造語と転用
この本に出てくることばのうち、「社会」「個人」などは西欧語を翻訳するにあたって、作られたことばです。「自然」「自由」「彼」などは、西欧のことばに、もとからあった日本語を当てはめたものです。
翻訳にあたって作られた漢字があるのかどうかは知りませんが、前者はもとからあった漢字を組み合わせたものです。そのときに「漢字がもつ意味」は重要です。どの漢字を使うかということは、訳者の知識が重要です。外国語の知識と漢字の知識です。もともとない事物や概念を表すわけですから、その努力は大変なものです。この本にはあまり出てきませんが、西周が作った多くのことばは、勉強すればするほど「すごいな」と思わされます。その後の日本の思想界は西周の手のなかで動いているだけなんじゃないか、と思えるほどです。それは、西周がとらえた言語の意味です。私には、自分がプラトンやデカルトを勉強しようとしているのか、西周を勉強しようとしているのか、区別がつきません。西欧哲学は人によって解釈が違います。また、西欧では日常語であったものも、哲学者はそれを自分独自の意味で使います。それに、ことば自体が持つ意味合いも変化していきます。ことばは生き物のように動き続けるのです。
後者は、日本に従来からあったことばで、原語が持つ意味合いを持った日本語を当てます。ところが、前述のとおり、訳語を当てるということは、その「物」や「考え方」「概念」が日本にはなかったということです。ですから、原語の意味がそのまま当てはまることばは日本にはありません。そこには大なり小なりの差があります。それが「誤解」のもとになります。たとえば「私の自由でしょ」と「私の勝手でしょ」のように。
価値観を伴う翻訳語
この本は、主に明治以降に外国語を翻訳しようとした先人たちの苦労を描いています。口にする日がなかったとしても、聞いたり見たりしない日がないほど一般的になった「翻訳語」を取り上げています。でも、それの意味を本当にわかって使っているでしょうか。「権利は義務を伴う」とか「自由を履き違えるな」と言ったときに、「権利・人権」や「自由」を具体的に映像として思い浮かべることは難しいです。
つまり、初めに、意味の乏しい「近代」ということばの形があって、それがやがてしかるべき意味を獲得していった、というわけであり、それは、私たちにおける翻訳語の意味形成過程を、典型的に物語っているのである。(P.64)
「抽象的な脈略のままで使用」されうるのは、その抽象的概念が存在することを前提とし、そこから現実の事象を演繹的にたどるという論理と、その過程で抽象的概念が意味づけられていくという思考方法がありました。そして、現実をそのことばで判断していくのです。
こうして観念として純化された「恋愛」は、当然、日本の伝統や現実のうちに、その実現をとらえることが困難になっていく。したがって、「恋愛」は、現実に生きている意味ではなく、日本の現実を裁く規範になっていく。これは、私たちの国の翻訳語の宿命である。(P.105)
先進諸国から輸入されたことばは、高級であり、あるべき姿であるという価値観を持ちます。そして、それによって「現実の社会」や「具体的な恋愛」の良し悪しが判断されるのです。
私たちは、自分の感情を「恋愛」ということばで表すだけではなくて、「恋愛は尊いもの」という価値観を持ったり、さらに「恋愛はするべきだ」「しなくてはならない」と思い込んではいないでしょうか。
西欧語と日本語
「個人」という翻訳語について福沢諭吉は、
このような現実の根底に、福沢は、「独立して自家の本分を保つ」「人」が欠けていることを見る。それこそが「交際」の単位だからである。「権力の偏重」は、「治者」と「被治者」という「人」の「二元素」をつくりだしている。(P.38-39)
と考えました。これが、『学問のすゝめ』の「天は人の上に人を造らず人の下に人を造らず」ということばににつながっていくのだと思います。つまり、日本には「独立して自家の本分を保つ」「個人」、つまり〈自己(自我)〉というものは存在していなかったのです。「書かれた〈歴史〉」は、「権力の歴史」です。私はそこには「治者と被治者」という意識すらなかったと思います。〈自己〉がなければ「自由・平等・民主主義」などが発生するはずもありません。「民主国家」を作るためには、まず〈自己〉つまり「個人」がなければならないのです。
「幸せで満ち足りた人に、あなた方は迷える羊で救い主たるイエスを必要としているのだと得心させること。バイオラ大学での福音学の恩師、カーティス・ミッチェル博士はよく言っていた。「救いの前に彼らを迷わせなければならない」と。」(『ピダハン―― 「言語本能」を超える文化と世界観』ダニエル・L・エヴェレット著 みすず書房 P.369)西欧の近代と、キリスト教は両立します。
自己があって、そこに〈他者〉が生じます。「自己と他者」あるいは「多くの自己」が集まって、そこに「社会」が出来上がります。
「自然」についての論争を著者は、
このことから、また、natureは客体の側に属し、人為のような主体の側と対立するが、伝来の意味の「自然」とは、主体・客体という対立を消し去ったような、言わば主客未分、主客合一の世界である、といえる。(P.133)
と言っています。
ここで言われている「主体」とは、〈自己〉と同じです。中心には〈自己〉があって、それの集まりが「社会」であるように、「人間」が中心にあって、客体としての「自然(nature)」が考えらるのです。
「恋愛」は
しかし、魂と肉体とを区別して理解しようとする考え方、ものの見方がそこにはある。私たちの伝統的な「恋」や「愛」が、心と肉体を常に切離さず、一つに扱ってきたのと対象的である。(P.94)
つまり、〈自己〉というのは、自分の「魂」です。その「魂」からみれば、「肉体」は客体となるのです。「私の体が目当てだったのね」と言う発言は、この「主客分離」の世界で生じるものです。「セックスと恋愛」や「結婚と恋愛」について日本人が悩みだしたのは「明治以降の出来事」とも言えます。
これらのことばが表す「こと(事物)」が日本になかったというのは、日本には〈自己〉というものがなかったということです。「そんなことはない。どこの国だって、いつの時代だって「自分」〈私〉はあっただろう」と言われそうですが、日本に〈自己〉が輸入されたのは、百数十年前なのです。〈自己(私・自我)〉というのは、ひとつのイデオロギーなのです。このことは「いい・悪い」「進んでいる・遅れている」というものではありません。西欧と日本は「違う(違っていた)」ということです。なぜ違ったのか。
そこで、日本語では、とくに抽象的な、基本的な動詞が名詞化されにくいということ、これは重要であろうと私は考える。(P.118)
これには、深い根拠があるのであって、「存在」論や、「有」論は学問になるが、「ある」論は学問にならないのである。なぜなら、古代ギリシャ以来、哲学に限らず、学問は、名詞形の言葉を中心に組み立てられてきたからである。これには、西欧の言語構造が、深い係わりをもっている。西欧文は、名詞形の主語を必ず持ち、三人称代名詞や、関係代名詞など、名詞を中心に文を展開するようにできている。このような機能は、日本語では弱いか、またはないというべきである。(P.119)
さらに著者は、
heやsheなどの西欧文における役割は、第一に、行為の主体である主語を、常に明確にしておく、という構文上の機能である。横文字の文章では、heやsheなどは、いくらでもくり返される。言わないと分からないからではない。論理的に必要である以前に、形式上の要請であり、三人称代名詞など人称代名詞の多い文は、西欧人にとって、読者が親しみを持つ第一の条件なのである。その背後には、行為の主体を常に明言し、責任者を、個体としてとらえて明らかにしておく、という思考の構造がある。(P.204)
つまり、「言語構造(文法)」が文化に影響を与えているのです。「行為と主体」「主体と客体」「精神と肉体」などを分けて考えるのは「西欧語(インド=ヨーロッパ語)」が要請しているのです。そして、日本語にはそれがありませんでした。明治時代の翻訳者の苦悩の原因は、そこにあったのです。
やまとことば
今「学ぶ」ということが、「記憶する」ことと同義になりつつあります。より多くの本を読んで、より多くのことを覚えることが勉強するということです。そして、それを試験で「点数化」するのです。
日本は世界有数の翻訳文化です。外国語がわからない私も翻訳で十分西欧の文化に触れることができます。そして、どんどん新しいことばが使われています。近年は、新しい概念を「漢字」に翻訳せずに西欧語のまま使うことが流行っています。「セクシャリティ」や「ジェンダー」「ハラスメント」などのことばです。それらは西欧では日常語です。横文字のまま使うことで、「ふつうの意味じゃない」ということ、それが「歴史的に持つに至った意味(概念)」であることが印象付けられます。その横文字はやはり日本にはなかった「物」や「概念」です。だから、そのたびに「どういう意味で使われているのか」を考えなければならないのです。翻訳語や外来語が現れるたびに、その意味を勉強して覚えなければならないのは辛いです。考えることよりも覚えることに重点を置かざるを得ません。
さらには、「横文字にする必要がなさそう」なものも、横文字で書かれます。「ソーシャル・ディスタンス」や「ゴーツートラベル」は、どうして日本語で表さないのでしょうか。「横文字を使うとかっこいい、頭良さげに見える」という「エリート意識」はなかなか無くならないようです。
一般に、どんな翻訳語が選ばれ、残っていくのか、という問いに答えることはやさしくない。しかし、およそ、文字の意味から考えて、もっとも適切なことばが残るわけではない、ということは言えるであろう。
一つ言えることは、いかにも翻訳語らしいことばが定着する、ということである。翻訳語は、母国語の文脈の中へ立入ってきた異質な素姓の、異質な意味のことばである。異質なことばには、必ずどこか分からないところがある。語感が、どこかずれている。そういうことばは、逆に、わからないまま、ずれたままであったほうが、むしろよい。母国語にとけこんでしまっては、かえってつごうが悪いこともある。
日本語のなかで、音読みされている漢字のことばは、元来、異国の素姓のことばであった。日本語は、この異国語を、異質な素姓を残しつつ、やまとことばと混在させてきたのである。近代以後の翻訳語に、漢字二字の字音語が多いのも、この伝統の原則に自ずから従ったのである。そして、二字の字音語のうちでも、母国語にしっくりとなじむことばよりは、どこか違和感のあることばの方がよい。人々が意識的にそう選ぶのではなく、いわば、日本語という一つの言語構造が、自ずからそう働いているのである。翻訳語とは、伝来の母国語からみれば、区別されたことばである。人々が直観的に感得できるような、区別のしるしをどこかに持っていることばなのである。(P.186-187)
今まで「公文書」は漢字が多く、分かりにくい、「お役所ことば」だ、と言われてきました。それは第一義には「論理的に正しい文書」を目指したものですが、そこには「わからないまま」「曖昧さ」という要素が多くあったのかもしれません。
言語と文化
文化がことばの意味を決めます。私たちは、「ある文化」の中に生まれ、育ちます。自分が生まれる文化を選ぶことはできません。「親ガチャ」と同じです。でも、そのことばを使うのは私たちです。そして、どんどん新しいことばを作ります。「元カレ」「元カノ」ということばは、私の家にある『広辞苑』(第5版ですが)にはありませんでした。私たちが生みだしたことばは、新たな文化を生みだします。
ことばも文化も、普遍(変わらない)なものではありません。「すでに/つねに」ありながら、私たちが「どの言葉を使うか」「どういう状況で使うか」で変わっていきます。
ただ、ある「ことば」に「どういう意味を感じるか」、「どういう価値を見るか」が、どこまで既成の「文化」なのかは、とても分かりにくいのです。私にとって「自由・平等・民主主義」というのは「善いもの・正しいもの」として感じられます。そして「そうではない現実」を「腹立たしく・残念」に感じます。そうではない国(例えば、中国)に反発を覚えます。ロシアの侵攻は「悪いこと」でウクライナの抵抗は「正しいこと」だから、応援しなければならない、と感じます。
でも、もし「戦争で人が死ぬこと」が「絶対に許されないこと」だとすれば、ウクライナの大統領が決断しなければならかったのは、降伏するか逃げるかだったとも思うのです。
身近なことで言えば、私が女好きだということ。男は女を好きになるもの、あるいは好きになるべき、というのは「文化」あるいは「社会」に植え付けられた「イデオロギー」じゃないといい切ることは難しいのです。「LGBT」ということではありません。「母は子どもを愛するもの」あるいは「愛するべき」だというのはどうでしょうか。「母性本能」というやつです。これも怪しいです。「お店の商品を盗んではいけない」というのは。これは思い込みだと思います。上記の「人を殺してはいけない」というのは。これはよくわかりません。でも、牛や豚は殺して食べるのだから、なぜ人間はだめなのかは明確ではありません・・・
物心ついたときから、「これはだめ」「これは正しい」「こうするべきだ」等を親や学校から教わりました。60歳を過ぎてから、自分が「当たり前だ」と思ってきたこと、怒りなどの自分の感情を引き起こすもの、を一つ一つ疑っています。デカルトのような境地になれるかどうかはわかりません。デカルトが頼りにした「数学的公理」すら、私には「疑いの対象」です。「論理(西欧論理)」そのものを疑っているからです。
この本に出てくる「翻訳語」は、その一つ一つを考えると、どうも私にとって「明確」だとは言えないようです。その他に、「正義」や「民主主義」なども「明確」ではありません。抽象的なことばなので、具体的なものが浮かばないのは当然です。
「一般化」は具体的なものかは始まっているので、分かります。「ねこ」というのは「三毛」や「たま」などの具体的なものから帰納的に得られたものです。でも、抽象的なことばが具体性を欠いているのは、それが「日常的な」ことばではないからです。まず、ことばが先にあって、そこから演繹的に具体的なものがあります。
これが本書の著者のいう「翻訳的演繹論理の思考」(P.40)です。これは、「イデア論批判」に通じます。
少なくとも基本的な態度として、一つの普遍的な観念としての「美」を先に立て、その特殊な場合として日本的「美」がある、という思考方法は間違いである、と私は考えるのである。(P.72)
そして、著者は言います。
人がことばを、憎んだり、あこがれたりしているとき、人はそのことばを機能として使いこなしてはいない。逆に、そのことばによって、人は支配され、人がことばに使われている。価値づけして見ている分だけ、人はことばに引きまわされている。(P.46-47)
今日、『映像の世紀バタフライエフェクト「ヒトラーVSチャップリン 終わりなき闘い」 』を観ました。この作品は、数年前ならチャプリンに対する私のあこがれ、ヒトラーに対する憎悪、を強めて私は号泣していたでしょう。でも、私は「自由」「民主主義」あるいは「共産主義」「ファシズム」ということばを、「あこがれ」や「憎悪」、つまり感情として使っていなかったでしょうか。「ねこ」が好きな人も、猫アレルギーの人もいるでしょう。でも、「ねこ」ということばで浮かんでくる感情と、「民主主義」「ファシズム」ということばで抱く感情は違いませんか。
私が「民主主義は正義(正しい)」「民主主義にならなければいけない」という思いに対するある種の違和感、「正しい」「〜する(ある)べき」あるいは「倫理」に対する私の違和感の正体の一つは、これなのかもしれません。
敵国語、言葉狩り
この翻訳用日本語は、たしかに便利であった。が、それを十分認めたうえで、この利点の反面を見逃してはならない、と私は考えるのである。つまり、翻訳に適した漢字中心の表現は、他方、学問・思想などの分野で、翻訳に適さないやまとことば伝来の日常表現を置き去りにし、切り捨ててきた、ということである。そのために、たとえば日本の哲学は、私たちの日常に生きている意味を置き去りにし、切り捨ててきた。日常ふつうに生きている意味から、哲学などの学問を組み立ててこなかった、ということである。それは、まさしく、三五〇年ほど前、ラテン語ではなくあえてフランス語で『方法序説』を書いたデカルトの試みの基本的態度と相反するのであり、さらに言えば、ソクラテス以来の西欧哲学の基本的態度と相反するのである。(P.124)
「ことばに引きまわされ」ないために、自分の考えていることを「やまとことば」で表現してみるといいかもしれません。デカルトに倣って、漢字の音読みを止めて、全部「訓」で自分の考えを表現して見るようなものです。私にはとてもできません。言語学をやっている学者にも難しいのではないでしょうか。
私は別に、「西欧語を使うな」と言っているわけではありません。戦時中の「敵国語を使うな」という標語どおりなら、中国と戦争になった時には「漢字を使うな」ということになるのでしょうが、それは多分不可能です。
最近、「言葉狩り」が気になります。実体がまるで変わらず、呼び方だけを変えるものです。たとえば差別語であれば、新しい呼び名が「徴」を得るのです。また、呼び名を変えることで、実体を隠蔽することもあります。昨日聞いたことばで「コーポレート・ガバナンス」というのがあります。「会社を監視する」と説明のアナウンスがありましたが、「ガバナンス」が持つニュアンスを隠蔽していると思います。
この本が書かれて40年が経ちます。その間にことばは変化しています。「社会」や「恋愛」の「存在」を疑う人はどんどん少なくなっています。英語が英語の発音のまま(翻訳されずに)、どんどん使われ始めています。それらがやまとことばのような「現実に生きている意味」(P.105)を持つことは難しいと思います。でも、そういう言葉を使うことによって、人々の思考方法が変わっていくことは大いにあり得ると思います。
[著者等]
柳父 章(やなぶ あきら、1928年6月12日 - 2018年1月2日)は、翻訳語研究者、比較文化論研究者。桃山学院大学名誉教授。本名・章新(ゆきよし)。
まえがき
「日本の学問・思想の基本用語が、私たちの日常語と切り離されているというのは、不幸なことであった。しかし、それには漢字受容以来の、根の深い歴史の背景がある。他面から見れば、翻訳語が日常語と切り離されているおかげで、近代以後、西欧文化の学問・思想などを、とにもかくにも急速に受け入れることができたのである。ところが同時に、そこには、本書の至る所で述べているように、いろいろとかくれた歪みが伴っていた。」(P.ii)
1 社会 ーーsocietyを持たない人々の翻訳法
「しかし、かつてsocietyということばは、たいへん翻訳の難しいことばであった。それは、第一に、societyに相当することばが日本語になかったからなのである。相当することばがなかったということは、その背景に、societyに対応するような現実が日本にはなかった、ということである。」(P.3)
「「交際」は、ここで、「人間」にも、「家族」にも、「君臣」にも通じるような上位の概念として抽象化されているのである。」(P.11)
「だが、福沢の思考方法は、societyの概念を初めに置いて、そもそも近代市民社会とは、などというように、そこから天降(あまくだ)ってくるような、分析、批評ではなかった。いわゆる演繹的な分析、批評ではない。その逆である。日本人が日常ふつうのことば感覚を通して理解できる概念が、その根拠である。そこから出発し、ことば使いの構成の工夫を通じて、意味の矛盾を引出し、その矛盾によって新しい意味を造りだしていく。それは、単にことばの上だけでの工夫ではなく、現実に生きている意味の重みを負ったことばを操作し、組み立てていく。その彼方に、societyにも匹敵するような「交際」の意味の展望を切り開こうとするのである。」(P.12)
「livertyに対立するものとしてsocietyに着眼したことは、ミルの発見であり、新しい時代の先覚者としての業績でもあった。」(P.13)
「つまり、それは肯定的な価値をもっており、かつ意味内容は抽象的である、と。」(P.19)
「翻訳語は、先進文明を背景にもつ上等舶来のことばであり、同じような意味の日常語と対比して、より上等、より高級という漠然とした語感に支えられている。」(P.20)
「このころつくられた翻訳語には、こういうおもに漢字二字でできた新造語が多い。とりわけ、学問・思想の基本的な用語に多いのである。外来の新しい意味のことばに対して、こちらの側の伝来のことばをあてず、意味のずれを避けようとする意識があったのであろう。だが、このことから必然的に、意味の乏しいことばをつくり出してしまったのである。(LF)そして、ことばは、いったんつくり出されると、意味の乏しいことばとしては扱われない。意味は、当然そこにあるはずであるかのごとく扱われる。使っている人がよく分からなくても、ことばじたいが深遠な意味を本来持っているかのごとくみなされる。分からないから、かえって乱用される。文脈の中に置かれたこういうことばは、他のことばとの具体的な脈絡が欠けていても、抽象的な脈絡のままで使用されるのである。」(P.22)__気をつけよう(汗)
2 個人 ーー福沢諭吉の苦闘
「ところで、「人」ということばは、ごくふつうの日本語であるから、indeividualの翻訳語として使われると言っても、それ以外にもよく使われる。他方、individualということばは、ヨ(FF)ーロッパの歴史の中で、たとえばmanとかhuman beingなどとは違った思想的な背景を持っている。それは、神に対してひとりでいる人間、また、社会に対して、窮極的な単位としてひとりでいる人間、というような思想とともに口にされてきた。」(P.32-33)
「こういう新たなことば使い、構文の中で、「穏やかなる日本語」の意味も変質する。「人」は「天」の前における独立したひとりの存在となり、「交際」は、目に見えぬ範囲の多数の人々との平等な人間関係を意味するように変えられていくのである。」(P.35)
「だが、こういう新しい文字の、いわば向こう側に、individualの意味があるのだ、という約束がおかれることになる。が、それは翻訳者が勝手においた約束であるから、多数の読者には、やはり分からない。分からないのだが、長い間の私たちの伝統で、むずかしそうな漢字には、よく分からないが、何か重要な意味があるのだ、と読者の側でもまた受け取ってくれるのである。(LF)日本語における漢字の持つこういう効果を、私は「カセット効果」と名づけている。カセッ(FF)ト cassette とは小さな宝石箱のことで、中味が何かは分からなくても、人を魅惑し、惹きつけるものである。」(P.36-37)
「が、福沢は、西洋文明の先進性を十分認めながら、他方、いつでも日本の現実に生きていたことばから出発して、そこからことばを組み立て、その彼方に文明の展望を開こうとしていたのである。」(P.38)
「さらに福沢は、同書の中で、この「権利の偏重」の現実を、熱烈に説き続ける。従来の歴史が知者の歴史であって、被治者「人民」の歴史が書かれていないこと、宗教・学問が、被治者の立場を忘れていることなど、日本の過去と現実を厳しく弾劾していく。(LF)このような現実の根底に、福沢は、「独立して自家の本分を保つ」「人」が欠けていることを(FF)見る。それこそが「交際」の単位だからである。「権力の偏重」は、「治者」と「被治者」という「人」の「二元素」をつくりだしている。」(P.38-39)
「この思考の行き詰まりのところで、「独一個人」という翻訳語が登場した。それは、あたかも思考の困難を解決するかのごとく現われている。この未知のことばに、それから先は預ける。前述の「カセット効果」に期待するのである。ことばは正しい、誤っているのは現実の方だ、というところで、一見、問題は解決したかのごとき形をとる。それは、以後今日に至るまで、私たちの国の知識人たちの思考方法を支配してきた翻訳的演繹論理の思考であった。」(P.40)__自由・平等・民主主義
3 近代 ーー地獄の「近代」、あこがれの「近代」
「ことばがこうして、いいとか、悪いとか価値づけされて受けとめられている、ということは、ことばが、人間の道具として使いこなされているのではなく、逆に、何らかの意味で、ことばが人間を支配している、ということを示している、と考える。」(P.46)
「人がことばを、憎んだり、あこがれたりしているとき、人はそのことばを機能として使いこ(FF)なしてはいない。逆に、そのことばによって、人は支配され、人がことばに使われている。価値づけして見ている分だけ、人はことばに引きまわされている。」(P.46-47)__Nota bene!!
「つまり、初めに、意味の乏しい「近代」ということばの形があって、それがやがてしかるべき意味を獲得していった、というわけであり、それは、私たちにおける翻訳語の意味形成過程を、典型的に物語っているのである。」(P.64)
4 美 ーー三島由紀夫のトリック
「きわめて簡単明瞭なことなのであるが、近代以前、日本では、「美」ということばで、今日私たちが考えるような「美」の意味を語ったことはなかったからである。beautyやbeantéやSchönheitなどは、西欧の詩人や画家などが、作品を具体的に制作する過程で、立止って考えるときに口にすることばなのである。」(P.69)
「しかし、私がすでに述べたような、違っている、という面もやはり重要である。そしてこの違いは、日本的「美」意識の特殊性とか、西欧の「美」と日本の「美」との違い、というように、「美」を前提としてとらえてはならない、と私は考える。少なくとも基本的な態度として、一つの普遍的な観念としての「美」を先に立て、その特殊な場合として日本的「美」がある、という思考方法は間違いである、と私は考えるのである。」(P.72)__微妙ですね。観念としての普遍的な「美」の存在を前提として、演繹的に考えてはいけないということ。イデアは存在しない、ということ。
「始源の意味の形成過程には、ふた通りある。一つは、ともに書き、それを示し合う人々の間につくられていく意味である。たとえば、ここでレビィ・ストロースと酋長との間で、不完全な姿ではあるが、暗黙のうちに、しだいに了解されていくような意味である。(LF)もう一つは、もっぱら書き、それを示す人と、自ら書かず、示される人々との間に成り立っていく意味である。(LF)この前者の意味は、言わば民主的意味であるが、後者は、権力支配的な、階級的な意味である。」(P.84)__文字がそういう性格を持っているのはそのとおりだ。でも、ことばの意味は文字とは別に成り立つ。
「その文字は、意味によるよりも、まずその「くねくねとした」不可解な形によって人々を惹きつけ、貴重であるとされ、独占されたのである。」(P.85)
5 恋愛 ーー北村透谷と「恋愛」の宿命
「この翻訳語「恋愛」によって、私たちはかつて、一世紀ほど前に、「恋愛」というものを知った。つまり、それまでの日本には、「恋愛」というものはなかったのである。(LF)しかし、男と女というものはあり、たがいに恋しあうということはあったのではないか。万葉の歌にも、それは多く語られている。そういう反論が当然予想されよう。その通りであって、それはかつて私たちの国では、「恋」とか、「愛」とか、あるいは「情」とか「色」とかいったことばで語られていたのである。が、「恋愛」ではなかった。」(P.89)
「しかし、魂と肉体とを区別して理解しようとする考え方、ものの見方がそこにはある。私たちの伝統的な「恋」や「愛」が、心と肉体を常に切離さず、一つに扱ってきたのと対象的である。」(P.94)
「おそらく当時の日本人が、初めて、いわば堂々として肯定できるような「恋愛」を教えられたのである。それはまず、ことばとしてやってきた。とにかく大事なもの、立派なことである。その意味・内容については、まだよく分からない。が、とにかく大事である。」(P.98)
「こうして観念として純化された「恋愛」は、当然、日本の伝統や現実のうちに、その実現をとらえることが困難になっていく。したがって、「恋愛」は、現実に生きている意味ではなく、日本の現実を裁く規範になっていく。これは、私たちの国の翻訳語の宿命である。」(P.105)
6 存在 ーー存在する、ある、いる
「哲学における「存在」論の中心テーマは、石ころが「存在」するとか、人類が「存在」するとかではなくて、人間の、自分自身の「存在」にある。」(P.111)
「すなわち、「存」は、人間主体の行動として、時間的推移とともにある、という意味をもつ。(LF)(FF)また、「在」は、在宿、在宅、在郷、在世というように、空間的・社会的にある、主体的に行動する者が、人間関係においてあることを表している。」(P.111-112)
「そこで、日本語では、とくに抽象的な、基本的な動詞が名詞化されにくいということ、これは重要であろうと私は考える。」(P.118)
「これには、深い根拠があるのであって、「存在」論や、「有」論は学問になるが、「ある」論は学問にならないのである。なぜなら、古代ギリシャ以来、哲学に限らず、学問は、名詞形の言葉を中心に組み立てられてきたからである。これには、西欧の言語構造が、深い係わりをもっている。西欧文は、名詞形の主語を必ず持ち、三人称代名詞や、関係代名詞など、名詞を中心に文を展開するようにできている。このような機能は、日本語では弱いか、またはないというべきである。」(P.119)
「この翻訳用日本語は、たしかに便利であった。が、それを十分認めたうえで、この利点の反面を見逃してはならない、と私は考えるのである。つまり、翻訳に適した漢字中心の表現は、他方、学問・思想などの分野で、翻訳に適さないやまとことば伝来の日常表現を置き去りにし、切り捨ててきた、ということである。そのために、たとえば日本の哲学は、私たちの日常に生きている意味を置き去りにし、切り捨ててきた。日常ふつうに生きている意味から、哲学などの学問を組み立ててこなかった、ということである。それは、まさしく、三五〇年ほど前、ラテン語ではなくあえてフランス語で『方法序説』を書いたデカルトの試みの基本的態度と相反するのであり、さらに言えば、ソクラテス以来の西欧哲学の基本的態度と相反するのである。」(P.124)__Nota bene!!この本は原語が持つ意味を書いた本ではなく、翻訳語とは日本(語)にとってどういう意味があるのかを書いている。和語と漢語。やまとことばで哲学は可能か。
7 自然 ーー翻訳語の生んだ誤解
「第一に、伝来の「自然」は人為と対立し、両立しない。「自然」であるとは、人為的ではない、ということである。一方、natureは、人為art、Kunstと対立するが両立する。と言うよりも、たがいに補い合っている。natureの世界は、artの世界と、対立しつつ補い合う関係である。」(P.133)
「このことから、また、natureは客体の側に属し、人為のような主体の側と対立するが、伝来の意味の「自然」とは、主体・客体という対立を消し去ったような、言わば主客未分、主客合一の世界である、といえる。」(P.133)__artは「技術」でもある。リンゴと家はどちらも必要であり補い合っているのであって、対立するものではない。
「また、巌本や花袋が、意識的にはnatureと同じと思いながら、伝来の「自然」の意味を動かしがたかったように、ことばの意味は、使用する人の意識をも超えた事実なのである。」(P.145)
8 権力 ーー権利の「権」、権力の「権」
「もちろん、改めてこの「訳字」は「原意を尽くすに足」りるのか、と問われれば、否定する人も少なくないだろう。だが、ことばが現実に使用されていく家庭は、使用者の意識を超えているのである。それは、翻訳語を含むことばの構造が私たちに働きかけ、意識を左右しているのであって、「訳字」というものは「原意を尽くすに足」りるはずであるかのごとく働くのである。」(P.155)
「rightとは、元来抽象的な、目に見えない観念であって、たとえ具体的な運動はつぶされても、それとは別に人々の精神のうちに残っていくはずである。自然法や自然権の西欧における歴史た、それを物語っている。」(P.171)
「rightとか、福沢諭吉の「通義」が、道徳的な正しさと意味のつながりを保っているのに対して、私たちの「権」には、どこか、力づくの、押しつけがましさ、というような語感がぬぐい切れない。」(P.172)
9 自由 ーー柳田国男の反発
「「自由」ということばは、正しく理解されればいい意味であり、「はき違え」て理解されれば悪い意味になる、というように、私たちは漠然と考えがちであるが、そうではない、と私は考える。問題は、理解の仕方にあるのではない。母国語の中に深い根をおろして歴史を担っていることばは、「はき違え」ようがないのである。(LF)「はき違え」られている「自由」は、翻訳語「自由」である。(LF)近代以後の私たちの「自由」ということばにも、英語で言えばfreedomやlibertyのような西洋語の翻訳語としての意味と、伝来の漢字のことば「自由」の意味とが混在しているのである。そして単純化して言えば、西欧語の翻訳語としての「自由」はいい意味、伝来の「自由」は悪い意味である。」(P.177)
「一般に、どんな翻訳語が選ばれ、残っていくのか、という問いに答えることはやさしくない。しかし、およそ、文字の意味から考えて、もっとも適切なことばが残るわけではない、ということは言えるであろう。(LF)一つ言えることは、いかにも翻訳語らしいことばが定着する、ということである。翻訳語は、母国語の文脈の中へ立入ってきた異質な素姓の、異質な意味のことばである。異質なことばには、必ずどこか分からないところがある。語感が、どこかずれている。そういうことばは、逆に、わからないまま、ずれたままであったほうが、むしろよい。母国語にとけこんでしまっては、(FF)かえってつごうが悪いこともある。(LF)日本語のなかで、音読みされている漢字のことばは、元来、異国の素姓のことばであった。日本語は、この異国語を、異質な素姓を残しつつ、やまとことばと混在させてきたのである。近代以後の翻訳語に、漢字二字の字音語が多いのも、この伝統の原則に自ずから従ったのである。そして、二字の字音語のうちでも、母国語にしっくりとなじむことばよりは、どこか違和感のあることばの方がよい。人々が意識的にそう選ぶのではなく、いわば、日本語という一つの言語構造が、自ずからそう働いているのである。翻訳語とは、伝来の母国語からみれば、区別されたことばである。人々が直観的に感得できるような、区別のしるしをどこかに持っていることばなのである。」(P.186-187)__学校で教えてほしい。少なくとも、学者には知っていてほしい。私が知らなかっただけで、学者はみんな知っているのかな。
10 彼、彼女 ーー物から人へ、恋人へ
「第一に、heは三人称代名詞だが、「彼」はもともと指示代名詞である。日本語には、三人称代名詞は元来なかったし、今日でも、実はないと言った方がよい、と私は考える。このことは、私たち日本人にとって、とくに外国語教育を十分受けた人ほど、意外に分かりにくいようである。」(P.197)
「heという人間は、Iやyouという人間と、対等に対立している。ところが、「彼」は、コレやソレよりも縁の遠いものである。意味が薄くなる。価値が低い。たとえば、ある人を指して、今日でも「アレ」と言うことがあるが、見下(みくだ)したような調子が含まれている。「彼」の場合も、もとはそうであった。」(P.198)
「「彼」ということばの近代以後における意味の変化や発達は、第一に翻訳語として使われたためであり、次いで、翻訳文をお手本として日本語の文章が変化し、その新しい文章のなかで使われるようになったためである。」(P.199)
「「彼」という翻訳語は、「空白」をうめるように日本文に入ってきたのではなく、よけいなことばとして侵入してきたのだ、と私は考える。」(P.202)
「heやsheなどの西欧文における役割は、第一に、行為の主体である主語を、常に明確にしておく、という構文上の機能である。横文字の文章では、heやsheなどは、いくらでもくり返される。言わないと分からないからではない。論理的に必要である以前に、形式上の要請であり、三人称代名詞など人称代名詞の多い文は、西欧人にとって、読者が親しみを持つ第一の条件なのである。その背後には、行為の主体を常に明言し、責任者を、個体としてとらえて明らかにしておく、という思考の構造がある。」(P.204)__どこかの町長の謝罪会見。「一般論ですが」「と思う」
「もう一つ、主語が表しにくい場合が、日本語にはある。たとえば日本語固有の「自発の助(FF)動詞」が使われる場合が一例である。私が本書のような文章を書いていて、「・・・と私は考える」と書けば、言ったことに全責任を追わなければならないが、「・・・と考えられる」と書くと、なんとなく責任が軽減されるようであり、やや自信のないときは、つい使いたくなる。」(P.204-205)__よく分かります。(笑)


