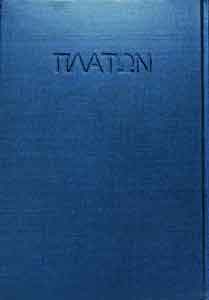四
「ぼくは、あのデルポイの社の銘が命じている、われみずからを知るということがいまだにできないでいる。」(P.138)
五
「ところが、土地や樹木は、ぼくに何も教えてくれようとはしないが、町の人たちは何かを教えてくれる、というわけなのだ。」(P.140)__人しか見ないソクラテス。日下部吉信
六
(パイドロス)「じっさい、恋をしている人たち自身でも、自分が正気であるというよりはむしろ病気の状態にあることを認め、また、自分の精神の乱脈ぶりを知りながらも、ただ自己を支配することができないのだということを、認めているのだから。」(P.142)
七
(パイドロス)「なぜならば、恋する者たちは数多くの事柄に苛立ち、何かあれば、それはすべて自分の損害になるとみなすからである。彼らが、自分の恋人が他の人々と交わるのをはばもうとするのも、そのためにほかならない。」(P.144)
八
(パイドロス)「そしてつぎに、恋する者の多くは、恋人の性格を識(し)ったり、またその他一般に恋人の身の上の事柄に通じたりするより前に、まずその肉体をほしがるものだ。だから、ひとたびその欲望がさめたとき、彼らがなおも恋人たちと親しくすることを望むかどうかは疑問である。」(P.145)
一四
「さて、そもそも〈恋〉とは、一つの欲望であるということは、だれにも明らかな事実である。しかし他方、われわれはまた、恋をしていない者でも、美しいものに対して、やはり欲望をもつことを知っている。そうすると、いったいわれわれは何によって、恋している者と恋していない者とを区別したらよいのであろうか。(LF)ここでひるがえって、次のことに注意する必要がある。それは、われわれひとりひとりの中には、何かわれわれを支配しみちびく二つの種類の力があって、われわれはこの二つのものがみちびくままに、その方に向かってついていくものだ、ということである。その一つは、生まれながらにして具わっている快楽への欲望、もう一つは、最善のものを目ざす後天的な分別の心である。われわれの心の中では、この二つが、互いに相和するときもあるが、互いに相争うときもある。そして、あるときには一方が、あるときには他方が勝利を得るの。で、その場合、分別の心がわれわれを理性の声によって最善のものの方へとみちびいて、勝利を得るときには、この勝(FF) 利に〈節制〉という名があたえられ、これに対して、欲望がわれわれを盲目的に快楽のほうへと惹きよせて、われわれの中において支配権をにぎるときは、この支配に〈放縦〉という名があたえられている。」(P.157-158)
「さて、どのような欲望を目標において以上すべての事柄を述べてきたかということは、もうほとんど明らかだといってもよいが、しかし言葉に表現されたほうが表現されないままでいるよりも、何といっても明確になるだろう。つまり、こういうことなのだ。ーー盲目的な欲望が、正しいものへむかって進む分別の心にうちに勝って美の快楽へとみちびかれ、それがされに、自分と同族のさまざまな欲望にたすけられて、肉体の美しさを目指し、(FF) 指導権をにぎりつつ勝利を得ることによって勢いさかんに(エローメノース)強められる(ローステイサ)とき、この欲望は、まさにこの力(ローメー)という言葉から名前をとって、〈恋〉(エロース)と呼ばれるにいたった、と」。」(P.158-159)__言葉が欲望(快)を明確にする。節制する言葉と快(両方)を強める言葉。肉体から言葉へ。言葉から肉体へ。言葉と肉体(肉体と言葉)は近い。
ディテュランボスは、ディオニュッソス(バッコス)を讃える歌の形式。(P.159、注)
一五
「さて、欲望に支配され、快楽の奴隷となっている者が、その恋する相手を、できるだけ自分にとって快いものに仕立てあげるのは、けだし必定のことであろう。しかるに、ひとが病んでいるときには、すべて自分にさからわないものが快く、逆に自分より力づよいもの、等しい力をもったものはいとわしい、だから、恋する者は、愛人が自分より力づよい者であるのも、自分と等しい力をもった者であるのも、がまんする気にならないで、つねに、相手を自分より劣った、力の弱い人間に仕上げることになる。」(P.160)
「だから、恋する者は必然的に嫉妬ぶかくならざるをえない。」(P.161)
一六
(P.162)__私のことだ!
「すなわち彼は、自分の恋人が、父もなく、母もなく、身内の者もなく、友だちもいないことをのぞむだろう。彼はそういう人たちを、恋人とのまたとなく楽しい交わりを非難する邪魔者であるとみなすからだ。」(P.162)
「こ(FF)のゆえに、恋する者が愛人に財産があるのをこころよく思わず、逆に財産がなくなればよろこぶのは、まったく必然の道理なのだ。」(P.162-163)
一七
「しかしこういった連中とても、少なくともその日その日かぎりのことだけなら、こよなき悦楽をあたえてくれる人種なのである。(LF)ところがこれにひきかえ、恋する者ときたら、その寵愛をうける者にとっては、ただ有害であるばかりか、ともに日をすごす相手として、およそこれくらい不愉快なものはない。なぜならば、すでに古いことわざにも、『齢(よわい)同じならざれば、たのしみも同じからず』とあるではないか。これは思うに、年ごろが同じであれば、互いに似かよっているために同じ楽しみへとさそわれて、親しみがわくからであろう。」(P.163)
一八
「そして、恋する者の愛情とは、けっしてまごころからのものではなく、ただ飽くなき欲望を満足させるために、相手をその餌食とみなして愛するのだということを、知らなければならない。」(P.166)
二二
「しかしながら、実際には、われわれの身に起こる数々の善きものの中でも、その最も偉大なるものは、狂気を通じて生まれてくるのである。もちろんその狂気とは、神から授かって与えられる狂気でなければならないけれども。」(P.174)
二四
「魂はすべて不死なるものである。」(P.177)
「このようにして、自分で自分を動かすものは、動の始原であり、それは滅びることもないし、生じることもありえないものなのである。」(P.178)__ヘラクレイトス批判。
二五
「そこで、魂の似すがたを、翼を持った一組の馬と、その手綱をとる翼を持った馭者とが、一体になってはたらく力であるというふうに、思いうかべよう。」(P.179)
「魂は全体として、魂なきものの全体を配慮し、時によりところによって姿を変えながら、宇宙をくまなくめぐり歩く。その場合、翼のそろった完全な魂は、天空たかくに翔けあがって、あまねく宇宙の秩序を支配するけれども、しかし、翼を失うときは、何らかの固定にぶつかるまで下に落ち、土の要素からなる肉体をつかまえて、その個体に住みつく。つかまえられた肉体は、そこに宿った魂の力のために、自分で自分を動かすようにみえるので、この魂と肉体とが結合された全体は『生けるもの』と呼ばれ、そしてそれに『死すべき』という名が冠せられることになったのである。」(P.180)
二六
「神にゆかりのある性質ーーそれは、美しきもの、知なるもの、善なるもの、そしてすべてこれに類するものである。したがって、魂の翼は、特にこれらのものによって、はぐくまれ、成長し、逆に、醜きもの、悪しきもの、そしていま言ったのと反対の性質をもったもろもろのものは、魂の翼を衰退させ、滅亡させる。」(P.181)
「まことに、この天のかなたの領域に位置を占めるもの、それは、真の意味においてあるところの存在ーー色なく、形なく、触れることもできず、ただ、魂のみちびき手である知性のみが観ることのできる、かの〈実有〉である。真実なる知識とはみな、この〈実有〉についての知識なのだ。」「一めぐりする道すがら、魂が観得するものは、〈正義〉そのものであり、〈節制〉であり、〈知識〉である。この〈知識〉とは、生成流転するような性格をもつ知識ではなく、また、いまわれわれがふつうあると呼んでいる事物の中にあって、その事物があれこれと異なるにつれて異なった知識となるごとき知識でもない。まさにこれこそほんとうの意味であるものだという、そういう真実在の中にある知識なのである。」(P.183)
二九
一万年、三千年
「なぜかというと、人間がものを知る働きは、人呼んで〈実相〉(エイドス)というものに則して行われなければならない、すなわち、雑多な感覚から出発して、思考の働きによって総括された単一なるものへと進み行くことによって、行われなければならないのであるが、しかるにこのことこそ、かつてわれわれの魂が、神の進行について行き、いまわれわれがあると呼んでいる事物を低く見て、真の意味においてあるところのものへと頭をもたげたときに目にしたもの、そのものを想起することにほかならないのであるから。」(P.187)
「人間はじつにこのように、想起のよすがとなる数々のものを正しく用いてこそ、つねに完全なる秘儀にあずかることになり、かく(FF)てただそういう人のみが、言葉のほんとうの意味において完全なる人間となる。しかしそのような人は、人の世のあくせくとしたいとなみをはなれ、その心は神の世界の事物とともにあるから、多くの人たちから狂える者と思われて非難される。」(P.187-188)
三〇
「ーーこの狂気こそは、すべての神がかりの状態のなかで、みずから狂う者にとっても、この狂気にともにあずかる者にとっても、もっとも善きものであり、またもっとも善きものから由来するものである、そして、美しき人たちを恋い慕う者がこの狂気にあずかるとき、その人は『恋する人』と呼ばれるのだ、と。」(ママ、P.188)
「そのとき、きよらかな光を見たわれわれもまたきよらかであり、肉体(ソーマ)と呼ぶこの魂の墓(セーマ)、いま牡蠣のようにその中にしっかりと縛りつけれれたまま、身につけてもちまわっているこの汚れた墓に、まだ葬られずにいた日々のことであった・・・」(ママ、P.190)
三一
「というのは、われわれにとって視覚こそは、肉体を介してうけとる知覚の中で、いちばんするどいものであるから。〈思慮〉は、この視覚によって目にはとらえられない。もしも〈思慮〉が、何か〈美〉の場合と同じような、視覚にうったえる自己自身の鮮明な映像をわれわれに提供したとしたら、恐ろしいほどの恋ごころをかり立てたことであろう。そのほか、魂の愛をよぶべきさまざまの特性についても、同様である。しかしながら、実際には、〈美〉のみが、ただひとり〈美〉のみが、最もあきらかにその姿を顕わし、最もつよく恋ごころをひくという、このさだめを分けあたえられたのである。」(p.190)__〈美〉は社会によって作られる。〈美というもの〉はない。
「そこで、この魂が、少年にそなわる美をまのあたりに見つめながら、そこから流れてやってくる粒子をーーこのように粒子(メレー)の流れ(ロエー)の放射(ヒーエナイ)であるがゆえに、それは『愛の情念』(ヒーメロス)と呼ばれるのであるがーーこの愛情を受け入れて、うるおいをあたえられ、熱くなるときは、魂はそのもだえから救われて、よろこびにみたされることになる。」(P.192)__少年愛
「これにまさる善きものは、人間的な正気も、神のさずける狂気も、決して人間に対して与えることはできないのだ。」(P.202)__理性=倫理、つつしみ=徳
三九〜
(P.206~)__文を書くこと、話を作ること
四二〜
(パイドロス)「ほんとうの意味で正しい事柄ではなく、群衆にーー彼らこと裁き手となるべき人々なのですがーーその群衆の心に正しいと思われる可能性のある事柄なのだ。」(P.213)__ソフィスト
「しかるに、狂気には二つの種類があって、その一つは、人間的な病によって生じるもの、もう一方は、神に憑かれて、規則にはまった慣習的な事柄をすっかり変えてしまうことによって生じるものであった。」(P.230)
五〇
「このぼくはね、パイドロス、話したり考えたりする力を得るために、この分割と総合という方法を、ぼく自身が恋人のように大切にしているばかりでなく、まただれかほかの人が、ものごとをその自然本来の性格に従って、これを一つになる方法へ眺めるとともに、また多に分かれるところまで見るだけの能力をもっている(FF)と思ったならば、ぼくはその人のあとを追うのだ、「神のみあとを慕うごとく、その足跡をたどりつつ」ね。さらにまた、ほくは、このことを実行できる人たちのことを、正しい呼び方かどうかは神のみが知りたもうところとして、とにかくこれまでのとこころ、哲学的問答法(ディアレクティケー)を身につけたものと呼んでいるのだ。」(P.232-233)
五四
「およそ技術のなかでも重要であるほどのものは、ものの本性についての、空論にちかいまでの詳細な議論と、現実遊離と言われるくらいの高遠な思索とを、とくに必要とする。」(P.242)
知性(ヌゥス)(P.242)
「どちらの場合においても、取りあつかう対象の本性をーー医者の場合には身体の本性を、弁論術の場合には魂の本性をーー分析しなければならない。」(P.243)__魂=理性?
五五
(P.245)__個々人の魂=ego=理性?
五六
「「狼の言い分でさえ聞いてやるべきだ」」「悪いものでも自分の立場を弁明する権利があるという意味のことわざ。その由来は、羊飼いが食事に羊の肉を食っているのを狼が見て、「自分があれと同じことをしたらどんな騒ぎになるだろう」と言ったという話。」(P.249、注)
五九
「ただしその真意は、彼ら古人だけが知るところだけれどもーー。」(P.254)__歴史と解釈。話すことと書くこと
「「王様、この文字というものを学べば、エジプト人たちの知恵はたかまり、もの覚えはよくなるでしょう。私の発見したのは、記憶と知恵の秘訣なのですから」。ーーしかし、タモスは答えて言った。(LF)「たぐいなき技術の主テウトよ、技術上の事柄を生み出す力をもった人と、生み出された技術がそれを使う人々にどのような害を与え、どのような益をもたらすかを判別する力をもった人とは、別の者なのだ。いまもあなたは、文字の生みの親として、愛情にほだされ、文字が実際にもっている効能と正反対のことを言われた。なぜなら、人々がこの文字というものを学ぶと、記憶力の訓練がなおざりにされるため、その人たちの魂の中には、忘れっぽい性質が植えつけられることだろうから。それはほかでもない、彼らは、書いたものを信頼して、ものを思い出すのに、自分以外のものに彫りつけられたしるしによって外から思い出すようになり、自分で自分の力(FF)によって内から思い出すことをしないようになるからである。じじつ、あなたが発明したのは、記憶の秘訣ではなくて、想起の秘訣なのだ。また他方、あなたがこれを学ぶ人達に与える知恵というのは、知恵の外見であって、真実の知恵ではない、すなわち、彼らはあなたのおかげで、親しく教えを受けなくても物知りになるため、多くの場合は本当は何も知らないでいながら、見かけだけはひじょうな博識家であると思われるようになるだろうし、また知者となる代わりに知者であるといううぬぼれだけが発達するため、つき合いにくい人間となるだろう」。」」(P.255-256)
六〇
「じっさい、パイドロス、ものを書くということには、思うに、次のような困った点があって、その事情は、絵画の場合と本当によく似ているようだ。すなわち、絵画が創り出したものをみても、それは、あたかも生きているかのようにきちんと立っているけれども、君が何かをたずねてみると、いとも尊大に、沈黙して答えない。書かれた言葉もこれと同じだ。」「それに、言葉というものは、ひとたび書きものにされると、どんな言葉でも、それを理解する人々のところであろうと、ぜんぜん不適当な人々のところであろうとおかまいなしに、転々とめぐり歩く。そして、ぜひ話しかけなければならない人々にだけ話しかけ、そうでない人々には黙っているということができない。」(P.257)
六一
「してみれば、その人は、そういった知識の内容を「むなしく水の中に書きこむ」ーー黒い水をつけて書くというようなことを、まじめな目的のためにはしないだろう。葦の茎を用い、自分を弁護することも、納得の行くまで真実を教えることもできないような言葉を用いて、大切なそれらの種をまきはしないだろう。」(P.259)
「そういう人が、文字という園に種をまいて、ものを書くのはーーもし書くとした場合のはなしだがーー、慰みのためにこそそうするのだろうと思われる。それは、「もの忘るる齢の至りしとき」にそなえて、自分自身のために、また、同じ足跡を追って探求の道を進むすべての人のために、覚え書きをたくわえるということなのだ。」(P.260)
六二
「語ったり書いたりするひとつひとつの事柄について、その真実を知ること。あらゆるものを本質それ自体に即して定義しうるようになること。定義によってまとめた上で、こんどは逆に、それ以上分割できないところまで、種類ごとにこれを分割する方法を知ること。さらには魂の本性について同じやり方で洞察して、(FF)どういうものがそれぞれの性質に適しているかを見出し、その成果にもとづいて、複雑な性質の魂にはあらゆる調子を含むような複雑な言論をあたえ、単純な魂には単純な言論を適用するというように、話し方を排列し整理すること。」(P.261-262)
六三
「これに対して、書かれた言葉の中には、その主題が何であるにせよ、かならずや多分に慰みの要素が含まれていて、韻文にせよ、散文にせよ、たいした真剣な熱意に値するものとして話が書かれたということは、いついかなるときにもけっしてないし、」(・・・、P.263)
六四
「これを「知者」と呼ぶのは、パイドロス、どうもぼくには、大それたことのように思われるし、それにこの呼び名は、ただ神のみにふさわしいものであるように思われる。むしろ、「愛知者」(哲学者)とか、あるいは何かこれに類した名で呼ぶほうが、そういう人にはもっとふさわしく、ぴったりするし、適切な調子を伝えるだろう。」(P.265)