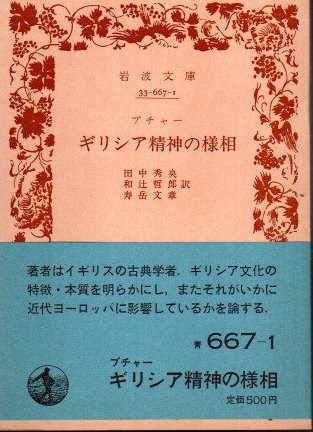
本書について
領収書は2021/02/23になっているので、その頃に読んだ本です。どうして読もうと思ったのかは忘れました。なにかに引用されていたのですが、この本を探すのにけっこう苦労しました。この文庫本自体が古いものです。初版は1940年。原書は
S.H.Butcher, "Some Aspects of the Greek Geniun, 3rd. Ed., 1904"
です。1923(大正12)年に『希臘天才の諸相』(岩波書店)という本が出版されています。訳者は田中秀央と和辻哲郎です。多分同じ本です。'Geniun' を「天才」と訳したのではないかと推察します。
「凡例」によると、ブチャーの弟から翻訳の許可が降りたのが1913年頃。田中と和辻で翻訳をしたのが1923年とあります。そして1939(昭和14)年に寿岳が参加して本書ができたとあります。いずれにしても戦前の本です。
ちなみに筑摩書房から両角克夫訳で『ギリシヤ文化の特質』(1942(昭和17).7)というブチャーの訳書が出ています。原書は "Harvard lectures on the originality of Greece" だそうなので、別の本です。
ブチャー(Samuel Henry Butcher, 1850-1910)は「オデュッセィアー」のすぐれた英訳者でギリシア思潮の闡明者(せんめいしゃ)だそうです。
"Butcher" は「肉屋(屠殺者)」です。私は「アブドーラ・ザ・ブッチャー」がすぐに頭に浮かび、「ブッチャー」としか読めません。イギリス人の名字は職業から来ているものが多いですね。「肉屋のサムちゃん」といった感じですか。
この本をネットで探したときに、表紙の文字が旧字体で右から左に書かれているものもあり、「旧字体は嫌だなあ」と思って、新字体で書かれているこの本を見つけました。「1986/04/04,第7刷」ですが、本文は一部旧字体、旧仮名遣いでした(表紙だけ新字体にしたということか)。
旧字体は一部なので、読みやすい本です。
旧字体が困るのは、書抜きを入力すると、その漢字が IME で優先されることです。しばらくは変換が変なことにあるのです。面倒なので、新旧漢字変換表と変換プログラムを作ってしまいました(一般的なものではなく、この本専用です)。
我々がギリシアに負うてゐるもの
著者は古典時代のギリシアをよく知っています。自分の研究対象を好きでたまらないのは当然でしょう。西欧人の古典ギリシア好きは特別なもののようです。
してみると、我々は、科學を愛すること、藝術を愛すること、自由を愛することを、ギリシアに負うてゐる。(P.42)
ギリシアは既にあらゆる方面での自由を獲得してゐたのである。ーー社會の自由を、個人の自由を、思想の自由を。ギリシアはすでにその精神を書籍のうちに、また石の板の上に書き了へてゐた。それらのものを時が我々に讀ませようと取つて置いてくれ、さうして、それらは感覺に對する理性の、物質に對する精神の優越を記録してゐるのである。(P.46)
その古典ギリシアの文化はルネサンス期に復活し近代西欧文化として、世界中に広まっていきます。今の日本もその中にあります。
ただ、その古典ギリシア文化(プラトンやアリストテレスなど)はそのまま受け継がれてきたわけではありません。まず基督教の影響をうけました。
さうして我々の宗教は東洋から我々を訪れた、ーーがその東洋はギリシアが出て來たあの東洋、或はギリシアがサラミェで打ち破つたあの東洋となんと異なつていたことか!あのいにしへの時代に於いてならば、ギリシアに對する東洋の勝利は、人間に對する自然の、道徳的自由に對する必然の、自由な組織と知力に對する階級組織或は專制政治の、進歩に對する停滞の、美に對する表號的表現の、山と海とに對する乾燥した平原の勝利であつただらう。(P.46)
西欧人のいう「東洋」は「アジア」でなく、今の「中東」であることが多いです。ここでいう「東洋の宗教」は仏教ではないですよね。間違いなく基督教です。それは日下部吉信さんの言う「巨大な主観性」です。しかし、
が、基督教の勝利に際して起つた西洋に對する東洋の現實の勝利は、そのやうな凶い意味を一つも持たなかつた。ギリシアは既にあらゆる方面での自由を獲得してゐたのである。(P.46)
「自由」というのは「主観性」がもたらしたものです。その主観性が何処から来たのかはわかりません。日下部さんはそれをピタゴラス派だと考えているようです。基督教以前の東洋(中東)にも主観性はあったと思いますが、それは「マギ的要素」の中に埋もれていたのかもしれません。ブチャーがここで言っている東洋の宗教(思想)はそのマギ的要素のことです。「専制政治」についてはわかりませんが。
ギリシア人の国家觀念
それは、警官や収税吏に率ゐられ、すべて最高立法府の指令によつて働く大勢の役人たちと、政府の諸部門から成り立つ一つの有機的統一體である。(P.48)
ギリシアの一般知識にとつては、國家或は都市は組織ではなく有機體であつた。(P.51)
個人は國家に包攝されて初めて完全であつた。(P.52)
ソクラテスがあえて毒杯を飲んで死んだのは、国家と個人とが「有機的統一体」だと考えていたからです。国家(国法)は私を生み育てたものだ、とソクラテスは言います。
お前はわたしたち(国法・・・引用者)と国家に対して、何を不服として、わたしたちを破壊しようと企てるのか。まず第一に、お前に生を授けたのは、わたしたちではなかったのか。つまりわたしたちのしきたりによって、お前の父はお前の母を娶り、お前を産ませたのではないのか。(『クリトン』プラトン全集第1巻、P.140)
そしてわたしたち国法は、どれを取ってみても、お前たちのうちの誰かが、わたしたちとこの国とが気に入らない場合、植民地へ出て行きたいと思うにしても、またどこかよその国に寄留しようと思うにしても、どこでもその欲するところへ、自分の持物をもって行くことを、妨げもしないし、また禁止もしていないのである。しかしお前たちのうちで、わたしたちがどのような仕方で裁判をし、その他の点でも、どのように国政を運営しているかを見て、ここにとどまる人があるならば、その人はすでに、これからはわたしたちの命ずることは、何でもするということを、行動によって、わたしたちに向かって、同意したのであると、わたしたちは主張する。(同、P.143)
問題は、この主張の内容というより、なぜこのことをクリトンに言わなければならなかったのか、そしてプラトンはなぜこれを書かねばならなかったのか、ということです。ソクラテスにとって、個人と国家は不可分なものです。というか、親子の関係のようなものです。「親子」というだけで、国家と個人との分離の可能性があります。今のわたしたちは「親子といっても他人」と考えてしまうかもしれません。でも、当時のギリシア人にとっては「親子は一体・不可分なもの」という考えが強かったのでしょう。だからこのような例をソクラテスは挙げたのだと思います。そしてクリトンも反論できませんでした。
クリトンもプラトンも、「国家と個人は別」だと考えていたのです。だから、ソクラテスに罰金の申し出や逃亡の申し出をしたのです。
ソクラテスは『弁明』のなかで、自分はダイモーンの声に従ったのだ、といいます。それはギリシア人にとっては奇異なことではなかったのだと思います。ソクラテスの有罪判決は僅差でした。ところが、量刑判決にあたって、プラトンらの弟子は「罰金を払って死刑を免れましょう」と勧めます。そのためにお金も出すと。ソクラテスにはそんな気はありませんでしたが、弟子たちの顔を立てます。
ソクラテスの罪状は、若者をかどわかした罪と、邪教を広めた罪だと言われています。若者をかどわかす点については、訴訟経緯を見ればわかります。邪教については多分ダイモーンのことを言っているのではないかと思います(デルポイの神託のことではないでしょう)。でも、それは一神教的な見方で、当時のポリスはそれぞれが別の守り神を持っていたわけだし、家によっても信じる神が違ったのではないでしょうか。そしてダイモーンはソクラテスに話しかけるだけなのです。
ソクラテスにとっては「死」は、
ほかでもなくそれは、魂が、肉体から離れ別れることではないだろうか。(『パイドン』プラトン全集第1巻、P.178)
肉体があるからこそ、「知」に近づけないのです。
というのも、どうしてもわれわれは肉体を養わねばならず、それゆえに、かずかぎりのない煩わしさがいつも肉体によってわれわれにはもたらされてくるからだ。(同、P.184)
すなわち、もしも純粋になにかを知ろうとするならば、われわれは肉体からは離れ去らねばならず、まさに魂それ自身によって、それ自体を観なければならない。(同、P.186)
すなわち、この、魂の肉体からの解放と分離こそが、そっくりそのまま、知を求めるの者の不断の心がけであったのだ。(同、P.188)
それとも、どうかな、知を求めること(哲学すること)とは、まさに死の練習である、としていいのではないだろうか(同、P.234-235)
ソクラテスにとっては個人が国家に従うことと同様に、哲学者が死を求めることも当然だったのだと思います。そしてそれは当時のアテネの市民としても不思議なことではなかったのです。ソクラテスが語らねばならなかったこと、そして弟子たちが死刑を免れようとお金を出そうとしたことは、まさにその東洋の宗教、主観(個人)の出現の前兆であり、アテネの市民たちには受け入れがたいことでした。だから、死刑判決は大差でなされたのです。
私は当初、ソクラテスが逃げずに死を選んだことは理解できないし、有罪判決が僅差なのに死刑判決が圧倒的な多数であったことを不思議に感じました。でも、それがアテネの市民にとって主観性の侵入を嫌悪する行動であったと考えると、なんとなく納得できるような気がします。
ギリシア人の憂鬱
アリストテレースの云ふやうに(『問答集』・・・引用者)、天才は憂鬱な氣質の人である、といふことが眞實であるならば、最も高い天分にめぐまれたこの古代の民族が、さうした感情の一脈をそなへてゐたことは極めて自然である。(P.154)
天才だけでなく、当時のアテネの市民も不安を感じ「憂鬱」になっていたのだと思います。それは、国家から個人が分離されること、親から子が分離されること、自然から人間が分離されることに対する不安です。故郷から離れて「根無し草」になることの不安です。その「故郷喪失性」(日下部吉信)の不安と反発こそが、ピタゴラス派を虐殺したギリシア人の心情であり、主観性に囚われたソクラテス以降の哲学だったのではないでしょうか。
次に、歴史に於いても、ギリシア人は初めて、科學と藝術とを、理性と想像とを結合した。(P.26)
自然からの人間の分離によって、自然を人間とは別のものとして、対象として捕らえることが可能となります。それが「科学」の基礎です。ギリシア人は「結合した」のではなく、その分離に自らが驚き、一体を回復しようとしたのです。自然(故郷)への回帰、胎内への回帰こそがその時以来現在まで続く哲学の課題のみならず、科学や理性そのものの課題となってきたのです。
対象を捉えること、つまり「存在論」が成り立ち、解決されない所以です。
憂鬱の感情は、新しいさうしてほとんど近代的な自然觀照と混じてゐる。自然の常住不變な莊嚴は、人間の無常迅速な力と對照され、詩人は支持と同情とを求めて自然に向かふ。(P.153)
叶うことのない自然との一体性の回復、その気持が近代まで続く詩人や画家の心です。
「私は世界をその神祕の故に僧む。」(P.151、『ギリシア詞華集』)
憂鬱の感情は、新しいさうしてほとんど近代的な自然觀照と混じてゐる。自然の常住不變な莊嚴は、人間の無常迅速な力と對照され、詩人は支持と同情とを求めて自然に向かふ(P.153、同)
対象(客観)は、その主観との距離ゆえに解明されることのない神秘として現れます。科学はこれからもどんどん細分化、複雑化していくでしょう。でもその「思考方式(近代西洋的思考法)」は、自分の尻尾を追いかける犬のように、際限がありません(犬だって、すぐに飽きます)。
書かれた言葉と話された言葉
じっさい、パイドロス、ものを書くということには、思うに、次のような困った点があって、その事情は、絵画の場合と本当によく似ているようだ。すなわち、絵画が創り出したものをみても、それは、あたかも生きているかのようにきちんと立っているけれども、君が何かをたずねてみると、いとも尊大に、沈黙して答えない。書かれた言葉もこれと同じだ。(中略)それに、言葉というものは、ひとたび書きものにされると、どんな言葉でも、それを理解する人々のところであろうと、ぜんぜん不適当な人々のところであろうとおかまいなしに、転々とめぐり歩く。そして、ぜひ話しかけなければならない人々にだけ話しかけ、そうでない人々には黙っているということができない。(『パイドロス』プラトン全集第5巻、P.257)
この、文字に対するソクラテス(プラトン)の嫌悪の正体がよくわかりませんでした。
あらゆる民族のなかで、人類の知的進歩に最も多くをなした民族、その殘した文學が一度ならず西方の世界を新思想の衝撃によつて昏睡から精神的活動に起たしめた民族、その民族は書籍については僅かしか知らず、文學に託して書くことは、思想を呼び起こすうへにどれほどの價値があらうかと疑問視してゐた。(P.157)
書くことが一般に行はれるやうになつた後にさへも、ギリシア人はなほそれを外來のものと考え、アルファベットを「ポイニーケーの符徴」と呼んだ。かんたんに云へば、彼らは文字を學ぶ天性を持たなかつたのである。さうして讀むこと書くことに對する彼らの初期の不向は、後期に至つても、彼らが外國のアルファベットを知らぬこと、外國文學を閑却すること、などのうちに現はてゐる。(P.159)
もしギリシア人がエヂプト人のやうに觀念を象徴する文字の術を作り上げて行つたならば、書くことは話すことと同じく藝術の一種となり、從つて尊敬されたであらう。自然的であつて傳習的ではなかつたであらう。さうして口言葉と字言葉との關係が、いな等價さへも、明らかとなつてゐたであらう。言葉と觀念との間に必然の聯絡があるといふことは、ギリシア思想家のある一派によつて主張された。名はその現はす事物の精密な模像、音を以つてする模倣だ、ーー音と意味との一致は完全だ、と考へられた。しかし、思想の表現としての繪言葉の説はしばしば認識されたけれども、書くことそれ自身が、本來は對象物の藝術的模倣であつた繪符號から來たかもしれないといふことは、ついぞギリシア人の心には浮かばなかつた。彼らはポィニーケー人から、その意味は容易に解らず、その使用法は機械的で、その他との關係は最初殆ど純粹に商業的であつた一揃への出來あひの符牒を、型になりきつた文字を受けとつた。從つて、書かれた文字は彼らにとつて最初から功利主義の印號を捺され、藝術からはできるだけ遠ざけられた。(P.159-160)
なるほど。良い説明だと思います。アルファベットも元々は象形文字だったようです。でも、ギリシアには商取引上の符号のようなものとして伝わったということです。
叙事詩と戯曲とは、たとひその存在そのもののためではないまでも、少なくともその活力のために、生きた聲と耳かたむける聽衆とに依存するものではないか。のみならず音樂の伴奏を持つた詩は、外的の助けや工夫なしに記憶され得るのである。
しかしギリシア人に書きものを疑問視させた原因は、彼等の藝術的本能のみではなかつた。行為に於いても亦彼らは形式の前にたじろいた。不變の規則は行為を硬化させる。屈伸自在に彈力的なこと、不斷に調整することの必要は強く感ぜられた。法律に對するギリシア精神の態度は顯著な適例である。たいていの東洋民族は書かれた宗教法典を持つており、それは直接に神の心か又は手から來たと想像され、特殊の神聖さを與えられてゐた。(P.160-161)
ギリシア人の考へてゐた法律は、外からの力、外から加へられる壓抑ではなく、ギリシアの國家そのもののやうに、彼らの生活の一部であつた。すなはちそれは、彼らの眞實な、彼らの合理的な自己の代表者、彼らの道義生活の影像。個人的自由の否定ではなく、自由の實現。(P.162)
成文法への抗議は次の形式で表はされたーー「人事の不規則な限りなき働きは、普遍的な單純な規則を許さない」、しかるに法律は、個人の特殊性や變わりやすい事情を閑却するとりかへしのつ(FF)かぬ單純さを目指すのである。(P.163-164)
それは一般的であつて特殊の場合の間に合はない。(P.164)
存在を文字で表すこと。対象となった存在を認識するためには、それを固定しなければなりません。文字というのはその固定にはとても便利です。逆かもしれません。文字によって、固定した認識が可能になったのかもしれません。固定した認識は「定義」となります。でも、対象となる存在(具体的なもの、特殊なもの)はどんどん変化(運動)していきます。だから定義はどんどん変更され、付け加えられます。科学における定義もどんどん細分化され、変化していきます。法律書のページはどんどん増えていきます。世界中に書物があふれ、限られた書物以外は捨てられていきます。焚書はその典型的な例です。新しいものが常に必要とされ、そのために古いものがどんどん捨てられていきます。「消費」するのではなくて「投棄」するために物が作られます。
一般と特殊の関係は、普遍と個別との関係であり、国家と個人との関係です。それは「一体のもの・分けられないもの」のはずでした。それは論理的には「演繹と帰納」の関係になります。まさしく数学的な関係です。法(法則)とその適用(一般から個別・具体へ)、個別の事例から一般的な法則の抽出(抽象)を導き出すという関係です。イデア論はその典型です。「一つ一つの机」とは別に「机(なるもの)」を考えるということです。「美しい花々」の他に「花の美しさ」というものを想定します。「可愛い女の子」ではなくて「女の子の可愛らしさ」を描こうと思ったりします。
物数を極めて、工夫をし尽くして後、花の失せずところを知るべし」美しい「花」がある、「花」の美しさといふ様なものはない。彼の「花」の観念の曖昧さに就いて頭を悩ます現代の美学者の方が、化かされてゐるに過ぎない。肉体の動きに則つて観念の動きを修正するがいゝ、前者の動きは後者の動きより遥かに微妙で深淵だから、彼はさう言つてゐるのだ。(小林秀雄『当麻』筑摩書房 日本文学全集42 「小林秀雄集」 1970/11/01 P.366)
「美しい花の絵」は「絵」であって、「花」ではありません。でも、それを「花」だと思ってしまうのは、認識と論理の問題です。「刑法」は「個々の犯罪」ではないのです。「かに風味かまぼこ」は「カニ」ではないのと同じです。
「テレビに映っている人間」は「人間」ではありません。テレビで放送されている事件は「事件」ではありません。書物は「紙とインクのシミ」です。
同じものがもつと立派な完全な形に表現せられてゐても、書物の中で讀まれれば、ひどく退屈に感ぜられるだろう。このことは、講義者が何ら著しい人格も、また何ら特別な聲や素振りの魅力を持たないところでさへ、屢ゝ起こる。その理由は、おそらく幾分かは次の事情に見出されるのではあるまいかーー語り手が人間であると云ふ事情に。これは同じ人間にとつて絶え間なく興味をそそる事實である。たいていの書物は或る意味で人間的ではない。自分をあるがままに文章に現はし、その人間の眞の印象を與える人の、いかに少ないことだらう!一度紙に託せられると、人は彼自身の性格を失ひ易く、また中性や非人格的になるか、或は假構の人格をーー無意識にーーとり易い。(P.179)
インターネットの中の人間ももちろん生身の人間ではありません。だから、SNSなどの「匿名性」も可能になります。それと同時に、ネカマやなりすましも可能になります。そうではなくても、普段の自分とは別の人格も表現できます。過激な発言や、告発、誹謗中傷なども可能になります。
学問は買うもの?
書物は不斷の調整ができぬといふことの他に、プラトーンが書物を信頼しなかつたもう一つの理由は、彼が知識の尊厳について抱いてゐた高い概念に附随する。眞の知識は賣物にできる品の中にはない、ーー消費者の好むままに小賣でも卸賣でも賣られ得るもの、出來合いで供給され、書物といふ持ち運び易い形で運搬され、さうしてそこから學ぶ人の心の中へ恰も器から器へのやうに注ぎあけられ得るものの中にはない。(P.175)
少し前に、TVで学習塾?のCMをやっていて、ドキッとしました。「数学無料」。詳しい内容はわからないし、どうでもいいのですが、数学は「買うもの」でしょうか。買うものだと考えているから、「無料だよ」という宣伝ができるのですね。確かに、参考書を買ったり、授業料を支払ったりします。でも、お金を払えば数学が身につく、という発想は私にはありませんでした。ジャケットのように買って着れば数学が身についたり、「数学の素」のような飲み物があってそれを飲めば数学が身につくのなら楽だし、同時にお金のない人(貧乏人)は数学を身につけることができない、ということですね。
あながち否定できないのは、参考書を買って授業料を払っても数学が身につくとはかぎらないけど、参考書を買わず授業料も払わなければ数学が身につくことは難しい、と考えてしまうから。
私は塾に行ったことはないけど、参考書は買いました。それ(塾に行かなかったこと)が自慢でもあったけど、お金を払って学問を買っていることには変わりないですね。
ソクラテスは、
どこの国へでもでかけて行って、そこの青年たちに、かれらは、自分の国の人なら、誰とでも好きな人と、ただで交際することができるのに、そういう人たちとの交際をすてて、自分たちといっしょになるように説きすすめ、それに対して金銭を支払わせ、おまけに感謝の情まで起こさせるという、そういうことができるのです。(『ソクラテスの弁明』前掲、P.56)
と、ソフィストを非難していますが、ソクラテス自身もアナクサゴラスの『自然について Περι φὺσεως』を1ドラグマで買いました(これはソクラテスにとっては大きな出費だったようです)。期待を持って読んだ結果は、
ところがああ、これほどの期待からも、友よ、わたしは突き放されて、むなしく遠ざからざるを得なかったのだ。(『パイドン』前掲、P.286)
ということだったようです。本は期待通りの結果をもたらすわけではありません(他の商品と同じように、食べたり読んだり使ったりしてみないと美味しいかどうかわからない)。そして、反論することはできないのです。もし反論することができたら、お互いの考えが深まっていたかもしれないし、歴史が代わっていたかもしれません。
「花」という字が「花そのもの」ではないように、本はその著者そのもの(あるいは著者の考え・気持ちそのもの)ではありません。ですから、2500年たった今でもギリシア哲学に関する新しい解釈が可能で、新しい著書が生まれます。
翻訳
初期ギリシア哲学の舞台になったギリシアの台地の上に立つとき、不思議な解放感を感じるのはなぜでしょうか。おそらくこの解放感はブラジルのボロロ族の中にあってレヴィ・ストロースが味わったのと同じ性格のものでしょうが、それは地中海気候の陽光のためばかりではないでありましょう。わたしたちはそこに立つとき、主観性の眼差しと告発的意識から解放されている自分を見出すのであります。(日下部吉信著『ギリシア哲学30講』明石書房、上P.29-30)
わたしはギリシアに行ったことがありません(瀬戸内海も見たことがありません)。
思想は風土に根ざす、というようなことを言うことがあります。風土は食を始め様々な文化を生み出します。そして「言語」もその文化に根ざしたものです。
我々は言語と思想とを分離すべきではない。それらは偶然に關係づけられたのではない。古典教育の失敗の殆ど凡ては、この二つの要素を別々に取り扱はうとする企てに歸せられ得る。言葉を意味なしに知ること、および意味を言葉なしに知ることーーこれは劣悪な學者や淺薄な思想家の特性を一括してゐる。否、言語は思想を開くための鍵、唯一の合鍵である。(P.202)
しかし飜譯は、最もよいものですら、原作の影に過ぎぬ。諸君は一つの詩の生血をどんな飜譯にも輸血することはできぬ。のみならず、一つの國語は他の國ごと違ふーー特に古代語は近代語と違ふーーただ外的形式に於てのみならず、内的な本質的な特性に於ても。それらは同一物を違つたやり方で表現すると言ふわけではない。違つたものを、全然或は部分的に違つたものを、各々その獨自なやり方で、表現するのである。
言葉は、兩替し得べき價値のある貨幣ではない。尤も、科學上の述語は國際為替が可能である。その傳へる觀念は、情緒に染められず聯想に觸れられずに、國から國へと通過させることができる(P.203)
翻訳の不可能性を的確に表しています。
この本のキーワードはたくさんあります。哲学、思想、学問、自由、歴史、言語・・・。それらの殆どは「翻訳のために作られた日本語」です。
昔、『空想から科学へ Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft 』の勉強会をやったときに「Wissenschaft は科学ですか、学問ですか」と聞かれたことがあります。その時、外国語が苦手な私には答えるべくもありませんでした。その後もドイツ語を勉強したことはありませんが、今なら少し答えられます。「Wissenshaft にピッタリ当てはまる日本語はないんだよ」と。つまり、著者の言う「科学」に当てはまる日本語も、実はないのです。
日本では現在は科学の一分野である「自然科学」を指すものとして使われることがほとんどですが、多分この本の言語は「 science 」でしょう。「 science 」は古いフランス語で、元々はラテン語の「 scientia 」から来ています。これは「知ること、知識」くらいの意味ですから、「Wissenshaft 」というドイツ語はなるほど、です。アメリカにもイギリスにも行ったことはないけど、英語圏でも日本語の「科学」より広いニュアンスで使われているのでしょう。当たり前のことですが、言葉は文化の中で使われ解釈されます。日本語を知らない人に「kagaku 」と言っても理解させません。「味噌汁」を味噌汁の文化のない英語でどう表しているのか見てみると、「 miso soup 」という訳(?)が多いですが、「 bean soup 」とか「miso pottage 」なんていう訳もありました。でも、「 bean 」と「味噌」は違うし、「 soup (pottage) 」と「汁」も違うでしょう。それでも「 miso 」は別として、「 bean 」も「 soup 」も「 pottage 」も日常語です。
ところが、「科学」や「思想」は違います。「自由」はかなり昔から仏教(禅)用語として使われていたようですが、「 freedom 」「 liberty 」の翻訳語として定着したのは明治以降です。だから、「自由」は「味噌汁」のように意識にピッタリと来ないのです。その他の翻訳語も同じです。
ところが、学校で英語を学ぶときに「 freedom の意味は」と英和辞典を調べると「自由、・・・」と書いてあるので、「ああそうか自由か」と納得してしまいます。でも、「自由ってなんだろう」と考えるとピンときません。頭で思うだけで、肌で感じることができないのです。
古典時代に於いては文學と人生との間の隔離はなかつた。著作家や思想家は市民であり活動家であつた。後になつて、彼らは庶民的感情の調子を失つた。文學はこの變化に敏感であつた。語ることと書くことの分離は、衒學、書物臭さ、および非現實性へ導いていつた。(P.182)
著者の抱くこの感情は、その「肌感覚」に近いのではないでしょうか。
ある人がブログに「古典ギリシア語と現代ギリシア語との違いは、源氏物語と現代文学の差よりも大きい」と書いてあるのを読んだことがあります。きっとそうなんでしょうね。更にそれを日本語に翻訳するときには、日常語ではなくて翻訳語を使わなければならないのです。日本の哲学書が難しいのはその二重の困難を抱えているからでしょう。
かやうに人間化された
知識は既に叡智への半途にある、なぜなら知識は生活と接觸させられたときにのみ叡智となるのだから。(P.183)過度の專門化は
學問を人生から絶縁させることに傾く。思想の人を實行の人から、學者を市民から、卽ち學問ある者の世界と學問なき者との間に大きな溝渠をつくることに傾く。(P.197)
ギリシア人は、「科學と藝術とを、理性と想像とを結合した」(P.26)のではなく、「言葉と論理」「感情と理性」を「分離」したのです。それは、東洋(中東)の影響だったかもしれません(東洋、インドや中国ではどうだったのかはわかりません)。それでも、その言葉は「學学問の世界でのみ行はれる方言」(P.209,学術用語)であったとしても、まだ「日常語」の意味の拡大や厳密化です。どこか皮膚感覚が残っていると思います。それが日下部さんが感じた「エーゲ海の風と光」なのではないでしょうか。


