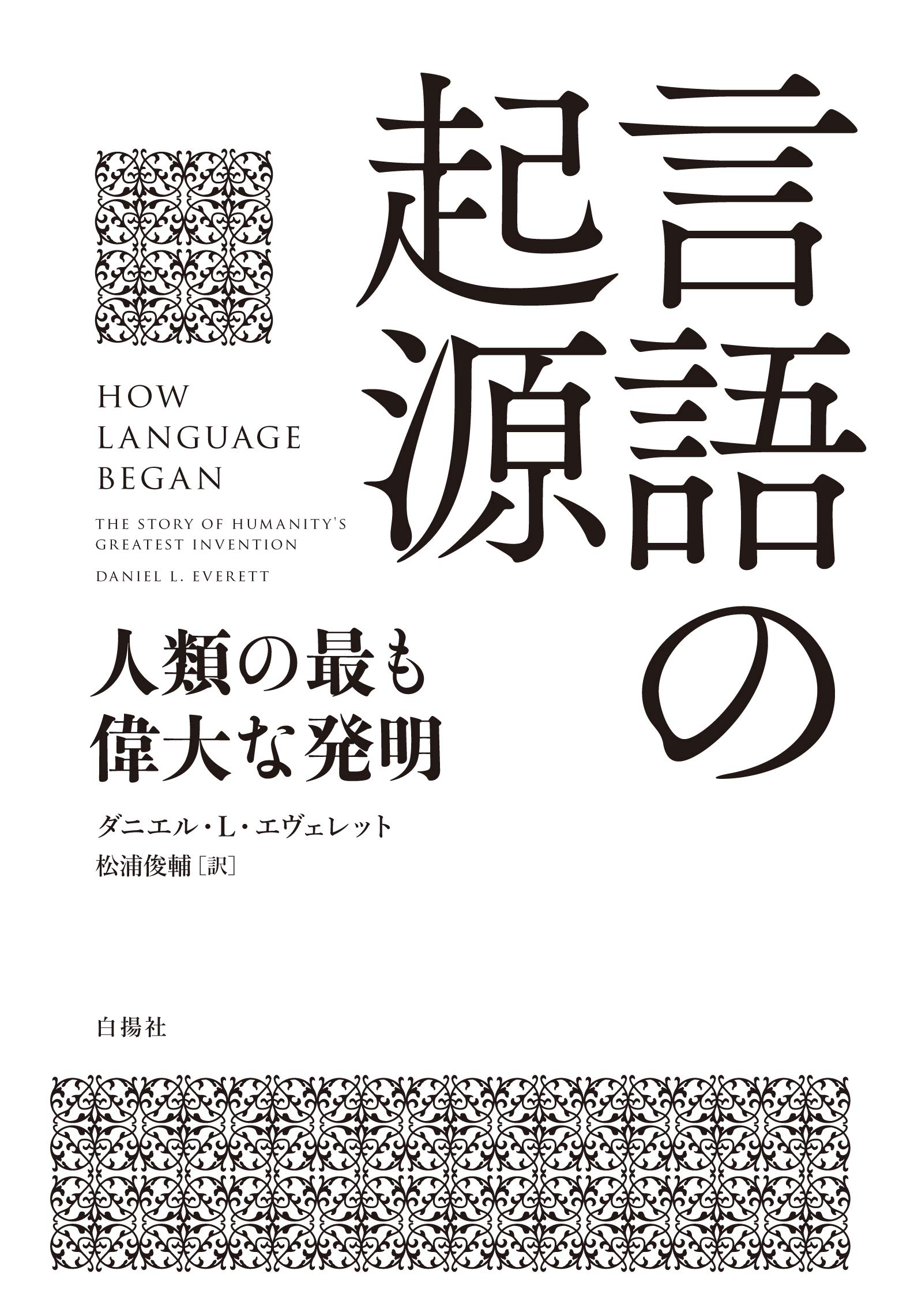謝辞
序
「誰もが文化の一部であり、誰かの創造性、アイデア、先行する試み、自分が住まう知識の世界の一部をなしているのだ。あらゆる発明は時間をかけて、すこしずつ積み重ねられていく。言語もまた、例外ではない。」(P.15)
はじめに
「録音機器をもった研究者の存在が仇となり、出てくる言葉を汚染してしまう。」(P.18)
「会話はまた、実際に伝えた(FF)いことよりもつねに言葉足らずで、言外の前提を何らかの方法で解釈することを聞き手に任せる。」(P.20-21)__非明示性(underdeterminacy)
「非明示性とは、あらゆる会話のあらゆる発話、あらゆる小(FF)説のあらゆる一節、あらゆるスピーチのあらゆるくだりに「空白の点」、つまり話されることのない暗黙の知識、価値、役割、感情が含まれていることを意味するーー私が「ダークマター」と呼ぶ、言葉で特定されていない内容のことだ。」(P.22-23)
「今挙げたことを考慮すれば、理解すべきことを記したリストの先頭に「会話」を持ってこない限り、言語の起源に関して有意義な議論ができない理由がわかるだろう。」(P.23)
「だが、人類の生物学的・文化的進化に関する形跡を入念に調(FF)べていくと、それとはまったく異なる仮設が浮かび上がってくるーーすなわち、言語起源の記号進展理論(sign progression theory)だ。この言い回しの意味は単純で、言語は指標記号(インデックス、足跡が動物を指すように、物理的につながりのあるものを表す事項)、類像記号(アイコン、実在の人物の肖像画のように、表そうとする事物と物理的ににている事物)、それから最後に象徴記号(シンボル、ほとんど恣意的な、慣習的な意味の表し方)の創造へと、徐々に現れてきたということを意味している。」(P.25-26)
「各種エビデンスは、人類が「突然の跳躍」によって独自の言語的特徴を得たわけではなかったこと、現代人類に先行する種(ホモ属、あるいはそれ以前のアウストラロピテクス族に分類されるもの)がゆっくりと着実に発展して言語を手に入れたことを示している。」(P.28)
「ジェスチャーは言語にとって決定的に重要なものなのか?答えはイエスだ。」(P.30)
第Ⅰ部 最初のヒト族
第1章 ヒト族の登場
「科学とは「正しい」理論を見つけることではない。科学者が何かの理解へ向かって手探りで進みながら、その中で最も良い理論を見つけることなのだ。」(P.34)
言語は、意味(意味論 semantics)、用法においての条件(語用法 pragmatics)、使える音の物理的特性(音声学 phonetics)、文法(統辞 syntax あるいは構文)、音の構造(音韻論 phonology)、単語の構造(形態論 morphology)、談話の会話編成原理、情報、ジェスチャーの相互作用からできている。言語はゲシュタルトをなすーーつまり、全体は部分の和より大きい。言い換えれば、個々の構成要素を調べるだけでは、その全体は理解できないのだ。」(P.36)
「そして、この進展の中で最も原始的な部分となるインデックスという形式は、それが指し示すこととの実際の物理的なつながりを明らかに示すのもだ。猫の足跡はインデックスであり、それは猫がいることを指し示し、予想させる。焼けるステーキの匂いがあれば、ステーキとオーブンが思い浮かぶ。煙は火の指標となる。アイコンはそれが指し示すものを物理的に喚起する記号のことで、彫像や肖像は、描かれている対象を物理的な類似を通じて指し示す。「バン」とか「カチン」といった擬音語は、それぞれの音を呼び起こす。(LF)シンボルはそれが指し示すものとの慣習による結びつきであり、それが指し示すものとの類似も物理的関連も必要としないため、他の記号よりも複雑になる。それは社会によって合意されたものだ。「3」という数字は三つあるものの数を指し示すが、これは「ダン」というのがその名の誰かさんを指し示すのと同じことで、「さん」という単語にその数との物理的関連や類似があるから「さん」なのではないし、「ダン」という名の人物すべてに共通するダンらしい物理的特徴があるから「ダン」なのではない。」(P.38)
「人の脳を作ったのは進化だが、人類はそこから後を引き継いだ。」(P.40)
「とはいえ、時計職人のたとえに対するおそらく最も効果的な反論は、文化によるものだ。時計はその材料を含め、一人で作ることはできない。時計は文化の産物であって、デザイナーが生み出したものではない。」(P.44)
「進化は確固たる事実だ。理論と言えるのは、進化がどのように起きるか、あるいはどう見えるかの説明ーー自然淘汰、遺伝、系統樹ーーのところだけであって、進化そのものは理論ではない。」(P.44)__いくつもの理論があり、どれも証明できない。歴史は再現実験ができない。
「一方で、自己複製を行うDNAは宇宙由来で、隕石や小惑星によってもたらされたという筋書きも、科学者からは提示される。DNAの起源についてのこの説は「パンスペルミア」説と呼ばれる。」(P.44)
「実際には、大進化はたいてい、もっと小規模な、場合によっては一個の対立遺伝子の変異ほど小さい規模の、「小進化(microevolution)」と呼ばれる進化による変化が蓄積して生じる。」(P.53)__大進化 macroevolution
「進化科学者は時間とともに生じるあらゆる形の生物学的変化(つまり進化)を理解しようとしている。大進化と小進化は、自然淘汰による改変の巨大な連続体の上に存在する点にすぎない。」(P.53)
「遺伝的浮動は、メンデルの対立遺伝子選択の無作為原理によって生じる、自然に起こる遺伝的多様性の減少のことだ。重ねて言うが、これは自然淘汰によって生じるのではない。この結果に〔環境への〕適応度はまったく関係がないからだ。」(P.55)
第2章 化石ハンターたち
「男女の体も違いが少なくなったーーつまり性的二形が縮小した。ヒトの雄は雌よりも平均で約一五%大きいが、この差は他の霊長類の各種と比べると小さい。霊長類の系統における性的二形(FF)の縮小には社会的な含意がある。霊長類の間では、雌雄の大きさが近いことは、つがいの絆、つまり単婚と相関している。雄の霊長類は、雌の餌や子育てを手伝う時間が増える。これはこの成熟に時間がかかるヒトのような霊長類にとってはとくに重要だ。(LF)西洋の工業化された文化の中には、「子供時代」(自立した成人に達するまでに必要な時間)が人の平均寿命の三分の一にも及ぶところもある。雌雄が一生、あるいは子育ての間だけでも一緒にいるのであれば、雄はそれ以上、交配相手を求めて他の雄と争う必要はなくなる。」(P.68-69)__「〜に有利だ、〜することができる」因果律に縛られている。進化論的な思考。現在の文化の中での推論。単婚、等。「争う必要はなくなる」なくならないだろう。
「そして二足歩行や性的二形の縮小とともに、視覚優位がもたらされた。ヒトは他の霊長類より、あるいは他の殆どの生物より遠くが見え、それによってヒトは目に見える目標に向かって早く走れる。」(P.69)__同上
「ホモ・エレクトゥスは百万年も前に火の扱いを覚えた。食物に火を通して食べるようになったことで、ホモ・エレクトゥス以前のヒト族は、これまで摂取してきた脂肪とタンパク質を消化系で分解しやすくなった。逆に言えば、このときまでのヒト族は他の霊長類と同じように、食物に含まれる大量のセルロースを分解するためにより大きな腸が必要だったのだが、火を通すようになったことで、肉を多く食べられるようになり、その結果、前よりエネルギー豊富な食物の消費量を増やし、消化しにくい非加熱の植物への依存度が大きく下がった。そして、この火を使うことで可能になった食物の変化によって、自然淘汰でヒト族の脳が大きくなりやすくなった。なぜなら、消化器が必要とするエネルギーが減り、人体に占めるスペースも小さくなる一方で、〔肉食が可能という前提で〕カロリーを以前よりもはるかにすばやく、大量に摂ることが可能になったからだ。」(P.70)__火を使わない(あまり使わない)民族もいる。狩猟採集生活にとっては、主は採集で狩猟は儀式的なもの(なくてもいいもの)だった。人間中心主義というか西欧中心主義。
「直立した体は、四足動物の体よりも直射日光にさらされる表面積が小さいため、人類はあまり体毛を必要としなくなった。さらに体毛を捨てる副次的な利益として、体を冷やしやすくなった。体毛の喪失に伴い汗腺も発達し、温度調節はさらに効率的になった。」(P.71)__逆かも知れない。体毛が喪失したことによって、衣服の文化が発展した。
「哺乳類は動物界で最も知能がある生物だ。」(P.73)
「言語のためには、必要ないくつかの前提条件、いわゆる「プラットフォーム」〔共通の足場〕がある。そのうちの二つが、文化と「心の理論」(FF)(人がみな同じ認知能力をもっていることの意識)だ。」(P.73-74)
「このような一見単純な想定さえ、それを引き出す元となる文化的知識の量は膨大である。」(P.74)
「理由は人は誰もよく似た脳を持っているからであり、要するにこれこそが心の理論なのだ。」(P.74)__死が悲しいのは、自分が悲しんでいるのではなく、死んだ人自身の悲しみを悲しんでいる。死んだ人は悲しめない。
「他人も自分と同じように考えていて、こちらが伝えたいことを理解するだろうと信じていればこそ、言語は機能する。」(P.75)__言語は文化であり、個性だ。人にとっては宇宙であり、小さい。子供の頃の公園・近所
「ただ、人間に近い認知能力が動物にあるかをめぐる、科学の世界での長きにわたる議論の中でもとくに問題をはらむ論点の一つは、認知には言語ーーそれも人間のような言語ーーが必要で、したがって言語のない動物には認知はありえないという、本質としては循環的な想定だ。これはたんに、人間だけが認知をするという信条を、研究を行う前から宣言しているにすぎない。そのようの考え方は、問いを人間を中心に構成しているところが間違っている。」(P.76)__人間の解剖は、猿の解剖の役に立つ。擬人化。「言語で考える」というのも同じ(かも知れない)。「猿にもこんな事ができる」「犬にもこんな事ができる」「昆虫にもこんな事ができる」・・・という驚き!!
第3章 ヒト族の分離
「同様に、文化は道具技術などの知識を世代から世代へ模倣と教育によって伝えることだけを指すのではない。文化は人やその創造物に、価値、知識構造、社会的役割を付与する。つまり、道具もそれ自体が意味(FF)を持つ、ということだ。そのため、道具は文化の構成員に、それを使って行う仕事のことをーーたとえその仕事をしている最中ではなくてもーー思い出させる。」(P.90-91)
「道具を使えるのはたいしたことだが、文化は人工(FF)物を状況と関連づけることによって、さらにその先へ行く。それがあればこそ、特定の文化に由来する道具が、それが使われていないときにも意味を換気できるようになるのだ。」(P.91-92)
「この両者の違いを見分けるには、単独の一族や単一の個体がたまたま道具を使ったというような、一度きりの、あるいは特異な発明から道具が生じたのではなく、ある体系から道具が生まれていると言える証拠を調べるしかない。」(P.92)__鳥のつがいは文化につながらなかったのか。鳥が文化を持つかどうかではなく、人間の生態を文化という。
(P.94)__子供の数を多くすれば、自我は減るかも知れない。
「それでもG1言語は「本物の」言語だ。本物の言語とは質的に異なる「原型言語(protolanguage)」ではない。」(P.99)
「それは文法によって課せられる語順があるためであり、それが文がとりうる意味に対する(弱い)フィルターとして働いているからだ。G1言語の場合のように、文法的フィルター(FF)の目があまり細かくない場合には、意味を補助する文化の役割はさらに大きくなる。ただ、どんな言語であっても文化は必ずこうした役割を果たしている。」(P.99-100)
第4章 みな記号の言語を話す
(P.108)__言語は文化で理解される。そして、状況において状況をいかに認識するかも文化が決める。犬が道を認識するのも、環境による。アメリカでコメディーを演じること。
「これによってフエンテスが意図しているのは、研究者はたとえば人間の言語のような、(FF)種が有する個々の形質の進化を語るべきではなく、当の生物全体、その行動、生理、心理、ニッチ、ならびに他の種との相互作用を理解する必要があるということだ。フエンテスは、ヒトという種の全体像には、この拡張進化論的総合に基づく理解をなすものとして、生物学的なもの、文化的なもの、心理的なものが同時にかかわっていると主張する。」(P.109-110)__分解(細分化した学問)は、当然全体像を求める。でも、それでは何もわからない。分解すること自体に無理がある。
「文化の理論は言語進化の理解の根底にある。実際、しっかりした文化の理論がなければ適切な言語進化の理論もありえないのだ。文化に関して私なりに説明すれば、その一つはこうなる。(LF)文化とは、社会的な役割や階層構造化された知識の諸領域、ランクづけされた諸価値を形成し、(FF)結びつける抽象的なネットワークである。文化は動的であり、変化し、その時々に解釈し直される。文化の役割、知識、価値は、文化の構成員の体と(脳も体の一部だ)、あるいはその行動の中にのみ見つけることができる。(LF)文化が抽象的というのは、それが触れたり、見たり、嗅いだりすることができないーーつまり、直接には観測不可能だからだ。しかし、芸術、書物、政治的役割、文学、科学、宗教、様式、建築、寛容/不寛容のような文化の産物は、抽象的ではなく、目に見えるし触れることもできる。ただ、動態としての文化は、社会の個々人にのみ見つかる。どんな社会の構成員も、価値の幅や認められる価値の相対的な優先順位において一致していれば、一つの文化を共有していることになる。」(P.110-111)
「言い換えると、言語は文法の単なる同義語ではなく、意味、形式、ジェスチャー、音高の組み合わせである、ということだ。文法は言語を助けるが、それ自体が言語なのではない。」(P.113)
「斉一説は、現在の動き方は過去の動き方でもあったという考えで、つまり今日の世界に作用している力は、世界が始まって以来、世界を形成してきた力と同じとする。」(P.113)__演繹法
「これに対して激変説は、地球上の生命の起源と発達の理由を、たとえばノアの洪水や突然変異率の上昇などの大規模な変動に帰する。」(P.114)__歴史とは進化の別名である。
「斉一説をとった場合、太古の生物が漸進的な「遅々とした歩み(ベイビー・ステップス)」を経て現代の生物に変化することを、自然淘汰のモデルが説明するということになる。」(P.114)
「それに、もし仮に言語能力が突然変異によるものだったとしても、それが生み出せるのは言語を学習する能力ーーしかも皮肉なことに、言語が存在しなかった時代にーーだけである。さらに言えば、突然変異のようなものを主張するのであれば、必要な時期と突然変異の時期が合致しないこと以外にも、突然変異が生じた時期において、言語のような特定の形質に、生存に関わるどのような有利さがあったかについて説明しなければならない。」(P.115)
(P.116)__偶然に根拠は必要ない。
「しかし、コミュニケーションが言語の基本的機能だとすれば、人間の言語は、一部の言語学者、哲学者、神経科学者が想定するほどには、他の生物のコミュニケーションと違わないことになる。」(P.120)__論理的思考はコミュニケーションの前提ではない。それは伝えられないから。
「この研究によれば、両義性は、効率的なコミュニケーションを維持しつつ、記憶しなければならない量を小さくする必要から生じる。」(P.121)
「(これはもちろん英語の例でしかないが、同音異義語はどの言語にもあるらしい)。」(P.121)
「さらに言えば、書いたり話たりする際の両義性は、言語に本質的に存在する問題ではない。」(P.122)
「同じことは言語にも言えるーー両義性、曖昧さなどの言葉の欠点は、たいてい、話す前あるいは書き出す前に計画したり、考えたりすれば避けられる。コミュニケーションのための計画は、たいていの活動の場合と同様に役に立つ。」(P.122)
「確かにコミュニケーションは失敗することがある。しかし思考もまた同じだ。人の思考は本人に対しては両義的でないという仮設は、あくまでも仮説にすぎず、精査が必要だ。また、すべての人々がつねに(あるいはほとんどの場合に)、言語によって思考しているというのも、決して確実とは言えないことに注目しておくべきだ。」(P.122)__というか、話したり書いたりしようとするときに言語化される。それは文字文化の影響である。
「言語にとっては、形式と意味の必然ではない文化的な結びつきが必須となるからだ。」(P.136)
「まず、ピダハン族の女性は男性より、印象的には「咽頭音の〔k、gなど、口の奥の方で出す音〕」言葉を用いる。これは、ピダハン族の発声器の使い方が、文化的な動機によって二通りあることから生まれる。」(P.138)
「こうして音素の数の違いを伴う異なる発音を使うことは、話し手の社会的地位や性別を、音を介して類像的に表す方法となる。」(P.138)
(P.140)__文字は別の話。
「あるいはそれは、ほとんど普遍的と言ってよい「とりあえず満足(サティスファイシング)」の原理、言い換えれば最善を求めるよりも、「まずまず良い(グッドイナフ)」で満足する自然な傾向の結果かもしれない。」(P.153)__進化であると何故言わなければならないのか。歴史、一回性。
「地位は装飾や個人に内在するものではないし、装飾品が地位を与えることもない。」(P.158)
「地位は文化に由来するものだ。そして、ステータス・シンボルは社会的な記号であり、それが持つ意味は、抽象的で外置された文化的価値に依存している。つまり、ステータス・シンボルは言語的シンボルではないというのは正しいが、言語的シンボルもステータス・シンボルもともに恣意的であり、社会的な指標であり、外置されている。したがって、両者は概念的に同類といえる。」(P.158)
「外置はステータス・シンボルにはないと言う人もいるが、この外置という要素はそれ自体が文化的制約を受けている。シンボルを発達させる決め手になる成分は、外置ではなく、恣意性や志向性の方だ。だが外置はステータス・シンボルにも道具にも存在する。この二種類の人工物はどちらも、文化(FF)の構成員全員の心の中にある文化的価値、社会的役割、構造化された知識をはじめとする抽象的存在物を指している。」(P.158-159)
「世界中の言語に見られる類似性が教えてくれるのは、人間のコミュニケーションの働き方についてであって、人間の進化あるいは人間の言語本能がもとからそのようにできているから、ということではない。」(P.163)
(P.165)__歴史は進化であるということもできる。歴史=進化なのだ。論理は科学者、哲学者が言うように「自然に沿ったもの」「自然を言語化したもの」だ。それはたまたまそういう発想であっただけで、自然を(存在を)説明する仕方は一つではない。人類の一部はたまたまそうなった。それが優性だったわけではない。言語が違うように、説明も違いうる。いや、言語の数だけ(文化の数だけ)説明はある。その理性(論理)によって人類の優位を説明することは、単なる自己満足でしかない。進化したわけではない。進化しよう、生き残ろうとした(思った)わけでもない。意識や言語を持とうと「思って」(あるいは便利だと「思って」)もったわけではない。
第Ⅱ部 人間の言語への生物学的適応
第5章 人類、優れた脳を得る
「脳がなくても話せるのなら、おそらくそのままの方が幸せだっただろう。脳はたしかに愛や分かち合い、音楽や美、科学や芸術の源泉である一方で、テロや偏狭、戦争や強権支配の元凶でもあるからだ。」(P.169)__戦争の元凶ではあるが、愛の源泉ではない。ここでいう脳は理性のことであり、自意識のことである。
(P.170)__今の人類は最高だともそうでないとも言うことはできない。それは意味のないことだ。親と自分、自分と子供を比べても仕方ない。それでも、昨日より今日は進んでいなければならないのだろうか。
「もっとも、どうやら人間の脳の発達が止まったらしいことは、まったく恥ずかしいことではない。(FF)おそらくこれは、われわれの種が、順調な暮らしを送れているという単純な事実によるものだと思えるからだ。」(P.170-171)__そうだろうか。一万年前より「順調」だといえるのだろうか。言う必要があるのだろうか。現状を(現在を)肯定する(したい)だけのように思える。
「ホモ・サピエンスは言語の技術が向上し、それによって文化的な成果も大きくなったのだろうか。「そう単純ではない」というのが答えだ。(LF)言語はきわめて複雑であり、まさしく謎そのものだという、一九五〇年代にさかのぼる長い歴史を持つ言語観は存在するものの、ここまで見てきたように、実は言語自体はそれほど難しいものではない。こうした言語観とは対象的に、われわれが見てきたのは、言語の核になるのはシンボルと並べ方であって、われわれの脳にとってそうした成分を発達させるのはさほど難しくはないということだった。その一方で、話すべき内容を得るのは難しいかも知れない。そしてそれは文化と個人の知能の両方に依存する。ホモ属の脳が進化して、われわれの種としての知能も高まる間に、言語自体はさほど改良されなかったが、それを使う能力は向上した。頭が良ければ、同じ道具でもうまく使える。もちろん、道具を改良することもできるだろう。」(P.171)
「言語と高まった知能が組み合わさることで、時間とともに蓄積した知識が、やがてサピエンスがアフリカを出た時ーーつまり、一〇万年前のーー第二の認知革命をもたらしたのだろう。」(P.172)__??
「そのような社会には司祭や専業の音楽家や大工などをはじめとする、あらゆる専門職業が存在しない場合が多い。これは狩猟採集民によって認められる文化的課題(何に価値があると思うか、その環境で何ができるか、そこで暮らすことをどのようにして選んできたか)が、ほとんど専門化の余地を与えないからだ。」(P.172)
「サピエンスの脳は良くなっている。だが、さらに重要なのは、サピエンスの文化と歴史が豊かになったことだ。サピエンスは他のホモ属の種から多くのことを引き継いでいて、古くからの知恵をその文化、言語、思考に組み込んでいる。サピエンスが他の種から分かれて以来の独自の肉体的、文化的発達に、そうした付着物が加わる。言語はもちろん、ホモ属の中で、過去一九〇万年ほどの間に変化している。しかしホモ属の生物学的な面も大いに変化した。エレトゥスなど他の種は、サピエンスとは個体の発達のしかたが違う。(LF)生物人類学者はホモ属の各種のいろいろな「生活史」について書いてきた。サピエンスはホモ属の生物先祖よりも発育が遅い。ホモ属と他の霊長類の生活史の違いとしては、妊娠期間が長くなり、成長にかかる時間が長くなった(サピエンスは、どうやらネアンデルタール人やエレクトゥスも含めた他の霊長類よりも、授乳期も長く、成人してからの時間も長い)ことなどが挙げられる。人類は長生きするためにゆっくり生きなければならない。これは動物界ではよくあることであり、成長が遅ければたいてい寿命は長くなる。しかし人間の生物学的な性質はこの単純な構図とはすこし異なる。人間は誕生と誕生の間が非常に短いからだ。これはたいてい、寿命が短い生物の特徴だ。この点で、人類はクジラのようなところもあればウサギのようなところもある。」(P.173)
「鉄器時代にも人々は木器を使っていたし、現代のイノベーションの時代においても、ホモ・サピエンスの大半はたいしたイノベーションはしていない。」(P.182)
「しかし同じくらい重要なのは、脳は他の脳ともネットワーク化されいることだ。哲学者のアンティ・クラークが以前から言っているように、文化はわれわれの脳を(FF)「超大型化」する。」(P.182-183)
「このおそらくは人を驚かせるであろう主張は、とくに遺伝する言語障害があることを示す説得力のある証拠が今のところ存在しないという事実によって裏付けられる。言語障害は他の身体的あるいは心的問題に根ざしているのだ。」(P.184)
「脳を機械と見なしたがる欲求は、ガリレオが宇宙を時計にたとえたところにまでさかのぼる。」(P.185)
「端的に言って、概念的な内容について、すべての人間に生まれつき備わっている源は存在しない。概念は決して生得ではなく、学習されるのだ。」(P.186)
(P.192)__体が大きい=脳が大きい=優秀。鶏が先か卵が先か=親が先か子供が先か。
「ホモ・フローレシエンシスがホモ・エレクトゥスよりも知能が低かったことを示す証拠は、頭蓋の大きさ以外にない。両者が本当に同じくらいの賢さだったら、現代人類と比べると農の大きさがだいたい三分の二だったホモ・エレクトゥスも、ホモ・サピエンスと同じくらい頭が良かったかもしれない。この問いの要点は、化石人類の知能に関わる証拠を探している場合、文化的な証拠が身体的な証拠よりも重要かもしれないということだ。」(P.194)__どちらが優秀か、どちらが賢いうかという議論の意味。人類と猿、人類と新コロ。
「ダンバーは、人間の知能の発達を促したのは生態学的変化による問題解決の必要ではなく、知能や脳化の圧力は、人間社会の規模が大きくなったことによるものだと論じる。」(P.195)
「さらに言い換えれば、集団の大きさが増すと、人間の皮質も大きくなる。」(P.196)
「すでに見たように、性淘汰は、美しさ(雄の孔雀の羽)や、女性の胸が他の霊長類に比べて大きいことや(初期のヒト族も胸が豊かな女性を好んだらしい)、男性のペニスが長いことなどの身体的特性に関連する、進化による変化の大きな力としてダーウィンによっては早い段階から認識されていた。(LF)また、高い知能の持ち主の方が、知能を減退させる副作用がある精神や神経系の病気(髄膜炎のような)を生き延びる可能性が高いというのも、知能の向上を有利にする対価に加えられるかもしれない。あるいはそこから、雄も雌も、障害や長期的影響が比較的少ない形で病気を生き残った相手を選んだという形で性淘汰を促したかもしれない。」(P.197)__大きなペニスも好んだ?きっとエヴェレットは大きなおっぱいが好きなのだろう。「圧力が高まる=>変化する」この因果関係を問え!!多分「大きくなるべき」という発想。
「こうしたコミュニケーションの方法を使うようになると、人々は一緒に考えられるようになり、身の回りの世界を知り、その未来の形を予測する互いの能力を高めることができた。サピエンスの先祖の頭を占めるようになった疑問は次のようなことだった。「数秒後にあの動物はどこにいるか」、「あの火はどの方向に燃えひろがるか」、「今度雨が降るのはいつか」、「あの川はどこへ流れ、上流へ行くと何があり、下流に行くと何があるか」、どうしたことを問いながら、自分たちの社会的相互作用を整理し、近親者などの関係者を特定して、認知能力の一般的向上をもたらすために、言語使用が必要になった。」(P.198)__知能を比較する意味は?数値化できたとして、それが「知能」なのか。これらの疑問が知能だとすれば、人間は生物の中でも下位に属する。そんな知能や言語がなくても、他の動物、あるいは植物も生きている。「考えるまでもない」ことだ。
「ヒトの雄のペニスは霊長類の中では体の大きさに比して長い。これは人類が習慣的に対面して交接を行う唯一の霊長類であることの結果かもしれず、さらにこれが雌雄の絆を強化したこともありうる。あるいは、何らかの理由で、ヒトの雌が巨根の雄に惹かれるようになったという可能性もある。」(P.199,注)__デカパイ、巨根、さらには巨尻も魅力だというのか。対面位(正常位)が「正常」なのか。正常位では胸を揉むことが難しい。後背位のほうが気持ちいい(奥まで届く)し、胸も揉むことができる。猿も人の正常位を見て真似ることがるらしいが、すぐやめてしまうようだ。気持ちよくないんだろうな。
第6章 脳はいかにして言語を可能にするか
(P.201)__人間の認知能力が低いこと(犬のように鼻が利かない、トンビや鷹のように遠くを見ることができない、など)が、知能の原因かもしれない。Nota Bene!!!
「しかしこうした大脳と爬虫類の脳の痕跡的部分が機能上の言語系の一部であるなら、それは言語を司る部署が、ただ言語だけでなく、われわれの心的あるいは皮質的生活のさらに高い水準の編成に複数の形で寄与する脳のさまざまな領域とともにあることを示す。これは言語が少なくともその一部は、一連の後天的な習慣や定型作業であり、スキーをしたり自転車に乗ったりタイピングをしたりなどの作業と同じようなものだということを教えてくれる。そもそも、習慣と定型作業は大脳基底核の掌握範囲なのだ。」(P.202)
「確かに、言語に結びついた脳の部分はいくつかあるし、実際、なければならない。ただそうした部分は一般に言語だけに充てられているのではない。ブローカ野のような脳のある領域において、言語や文法だけに焦点を当てるのは、フォークさえ見ればキッチンの機能はくまなく研究できると言っているようなものだ。」(P.206)
「人間の脳は柔軟なので、そのいろいろの部分が、ホモ属のエレクトゥス以後の進化の歴史のさまざまな時期に用いられるのではないかとと思われる。現代人類によって用いられる脳の部分は、たんに今のホモ属の脳が利用する神経生物学的な仕組みである等だけかもしれない。それ以前の種が統辞のために別の脳構造を用いていた可能性は大いにある。」(P.225)
「骨相学という廃れた「科学」、あるいは局在化は、頭蓋骨の物理的特徴を、そこに収まっている脳の認知、情動、道徳的特性に結びつけようとした結果だった。これもまた、宇宙や脳を時計仕掛けであるかのように見る、ガリレオ的メタファーの濫用による誤りだ。」(P.227)
「長期記憶は「宣言的記憶」と「手続き的記憶」に分けられる。」(P.229)
「宣言的記憶はさらに、意味記憶とエピソード記憶に分かれる。意味記憶は「バチュラーとは結婚していない男性である」というような、どんな文脈からも独立した事実に対応する。」(P.230)
「他方、エピソード記憶は、特定の文脈に対する長期記憶であり、したがって、個人的になる。」(P.230)
「さらに脳の思考はおおむね、人が保存し、色どりを与えた個人的体験全体から来ている。」(P.231)
「フランスの哲学者ルネ・デカルトの星であり、その後の西洋世界の文化と歴史の基準を築いた人物だ。それ以前の五世紀以上にわたって、概念ではなく人について語られる時代が続いていたが、そこでデカルトは、あらためて斬新かつ独自の思考を流行らせる先駆となった。デカルトを始めとする少数の人々が登場する前は、「論証(リーズニング)」とは、すなわち力を伴う行為(act of power)であるとされる。千年近く続く抑圧的な暗黒時代がぽっかりと口を開けていた。このため当時、ある人(FF)の見解につての論じ方は、対人(アド・ホミネム)論証という、核心にある考え方ではなく、人の評判に基づいて論じることが標準的だった。」(P.231-232)__弁証法。陪審員制度。
「チョムスキーはデカルトの、身体は機械だが、心は明らかに物理的なものではないという主張を支持しているようだ。(LF)二元論は人間の思考を進化で説明することを難しくする。これは、非物理的なものであれば、進化のしようがないという単純な理由による。」(P.232)
「ウォレスは実際、デカルト派の非物理的実態である心は進化しえなかったと信じていた。」(P.232)
「こうした接続の多くは、最初は自然発生的であるが、何度も同じタスクにさらされると定型になり、学習が起きたことを示す。こうした活動には一貫した筋があるが、それは解剖学的というより電気化学的だ。つまり、静止的かつ配線済みではなく、流動的でダイナミックに変化する。(LF)脳の組織では化学物質が支配者であり、感情や思考過程や食事や生体全体の状態によって生成されるホルモンがわれわれを制御している。そのため、多くの神経科学者が、脳は「身体化されている(embodied)」ーー解剖学的、化学的、電気的、物理的に制約された系、つまるところわれわれの体に組み込まれているーーという理論をとっている。そのような研究者にとっては、脳が考えているというより、個体全体が考えるということになる。つまり脳は他のどの器官とも同じ、身体的器官であり、体の構成素なのだ。この身体化は、思考における文化の役割とともに、脳が体を通じて物理的(FF)に世界に組み込まれていて、コンピュータとは違うということを意味する。(LF)すると、ここに現れてきた脳の姿は、認知的にはモジュラー的ではない器官で、生まれつき言語に(あるいは料理やギター演奏に)特化した組織はない。これは、身体能力に関して存在する、生まれつき特化した領域とは正反対だ。一方で文化あるいは概念にかかわる能力にはそうした領域はない。」(P.234-235)
「私が Language: The Cultural Tool〔言語ーー文化の道具〕で論じているように、鳥の鳴き声のような他の動物のコミュニケーション方式には、わたしがさらに Dark Matter of the mind で定義したような文化の成分がないので、他の動物は言語を持ちえない。それに文化は、存在するかもしれないとされているような生得のバイアスを無効にすることもできる。」(P.235、注)
第7章 脳がうまく働かなくなるとき
SLI(特異的言語障害)(P.238)__
「ある障害をどう定義するかが、その人が見るものを決めることがありうるのだ。」(P.241)__心は遺伝するか。しない。多分。
「そして、ASDにかかっている人は往々にして、複数の人々が同じ「仲間」で互いに相手を受け入れていることを確かめる、この相互の「グルーミング」行動を取る能力に欠けている。」(P.250)
「つまり、何度も見てきたとおり、言語は共生的であり、言語の複数の成分あるいは使い方が、互いに互いを可能にしているということだ。」(P.251)
「言語は、いかなる意味においても完璧な生物学的系とはほど遠いだけでなく、上滑りするだけで自分が思うようなコミュニケーションがとれない場合も多く、聞き手は環境の文脈や世界の知識の一般的な事実を使いながら、そこで言われていることを解釈することになる。」(P.252)
「言語障害は、人間の脳と、脳の言語に対する準備段階を覗く窓になる。しかし言語(ランゲッジ)は脳だけのことではない。音声による言葉(スピーチ)を可能にする肺から口までの構成要素を含む、体全体の機能だ。言語体系(ランゲッジ)と運用言語(スピーチ)は別物であり、「運用言語」にはいろいろな種類ーー視覚言語、手話言語、音声言語ーーがあるが、世界のあらゆる言語体系において、運用言語の第一の形態は口頭によるものだ。」(P.255)
第8章 舌で話す
「音声言語は言語の後に現れた。」(P.256)
「人間による創出物は、ときとともに良くなっていくものだ。」(P.257)
「そして最も重要なところは、言語にとって、われわれが知っているような音声言語(スピーチ)は必須ではないということだ。言語は口笛でもハミングでも出せるし、子音があってもなくても母音一個でも話せる。われわれに言語をもたらしたものは、文化とホモ属の脳の融合だ。ただ、われわれの現代の音声言語は、優れた、機能的なアドオンの一つなのだ。」(P.258)
「言い換えると、耳と口は、何百万年もの間ともに進化してきたために、一緒になってうまく働くということだ。」(P.252)
(P.275)ボールドウィン効果__「アメリカ合衆国の心理学者ジェームズ・マーク・ボールドウィンが提唱した初期の進化の理論である。ボールドウィン進化(英: Baldwin evolution)とも。大まかに言えば、学習能力が高くなる方向に選択が進むことを示唆したものである。選択された子孫は新たなスキルを学習する能力が高くなる傾向があり、遺伝的に符号化された固定的な能力に制限されない傾向が強まる。種やグループの持続的な振る舞いが、その種の進化を形成するという点を重視する。 」(Wikipedia.jp)
「しかし、サピエンスの高性能の声道は、音声言語にも言語にも必須ではない。持っていればとても良いということだけだ。」(P.275)__「便利」が何を生み出すか。
「要するに、われわれの脳の発達は、言語の他のモードあるいはチャンネルを使えないほど、言語音と密接に結びついているわけではない。すべての人間が、進化によって、ある人は手話用、ある人は音声言語用というように別々の神経ネットワークを備えれ生まれるというのはありそうにない。」(P.280)
「話しながら食べると命取りになったり、重大な問題をもたらしたりする。」(P.281)
第Ⅲ部 言語形式の進化
第9章 文法はどこから来たか
「言語は決してすべてを表現はしない。文化がその細部を埋めるのである。」(P.294)
「言い換えると、「cat」には「c-a-t」と三つのスロットがあり、それぞれのスロット用のフィラーは英語の言語音から得られる、ということだ。」(P.298)__文字で音素を考えるが、韻は文字で考えない。音を文字で考えてはいけない。c-a-tではなくcatで考えるべき。pat、pet。cat が c-a-t だと考えるのは文字文化。cat はそれで一つの音。アルファベット文化。ねこ、猫。中国語では一音節。「おはよう」は「お-は-よ-う」ではない。
「歴史と文化は、何もなければ純粋に音素によって編成されたであろう音節を乱したり覆したりするように作用する、ありふれた因子である。(LF)音節のこの知覚的かつ調音的編成は、言語に無理なく二重のパターン化をもたらす。音が聞きやすくなるように編成することによって、言語は結果的に追加の労力なしでこのパターンを得る。音節の両側のそれぞれと核が横の音節編成をなすのに対し、端に置ける音、核における音がフィラーとなる。そしてこのことは、音節がある意味で文法より複雑な言語に至る鍵だったかもしれないことを意味する。あらためて言うが、音節の基となる考え方は単純で、「音を聞きやすく、覚えやすくなるようにチャンクせよ」とうことになる。」(P.300)__「オス」「オス」だけで文はできる(オリバーな犬)。何度も「グー」を出して意思を伝える。
「音韻組織は、人間行動の他のすべての形式と同じく、記憶対表現の綱引きに制約されている。言語にユニットが多くなるほど、メッセージを表す際の曖昧さは減るが、一方で学習すべきことや記憶すべきことが増える。」(P.301)
「言い換えれば、発音あるいは音生成のしやすさに関係なく、その地方の好みによって変更が行われる。こうした仕上げは、単語の中の一定の音の知覚のみならず、グループの識別にも有効だ。そのため、聞きやすさ発音のしやすさ、あるいは文化的な理由を動機にして、ある音をその集団のものだとわかるようにするために変更が加えられることがあっただろう。」(P.305)__方言、若者言葉、ギャル語、官庁ことば、犬のおしっこ
(P.306)__韻を踏んでいるかいないかは文化によって違う。文字の影響もある。
「われわれはことばで考えるようになったことで、たとえばたんに映像で考えるよりも思考が明瞭になったのかもしれないが、それはあくまでも言語の副産物だろう。思考自体は言語の目的ではない。」(P.340)__話せるようになっていたから話した。同時に聞けるようになっていたから聞いた(意味がわかった)ということ。イノベーションではない。
「それでもチョムスキーの研究成果は洞察に満ちていて、情報科学者、心理学者、言語学者によって何十年も使われているが、そこでは言語がコミュニケーションのためのシステムであることを否定している。」(P.315)
「ここで言おうとしているのは、一部の理論に反して、世界の言語や文化に利用できる種類の異なる文法が存在するということだ(線形文法、階層文法、再帰的階層文法)。この三つの方式はあらゆる言語に使えるものであり、文法を編成するための方式はこれだけしかない。人間の統辞に向かう編成用の雛形は三つだけであり、しかも原理的にはあまり難しいものではない。」(P.315)
「逆に、いままでに得られたデータは、いかなる細かな文法であっても、それが短期記憶を補助し、発話の理解を促すように進化してきたことを示している。」(P.316)
第10章 手で話す
「したがって、言語進化のどんな理論も、手、口、脳の共生と、この三つがどう進化してきたのかの分析によって説明されなければならない。」(P.331)
「目が見えなければ、音声言語のコミュニティでのジェスチャーを観察したことがないので、その(FF)ジェスチャーはその土地で見られるジェスチャーとは正確に一致しない。しかしまさにその事実が、ジェスチャーがコミュニケーションの一部をなしていて、言語が全体論的であることを示している。われわれはコミュニケーションをとろうとしているとき、できる限り自分の体を使う。つまり、われわれは自分が言っていることを手足や顔などで「感じて」いるのだ。」(P.345-346)
「マクニールは「共始原性(equiprimordiality)」という用語を導入した。これはジェスチャーと言語音声は、言語の進化において同等、かつ同時に存在したということを意味する。つまり、ジェスチャーがなかったら言語は存在しないし、存在しえないということだ。」(P.346)
「つまり、言語は文法、意味、ハイライターなしには(FF)ありえないということだ。その理屈で言えば、言語なしのイントネーションも、イントネーションなしの言語もありえなかっただろう。」(P.346-347)
「つまり、こうした初期の発話には「部分」はなく、全体だけがあるということだ。」(P.347)__いまでも全体しかない。
「ここでジェスチャーが用いられる理由の一つは、志向的動作には体全体が関わるからだ。」(P.348)__下を向いて殿様と話す家来は肩でジェスチャーをしているか。ジェスチャーの少ない日本。
「まず、言語音声でジャスチャーを置き換えるとこはできない。ジェスチャーと言語音声は統合された一つの系を生る。」(P.349)
「ただここで肝心なのは、ジェスチャーが言語音声と共進化したということだ。手話言語、言語はめ込みのジェスチャー、手まねが言語音声に先行するとしたら、言語音声が発達する機能的な必要はなかったことだろう。」(P.350)
「世界中のすべての言語と文化で誰もがジェスチャーを用いるらしいという事実は、知識はつねにあらかじめ存在するというプラトン的な見方よりも、知識は学習されるものだというアリストテレス的な見方の方を支持する。」(P.351)
「そしてどんな発話であってもその主要な要素は、伝えようとする事物やそれに何が起きたのかであるため、文はトピック(話題)とコメント(評言)によって編成される傾向がある。文(もっと大きい語ではなく)のトピックは、議論されている旧情報か、聞き手がまだ知らないだろうと話し手が想定する情報のいずれかになる。コメントはトピックに関する新たな情報だ。必ずとは言えないが、次の例のように、トピックは主語と同じで、コメントは述語、つまり動詞句と同じになる場合が非常に多い。」(P.356)__論理の上では知らないことを伝える。情報。でも、ジョークは?新しい「形」で伝える?和ませる、関係を再生産する。
「実は、英語はかつて前者のグループに属していた(ドイツ語と近い関係にあった)が、一〇六六年のノルマン人の侵攻の後、イギリスはフランス語と同じ、主語・動詞・目的語の順に切り替わった。」(P.357)
「言語が採用する語順は、その社会の歴史に影響を与える文化的な圧力の結果である。」(P.358)
第11章 まずまず良いだけ
「「常識」とはまさしく経験であり獲得された文化的情報なのだ。」(P.362)
「文化がなければ言語はない。」(P.365)
「人はこうしたことを教えてもらう必要はない。自然とそういうふうにふるまうものだからだ。」(P.365)
「グライスの原理の四つの格率ーーすなわち、質の格率、量の格率、関連性の格率、マナーの格率は、すぐに言語学者、哲学者、心理学者、社会科学者の間で人気を得た。そしてこれらはシンプルかつ直感的に正しいという点において発見としては申し分のないものだった。」(P.366)__分けることは何も生み出さない、かもしれない。あまりにも豊か(莫大)だから。書は言を量的に超える。どうして分けてしまったのだろう。「パンドラの箱」を開けた(分けた)せいか。便利な道具が人を支配するようになる。
「実は、ピダハン語をはじめとして、動詞を実際に文中で使う際に、自分が言っていることにどれだけ確証があるかーー推測なのか、噂なのか、直接見たことなのかーーを聞き手に伝えるための接尾辞(FF)をつけなければならない言語は多い。」(P.366-367)
「グライスの格率は文化を補完するものではない。文化を前提にするのだ。」(P.370)
「言語はその意味を一意に定めることができない。そのため文化なしには、サピエンスであろうとエレエクトゥスであろうと、コミュニケーションは存在しない。」(P.372)
「つまりわれわれは自分の意図を言葉にしないし、言葉にしたことを意図しているとも限らないのである。」(P.376)__建前と本音
「ただ、会話の含意だけが、発話の解釈、暗黙の情報、言語行為に対する文脈のすべてをなしているわけではない。とはいえ、含意によって文法は、必要とされる文よりも少ない情報を特定するだけでよくなる。意味の残りはやりとりの文脈や文化から話し手が推測するに任せるのだ。」(P.378)__「聞き手」の間違い?
「関連性理論の見方では、話が語られる、会話が行われる、あるいは文が発話される場合には、つねに発話の文脈があるとされる。」(P.380)
「いずれにせよ、ピダハン語の歴史的展開の中では、交換を目的とする語彙を発達させる必要はなく、逆にお返しの期待がない贈与を表す言葉のほうが必要になったということだ。」(P.385)
「背景の文脈にはあまりに多くの情報があり、われわれの記憶の中にある、解釈には用いるが実際には言わない(そしてしばしば自分が知っていることすら知らない、あるいは使っていることも知らない)情報も多すぎる。そのため、どれほどジェスチャーやイントネーションやボディランゲージで補強しようと、たんなるシンボルによってすべてを表現することはできない。したがって、言語が進化するにつれて、言語行為、間接的言語行為、会話、語りは、協業や、暗黙の(語られない)情報や、文化や文脈に大きく依存することは明らかだ。これまで言語が機能してきたのは、そのやり方でしかありえないからだ。」(P.386)
第Ⅳ部 言語の文化的進化
第12章 共同体とコミュニケーション
「それでも、この言語年代学や歴史言語学の分野全体は確かに、言語は変化し続けるということを示している。実際、言語学者は現代諸語の変化は主に、一種の言語自然淘汰の結果であることを認識している。」(P.394)__言語がどんどん減っているのも、「自然」淘汰か。
「言語は文化的人工物なので、言語を理解するためには文化を理解しなければならない。」(P.395)
「文化は人々を区別し、形成する。たとえその役割が「父」のような、一見普遍的で表面上は文化から独立しているように思える場合であってもだ。イタリア人の父親もあればアメリカ人の父親もあるが、「父」の概念はすべての文化で同一ではない。どのような文化どうしを比較したとしても、父の役割は、その一部は重なっていても、決して同一ではないらしい。それどころか、同じ文化にいるように思える父親どうしで(FF)さえ、時代が違えばその役割の性格が違っている。」(P.398-399)
「それは「父親」の文化的役割が、変化する文化の価値観によって定義されるからだ。」(P.400)
「こうした心の共通項目が生じる理由は、一部にはそれぞれの人が一生の間に、経験、教訓、関係を蓄積するからだ。こうしたことはすべて、ある意味でわれわれの心と体に同化している。同じ共同体で育った人々は同じよな経験ーー気候、テレビ、食べ物、法律、価値観(脂肪は良くないとか、正直は善だとか、懸命に働くのは神の教えに忠実であるといった)ーーを持つ。エピソード記憶と運動記憶がさまざまな経験を、われわれの中に埋め込まれる文化的経験として一つにまとめる。われわれの「自己」あるいは少なくとも「自己の感覚」は、この記憶と統覚の蓄積にすぎないのだ。」(P.400)
「インデックスでもアイコンでもシンボルでも、それを理解するのは、直接であれ間接であれ、意図的な行為である(これは、理解するためには少なくとも記号と指示対象とのつながりを暗黙のうちに認識することを必要とするからだ)。ただし当のインデックスは意図的なものではない。足跡は人に結びつけることを意図してつけられるのではない。それはただ結びついているだけだ。(LF)文化的な情報を解釈する能力を獲得するには時間がかかる。すべての人は文化と言語の外で生まれる。われわれはみな、母の胎内から出てくるときは部分的には異邦人だ(「部分的」というのは、新しい文化や言語についての学習は体内で始まっているから)。」(P.401)
「その一九世紀の例が、一八六七年のメディシンロッジ条約だ。(LF)この条約は最初から無効だった。少なくともそのときに先住民と結ばれた公式の条約が無効だったと言えるのは、政府側が不誠実だったせいではなく、言葉はそれが話されたものであれ、条約に書か(FF)れたものであれ、それぞれの共同体の価値観、知識、経験(つまりは文化)に由来する理解の不可視の宇宙における見える部分だけにすぎないこということを、調印する者どうしが認識できていなかったからだ。」(P.401-402)
「しかし自分の家族以外に対する恒久的な義務というのは、先住民の価値観や世界の仕組みについての理解とは相いれなかった。」(P.402)
「白人との取引において、その場では言及されていないダークマターの重要性に留意することを知り、その後は、結ぼうとする条約に調印する前に、白人が立てているかもしれないと考えられるあらゆる想定の可能性について問いただした(ある文化の外にいながらすべてに適切な問が立てられる人間はいないとはいえ)。」(P.403)
「言われていることの意味は、会話で話されている言葉だけに基づいているわけではない。それどころかそれは、主な基礎ですらない。」(P.403)
「人間の言語あるいは人間の社会のいかなる人工物も、それが解釈される文化によってしか理解されない。」(P.403)__Nota Bene!!!
「(「構造化された知識」とは、知識の一覧を知っているだけでなく、そこに載っている知識どうしがどう関係するかも知っているということを指す)」(P.404)
「集団が唱えることが個人の価値観になれば、社会と個人が結びつく。これが文化を形成し、言葉を変える。単語が新たな意味をまとい、新たな単語、新たな意味が生まれる。文化の変化は言語の変化をもたらす。」(P.404)
「私はこの「話をともにする相手のように話す」という原理は、人間のあらゆる行動について言えると思う。食べるのをともにする相手のように食べるし、考えるのをともにする相手のように考えるといった具合に。われわれは広い範囲の共有属性をまとう。われわれのつながりが、生き方、行動のしかた、外見ーーつまり表現型を形成する。文化はわれわれのジェスチャーや話に影響する。体にさえ影響する。アメリカ人としては早い時期の人類学者だったフランツ・ボアズは、環境、文化、体系の関係を詳細に調べ、人間の体形は高度に柔軟で、その土地の生態的文化的両方の環境の力に適応して変化するという確かな説を打ち立てた。」(P.405)__!!!
「ピダハン族の表現型が似ているのは、ピダハン族が必ず単一の遺伝子型を共有しているからではなく、価値観ーーたとえば食事についてであれば、何を食べるかの知識、どれだけ食べればよいのかの基準ーーを含む文化を共有しているからだ。(LF)こうした例は、文化と人間の社会的行動の研究は「話をともにする相手のように話す」、あるいは「成長をともにする相手のように成長する」というスローガンに集約されるというさきほど取り上げた所見からは、身体ですら逃れられないことを示す。」(P.406)
「文化を構成する構造と価値が進化するには時間がかかる。」(P.407)__それでも「進化」というのか。「変化」ではだめなのか。
「確かに人間はみな、何らかの価値を共有している。だがこの対極にいる、あらゆる文化はすべて違っていると説く文化相対主義者もまた、正しい。どんな文化や個人もすべてが同じ知識構造を有しているわけではないのだ。」(P.408)__韻の地域差と人間の地域差。「文化の定義」とは差の表現にすぎない。私は文化相対主義者か。
「すべては全体との関係で構造化されている。そしてこの階層構造は逃れようもなくゲシュタルトの出力を生み出す。つまり、われわれが知っていることの総体は、われわれが知っていることのすべてをただまとめたものより大きい系を形成することを意味する。交響曲はその音符のリストよりも大きいのと同じだ。」(P.409)
「そうであれば、こうした価値の優先順位が、体形の違いを生み出すといってもいいように思える。」・・・「つまり、こうした考察を行うためには、集団における価値がどのようなものであるかだけでなく、価値どうしの優先順位についても知っておかなければならない。しかしながら、集団の持つ価値観がどのようなものかを知るには、詳細な調査が必要となる。つまり、ホモ・エレクトゥスの各共同体の文化について、多くのことは推測できないということだ。」(P.411)
「たとえボストンの投資銀行の職員だろうと、アマゾン川流域の狩人だろうと、あるいはエレクトゥスの船乗りだろうと、それぞれがそれぞれの社会の中で占める地位と役割を見いだす。こうした役割は通常、個人によって創出されるのではない。それは個々の文化によって、出現したり、出現しないようブロックされたりしている。」(P.412)
「こうした行動はみな文化の文法に収まっており、その中ではそれぞれの人が単独であれ共同であれ、何らかの役割を担っている。」(P.413)
「知覚のしかたや思考の範囲は、その相当部分が文化的ネットワークによって形成される。そして結局のところこれは、ヨーロッパの社会においては、デカルトの二元論とアラン・チューリングによるコンピュータとしての心というアイデアによって、認知の核は表されるということだった。だがそれ(FF)はどうやら間違っているらしい。」(P.414-415)__!!!
「サーモスタットがエアコンのスイッチを入れるのは暑いと思っているからだと言うこともできる。あるいは、足の指先が丸まるのは、そうすれば暖かくなると指が考えれいるからだとか、あるいは植物が太陽に向かって伸びるのは、そうすべきだと信じているからだとか。確かに実のところ、会話の便法として信念が動物や雲や樹木などにもあるという言い方をする文化は、ピダハンやワリを始めとしてたくさん存在する。だが、私が生活をともにして調査をした部族はほとんどの場合、このような信念があるとするのを文字通りに意図しているわけではなかった。(LF)信念とは、体(脳を含む)が、何かーーたとえそれが概念であっても植物であってもーーの方へ向けられているときに生じる状態だ。信念は言語と文化に参加している個人によって形成される。」(P.415)
「道具は文化的知識にあふれている。道具は文化の結晶であるとさえ考えることができる。道具には、シャベル、ペンキ、帽子、ペン、皿、食べ物のような物理的なものもあるが、そうでない道具もまた、非常に重要だ。人間の最も重要な道具は言語かもしれないし、実のところ、文化そのものも道具の一つだ。」(P.416)
「文化に対する慣習や個人の重要性を議論すると、文化を認知の核として理解するようになる。つまりここでは、文化がなければ、新たな思考を支える意味的な理解も背景も暗黙の知識もありえないということになる。」(P.420)
「現代人類がホモ・エレクトゥスに負っている借りははかりしれない。エレクトゥスは穴ぐらの原始人ではなく、文化的につながった共同体の中で話し、生活した最初の男であり、女であり、子どもであり、人類だったのだ。」(P.420)
おわりに
「言語の中核をなすのはシンボル、つまり、文化的な合意を経た形象を文化により発展した意味に組み合わされたものだ。この過程は人類の知覚と思考の制限の下で進行するが、大部分は人類の社会、価値観、社会構造の産物である。(LF)シンボルは、たとえば木の根をヘビと間違えるなど、二つの対象を誤って結びつけたことで生まれたのかもしれない。あるいは、パブロフの犬がベルの音と餌の関係を学習したように、ある事物と(FF)対象との順当な結びつきの結果なのかもしれない。とにかくいったんこうした結びつきができあがると、人々によるシンボルの利用が始まり、各々が他者から学んでいくようになる。」(P.423-424)
訳者あとがき
「そこで著者が強調するのは、言葉を全体として見るということです。」(P.427)
「単純なものが複雑になる成長の物語というより、もともと複雑な一つの全体から、言語やその様々な側面が分化して豊かになる話と言えばいいでしょうか。」(P.428)
《終わり》