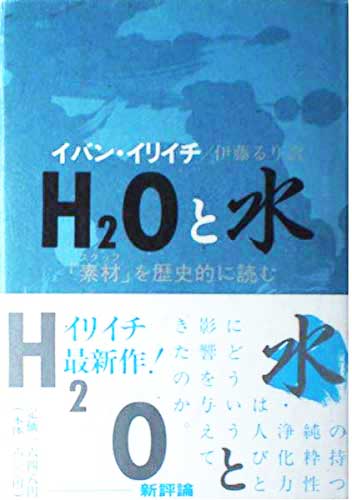
ダラス市人工湖
ダラス市のなかに人工湖を造るという計画が持ち上がり、イリイチは市民運動の側(たぶん反対派)から発言を求められました。その回答が本書です。
それは、推進する側も反対する側も、湖水の自然美がダラス市民の精神生活を向上させるという点において、暗黙の合意に立っているということである。(P.9-10)
いわゆる「都会のオアシス」というやつでしょうか。原発推進派も反対派も「電気は必要」という点ではほぼ合意しています。ロシア・ウクライナ戦争(?)にはほとんどの日本人が反対しているでしょう。でも、ロシアの石油も天然ガスもいらない、ケータイは使わない、夜はロウソクで我慢する、と言える人がどのくらいいるでしょうか。
実はイリイチは賛成・反対を明確に述べていません。ただ、
私は、以上の考察がダラスの選挙民にとって市内に人口湖を造るかどうかを決める際の参考になると信じている。(P.168)
と言っているだけです。
イリイチが述べているのは「水」の歴史、そして「H2O」との違いだけです。
H2Oと水
いくら理科が苦手でも、たいていの日本人は「H2Oは水だ」と答えると思います。そして「水はH2Oですか」と訊かれれば「そうだ」と答えるでしょう。そして、「百年前も、千年前も、一万年前も水はH2Oだった」と考えます。「H2O」は「超歴史的存在」です。いや、イリイチの言葉でいえば「没歴史的」(P.17)です。
それに対して、「水」がもつ意味は、地域や時代によって変わっています。古代ギリシャにおいても、古代インド、古代中国においても「世界の成り立ち」を考えるとき、世界を構成する「元素(要素)」として「水」が考えられることが多くありました。
この本の原題は
H2O and the Waters of Forgetfulness : Reflections on the Historicity of "Stuff" The Dallas Institute of Humanities and Culture, Dallas, 1985
です。これを伊藤るりさんは『H2Oと水 「素材(スタッフ)」を歴史的に読む』というタイトルにしました。
ここでいう素材は「元素」に近いかもしれません。しかし、さまざまな文化や歴史によって意味づけられる「水」ではなくて、「〈物質〉としての水」「人間とは無関係に客観的に存在する水」と言ってもいいかもしれません。そういう意味での水という素材は、
なぜなら「素材」そのものは没歴史的なのだから。(P.17)
そもそも最初から、私はすべての水が H2O に還元できるなどと想定することを拒否しているのだ。(P.18)
イリイチは「水はH2Oではない」というのです。
空間
「〈物質 matter 〉としての水」と書きましたが、物質についてイリイチは、ガストン・バシュラールの『水と夢』を取り上げ、
物質とは、すなわち、われわれの想像が姿かたちをあたえる、あの「素材」を指す。私もまた、バシュラールの思索の方向にしたがって、「素材」とその形態を区別し、都市を造りあげている二種類の素材ーー都市空間と都市用水ーーの間に想像力が生み出したきずなについて考察しようと思う。(P.16-17)
「想像(イデア、形相)が姿かたちをあたえる、あの「素材」」とは、アリストテレスの言う「第一実体(質料)」ですね。
まずは「空間」です。
近代都市の住人に「物質としての空間」という感覚を思い起こさせるのは至難の業である。かれらは空間を「素材」として感じとることができない。(P.42)
プラトンの「容器」(hypdechomene)は、アリストテレスによって、存在の論理的な四つの「原因」の一つと化し、「質料(hyle)」と同一視されてしまう。アリストテレスは、西洋の空間知覚の最終的な土台、すなわち容器としてではなく、広がりとしての空間認識を築いた。(P.46)
プラトンは「空間=容器」として捉え、アリストテレスは「空間=質料=広がり」と捉えているということです。「容器」であれば、そこに「内側」と「外側」があります。内側と外側を隔てるもの、それが古代の都市であれば「城壁」、家であれば「壁」です。共同体と共同体の境は、日本では「山」や「峠」であることもありました。その向こうは「鬼が住む異界」でした。
それを歩いて越えることは可能です。でも、文化がそれを禁止していました。文化が禁止していること、それを行うことはまさしく「共同体を離れる」ことです。それは「死」と同じです。
でも、それを「広がり」として捉えるなら、自分の都市は無限に続く空間の「一部」でしかありません。そしてそれを越えていくことも可能になります。それ(デカルト流の幾何学的連続体)を(高速)道路でつなぐことも、飛行機で渡ることも可能です。しかし、
ほとんどの文化は、数学や物理学の形式的連続体になじまない「外界」の現実をみる眼をもっている。ギリシャの神々も、民衆文化のなかの幽霊たちも、また、バラケルススがニンフ、空気の精、小人や火の精について表わした論文によれば、四大元素〔地・水・火・風〕のなかに宿るという火や水や空気の自然の精霊たちも、そのようなデカルト流の連続体のなかには住みえない。幾何学は、私の想像を紡げるような糸を巻ける紡錘ではないのだ。」(P.58-59)
寂しさ
「数学や物理学の形式的連続体になじまない「外界」の現実」、それは「科学で捉えられるもの」ではないし、「真理」でもありません。「普遍的なもの」、「唯一なもの」でもありません。地域や時代によって、つまりその時の文化に応じて千差万別なものです。それは、イリイチが言う「ヴァナキュラーなもの」です。例えば「地球は動いている」という考え方は、西欧の、それも500年(コペルニクス『天体の回転について』1543年)ほどの考え方です。これを「真理・普遍的なもの・唯一の考え方」などと考えることは、どれほど傲慢なことなのでしょうか。私は「頭」では分かっているつもりですが、地震のときとめまいがするとき以外には「地球が動いている」と感じることはありません。あるいは細菌やウィルスが病気を起こすと信じていますが、それを自分の目で見たことはありません(コッホが炭疽菌を発見したのは1876年)。
太陽がまわっていると考えることも、疫病神(疫病神)が病気を起こすと考えることも、神が世界を作ったと考えることもできます。
文化はそれぞれ、独自の空間を形造るし、また、このみずから生み出した空間自体が文化ともなりうるのである。(P.27)
「数学や物理学の形式的連続体」を唯一の真理と考えたとき、「火や水や空気の自然の精霊たち」がいなくなったときに感じる「寂しさ」を逃れることはできるのでしょうか。デパートやスーパーマーケットやコンビニに並んでいる「画一的な商品」を見たときに感じる寂しさと、手作りのものを見たとき感じる暖かさはどこからくるのでしょうか。
「科学」や「論理」、「愛」や「自由・平等」というようなことばに感じる「薄っぺらさ」、どこかに自分を固定していないと(たとえば、故郷とか、自分のルーツだとか、自分が所属する国家だとかに)自分が「根無し草」のように感じるのはなぜなのでしょうか。それが「「外界」の現実をみる眼」なのではないでしょうか。
ムネーモシュネー
水の流れは、レーテー河が死者の足もとから洗い落とした記憶を、この井戸にまで運び、そのことによって、死者を単なる影に変えてしまうのである。この記憶の井戸を、ギリシャ人は「ムネーモシュネー」(Mnemosyne)と呼んだ。(P.74)
「レーテー河」は、日本でいえば「三途の川」でしょうか。ムネーモシュネー(ムネモシュネ)は、記憶の女神です。
宇宙の一元素ーー洗い流す水ーーは、ティーターン神族のなかに位置づけられることで、記憶の源となり、文化の水源となり、そして女性の諸特徴を付与されたのである。
しかしながら、壮大な叙事詩の口承文化が廃れたとき、口承文化における最初の女性もまた忘れ去られてしまう。古代ギリシャの詩人は、以来、記憶するのに「はるかむこう」の力を必要としなくなるのである。詩の源はテクストとなって、凍結されてしまう。(P.77)
ことばを発するとき、人は、思考と言説とを区別することなど想像もしなかったのである。声は保存しておけなかったし、それは跡形もなく消えゆくものであった。(P.78)
文化的英雄としてのプロメーテウスが人類に持ち帰った土産のなかには、「あらゆるものを記憶のなかに留めることができる文字の組み合わせ、すなわちムーサイの芸術を生む創造の母」があった。ムーサイを厚かましくも文字のなかに閉じ込めようとするプロメーテウスを、ゼウスは厳しく罰した。(P.80)
水の(記憶の)女神は「文字」によって忘れ去られました。語られた(口承の)叙事詩は「文学」になって、固定されてしまいます。世界は固定可能なもの、「(思考、考察、操作、支配の)対象」となったのです。ヘラクレイトスの「流れ」は止まってしまいました。対象を止めることによって、つまり「同一性原理」によって、世界は「科学(学問、知識)的に捉えるもの」になったのです。
におい
都市には人が集まります。そこは糞尿の臭いや死臭が漂う場所です。
当然のことながら、都市は歴史上、一貫して臭い場所だった。(P.110)
そのため、死体(遺体、遺骨、墓)を都市から締め出し、糞尿を街の外に運び出します。そして、「水」によって、それを流しだすようになります。水は街を「浄め」、臭いを消します。
においとは人間が居住することによって環境に残す痕跡である。(P.118)
人間も、他の生き物にも「におい」は大切な情報です。おいしい食べ物を見つけたり、腐った食べ物を区別したりするだけではなく、相手の発情期を知ったりします。においはある風景や経験とも結びついてもいます。物や人(他者)を識別したり認識したりするときには、視覚情報だけじゃなく聴覚、臭覚、触覚あるいは味覚の「五感」をフル動員します。実際には5つ以上の感覚があるとも言われていますが(Wikipedia)、それらは分けることができないのではないかと私は思っています。少なくとも、「五感」というのは地域や文化、歴史に根ざした分類方法です。虹の色が7色だというのと同じように。
いまの日本では「生活臭」という言葉は、「良くない」意味をもっています。それは消し去るべきもののようです。いつ頃からか、日本に「芳香剤」というものが流行りました(それまでも日本には「香」の文化がありました。でも、それは芳香剤とはまったく違うものです)。それは「湯上がりの石鹸の匂い」(石鹸の匂いではなくて、石鹸に添加された香料のにおいですが)が変化して、「香りの柔軟剤」になりました。それらは「付け加えるにおい」ですが、それが「脱臭」に発展します。毎日風呂にはいるだけではなく、「朝シャン」も一般的になっているようです。
「におい」はその人の「由来」であるとともに「生き様」でもあります。それを消そうとすることは、まさしく「匿名化」することです。
排泄物だけでなく、身体自体も悪臭を発することが発見された。(P.129)
においの社会的弾圧は、互いに収斂する三つの態度をもたらした。一つは羞恥心。ノルベルト・エリアスによれば、人を文明化する羞恥心は、自分の不潔さを屈辱的にもあざけられることへの習慣的な恐怖として理解することができる。恥をかいた人間には自分のにおいを他者に押しつける大義名分がないために、かれの怒りは内向する。けれど、いまとなっては洗うにも遅すぎるので、顔を赤らめるのである。第二に、困惑。困惑は羞恥心とは別のものである。それは、都市の無臭空間を足のむくままに歩くうちに自分と同じ環境世界からくる人間に、においからそれと気づき、自分の汚れた、忌むべき過去をあらためて自覚されたときの、とげに刺されたような痛みである。第三に、羞恥心は困惑の恐怖と重なって、においに対して敏感な感性を生み出す。個人がそれぞれ、〔においが漏れないように〕自分をしっかりと包みこんでしまうのと同時に、この、いまや文明の徴となった清潔さは人を他者の私的空間から遠ざけるのである。こうして、人はみな、他者にとってのスカンクとなる。(P.134-136)
そして、
水は、においを洗い落とす洗剤となった。(P.132)
漂白剤を使えば多くの汚れは見えなくなります。でも、それは汚れがなくなったとは限りません。雑菌もついたままかもしれません。逆ににおいは見えません。でも、目で見えなくてもにおいはいつまでも体(部屋)につきまとって、「私」の存在を脅かし続けます。目で見える姿だけではなく、その内部をさらけ出すことは「自我の壁」を壊されることです。「プライバシーの侵害」と呼ばれるものです。
においを放つことは、その人の影や鏡に映る姿や地面に残った足跡と同じ程度に人格の一部をなしている。これらのものすべてのなかにオーラを知覚することができる。人々は相手がどこの出身であるのか、においをかぎあてることで、相手の素性を知る。(P.119)
「立ち居振る舞い」「訛(方言)」そして「におい」などがその人の「オーラ」を作っています。それは地域やその文化という意味ではイリイチのいう「ヴァナキュラー」なものですし、それを個人や個体について言えば「パティキュラー」なものです。それは、ミアズマ(瘴気、μίασμα, miasma)であり、衛生的、社会的な観点から無くさなければなりません。
ユートピアを創出するために都市空間を脱臭するこの努力を、私たちは、近代的首都の建設にむけて都市空間の「大掃除」にとりかかる遠大な計画の一環として把握する必要がある。それはまた、臭いにおいのする人々が、同じように臭いにおいのする庶民と群れを作り、かれらの分散したオーラを統一するのを弾圧する動きとして解釈できる。かれらの「共通した=庶民的な(コモン)」オーラは消滅しなければならないのである。なぜなら、そうなって初めて個人といえるような個人が無限に自由に循環できる新しい都市空間を作ることができるからである。オーラのない都市は、臭覚にとって文字通り「どこにもない場所」=ユートピアなのだ。(P.120-122)
悪臭(瘴気)が漂い、不潔なロンドンやパリなどの都市は「水道」による水の供給と「下水道」による汚水の排除で無臭化を目指します。都市も個人もそのオーラを失って「均一」になることを目指します。
「素材」の回復
ところが二〇世紀後半になると、蛇口から出てくるものは無臭ではなくなって、そのなかにはまったく新しい、そして考えられないような汚染物質が入っていることが知られるようになったのである。多くの人は、水を子供たちに飲ませることを拒否するようになった。H2Oは完全に、洗浄用の液体と化してしまった。かつては、水にふれることで、人はその奥深くに潜む純粋性と交信することができたし、水は精神的な汚れを洗い落とす神秘的な力をもっていたのだが、二〇世紀に生きる私たちの想像の世界では、水はその両面における力を失ったのである。(P.166)
フレッド・ピーボディ監督『すべての政府は嘘をつく』でオバマ大統領が、汚染が問題となっている水道水を「飲むふり」をするシーンが思い出されます。
私の住む田舎の地方都市では、まだ「水道の水」を飲むことができます。それでも水道料金は必要です。いつの間にか水は「コモンズ(共有物)」ではなくなって、「買うもの(商品)」となりました(斎藤幸平著『人新世の「資本論」』、堤未果著『日本が売られる』参照)。
水はもはや浄化の担い手ではなくなり、逆に人間が水の浄化を自分の責務と心得るようになった。H2Oと水は象徴的な反対物といえる。H2Oは近代の社会的な創造物であり、技術的な管理を要する稀少な資源である。それは近代的精神の発露であり、理性の夢によって育まれる怪物なのだ。H2Oには夢の水を映しだす力がまったく残されていない。今日、都会の子供は生きた水にふれる機会をほとんどもっていないし、そのような機会があったとしても、せいぜい街路掃除人がまだ取り除いていない雨水や水たまりに思いをよせることで想像されるだけとなってしまった。(P.167-168)
ペットボトルの水を買うこと、朝シャンをすること、SNSに匿名の書き込みをすること、文字を「ことば」以上のものと考えること、においのない街(部屋)に住もうとすること、水とH2Oが「同じ」だと感じること・・・、それらはけっして「没(超、汎)歴史的」なものではありません。それぞれが歴史的なものであるとともに、文化的なものなのです。イリイチは、それを「史的事実」を列挙することで明らかにします。ダグラス市内に人工湖を造るかどうか、あるいはいま日本で行われようとしている「原発処理水の海洋投棄」を認めるかどうか、その判断は「H2Oと水」は同じなのかと言う問いなのです。この問題提起に答えうるのか、私にもまだはっきりとした自信はありません。それは学者(専門家)だけが考えればいいことではありません。SNSを見る(書き込む)、ペットボトルの水(お茶でもコーヒーでもいい)を買う、歯を磨いて口臭を消す、マスクをしたり石鹸で手を洗う、などの日常的な行為を行っている一人一人が造り出している「文化」そのものの「問い」です。
[著者等]
イヴァン・イリイチ[wiki(JP)](Ivan Illich)
1926年9月4日 - 2002年12月2日。オーストリア、ウィーン生まれの哲学者、社会評論家、文明批評家である。現代産業社会批判で知られる。イヴァン・イリッチとも表記される。


