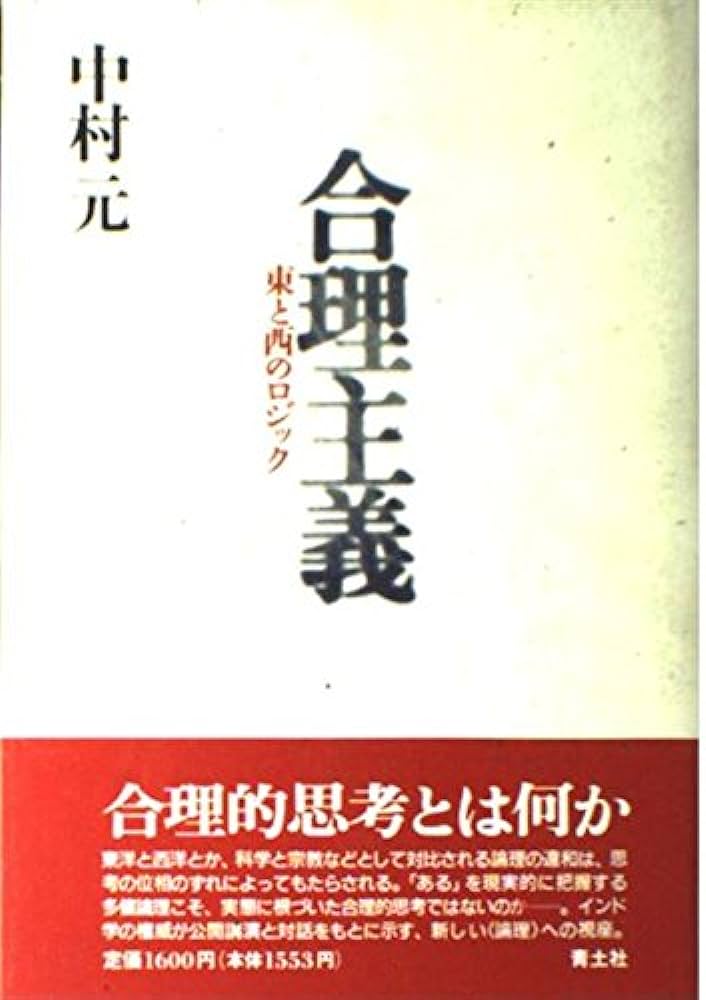
図書館から借りてちょっと読んだら面白そうだったので、古本で買いました(図書館の本には線が引けないので)。140円+送料350円。
中村元の本は『自己の探求』以来。2冊目。『自己の探求』はとても面白かったので。
自然科学を専攻する学生に向けての講演という特殊な状況(公開講演ですから、その他の人も来ていたでしょう)だったのかもしれません。でも、出版したのですから、著者の意図と外れているわけではないと思います。
著者の専門はインド哲学、仏教学、比較思想(後付著者紹介)です。この本の主題は「宗教と合理主義」ということになります。ですから、「科学と合理主義」の話があまり出てきません。それを「当然のこと」と聴衆と共有しながら話を進めます。「科学」が西の論理(ロジック)で、「インドや中国の思想」が東のロジックです。
ごうり‐せいガフリ‥【合理性】
〘 名詞 〙
① 道理にかなった性質を有していること。論理の法則にかなった性質をもっていること。
[初出の実例]「神の有無を論じ、神の人格性を難じ、乃至は宗教的信仰の合理性を評せんとするが如き」(出典:自覚小記(1906)〈綱島梁川〉)
② むだがなく、能率的に行なわれるような物事の性質。
[初出の実例]「『それはもういらないのだから、どうぞ棄てておくれ』と、木村が云った〈略〉木村の口から始て合理性(ガフリセイ)的な詞が出たと思ったことだらう」(出典:田楽豆腐(1912)〈森鴎外〉)(精選版 日本国語大辞典)
ごう‐りガフ‥【合理】
〘 名詞 〙 道理にかない正当であること。論理の法則にかなっていること。〔哲学字彙(1881)〕
[初出の実例]「名誉ある議員の挙動はげに一応は奇怪にも不都合にも見ゆべけれど、又よく思へば且自然にして且合理(ガフリ)なりと言はざる可らず」(出典:春迺屋漫筆(1891)〈坪内逍遙〉政界叢話)
[その他の文献]〔新唐書‐百官志一〕
合理の語誌
「合理」という表記は「新唐書」や「書紀‐継体六年一二月」の「教示合理」に見られるが、明治初年に rational などの訳語として用いられた「理に合(かな)う」から、新たに成立したものか。(精選版 日本国語大辞典)
ろんり‐てき【論理的】
〘 形容動詞ナリ活用 〙
① 論理の法則にかなっているさま。理屈に合っているさま。思考、推理のわざに巧みなさま。
[初出の実例]「属を分て種となす方法を、論理的分類と云ふなり」(出典:教育学(1882)〈伊沢修二〉四)
② 論理学に属するさま。また、前提された事件や事情から正しく推論するさま。(精選版 日本国語大辞典)
ろん‐り【論理】
〘 名詞 〙
① 議論・思考・推理などを進めて行く筋道。思考の法則・形式。論証の仕方。
[初出の実例]「如此に論理を尽し、日月を経て、商定せる憲法なれば」(出典:米欧回覧実記(1877)〈久米邦武〉一)
② 物事の中にある道理。また、事物間の法則的なつながり。
③ 「ろんりがく(論理学)」の略。(精選版 日本国語大辞典)
中村さんは、その語源についてはっきりと言っていません。中村さん監修の『新・佛教辞典』(1962)には、「合理」の項目も「論理」の項目もありません。なので、単語としては「ratio, rational」「logos, logical」などの翻訳語だと言っていいでしょう。普段使われてる意味もそうだと思います。
最近は、西洋の言葉(概念)をそのままカタカナで輸入することが多いのですが、明治期の翻訳者はその横文字に何とか漢字(の意味)を当てはめようと頑張ってくれました。そのためには、その西欧語がどのように使われているのかの膨大な知識が必要だったでしょう。そして最終的には、その翻訳者が最も納得した意味、その多くは当時西洋で主流だった(流行っていた)西洋思想の意味です。
私が知る「論理」の語源はギリシャ語の「λόγος」です。動詞形は「λέγω」。「(果物などを選んで)摘む」「数える」といった意味ですが、「意図的に何かを選んで口に出す」のようにも使われるようになりました。おもちゃの「レゴ」はここ(lego「組み立てる」というラテン語)からきているのでしょう。
λόγοςは「μύθος(ミュトス、神話)」の対立概念で、簡単に言えば「人の言葉」と「神の言葉」でしょう。当然「神の言葉」の方が大事だと考えられていたのですが、ソクラテス・プラトンあたりの時代に「人の言葉」の優位性が増してきます。「神話は作り話だ」という人も現われます。なんかそういう人がいつの時代にもいますよね。そしてそれが当時の社会(政治)状況とマッチして流行ります。「(人の)言葉(当時のはやりで言えば弁論)」の優位性は、森羅万象の法則はロゴスだ、世界はロゴスで成り立っている、となっていきます。Wikipediaの「ロゴス」の項目には、
1.言葉、言語、話、真理、真実、理性、 概念、意味、論理、命題、事実、説明、理由、定義、理論、思想、議論、論証、整合、言論、言表、発言、説教、教義、教説、演説、普遍、不変、構造、質問、伝達、文字、文、口、声、ダイモーン、イデア、名声、理法(法則)、原因、根拠、秩序、原理、自然、物質、本性、事柄そのもの、人間精神、思考内容、思考能力、知性、分別、弁別、神、熱意、計算、比例、尺度、比率、類比、算定、考慮などの意味。
転じて「論理的に語られたもの」「語りうるもの」または「言葉(言詮)を通じて表される恒常的真理もしくはそれに付随する言詮内容」という意味で用いられることもある。
2.万物の流転のあいだに存する、調和・統一ある理性法則。
3.「宗教(ミュトス)的位相」であるキリスト教では、神のことば、世界を構成するミュトスに基づく論理としてのイエス・キリストを意味する。(Wikipedia)
というたくさんの意味が載っています。「ロゴス・フィーバー」の観があります。
「ratio」は、「reason、reality」などの基になったラテン語ですが、元々は「res(与えられた)もの」、動詞形は「reor(解する)」の名詞形です。これがロゴスのラテン語訳にも転用されました。
完了分詞 ratus から別の名詞 ratio (英 reason の祖形)が派生、ロゴスの羅訳語に転用された。類義語に動詞 scio がある。こちらは原意が「割る」「割く」「分ける」。和語で古形「分く」から「分かる」が派生したように、 scio からは「理解する」「知る」の意も派生する。名詞形 scientia (英 science の祖形)はエピステーメーの羅訳語となった。(古田裕清著『西洋哲学の基本概念と和語の世界』中央経済社、P.167)
つまり、さまざまな時代の変遷を経て、同じことを表したり、別の意味が加わったりしているわけです。それぞれの時代の流行にマッチしたり、流行を作り出したりしていたのです。
私が重要視したいのは、中村さんの言葉で言えば「思惟形式の方向」の推移です。「神、自然」などから人間を見る視点と、その逆の視点です。変遷の流れを貫いているのは「人間を中心」とする見方の強まりです。もっと言えば「自分を中心」とする「見方」です。神や自然、そして他者は「自分(我)から見た(見える)」もので、人間(自分)の外にあり、観察、研究、管理、制御、支配、処分などの「対象(客観)」となります。そして人間(自分)は「主体(主観)」となります。そして、人間が「神の視点」に「上昇」し、世界、自然、人間、そして「我(自己)」や「汝(他者)」をも見渡す(見下ろす)ようになります。
論理も合理も「理」という言葉がつきます。そのほか真理とか道理とか倫理とか有理・無理、理の付く言葉はたくさんあります。理は「たま(玉)へん」に「里」です。「玉」は「宝石」、「里」は音符で「すじ目」の意味です。「みがかれた玉にすじめの現れる意を示す(『新釈漢和』明治書院、1969)」。
中村さんの説明は、
ここに「正理」(Ñāya = Nyāya)と「理法」(dhamma = dharma)という相似た語が用いられ、ゴーダマ・ブッダはそれに従って生きて来たのだと言う。或いは「それを説いた」(pavaiī = pravaktṛ)のだと言う。この両語の区別ははっきりしないが、次のように理解し得るのではなかろうか。(1)正理(Nyāya)とは、論理的必然性を持った道理を言う。これはインド一般の理解であるが、また自然界における必然性の道理もこの部類に入るであろう。これは、人間の主観的意欲によっては如何ともし難いものである。そこには選択の自由はない。
(2)「理法」(dharma)とは、人間の取るべき道である。それは人間の意志によって実行することも実行しないこともできる。道徳の理法である。そこには選択の自由がある。
両者はしばしば混じて考えられる。東洋人が「理」というときには多くは(2)を意味するが、西洋人が理性(reason, Vernunft)と言うときには多くは(1)のほうの理を意味する。そこで(1)のほうは、人間の感情や美的感覚を完全に無視することになる。
その区別は現在の日本語の中にも生きていて、「あの人は理性的な人だ」と言うと「冷たい人」という印象を与える。
この意味で「合理主義者」と言うと「計算ずくの人」ということになる。
ところが日本語で古来の表現として「有理」と言うときには、多くは人間的な理法、すなわち(2)を意味する。(P.35-36)
人間の「外の世界」に「理(法則)」があると考えること(正理)、だから人間(自分)はその「道」(PUFFY『これが私の生きる道』の「道」)に沿って生きなければならない(理法)ということです。「論理と倫理」と言い換えてもいいかもしれません。正理も理法も人間(自分)の「外」にあります。外にあるから、人間はそれにしたがって生きることもできるし、意図的かどうかは別として、そうじゃないこともする(してしまう)。だからそこに「自由」が生じます。もし人間(自分)がその中にいれば「自由はない」、というか、「そんな面倒な事は考えない」のです。西田幾多郎の「主客未分」です。
私は、その主客構造から発生する「面倒な事」に悩みたくありません。「楽をしたい」ということじゃなくて、悩んだり困ったり苦しんだりしたとしても、「それ以外のこと」に悩んだほうがいいと思います。ちょうど「モノがない悩み」と「お金がない悩み」のような違いです。「面倒な事」「お金」自体を目的に思う人がいます。多くの学者(と言われる人)や「通帳の数字を見てニヤニヤしている人」などです。本当の目的は「悩み」や「お金」自体ではありません。恋愛だったり、食べ物だったりが目的で悩みやお金はそのための手段です。
目的(τέλος テロス)と手段(πορος ポロス、或いは methodus、μέθοδοςなど?)との混同や取り違えはママあります。カントの有名は定言命法「人格(他者)は常に目的として扱われねばならず、決して手段とされてはならない」なども、その取り違えを批判しているわけです。
でも、本当に批判すべきは「どうして目的と手段が分離するのか」、言い換えれば「どうして〈他者(というもの)〉が存在するのか」ということだと思います。そしてそれは翻って「どうして〈自己〉が存在するのか」ということです。
文頭にも書いたように、中村さんは『自己の探求』(1980)という本を書いています。デカルトの「我思う、ゆえに我あり」を持ち出すまでもなく、「私がある(いる)」ということは当然のように思えます。
〈自己〉とはなにか?この問題は、古来幾多の哲学体系・宗教思想において中心問題であった、と言えるであろう。(『自己の探求』青土社、P.11)ただわたくしは、近代西洋で強調され、またこのごろの日本ではやっている〈人格の尊重〉ということばには、何かしら〈いやらしさ〉を感じる。いかにも虚構にみちているという感じである。たえず〈員数〉として扱われている点には〈尊敬〉の扱いを受けているとは思われない。(同書、P.76)
私も「マイナンバー」という番号をつけられ、1億2千万分の1の扱いしかされないところに、〈人格の尊厳〉とは正反対のものを感じます。
ところで自我を〈実体〉とみなす見解は論理的に一つの誤謬を含んでいる。「実体」とか「性質」とかいうのはカテゴリーであって、現象世界についてのみ適用され得るものである。経験世界においてのみ適用され意義をもつところの「実体」というカテゴリーを、経験世界をこえた領域においても意義をもつと考えて、自我を実体としてとらえたところに、デカルトやインドの自然哲学者たちの誤謬がある。自我は疑えないものであるが、それが実体であるという結論は、そこから出てこないのである。(同書、P.46)真実の自己は絶対の主体であるから、対象化することができない。それは、
(1)概念的に規定することのできないものである。
(2)数や量によって規定して叙述することのできないものである。
したがって具体的には形や色をもっているものではあり得ない。もしも言語で表現し得るものであるとすると、〈語〉は他人と共通のものであり、他人と共通の手段または資材を用いて理解しようとする限り、独自の自己がまさにその人の自己として独自である所以のものは逃げ去ってしまう。(同書、P.95)
つまり、「ある」というのは「対象」についてのみ言えます。「観察(知覚)されるもの」「考えられるもの」が対象です。「我思う」と言おうとすると、「我」は「対象(客体)」になってしまうのです。そこから「我あり」という結論はどうやっても出てこないのです。「「我を考える我」を考える我」を考える我・・・」。主体は決して客体(対象)にはなれないのです。
自己は自己の對象となることはできない。自己の對象となるものは自己ではない。(西田幾多郎「デカルト哲學について」『哲学論文集 第六』所収、旧全集第十一巻、P.148)
「考えられる我」は認識・知覚・考察の対象となりますが、「考える我」にはそれができません。デカルトにもそれがわかっていたんだと思います。たしかに「考える我」は疑いなく「いる」ように思えます。でもそれだけでは「我あり」とは言えないのです。だから、デカルトは「神」を持ってこざるをえなかったのです。
しかし、仏教的心情が浸透しているわが国では、動物実験の犠牲となった動物のための慰霊祭が行われる。西洋にはないことである。人間のエゴイズムを否定することはできないが、西洋におけるように無反省に放置されているのではなくて、第三者の高い立場から見るということが行われているわけである。(前掲『自己の探求』、P.249)
「第三者の高い立場」、それがデカルト(西洋)の神です。「我あり」と言えないということは、我から見た対象である「他者」や「他物」が「ある」ことも確実ではなくなります。そう言っている「我」がいないのですから。つまり、主体と客体が「ある」という為に(代わりに)「神」だけが「ある(存在している)」。そのおこぼれとして(神を分有することによって)「自分たち(私、あなた、人間、動植物、自然、宇宙)」があるというのがデカルトの論理だと思います。
「論理」は「考えられたもの(客体)の間の関係」です。それじゃあ「倫理」は「主体と客体の関係」と言えるかもしれませんが、その時の主体とはあくまでも「考えられた私としての主体」です。
「普遍論争」は、
五百年以上も続いて決着を見ず、結論が附かないでも人知にも人生にも殆ど何の影響もなく、果てはその問題そのものが忘れ去られて僅かに中世哲学史に記載されているような問題、それが普遍論争であった。簡単に言えば概念は実在するか、たんなる考えた物で実在はしないのか、という問題を繞る論争である。このような問題に本質的意義があろうとはどうしても思えない。そしてそれが実証科学の興隆を永らく阻んだということ、そして事実古代には実証科学の萌芽が明らかに見えていたのに、人間の知性がこのような不毛の問題に勢力を奪われて、謂わば立ち枯れになったことなどを考え合わせると、偶然の運命とは言いながら、学問の発展にとっては甚だ不幸な歴史の経過であったと見做さざるを得ない。」(P.19、下田弘『哲学総論』Ⅰ 、明玄書房 P.347からの中村の引用)インドにおいては「不合理なるがゆえにわれ信ず」(credi quia absurdum)というような思想は、ついに現われなかった。またインド人は、一般に普遍を重視する思惟傾向があるために、同時に論理的でもある。論理的にして且つ合理的なのである。(P.85)
このように永遠にして普遍的な法を承認する宗教は、著しく論理的であり、西洋の非論理的宗教に対立するものである。(P.113)
普遍と対を成すのが特殊です。
「普遍」は『哲学字彙』が英 universal に充てた訳語。「あまねく」を意味する古来の仏教語の転用。原語の淵源はアリストテレスの論理学用語 καθόλου 〔カトルー〕。κατἀ μέρος 〔カタ メロス〕(英 particular )、καθ´ ἓκαστον 〔カタ ヘカストン〕(英 singular )と三組をなす。西周はこの三つをそれぞれ「全称」「特称」「単称」(いずれも新造語)と訳した。『和英語林集成』は universal を「一般」と訳した。「一般」は一様な、一切合切、などの意で江戸期以来の日常頻用語。『哲学字彙』は「一般」を general (genus 「類」の形容詞形)の訳語に充てた。類は種(英 species、形容詞形は special )と対語。アリストテレス論理学で類種ヒエラルキー(ポルピュリオスの樹、第4章参照)をなす。(前記『西洋哲学の基本概念と和語の世界』P.179)
「普遍」は昔から日本にある言葉です。
ふ‐へん【普遍】
〘 名詞 〙
① ( ━する ) ひろくゆきわたること。あまねく万物に及ぶこと。
[初出の実例]「紹隆三宝、遂共彼、普遍六道」(出典:知恩院本上宮聖徳法王帝説(917‐1050頃か))
② 一定範囲内の事象すべてに共通し、例外のないこと。特殊に対していう。
[初出の実例]「一糸も乱れぬ普遍(フヘン)の理で」(出典:思ひ出す事など(1910‐11)〈夏目漱石〉七)
③ ( [英語] universal の訳語 ) 哲学で、多くの事物に共通の性質またはそれをあらわす概念。⇔個物。
④ 論理学で、宇宙全体に通じてあてはまる名辞。いくつかの特殊を自分の下位クラスとして持つ一つ上位のクラス。たとえば「日本人」に対する「人類」をさす。(精選版 日本国語大辞典)
元々日本語で使われていた普遍は、字のごとく「ひろくゆきわたっていること」「共通すること」でした。それが「特殊」や「個物(個別)」に対する語と変化してきたのです。西洋においても同様なのでしょうが、プラトンのイデアやアリストテレスを再解釈する(あるいはキリスト教との整合性をとる)中で、「観念」或いは「概念」と似たような意味に変化してきたのだろうと思います。
「普遍と特殊」「全体と部分(個物)」、あるいは「社会と個人」という対立構造に変化してきたということです。特殊や部分や個人が優位になったこと、それはミュトスよりもロゴスが重要になったことと同じことだと思います。
かつてsocietyということばは、たいへん翻訳の難しいことばであった。それは、第一に、societyに相当することばが日本語になかったからなのである。相当することばがなかったということは、その背景に、societyに対応するような現実が日本にはなかった、ということである。(柳父章著『翻訳語成立事情』岩波新書、P.3)
「society」は「社会」と訳されたり「会社」と訳されたりしていましたが、「会社」のほうは「company」の訳語に、「社会」は「society」の訳語に定着したようです。
どうして日本に「社会」がなかったか。私は単純に「個人がなかったから」だと思います。どの地域だってどの時代だって「人の集まり」はあります。でもそれは「society」ではないのです。societyは「個人 indivisual 」、つまり「自己」とともに発生します。しかし、それは自己と対立するわけではありません。その自己が肥大していったときに、社会と対立し始めます。
普遍があるかないかというのは、個物(個人・部分)がなくても全体があるかどうか、という問題です。アリストテレス以来の「種(spieces)」は、ダーウィンではどう表現されたでしょうか。「生存競争」「適者生存」「自然選択(自然淘汰)」、後には「突然変異」などという言葉で「個(個体)が変わることによって種(全体)」が変わると考えられてきたと思います。それが「弱肉強食」などの「社会ダーウィニズム」「社会進化論」になっていきますが、当時はまだ「遺伝物質(のちのDNAなど)」が発見されていなかったはずです。ダーウィンは地層のなかの化石などから「生物は変化してきた」ということ(事実)と、そのメカニズムを仮説として提唱したのです(「進化」そのものを見た人はいません)。自然を「神」とするならば、「自然選択」はキリスト教と矛盾しないと思います。でも、「適者生存」と見ると、個体(主体)の優位性が見えてきます。ダーウィンがどう考えていようと(私はダーウィンを読んだことがない)、西洋において「個体(主体)の優位性」が増大していったことは想像できます。
西洋においても別の流れはあります。一つは「遺伝」ということそのものです。獲得形質が遺伝するかどうかはわかりませんが、遺伝するということそのものが「主体性」とは異質なものです。本人の「意志」ではありませんから。もう一つは「本能」という言葉です。これも本人の「意志」とは逆なものです。でも、どちらも本人の意志の原因にされ、意志の正当性のために利用されるようになります。
さらにもう一つは、「個体発生は系統発生を繰り返す」というヘッケルの反復説です(『有機体の一般形態学』1866。邦訳があるのでしょうか。なければ日本語以外わからない私には手も足も出ません)。この説には様々な解釈や批判があるようですが、西田風に解釈すれば「個体が種とその歴史を代表する」ということです。今西錦司は、
それはそれでよろしいが、もしここへ全体と部分という考えをもってきたら、どうなるのであろうか。個々の個体は種という全体を構成している部分である。すべての個体が入れかわっても、種は変わらない。種は変わらないままで変わってゆく。私の身体を構成しているすべての細胞が入れかわっても、私は変わらない。私は私である。それにもかかわらず私自身も、年とともに変わっていく。(『主体性の進化論』中公新書、P.205)
同種の個体である以上は、危機にのぞんで、どの個体もが同一の突然変異を現すのでなければならない。同種の個体とは、そういうときにそなえて、はじめから、同じものとして作られているのである。(『進化とは何か』講談社学術文庫、P.27)
と言います。私は「自己」であると同時に、人類という「種」を代表しています。個(個別・特殊・部分)は全体(普遍・一般・概念)を表してもいるのです。そして、私がいなくても私が所属する社会(あるいは人類)は存在します。私には理解できていない西田幾多郎から引用します。
有機體と環境との相互整合的に、形が形自身を維持する所に、我々の生命があるのである。それは私の所謂主體と環境との矛盾的自己同一的に、時間と空間との矛盾的自己同一的に、全体的一と個別的多との矛盾的自己同一的に、形が形自身を限定すると云ふことに他ならない。(西田幾多郎「一 生命」『哲学論文集 第七』所収、旧全集第十一巻、P.291)
多と一との矛盾的自己同一として、全體が自己の中に自己を表現する、私の所謂矛盾的自己同一的世界が、自己の中に自己を表現的要素を有つとき、それが創造的要素として作るものと考へられるのである。(同書、P.304)
今西さんの表現と似ていませんか。
的確な引用かどうかわからないのですが、ずっと同じこと(ひとつのこと)を言っているように思えています。部分と全体は「同じもの」ではないけど「別のもの」でもない、「同じもの」とか「別のもの」と考えること自体が問題なのだと。
「矛盾的」「自己同一的」という言葉がいいのか悪いのかはわかりません。「矛盾」は「たて・ほこ」、中国の古典『韓非子』に出てくる故事です。「自己同一(性)」は「(self, ego) identhty」の訳語です。私が子供の頃「IDカード」の意味がよくわかりませんでした。「身分証明書」は「身分」を「証明」するもの、なんとなくわかりますが、「自分が自分であること」なんて「証明すること」じゃないと思ったし、言われてみると「証明が難しい(できない)」ことのようにも思いました。前後して三田誠広さんの『僕って何』(1977)が芥川賞をとり、「自分探し」なども流行りました。探さなければならないような「僕」や「自分」。そんなもの証明できるわけがないじゃないですか。
たとえば identity は、翻訳者泣かせの言葉のひとつである。「自己同一性」と訳されたこともあるが、この造語をもってしても、何のことだかさっぱりわからないという事実に変わりはなかった。そこで翻訳者は降参し、こう書きつけるのである。「アイデンティティ」と。(ウヴェ・ペルクゼン著『プラスチック・ワード』藤原書店、P.216、エーファ・オトマー(福岡大学人文学部講師)「日本語版に寄せて」)
「society 社会」同様「individual 個人」がなかった日本に、アイデンティティがあるわけがないのです。
「あるものがあるものであること(A = A)」、「あるものがあるもの以外ではないこと(A ≠ B)」、「あるものがあるものであって同時に別のものじゃないこと」は「同一律・排中律・無矛盾律」という古典的な(アリストテレス以来の)論理学の三原則です。
仏教の論理学(因明 いんみょう)でも西洋の形式論理学でも、真偽論は原則的にはもちろん同じである。東洋人だって西洋人だって、真理は真理、誤謬は誤謬であるからである。ただ、三段論法で小前提の中概念が「Aでもなく非Aでもない」と言う場合、西洋の論理学ではこれは誤謬になる。「Aでもなく非Aでもない」ということはあり得ないわけであるから。ところが仏教の論理学では、その小前提の中概念を用いた思考から出て来る結論は誤謬ではなくて「不定」になる。つまり、真とも偽とも言えないというのである。そういうことが仏教の論理学では認められているのである」(P.27)アリストテレスの論理学は、同一次元または同一領域に関しては成立するが、異なった次元、異なった領域のことを考えていない。
それに対して仏教の論理学は多次元的・多領域的思考であると言えよう。(同)
つまり、次元が違えば三原則が成り立たないということです。
日本では、鴨長明の『方丈記』の文章「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。」(『日本古典文学全集 第27巻』P.27)が有名です。また、古典ギリシアの哲学者ヘラクレイトスが「同じ川に二度入ることはできない」(万物流転、パンタ・レイ)といったのに対してソクラテスは、
では、仮にそれが不断にわずかずつこっそり逃げ去って〔流転して〕いるとするならば、いったいわれわれはそれに向かって正しい名称で話しかける〔それを正しく規定する〕ことができるだろうか。第一に、かのものであることを、それから、そのようなものであることをね。それとも、われわれが言う瞬間に、もうそれは別のものとなり、身をかわして逃げ去っていって、もはや言われたとおりのものではないことが必然だろうか。(中略)いや、そればかりか、そのようなもの〔決して同一状態にないもの〕は、何者によっても認識されえないことになるだろうね。なぜなら、認識しようとする者がそれに近寄った瞬間に、それはもう別のもので別の性質のものになっているので、それがどのようなものであるのか、あるいはどのような状態にあるかは、もはや認識されえないだろうからね。そして、いかなる認識も、それが認識しようとする対象がいかなる一定の性状をももたないならば、これを認識することはないだろうからねえ。(プラトン『クラテュロス』439,旧プラトン全集第2巻、P.167-168)
ものが変化(運動)していると認識できない、ということです。「運動がない」と言うべきか、「認識できない」と言うべきか、ソクラテスの答えは、
しかし、もし一方において認識するもの〔認識の主体〕が常に存在しており、他方において認識されるもの〔客体〕が常に存在しており、美が存在し、善が存在し、もろもろの有るもののそれぞれが〔常に〕存在しているのであるならば、われわれ〔ぼく〕が今あげたこれらのものは流動にも運動にも全然似ても似つかぬものであることが、ぼくには明白だね。(同書440,P.169)
つまり、運動や変化じゃなくて、「〔常に〕存在している」んだから認識できるんだ、と言っています。生成・消滅・運動・変化じゃなく「(それらを内在しつつ)常に/すでに存在しているもの」それが「イデア」だ、と(プラトンは?)言うのです。主体が認識するのは「対象(自体)」ではなく「そのイデア」ということです。ソクラテス(プラトン?)においてはまだ「個物(個人)」よりも「普遍・概念・全体・社会」が優先されていたイメージがあります。ソクラテスは裁判で死刑(服毒死)になるわけですが、ソクラテスは「国家(ポリス・社会)」を優先してその刑を受け入れます。プラトンが「賠償金を払って死刑を免れましょう」と言うのを悲しい気持ちで聞いていたと思います。
アリストテレスは師匠プラトンの「イデア」を「形相(因)」として受け継ぎ、「イデアが宿るもの」としての「質料(因)」を考え、それを「第一実体」としました。ソクラテスやプラトンよりも「個物」を重要視したことになります。アリストテレスを読んだことがないのでこれ以上は書けませんが、ミュトス(神の言葉)からロゴス(人の言葉)に重点が移動したことと並行関係にあるような気がします。
言語と思考
中村さんは、西洋の思想や宗教と東洋(インドや中国)の思想や宗教の「相違点」を強調し、それによって「合理主義」「論理」を再定義しようとします。
たしかにインドにおけるブラフマンとアートマンの関係は「社会(宇宙)」と「個人(自我)」との対立とは異なります。インドでは「独立した個人 individual」よりも「関係としての個人」が強いからです。カースト制度が象徴的です(ルイ・デュモン著『インド文明とわれわれ』参照)。
本書第二部の「対話」で、今井功氏から、
つまり思考形式はその人間の言葉の使い方と関係が深いのではないかということです。それをもう少し広げてみますと、人間の生活する環境と思考形式は非常に関連があるのではないか。(P.187)
と質問されたときに、答えるまでに間があります。私はその時の中村さんの頭の中には「インドも西洋もインド・ヨーロッパ諸語だよなあ」という思いがよぎったのではないかと想像しています。「一高(東大)気質」に話をずらして、インド(と仏教)の思考形式に戻ります。
そして今井さんの質問にこう答えます。
言葉と思惟方法の問題は非常に重要だと思います。部分的にはむしろ素人みたいな学者がよくやっています。『ゾウは鼻が長い』という書物がありますね。あれはオーソドックスな言語学者は問題にしないけれど、しかし、われわれが見たら考えなければならない問題です。(P.197)
三上章を「素人みたいな学者」と言っちゃっていいのでしょうか。別の学者のことかな。少なくとも「非常に重要な問題」だとは思っているのでしょうが、「第一部 論考」では一切触れられていません。聞いている学生や先生は、多分欧米の論文を読んでいるでしょうし、自分の論文を英語で書いているでしょう。その時の思考形式は多分印欧語的だろうと想像します。私はサンスクリット語も中国語もわかりませんが、日本語よりもずっと印欧語的ではないでしょうか。
中村さんは、印欧語的思考形式の中で「東と西のロジック」を考えているように思います。
統制的宗教団体が存在しないから、在俗信者は俗人としての戒律を守らなくても、処罰されたり排斥されたりすることはないにもかかわらず、なお斎戒を守るのである。これは、日本の仏教界において宗派別の政治的経済的統制が厳重に行われているにもかかわらず、戒律がさっぱり守られていないのと、ちょうど正反対である。中国の仏教徒は、戒律を守ることを、教団の命令の故にではなくて、絶対者に対して守るべきものと考えているのである。(P.121)
なるほど、と思います。政治団体でも同じですね。最近「法令遵守」という言葉が声だかに叫ばれます。誰かが「法を守れという法はない」と言っていましたが、だから「法令遵守」というのは「法」ではありません。個人がなかった日本において、個人の関係を規定する「(初めは神の定めた、のちには人が定めた)法」というものの意識が薄いのは当然だと思います。
日本およびドイツの哲学者たちの悪い傾向は、事実の詳細を知らず、また知ろうともせず、僅かの図式(Schema)をもてあそんで理論を作ることに急なることである。例示した事実が誤っていることが判明すると、理論そのものがくずれてしまう。これがいわゆる合理主義哲学の欠点である。むしろ事実をして理論を提示せしめるということが必要ではなかろうか。(P.46)
ただ、日本の哲学者は、外国の思想のことは、よく勉強するが、自分で考えようとしないという欠点が顕著である。(P.47-48)
私は学者ではないのでよくわかりません。
東洋の宗教のあるものには、以上に指摘したような合理主義的性格が存する。ところがかかる合理的な宗教も、日本に来ると、日本人一般の非合理主義的態度の故に、ある点では著しく変容されてしまった。(P.132)
これこそが言語の問題だと思います。「日本語は論理的ではない(論理的文章に向いていない)」と言われることもあります。それが非合理(非論理)だというのなら、非合理(非論理)こそが日本の文化であり、それは優劣の問題ではありません。それこそ「次元が違う」のだと思います。
自然科学は今後ますます発達するであろうし、また人間生活に寄与する点がますます多くならねばならぬが、それはいかなる時期に到達しようとも、人間の存在目的に対する素材的手段的意義を有するものであるという限界を超えることはできない。(P.146)
近代社会においては、個人に対する集団の影響支配が非常に強力であるから、今後自然科学ないし、工業技術の有する社会的意義は非常に大きいと言わねばならぬ。そうして自然科学ないし工業技術の意義をこのようなものとして自覚して、人間としての全生命の具現として実現するためには、宗教的とでも言うべき暖かい心情を必要とする。それは愛と呼ばれてよい。しかも、純粋化された愛であって、人間を超えてしかも人間のうちに実現されるべき慈悲と呼ばれるものにまで高められねばならぬ。(P.150)
目的と手段の話はすでに書きました。そのうえで中村さんは「同じ土俵」に立とうとします。それは「民主主義」という土俵の上で闘っている右翼政党と左翼政党(といわれる)と同じ構造です。「東と西のロジック」、中村さんは仏教学者として「東のロジック」に重点を置くのですが、論理という同じ土俵で闘ったときに勝つのは「強いもの」です。土俵そのものがそういうロジックでできているからです。
同じ土俵には立つ必要はないし、その土俵が成立しているロジックそのものを批判できるのは「非合理的日本文化」なのではないでしょうか。
私は日本文化や日本語が「世界を平和にする」とは思えません。「自由・平和・民主主義」などの言葉も「ロジック」から発生しているからです。「すぐれた文化・言語」などというものは西洋のロジックでしかありません。
もしも人類の指導者ないし一般民衆が依然として旧来のような蒙昧で野蛮な心情を持っているならば、人類の破壊は火を見るよりも明らかである。殊に、近代科学の破壊性に対する無自覚はもはやひとつのおそろしい罪である。近代科学の発達の結果として、一般に残虐な戦術の下手人たちは、実際におのれの残虐行為を身近に感ずることがない。かれの行為はただ残虐な行為のためにボタンを押すというひとつのことに過ぎない。(P.149)
中村さんが憂慮している気持ちはわかります。(「蒙昧」とか「野蛮」とかいう言葉は嫌いですが)私も同感です。でも、ボタンを押す必要すらないのです。そう命令すれば(口に出せば)いいのです。口に出すということ、ある思考方法(形式)を言語化すること、こそが問題だとおもうのです。西洋においても英語が共通言語になりそうに思えます。中国語においても普通話(北京語)が支配的になっています。日本においても共通語(標準語)がほぼ支配的です。私はイリイチの言うように、「教えられた母語」ではなく「ヴァナキュラーな(地域的な、風土的な、土着の)言語」を取り戻すことにしか希望を見いだせないのが現状です。
仏典では宗教という場合には、宗と教に分けて考えます。「宗」は基のもので、これは言葉で言い表せないものです。言葉で言い表せない基のものですけれども、何かの仕方で言語を借りて表現して人に教えようとする。それが「教」になるわけです。(中略)教というものはいくつあってもかまわない。相対的な存在ということになりましょう。(P.196)
なるほど、と思いました。これからはそういう意味で使っていきたいと思います。
言語化される前のもの、それは諸言語を構成している特色(仮に「文法」と呼んでおきます)の影響を受けにくいもののような気がします。チョムスキーの普遍文法など論外な存在です(「存在」すると仮定すれば)。アリストテレスの「ὑποκείμενον (ヒュポケイメノン、第一実体)」のもう一つの意味、「構造化・言語化以前」(前出『西洋哲学の基本概念と和語の世界』P.5)のもの、と共通点がありそうです。
[著者等]
中村 元
1912~1999。東京大学印度哲学梵文学科卒業。インド哲学者、仏教学者。東京大学名誉教授、日本学士院会員。専攻はインド哲学・仏教学。勲一等瑞宝章、文化勲章、紫綬褒章受章(「BOOK著者紹介情報」より:本データは『 バウッダ[佛教] (ISBN-13: 978-4062919739 )』が刊行された当時に掲載されていたものです)


