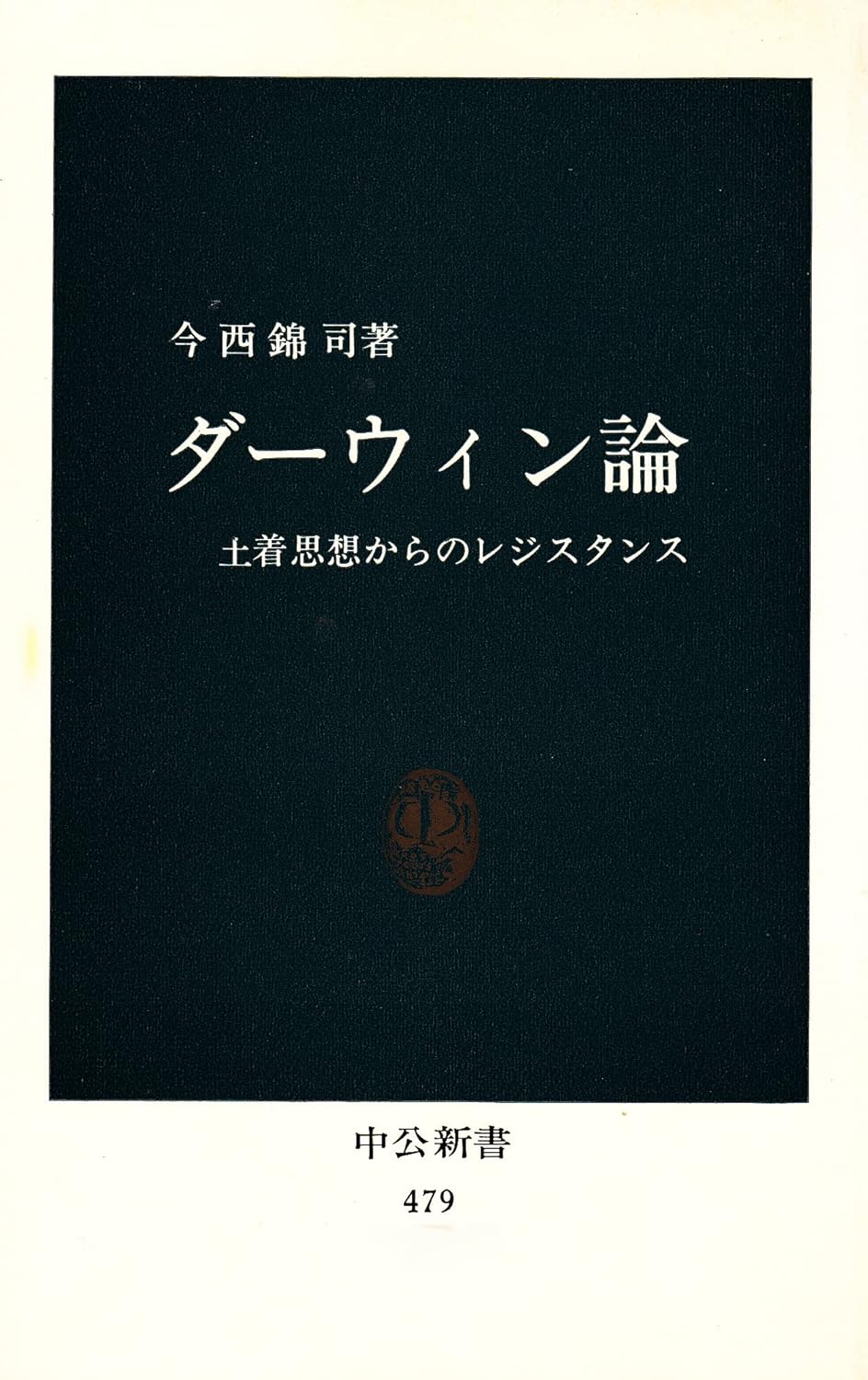
天才(変人)
自然淘汰で適者が生存するとするならば、生存しているものはみな適者であり、生存競争の勝利者であるという理屈が、とおらぬわけでもあるまい。私にこの話をして、はじめて進化論にたいする眼を開いてくれたのは、旧制第三高等学校の同級生で、いまは亡き言語学者の三上章であった。(『主体性の進化論』、以下「主」と記載、P.43)
三上章は『象は鼻が長い』などの著作で、日本語文法学に変革をもたらした人です。天才(変人)は天才(変人)を呼ぶのだと思いました。こういう仲間がいることが羨ましいけど、今西だからこそ、三上と知り合いになれたのかもしれません。
二人が生まれたのは1902・1903年(明治35・36年)。旧制第三高等学校は、京都大学の前身です(その後、三上は東京帝国大学に行きます)。どうしてだかはわからないけど、京大出身者は面白い人が多いですね。風土がそういう人を育てるのかな。環境とそこで育つ人や生きものは関係があるんでしょうね。環境と生物の関係。ダーウィン進化論(正統派進化論)にたいする今西の批判の論点の一つです。
キリンの首はなぜ長いか
(キリンは・・・引用者)その生活する地域は殆ど常に乾燥し、また草も生ぜず、それが為にこの動物は木の葉を食し、そして絶えず木の葉に届くやうに努力しなければならなかった。持続されたこの習性の結果として、その前脚は後脚よりも長くなり、その頸は、その後脚で立って伸び上がらなくとも、其を上げれば六米の高さに達する程に、伸びることになつたのである(ラマルク『動物哲学』、主、P.24)
小さい頃から聞いたことのある説明です。私は「そうなんだあ」と疑問に思うこともなく納得していました。
これに対して、今西は言います。
移動せずに踏みとどまって、高い木の葉を食うのも、もちろん気候変化に対応した生き方として、結構なのではあるけれども、それはおとなのキリンにたいしていえることであって、キリンでも子供のときは、そんな高い木の葉は食えないであろう。その場合、子供を飢え死にさせたのでは、種が絶滅してしまうではないか。子供に高い木の葉を食わないでも生きられる方法があったのなら、おとなのキリンだって、おなじ方法をとることができたのではないか。現在キリンが高い木の葉を食っているのは、首や足が長くなり、高い木の葉が食えるようになったから、食っているのに、すぎないのでなかろうか。(主、P.26-27)
痛快です。このように、通常「当たりまえ」だとおもわれていることに対して、今西は次々と疑問を投げかけます。でも、今西が言いたいのは「当たりまえじゃないよ」ということではなくて、むしろ、「なぜ当たりまえだとおもうのか」ということです。
これは、しかし、どうして納得するのであろうか。キリンが高い木の葉を食おうという欲求をもち、そのための努力をつづけたかどうかというようなことは、実証のかぎりではない。しかるに、そういう説明で子供もおとなも納得するということは、じつは自分をキリンのおかれた環境に投影して、自分だってそんな状態におかれたら、要求を実現さすための努力をしたであろう、とおもうからこそ納得するのである。そしてこれが、さきほどの引用にもあった、現在の科学の排斥する「擬人主義」である。(主、P.25)
簡単にいうなら、理性が発達してきて、人間が理屈っぽくなりだしたからであろう。これは、フランス革命の前後から目立ってきた、近代的人間の特徴の一つであって、科学の発達も、もちろんこのことと無関係ではないばかりか、進化論というものもまた、この風潮に便乗して、現れてくるようになったのである。」(主、P.37-38)
ある事実があって、それをどう知覚し、どう認識するのかは、地域や時代によって異なります。さらにそれをどう説明し、どう納得するのかも地域や時代によって異なります。なにか「対象」があって、それを知覚し認識するときにそこには文化のフィルターがあります。さらに、多くの場合はそれを「言葉(知識)」を媒介として「説明」し、その説明に納得したり、しなかったりします。どんな説明に納得するのかにも文化のフィルターがあります。たとえば、ある文化では「生物種は神が造った」という説明で納得するかもしれません。聖書の『創世記』には、神がすべての動物を造ったとあるので、カトリック教会は進化論を認めたのは1996年です。ダーウィンの『種の起源』が刊行されたのが1859年ですから、137年後のことです。「認めた」のかどうか、いろいろな意見がありそうですが(「ChristianAnsers.Net」、どんなサイトなのかは知りません)、大切なのは「認めたかどうか」でも「なぜそれまで認めなかったのか」でもなくて、「なぜ認めた(とおもわれている)のか」ということです。今西は、中世キリスト教社会と近代(現代)西欧社会との連続性よりも断絶性を強調したいようにみえますが、私が気になるのはその連続性(同質性)です。
ダーウィンの進化論
先に進む前に、ダーウィンの進化論(ダーウィン・ドクトリン)を著者がまとめているので、それを引用しておきます。
ここで私のいうダーウィン・ドクトリンを、もう一度まとめておこう。
(1)種に属する各個体間に、個体変異あるいは個体差があること
(2)生物の種はその種の維持存続に必要な以上の個体数を、子孫として生産すること
(3)したがってそこには個体間の直接的あるいは間接的な生存競争が生ずること
(4)たとえわずかでも生存上に有利な個体差をもった個体が、適者生存して生存競争に勝ちのこること
(5)適者生存した個体は、その有利な個体差を遺伝によって次代へ伝えること、以上である。
その後になってご承知のように、ダーウィンが考えていたような個体変異ないしは個体差は、突然変異にたいし、遺伝のある枠組のなかで一般に認められる彷徨変異ということになり、新種の形成に役立つのは、突然変異をおいて他にない、しかもその突然変異が有利な個体差として、それを生じた個体を適者生存せしめる場合にかぎる、とされるようになった。(『ダーウィン論』、以下「ダ」と記載、P.21-22)
どうして19世紀の中頃に『種の起源』が発表され、それが受け入れられたのか(すぐに受け入れられたわけではありませんが)。
当時は変わるということが変わらないということよりも、高く評価された。変わるということと進歩するということとが、等しいようにも受けとられていた。(ダ、P.36)
それ以降、現在まで「変わること」、つまり「新しいこと」が高く評価されています。つまり「価値がある」と思われています。
カラー写真が登場して、白黒写真は「不完全なカラー写真」になりました。BDが普及し、DVDは「画質の悪いBD」になりました。発展(進化)が正の価値を持っているとするならば、古いもの(過去)は乗り越えられた(劣っている)現在にすぎません(老人に価値はありません)。(拙稿「あなたの孤独は美しい」感想文)
進化 evolution は ē-volvō (ex+volvō) で、今の英語でいれば un-rolling つまり、「巻いてあったものを広げる」というようなニュアンスの言葉です。同じような言葉で「発見 discovery」がありますが、これは文字どおり「dis-cover(カバーを剥がす)」という意味です。同じように「発明 invention」は「in-venīre ( into-come )」で、あるものが「こちら側に来る」という意味です。どれも「すでにあった何か」の「覆いを外し、広げ、見えるようにする」というニュアンスがあるように思います。今までなかったものを「造る」ことができるのは「神」だけですから(神も無からつくるのではなくて、「混沌(カオス)」を「秩序付ける(」のですが)。「無から何かをつくることはできない」という思いはいつの時代にも、どの文化にもあるように思います。今西の「変わるべくして変わる」というのも、ある意味では同じです。
それがあるとき、ある文化では「人間は無から有を作り出すことができる」と思うようになりました。人間が動物を超え、神をも超えるのです。すべてのものは人間が理解することができます。そして、すでにあるものの上に人間が何かを「加える」ことは当然可能だし、ないもの(価値)をつくりだすことができるのです。だから、すべての判断の基準は「人間」にあります。その一つの例が「擬人化」です。そして、それが人間同士の場合には、「独我論」となります。
私が独我論とよぶのは、けっして私独りしかないという考えではない。私にいえることは万人にいえると考えるような考え方こそが、独我論なのである。(柄谷行人『探求Ⅰ』講談社学術文庫、P.12)
その時に絶対的な中心となっているのが「自我」です。それは今西がいう「主体(性)」とは違うのですが、私が『主体性の進化論』を読もうとおもったのは、その主体性(自我)がどのようにできたのかを今西が考えているのではないか、という勘違いからでした(笑)。でも、「擬人化」を批判するとき、今西は徹底して自己を相対化します。中心を自我からずらして、自然(山の中や、鴨川のほとり)の中に置こうとします。それは、結局のところ、「生物の主体性」ということに結果します。
変わらないというのは、言葉を変えたら、自己同一性(アイデンティティ)を保っているということであるから、私も種も、自己同一性を維持しながら変わってゆく、ということだろう。そして、自己同一性をもちながら、変わるべくして変わってゆくもの、あるいは自己運動によって変わってゆくようなもののことを、ここであらためて主体性をもったもの、と定義しよう。しかし、変わるべくして変わるということは、この空間的・時間的な世界に存在するあらゆるものについて、いえることではないか。そうすると、私はこの世界に存在するあらゆるものに主体性を認めよう、としていることにならないだろうか。(個体に主体性を認め、種に主体性を認めるのであったならば、もろもろの種によって、くわしくいうなら種社会によって、構成された生物全体社会にたいしても、やはり主体性を認めないわけには、ゆかなくなるのでないだろうか。(主、P.209)
いま『生物の世界』以来のことを考えてみると、私の進化論はけっきょくのところ、主体性の進化論、もすこし丁寧にいえば、主体性を前提とした進化論である、といわれても仕方ないかもしれない。(主、P.213)
生物と環境
進化論(あるいは適応)は、環境に応じて生物は進化(変化)するというものでした。そこには、暗黙としての「環境の主体性」と「生物の従属性」が前提されていたのではないでしょうか。環境(自然)を生物(人間もふくめて)が変えることはできない、変えられたとしても自然を超えることはできない、という思いです。「人間はちっぽけな存在だ」という思いです。そこでは、創造主としての神は「自然(環境)」に置き換わっています。
環境と生物とがたとえ切りはなしがたい存在であろうとも、この両者がそれぞれ別個に、独立に変わっていけないということもないし、別々に変わりうる可能性も、多分にあるとおもわれるのである。そして、ここまでくると、われわれももう少しは環境ばなれして、なにでもかでも環境にもってゆこうという悪いくせ
それはなんでもかでも適応にもってゆこうとした悪いくせと表裏一体のものかもしれないがから、足を洗うことが必要になってくるのとともに、要因論などというものが、いかに人惑わせな落とし穴であるかということに、一日も早く気づかねばならないのである。(主、P.174)
自我(主体)を認めながら、つまり擬人化しながら(擬人化というのは、自己を他者・生物に投影することである)、主体は環境に従属している、あるいは社会や構造に従属しているという思考方法が、近代西洋がキリスト教(一神教・創造主の存在)の嫡出子であることを物語っていると私には思えます。
歴史の一回性
生物全体社会に主体性をみる考えを広げれば、生物以外、物質(自然)全体にも自主性を認めることになります。それが「歴史」です。
進化とは一種の歴史である。宇宙や地球の歴史と人間の歴史とをつなぐ一種の歴史である。歴史に法則性があるかどうか、私にはよくわからないが、すくなくとも進化というのは、この地球上では繰りかえしのない、一回きりのものだという点では、なによりも歴史に似ている。(ダ、P.129)
そしてここで、進化ということを、自然現象とみるか、それとも歴史とみるか、という、ものの見方のちがいが、問題となってくるのである。自然現象とみればなにか納得のゆく説明がほしくなってくるであろう。しかし、歴史としてみるなら、説明は与えられていなくとも、首尾一貫でよいのではないか。(ダ、P.131)
後戻りのできない歴史や進化。これが定向進化に繋がります。ただし、その方向は何らかの「目的(目標)」があるものではありません。ですから、そこに「因果関係(必然性)」があるわけではありません。「一回性の歴史」は再現できないし、それを支配するのは「偶然性」です。偶然性を優先すれば、それは「突然変異説」になります。でも、今西はその「偶然性」も否定します。
けれども、いったん特殊化への道へはいったものは、もうなににでもなれるという適応放散のスタートへはもどれず、特殊化のすすむにつれて、変化しうる可能性の幅がおのずと限定され、完成とはつまりもうそれ以上は変化しようがない、という状態を指すものであろう。
ウマの進化の場合なら、一本指まできたらもうそれ以上に変化することは、考えられないから完成といったのである。また哺乳類を起用しないで、なぜ爬虫類の残党で間に合わせなかったのかという問題も、爬虫類はすべてもう特殊化をとげていたから、適応放散のスタートを、切るようなものがいなかった、ということで説明がつく。爬虫類の時代は生物の歴史において、しょせん、一回きりのものであったにすぎないのである。(ダ、P.132)
「変わるべくして変わる」という今西進化論の言葉は、必然性をあらわしたものではありません。それは必然性も偶然性も超えたところにあります。なんか禅問答のようです。
今西と西田哲学
これは、棲みわけという現象をとおして、種がみずからを限定したものである。種の自己限定であり、そういう意味では種がみずからの生活の場にたいしておこなった、一種の縄ばり宣言であるというようにも受けとれる。(ダ、P.101-102)
私は生物の構成単位である種にも、やはりきまりがあったほうがよいと思うものであって、その自己限定としての棲みわけを、高く評価するゆえんの一つはここにある、といえよう。(ダ、P.104)
私は、「自己限定」という言葉を聞くと、西田幾多郎を思い出します(西田幾多郎「一般者の自己限定と自覺」)。私は西田を読んでいないので、いい加減なことを書きますが、「一般者」は自然であり、神であり、自己です。それが限定されることによって(他との差異を確認することによって)「自覚」に至ります。今西のいう「同一性」や「場」なども、西田の用語としてとらえるとわかりやすいのではないでしょうか。他(対象)の認識はAをB(あるいは全体)から区別することが「限定」です。そして、その始まりは「自己を他者から区別すること」、つまり「自己認識」です。
ルクスとルーメン
擬人化や独我論から逃れることは困難です。私たちはなんとなく、意識の外に物があって、それからの刺激を知覚・認識していると思いがちです。
昔、電球の明るさは「ワット(消費電力)」で表されました。「40W」とか「100W」とか書いてあるやつです。それが蛍光管になると電球よりも少ない消費電力なので、ワットとエネルギー(あるいは仕事量)との関係が崩れました。最近、電気代が高くなっているのでLEDに切り替えたいのですが、LEDの消費電力と「明るさ」の関係は曖昧で、ワットの代わりに「ルクス」や「ルーメン」という言葉が使われます。それぞれの意味は調べてもらうとして、イリイチはこう言っています。
ルクスとは、主観的に知覚されるときの光のことであり、ルーメンとは、対象物を照らすために目から来る流れのことである。ヴァナキュラーな実在とは、その切れ端がそれぞれ虹色、つまりそのルクスをもっている巨大なキルトである、と考えられよう。ジェンダー分析のルーメンでは、それぞれの文化は二つの異なる組み合わせの道具(注解86、87)に関連し暗喩、つまり暗喩的な相互補完の関係(注解55-57)として現れるのである。これらは世界が理解ないし把握され(注解89)、語られる(注解94-101)ところの、互いに異なるが関連した様式のなかに表現を見いだす。(イリイチ『ジェンダー』岩波現代選書、P.146)
アリストテレスかプラトンも同じようなことを言っていて(ごめんなさい、確認できません)「おかしなことを言っているなあ」とおもっていたのですが、対象からの光(あるいは対象が反射する光)が目に入ってきたとしても(受動)、それを認識することはできません。世界は「混沌とした光の織りなすキルト」でしかありません。そこに「あるもの」を見いだすことができるのは、ルーメン、つまり、自分の目から出る流れです(能動)。知覚(認識)はすでに「自己」あるいは「自己の文化」が投影されています。対象を「自己限定(区別)」することでしか、認識は可能でないのです。イデア(概念)は「常に/すでに」あります。対象(客観)と自己(主観)を区別することはできません。
それは、「客観しかない(たとえば唯物論)」ということでも「主観しかない(たとえば唯心論や唯名論)」ということでもありません。「どちらもある」ということでもありません。主観が客観をつくると同時に、客観が主観をつくります。客観と主観は不可分な対立なのです。その「主客構造」を、無理に「絶対矛盾的自己同一」として統一(あるいは忘却)することはできないのです。
できることは、常に客体を主観のなかに取り入れ(知識)、それを相対化(懐疑・批判)してゆくことだけです。そこに「コース」があるかどうかわかりません。ただ「プロセス」あるいは「実践」のみが、近代西洋文化がもたらした「自我(自覚した自己)」をもつわれわれにできることかもしれません。今西が生涯をかけておこなったのは、山(自然)に登りながら、科学(自我)を「見つめ直す」プロセスなのではないでしょうか。
子供の頃お腹が減った経験があるか
どうしておなかが減るのかな
作詞:阪田寛夫、作曲:大中恩
どうして おなかが へるのかな
おやつを たべないと へるのかな
いくら たべても へるもんな
かあちゃん かあちゃん
おなかと せなかが くっつくぞ
私は子供の頃、お腹が減った記憶があります。ところが「飽食の時代」と言われた頃から、食べることは「義務」のようになってきました。「栄養」「健康」という言葉が溢れ、戦後の食糧不足を経験した親たちは、食べることを強制しました。強制されると食べたくなくなるものです(汗)。そのうち、「健康優良児」は「肥満」といわれ、「メタボ」なる言葉が生まれて、「痩せていること」に価値が生まれました。
街には食べ物が溢れ、テレビでは「グルメ番組」や「トレンドのデザート」が溢れています。「貧困」という言葉の性格が変わります。「おなかが減ること」ではなくて、「2000円のラーメンやデザートが食べられないこと」になります。
今日、熱製本機が届きました。新品なら1万数千円するのですが、3200円で、製本用の表紙が30冊分ほどついているものをメルカリで買いました。多分、表紙代だけで3000円以上します。私は引きこもっている関係上、ネットで物を買うことも多いです。こんな地方都市では、大きな古本屋もないし、中古の家電屋さんもありませんし。実は、製本機を買うつもりもなかったのです。なんとか手作業で作ろうと、途中まで頑張っていたのですが、印刷用の用紙やカバーを探しているうちに見つけてしまいました。ネットで検索していると、欲しかった以上のものを紹介されます。私はあまりスーパーにも行きませんが、みなさんどうなのでしょうか。牛乳がなくなったので、牛乳を買いにスーパーに行って、牛乳だけを買ってくることがあるでしょうか。だいたい、スパーに買い物に行くのに、これとこれは必ず買い、それ以外のものを買わない、という買い物をする人は少ないんじゃないでしょうか。スーパーに行ってから、「今日の晩御飯は何にしようかな」と考え、目についた美味しそうな肉や魚や野菜から、献立を決めることもあるし、「50%OFF」のシールが貼ってあるということで食べるものを決めることも多いでしょう。「欲求」があって買い物をするのではなく「スーパーで欲求がつくられる」のです。
特に注目すべきは、人々が食品の匂いや味ではなく、見た目によって選ぶようになったという点である。一九二〇年代末のアメリカでは、セルフサービスのスーパーマーケットが次第に広まりつつあった。食品の小売方法の変化とともに、あらかじめ缶やボトルに入った加工食品を食べることが日常的になったことで、人々が何を食べるかだけではなく、何をどのように選ぶかも大きく変化したのである。(久野愛『視覚化する味覚: 食を彩る資本主義』岩波新書、P.133-134)
対面販売で、カウンター越しに「〇〇ください」というと、店の人が後ろの棚から出してくるというシーンをドラマや映画で見たことがあると思いますが、そこには「欲望」をもったひとが、その欲望の充足(だけ)をしにきます。ネットはそれを加速します。
本書でみてきたように、食べ物の「あるべき」色・「自然な」色は、長い歴史の中で作り出されてきた。そうした色を人々が内面化し、ある程度共通認識をもっているからこそ、ネットスーパーの写真は成り立つのだ。つまり、多くの食品において、その色、また味や形が標準化されてきたこと、そして標準化された色を「自然な」または「普通の」ものだと多くの人が考えるようになったことによって、ネットスーパーが機能しうるのである。(同書、P.186)
自然(nature)と人工物(art)との関係が大きく変わったのですが、それは日本語でいう自然と人工との関係です。私は入れ墨(tattoo)が大嫌いですが、国際的なスポーツを観ていると、黒人も白人もアジア人にもtattooをしている選手が多い。韓国では整形手術が(化粧などと同じように?)当たり前になっているとも聞きます。「青いラーメン」や「原色のマカロン」を、私は「美味しい」とは感じない(思えない)のですが。
日本には、「虫の声を聞く」文化や、「香を聞く」文化が残っています。視覚や聴覚は五感の一つですから、聴覚や視覚がない文化はないでしょう。でも、どの感覚に重点を置くのかは文化によって(時代によって)違うように思います。近代文化は視覚(あるいは文字)が優位です。もっとも、西欧では昔から比較的視覚に重点が置かれているように思います。「見る」と「聞く」の大きな違いは、主体の置き方です。見るというのは聞くより能動的行為です。見るというのは、自分中心です。目をつぶれば見えませんが、音は「聞こえてくる」ものです。それはちょうどルクスとルーメンのちがいに対応します。
そして、視覚としての欲望は「自分の(内発的な)欲望」なのか「与えられた(外在的な)欲望」なのかを区別することが困難です。お腹が空いた経験がある人は、ある程度「内発的な欲望」がわかるはずです。ある程度以上を食べることは不可能ですから。でも、外在的な欲望はみたされることがありません。美味しいケーキが「トレンド」だといわれ、欲しくなるのは「みんなの欲望」をみずからの欲望と感じているので、「みんなの欲望」が満たされるまで、なくなることはありません。逆に満たされたとき、その欲望(トレンド)は過去のもの(古いもの、ダサいもの、価値の低いもの)となります。
この「他者の欲望」こそが、イリイチのいう「稀少性=欠如性 desire」です。「飽食の時代」は「欠如性(欠乏)の時代」です。物がない欠乏ではなく、物があっても満足できない欠乏(貧困)です。
お腹は減ります。食べても食べても減ります。新陳代謝です。
これはアナロジーだが、個体の生命に寿命があって新陳代謝がおこなわれるように、種というものにも寿命があって、その寿命が尽きたから滅びたんだ、という場合も考えられないことではない。(ダ、P.48-49)
生物であると無生物であるとを問わず、また自然物であると人工物であるとを問わず、すべてのものが一定の場を占めているということは、そのこと自身が空間の構造ということに関連している。あるいは構造をとおして、空間を形成しているといってもよい。もすこし強くいうなら、この構造をくずさぬように守ることが、すべてのものに課せられているのである。物理学でいう慣性が、じつはそれなのである。生物には慣性という言葉は適用されないが、生物に変わらないという一面があるのは、その現れである。しかし、われわれの世界には空間のほかに、時間というものがあり、この時間にせまられて、すべてのものは現状維持ができなくなる。そこで生物だったら、細胞をとりかえたり、個体をとりかえたりするのだが、そうしておってもやはり現状維持がむつかしいときには、徐々に、あるいは急速に、身体を変えてゆかねばならなくなる。(P.204-205)
環境を無視しようというのではないけれども、この個体にみられる成長という現象は、もともと私の身体にそなわった自発的現象であり、これをはたからみたら、私という主体のあらわす一種の自己運動である。
すると進化において、種が変わらないままで変わってゆくということも、環境に誘発されたり誘導されたりしなくても、もともとその種にそなわった一つの自己運動である、というようにみなせないものだろうか。時間のスケールにちがいがあることはもとよりだが、成長も進化もこれを時間軸に沿った一つのコースとみるかぎり、いずれも主体のあらわした自己運動の軌跡である、と見なしてよいのでなかろうか。」(P.206)
「どうしておなかが減るのかな」という問いと「進化とは何か」という問いは、実は同じなのではないでしょうか。今西が西田哲学から考えているのは間違いありません。西田哲学をどう評価するのか、それはまた別の機会に書きたいと思います。ただ、今西が西田哲学から得た結論は「(自然)科学的」かどうかの評価とは別に、とても本質的なものです。それだけでも西田哲学を評価したい気になってしまいます。
「飽食の時代」とか「物質文明」とかという言葉に惑わされることなく、今西進化論を読めるのは「お腹がすいた経験」がある人だけなような気がします。逆に、その経験がある人なら、きっと今西進化論がわかる可能性があります。私はその「可能性」を信じたいと思います。
つぐみ
庭に毎年、酸っぱい実のなる一本のぶどうの樹があります。今年は気候のせいか、とても甘い実がなりました。いつもは殆ど食べない私も、今年の実は美味しく食べていました。
ある日、見慣れない鳥が庭で遊んでいました。雀より大きな鳥で、調べてみるとつぐみでした。へえ、こんなところにつぐみが来るんだ、と思っていたのですが、翌日、まだ収穫していないぶどうがすべて、一粒残らずなくなっていました。
昨日の新聞に、「ぶどう収穫減、野生のつぐみか」という記事が載っていて、やっぱりあのつぐみが食べたんだ、と確信しました。
今年は、クマをはじめ多くの野生動物の被害がニュースになりました。気候のせいで、山林の食物が少ないのだそうです。クマが人間を襲うという事実を私は認めます。私は常々、それは人間がクマの領域(縄ばり)に侵入したからだ、と考えていました。開発で、住宅街はどんどん郊外に広がっています。山の木々は人間の都合でどんどん伐採されています。そこにクマの食料となる木を植えよう、などとはけっして考えません。そして、気候のせいで、どんぐりや山葡萄などが不作になればお腹をすかせたクマが人里に降りてきます。そこで人を襲うこともあるでしょう。さらに、人の肉の味を覚えたクマは、どんどん人を襲うとも聞きます。
これらはどこまでが「事実」なんでしょうか。よく分からなくなりました。お腹をすかせたクマは作物や人を襲う、そこに擬人化はないでしょうか。蚊が人の血を吸う、と、クマが人間を襲う、は同じなのでしょうか。蚊が人間に限らず、動物の血を吸うのは蚊の本性(本能)のような気がします。でも、クマが人間を襲うのはクマの本性(本能)だとは、私には思えないのです。
理性
人間は、お腹が空いたからとって、他人の畑の作物を食べたり、他人を殺してその肉を食べたりは(めったに)しません。動物がそれをおこなうのは「理性(あるいは社会性)がないからだ」と説明されることもあります。動物が「神様の使い」だと思われていたのは、そんなに昔のことではありません。それは、動物が持つ知性(本能)に対する「尊敬の念」なような気がします。動物を敬う気持ちは、神を敬う気持ちと同様、自分たち人間を敬う気持ちです。それを「理性」「社会性」などというものに押しつけるから、戦争がなくならないのではないでしょうか。戦う相手には理性はないが、私には理性がある、という考え方は「クマ対人間」と同じ構造です。人間に理性がないから(あるいは十分に発達していないから)戦争が起こるのでしょうか。
(・・・)オーストラロピテカスが現在の人類の直系の先祖であって、パラントロパスはオーストラロピテカスによって絶滅さされた、傍系の種類であると、書いてあるではないか。私はその行に赤線を引いて、これを抹殺した。(主、P.177)
人間は、他の種族を絶滅して生きのこった、というまことしやかな説が流通しています。そしてそれを旧約聖書の「カイン」の話まで引っ張ったり、あるいは「原父殺し」と結びつける人もいます。でも、それは近代西欧諸国が他の国々を侵略していたことを投影(擬人化)したものにすぎないのではないでしょうか。ライオンがガゼルを捕らえて食べる映像や、鷹が野ネズミやうさぎを襲う映像を同じような気持ちで観ていないでしょうか。
「弱肉強食」「適者生存」「自然淘汰(自然選択)」などの、ダーウィニズムの影響はないのでしょうか。
これはしかし、進化論適用の行きすぎであり、一歩誤ればいわゆる社会ダーウィニズムにおちいる危険があるのではないか。逆にいえば、これはもともとダーウィニアン・ドクトリンにしのびこんでいた擬人主義が、人間の社会にはねかえって、人間の行為を正当化するために使われようとしている、ということかもしれない。(ダ、P.141)
種の中での個体間の関係と、種同士の関係がごちゃまぜになっているし、この擬人化は植物の場合を考えると幻想であることがわかります。
植物の種子は自発的には動けないのだから、種子と種子とがよい条件をそなえた土地をめぐって、なぐりあいのけんかをするはずはないのである。植物は太古からこの方法をかえずに生活してきた。なぐりあいのけんかのないところで、生存競争というのもたいそうすぎるから、生存競争というかわりにこれを個体間のコムペティション competition というようになったが、生存競争だってコムペティションだって、思想的・内容的には、たいした変わりはない。いずれも西欧的近代社会の申し子であるという点では。(ダ、P.37)
ライオンばかりの世界はないし、蚊ばかりの世界はありません。そのときダーウィニズムは「食物連鎖」あるいは「生態系」をもちだします。ライオンがガゼルを食べ過ぎ、ガゼルが減り、ライオンが増えすぎると、ライオンは食物不足になり、減少する、するとガゼルが勢力を伸ばし、・・・。でも、そんなことがクマと人間の間におこっているのでしょうか。
今西の「棲みわけ理論」はこれとは正反対です。種同士は空間的(あるいは時間的)に棲みわけ、いわば共存しているし、種のなかの個体同士も競争しているわけではありません。そして、種社会は生物全体社会とともに、変化しながら同一性を保っています。それを今西は「主体性の進化論」と名付けましたが、その主体性は、近代西欧人がもつ「理性的自我」とは全く別ものです。
戦争が起こるのは「理性(知性)」が足りないからではありません(ホモ・サピエンスは「知性的な人」の意)。教育が高度化し、知性(知識)が増えたらかといって、あるいは「科学」が発展し、物が溢れたからといって、戦争がなくなるわけではないのです。それは歴史を見、あるいは自然を見れば、明らかなことなんじゃないでしょうか。
知識や科学技術が進み、物質的に豊かになれば戦争はなくなるのでしょうか。私にはそうは思えません。お腹が減っていないのに「眼が欲しがっている」、今の欲望(渇望、desire)とはそういう欲望です。そして、眼が欲しがっているあいだは決して満足することはないのです。
その欲望は、「自己統御」あるいは「禁欲主義」でなくなる性格のものではありません。もちろん、より多くの知識を得たからといってなくなるものでもありません。「自覚(気づき)」や「悟り」の問題でもないと思います。どうすればいいのか、私にはわかりません。残念ですが。



