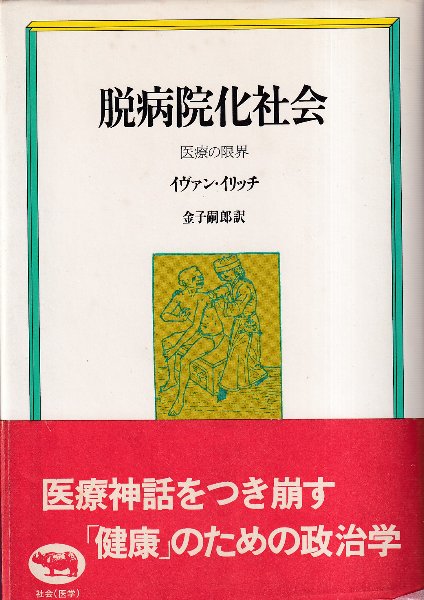「LIMITS TO MEDICINE - MEDICAL NEMESIS: THE EXPROPRIATION OF HEALTH, 1976
NEMESIS ネメシス、天罰、天罰を加える人、強い相手
EXPROPRIATION (土地の)収用
謝辞
イヴァン・イリッチ クエルナバーカ、メキシコ、一九七六年一月
ノート
序
「医療機構そのものが健康に対する主要な脅威になりつつある。専門家が医療をコントロールすることの破壊的影響は、いまや流行病の規模にまでいたっている。医原病(イアトロゲネシス)というのがこの新しい流行病の名であるが、これは医者をあらわすギリシャ語のイアトロス、起原をあらわすゲネシスが結合してできた。」(P.11)
「異常性欲も、それが医学の解釈と介入に値し、かつそれを正当化するときだけ、「合法的」なのである。社会がすべての市民に対して、医療システムからほとんど無制限に診療を受けるようにと関与するとき、自律的な治癒という、生活を営む人々に必要な、環境的・文化的条件はいつでも破壊されるおそれがあるのだ。」(P.14)__フーコー。民間療法->個人に合わせた治療。痛みには人の手(当て)、声がけ。
「健康ケアを病気をつくり出す企てに変化させたものは、人類の生存を有機体の行為から技術的操作の結果に転化した、工学的努力の強度そのものであることをいま理解しなければならない。」(P.15)
「現代の医療が住民全体の健康に対して示す脅威は、交通量と交通強度が稼働性に対して示す脅威、教育と伝達手段が学習に対して示す脅威、都市化が自己の家を建てる能力に対して与える脅威と類似のものである。いずれの場合にも、主要な制度的努力は反生産的に転化する。交通における、時を消費する加速化、騒々しく混乱したコミュニケーション、より多くの人々により高い水準の技術的能力を身につけさせ、全体的には無能力である専門バカをめざして訓練する教育、これらすべては医療による医原病の生産と非常によく似た現象である。いずれの場合も、主要な各分野の制度は、それがつくり出し、技術的な手段を与えた特定の目的から社会の方向をずらしてしまうのである。」(P.16)__血圧130。余命半年、最短は?明日死ぬかもしれない。生命保険、交通保険、医療保険。虫歯。風邪。
「社会関係にはめこまれた医原病は、いまやすべての関係に影響を与える。それは豊かさによる自由の内在化された植民地化の結果なのである。富める国家では医療の植民地化はいやというほどにすすんでおり、貧しい国家も急速にそのあとを追っている。」(P.17)
Ⅰ 臨床的医原病
1 現代医療の疫学
「ほとんどすべての人が、医師の技術なくしては一人の友人さえも生存していなかったろうし、元気でもありえなかったと信じているにしても、実際には疾病の変化と医学の進歩との間には直接の関係は存在しないのだ。」(P.21)
医師の有効性 一つの幻想
「流行病がクリニックでおこなわれる儀式によって決定的に緩和されなかったのは、神の社で通常行われる厄ばらいによって変化を受けなかったのと同様なのである。」(P.22)
「さらに最初の療養所が開設された一九一〇年には、万対一八〇まで低下したが、それでも結核は人間の死因の第二位を占めていた。第二次世界大戦終了後、抗生物質の使用が当たり前になる以前に、すでに死亡原因の第一一位まで落ち、死亡率は万対四八となったのである。コレラ、赤痢、チフスなども同様に、医師のコントロールと無関係に頂点にいたり、ついで勢いを減じてきた。それらの疾病は、その病原が理解され、特定の療法が発見される以前に、その毒性を、ついで社会的影響の多くを失ってしまっていた。」(P.23)
「これらの事実は、一つには微生物の毒性の減退あるいは住宅の改善などによっても説明されようが、最も重要な要因は、栄養が改善されたために宿主(人間)の抵抗力が高まったためと考えられる。」(P.23)
「一世紀以上の間の疾病傾向を分析してわかることは、環境こそが一般的な健康状態を決定する第一義のものであるということである。医学的地理学、疾病史、医学的人間学、そして病気に対する態度の社会史は、社会政治学的公平さの水準および人口を安定させる文化的機構との相関のなかで、健康な成人がいかに感じるか、また一般に成人は何歳で死亡するかを決定するさいに、食料と水と空気が、重要な役割を果たしているということを明らかにしてきた。古い病気の原因が衰退するにつれて、新しい種類の栄養障害が最も急速に拡がる現代の流行病になりつつあるのである。かつては致命的であっただろう低栄養のレベルでも、人口の三分の一は生存するだろうが、一方、より豊かになっていく人々は、食事の中からますます多くの毒物や突然変異をもたらす原因を吸収するようになる。」(P.24)
「この中には避妊法とか、小児にたいする種痘、水処理、排泄物処理などの医学に属さない技術、助産婦の石鹸や鋏の使用、数少ない抗菌性物質、殺虫剤などが含まれる。」(P.24)
役に立たない医学的治療
「性病の増加は新しい社会的慣習によるもので、医学が無効であるというわけではない。マラリアが再び出現したのは、薬剤に抵抗する蚊が生まれてきたためで、新しい抗マラリア剤がないからではない。予防接種は文明国の病気であるポリオをほとんど征服した。ワクチンは百日咳、麻疹の減少に貢献して、「医学の進歩」という一般の信仰に一致するように見える。しかし、他の伝染病の大部分に対しては、医学はそれと比肩できるほどの成果をあげていない。薬物療法は、結核、破傷風、ジフテリア、猩紅熱の死亡率の低下を助けたが、化学療法は、他の病気の死亡率を全般的に下げることについてはそれほどの役割を果たしていないのである。」(P.26)
「しかし、癌の九〇パーセントを占める一般の癌の生存率は、この二五年以上の間不変である。」(P.27)
「乳癌の術後五年の生存率は五〇パーセントであり、それは医学検査の回数と治療法にかかわりのないものである。この率が治療を受けなかった婦人の癌の生存率と異なるという証明はない。」(P.27)
医師によってもたらされた損害
「診断と治療の非人間化は、誤った医療を倫理的問題から技術的問題にかえてしまった。」(P.30)
防禦されない患者
「私はこの制度的な負のフィードバックの、自ら強まっていく輪を、古典ギリシャ語の同義語をとって、「医学的ネメシス」と呼びたい。ギリシャ人は、自然の力の中に神々を見た。彼らにとっては、ネメシスは、神々が自らのために守っている、他人の羨望の的となっている特権を犯した人々を襲う神々の復讐なのである。ネメシスは、人間であるよりは英雄であろうとする、人間の非人間的な試みに対して必ず加えられる罰なのである。多くのギリシャ語の抽象名詞のように、ネメシスは神性の形をとっている。それは傲慢すなわち神の属性を得ようとする人間の厚顔に対する自然の反応なのである。現代における衛生上の傲慢さが、新しい医学的なネメシスの病状を招いたのである。」(P.33)
「医学のネメシスは医学的治療に抵抗するものである。これは素人によるお互いのケアの意志を回復することと、このケアに対する権利を、法的にも政治的にも制度的にも認めることによってのみ逆転しうるのであり、それが医師の独占を制限するのである。」(P.34)
Ⅱ 社会的医原病
2 生活の医療化
医原病の政治的伝達
「近年にいたるまで、医学は自然現象を促進させようと努めてきた。医学は創傷が治癒し、血液が凝固し、細菌が自然免疫によって征服される傾向をすすめてきたのである。」(P.37)
社会的医原性
「個人の健康に対する医学的損害が社会政治的伝達様式によって産み出されるとき、私はそれを「社会的医原病」と呼び、この言葉で、健康ケアの制度的形態にとって、より人目を引き、可能な、かつ必然なものとなった社会経済的変容によるすべての健康に対する損害を指そうと思う。社会的医原病はたくさんの形式の病原の種類を示している。医療の官僚性がストレスを増加させ、不能をもたらす依存性を倍加し、新しい辛い需要を生み、不快と痛みに対する許容性を下げ、個人が苦しむ際に人々が譲歩する余地を低下させ、自己ケアの権利すら放棄させることによって不健康をつくり出すとき、社会的医原病は隆盛になる。健康ケアが基準化された項目・特色とされてしまうとき、すべての苦悩が「入院させられ」、家庭が誕生・病い・死に対して適さぬものになるとき、人々が自己の身体存在を体験する際の言語が官僚的でまわりくどいものになるとき、苦悩、悲しみ、(FF)治癒が患者の役割の外側のものになり、異常性のレッテルをはられるとき、社会的医原病は働きはじめるのである。」(P.38-39)__Nota Bene!!!自分の父母や祖父母を考えたとき、彼らは痛み・苦しみに耐えることを知っていた。それらを感じるすべを知っていたと思う。祖父母は最後までそうだった。家族がいたから。父母もそうだったが、家族がいなくなったとき、痛みを我慢せずに病院に行くようになったような気がする。ネットで他人を攻撃するような人は、やっぱり痛みを感じないだろうと思う。その人は、きっと、痛くなる前に薬を飲むような生活をしてきたし、そういう意味では現在も自分の健康に気を使っているのかもしれない。
医療の独占
「交通手段に取りかこまれて都市が建設されると、人間の足に対する評価は低くなる。学校が学習を占有してしまうと、独学者の価値は低くなる。病院が危機の状態にあるすべての人々を集めてしまうと、社会に新しい死の形式がおしつけられる。独占一般は市場を買いしめるが、根底からの独占は人々が自ら行為し、自らつくる能力を奪ってしまう。商業上の独占は商品の流通を制限する。社会的独占が執拗になるほど非市場的な使用価値は麻痺させられるのである。根底からの(FF)独占はさらに自由と独立を犯すのである。それは環境の形をかえ、人々に自ら戦う力を与えていた環境の諸特徴を「盗む」ことによって、社会的に広範囲な商品使用価値がある代替物を押し付けるのである。集約的教育の結果、独学者は雇用されず、集約農業は自作農夫を破壊し、警察の発展は地域社会の自己制御を蝕んでしまう。医療の悪質な拡大も同様の結果をもたらす。すなわち相互ケア、自己投薬を悪事、重罪であるとしてしまうのである。」(P.43−40)__買うことと使うことの差がなくなる。つくることは忘れられる。商品・社会の均質化。民間療法は「悪・犯罪・詐欺」の代名詞。
価値をはなれた治癒
「人々を法律的に病気であるとする力が、治療用の薬の潜在毒性とともに医師の力のなかに潜んでいるのである。魔術師(メディシンマン)は毒と魅力とを使いこなす。ギリシャ語の「薬」をあらわす唯一の単語 ファルマコン は治癒の力と殺す力とを区別していない。(LF)医学は倫理的事業であり、それゆえ必然的に善をも悪をも満足させるのである。どんな社会においても医学は法律や宗教と同様に正常であるもの、適切であるもの、望ましいものを定義する。医学はある人の訴えに合法的な病気であるというレッテルを貼り、他の人が訴えもしないのに病気であると宣言し、また他の人間の苦痛、不具、そして死さえも社会として認めることを拒否する権威さえもつ(FF)のである。ある訴えが「たんなる主観的なもの」であり、ある障害が仮病であり、ある死が、別の死とはちがって自殺であると決めつけるのは医学である。裁判官は何が法律に適っているか、だれが有罪であるかを決定する。僧侶は何が聖であり、だれがタブーを破ったかを宣言する。医師は何が病状であり誰が病気であるかを決定する。彼は悪を正すべき審問官の力を与えられた道徳上の勧進元のようなものである。医学はすべての十字軍と同様、新しい診断基準をつくるたびに新しいアウトサイダーの群れを生み出す。」(P.41-42)
「医師のみが現在、何が病気をつくるか、誰が病気か、また特別の危機にあると考える病人に彼らが何をすべきかを知っているのである。」(P.42)
「医学と道徳の分離は以下の根拠にもとづき弁護されうる。すなわち医学の範疇は、法律や宗教のそれとは違って、道徳的評価を免除された科学的基礎づけがあるということである。医学の倫理は理論を実践と一致させる特別の部門に生まれてきた。」(P.43)__アスクレーピオス(古希: Ἀσκληπιός, Asklēpios)は、ギリシア神話に登場する名医・医神である。ラテン語ではアエスクラーピウス(Æsculapius / Aesculapius)という。長母音を省略してアスクレピオス、アスクラピウスとも表記される[1]。また、医療の神としての名称でパイエオン(Paeon)がある。
優れた医術の技で死者すら蘇らせ、後に神の座についたとされることから、医神として現在も医学の象徴的存在となっている。ユーロ導入まで発行されていたギリシャの旧10000ドラクマ紙幣に肖像が描かれていた。
「医師の技術的な事業は価値から自由な力を要求する。」(P.43)__科学的対象として「物」=病気・病人、が存在する。それを疑ってはいけない。
「価値から自由な治療とケアという主張は明らかに悪しき無意味であり、無責任な医学を保護してきたタブーは弱体化しはじめている。」(P.43)__「命」の絶対性。
予算の医療化
「一九五〇年から一九七一年の間、健康保険のための公的支出は一〇倍に増え、私的保険の利益は八倍に増え、直接ポケットから支払った額は三倍になっている。」(P.44)
「病院の建設には一ベッドあたり八五〇〇ドルかかるが、その三分の二は機械設備であり、その設備は一〇年以内で旧式になってしまうのだ。この比率は現代の兵器コスト増のほぼ二倍になり、(FF)旧式化するのも同じ比率である。健康、教育、福祉計画におけるコスト増は、ペンタゴンのそれを上まわっている。一九六八年から一九七〇年の間の医療コスト増は、そのサービスに従事する人間の数の増加の三倍である。過去四年間で病院保険の利益はコストでほぼ二倍、医師への報酬は計画されたときの二倍ほど早まっている。」(P.45-46)__ベトナム戦争で使われた同じ型のヘリコプターがいまだに使われている。
「成人男子の特定年齢の死亡率と全世界の医療費はともに急上昇している。」(P.46)
「しかし税金がこのぎりぎりのコストをこえて治療に向けられるときは常に、医療ケア制度は、税金を払う大多数を離れて、金、教育、家柄のゆえに選ばえるか、あるいは実験的な外科医の興味の対象となったために選ばれた少数者へと投資の対象をかえるための働きをすることになる。」(P.50)
「しかし、国営健康サービスを通じて、公衆が誰が治療を「必要とするか」を決める力を医師に与え、実験もしくは治療をされる人に公的援助をおしみなく与えるならば、常に搾取は存在するのである。治療を誰が必要とするかを決めることを医師にだまって独占させておくことは、医師が彼らのサービスを売る基盤を拡げることになるのだ。」(P.50)
「あまりに多額の金は健康を損なう。ある限度をこえると、金を産み出しうるもの、金で買いうるものは自ら選んだ「人生」の範囲を制限してしまう。生産のみならず消費もまた時間、空間、および選択の乏しさを強めるのである。それゆえ医療的産物の威信は健康という栽培物の樹液を吸い、それはある環境にあっては相当程度まで生まれつきの気質に依存している。商品としての医療を生産する際に、人々が余計の時間、労力、犠牲を払えば払うほど、副産物もおおっくなる。その副産物とは、すなわち社会が「健康」を供給するのであり、また掘り出し市場化すべきものとして健康をしまい込んでいるという誤った考え方である。金のマイナスの機能は、買うことのできない商品とサービスとの平価切下げを指示する機能である。福祉が徴発される際に、値札が高ければ高いほど、個人的健康を収奪することの政治的威信は大きくなる。」(P.53)__健康(あるいは治療)のだめに、どれほどの時間と、労力と、金を使っていることか。そしてそれは限度がない。完全な健康とはなんだろうか。それはあるのだろうか。
薬剤の侵略
「医師の診療をうけろという警告は、買う者をして自分には警戒する能力がないと信じさせてしまう。」(P.55)__わたしは素直だから、「血圧を下げないとすぐにでも死ぬよ」という医者の脅し(冗談?)に負けて、薬を飲んでしまう。
「アメリカ合衆国ではチフスは稀であるから、四〇〇例中一例だけがこの薬による治療を「必要としていた」にすぎない。奇形をおこすサリドマイドと異なって、クロラムフェニコールは殺人をおかす。」(P.55)
「一九七三年チリのクーデター勃発後一週間以内で、薬剤の輸入と乱費よりはむしろ地域活動にこそチリの医療の基礎をおくことを主張した人々の多くが殺害されたことは注目すべきであろう。」(P.57)
「それは消費者自身がほとんど選択できない生産物である。生産者の販売努力は、「媒介的消費者」すなわち処方はするが自分では薬価を支払わない医師に向けられる。」(P.58)
「しかし驚くべきことは、全世界の一人当たりの処方された薬剤の使用量は、商業的な販売促進とほとんど関係がないのである。それは主として医師の数と相関がある。それは医師の教育が製薬産業の広告を受けず、会社の薬の販売のための宣伝が制限されている社会主義国家でも同様である。工業社会における総体的な消費量は、処方により店頭もしくは非合法的に売られる品目の比率には基本的には影響をうけず、またその代金が自分のポケットから払われるか、前払い保険によるか、あるいは福祉基金によるかということも影響がないのである。すべての国において、医師は二種類の嗜(FF)癖者を治療している。その一群は医師の処方による嗜癖者、もう一群はその結果に悩むものである。社会が豊かになるほど、この二つの群に属する人々のパーセントは上昇する。」(P.58-59)
「新しい薬の時代は一八九九年、アスピリンとともにはじまった。」(P.59)
「薬の侵略が、自己もしくは他人による侵略による投薬へと人々をみちびき、そのために自らケアができるはずの身体をうまく取扱う能力を失ってしまうのだ。」(P.61)
診断の帝国主義
「大多数の人々が異常者であると証明されるような社会では、このような異常な多数者の住む環境は病室に似てくる。病院の中で人生をすごすことは健康にはよくないことである。(LF)かつての社会組織では、医学が難産、新生児、閉経期、その他の「危機の年代」においてだけ人々を患者として扱い、人々は自律性の幾分かを治療者にゆずりわたしていた。人生の諸々の時期の儀式化は決して新しいものではない。新しいのはその過度の医療化なのである。」(P.62)
「一生つづく医学的監視は別のものである。それは人生を危機の時期(FF)の連続にしてしまい、常に特別の保護を要求する。」(P.62-63)
「富者にとっても貧者にとっても、人生は検査と診療を通じて出発点までもどる巡礼になってしまった。人生はこうして、善きにせよ悪しきにせよ、制度的に計画され、形づくられなければならない統計的な現象、「生存期間」におとしめられてしまったのである。」(P.63)
「人生の各段階で、人々はそれぞれの年齢に特異的な障害者ということになる。老人が最もわかりやすい例である。すなわち、彼らは治療すべくもない状態に対して割り当てられた治療の犠牲者である。(LF)人間の苦悩の大部分は急性で良性の病気から成り立っており、これらは自らなおるか、ほんの二,三ダースのきまりきった医療の介入でよくなるものである。広範囲の病的状態においては、治療を受けることの最も少なかったものが最も回復しやすいのである。」(P.63)
「ある特異的病状の治療については現代医学が非常に有効であるという事実は、それだから医学は患者の健康にとって有効になったということを意味してはいない。」(P.64)
「老人ケアに対する要求は大きいが、それは生存する老人が多いという理由からよりは、老年は治療されるべきだと主張する老人がふえたからである。(LF)寿命の最高は変わっていない。ただ平均寿命が変わったのである。」(P.65)
「より多くの老人が専門家のケアをうける権利を獲得するにつれて、自ら独立して老いる機会が失われていくのである。より多くの人々が施設にのがれようとする。」(P.66)
「しかし老人に対するコスト高のケアの急増の制限を弁護することは容認されやすいとしても、子供に対するおわゆる医学的投資について制限しようとするのはいまだタブーのようである。工業化社会の親たちは、一六年の形式的教育によってつぶされ型にはめられないならば誰も適応できぬ社会のために、人的資源をおくり出すように強いられ、自分で子供をケアする自信がなく、絶望して子供に薬を浴びせかけることになる。」(P.67)
予防の烙印
「疾病ケアとともに(FF)健康ケアが商品になった。ということは自らなすものでなく購入するものとなったのだ。」(P.70-71)
「病気でもないのに、人々は病人にされてしまう。予防の医療化はかくて社会的医原病の主要な病状になるのである。それは将来に対する個人の責任を、代理者による管理に変える傾向をもつ。」(P.71)
「獣医が牛のディステンバーを診断しても、それか患牛の行動にまで普通は影響を与えない。医師が人間を診断すると、患者の行動に影響を与えてしまう。」(P.71)
「誰も、元アレルギー、元虫垂炎の患者に興味をもったりしないし、元交通違反者として記憶にとどめられることはない。しかし別の場合には、医師はま(FF)ず第一に保険統計士として行動し、彼の診断は患者と時にはその子供の評判まで終生おとしめることもあるのである。個人の同一性を非可逆的におとしめ、それに永遠の烙印をおしてしまう。」(P.71-72)
「理論的には、医師は初診で彼の患者がある病気にかかっていると考えなくても、フェイル・セイフの原(FF)則によって、医師は病気を見のがすより、患者にある病気があるとした方がよいかのように振舞うのである。医学的決定の規則が医師をかりたて、健康よりは病気を診断することで安全さを追求させることになる。」(P.73-74)
(P.75)__「妊娠している可能性がある人は申し出てください」=>妊婦(胎児)に影響があるのなら、卵子にも影響があるのではないか。
「大きな集団に早期診断のための検査を日常的に行うことで、医学者は研究目的に最も適切かつ最も有用な患者を選択する基盤が広くなる。その際その治療が患者を治癒 社会復帰させようがさせまいが、また患者の苦痛を和らげようがそれを増そうが、かまうところではないのである。こうした過程の中で、人々は自分たちは機械であって、しばしば修理工場にいかないと長もちがしないという信仰を強めさせられ、医療組織体のための市場調査と販売活動との費用を払うことを余儀なくされるのみならず、圧力まで受けるのである。(LF)診断は常にストレスを強め、不能力を定義づけ、不活動を課し、不治・不確実と未来における医学の発見に関心を集めさせる。そしてこれらのすべてが自律性を喪失させることになる。」(P.76)
「最後には、このように内部指向型の社会の主要な活動は、商品としての余命という幻の生産に向けられていく。統計的人間を生物学的に唯一である人間と等置することで、有限の手段に対しての癒やしがたい要求が生み出される。個人は全体のより大きな「ニーズ」に従属させられ、予防処置は強制的になり、社会はより金のかかる治療処置という重荷に耐えられないのだから、患者はこの診断に服する(FF)べきだと医師が論じるとき、患者が治療に対して同意を留保する権利は消えてしまうのだ。」(P.76-77)
終末の儀式
「銀行、国家、寝台の危機の管理者のように、彼は破滅的な作戦を立て、無駄で無用、かつ奇怪にすらみえる手段を動員するのである。最後の瞬間に彼は、患者ひとりひとりの絶対的な優先権という要求に約束を与えるのであるが、大多数の人々は自分自身それを要求できるほど重要なものと考えられていないのである。」(P.77)
「死者をコントロールする役目を与えられた者は普通人であることをやめてしまう。トリエイジの監督官によって、殺人は政策的に隠蔽されてしまう。」(P.78)
「終末ケアの医療化はただ単に不吉な夢を儀式化し、みだらな努力に対する専門的免許を拡大するだけではない。臨終の治療がエスカレートすることで、医師は彼が用いる手段の技術的有効性を証明する気持ちがなくなってくるのである。より多くを要求する彼の力に再現はない。」(P.78)__「最善を尽くしましたが・・・」。死の確認の儀式。公認の死。
「市民の最後の日々にかかるコストは一二〇〇パーセント増であり、健康ケア全体のコストの増加より急速である。」(P.78)
「そして医療によるコントロールの下に、葬儀、遺品の埋葬などと分離されてしまって(FF)いる。医療の助力なしに死んでいく者の恐怖を反映し、墓地から病棟へと過剰な出費が切りかえられ、被保険者は自分自身の葬儀に参加するために支払うのである。(LF)医療をうけない死に対する恐怖は、一八世紀におけるエリートによってはじめて感じられた。彼らは宗教の助力を拒否し、死後の生が存在するという信仰をしりぞけたのである。この恐怖の新しい波はいまや富者をも貧者をもまきこみ、平等主義のパトスと結合して、新しい商品をつくり出した。」(P.78-79)
「自分ひとりで死にたくないという患者の気持ちが、彼を悲劇的にまで依存(FF)的なものにしてしまったのである。患者は自分に自ら死ぬ能力(それは健康の最後のあらわれであるが)があるという信念を失ってしまい、専門家によって殺される権利を重要問題としたのである。」(P.79-80)__点滴の針を抜く力、それがないことは健康ではない、死ぬ能力がないことを意味するか。点滴で生きることが問題ではないか。
黒魔術
「プラシーボ(ラテン語で「よろこばせてあげる」という意味であるが)は単に患者のみならず、投薬した医師をもよろこばすのである。」(P.83)
「アメリカ合衆国における扁桃腺切除の九〇パーセント以上は不必要であった。」(P.86)__扁桃腺、虫垂など「不要(余計なもの)」だと思われることは、「社会に役立たない人」も「不要」だと思われる社会。それらは「必要」なんじゃなくて、「必要」という考え方が「普遍的」なものではないこと、「必要・不要」だと思う「主体」も「必要・不要」ではなくて、「ただある」ということに気がつくこと。主体の存在の「偶然性」。
「社会的医原病はマイナスのプラシーボ、すなわちノシーボ効果としてかなりな程度まで説明可能である。」(P.88)
「ノシーボ効果はプラシーボ効果と同様に医師の行為とはほぼ無関係なのである。」(P.88)
「奇蹟の医療化はさらに臨終ケアの社会的機能に対しても洞察を与えてくれく。患者は皮紐でくくられ、宇宙飛行士のように制御され、テレビにうつし出される。これらの英雄的な処置は何百万人もの人々にとって雨乞いの踊りとなり、自律的生活に対する現実的希望は、医師が外の空間から健康を配達してくれるだろうという妄想に変質してしまっているのである。」(P.89)
患者の多数
「なぜ新生児が、死に行く者が、民族優越思想の持ち主が、性的不適応者が、神経症者が、他の興味の対象とならない、時間の空費である診断の情熱の犠牲者とともに医学の辺境の外におしやられ、非医学的な治療の調達吏すなわちソーシャル・ワーカー、テレビのプログラマー、心理学者、役人、セックス・カウンセラーの患者に変えられてしまうのか。医学の権威を反映しているこの権限を与える仕事は、病人の役割に対してまったく新しい環境をつくり出したのである。(LF)どんな社会でも安定しようとすれば証明書つきの異常を必要とする。奇妙な様子をしたり行動のおかしい者は、彼ら共通の特徴が公式的に命名され、彼らの人を驚かす行動が一般に認められる整理棚に整理されるまでは破壊的なものである。名前、役割を与えられることによって、不気味で人を驚かす変わり者は馴らされるし、あまやかし、除け者にされ、抑圧され、追放されうる予言可能な例外者になってしまう。大部分の社会では、普通でない者に役割を与える人々がいる。」(P.90)
「しかし全体的にいえば、病者の役割は近年まで伝統的な性格のものであった。ところが前世紀において、フーコーのいう新しい臨床的ヴィジョンは釣合いを変えてしまった。医師は次第に人間研究家としての役割をすて、啓蒙化された科学の企業家の役割をもつようになった。病人を病気の責任から免除させることが重要な任務になり、病気についての新しい科学的範疇がこの目的のためにつくり出されてきた。(P.92)__フーコー『臨床医学の誕生』
「健康であると証明されるまでは市民は病気であるとみなされる。」(P.93)__そして多様化する病気のために、健康な人はどんどん減少する。
「病気でない人々は将来の健康のために専門的ケアに依存するようになった。その結果として、普遍的医療かと、普遍的病的状態を証明する病的社会が生まれるのである。(LF)病的社会においては、定義され診断された不健康の方が他のいかなるレッテル、あるいはレッテルなしよりも遥かに望ましいという信仰が有力である。それは犯罪的あるいは政治的以上よりもましであるし、怠惰よりましであるし、自分の意志で仕事をさぼるよりもよいのである。人々は意識下で、自分たちは病気であり仕事にも受身のレジャーにもあきあきだということをますます知るようになっており、身体的病気は社会的、政治的責任を免除してくれるという虚言をききたがるのである。」(P.94)__病気自慢。
「工業化社会の医療化はその帝国主義的性格を究極的に成就させようとしているのである。」(P.95)
Ⅲ 文化的医原病
小序
「まず第一に臨床的医原病であるが、これは有機体の闘う能力が他律的な管理におきかえられる結果である。第二は社会的医原病であるが、そこにあっては、環境は個人、家族、隣人に、自らの内部の状態と状況に対する制御力を与えていた条件を奪われてしまうのである。文化的医原病は医療による健康否定の第三の次元となる。それは医療企業が、人間が現実に耐え忍ぶ意志を吸い取るときにはじまる。」(P.99)
「その際、それは個人が現実に直面し、自己の価値を表現し、避けがたくしかもしばしば癒やしえない痛み、損傷、老衰、死を受け入れる能力を駄目にしてしまうのである。(FF)(LF)健康であるということは、単に現実との闘いに成功することだけでなく、その成功を享受することをも意味しているのだ。それは喜びと苦しみの中にあって生命を感じられることを意味している。」(P.99-100)__Nota Bene !!
「どんな文化でも健康についての独特なゲシタルト(形態)と痛み、病気、損傷、死に対しての独特かつ適切な態度を形成する。そして痛み、病気、損傷、死のそれぞれは、伝統的に受苦の技術と呼ばれる人間の一群の行為を示すものなのである。」(P.100)__「技術」=Art か?人工物という近代的なイメージではなく、文化内での人間行為、規範等を意味するイリイチ独特の表現か。
「すべての伝統的文化は、各個人が痛みに耐えられるようにし、病気、怪我を理解できるものとし、死の影を意味あるものにする手段を与える能力から、その衛生的機能を引き出す。そのような文化の中では健康ケアは常に食べ、飲み、働き、呼吸し、愛し、政治をし、運動をし、歌い、夢をみ、戦い、受苦するための計画なのである。癒やすということの大部分は、人々が癒える間じゅう彼らを慰め、配慮と安楽を与える伝統的な方法であり、病人のケアの大部分は、苦しんでいる人に及ぼされた寛容の一形式である。一群の遺伝的素質、その歴史、その状況、そして競合する隣人たちのグループが代表する特有の挑戦に対して適合している、成長しうる法則を与える文化のみが生き残るのである。(LF)現代の無国籍な医療企業により鼓吹されているイデオロギーは、このような機能にさからうものである。」(P.101)__Nota Bene !!
「医療的文化は痛みをこらえ、病気を除去し、苦しみ、死んでいく技術に対する需要をなくすために設計され、組織された。」(P.102)
3 痛みの抹殺
「無数の異なった道徳が剛毅さとは伝統的に痛みの感覚を挑戦であると認識し、それによって個人の体験を形成することを人々に可能ならしめたのであった。」(P.104)
「伝統的社会は、身体的・精神的苦痛に打ちひしがれても、人間が自分自身の行為に責任をもつことを教えたのである。痛みとは、つねに自分自身を見出し、それに対する自分の意識的反応によってたえず形づくられる自己の身体についての主観的現実の欠くべからざる一部だと考えられていた。」(P.104)
「現代では、すべての痛みは人間がつくり出すものとなり、産業発展の戦略の二次的効果となってきて(FF)いる。痛みは、すでに「自然な」「形而上的」悪ではなくなってしまった。それは社会的な呪いである。「大衆」が痛みに打ちひしがれているときに、大衆に社会を呪うのをやめさせるために、産業システムがすぐ反応し、大衆に医学的な痛みどめを与えてしまうのである。このようにして痛みは、より多くの薬、病院、医療サービス、他の非個人的な団体によるケアへの要求に変化してしまい、さらに、人間的、社会的、経済的にどれだけのものを失おうとも、さらに団結した成長を政治的に支持することになってしまったのである。痛みは、麻酔消費者の側の、人工的につくられた無感覚、うわの空、無意識に対して雪だるま式に大きくなる要求をよびおこす政治問題になってしまっている。」(P.104-105)
「二〇世紀の苦の園においては、痛みは異常な介入によって処理されるべき緊急の偶発事件として扱われるのである。(LF)脳によって受け取られた痛みの情報から生じる痛みの経験は、その性質と量において、遺伝的所与およびその刺激の性質と強度のほかに、少なくとも四つの要素、すなわち文化、不安、注意、解釈に左右される。これらのすべては、社会的決定要因、イデオロギー、経済構造、社会の性格によって形づくられるのである。子供が生まれたとき、母か、父か、それとも両方ともに苦しむべきかは文化が決める。状況、習慣が苦悩する人の不安のレベルと、自らの身体感覚への注意を決定するのである。訓練と確信が身体的感覚に与えられた意味を決定し、痛みが経験される程度に影響を与える。」(P.105)__出産の痛み
「性のクライマックス近くで受けた傷は、英雄的行為による傷と同様しばしば感じられないのである。」(P.106)
「文化が医療化されるにつれて、痛みの社会的因子は歪められてしまう。文化が痛みを、本質的で身近な、伝達しえない「負の価値」と認識するのに対して、医療的文化は痛みを、証明でき、測定でき、制御できる体系的な反応としてまず注目する。第三者によってある距離をとって認識されたこのような痛みだけが、ある特定の治療を要求する診断をつくりあげるのである。」(P.106)
「痛みの中にある人は、しばしば自分を圧倒しようとするこの経験に意味を与えてくれる社会的文脈がますます希薄になった状態に放っておかれるのである。」(P.106)
「ちょ(FF)うど「私の痛み」が、独特のあり方でただ私にだけ属するものであるように、私は私の痛みとともにまったく孤独なのである。私はそれを他人に与えることはできない。私は痛みの体験の実存性に何らの疑問を持たない。私は他人は「彼らの」痛みを持つだろうと推定する。もっとも彼らが痛みについて語っても、彼らが何をいっているか知覚しうるわけではないのであるが、私は彼らの痛みの存在を確信している。私が彼らに対する私の同情を確信しているという意味においてのみであるが。しかし、私の同情が深ければ深いだけ、自らの体験に関して相手の完全な孤独さについての私の確信もますます深まるのである。痛みの中にある他人のサインを私は認識する。たとえその体験が、私の助力とか真の了解の範囲を超えたものであるとしてもである。極度の孤独を意識することは、身体的痛みに対して感じる同情の特異性であり、この特異性は痛みの体験を他の体験を他の経験 苦悶の中にある人々、悲しむ人々、虐げられた人々、不具の人々への同情と別のものにする。極端なあり方であるが、身体的痛みの感覚は、原因と他の苦悩の中に見出される体験との間の距離が欠けているのである。(LF)身体的痛みを他人に伝達することは不可能であるにもかかわらず、他人の身体的痛みを知覚することは基本的に人間的なことであるから、これを括弧の中にくくってしまうわけにはいかない。患者は医師が自分の痛みに気づかぬ存在だとはとうてい考えられないし、それはちょうど拷問台の人が虐待者について同様に考えられぬのと同じである。われわれが痛みの感覚を共有するという確実性は特別なものであって、われわれが人間性を共有するという確実性より以上のものである。」(P.108-109)
「犬は傷つけられることがあっても痛みに悩むことはないのだから。」(P.110)
「身体的痛みは、内在的で、身近にあり、伝達不可能な負の価値として体験されるのであるが、それはわれわれの意識の中に、悩む人間が存在する社会的状況を包含しているというのが私のテーゼである。社会の性格が、ある程度まで悩む人間のパーソナリティを形成し、かくて、彼らが自分の身体的苦痛や傷を具体的な痛みとして体験する方法を決定する。この意味において、社会の医療化にともなった痛みの体験の方向を研究することは可能であろう。痛みを悩むということはつねに歴史的次元のことなのである。」(P.110)
「痛みを客観化する能力の進歩は、医師に対する過度に激しい教育の結果の一つなのである。」(P.111)
「ロボトミーを受けた患者は、痛みを強制的にとりあげられた極端な例である。彼らは「家庭内の病人、あるいは家族のペットのレベルで適応している」。ロボトミーを受けた患者も痛みは感じるが、それを悩む能力がない。痛みの体験は、臨床名をもった不快感にまでおし下げられているのである。(LF)十分な意味で、痛みの体験が苦悩を形成するためには、それが文化の構造にあてはまらなければならない。個人が身体的痛みを個人の体験に変容させることを可能にさせるためには、すべての文化は、少なくとも四つの関連ある下位のプログラム、すなわち言葉、薬、神話、モデルを備えなければならない。」(P.112)
「人間は痛みに耐える能力のみならず、それを御する能力とともに進化してきたのである。石器時代の中期にけしは栽培され、それはおそらく穀物の栽培に先立つものであった。マッサージ、鍼灸は歴史の黎明期から知られていた。痛みに対する宗教的、神話的な論理的根拠はすべての文化においてみられるのである。」(P.112)
「医療化はすべての文化から痛みを取扱うためのプログラムの統一性を奪っているのだ。」(P.113)
「現代医学の従事者は異なった位置におかれている。すなわち、彼の第一の方向づけは治療であって治癒ではない。」(P.114)
「新約聖書の中では、痛みは罪と密接にからんでいると考えられる。古代ギリシャ人にとって痛みは快楽をともなうはずであったが、キリスト教徒にとっては、痛みは楽しみに身をゆだねた結果だったのである。いかなる文化も伝統も、現実の忍従を独占するものではない。(LF)ヨーロッパ文化における痛みの歴史は、さかのぼればこれらの古典、セム族の根源までいたり、そこには痛みを個人が耐えることを支持するイデオロギーを発見することもできる。」(P.115)
「個人の問題として理解され、耐えるべきものとしての痛みに反対するキャンペーンは、デカルトが肉体と魂とを分離したときはじめて。彼は身体のイメージを幾何学、機械、時計製造、技術者によって修理できる機械にかたどった。身体は魂によって所有され、支配される装置になってしまったが、身体と魂の距離はほとんど無限になったのである。」(P.117)
「文明における進歩は、苦痛の総体を減少させることと同意語になってしまった。そのときから、政治とは幸福を最大限にするというよりは、痛みを最小とする活動であると考えられるようになった。その結果、痛みは本質的に(FF)医療団体の道具箱が無力な犠牲者に有利に用いられないという理由で、彼らに加えられる受身の出来事であるとする見方が出てきたのである。(LF)このような文脈においては、痛みに直面するよりは痛みから逃れる方が合理的に思われる。たとえ激しくいきいきとした状態を放棄する犠牲を払ってでも、である。」(P.118-119)
「痛みに対する感受性が次第に低くなれば、人生の素朴な喜び、楽しみを経験する能力も衰えるものである。麻酔された社会では、人々に生きているという感覚を与えるためには次第に強い刺激が必要となってくる。薬物、暴力、恐怖が、自我の経験を引き出す次第に有力となりつつある刺激なのである。」(P.119)
「病苦は責任のある活動であるという暗示は、快楽と工業生産物への依存とが合致している消費者にとっては、ほとんど耐えがたいことである。すべての人々が避け難い痛みに対して反応せざるをえないが、これを「マゾヒズム」と同義であるとすることで、人々は自分たちの受動的な生活様式を合理化してしまう。」(P.119)
「伝統的文化が進化させてきた忍耐心の対象であった病苦は、ときに耐えられなぬほどの苦悩、苦しみを求める祈り、狂気の冒瀆などを生み出すが、これらは自己規制的なのである。威厳のある受苦に代わる新しい経験は、人工的にひきのばされた、不透明な、非個人化された保持である。痛みを殺すことで、人々は、自分自身の次第に枯れ衰えていく自我の無感情な観客にしてしまっているのである。」(P.121)
4 疾病の創造と除去
「病院がその住人の健康を改善する治療を施すための道具であると考えるものは誰一人いなかったのである。」(P.124)
「社会を健康的に工学化しようとする計画は、文明の害悪を除去しようとする社会改造への要求とともにはじまる。」(P.124)
「もし「病気」と「健康」とが公共の財源を要求するとなれば、これらの概念は操作的とならねばならない。病気は人間を悩ます客観的な疾病にならなければならず、実験室にうつされ、培養され、病棟、記録、予算、博物館に適合するものにされなければならない。こうして病気は行政的管理に適応された。エリートの一部が支配階級からその制御と排除における自律性を委任されたのである。医学的治療の対象は、隠れてはいるが新しい政治的イデオロギーによって定義され、医師からも患者からもまったく独立して存在する実在物の地位を獲得したのである。」(P.125)
医学における新しい目的にかなう論理構造はすでに述べられている。すなわち(a)測定による操作的な立証、(b)臨床的な研究と実験、(c)工学的基準にもとづく評価、にしたがうべきものなのである。」(P.225)
「物理的測定法の使用が、病気が真に存在するという信仰、病気は医師と患者の知覚から存在の自律性を持つという信仰を準備した。統計の使用はこの信念を補強した。」(P.126)
「今日では、隔離病棟は区画化された修理店になっている。」(P.128)
「病気と同様に、健康が臨床的位置をもちはじめ、臨床的病状の欠如ということになった。正常というものの離床的基準は健康であることと結合したのである。」(P.128)
「事実、彼らは興隆しつつあったブルジョアジーの言語をおしつけ、それはまた生産手段に対する管理力をも及ぼしていたのであった。新しい資本家という生産者階級の言語は、すべての階級に対しての規範となった。」(P.129)
「ラテン語の「ノルマ」は定規、大工の定規を意味する。一八三〇年代にいたるまで、英語の「正常(ノーマル)」とは地上に直角に立つということであった。」(P.129)
「基準からの異常としての病気が、治療の方向づけを与えることで医療の介入を正当化するだけで十分だった。」(P.130)
「社会がひとつのクリニックになり、すべての市民は病人となり、いつも血圧を測定され、正常範囲「以内」に血圧を安定させられる患者なのである。」(P.130)
「すべての病気は社会的に創造された現実である。」(P.130)
「高度工業社会は、疾患の存在の認識論的正当さを保持つづけるためにひじょうに危険な賭けをしている。病気が人間を把えてしまう何ものかであり、人々が「つかまえたり」「手に入れる」何ものかであるかぎりは、こうした自然の過程の犠牲者は、自らの状態に対して責任を取る必要はない。彼らの主観的現実に耐える際の、他愛ない、劣った、無能な行動のために非難されるよりは、むしろ同情をかうのである。もし彼らが、自分たちの病気を「物事のあり方」の表現として素朴にうけ入れるならば、彼らは御しやすく、有益なものに変えられるのであり、高度に集中した工業のストレスを増加させることに協力したという政治責任から免れるのである。高度工業社会は、人々が自分のおかれた状況と闘う力をうばうがゆえに、病気をつくり出すのである。そして人々が倒れるとき、その社会は破壊された関係の代わりに「臨床的」補綴を行うのである。」(P.132)
「彼は医師が闘う無縁の実在について教えてもらうけれども、それは医師が医療的介入と環境の工学化において患者の協力をうるのに必要であると考える範囲内においてである。言語は医師によって引きつがれ、病者は自分の苦悩をあらわすための意味のある言葉をうばわれ、さらに言語的ごまかしによって苦悩は増大するのである。」(P.134)
「要するに社会的に認容される言葉が次第にエリート専門家の特別の言語に依存する度合いが増すにつれて、病気は階級支配の道具になってしまった。大学教育を受けた者、官僚は医師が配分する治療における共働者となり、他方、労働者は主人の言語を話さぬ臣下としての位置を与えられているのである。」(P.134)
5 死対死
商品としての死
死者の敬虔な舞踏
「死は生命の新生の機会であった。死者とともにその墓の上で踊るという(FF)ことは、生きているという喜びの確認の機会であり、多くのエロティックな歌と詩の源泉でもあった。」(P.137-138)
「自分自身の身体の形をとることで、各人は自分の死を持ちはこび、一生の間、それとダンスを踊る。」(P.138)
「そして、後になって「自然の私」とも呼ばれるイメージが出現することになる。死の舞踏は、この準備を表しているのである。死はいまや人生の避けることのできない本質的な部分となり、異質的因子による決定ではなくなった。死は自律的なものとなり、三世紀の間、不死の魂、神の意志、天使、悪魔とは別個のものとして、しかも共存したのであった。」(P.139)
死の舞踏
「死は、一生の間対面すべきものであったのが、一瞬の出来事に化したのであった。」(P.140)
「連続する時間が優位になるにつれて、その精確な測定といくつかの事件の同時性の認識に対する関心もたかまり、個人の同一性の認識のための新しい構造が工夫されたのである。個人の同一性は、個人の一生の完全さの中にではなく、事件の連続と関連してもとめられるようになった。死は一つの全体の終わりではなくなり、連続の途絶となったのである。」(P.140)__Nota Bene !! 一コマ・断面としての、静止した同一性の連続。映画フィルムのように。
「開いた墓地が天国や地獄の門よりも広く開かれて浮かび上がり、死との対面は不死よりも、王、僧侶、神自身よりも、確実なものとなったのである。人生の目的というよりは、人生の終わりになってしまったのである。(LF)個人の死の究極性、内在性、親近性は、ただ単に新しい時間間隔の部分ではなく、新しい個人性の出現でさえあった。」(P.141)__日本においても、自分が死ぬことがいつでも恐怖だったわけではない。切腹は怖いものではない。戦死も名誉だったかもしれない。
(1491年?『アルス・ミリエンディ』「自らをよく知りかつ死ぬ技術と技工」)「それは、現代的意味での「ハウ・ツー」ものであり、死ぬという事業に対する完全な案内であり、健康な時期に身につけておかねばならぬし、その逃れられない時にはいつも自由にあやつることができなければならない方法なのであった。」(P.142)
「ルネサンス初期のヒューマニストたちは、死者を幽霊とか、悪鬼とか、魂とか、聖者とか、象徴としてではなく、永続する個人的歴史的存在として記憶したのである。」(P.142)
「一七世紀の幽霊・霊に対するグロテスクな関心は、神の審判ではなく死の呼び声に直面した文化の巨大化しつつある不安を強調している。」(P.143)
「宗教改革以後、ヨーロッパの死は、気味悪い(マカブル)ものになり、その状態が続いたのである。」(P.143)
「ある人はやがて自分をのみこむ大地の上へベッドからおろしてほしいと望んでいるとされ、祈祷がはじまるのであった。しかし傍の人々は、死が入って来やすくするために戸は開いておくこと、また死を恐れをもって追いはらうことのないように、音を立てないこと、また、この最も個人的な事件において、死にい(FF)く者をひとりにしておくために、最後にはうやうやしく自分たちの視線を彼からそらすべきことを知っていた。」(P.143-144)
「超越を除外することもなしに、死は自然現象になったのであり、なにか凶々しい要因の責任にする必要もな(FF)くなったのである。(LF)新しい死のイメージが人体を対象物にまでおとしめるのに役立った。これまで、死体は他の物体とはまったく異なる何物かであると考えられてきた。死体も人間と同様の取扱いを受けていたのであった。法律が死体の立場をみとめていた。すなわち、死者も訴えたり、生者によって訴えられたりすることも可能であり、死者に対する刑事訴訟も一般に行われていた。」(P.144-145)
「自然死の出現というものは、死体がその法律的立場の多くの部分を失うのに必要なことであった。」(P.145)
「しかし知識も技術も病気を真に癒す能力の進歩とは、あまりにも歩調がちがいすぎる。医学的儀式は、不気味(マカブル)になってしまった死によって生み出された不安と恐怖に方向を与え、抑えしずめるのに役立ったのである。」(P.146)
ブルジョアの死
「まさに死の平等がこの世の特権を小さなものにしてしまうという理由で、それはまたこの世の特権を合理的なものとしてしまう。しかし、ブルジョア家族の興隆とともに、死における平等は終わり、余裕のあるものは死を遠ざけるために金を払いはじめたのである。(LF)フランシス・ベーコンこそ、人命をのばすことが医師の新しい仕事であると言った最初の人である。彼は医学の職務を三つに分けた。「第一は健康の維持、第二は疾病の治癒、第三は生命の延長」であるとし、とくに第三の職務、生命の延長は新しい役割であり、欠陥はあるが、三つのうち最も高貴な仕事であるとして激賞した。」(P.147)
「歳をとることは、資本主義化された生を生きる一つの方法となった。それがカウンターのものであろうと学校におけるものであろうと、市場において利益をもたらすことになった。中産階級の若者は、才能があろうとなかろうと、はじめて通学するようになり、そのため老人が仕事にとどまることもできるようになった。引退することをまぬがれることで「社会的な死」を除去する余裕のできたブルジョアは、若者たちを管理の下におくために、「子供時代」というものをつくり出したのである。(LF)老人の経済的地位にともない、彼らの身体的機能の価値が増田。一六世紀においては、「若い妻は老人にとって死」であったけれど、一七世紀には、「若い娘とたわむれる老人は死とダンスを楽しんでいる」とされた。ルイ一四世の宮廷では年老いた好色家は笑いぐさであった。ウィーン会議の頃までには、彼はせん望の的になった。孫の恋人にいいよっている間に死ぬことは、のぞましい目標ともなったのである。(LF)老人の社会的価値に関する新しい神話が展開された。未開の狩人たち、収集家たち、遊牧民は、普通老人を殺したものだった。そして農民たちは老人を裏部屋にとじこめたのであるが、いまや家長は文字どおり理想とされたのである。」(P.149)
「長く生き残る能力、死以前に引退することを拒否すること、不治の状態においても医療の助けを求めること、この三つが協力して新しい病気の概念をつくり上げた。すなわち、老年がのぞむ新しい型の健康の概念である。」(P.150)
「対象的に、貧者の病気については逆の判断がなされた。彼らの死因となった病気は治療の不可能な病気と定義された。これらの病気に対して医師が施しうる治療が、病気の進行に何らかの影響を与え(FF)うるかどうかは、まったく問題ではなかった。こうした治療があまり行われていないということは、彼らが「自然の死ではない死」の宣告をうけているということを意味しており、それは貧者を無教育で非生産的であるとするブルジョアのイメージに適合している。その時以来、「自然の」死を死ぬ能力はある一つの階級のために予約されたのであるが、その階級とは、患者として死ぬ余裕のある人々である。」(P.150-151)
臨床的死
「死は神のお呼びであったのだが、「自然」の事件となり、さらに「自然の力」へと変わったことがわかる。さらに変わって、現在では死は、もし健康な老人に訪れない場合は、「時宜に適していない」とされるのである。いまや、死は医師によって証明されたある特定の病気の結果となったのである。」(P.152)
「「時宜をえた」死がブルジョアジーの階級意識の形成とともに生じたが、「臨床的な」死は、新しい、科学的訓練をうけた医師の職業意識の形成から生まれてきたのである。こうして、臨床症状をもった、時宜をえた死は、中産階級の医師の理想となり、それはやがて労働組合の社会的目標に取り入れられることになる。」(P.153)
労働組合の自然死への要求
「哲学的概念についての評判が高い辞書は、「自然死はそれに先行する病気もなく、明確な特異的原因なしにおこるのである」と述べている。社会の進歩という概念とからみ合うのはこの不気味で幻覚をおこす死の概念である。臨床的な死における平等という法律的に妥当な要求は、労働者階級の中にブルジョア個人主義の矛盾を拡大した。」(P.154)
「まず第一に、この新しい死のイメージは、新しいレベルの社会的コントロールを保証した。社会は(FF)各個人の死を防ぐ責任をもつにいたった。すなわち有効であろうがなかろうが、治療は義務となった。」(P.154-155)
「死に対するわれわれの新しいイメージはまた工業的エトスにぴったり符合する。今世紀の変わり目におけるように、すべての人々は生徒であるとされ、根源的な愚かさの中に生まれ、生産的生活を送る以前に八年の学校教育を必要とする立場に立っていたのであるが、今日、人々は生まれつき病人であるという印をつけられ、正しく生きようとすれば、すべての種類の治療を必要としている。ちょうど義務教育による消費が、労働における識別の手段として役立つように、医療における消費は、不健康な労働、汚れた都市、神経をまいらせてしまう交通を和らげるための手段として用いられるにいたっている。医師が生命を救う者として工業的な設備の助けをかりて行動しているとき、殺人的な環境を思い患う必要が、いったいあるのだろうか。」(P.155)
「鏡の中の自分のイメージとの舞踏の中で、ヨーロッパの死は、他人の意志とは独立のものとしてあらわれたのであり、自分で直面せねばならない自然の仮借なき力としてあらわれたのであった。」(P.156)
「いまや患者ではなく、医師が死と闘うようになったのである。」(P.157)
「種族の長が死んだ場合の魔女狩りは現代化されつつある。早期の、もしくは臨床的に必然でない死のすべてに対して、何者かもしくは誰かが無責任にも医療をおくらせるなり、妨げたとされるのである。」(P.158)
「しかし、同じ種類の死に対して、平等な医療ケアへの要求は、一方、現代人が際限なく拡大する産業システムに依存する傾向を堅固なものにするのに役立った。」(P.158)
集中治療装置のもとの死
「死、すなわち私の世界の終わりと、アポカリプス、すなわち世界の終わりとは密接な関係がある。この両者に対するわれわれの態度は原子力時代によって深い影響をうけたことは明らかである。アポカリプスは単なる神話上の推測ではなくなり、現実の偶発事件になってしまっている。神の意志、人間の罪・自然の法則によるかわりに、最終戦争(アーマ・ゲドン)は人間の直接的決断の結果としてもおこる可能性があるのである。」(P.159)
「すべての人が同種の死に向かうのが進歩であるとする神話は、「持たざる者」の醜い死を、現存する低開発の結果と見なすことで、「持てる者」の側の罪の感情を減じてしまうのである。」(P.160)
「文化に一貫性を与えている自己のイメージは解体され、ばらばらになった個人は高度に「社会化」された健康消費者の国際的(インターナショナル)大衆に統合される。医療化された死への期待は、富者を限りのない保険料支払いに拘束し、貧者を鍍金された死のわなに誘う。ブルジョア個人主義の矛盾は、人々が死に対しての現実的態度をもっていながら死ぬ能力がないということで深まってくる。上部ヴォルタとマリとの国境を守る税官吏は、私に死と健康との関係でとらえることの重要さを説明してくれた。ナイジェル川沿岸の村々ではそれぞれ異なった言語をしゃべるのに、いったいどうやって相互に理解できるのかを、私は教えてもらいたかった。彼によれば、別に言語と関係はないという。「少年の割礼の方法が同じで、われわれ自身の死(FF)を死ぬかぎり、よく理解できるのだ」と。」(P.160-161)
「死の医療化によって、健康ケアは一体化した世界宗教になり、その教義は義務教育で教えられ、その倫理的ルールは環境の官僚主義的再編成に適用される。つまり、性が講義の題目となり、一つのスプーンを共有することは、衛生上の理由でやめさせられる。」(P.161)
「社会的に同意が与えられる死は、人々が生産者としてだけでなく消費者としても役立たずになったときにおこる。それは、多額の金をかけて訓練された消費者が、まったくの損失としてついに帳消しにされる時点である。死ぬことは消費者の抵抗の究極的な形式である。」(P.162)
Ⅳ 健康の政治学
6 反生産性
「時間を浪費する加速化、麻痺させる教育、自己破壊的な軍事的防衛、方向音痴な情報、人騒がせな住宅計画と同様に病気をつくりだす医療は、人間の自律的行動を麻痺させる過剰生産の結果である。」(P.165)
限界非効用
「たとえば、排気ガスが原因である癌の治療費は、癌の発見、手術、汚染予防措置やガ(FF)スマスクによる予防の費用を燃料の一ガロン当たりに追加すればよいのである。しかし大部分の外部効果は量化されず内化されないのである。もしガソリンの価格が石油の備蓄と大気中の酸素を増やすために上げられれば、旅客ーマイルあたりのコストはさらに高くなり、特権的なものになるだろう。環境破壊は減るが、社会的不公正は増加する。工業生産の強度がある点をこえると外部効果は減少せず、ただ場所を変えるだけだ。」(P.166-167)
商品対使用価値
「そして史上はじめてのことだが、人間が消費する食料は地域間の市場を通じて流通している。このように過度に工業化された社会においては、人々は物事を自らなすというより、それをなすように条件づけられているのであり、自ら創造するものより自分が買うものを評価するように訓練されている。自ら学び、自ら癒やし、自分で自分の道を見出すよりは、教えられ、動かされ、治療され、導かれることをわれわれは欲するのである。非人格的な制度に人格的機能が与えられる。治癒することは病者の任務ではなくなってしまった。それは初めは個々の身体の修繕屋の仕事になり、やがて人間的なサービスから名称のない機関の仕事にかわってしまうのである。この過程において、社会は健康ケア制度のために再組織され、自分自身の健康をケアすることはますます困難になってくる。商品とサービスは自由の領域を荒らしているのだ。(LF)学校は教育を生産し、自動車が旅行を生産し、医療が健康ケアを生産する。」(P.168)
「学校教育、自動車交通と同様、臨床的ケアは、資本を集約した商品生産の結果である。すなわち、生産されたサービスは他人のためにデザインされたもので、他人とともに、あるいは生産者のためにデザインされたものではないのである。」(P.169)
「最も価値のある学習、身体運動、自らの治癒はGNPにはあらわれてこない。人間は母国語を習い、動きまわり、子供を生み育て、折れた骨をふたたび使用できるようにし、地方特有の食事をととのえるが、これらの仕事をかなり有能に、また結構たのしんで行っているのである。これらの価値ある活動はほとんどいつも金のために行われるわけでもなく、金のためになしうるものでもないが、たくさんの金があってもその価値がさがるわけではない。」(P.169)
「一九世紀末にいたるまでは、西欧諸国においてすら、大多数の家族は既知の治療法を身につけていた。学問、交通、治癒の大部分は各人が自らのために行い、必要な用具は家族や村の中で生産されたのであった。」(P.170)
「自律的生産様式と他律的生産様式の間の共働はかくして負の色彩をおびてくる。社会が管理された生産様式に傾き、調整機能をもてば、究極的には二つの破壊的側面があらわれてくる。すなわち、人々は行動よりはむしろ消費に馴らされてくるし、同時に行動の範囲が狭められてくる。道具が労働者と労働を分離してしまう。いつも自転車で通勤する人は、交通があまり烈しくなれば道路からしめ出されてしまい、自分の病苦を自分でケアしてきた人は、過去に自分で使用してきた薬も(FF)処方がなければ利用できず、入手すら困難になってしまう。自律的生産と贈物の関係が衰微するにつれて、賃金労働と顧客関係は拡大してくるのである。」(P.170-171)
貧困の近代化
「価値の非人格化による典型的な犠牲者は、産業により富裕になった環境の中の力なき人々である。」(P.172)
「自律性を防御するよりは多くの生産物を約束することで、無能力化につながる依存性をつよめてしまう。」(P.172)
「低開発諸国に新しい生産機械 それはその地域における有効性のためというよりは財政的有効性のためであり、素人ではなく専門家のみがコントロールできるものであるが が侵入してくると必ず伝統と自律的学習は失格させられ、教師、医師、ソーシャルワーカーの治療への需要が生み出されてくる。道路やラジオが工業水準にまで人々の生活をあげ、その人々の生活に手を加えはじめると、置き換えた技術を破壊する以上の速度で、手工芸、住居、健康ケアを低下させてしまうのである。」(P.173)
「個人の需要を知ることが専門家の診断の結果ということになれば、依存性は痛ましき無能力へと変わってしまう。アメリカにおける老人が、実例として役立つ。彼らはどんな水準の相対的な特権によっても決して満足させえないほどの烈しい要求を経験するように訓練されてきている。彼らの弱さを支えるのに用いられる税金が多ければ多いだけ、彼らの衰弱感は痛切なものとなる。同時に自己ケアの能力はおとろえ、彼らに自律性を発揮させようとする社会の方策も消えていくのである。老人は、サービスの専門家の生きすぎが生みだした貧困の特殊な例である。アメリカの老人は高いコストをかけた収奪によって進められた苦悩の極端な例である。老年を病気に近いものだと考えることにならされたために、彼らはたえず有効でもない治療に対して支払うというきりのない経済的需要を発展させており、しばしば尾羽打ち枯らし、痛ましくさえある。そして特別の環境の中に隠居したいという気になるのだ。」(P.174)
「自分の環境と文化の中に、自分の苦悩と折りあうための助けになる手段はますます少なくなってくるし、こうしてつまらぬことにまで医療サービスの助けをもとめることになる。人々は障害や苦悩とともに生活するという能力がなくなってしまい、それぞれ専門化したサービスを業とする人々によって、すべての不快を処理してもらおうと依存的になってしまっている。」(P.174)
「個人と環境の間の関係に機械が介入し、それがある強度以下であれば、すなわち個人の行動の自由の領域にとって相対的なものにとどまれば、このような介入は生体が闘い自らの未来をつくり出す能力をむしろ高めるのである。」(P.175)
7 政治的対応策
「彼らは末期の痛み 通常は主として根拠のうすい、不成功に終わった癌の外科手術の犠牲者によって感じられる痛みであるが この痛みを和らげるための特別の病院が必要であること、また医療によってもたらされた疾患に悩む人々たちのためのベッドの必要性を予見していなかったのである。」(P.177)
「ラルフ・ネーダーは保健の消費者に金銭と質とを意識させた。生態学の運動が、健康は環境 食事、労働条件、住居 に依存するのだという意識を生みだし、アメリカ人は自分たちの殺虫剤、添加物、菌毒、そして環境の悪化による他の健康に対する危険物に脅かされているという観念をうけ入れるにいたった。婦人解放運動は自分の身体に対する管理が健康ケアにおいて果たす重要な役割をたかめた。」(P.178)
嗜癖者に対する消費者保護
「医療ケアは不確実で予見できないものである。多くの消費者はそれを望んではおらず、自分にそれが必要だということを知らないのである。そしていくらかかるかあらかじめ知ることもできない。彼らは経験から学ぶことはできない。供給する側を信頼し、よいサービスをうけられますと(FF)いわれればそれを信用するほかはない。そしてサービスを売手にもどしたり、サービスを改善させるというわけにはいかない。一度購入してしまえば、治療の最中に気を変えるわけにはいかないのである。」(P.183)__消費すればなくなってしまう。
「さらに事態を複雑化しているのは、医療サービスには正常の消費者は存在もしないし、存在するはずもないということである。」(P.183)
「「健康な時間」は二つの理由で需要がある。すなわち消費財として個人的有用性の機能に直接的に流入するのである。さらに人々は通常病気であるよりは健康であることを望むからである。それはまた投資財としても直接に市場に流入する。この機能において「健康な時間」は、個人が仕事・遊び・稼ぎ・レクレーションに消費できる時間の総量を決定するのである。個人の「健康な時間」はこのようにして個人が生産者として共同体にどれだけの価値をもつかの指標とみなされるのである。」(P.184)
「医師の請求書と健康の間に因果関係があるという信仰は それは現代の迷信ともいうべきだが 医療経済学者の基本的な技術上の推定である。」(P.184)
「それは化学物質・装置・建物・専門家のパッケージからできあがっていて、顧客に配達される。そして顧(FF)客や政治ボスではなく、配達する側がそのパッケージの内容を決定する。患者は修理される対象 彼の身体 へと還元されてしまう。すなわち彼はもはや回復するために援助をうける主体ではなくなってしまっているのである。もし患者が自らの修理の過程に参加するならば、修理工の序列の最下位の小僧として振舞うということになる。しばしば彼は丸薬一つでさえも看護婦の指導なしでは、まかせてもらえない。」(P.185-186)
「不適切な医療サービスから消費者を保護するためにはじまったことが、第一に医師に継続的な需要を保証することになり、次にこれらのサービスのある部分を産業の分野にまかせる権力を与えることになる。他の分野とは食料、マットレス、休暇、訓練などの生産者である。消費者保護としてはじまったものはたちまちのうちに、独立した人々をなんとしてでも顧客に変様させてしまう運動に変わってしまうのである。」(P.186)
「どんな種類の依存も、自律的・相互的なケア、闘い、適応、治療の障害となるのであって、さらに悪いことには、人々を病気にする労働条件、家庭生活条件を変えることをさまたげる計画に化してしまうのである。」(P.187)
不法行為に対する平等の権利
「豊かな国では、少数異民族は権利を与えられていないが、それは一人当たりの金額に直せば、分け前が少ないからではなく、彼らが必要とするよ(FF)うに教えこまれたよりも実質的に少なくしか得られないからである。スラム街の居住者は医師を必要とするときも手がとどかない。さらに悪いことには、老人は、もし貧乏で「施設」にとじこめられているなら、医師からのがれられないのである。これらと同様の理由で、政党は健康への願望を、医療を平等に利用する権利に変えてしまう。政党は、通常は医療システムが生産する商品については問わず、特権者のために生産されたと同じものをすべての人々が手にする権利があると主張するのである。」(P.188)
「健康に対しては、自由と権利という二つの側面がある。」(P.190)
「ある水準の強度をこえると、健康ケアは平等に分配されても「自由としての健康」を窒息させるだろう。こうした基本的意味において、健康ケアは、秩序ある自由の問題である。この概念の中に、ある事柄をするという譲渡しえない自由の優先的地位が含意されているのであり、ここにおいて市民の自由は市民の権利と区別されなければならない。」(P.190)
「そうした権利は平等に意味を与えるのであり、政治的な自由は自由に形を与える。話す自由、学ぶ自由、癒やす自由を絶滅する一つの確実な方法は、市民の権利を市民の義務に変えることであり、それを制限することである。自らを教える自由は教育過剰の社会では短縮されるが、それはちょうど健康ケアの自由が過剰の薬物使用によって窒息させられるのと同じである。」(P.191)
専門家マフィアに対する公的なコントロール
「すなわちトップには国際間に通じる専門家、中位には官僚制、底辺には亡命者と専門化された平民からなる新しい半プロレタリアートがいるのである。」(P.195)
「医者に対する非難を根底的な様式にしてしまうことは、新しい健康意識によって燃料補給をうけている政治的危機を逃れる最も確実な方法であろう。もしも医師が顕著な犠牲の子羊になれば、だまされやすい患者は自分たちの治療に対する貪欲さの故に非難されずに済むことになろう。学校を非難することが、危機が最終的に教育を襲ったときに、制度的企みを救った。」(P.196)__医療ドラマ、学園ドラマ。
「費用がかさむ夢の欲求が満足させられないと、多くの人々は以下のように思うようになる。すなわち、義務的教育をどれほど与えても若い人々は産業社会のヒエラルキーに対して公平に準備されたことにはならないし、子供を非人間的な社会・経済制度に対して効果的に備えさせることは他人に対する体系的攻撃性を形成するということである。」(P.197)__塾、加熱する教育、少しでも勉強させる、親も学校も資本も。その勉強が自我を強める。競争。
「学校を攻撃することは、自由な校長を新しい血統の成人教育者に変様させた。それは単に教師の給料と威信を救っただけでなく、一時的ではあったがそれを高めたのである。危機的な状態にいたる以前は、教師の教育的攻撃性は一六歳以下の年齢のグループに限られていたのに、(そのグループは校舎の中で授業時間の間だけ、限られた教科の手ほどきをうけるために教師の前にさらされるが)新しい知識の商人はいまや世界が自分の教室だと考える。」(P.197)
生命の科学的組織
プラスチック子宮の工学
「一般的には、人間は遺伝子的所与というよりは環境の産物なのである。」(P.203)
(P.204)__都市の意義、大学の思想。
「患者中心の医療から環境中心の医療への転換は、二つの不吉な結果を予想させる。ひとつは、異常のいくつかの異なったカテゴリーの間の境界感覚が失われることであり、もうひとつは全面的治療への新しい合法性が生まれるということである。医療ケア、工業の安全性、健康教育、精神的最条件付け、これらは人間を工学システムに適合させるために必要とされる人間工学の別名なのである。」(P.204)
「すなわち、医学的治療か、教育的治療か、または他のイデオロギー的根拠によって行われる治療かの境界が次第にぼやけていくのである。」(P.204)
8 健康の回復
工業化されたネメシス
「プロメティウス」は英雄であり、「誰でも(エブリマン)」ではなかった。根源的な貪欲さ(プレオネキシア)に駆りたてられ、彼は人間の限界(アイテイアとメソテス)を超え、かぎりない傲慢さ(ヒュブリス)から、天国より火を盗んだ。彼はこのようにして、必然的に、ネメシス(報復)を自らの身の上に招いたのである。」(P.207)
「うけつがれてきた神話は、もはや行動に限界を設けることをやめてしまった。もし人類がその伝統的神話の喪失後にも生存していこうとするなら、羨望の念にみちた貪欲かつ怠惰な夢と、理性的、政治的に闘うことを学ばなければならない。神話だけでは、この仕事はもはやなしえない。工業の発展に対して政治的にうち建てられた制限が、神話による境界に代わらなくてはならなくなるだろう。」(P.208)
「自律的学習以上に計画された教育を評価する社会は、人に自らの技術化された場にしがみつくことを教えざるをえなくなる。交通を管理された輸送にたよる社会も同様である。ある水準をこえると、輸送に使用されるエネルギーは、名もない旅行者の大多数を動員して奴隷にし、エリートのみに利益を与えることになる。」(P.208)
「価値のある部分以上が工業的方法によって作られる場合、生存活動は麻痺し、公平さは衰退し、満足感の総体は減少するのである。」(P.209)
「やがてやってくる飢えは、富める国家と貧しい国家の地味の肥えた地域に工業化された農業が、必然的に集中化されることの副産物である。」(P.209)
「工業のヒュブリス(傲慢)がある水準をこえると、ネメシス(報復)がはじまる。なぜならば、進歩は魔女の徒弟のほうきのように追放するわけにはいかぬのである。」(P.209)
「ちょうどガリレオの同時代人が、自分たちの地球中心の世界観がゆるがされるのをおそれたという理由で、望遠鏡で木星の衛星をみることを拒絶したように、われわれの同時代人がネメシスに直面するのを拒否するのは、自分たちの社会的政治的構造の中心に、生産の工業的様式にかえて自律的様式を置くことができないと感じているからなのである。」(P.211)
受けつがれた神話から経験な処置まで
「宇宙の有限さは、操作的調査の対象であるが、私の考えでは、この機器の瞬間に、自然の神話的な神聖さを現代化するようないまの生態学的イデオロギーにのっとって、人間行動に限界を見出すのは重大な誤りだろう。」(P.212)
「最近の歴史は、伝統的文化のタブーは工業生産の過大な拡大と闘うこととは無関係であるということを示している。これらのタブーは、ある社会の価値とその生産様式とに連繋されているのであって、工業化の過程の中で決定的に失われるの実にこれらのタブーなのである。(LF)工業化社会の限界を、共有の福祉を目指し、警察力によって強制されなければならないような、実在する信念の共有化体系の上に基礎づけようとするの不必要でもあり、たぶん可能性もないことだろう。現在流行している何らかの生態学的独断の共通の認識にたよらずに、倫理的な人間行動に必要な基盤を発見することも可能であろう。新しい生態学的宗教あるいはイデオロギーにかわるべきものとは、基本的価値と手続き上のルールに関しての同意に基礎をおくものである。」(P.214)
「個人的自律性の回復は、こうして倫理的覚醒を強化する政治行動の結果となるだろう。人々は輸送を制限しようとのぞむ。なぜなら人々は効果的に、自由に、公正に移動しようと思うからである。また教育にも制限を与えるだろう。なぜなら人々は世界に関してというよりは、世界の中で学ぶための機会、時間、関心を平等にわかちあいたいと思うのだから。人々は医学的治療も制限するだろう。なぜなら人々は治癒の機会と力とを保存したいと思うだろうから。彼らはまた権力の規律ある制限のみが、公正に満足を共有できることを認識するだろう。(LF)自律的行動の回復は、人々が共有する新しい特定の目的によるのではなく、個人個人と各グループとが異なった目標を追求する際におこる葛藤を、解決にみちびくような法律的・政治的処置を用いることによる。よりよい稼働性は新しい輸送体系によるのではなく、個人のコントロール下にある個人の稼働性により価値をもたせる条件による。よりよい学習の機会は世界に関する情報がよく分配されていることによるのではなく、関心をそそる労働条件のために資本が集中するような生産を制限することによる。よりよい健康ケアは新しい治療基準に依存するものでなく、自己ケアへの意欲と能力のレベルによるものである。この力の回復は、現在の妄想を認識することにかかっているのだ。」(P.214)__対象化と自然。
健康への権利
「医原病は、痛み、病気、死が医療ケアの結果として生じたときには臨床的なものであるが、健康政策が不健康をもたらす産業組織を強化するとき、それは社会的なものになる。また医学が後おしする行動と妄想が、人間が成長し、お互いに愛し合い、年をとる能力を駄目にすることによって人々の生命力の自律性を制限するとき、あるいは医療的介入が個人の痛み、不具、損傷、苦悩、死に対する反応を不可能にするとき、それは構造的なものとなる。」(P.216)__コロナが死者に対面させないとき。
徳としての衛生
「健康は適応の過程を示している。それは本能の結果ではなく、社会によってつくり出された現実に(FF)対する自律的ではあるが、文化的に形成された反応なのである。それは変化していく環境に適応し、成長し、年をとり、損傷をうけたとき治癒し、苦しみ、死を平和のうちに待つという能力を明示している。健康は未来をも包含し、それゆえにともに生活しなければならない苦悩と内的な慰みとを含んでいるのである。」(P.218-219)
「最低のレベルまで専門家の介入をおさえている社会は、健康のための最善の条件を準備するだろう。自己と他者と環境に対する自律的適応の潜在能力が大きければ大きいほど、適応を管理する必要も少なくなり、我慢もしやすくなるのである。(LF)医療の介入が最低限しか行われない世界が、健康が最もよい状態で広く行きわたっている世界である。」(P.219-220)
「人間によって意識的に生きられている脆弱さ、個性、関連性は、痛み、病気、死の経験を人生の不可欠の部分にする。この三者と自律的に闘う能力は、彼の健康に対して基本的なものである。彼が自分の内奥のものを管理にまかせるとき、彼は自律性を手放し、彼の健康は衰えざるをえない。」(P.220)
原注
「世界的飢え、低栄養は、いずれにしても工業の発展とともに増加した。「全人類の三分の一から二分の一は毎夜空腹をかかえて就寝する。石器時代にはこのような人々は、もっと少数だっただろう。いまやかつてない飢えの時代で(FF)ある。現在、最も技術力の時代の進んだ中で、飢餓は一つの制度化されたものになっている。」(P.226-227)__サーリンズ『石器時代の経済学』
「薬物は、その望ましさ、効果に関しては、それが摂取される環境に左右される。薬物の選択は文化の機能であるが、薬物乱用は個人の機能である。薬物接種の儀式化は、その下位文化をつくり出す。かくして薬物嗜癖の歴史は、社会の歴史として数年ごとに書き改められねばならない。」(P.246)
「嗜癖者が自分たち自身のゲットーに入らざるをえない程度は、彼らを拒絶する社会に左右される。」(P.246)
「ほとんどの国家では、医師に対する薬物情報は、製薬企業がスポンサーとなっている刊行物で与えられる。」(P.252)
「全世界的な現代における栄養不良は、乳児の栄養不良の二つの型に反映されている。乳房から瓶への転換はチリの赤ん坊を風土病的低栄養生活へと導いた。同じ転換が、イギリスの赤ん坊に病気を招くような嗜癖的過剰栄養の生活をもたらした。」(P.258)__粉ミルクのせいだろう。粉ミルクは改良されて、多くの栄養素を含んでいるだろうが、本当にそれが摂取されるのだろうか。髪の毛。母乳による免疫の取得。母の乳房や産道の雑菌と、免疫。病院での出産。帝王切開。無痛分娩。無痛社会。
「「危機」はこのようにして支配者が与えるサービスと反比例して、権力をたかめようとする時に支配者の用いられるくん製のにしん(目をそらせるもの)になっている。それはつねに新しい結合(エネルギー危機、権威の危機、東ー西危機)をして、研究費の授与者を正当化するような学問的内容を「危機」に与えることで支払いをうける科学者たちに、研究費を豊富に与える無限のテーマになっている。」(P.264)
「啓蒙時代のエリートにとっては、死はそれに先立つ世代におけるものとは異なったものとなり、ずっとおそろしいものになった。外見上の死は世俗化した地獄となり、医学の主要な関心となった。」(P.264)
「自動的活動としての癒える権利は患者自らが行使すべきものであるが、それと医師が癒やすという他動的権利の主張と葛藤がはじまる。」(P.265)
「さけること、それは臨床的に実体のある予後を伝えることの失敗であるが、患者と家族とを暗闇の中におき、「自然のなりゆき」を発見させ、医師を時間のロスト事件から救い、患者がもし自分がなおらないことを知ったら拒絶するだろう治療をつづけることを医師に許すのである。不確かさは芝者場医師と患者が非可逆的なもの エトスに合わぬもの を受け入れるのをさけるため共謀することで起こるのである。」(P.265)
「安楽死、人間の生命を医学が止めることは、週末のケアが医療化される以前には重要な問題ではなかったことがしばしば忘れられている。」(P.266)
「結核患者から伝染する危険があると信じると、儀式化された処置、非合理的行為になる。たとえば、患者に防衛のためのマスクを強制するのはX線室に行くときだけで、映画や社交的あつまりに行くときはつけさせない。」(P.269)
「人間は自己を平衡に導く進化のメカニズムを自らの内に組み込んでいない。すなわち人間の創造的に利用する力は自らの環境に対して他の種に対するのと異なる特徴を与えるのである。それは習慣を自らの中心とする。」(P.273)
「歴史の対象となるべき痛みは、内在的痛みの人格化された経験である。すなわち痛みがおこる社会的状況が痛みの体験の中に包含されている。」(P.280)
「病気が人間から分けはなされ、医師によって扱われる存在となった時、人間の他の側面は突如分離しうるもの、使用できるもの、売れるものになった。」(P.286)
「ロサンゼルスの小児病院では、二〇パーセントの母親は子(FF)供の病気が何であるかを知らないし、五〇パーセントはその病気の原因を知らないし、四二パーセントは受けたアドバイスにそれを理解しないゆえにしたがわない。」(P.288-289)
「人は自らの死の主人であるかぎりにおいて、自らの人生の主人でありうるのみである。人の死は彼に属し、彼のみに属するのである。一七世紀以後、彼は自らの死に対する主権と同様、自らの生に対する主権も抛棄してしまった。」(P.298)
「健康部門における財政的資本の優位は、専門家の自律性の衰退の前兆である。なぜなら、専門家は組合を作らざるをななくなるからである。制度上の資格 それは医療チームのキャプテンすらも被雇者にしてしまうが それがこの傾向をつよめる。」(P.315)
「専門職業は認可にもとづいているという考えを私は以下の書に負っており、さらにその考えを追いたい。」(P.315)
訳者あとがき
「しかし、その論議の内実といえば、一方では医療問題が問題なのではなく、医療経済、さらには保険組合経済のみが問題なのであり、他方では医者なり病院に対するうらみ、つらみ、のろいで終わってしまっている。前者の代表としては、総資本と対決するはずの総評が、保険組合の既得権を守るためになんと日経連と手を組むというお粗末さにあらわれている。」(P.321)
「この医療化が各文化固有のもの、痛み、病気、死にいかに立ち向かい、耐え、許すかという態度を無国籍の、のっぺらぼうなものにしてしまったのである。そして、医原性的疾患という、本来医師・薬物・医療行為をもとにして生まれる新しい疾患を指す言葉を、(1)臨床的(2)社会的(3)文化的、の三つのレベルにまで拡げ、現状の文化史的背景にまで徹底した分析を加え、前記の痛み・病気・死に対する人間の自律的態度・行為をとりもどすための提言を行うのである。(P.323)
一九七八年一二月
<おわり>
<メモ>
ネットで他人を攻撃するような人は、やっぱり痛みを感じないだろうと思う。その人は、きっと、痛くなる前に薬を飲むような生活をしてきたし、そういう意味では現在も自分の健康に気を使っているのかもしれない。
私が小学生の頃、学校給食で「脱脂粉乳」が出ました。
健康って何?
健康ケアを病気をつくり出す企てに変化させたものは、人類の生存を有機体の行為から技術的操作の結果に転化した、工学的努力の強度そのものであることをいま理解しなければならない。」(P.15)
基本的な感情
人間は「道具」を発明し、文化(文明)を発展させてきました。道具、たとえば「車軸」を発明した人は、「便利になろう」と思ったのでしょうか。ノーベルがダイナマイトを発明したのは、人を殺すためではないでしょう。
私のように「便利になること」に「悦び」を感じる人は、いつの時代でも、どこの文化にもいても不思議はありません。「楽をしたい」「美味しいものを食べたい」「痛いのは嫌だ」「恋愛の苦悩と悦び」など、どの時代にも、どこの文化にもありそうな「基本的な感情」は、「当たり前のこと」だと思ってきました。そして、その感情を抑える文化的な動き、私の頭の中にあるのは一部のキリスト教の禁欲的な教えや仏教の修行などですが、それがその基本的な感情とともにあり、その二つの弁証法的な(?)相克が歴史の(ドラマの)原動力であるかのように思っていました。その過程で、「民主主義(自由や平等)」が発展してきたのだと。
でも、最近、その基本的な感情が「当たり前だ」と思っている自分に疑問を感じ始めました。単純には、「私の楽(痛み)」と「あなたの楽(痛み)」が「同じ」かどうかわからないということです。「それは多分同じだろう」という仮定のもとに、そう信じているだけではないかと。それを客観的に示すことができるのでしょうか。できる、という仮定はあります。
たとえば「視聴率」。みんなが同じに感じるわけではないけど、「多くの人」が面白いと感じているだろうということです。でも、これはみんな(多くの人)が「楽しい」と思っているかとは関係ありません。それでスポンサーが喜んだり(商品が売れたり)、興行収入が上がればいいのであって、「楽しい」と思っているかは「結果からの推測」に過ぎません。
あるいは、検査。脳波や脳内物質の量を測ってその人が「気持ちいい」と感じる要因を特定します。これも「楽」とか「快」を数値化したものとされます。でも、唾液の量や胃酸の分泌状態と「美味しい」と感じていることとは別なように、感覚を「数値化したもの」かどうかは不明です。
先日、失語症についての短い文章を読みました。「大脳の左半球には、言語野と呼ばれる領域」(笹沼澄子著「失語症」、P.201)があるのだそうです。その場所が損傷を受けると、言語使用に影響がでます。そうなんでしょう。だけど、その部分が損傷を受けると言語使用に影響が出るということと、その部分が言語を司っているということは同じではありません。
義務教育ってなんなのだろうか。
言語に共通点があるのだろうか。
意味や価値とはなにか。
なぜ、今その様になっているのか。昔はどうだったのか。
知識とは何か。理解するとは何か。
痩せ薬
死ぬということ、老いること
反官僚主義
責任
血圧を管理されるということ
世話(1)世間の話(2)せわしい(忙しい)から、面倒を見ること、手数をかけて苦労すること。福沢諭吉『学問のすゝめ』「世話の字に二の意味あり。一は保護の義なり、一は命令の義なり。保護とは人の事に付き傍より番をして防ぎ護り、或は之に財物を與え或は之がために時を費やし、其人をして利益をも面目をも失はしめざる様に世話をすることなり。命令とは人のために考て、其人の身に便利ならんと思ふことを差圖して不便利ならんと思ふことには異見を加へ、心の丈けを、盡して忠告することにて、是世話の義なり。」(岩波文庫、P.144、「慶應義塾大学メディアセンターデジタルコレクション」)
若い?イリイチ
まだ、力がみなぎっている。
でも、突き詰めたい気持ちがある。そして、知るということが新たな「知識」の獲得よりも、従来の知識に「疑問」を感じさせる。たとえば「水」。「みず」と「water」は違います。フランス語、ドイツ語、ヒンズー語
言葉が通じない場所にいると想像してみてください。あなたは水が飲みたい。「みず」と言っても、「water」と言っても通じない。そうだ、紙に書こう。「水」と書いても「water」と書いても通じない。そこで思いつきます。「H2O」と書いたら、通じた。相手も義務教育程度は受けたらしい。ところが、相手はどんな「みず」を持ってくればいいのかわからない。相手がどんな水を持ってくるのかもわからない。そこであなたは「コップで水を飲むジェスチャー」をします。通じた。相手は「飲み水」を持ってきてくれました。
そのほかにも、「体を洗うジェスチャー」「うがいのジェスチャー」「ホースで水を掛けるジェスチャー」などで、意味が通じるかもしれません。その時の「飲み水」「体を洗う水」「消火用の水」は単なる「H2O」ではありません。それぞれが「意味をもった水」「意味を背負った」なのです。
火葬場の予約制
痩せ薬