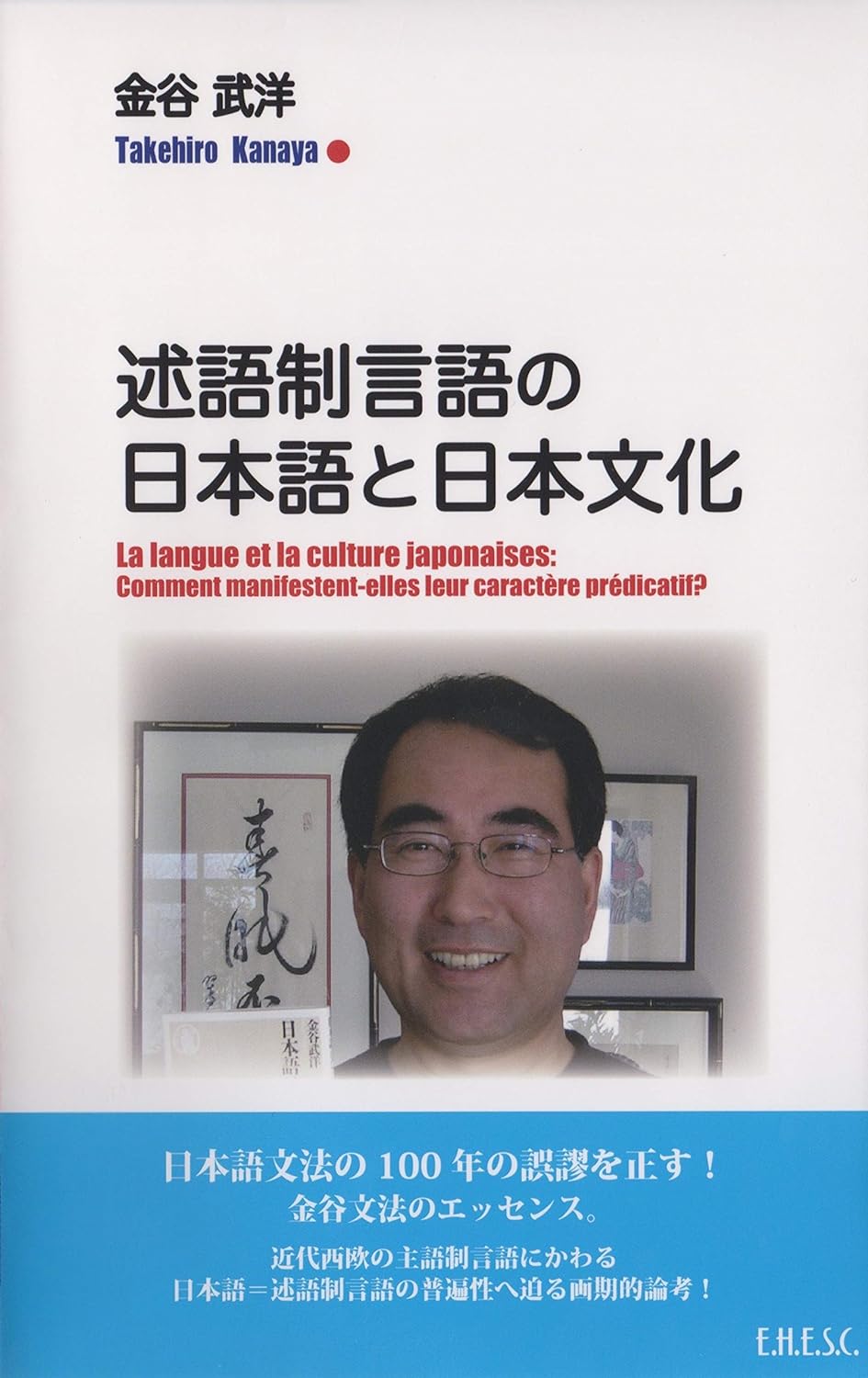
新書や選書よりちょっと具体的(専門的)な内容ですが、ほとんどが以前の著作と同じです。
私が今まで読んだ金谷さんの本は、
『日本語は亡びない』(ちくま新書、2010)
『日本語は敬語があって主語がない 「地上の視点」の日本文化論』(光文社新書、2010)
くらいだけど。
その他にも一般向けの本は色々あるので(Wikipedia)、金谷さんの具体的な言語理論については、それらの本を読んでください。難しくないです。
この本は、いろいろな所に連載したり、講演原稿(?)などを、多分そのまま集めています。なので、けっこう重複した内容が多いので、半分は流し読みで読めました。巻末掲載の英語の論文は、私には読めません。
序文で西田幾多郎の「日本語の自在性」という小論が引用されています。『青空文庫』や『Amazon kindle』で無料で読めますので、金谷さんが引用した部分ではなく全文を引用します。なお、題名は「国語の自在性」となっています。
文化の発展には民族というものが基礎とならねばならぬ。民族的統一を形成するものは風俗慣習等種々なる生活様式を挙げることができるであろうが、言語というものがその最大な要素でなければならない。故に優秀な民族は優秀な言語を有つ。ギリシャ語は哲学に適し、ラティン語は法律に適するといわれる。日本語は何に適するか。私はなおかかる問題について考えて見たことはないが、一例をいえば、俳句という如きものは、とても外国語には訳のできないものではないかと思う。それは日本語によってのみ表現し得る美であり、大きくいえば日本人の人生観、世界観の特色を示しているともいえる。日本人の物の見方考え方の特色は、現実の中に無限を掴むにあるのである。しかし我々は単に俳句の如きものの美を誇とするに安んずることなく、我々の物の見方考え方を深めて、我々の心の底から雄大な文学や深遠な哲学を生み出すよう努力せなければならない。我々は腹の底から物事を深く考え大きく組織して行くと共に、我々の国語をして自ら世界歴史において他に類のない人生観、世界観を表現する特色ある言語たらしめねばならない。本当に物事を考えて真に或物を掴めば、自ら他によって表現することのできない言表が出て来るものである。
日本語ほど、他の国語を取り入れてそのまま日本化する言語は少いであろう。久しい間、我々は漢文をそのままに読み、多くの学者は漢文書き下しによって、否、漢文そのものによって自己の思想を発表して来た。それは一面に純なる生きた日本語の発展を妨げたともいい得るであろう。しかし一面には我々の国語の自在性というものを考えることもできる。私は復古癖の人のように、徒らに言語の純粋性を主張して、強いて古き言語や語法によって今日の思想を言い表そうとするものに同意することはできない。無論、古語というものは我々の言語の源であり、我民族の成立と共に、我国語の言語的精神もそこに形成せられたものとして、何処までも深く研究すべきはいうまでもない。しかし言語というものは生きたものということを忘れてはならない。『源氏』などの中にも、如何に多くの漢字がそのまま発音を丸めて用いられていることよ。また蕪村が俳句の中に漢語を取り入れた如く、外国語の語法でも日本化することができるかも知れない。ただ、その消化如何にあるのである。
(『国語特報』第五号、昭和十一年一月、第十二巻)引用は『青空文庫』から。
(岩波旧全集 第12巻、『續思索と體驗』所収、「國語の自在性」P.152-153)
「優秀な民族は優秀な言語を有つ」というのは、時世におもねったものかもしれません。でも、西田はこういう思いを持っていたと思うし、自文化を卑下したり、むやみに否定するよりはマシです。このような思いが、京都学派や「近代の超克」論へと繋がります。戦後、民主的な雰囲気の中で、それらは批判されます。京都学派の戦争責任までが問われます。
私は「近代の超克」論は勉強したことがないのでなんとも言えませんが、「自由・平等・民主主義は無制限に正しい」という前提での批判だとすれば、その前提こそが問われなければならないと思ってしまうでしょう。
なぜか「東京学派」は世論からの批判が弱い気がします。政治や経済の中枢にいたのは東京大学(あるいは、東京の大学)出身者が多かったと思うし、それらの人たちが戦争を計画し、遂行したのではなかったのでしょうか。明治維新以後(藩閥が西南戦争で官僚制に変わって以降)、むやみに西洋文化を移入し、戦後(敗戦後)政治(経済)を導いてきたのも、その多くは東大(東京の大学)出身者だと思います。
「本当に物事を考えて真に或物を掴めば、自ら他によって表現することのできない言表が出て来るものである」というのは、奥義や事物の真実(核心)を捉えたときには、その表現は一意に決まってくる、ということでしょう。例えば「りんご」の本質を掴んだとして、その表現方法は一つでしょうか。日本画もあれば、セザンヌの『リンゴとオレンジのある静物』のような絵もあります。木彫もあるでしょうし、オノ・ヨーコは本物のりんごを展示し、ジョン・レノンと出会いました。確認できませんが、ジョンが死んでかなり経ってから、オノ・ヨーコはメタル製のりんごを作ったはずです。それらのどれかがりんごの本質を表しているのでしょうか。私は、オノ・ヨーコの「生のりんご」が一番近いと思うけど、それがりんごの本質を表しているとは思います。りんごというのは一つのイデア(概念)ですから。それを「りんご」と表しても「 apple 」と表しても同じです。ただ、文化によってそれが表す意味(あるいは対象)は異なるでしょう。
ところが、リンゴといえば赤ではなく、緑と決まっている国があるのだ。その代表はフランスである。フランスでは pomme (リンゴ)という果物を、一般的には vert (緑)と考える習慣があることに気付いて、いろいろと調べてきた。(鈴木孝夫著『日本語と外国語』1990/01/22、岩波新書、P.29)
『リンゴ追分』(美空ひばり、1952)には色が出てきませんが、並木路子の『リンゴの唄』(1945)は「赤いりんごに唇よせて・・・」です。赤いりんごと緑のリンゴとどちらが美味しく見えるでしょうか。私は断然赤いりんごです。緑のリンゴは酸っぱそうに見えてしまいます。
ある単語(語彙)は、言語によってそれが示す範囲が異なります(「木」と「 tree 」など)。そして、その単語が喚起するイメージも言語によって違います。「リンゴのようなほっぺ」といえば、私は元気な(血色の良い)子供を思い浮かべますが、フランス人は青ざめた(血色の悪い)子供をイメージするのかもしれません。
単語だけではありません。文そのものも、それが惹起するイメージが異なります。金谷さんが本書で何度も挙げている例で言えば「愛してるよ」と「 I love you. (Je t'aime.) 」とでは、「同じこと」を言っているようで、「異なる」のです。
どうちがうのか。それこそが言語学(という学問)の最大問題です。日本は世界でも類を見ないほどの「翻訳文化」ですから、「外国語と同じことを日本語で言える」という大前提で世の中が動いています。だからこそ、「翻訳の不可能性」を認識することはとても大切なことです。
「外国語の語法でも日本化することができるかも知れない。ただ、その消化如何にあるのである。」(西田、前記引用文)
学校で教えられている「日本語文法」は、基本的には西欧語の文法(主に英文法)を日本語に当てはめたものです。「単語」(明治期の和製漢語)、「語彙」、「音素」、「構文」・・・、全て欧米の言語学を日本語に当てはめたものです(「文法」は元々ありましたが、「 grammer 」の訳語として使われたのは明治以降でしょう)。
金谷さんは、「学校文法」の誤謬を3つ挙げています。
学校文法の問題は何かと言われたら、数多ある中から、(1)西洋の文法概念で日本語に不要な「主語」を使い続けていること、(2)平仮名に固執する為に、真の音韻分析が出来ていないこと、(3)日本語本来の述語制に支えられた「場所の文法」の最も美しい例である「受身・自動詞・他動詞・使役の連続線」が全く理解されていないこと、を三大誤謬として挙げたい。しかもこれらはお互いの足を引っ張り(FF)合って、誠に不幸な「負の相乗効果」を生んでいる。以上三点は、その順番で、構文論、音韻論、形態論の分野における問題であるから、学校文法のほぼ全域に及ぶ。(P.10-11)
実は私は『日本語に主語はいらない』を読んでいません。2002年に刊行されたこの本(講談社選書メチエ)は、今でも名著として読まれていると思います。英文法を基本にした日本語文法では、主語がない日本語を「主語は省略されている」とか「主語は文末の助詞に表現されている」とか、さまざまに説明してきました。それは「人間が話す言葉(文)には主語は必ずあるもの」という前提があるからです。
明治以前より、日本には「国学者」という人たちがいて、日本語、というか『古事記』などの古典の解釈をしていました。それは文字を中国から「漢文」として輸入した日本において、「漢学」に対応する学問として日本語(大和言葉、やまとことば)の研究をしていたのです。「 subject 」と訳語としての「主語」は当然使われていません。明治期に西欧の文献が大量に流れ込んできた時、学者たちはそれを日本語に翻訳しようと努力しました。それまで使われてきた「漢語」や「仏語(仏教語)」を転用したり、翻訳のための造語もたくさんされました。その結果、もともと使われていた漢語は、その意味が変化しました(「自然」「自由」など)。
中国から漢文が大量に流入してきた時と状況はいくらか似ています。その時日本には「文字」自体がなかったのですから、漢字そのままで日本語に当てはめたのです。「それ以前から日本独特の文字があった」という説もありますが、朝廷が漢字を「文字」として採用したのは間違いないでしょう。それは「平仮名」がうまれて、大きな変革が生じますが(「十世紀の「ひらがな革命」が生んだ国風文化」参照、P.47〜)、漢語(漢字)は使い続けられます。
「学校文法」は橋本進吉(1882-1945)による「橋本文法」に基づいているそうです(橋本進吉の著作は読んだことがない)。
橋本進吉をWikipediaで調べると、橋本文法は現代日本語文法での「四大文法」の一つだそうです。四大文法は、山田文法・松下文法・橋本文法・時枝文法で、それぞれ山田孝雄、松下大三郎、橋本進吉、時枝誠記が考えた日本語文法です。
どれも勉強したことがないので私にはわかりません。多分、私のような素人が理解できるものではないでしょう。というか、学校(義務教育と高校)で「日本語文法」を習った記憶がないのです。「五段活用」とか「上・下一段活用」とかの言葉は知っているので、どこかで習ったんでしょうね。でも、それは「古文」や「英文法」の付属品のような感じで憶えている気がします。だって、日本語を話すのに、日本語文法を知る必要はないですから。英語を勉強した経験から、何か「文法」があって「言語」があるような気になってしまいますが、文法とは言語から導き出されたものですから、それは間違いです。単語や品詞や音韻や統辞法などがあって、文章ができているのではありません。私は文法を知っているから日本語を話せるわけではないのです。文法を知らなくても話せる言葉、それを「自然言語」というのでしょうか(その対極にあるのがコンピュータ言語などの人工言語です)。
文法を知っていると、日本語を「正しく」使うことは出来ます。正しい日本語を話すことで、会話(コミュニケーション)がスムースになり、意思(データ、あるいはインフォーメーション)をうまく(論理的に)伝えることが出来ます。でも、それはイリイチのいう「教えられた母語」です。
ヴァナキュラーなジェンダーと性役割のちがいは、ヴァナキュラーな話しことばと教えられた母語とのちがい、生活の自立・自存と経済本位の生活とのちがい、になぞらえることができる。(『ジェンダー』岩波現代選書、P.171-172)
金谷さんは北海道生まれだそうです。彼にとって「ヴァナキュラーな話しことば」とは何でしょうか。彼がいう日本語とは何でしょうか。この本はその「ことば」で書かれているのでしょうか。
「平仮名に固執する為に、真の音韻分析が出来ていない」。なるほど、と思いました。言語学的には当然そうなんだろうと思います。
中学校で英語を習った時だったか、/v/ と /a/ をそれぞれ発音して、その間隔をだんだん短く続けて発音していくと「ヴ」になると教えられました。「ヴァヴィヴヴェヴォ・ /v/a/ /v/i/ /v/u/ /v/e/ /v/o/」。自分で練習して、どうも違和感を感じた記憶があります。/v/ と /a/ の間隔をどれだけ短く発音しても「ヴ」にはならないのです。まあ、そんな発音をしたことがないので、仕方ないんだな、と納得する「賢い子」でした。(笑)
今回改めて思ったのですが、学校文法が平仮名で音韻分析をしているというのなら、西欧の言語学は「音素」を自分たちが使っている文字「アルファベット」で分析しているだけじゃないかと。ヘリクツを言っているようですが、「音素」というのは「声(音)としてのことばの要素」です。手話をはじめ、言語は音だけではありませんから。「音」という波は、さらにフーリエ解析などで数字化(デジタル化)できます。実際音声解析はそんな手法も使っていると思います。それは「意味がない」ということなのでしょうか。
学校文法と「同じ土俵」で批判するなら、金谷さんの理論は「正しい(論理的)」だと思います。でも、それは言語(ことば)とは関係がないことなのかもしれないのです。「分析(解析)」という発想そのものにとても西欧的なものを感じるのです。
そんな事を言い始めたら、「単語」「品詞」「時制(テンス)」「相(アスペクト)」「態(ヴォイス)」「主語・述語」などの用語も学校文法と「対決するための武器」として用いられるだけにしなければなりませんが。
先ず、厳密に言うと、日本語の時制は現在のみで未来も過去もない。(P.184)
時制(過去・現在・未来)という観念が日本語で薄い、とすれば問題となるのは「日本人は時間をどう捉えていたのか」ということです。日本には「因果(応報)」という(多分仏教ゆかりの)考え方があります。今風に言えば「原因と結果」ということです。過去・前世(の行為)が原因で現在が生まれ、現在(の行為)が原因で未来・来世が作られると考えるのは、「輪廻転生」と密接にかかわっています。
西欧(キリスト教)には「輪廻転生」がありません。現在の生以外は「最後の審判」「終末」しかありません。直線的で「始まりと終わり」があるという時間観念です。現在の生を根拠付けるのは「発展(過去よりマシ)」という肯定的な観念です。そしてそれは現在は「未来より劣ってる」という否定とともにあります。
「繰り返される現在」からは「過去・現在・未来」という観念は生まれにくいのではないでしょうか。それを「日本語の特徴」というのが金谷さんの主張かもしれません。西田幾多郎の「絶対的現在」というのも、そこから来ていると思います。なんか、「卵が先か鶏が先か」の話をしている気がしてきました。
(私は「サピア・ウォーフの仮説」を「信じて」います。ちなみに中国語もテンスよりもアスペクトの言語だと思ってます。中国語を知っているわけじゃないけど。)
金谷さんは西欧の言語を、俯瞰で高いところから見下ろすような「神の視点」、日本語を地上にある「虫の視点」と表現します。
話者はこれまで通り、どこにでも動いていける「虫の視点」で、「いま・ここ」の状況の中にいる。それは「神の視点」から見た過去/現在/未来とは、部分的に似ている要素はあっても、本質的に異なるものである。結論を言えば、日本語ではテンスよりもアスペクト中心の表現をする。アスペクトを借りて、テンスを間に合わせている、と言ってもいい。アスペクトをテンスト「解釈」、あるいは「誤解」しているのだ。(P.185)
金谷さんは「虫の視点」を北山修氏の「共視」と同様なものだとしています。
私はビートルズ世代なので、ジョン・レノンが大好きです。先にオノ・ヨーコのリンゴに触れましたが、ジョンと彼女はカップルでした。
それは1969年にジョン・レノンとヨーコ・オノ(小野洋子)が平和イベントとして行った『ベッド・イン( Bed-in )』と「バギズム( Baggism )」のことだ。(P.29)同じベッドに入ると、同じ場所から同じ方向(例えば新聞記者たち)を見ることになる。この行為に、この本で何度も指摘した「共感」と「共視」を私は感じてしまうのだが、それは考えすぎだろうか。(中略)
この「袋入り」をして、二人は袋から顔を出してこちらを見て微笑む、それだけのパフォーマンスであるが、予想以上に深い印象的な意味とメッセージを含んでいる。
この小論をここまで読んでくださった読者なら「袋入り」なら日本語の基本文との共通点に気づかれると思う。この「袋入り」こそは日本語の愛の告白、「好きです」を具体化したものなのだ。(P.30)
その上で言うのだが、日本語ほど、話者と聞き手を分離せず、進んで同じ地平に立って、できれば同じ袋に入ろうとする言葉は他にない。(P.31)
当時「ベッド・イン」は、世界中に報道されました。性的なことを報道しにくい日本ではテレビで大々的に報道されたわけではなかったけど。その時発売されたアルバム『トゥ・ヴァージンズ』は二人の全裸の写真がジャケットに使われていて、日本ではそのジャケットでは発売されませんでした(私はその無修正のアルバムを持っています)。
反響は大きかったし、ジョンも積極的にマスコミにコメントを発表したけど、その真意は私を含めてあまり伝わらなかったんじゃないでしょうか。当時のヒッピー文化(フラワーチルドレン)やベトナム反戦運動の一つと捉えられていたような気がします。
金谷さんのこの説明は、とてもスッキリして納得できました。もちろん、ジョンやヨーコがそう思っていたのかどうかはわかりませんが。
「虫の視点」で私が思い出したのは、鈴木孝夫の『森林の思考・砂漠の思考』(1980、NHKブックス)です。
人間の思考方法は、森林的思考と砂漠的思考の二つに分けられること、それは、世界が「永遠」に続くと考えるか、「有限」であると考えるが、人間の論理にとってはどちらか一つに分かれることに根ざしているから、その二つにしか分けられないことを述べた。具体的には、森林的とは視点が地上の一角にあって、「下から」上を見る姿勢であり、砂漠的とは「上から」下をみる鳥の眼を持つことであった。「見とおしの悪さ」「見とおしのよさ」という対比でもある。「慎重」と「決断」の対比でもある。「専門家的態度」と「総合家的態度」の形容でもある。そして、その森林的思考、砂漠的思考は、かならずしも森林に住むか砂漠に住むかによって分かれるのではなく、森林的思想
具体的にはたとえば仏教のなかに育ったか、砂漠的思想具体的にはたとえばキリスト教のなかに育ったかということによるもので、好んで使われた図式、自然->生産関係->人間、すなわち自然は生産関係という中間項を媒介として人間に働きかけるという図式にならっていえば、自然->思考様式->人間、すなわち、自然によって生まれた思考様式をうけ継ぐことによって人間が自然にかかわっている、ということもできるであろう。しかも、思想は、それ自身の論理の力によって動くから、かならずしも現在の自然環境と対応して、森林的思考と砂漠的思考が存在しているのではない。むしろ、その起原は、五〇〇〇年前の乾燥化によって一神教が確立された時にある。(『森林の思考・砂漠の思考』、P.215-216)
「神の視点」が「砂漠の思考」、「虫の視点」が「森林の思考」に対応します。鈴木はそれを(言語ではなく)地質学(気象学)に基づいて語っているのです。つまり「風土」と関係しているということです。「時間」というより「空間」に関連付けているということです。
「空間」、つまり「場所」です。ジャック・デリダは『コーラ プラトンの場』でプラトンの『ティマイオス』に出てくる「場(場所、χώρα)」について書いていますが、私は未読。
「空間」について、イヴァン・イリイチはこう言っています。
文化はそれぞれ、独自の空間を形造るし、また、このみずから生み出した空間自体が文化ともなりうるのである。(中略)空間は、各々の文化のなかに秘められ、すべてに通底する非対称的な補完性から結果する社会的創造物である。(『H2Oと水 「素材(スタッフ)」を歴史的に読む』邦訳、P.27)「あなたはどこに生きて(live)いますか」と「あなたはどこに住んで(dwell)いますか」という二つの問いは同意である。これは、ほかの言語
非西欧言語もふくめてに訳した場合にも、大体いえることである。どこの言語でも意味が同じだということは、「生きること」と「住むこと」とが、昔から密接な関係にあったとということであろう。一方は存在の時間的側面を、そしてもう一方はその空間的側面を強調する。住むということは、自分自身の生の営みによって残された痕跡に留まることを意味し、そのことによって、人はつねに自分の祖先の生活の軌跡をたどるのである。(同書、P.28)
同書で、プラトンとアリストテレスの「空間」に対する考え方の違いを書いています。
プラトンの「容器」(hypdechomene)は、アリストテレスによって、存在の論理的な四つの「原因」の一つと化し、「質料(hyle)」と同一視されてしまう。アリストテレスは、西洋の空間知覚の最終的な土台、すなわち容器としてではなく、広がりとしての空間認識を築いた。(同書、P.46)
プラトンは「空間=容器」として捉え、アリストテレスは「空間=質料=広がり」と捉えているということです。
物質とは、すなわち、われわれの想像が姿かたちをあたえる、あの「素材」を指す。私もまた、バシュラールの思索の方向にしたがって、「素材」とその形態を区別し、都市を造りあげている二種類の素材都市空間と都市用水の間に想像力が生み出したきずなについて考察しようと思う。(同書、P.16-17)
「想像(イデア、形相)が姿かたちをあたえる、あの「素材」」とは、アリストテレスの言う「第一実体(質料)」ですね。「容器」であれば、そこに「内側」と「外側」があります。内側と外側を隔てるもの、それが古代の都市であれば「城壁」、家であれば「壁」です。共同体と共同体の境は、日本では「山」や「峠」、あるいは「森」であることもありました。その向こうは「鬼が住む異界」でした。「川」や「海」ということもあります。西欧においても昔は同様な感覚があったのではないでしょうか。神話や昔話に出てくる共同体の「向こう、彼岸、外界、別の世界」は数え切れないほどあります。
ほとんどの文化は、数学や物理学の形式的連続体になじまない「外界」の現実をみる眼をもっている。ギリシャの神々も、民衆文化のなかの幽霊たちも、また、バラケルススがニンフ、空気の精、小人や火の精について表わした論文によれば、四大元素〔地・水・火・風〕のなかに宿るという火や水や空気の自然の精霊たちも、そのようなデカルト流の連続体のなかには住みえない。幾何学は、私の想像を紡げるような糸を巻ける紡錘ではないのだ。(同書、P.58-59)
デカルトが三本の「数直線」で表した空間、永遠に続く空間は内側と外側の区別、境界を廃止します。そして空間は単なる「広がり」となります。それを歩いて越えることが可能となります。高速道路(鉄道)でつなげ、飛行機で越える(越境、超越する)こともできます。
でも、文化がそれを禁止していました。文化が禁止していること、それを行うことはまさしく「共同体を離れる」ことです。それは「死」と同じです。越えることが可能になれば、「死」は社会的(共同体的)ではなく「個人的」なものになります。同時にそれは「生」をも「個人的」なものにします。イリイチがいう「ヴァナキュラーなもの」はその境界に囲まれた中でしか成立しません。境界がなくなった時、ヴァナキュラーなもの、生死、あるいはジェンダーは失われ、「経済的なもの」「セックス(生物学的性別)」になってしまうのです。
形相と質料、内部と外部、個人と社会、人間と自然、部分と全体、また「時間(歴史)」と「空間」が融合するものとして「場(場所)」があります。
「場所」あるいは「場」といえば、冒頭から引用している西田の「場所の論理」がありますが、まだ理解できていないので別稿とします。
西欧科学(物理学)は空間と時間の対立を一見、解決したかに見えます。空間は一歩歩くだけで、いや「視点」を変えるだけで、移動することができます。でも、時間はタイムマシンが身近にならない限り移動することはできません(しかし、何もしなくても過ぎていきます)。先に引用したイリイチの文章に「「生きること」と「住むこと」とが、昔から密接な関係にあったとということであろう。一方は存在の時間的側面を、そしてもう一方はその空間的側面を強調する」とありました。西欧においても、時間と空間は対立するものではなく、同じものを「別の側面」から見たものでしかなかったのだろうと思います。「生きること」の二つの側面です。
私は学校で英語を勉強しただけですが、どうも苦手です。それ以外の言語を勉強しようと思ったことは何度もあるのですが、どれも3日と続きませんでした。何語だったか、「中動態」というのが出てきました。英語には「能動態」と「受動態」しかありません。日本語で言えば「する」と「される」ということです。金谷さんは「態」ではなく「相」という言葉を使います。
「中動相」とは、起源的には古典ギリシャ文法の「 mesóthès 」から来ており、英語の Middle voice (フランス語: médio-passif, voix meyenne )を和訳したものである。(P.213)
金谷さんは、中動の意味をE・ラゴン、E・バンヴェニスト、細江逸記、A・メイエ、J・ゴンダなどの説で説明しています。
金谷さんの結論は、
「印欧語古語には、行為者を全面に打ち出す能動相と対立する文法カテゴリーとして中動相があった。その機能は行為者の不在、自然の勢いの表現である。」そして「中動相」に変わる新しい文法用語を提案したいと思った。それが Diathèse éventive と Diathè agentive である。和訳すれば前者が「自然(じねん)相」で後者が「人為相」となる。自然(じねん)の意味は「何事かが起きる、出来(しゅったい)する」ということだ。そこに意思を持った人為はない。(P.230)
能動・中動・受動の関係を古田裕清さんはこう書いています。
(ディオニュシオスは・・・引用者)彼は能動を ἐνέργεια 〔エネルゲイア〕、受動を πάθος 〔パトス〕、中動を μεσότης 〔メソテース〕と呼んだ。前者二つはアリストテレス用語。能動は「人が肉を切る」や「火が木材を燃やす」などにおける動詞の語形(不定形で τέμνειν〔テムネイン〕、κάειν 〔カエイン〕)、アリストテレス的に言えば人や火(始原因)を主格としてその能動能力の発動を表現する語形。受動は「肉が切られる」「木材が燃やされる」など、肉や木材(質料因)を主格としてその受動能力の発動を表現する語形(不定形は τέμνεσθαι 〔テムネスタイ〕、καίεσθαι 〔カイエスタイ〕)。(『西洋哲学の基本概念と和語の世界』中央経済社、P.143)中動態は、主格が外部から独立に自己の内部で完結させる(あるいは主格自身が受益する)動き変化・状態とも形容できる。主格から発出する動き変化であっても、主格がその動き変化に内在するなら、中動態が用いられる。(「自分の体を洗う、λούομαι 〔ルーオマイ〕」など)。
他方、受動態は、自らが発出源でない動き変化・状態に、主格が巻き込まれることを表現する形態。主格は外的な他者が発出させた動き変化・状態を被ることになる。受動態の κεῖμαι は「横たえられる」、λούομαι は「洗われる」。つまり、能動・受動の対立は、動き変化・状態の発出源が主格かそれ以外かの対立。能動・中動の対立は、主格が動き変化・状態に外在的か内在的かの対立。両対立において能動の特徴づけは違ってくる。受動と対立する能動は、主格が発出源となる動き変化。だが、これは λούομαι のような中動態の一部についても言えるので、中動と対立する能動の特徴づけとしては的外れ。中動と対立する能動は、その主格が動き変化・状態の外部にあることの表現である。(同書、P.149)
ギリシャ神話は、神々と人間と自然の全体を、アイティア(責任・原因・・・引用者)の所在を含めて描き出す。自然的事物も人も神もこの全体の中に部分として位置づけられ、その位置を自らの運命として受け入れる。これは後にプラトンやアリストテレスが θεωρία 〔テオーリア〕(神の目線で見た光景)と呼んだもので、ギリシア自然哲学の母胎となり、近現代物理学へもつながった世界観である。同じ印欧系でも、アーリア人のヴェーダやペルシア人のアヴェスタが一方的に神々を崇拝するのみであるのと対比すると、極めて特徴的と言える。こうしたアイティアへの問いの浸透と軌を一に、中動態から受動態への転換が進んだ可能性がある。(同書、P.150)
まあ、私はまだよくわかっていないけど、人為(意思的行為)によるものが「能動・受動」、そうじゃないものが「中動」ということのようです。行為者がいないのですから、主語(行為の主体)になるものはないことになります。
結局、中動相構文とは、「印欧語における無主語文」なのである。(P.230)
その残骸が英語における「馬鹿主語」です。
語順が固定して必要になったものは馬鹿主語( dummy subject )である。(P.155)
例としてあげられているのは、It seems to us. 、It seemde to them. 、It seems to me.、 It thinks to me.などの「 it 」です。これらの文にある動詞は、
すべて「人間がコントロール出来ない」動詞というのが興味深い。これらは人間が意味的、認識的に主語に立てない動詞であるからだ。(P.155)
私がずっと悩んでいた「 It rains. 」の「 it は何を指すのか」の答えがここにある気がしました。
英語で言えば「 I (can) see Mt.Fuji. 」。
光がないと物が見えません。どうして物が見えるのか。現在なら「光が物に反射して目の水晶体を通って、網膜に映る。その映った像を脳が認識する」と考えるでしょう。でも、あるはずの物が見えなかったり(私は最近そういう事が多い)、ないはずのものが見えたり(今のところそういう自覚はない)、錯覚があったりします。
古典ギリシアの時代から、「どうして物が見えるのか」については「外送理論」と「内送理論」があります。上記の解釈は「内送理論(外から内に送られてくる)」です。送られてくるのは「光」だったり、「物質から発せられたもの(物質の表面から剥がれ落ちた何か)」だという説もあります。「外送理論(内から外に送る)」は目から何か(視線、プネウマなど)が放出され、それが対象を捉えるという考えです。不思議な考えに思えますが、「誰か(何か)の視線」を感じたことはだれにでもあるのではないでしょうか。
「自分が見えなければ、文は「自分の行為」を表し得ない。だから文の中心は「富士山」となる。英語の「 I see Mt.Fuji 」の視線は行為者である「私 ( I ) 」から富士山へと向かう。ところが「富士山が見える」では逆である。富士の姿が「虫の視点」を襲うのだ。かくて文は、富士山の「見える」という性質を表現する状態文となる。(P.130)
なんか英文が「外送理論」、日本文が「内送理論」に近い気がしませんか。
「 I see Mt.Fuji. 」というのは、「私」が「富士山」を「見るという行為を(能動的に)する」ということです。
「富士山が見える」というのは「能動」ではないし、「(私は)富士山に見られてる」という意味ではありませんね。「受動」でもないのです。富士山が見える状況(状態)に「ある」ということです。誰かに「富士山が見えるかい?」と聞かれた答えなら、聞いた人と同じ状況に私もあるということですが、「富士山が見えるよ、見てごらん」という意味なら、話し相手も同じ状況にあるよという意味です。
私は英語話者が「 I see Mt.Fuji. 」と言った時には「富士山が見える」と言っていると思います。「私は富士山を見ている」とは思っていないことが多いでしょう。そのために、英語には see ではなく、「 look, watch, view, glimpse 」など、意識して「見る」という動詞がたくさんあります。でも、英語話者は「 I 」をつけなければ落ち着かないのです。「 see Mt.Fuji 」では「富士山を見なさい」という命令文になってしまいますから。
「自分(私・自己・自我)」は「 I 」ではありません。「自分(私)はこう思います」は「 I think so. 」でしょうが、「自分で考えなさい」「自分はどう思うの?」は「 you 」です。
「社会」という時に、その社会には自分が入っている場合(私の社会)と、自分が入っていない場合(社会というもの)があります。これは明確に別の社会なのですが、両方合わせて「社会」という概念が生じます。「私の社会」とは別に「社会一般」というものがあるということです。「私」も同様です。「自分」以外に「別の私」「私一般(自我というもの)」、「私という概念」が生じます。「私」というのは、他とは絶対違う、唯一の、独自のものですが、それでも「他の自我(他者)」というものは存在すると言わざるをえません。そう思っていない人もいるかも知れませんが、たんなる「私」ではなくて、特殊な、「意思を持った」私、そういう私(デカルトの「我思う、ゆえに我あり」の「我」)を想定するときは、既に「他の私」が前提されているのです。デカルトにとって、「私を私たらしめているもの」は「神」なのでしょうが、その神の中には父母や、オランダ・フランスの人々などがいる(神を分有している)のです。彼が本を書かなければならなかった(あるいは出版を中止せざるをえなかった)背景には「他者」がいるのです。
野矢茂樹(Wikipedia)さんの『哲学・航海日誌』(春秋社、1999、まだ80ページしか読んでいない)に、他我問題が書かれています。「他人の痛みがわかるか」という問いです。他人の痛みを想像しても、それは他人の身体の中に想像した自分の痛みでしかないということです。だから問いを変形します。「痛み(自分の痛み)を想像しないで、他人の痛みを想像できるか」ということです。なんか禅問答のようですね。Wikipediaによると野矢さんは禅を実践しているようですから、そういう問いはしょっちゅうしているのでしょう。
他人の痛みを直接知ることはできません。知ることができるのは、他者が顔を歪めたり、声を上げたり、その部分を押さえたりする「外に現れた行動(見えたもの)」だけです。「他人の痛み」そのものは「空欄」のままです。空欄が埋められない原因は「大雑把に言えば、「自我から出発して他我へと到達する」という発想」(前掲書、P.46)です。そこで野矢さんは「この発想から手を切」(同)ります。そして「知覚的に現れている世界のさまざまな光景を「眺望」ないし「眺め」と呼び、視覚的眺望における「視点に」に相当するものを知覚一般に拡張して「眺望点」と呼ぶことにしたい。」(同書、P.70)と言います。
例えば、丘陵に近いあたりに大学の時計台が見えるが、言うまでもなく私はそれを立体として捉えている。(中略)そこにあるものが立体であり、その眺めが奥行きをもつということは、私がその時計台の方へ近づいて行ったり、あるいはその横の方や裏の方にまわりこんだりする可能性をこめて、この眺めを見ているということである。なるほど私はいまここから眺めている。しかし、可能的にはあらゆるところから眺めている。(同書、P.71)
それゆえ私はむしろ、他の場所に立っている人が眺めている光景を想像することはそれほど難しいことではない、と言いたい。そもそもそうした他の視点からの眺めの了解なくしては、私のこの位置からの眺めも成立しないのである。他人は、私がいまここで可能的に理解しているその眺望を現実のものとしているにすぎない。(同書、P.74)
だが、他我問題に囚われた者たちは、世界の非人称的構造ということに納得しようとはしないだろう。(同)
眺望点と眺望の関係の内に、「私」とか「彼」は含まれてこない。(同書、P.75)
「富士山が見える」に人称代名詞「 I 」が必要ないのは、「自分の視線(眺望点)」と「他者の視点(眺望点)」という区別を必要としないからです。これは北山修さんの共視論と同じだと思うし、日本語の特徴でもあると思うのです。
81ページ以降が楽しみです。
「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。」 川端康成の『雪国』の冒頭です。この文のサイデンステッカーによる英訳は「 The train came out of the long tunnel into the snow country. 」
日本語の方は、時間の推移を含んだ「コト」(出来事)を表しているのに、英語では汽車という「モノ」をわざわざ持って来て、それの「トンネルからの出現」という表現にすりかえてしまったとも言えるだろう。時間と空間を立体的に表現していた原文と比べて、訳文では時間の要素が無くなって文字通り「失速」してしまっている。(P.58)
これは私が読んだ金谷さんの著作に何度か出てくる例です。改めて取りあげたのは、これを「時間と空間を立体的に表現している」と言っているからです。前の著作でも言っていたかもしれません。前述の日本人の時間と空間に関する観念が日本語そのものに表れていると思ったからです。
多の自己否定的一として時間的に、一の自己否定的多として空間的に、多と一との矛盾的自己同一的に、自覚的体系において、それ自身によって有り、それ自身によって動く世界が構成される。かゝる世界に於いて、物は何処までも個物的多的に、相対しい相否定すると共に、何処までも矛盾的自己同一的に一である。(中略)物と物とは、現在が現在自身を限定する絶対的現在の場所に於いて、相対するのである。(西田幾多郎『哲学論文集 第六』所収「物理の世界」旧全集第十一巻、P.36-37、引用にあたって現代漢字仮名遣いにした)
読んだときはまったくわからなかったし、こうやって書き抜きしてもやっぱりわかりません。でも、なんか日本(語)的だなあ、と思うのです。西洋哲学において、「普遍と特殊(個物・個体)」「全体と部分」「社会と個人」などが、ずっとテーマとして語られています。そして、「個人があるから社会がある」「部分があるから全体がある」「特殊(個物)があるから普遍(種)がある」と考える傾向があります(ダーウィンの進化理論もそこから生まれています)。私自身もそう考えてしまうので、それをうまく否定できません。その逆も根強くありますが、そう考える人は「全体主義者」と非難されてしまいます。西欧において(少なくとも近代以降は)大切なのは「個(個人)」つまり「主体・自己」なのです。西田は「全体主義者」「ナショナリスト」などと非難されることもあります。日本人は「長いものに巻かれる」「自己主張をしない」「集団主義的」などと批判されることもあります。
私の知る限り、西洋においても「全体と部分」の対立は解消されていないと思います。だから、ナチスは西欧人にとっては「人ごと」ではないのです。ナチスは批判されるだけで、解決はされないのです。日本においては「一億総懺悔」というだけで、批判もあまりされない戦後社会があるのは、日本人の「意識が低い」とかいう問題ではありません。ましてや「日本語が非論理的」などという問題でもないのです。「主語」とともに日本に流入してきた「個人(主体)」主義が、日本語を英語のクレオール化(植民地言語化)し、部分と全体を対立化したのだと思います。それまでは日本に「社会がなかった」(柳父章『翻訳語成立事情』)のは、日本が「遅れていた」からではありません。それに比べて「西洋が進んでいた」というわけでもありません。
「全体と部分」の問題は、「我(個人・主体)と汝(他者・社会)」「主体と客体」「人間と自然」(誤解を招く言い方では経済学の「貨幣」と「商品」)などの対となって日本に入ってきました。それらは「自我から出発して他我へと到達する」という発想」(野矢、前掲書、P.46)であり、それそのものが近代西欧的なのです。西田が「多と一との矛盾的自己同一的」という時(西田の発想も禅から来ているようです)、それを西欧的に見れば「独我論(観念論)的」あるいは「全体主義的」に見えます。仏教的に言えば「自力と他力」に見えます。そして、西田にあってはそれは「人間というもの、意識をもつもの」としての「人間であれば仕方のないことだし、人の悩み(いわば「煩悩」)はそれに発する」と思っているように思います。そしてそれを救うのが(西田のいう)「宗教」のようです。
煩悩や「喜怒哀楽」というのは、どこでも、いつの時代にもあるでしょう。そしてそれから「煩悩一般」「喜怒哀楽一般」のような「概念(観念)」を想定することもできるのかもしれません。でも、「古代インドにおける煩悩」と「飛鳥時代における煩悩」とを「同じ」だと言う必要はありません。少なくとも現代日本における「悩み(煩悩)」は、その特殊な(ヴァナキュラーな)現れであることは間違いないと思うのです。
どんな仕事でも、その道のプロでしかわからないことがあることを認めます。私は学者でもなんでもありません(ただのサラリーマン)でしたが、現役の頃はその道のプロでした。それで飯を食っていたのですから、そう言えるでしょう。そしてその仕事に関しては、部外者には理解されないだろうことも知っています。別に犯罪を犯していたわけではありませんし、隠すようなこともありません。でも、すべての人がすべての仕事を知ることは出来ないのです。それだけです。
私は仕事を楽しいと思ったことも、やりがいを感じたことも「まったく」と言っていいほどありません。学者という職業はどうなんでしょう。「苦しみ」は多いでしょうが、きっと「やりがい」はあるんでしょうね。学者どうして喧々諤々しのぎを削っている分にはいいのです。私はその内容を知ろうともしないし、できないでしょう。ただ、それが学者以外の人(例えば私)に影響があるとすればどうでしょうか。「偉い先生が言ってるんだから」で済ませられません。私の仕事だって、誰かに影響を与えています(いました)。それでお金がもらえるということはそういうことです。グレーバーの言う「ブルシット・ジョブ」はあります。グレーバーが言いたかったのは「ブルシット・ジョブ」がある、ということではありません(そう思われたので、グレーバーの本は一定の読者を得ましたが)。ブルシット・ジョブを作り出す現代社会(近代西欧社会、あるいは資本主義社会とも言えます)そのものを提示したかったのだと思います。
学校文法が日本語に(日本に・日本人に)与えた影響は量りきれません。日本人の意識や思考方法を変えた、そして変え続けていると私は思うのです。「変えること」の結果が、いいことであろうと悪いことであろうと、「変えること(変わること)」そのものに「価値がある」と考えるのもその影響の一つです。いわゆる「社会進化論」です。
「その消化如何にある」という西田の言葉に込められた楽観主義を今の私は信じることが出来ません。第二次世界大戦も、原爆も、コロナワクチン開発も、「偉い先生が考えたことだから」と認めることは出来ないし、「いつか笑えるさ」とも思いたくはありません。「日本語では主語が省略されることが多い」というのなら、「主語とは何か、主語はどうして必要か」と問いたいし、「日本語は論理的ではない」というのなら「論理とは何か」と問いたいのです。そしてその可能性は「日本語そのもの」にあると思います。
ただ、そこから「日本語が世界を平和にする」と楽観視することはできません。金谷さんとは逆に、日本語はどんどん英語化(クレオール化)していると思うし、「教えられた母語」としての日本語は、どんどん主客未分ではなくなってきているように思えるのです。私のこの文章も、金谷さんの本もかなりの程度「学校文法」に則って書かれています。そうでなければ、今の日本人に理解されることはないでしょう(私の文章は、それとは関係なく理解されないのですが)。逆に西田の文章(明治から終戦までに書かれた)を私は理解できないかもしれません。
「経済的なセックス」は「ヴァナキュラーなジェンダー」があって成り立っています。
セックスの世界が成立しているとすれば、それは、ジェンダーのなごりがその中で生きのび、芽を出しているからにほかなりません。コンピューターが知覚の根源的なメタファーであるような、サイバネティックスによってモデル化された世界が、危険で深刻な意味をもつとすれば、それは、そうした世界のただ中に、なおもテクストの文字文化が存在するかぎりにおいての話しです。輸送システムは、車まで歩いていき、そのドアを開けるための足が人びとにないかぎり機能しません。病院というシステムが意味をもつのは、人びとがいまなお、まったく他者に頼ることなくおこなう活動、すなわち生きるという活動に従事しているかぎりでの話しなのです。(イヴァン・イリイチ著『生きる意味』邦訳藤原書店、P.359-360)
私が「生きている」ということ、大したことではありませんが、そこにしか「希望」がないように思います。
[著者等]
出版社からのコメント
日本語文法が主語のある英文法の引き写しによって根源的な誤 りを犯している。印欧語の構文構造と日本語のそれとを対比さ せ、日本語の本質から世界の言語理論へ寄与する通道を開く、 カナダ在住の著者の渾身の、日本で話題となっている金谷文法・ 言語論の明晰な本格論述。そして、助動詞の受け身・使役の連 続する関係の本質を解き明かす。などなど。 これを読まずして日本語は語れない!
著者について
1951 年北海道生まれ。函館ラ・サール高校から東京大学教養学部卒業。ラヴァル大学で修士号( 言語学)、モントリオール大学で博士号( 言語学) 取得。専門は類型論、日本語教育。カナダ放送協会国際局などを経て、2012 年までモントリオール大学東アジア研究所日本語科科長を務める。
*著書
『日本語に主語はいらない―百年の誤謬を正す』(講談社選書メチエ、2002 年)、『日本語文法の謎を解く―「ある」日本語と「する」英語』(ちくま新書、2003 年)、『英語にも主語はなかった―日本語文法から言語千年史へ』(講談社選書メチエ、2004 年)、『主語を抹殺した男/評伝三上章』(講談社、2006 年)、『日本語は亡びない』(ちくま新書、2010 年)、『日本語は敬語があって主語がない―「地上の視点」の日本文化論』(光文社新書、2010 年)
英語の主語制言語に対して、
日本語の主語なき述語制の構造を明らかに
示し、その日本文化を明証にする。


